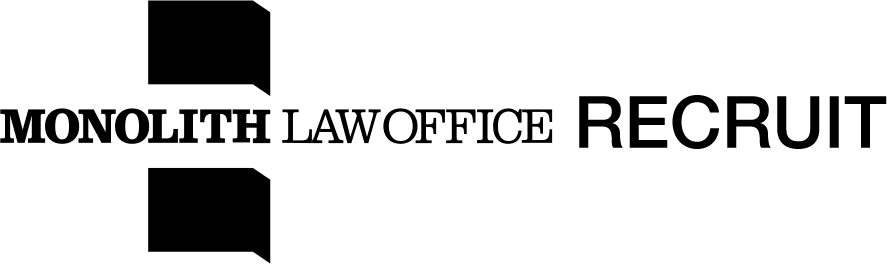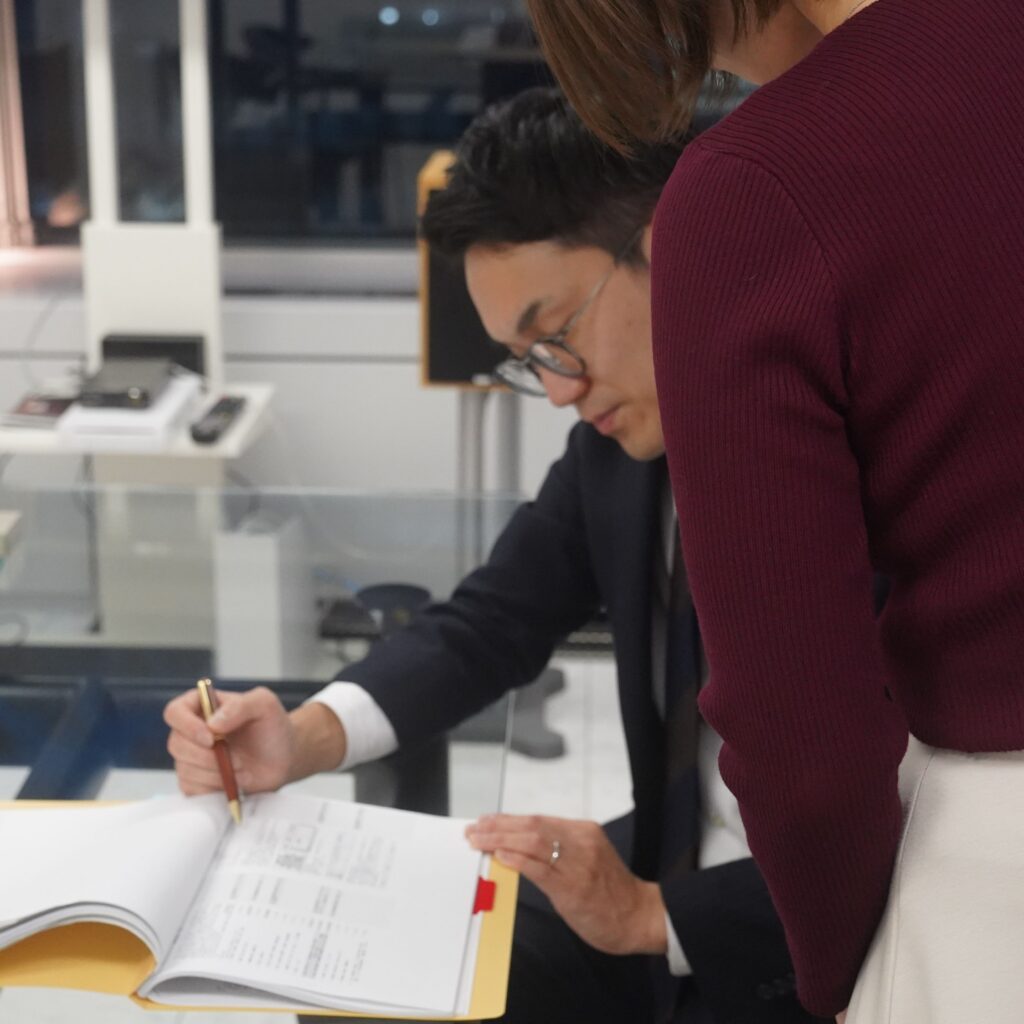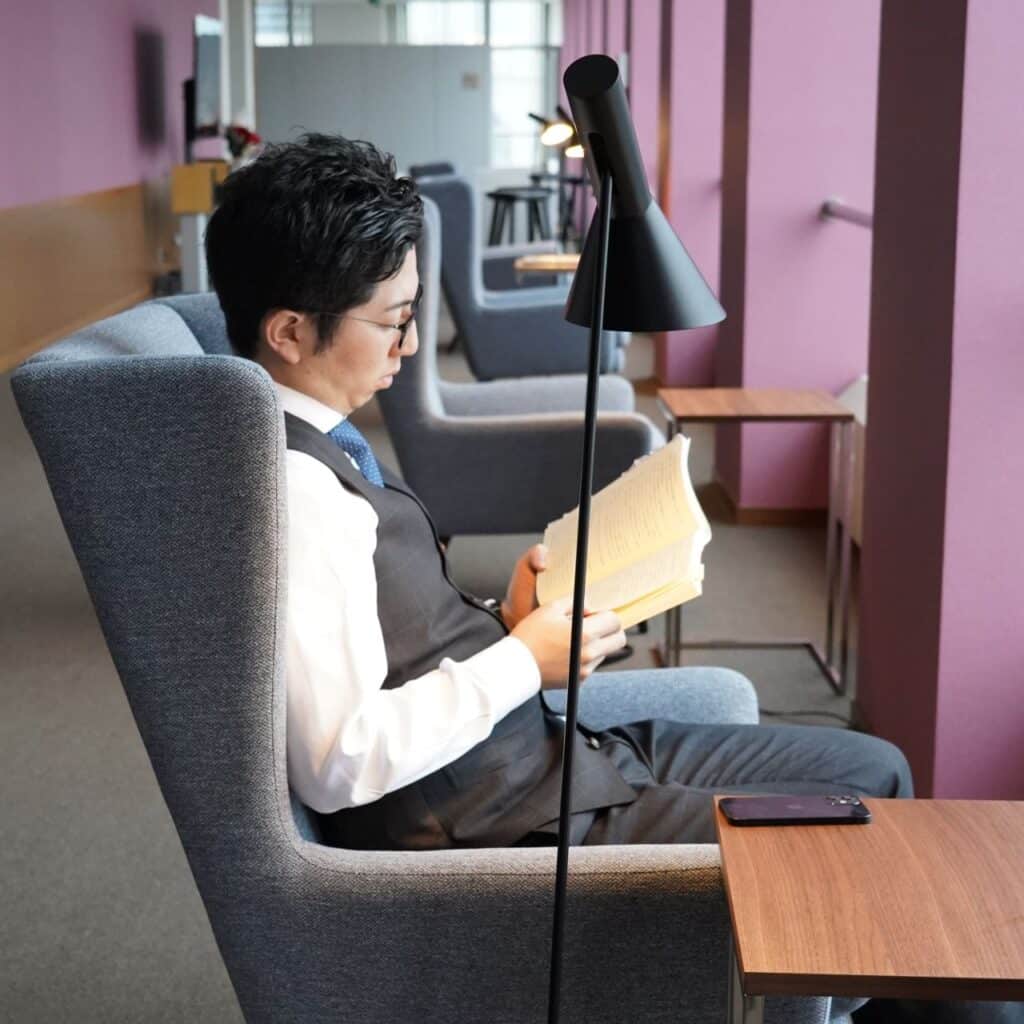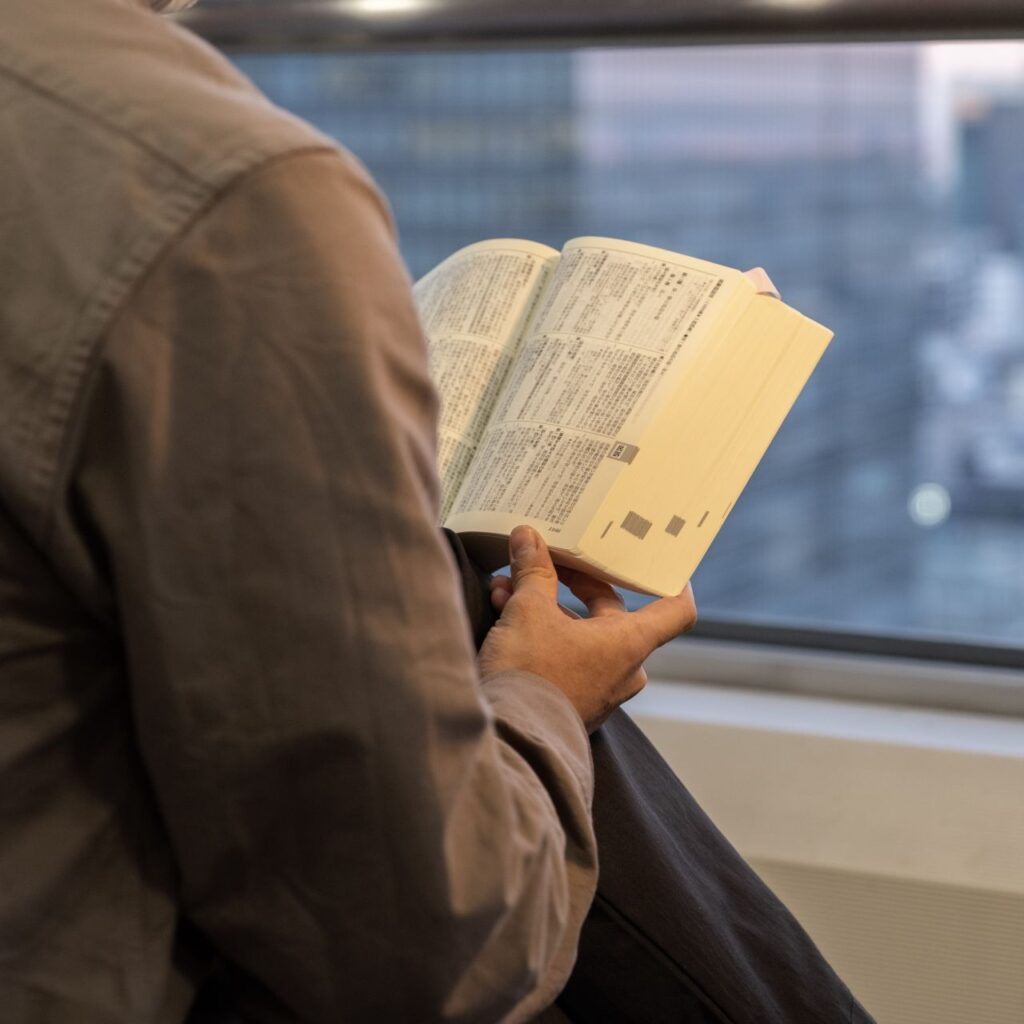一般民事から企業法務への転職は可能なのか?業務の相違点やキャリアパスについて解説

法曹の世界を目指す学生や司法修習生にとって、その進路を考える上で「一般民事」と「企業法務」という二つの分野は、しばしば対比され議論の対象となります。特に、司法試験予備試験合格者や上位の法科大学院出身者の中には、「ファーストキャリアで一般民事の法律事務所に所属すると、企業法務の法律事務所への転職は非常に難しくなる」といったイメージを持っており、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
モノリス法律事務所は、新卒採用だけでなく、第二新卒からシニアアソシエイトまで幅広い層の弁護士を積極的に採用しており、いわゆる一般民事系事務所からの中途採用実績も多数ございます。一般民事での経験は企業法務の業務にも役に立つと、当事務所は考えているからです。
一般民事と企業法務の業務内容やその相違点、そして一般民事の経験が企業法務のキャリアにおいてどのように活かされるのかについて、詳しく解説していきます。
この記事の目次
一般民事と企業法務とは?その相違点
一般民事と企業法務は、弁護士が取り扱う法律業務の中でも代表的な分野ですが、その性質や対象とするクライアントには違いが存在します。これらの相違点を理解することは、一般民事から企業法務への転職を考える上で、まず前提として重要になります。
クライアントの違い
一般民事の弁護士が主に対峙するのは、個人のクライアントです。これらの個人は、日常生活の中で遭遇する様々な法律問題に直面しており、その内容は多岐にわたります。例えば、離婚や相続といった家族間の紛争、交通事故や不法行為による損害賠償請求、金銭の貸し借りに関する問題、消費者問題などが挙げられます。これらの問題は、個人の生活に直接的な影響を与えるため、弁護士はクライアントの感情や個々の事情に寄り添いながら、法的解決を目指すことが求められます。
一方、企業法務の弁護士が主なクライアントとするのは、企業をはじめとする法人です。その規模は中小企業から大企業、上場企業まで様々であり、業種も多岐にわたります。企業が抱える法律問題は、その事業活動に密接に関連しており、契約書の作成や審査、株主総会の運営、M&A、知的財産権の保護、労働問題、コンプライアンス体制の構築など、多岐にわたります。企業法務においては、クライアントである企業の事業目標や経営戦略を理解した上で、法的な側面からサポートすることが重要となります。
扱う業務の違い
一般民事の弁護士が取り扱う業務は、紛争の解決が中心であり、例えば、個人間の契約に関するトラブル、不動産に関する問題、消費者と事業者間の紛争などです。これらの案件では、個々の事案に応じたきめ細やかな対応が求められることが多く、時には感情的な対立を伴うこともあります。
対照的に、企業法務の弁護士が扱う業務は、企業の事業活動全般に関わるものが中心です。これには、企業が事業を行う上で必要となる各種契約書の作成・審査、新規事業の立ち上げや事業提携に関する法的検討、企業組織再編の手続き、知的財産権の取得・管理、不祥事発生時の対応、訴訟や仲裁などの紛争解決などが含まれます。企業法務においては、個々の法律問題だけでなく、企業の持続的な成長やリスク管理といったより広い視点からの法的アドバイスが求められることが特徴です。
扱う法領域の違い
企業法務の大きな特徴の一つとして、会社の運営やビジネス活動を直接的に規制する法律を扱う頻度が高いことが挙げられます。代表的なものとしては、会社の設立、組織、運営に関する基本法である会社法、金融商品の取引や金融機関の活動を規制する金融商品取引法、資金移動や決済サービスに関する資金決済に関する法律などがあります。これらの法律は、企業の事業活動を適法かつ円滑に進める上で不可欠な知識であり、企業法務の弁護士はこれらの法律を深く理解し、クライアントに適切なアドバイスを提供する必要があります。
一方、一般民事の弁護士も、契約法や民法といった法律を扱いますが、その焦点は個人の権利義務関係や日常生活における紛争解決に置かれることが多く、上記のような企業活動に特化した法律を専門的に扱う機会は比較的少ないと言えます。
一般民事と企業法務の類似点

ここまで、一般民事と企業法務の主な相違点について解説してきましたが、これらの二つの分野は完全に独立しているわけではありません。実際には、両者の間には重なり合う部分も少なくありません。
例えば、企業も、個人と同様に、金銭の貸し借りに関する問題や、不動産に関する紛争、債権回収といった、一般民事的な相談を弁護士にすることがあります。このような場合、企業法務を専門とする弁護士であっても、一般民事の知識や経験が活かされることになります。
また、訴訟などの法的手続は、クライアントが企業であろうと個人であろうと、その基本的な流れや適用される法律に大きな違いはありません。訴状や準備書面といった書面の作成方法、裁判所とのやり取り、証拠の収集・提出など、訴訟遂行に必要なスキルは、一般民事と企業法務の両方において共通して求められます。
一般民事のキャリアは企業法務にどう活きる?
一般民事の経験を持つ弁護士が企業法務への転職を考える際、最も気になるのは、これまでの経験が企業法務の分野でどのように活かせるのかという点でしょう。結論から言えば、一般民事のキャリアで培われたスキルや経験は、企業法務においても非常に価値のあるものであり、多くの面で応用が可能です。
紛争対応の場面
前述の通り、訴訟手続きは一般民事と企業法務に共通する重要な業務の一つです。一般民事の経験を通じて培われた訴訟スキルは、企業法務においても直接的に活かすことができます。
訴訟において、訴状をはじめとする各種書面の作成は、弁護士の重要な役割の一つです。一般民事の案件を数多く手掛ける中で、事実関係を正確に把握し、法的根拠に基づいて論理的に構成された書面を作成する能力は、企業法務においても不可欠です。企業間の紛争においても、その主張を明確かつ説得的に裁判所に伝えるためには、高度な書面作成能力が求められます。一般民事の経験を通じて磨かれたこのスキルは、企業法務の訴訟においても大いに役立つでしょう。
予防法務の場面
企業法務への転職を考える弁護士の中には、ビジネスに関する法律や企業特有の業務経験がないことに不安を感じる方もいることもあります。しかし、この点についても過度に心配する必要はありません。
企業法務系の弁護士にとっての日常業務は契約書作成や契約書チェックですが、これらは、いわゆる「予防法務」であり、そして「予防法務」とは、紛争を予防するための法務です。
すなわち、「予防法務」とは、まだ実際に紛争が顕在化していない段階で、その契約に関して将来的に紛争が生じた場合において、契約書の条項が依頼者にとって妥当かつ有利な結論を導く内容になっているかを見極め、必要に応じて修正を加えるといった実務です。したがって、予防法務を適切に遂行するには、「将来的にどのような紛争が生じ得るのか」を想定し、かつ「その訴訟がどのような経緯をたどり、最終的にどのような判決となる可能性があるか」といった点を予測できる能力が求められます。
この意味で、紛争処理を手がけてきた経験は、予防法務にも役に立つのです。
業務のマネジメントスキル
一般民事の弁護士は、企業法務の弁護士と比較して、比較的規模が小さく、期間の短い案件を多く担当する傾向があります。そのため、年次の浅い段階でも、個々の弁護士が案件の開始から終了までを主体的に管理し、責任を持って遂行する経験を多く積んでいる傾向があります。
相談の受付から事件の解決まで、一連のプロセスを一人で担当し、案件を最初から最後まで責任を持って完遂した経験は、事件の見通しを立てる力、必要な情報を収集・整理する力、関係者と円滑にコミュニケーションを取る力、そして期日管理能力など、総合的な業務遂行能力を養うものだと言えるでしょう。
一般民事で培われた上記のような能力は、企業法務においても非常に重要なスキルとなります。企業法務の案件は、一般民事よりも規模が大きく、複雑な場合もありますが、その基本的な進め方や必要な管理能力は共通しているからです。

まとめ
この記事では、一般民事の経験を持つ弁護士が企業法務への転職は十分に可能であり、その経験が企業法務においても大いに役立つことを解説してきました。一般民事と企業法務には、クライアントや扱う業務、求められる法律知識などに違いがあるものの、訴訟スキルや紛争対応能力といった弁護士としての基本的なスキルは共通しており、一般民事の経験を通じて培われたこれらのスキルは、企業法務においても直接的に活かすことができます。
また、企業法務、特にITやベンチャーといった成長分野においては、常に新しい知識や挑戦が求められるため、一般民事の経験年数に関わらず、意欲と学習意欲があれば、十分に活躍のチャンスがある、という側面もあります。モノリス法律事務所は、第二新卒からシニアアソシエイトまで幅広い層の弁護士を積極的に募集しており、一般民事の経験を持つ弁護士の応募も歓迎しています。