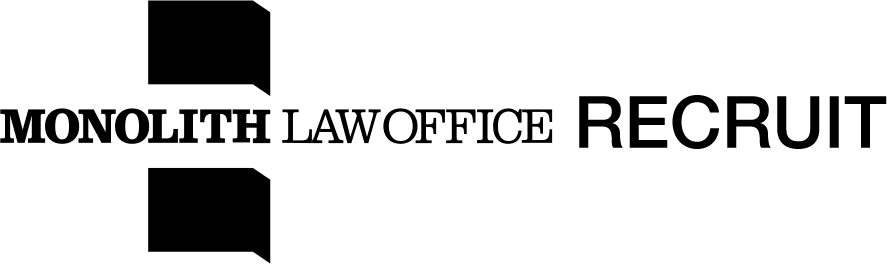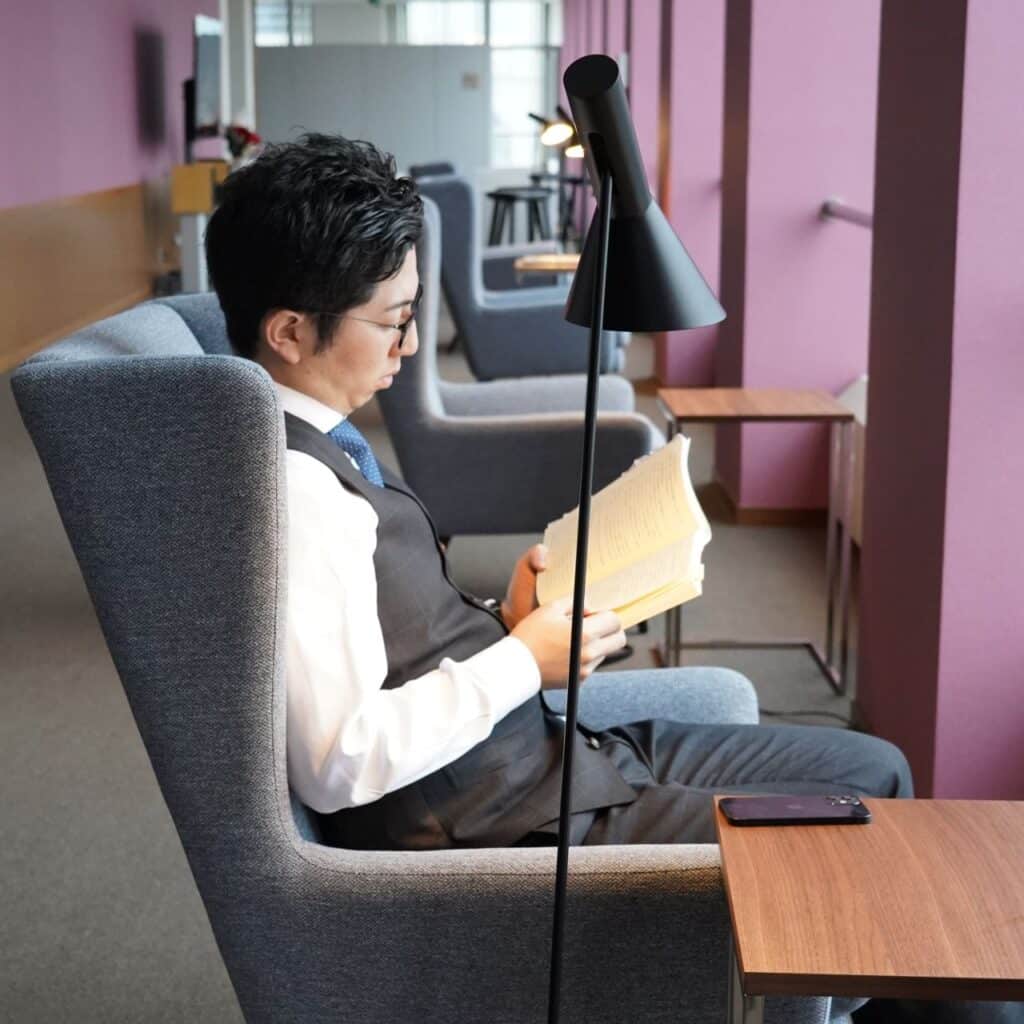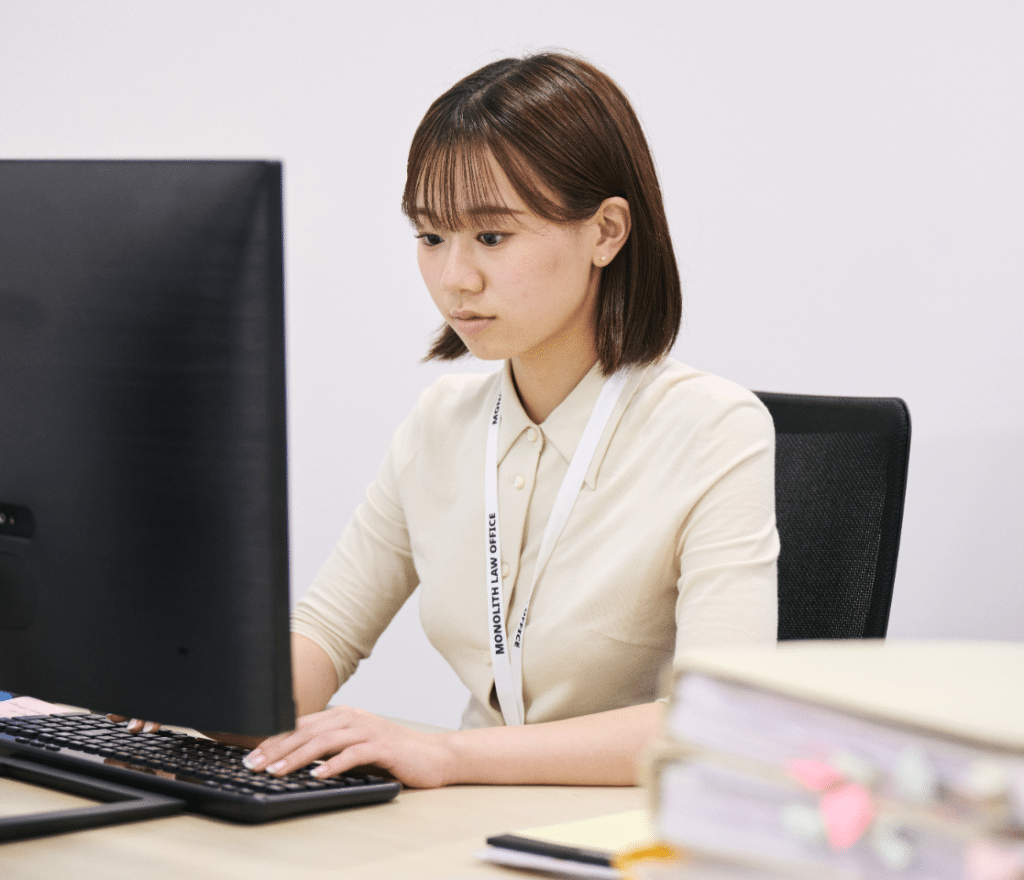企業法務弁護士は年次が上がるとどう業務が変化するのか:河瀬季(代表弁護士)
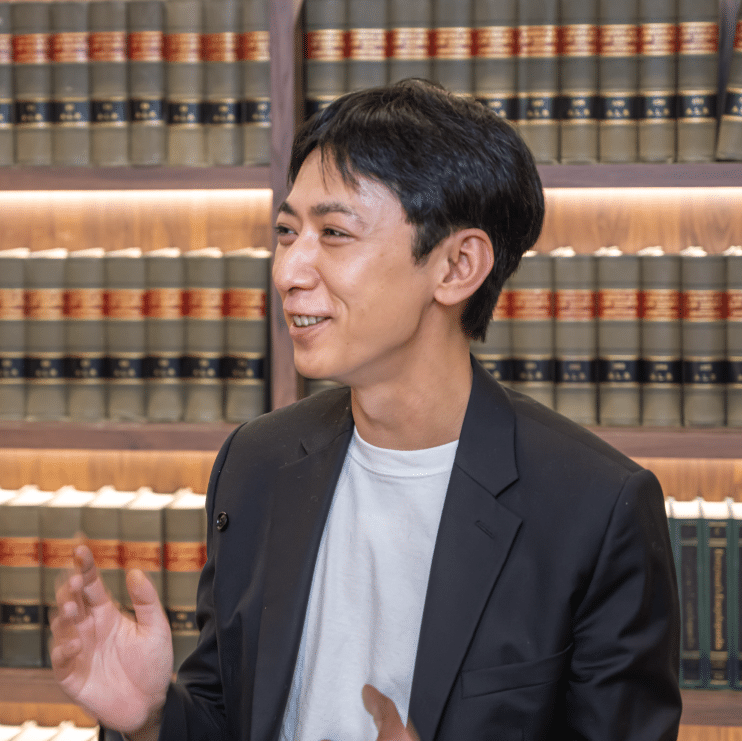
企業法務系の法律事務所に所属する弁護士の業務内容について、なかなか具体的にイメージできていない方も多いように思えます。特に、「年次が上がると、どのように業務が変化していくのか」という点は、実際にそうした事務所で働いた経験がないと、なかなか分からないのではないでしょうか。「企業がクライアントで、大規模な案件も扱う」「年次が進むと『営業』の能力も求められる」といった、ステレオタイプなイメージが、もう少しだけ具体的なものになるよう、解説します。
この記事の目次
企業法務系法律事務所における業務の行い方
企業法務系の法律事務所の特徴の一つは、「誰かが一人で行う業務」がほぼ存在しない、ということでしょう。例えば、企業法務系の法律事務所にとって「一般的・典型的」な業務と言えるような、クライアントが検討しているビジネスの適法性検討・業務委託契約書の作成、といった業務であっても
- クライアントと会話をしてそのニーズを汲み取る役割
- 契約書や報告書のドラフト、リーガルリサーチを行う役割
- 契約書の修正や報告書の校正などを行う役割
は、「先輩弁護士と後輩弁護士」といったように、年次の異なる複数の弁護士間で分業されることが通常です。これは
- クライアントのビジネス(やニーズ・技術的知識)を理解して法的に重要なポイント等を抽出する部分は専門性が高い
- リーガルリサーチなどの業務は(相対的に)専門性が低い一方で、工数が多い
- 契約書等の校正は、ヒューマンエラー回避のために複数人で行われる方が確実
といった理由によるものです。そして、上記のような傾向は、資金調達、M&A、上場支援など、大型の案件ほど、強くなります。
若手弁護士(2~4年目頃まで)の業務内容
数年目程度までの若手の弁護士の業務は、上記の例で言えば、「2.契約書や報告書のドラフト、リーガルリサーチを行う役割」という部分が中心となります。そして、そうした業務には
- クライアントのビジネスやニーズ、技術的知識等を理解している必要はなく、それらは自分以外の先輩弁護士によって「翻訳」された状態で伝えられることを期待して良い
- ただ、そうした先輩弁護士からの指示を、法的理論に関する知識等を前提として、整理された形で理解する必要はある
- 複数の案件に関する指示が出されている場合に、それらの納期や見込工数などを踏まえて、適切なタスクマネジメントを行う必要はある
- そのプロセスの中で、自分ができないことがある場合は、なるべく速やかにそのことに気付いてヘルプを求めることが求められる
といった性質があります。これらは、上記で例として挙げた「クライアントが検討しているビジネスの適法性検討・業務委託契約書の作成」に限らず、訴訟等の紛争処理系、M&Aなどの大型案件など、あらゆる業務に関して共通です。一つ付言すれば、「大型案件」という言葉の意味は
- 案件全体のサイズは「大型」であり、従って、「クライアントのビジネスやニーズ、技術的知識等」を理解して全体のマネジメントを行うためには高度な知識や経験等が必要となる
- しかし、分解されていく1個1個の部分、例えば「当該M&Aのためのデューデリジェンスの対象である、ある1個の業務委託契約書のチェック」という部分は、必ずしも専門性が高くない
- ただし、そのチェックが遅れたりすると、全体のスケジュールに重大な悪影響を及ぼす危険性がある(具体的にイメージしにくいという方向けに一個具体的な例を挙げれば、「M&Aの実行日をいつにするか、経営者同士でテーブル上で事実上合意されているケースも多いが、株主総会の招集通知を出すのが1日遅れたせいで、計画通りの進行が不可能になり、ディールブレイクすることだってあり得る」)
- このため、自分ができない場合は、なるべく速やかにヘルプを求めないと、重大な問題が生じる危険性がある
ということです。上記のような「性質」が、より顕著になる、ということです。
中堅弁護士(3~8年目頃まで)の仕事内容
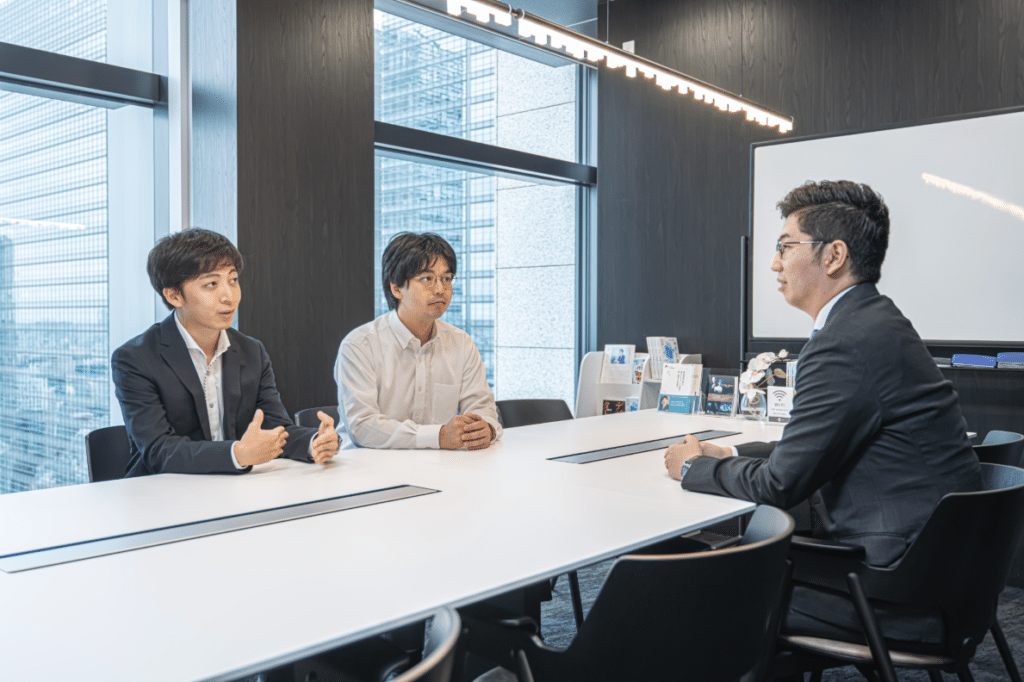
上記のような仕事を行っていくと、徐々に、「事務所の顧問先企業を担当する」という立場、ある案件をマネジメントする立場になっていくことになります。それは、「クライアントのビジネス(やニーズ・技術的知識)を理解して法的に重要なポイント等を抽出する」という部分を自分が担当して、自分以外の後輩弁護士に、「契約書や報告書のドラフト、リーガルリサーチ」といった業務を担当させる立場になる、ということです。
この立場になるために必要なのは、基本的には、若手弁護士としての業務経験、ということになるでしょう。前述のように「翻訳」された指示を受けて業務を行う経験を積んでいけば、「何故その翻訳ができたのか」という部分、つまり、ビジネス・ニーズ・技術的知識への理解が、少しずつ進んでいくはずだからです。
ただし、以下のような留保はつくことになります。
- 企業法務系の法律事務所にとって「一般的・典型的」な業務である、クライアントが検討しているビジネスの適法性検討・業務委託契約書の作成、といった業務では当該クライアントを「担当」するが、そのクライアントから大型案件の依頼があった場合は先輩弁護士に「担当」して貰えば良い
- 大型案件でなくても、難解な案件である、何らかの理由でトラブルが発生して対応が難しい、など、困った場合は先輩弁護士にバトンタッチして貰えば良い
つまり、先に述べたような「分業」、つまり
- 先輩弁護士が、クライアントからのヒアリングや「翻訳」、書面の校正等を行い、当該案件をマネジメントする
- 後輩弁護士が、ドラフトの作成やリーガルリサーチなどの業務を行う
という分業の、「先輩弁護士」の側、マネジメントを行う側に求められる知識や経験等は、案件が大型である・難解である・トラブルが発生した、といった場合ほど、高度なものになります。中堅弁護士は、「高度な場合には先輩弁護士にバトンタッチを求めて良いという留保付きで、それ以外の場合に前者を担当する」といった業務を行う事になる訳です。
また、このポジションを担当するということは、(基礎的な教育が行われている)新人弁護士等に仕事を教えながら案件を処理する、ということも、求められるようになるということです。
こうした、若手から中堅弁護士に求められる能力に関しては、以下の記事でも解説しています。
シニア・パートナー弁護士の仕事内容
パートナーとは、基本的には、上記で言う「バトンタッチ先」がいない立場で、シニアアソは、その一歩手前、ということになります。
ここで出てくる重要なキーワードは、「イレギュラー」だと思います。
企業法務系法律事務所の仕事の多くは、広い意味では、定型的なものです。…この言葉は少しミスリーディングなので詳しく書きますが、例えば、多種多様なクライアントは、日々、多種多様な新たなビジネスを模索しており、そうした多種多様なビジネスとの関係で必要になった契約書を作成する仕事は、当然に、一つ一つが異なる、それぞれに専門性の高い仕事です。しかし、それでも、それらを貫く一般論としての法律知識等は存在しますし、広い意味で言えば、それらは「定型的」な業務です。ある言い方をすれば、「ほぼ全ての業務を『定型的』なものだと捉えられるような知識や経験等がなければ、安定して高い品質の成果物を作り続けることはできない」とも言えます。
そして、そうした(広い意味で)定型的な業務を行うだけであれば、専門性の高い企業法務系の法律事務所で日々経験を積んでいけば、中堅弁護士あたりの年次までで、一通りの仕事をすることはできようになると思います。そこから先、いわゆるクライアントマネジメントを行うために本当に重要なのは、「イレギュラー」への対応です。クライアントとの信頼関係を維持できる、クライアントから紹介を受けて新たなクライアントを獲得できる弁護士とは、イレギュラーな事態の発生時にこそ、かえってクライアントの信頼を強化できる、そのために必要な判断と対応を行うことができる感覚や能力を持っている弁護士だからです。
これは基本的には、経験の問題だと思います。司法試験受験生向けに書けば
- 法律を勉強し始めたばかりの頃に司法試験の過去問を見ても、「全体として未知な問題」としか思えないはず
- しかし司法試験に合格する年には、過去問を見た際に、「あの最高裁判決をベースに、この法的論点とこの法的論点が追加されていて、1箇所だけ未知なので、この部分はアドリブ的に書かなければいけないが、あの本で見たあの枠組を転用できる」といったように分析できるはず
というような問題です。知識と経験、それらを前提とした分析が、「イレギュラー」への対応、クライアントマネジメントの基本です。
若手から中堅、パートナーへのステージの上がり方
企業法務系弁護士のキャリアパスは、基本的には、「前のポジションでの知識や経験等を積めば、次のポジションに進むことが出来る」というように、連続的に設計されています。具体的には
若手弁護士として、「翻訳」された指示を元に、書面のドラフト作成などの業務経験を積んでいけば、その「翻訳」を行う側として必要な知識等も身についていく。その意味で、案件をマネジメントする側の素養も身につく。
中堅弁護士として、「定型的」な業務のマネジメントなどの業務経験を積んでいけば、「イレギュラー」な案件等への対応を行うために必要な知識等も身についていく。その意味で、クライアントマネジメントを行うための素養も身につく。
という構造です。
ただ、最後に付言すれば、どのポジションの業務に楽しさややりがいなどを感じるか、ワークライフバランスをどう考えるかは、狭義に「人それぞれ」の問題だと思います。この記事では、具体的なイメージを持ちやすいように、具体的な年次を記載しましたが、これは、「この年次を超えても上の階層に上がらないこと、それ自体をネガティブに捉え、例えば退職勧告を行う」といった意味ではありません。