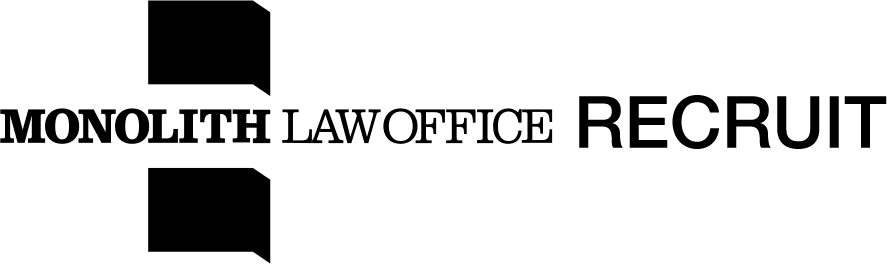言葉も文化も越えて──多国籍チームと歩む法律の現場

ブラジル出身の弁護士。ブラジルで弁護士資格を取得し、日本でのキャリア形成を目指して来日。修士課程を修了後、2023年にモノリス法律事務所に入所。現在は多国籍なメンバーと協働し、国際案件に柔軟に対応することで、日本と世界をつなぐ新たな法律実務を可能にするよう取り組んでいます。
この記事の目次
生まれ育ったブラジルから、日本で挑むキャリア
私はブラジルで生まれ育ち、ブラジルで弁護士として6年間勤務しました。幼い頃から日本に親しみを抱いており、現地の日本人学校で日本人教師から日本語や日本文化を学ぶ機会に恵まれました。文化的にも、西洋の価値観よりも日本の価値観に共感することが多く、自然と「日本でキャリアを築きたい」と考えるようになりました。
ブラジルでの仕事でも日本に関わる機会が多く、現地で事業を展開する日本企業のサポートなどを担当しました。そうした実務経験を重ねる中で、日本との結びつきがさらに強まりました。
モノリスで見つけた成長の場

2021年に日本で修士課程を学ぶために来日した際、モノリス法律事務所の求人を知り、応募しました。まず惹かれたのは、モノリス法律事務所が柔軟な働き方を推進している点でした。日本の法律事務所ではまだ珍しいリモートワークやフレックスタイム制度があり、従業員が信頼され、自律的に業務に取り組める環境に強く魅力を感じました。
また、モノリスでの業務内容は、私自身のこれまでの実務経験や将来の目標とも合致していました。特に国際色豊かな職場環境に惹かれ、モノリス法律事務所のウェブサイトで多くの外国人メンバーが活躍しているのを知り、「ここなら自分の力が活かせる」と感じました。英語でのコミュニケーションが可能であることも、非常に働きやすいと感じた大きな要因でした。
服装に関しても、クライアント対応時以外はカジュアルでよい点が新鮮でした。法律業界には堅苦しく上下関係が厳しいイメージがありますが、モノリス法律事務所はそれを覆し、人間味のある、親しみやすい法律の専門家像を築こうとしていると感じています。
案件の進め方についても、各人に裁量があり、クロスボーダーチームでは上下関係にとらわれることなく、フラットな関係で協力し合っています。スケジュール調整で問題が生じた場合も、チーム全体で話し合い、柔軟に解決策を見つけていきます。非常に協力的な職場だと感じています。
多国籍メンバーと共に築く新たな協働の形
2023年に修士課程を修了し、正式にモノリス法律事務所に入所しました。当時、フォーリンアソシエイトは私を含め2名のみで、日本での勤務も初めてだったため、日本の法律制度や職場文化など、すべてが新しい経験でした。日本語でのやり取りや文化の違い、ビジネスマナーに戸惑うこともありましたが、チームの温かいサポートのおかげで少しずつ馴染むことができました。
日本の法律実務に実際に関わることができたのは大きな学びとなり、チームの雰囲気や働き方にも強く魅力を感じました。その後は日本人弁護士と連携し、日本語の法律用語も使いこなせるようになり、クロスボーダー案件を担当するようになりました。契約書のレビューやドラフト作成、海外クライアントとの英語でのやり取り、法制度の調査など、幅広い業務に取り組んでいます。案件の量も質も高まり、チームとしての成長を日々実感しています。
大きな節目として、日本の法律事務所として初めて「Eurojuris(ユーロジュリス)」という欧州の法律事務所ネットワークに加盟したことが挙げられます。これは大きな責任を伴う仕事であり、日本の代表として国際社会と関わる重みを強く感じました。Eurojurisに加盟したことにより、欧州の法律事務所や日本市場に関心を持つ企業とのウェビナーを共催したり、渋谷区のスタートアップ支援プログラムと連携し、日本におけるビジネス機会に関する議論を主導しています。こうした取り組みを通じて、海外の法律事務所や将来のクライアントとの関係構築が進んでいます。
法と文化をつなぐ柔軟な対応力
クロスボーダー業務においては、異なる法制度や文化的背景の違いを理解し、調整する力が求められます。例えば日本では名刺交換が一般的ですが、国際的な場ではLinkedIn(リンクトイン)などを使う人が多くいます。ポルトガル語には「dance conforme a música(音楽に合わせて踊れ)」という表現がありますが、まさにその柔軟な姿勢こそが、国際法務では重要になります。
私たちのチームには、ロシア、ドイツ、台湾、中国出身のメンバーが在籍しており、それぞれが専門とする法律知識を活かしながら連携しています。多様な視点を持ち、互いの知識を尊重し合える関係が築けています。
また、文化や法律の背景によってコミュニケーションのスタイルにも違いがあります。控えめな人もいれば、率直に意見を表現する人もいます。民法系とコモンロー系、両方の法体系に通じたメンバーもおり、多角的な視点で法律を検討できるのも強みです。一方で、日本のビジネス慣習や価値観も大切にし、地域に根ざした対応を意識しています。
チームを導く中で見つけた自分の役割

国際案件への関与が増え、メンバーと協力しながら取り組む中で、少しずつ周囲をまとめる役割を担うようになりました。現在は、チームリーダーとして、メンバーそれぞれの強みや専門性に応じて適切に役割を分担することを意識しています。メンバーはそれぞれの国で資格を取得しており、担当分野も自然と異なってきます。例えば、海事法に強いメンバーがいる一方で、私は企業法やデータ保護を主に担当しています。
こうした知識の補完関係が、複雑なクロスボーダー案件を円滑に進める鍵となっています。未知の法域の案件では、その分野に明るいメンバーに相談することで、スムーズに対応することができます。モンゴル、フィリピン、ドイツなどの案件でも同様に対応しており、時間と品質の両面で成果を上げています。
文化的な違いの中でも、特にリスクへの向き合い方に差があると感じています。日本では慎重でリスク回避的な傾向が強い一方、他の国では計算されたリスクを取る姿勢が一般的です。両者のバランスを取ることが大切だと考えています。たとえばEurojuris(ユーロジュリス)への加盟を検討した際も、費用対効果に懸念がありましたが、長期的な視野での戦略的判断として前向きに踏み切りました。結果として人脈が広がり、新たな案件や国際的な機会が生まれています。
モノリス法律事務所のもう一つの魅力は、仕事以外でも個人的な交流が盛んな点です。職場の雰囲気は温かく、助け合いながら仕事を進めており、合間に笑い合うことも多くあります。プロとして高い基準を保ちながらも、多様性と包摂性を大切にしているこのチームは、これからの法律事務所のモデルになると感じています。
法務の現場で磨く対話の大切さ
国際的なチームにおいては、法律知識と同じくらいコミュニケーション能力が重要です。どれだけ専門知識があっても、それをうまく伝えられなければ評価にはつながりません。
わからないことは遠慮なく質問し、情報を明確に伝える姿勢が求められます。日本文化では対立や議論を避ける傾向がありますが、私たちのチームでは、オープンな対話と積極的な情報共有が円滑な業務遂行の鍵です。翻訳ツールやAIも活用しながら、伝え方の工夫を欠かさないよう心がけています。
コミュニケーションと信頼が、チームの成功の基盤だと確信しています。意見交換が活発であれば信頼関係が生まれ、納期が守られるようになり、仕事がスムーズに進みます。能力が高くても、チーム全体の流れや優先順位が理解できなければ、成果にはつながりません。
日本で働く中で、相手の立場や文化を尊重する姿勢が自然と身につきました。以前よりも広い視野で物事を捉え、チームやクライアントにとって何がベストかを考えられるようになったと思います。
結局のところ、私たちはそれぞれ課題や家族、目標を持つ一人の人間です。だからこそ、仕事の時間を前向きに、互いに敬意を持って過ごすことが何より大切だと感じています。私自身は、「働くために生きる」のではなく、「生きるために働く」という考えを大切にしていて、それが実現できる職場でチームにも恵まれ、日本で法務の仕事を実現しました。
カテゴリー: インタビュー
タグ: インタビュー:弁護士