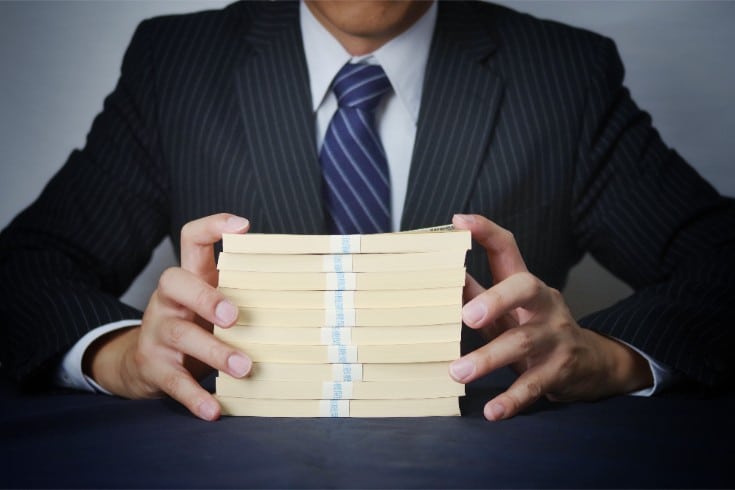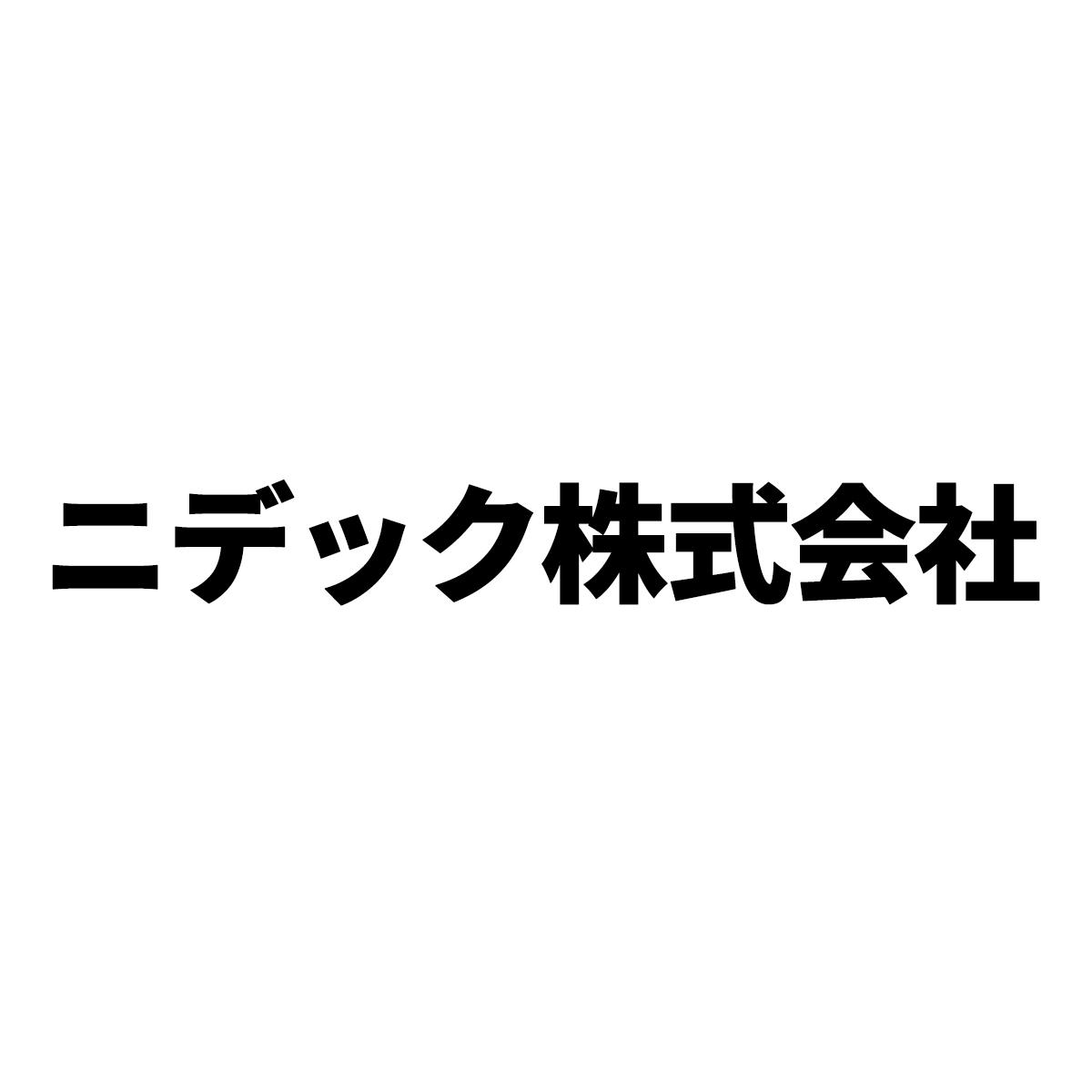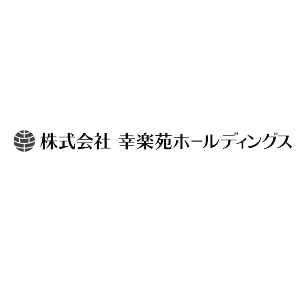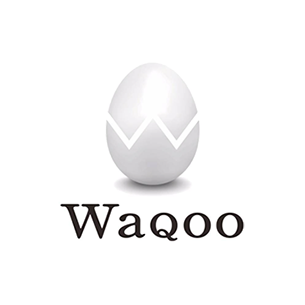補助金・助成金の不正受給対応
IT導入補助金やリスキリング助成金(人材開発支援助成金)といった国の公的支援制度において、
多くの企業が、意図せず、不適切な勧誘によって不正受給問題に巻き込まれています。
モノリス法律事務所は、このような複雑な状況に陥った企業をサポートする専門家として、問題解決に向けた支援を行います。
会計検査院の調査によると、リスキリング助成金(人材開発支援助成金)では、調査対象となった113事業者のうち約28%にあたる32事業者で不適切受給が発覚し、その不正金額は約1億700万円に上ります。同様に、IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)においても、376社の445案件中、約8%にあたる30社41案件で不正が認定され、不正受給総額は約1億812万円に達しています。これらの数字は、不正受給問題が一部の例外的なケースに留まらず、広範にわたる構造的な課題を抱えており、社会問題と言えることを示しているでしょう。
MENU
「実質無料」「キックバック」の不正受給
IT導入補助金やリスキリング助成金などの補助金・助成金の不正受給の場面では、「実質無料」や「キックバック」といった甘言による勧誘が横行していることが指摘されています。これらの手口は、単なる個別の不正行為に留まらず、助成金制度の理解不足や、悪質な支援事業者による組織的・計画的な勧誘スキームが背景にあることによるものです。これにより、多くの企業が意図せず不正受給に加担させられ、公金を不正に受給した者としての責任を問われる一方で、悪質な業者に騙された「被害者」としての側面も持つという複雑な状況に置かれています。
リスキリング助成金の不正事例としては、訓練費用を支払った後に業務協力名目での返金、感想文提出等の条件での高額謝礼支払い、経費の水増し請求、実態のない訓練などが挙げられます。会計検査院の調査では、約3割の事業者で不正が発覚しています。
IT導入補助金の不正事例では、IT導入支援事業者(ベンダー)による資金還流、すなわちキックバックが主な手口です。例えば、「業務協力費」や「広告掲載料」などの名目で資金が事業者に還流され、実質的な自己負担がゼロになるスキームが多発しています。また、架空のITツール導入、水増し請求、実態のない契約書や領収書の作成、導入したITツールが実際には使用されていない、あるいは申請時に記載した機能が実装されていないにもかかわらず補助金を受給するケースも確認されています。会計検査院の調査では、15社のITベンダーが関与し、1978事業(補助金交付額約58億円相当)に上る不正が確認されています。
また、人材開発支援助成金で悪用されるケースが多い、いわゆる「親子会社スキーム」など、類型的に問題視されているスキームは他にも存在します。(参考:人材開発支援助成金の「親子会社スキーム」と不正受給リスクを弁護士が解説)
不正受給が社会問題となっている補助金・助成金

IT導入補助金
調査対象となった445案件のうち41件、30事業主体で1.4億円以上の不正受給が指摘されるなど、大規模な摘発が行われています。

リスキリング助成金
訓練機関から「広告宣伝レビュー代」や「感想文提出」などの名目で金銭が返金されるケース等が摘発されています。

定額制訓練
定額制訓練型でも不正受給の摘発が行われており、特にいわゆる「親子会社スキーム」などの類型が問題となっています。

その他
雇用調整助成金・持続可給付金・事業復活支援金・デジタル化応援隊事業等でも不正受給が社会問題となっています。

補助金・助成金の不正受給の現状
助成金・補助金制度の大原則は、事業主が費用を全額負担し、その一部を国が助成するというものです。しかし、「実質無料」「キャッシュバック」「自己負担ゼロ」「100%受給保証」といった甘言を用いた勧誘が横行しており、これらはこの大原則に明確に違反する行為です。
例えば、「IT導入補助金2025」の公式ウェブサイトは、「IT導入補助金は不正を絶対に許しません」として、「ITツールを実質無償で提供する、減額する等の販売行為」を明確に「不正行為」と挙げています(不正行為にご注意ください | IT導入補助金2025)。不正なキックバックは名目ではなく実質によって判断されるため、資金還流のための名目が何であるかにかかわらず、実質的なキックバックは不正受給となります。

リスキリング助成金の2025年12月大規模摘発
2025年12月19日、東京労働局は、リスキリング助成金において、特定の訓練機関が関与した案件として、62,172,000円の不正受給を公表しました。そして、当該訓練機関であるコンサル会社が12月25日に行った報告会によれば、返還対象となる企業は、全国で178社に上り、その返還総額(ペナルティを含む)は約19億4,000万円という巨額に達することが判明しました。これは、かつてないほどの大規模な不正の摘発です。
この不正に関与してしまった企業は、「社名の公表回避」と「5年間の申請停止処分(不支給措置)の撤回」を最優先事項として対応を行う必要があります(リスキリング助成金、特定の訓練機関が関与した案件で返還対象178社19億円の不正受給)。
不正受給のペナルティ

金銭的ペナルティ
不正に受給した助成金の全額返還義務に加え、返還額の20%に相当する加算金(違約金)が追加で課せられます。さらに、不正受給日の翌日から返還完了日まで延滞金が発生し続け、IT導入補助金では年10.95%と高額になる場合があります。

事業者名の公表
行政処分として、自主申告ではない場合、事業主名、代表者名などが公表されることがあります。特に支給決定取消等を行った額が100万円以上の場合は原則公表対象です。取引先からの信頼喪失、金融機関からの評価低下、風評被害など、企業の信用が失墜します。

受給資格の喪失
不正受給決定日から5年間、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金などの雇用関係助成金を含む、全ての補助金・助成金の受給資格を喪失します。企業によっては深刻な悪影響となります。全額が返納されていない場合は期間が延長されます。

刑事罰の可能性
悪質な不正受給は、刑法第246条に定める詐欺罪に問われる可能性があります 。また、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性もあります。

「知らなかった」では済まない代表者の責任
補助金は国民の税金を原資とする公的資金であり、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金等適正化法)によって、その適正な執行が厳しく求められています。このため、補助金や助成金に関する不正行為は単なる契約違反ではなく、公金に対する背信行為といえます。
「代理人に任せていた」「自分は知らなかった」といった主張は、原則として認められません。たとえ第三者が不正を主導した場合でも、最終的な責任は申請事業者、特にその代表者に帰属するという厳格な原則が適用されます。これは、公金である以上、その管理・執行には極めて高い透明性と責任が求められるためです。企業は、悪質な業者に騙された「被害者」である側面を持つ一方で、公金を不適切に扱った「加害者」としての側面も持ち合わせるという、複雑な立場に置かれることになります。
不正受給の自己申告と弁護士のサポート
不正受給問題は「時間との勝負」であり、初動の対応が極めて重要です。弁護士への早期相談は、複雑な法的手続きの理解、法的なリスクの正確な評価、労働局や捜査機関への適切な対応支援、自主返還手続きの代行・サポート、そして経営者や担当者の精神的負担の軽減といった点で非常に有用です。
自主申告の推奨とそのメリット
既に不正受給を行ってしまった事実を認識した場合、労働局や補助金事務局による調査が開始される前に「自主申告」を行うことが、最も推奨される対応です。自主申告は単なる「自白」ではなく、企業が「被害者としての立場」を明確にしつつ、当局との信頼関係を構築し、ペナルティを最小化するための手段として機能します。
自己申告を行った事業主に関しては、原則として事業主名の公表が行われない方針が示されており、企業の信用力やブランドイメージを維持できる可能性が高まります。刑事告発回避・延滞金や違約金の軽減・企業の社会的信頼維持といった観点からも、自主申告にはメリットがあると言えます。
弁護士は、複雑な自主申告プロセス全体を設計・実行するパートナーとしての役割を果たすことができます。クライアントの状況を正確に分析し、自主申告のタイミング、内容、当局への説明方法、そしてその後のフォローアップまで、一連の戦略を立案・実行することで、企業は安心感を持って問題解決に取り組むことが可能になります。
補助金・助成金別の詳細情報
モノリス法律事務所は、補助金や助成金の不正受給を行ってしまった企業をサポートする法律事務所として、各種補助金・助成金別の詳細情報を解説する記事を公開しています。
当事務所の具体的なサポート内容
ヒアリングと検討
ヒアリング前には、案件に関する既存資料の収集・確認、関連法規制や契約書の事前精査を徹底します。ヒアリングでは、事案発生の具体的な時系列経緯、関与した人物・業者の詳細情報、契約書・請求書・領収書等の関連書類の有無、被害金額や未回収額の正確な算出、クライアント側の対応履歴と証拠保全状況などを必須確認事項として網羅的に聴取します。ヒアリング後は、内容の議事録作成と承認、不明点の整理、収集した書類のデジタルアーカイブ化、今後の進行スケジュールの策定と共有を行い、二次被害防止のため個人情報管理を徹底します。これらの情報に基づき、法的リスクを評価し、クライアントにとって最適な対応方針(自主申告の有無、業者への請求の可否、行政への対応順序など)を検討し、報告書を作成致します。
行政への通知・交渉
不正受給問題は、クライアント、不正業者、そして複数の行政機関(厚生労働省、経済産業省、警察、会計検査院など)が複雑に絡み合う多角的な交渉の場です。管轄の都道府県庁・経済産業局、地方自治体の消費生活センター、業種別の監督官庁、警察(詐欺等、犯罪性の高い案件)など、通知すべき行政機関を特定します。発覚前の自主返還を行うのと同時に、不正業者の情報提供を行い、クライアントの「被害者としての立場」を明確化します。その際には、通知に必要な書類・情報(事案概要報告書、関係者一覧、証拠書類、被害者リスト、対応履歴・交渉記録)を準備します。行政との面談・交渉時に弁護士が同行し、事前に行政の権限範囲を把握し、具体的な要請事項を明確にします。誠意ある対応と積極的な情報開示、返金計画の提案と実行可能な分割払いの交渉を通じて、ペナルティの軽減を目指します。業者への返還請求と行政への返還を並行して進めることで、経済的損失の最小化を図ります
業者への返金請求
不正受給の背景には、悪質な業者の存在が指摘されています。特に悪質な事案では、業者への返金請求も検討すべきです。
まず、民法上の不当利得返還請求(民法第703条)、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法第415条)、契約書における特約条項、消費者契約法上の取消権(第4条)の適用可能性を検討し、最適な法的根拠を特定します。次に、請求金額の明確化(元本・遅延損害金の区別)、返還理由の具体的記載(法的根拠を含む)などを明記した書面を作成し、内容証明郵便などでの送付を行い、業者との交渉を行います。交渉が不調に終わった場合は、催告書、最終通告書の送付、少額訴訟または支払督促の検討、訴訟提起に向けた準備を行います。
モノリス法律事務所の特徴
モノリス法律事務所は、元ITエンジニアで企業経営経験のある代表弁護士の下、IT・インターネット・ビジネスに関わる法務をその中心業務としています。単なる法律知識だけでなく、ITツールやリスキリングの実態を深く理解しています。IT導入補助金の「機能未実装」や「水増し請求」といった技術的な不正手口を正確に把握し、その実態を行政機関に論理的かつ説得力をもって説明することも可能です。単なる法律論に留まらない、実態に即した問題解決能力が、当事務所の特徴です。

深い知見と実績
リスキリング助成金、IT導入補助金などの不正受給問題に関して、会計検査院の調査結果や具体的な手口(「実質無料」「キックバック」など)を深く理解し、多数の相談実績があります 。

迅速な対応
不正受給問題における「初動対応の重要性」を深く認識しており 、スピーディーなヒアリングから、自主申告手続き、業者・行政との交渉まで、迅速かつ実効的なサポートを提供致します。

組織性と全国対応
当事務所は、23名の弁護士が所属する組織であり、特に行政との面談・交渉時には、全国のクライアント様との関係で、弁護士が同行することを原則としています。

ワンストップ
不正受給に関するクライアント対応、不正業者への返金請求、行政機関への通知・交渉、そして将来的なコンプライアンス強化まで、一貫したワンストップソリューションを提供することが可能です。
ご相談から解決までの流れ
モノリス法律事務所では、不正受給問題に直面された企業様が安心してご相談いただけるよう、以下のステップでサポートを提供いたします。
お問い合わせ
ウェブフォームからお問い合わせください。初回相談(オンラインまたは来所)は無料にて、事案の概要をヒアリングいたします。守秘義務を遵守し、安心してご相談いただける環境を提供いたします。
事案精査
事案の時系列、関与者、関連書類(契約書、請求書、領収書、メール履歴、振込記録など)を詳細にヒアリングし、必要な証拠を徹底的に収集・整理いたします。これにより、法的リスク評価と最適な対応方針の策定を行い、報告書を納品致します。
行政対応
適切な行政機関(厚生労働省、経済産業省、会計検査院など)を特定し 、事案概要報告書等の必要書類の作成を支援いたします。行政機関との面談に同行し、情報開示の調整、ペナルティ軽減に向けた交渉を行います。クライアントの「被害者としての立場」を明確にし、誠実な対応をサポートいたします。
返金請求
事案に応じて、不正業者に対して、法的根拠に基づいた書面を作成し、内容証明郵便などで送付いたします。業者との交渉を代行し、和解交渉を進めます。交渉が不調に終わった場合は、訴訟提起の検討と準備を行います。
アフターフォロー
問題解決後も、再発防止のためのコンプライアンス体制構築支援などを提供し、企業の持続的な成長をサポートいたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q.不正受給に心当たりがある場合、何から始めればよいですか?
A.まずは、速やかに弁護士にご相談ください。早期の対応が、ペナルティの軽減や企業名の公表回避につながる可能性が高まります。
Q.「実質無料」で補助金を受け取ってしまいましたが、不正になりますか?
A.助成金・補助金制度は、事業主が費用を全額負担することを前提としています。実質的に自己負担がない場合、不正受給と判断される可能性が極めて高いため、速やかにご相談ください。
Q.弁護士に依頼する費用はどのくらいかかりますか?
A.事案の複雑さや対応範囲によって異なります。初回相談(無料)時またはその後に詳しくご説明し、ご納得いただいた上でご依頼いただく形となります。
Q.自主申告をすると、必ず企業名が公表されませんか?
A.自主申告を行い、速やかに全額返還を行った場合、原則として企業名の公表は行われない方針が示されています。しかし、個別の事案によって判断が異なるため、弁護士にご相談の上、慎重に対応を進めることが重要です。
Q.担当者が勝手に行ったことで、会社に責任はありますか?
A.補助金は国民の税金を原資とする公的資金であり、その適正な執行には高い責任が求められます。「代理人に任せていた」「自分は知らなかった」という主張は原則として認められず、最終的な責任は申請事業者、特にその代表者に帰属します。
料金体系
事案精査
22万円(税込)~法的リスク評価と最適な対応方針の策定
※複数申請の場合などは都度見積
行政対応
完全成果報酬33万円(税込)~事案精査の後に完全成果報酬型にてお受けさせて頂きます
※既に受給済の場合や複数申請の場合、刑事事件化した場合などは都度見積
返金請求
完全成果報酬16.5%(税込)事案精査の後に完全成果報酬型にてお受けさせて頂きます
※訴訟手続を用いる場合などは都度見積