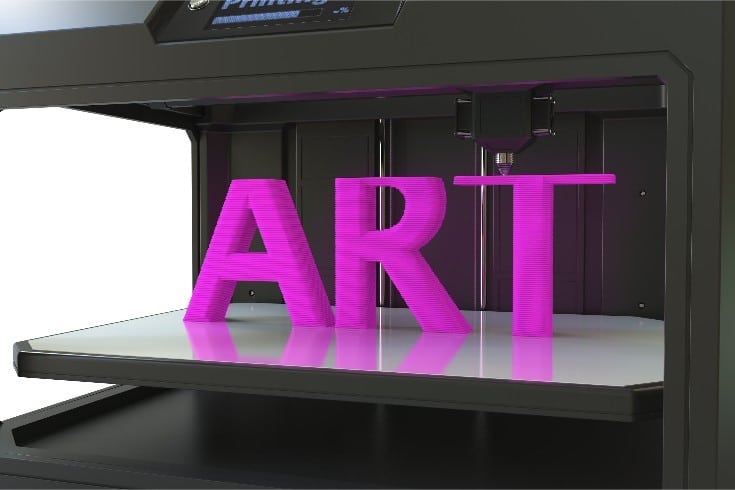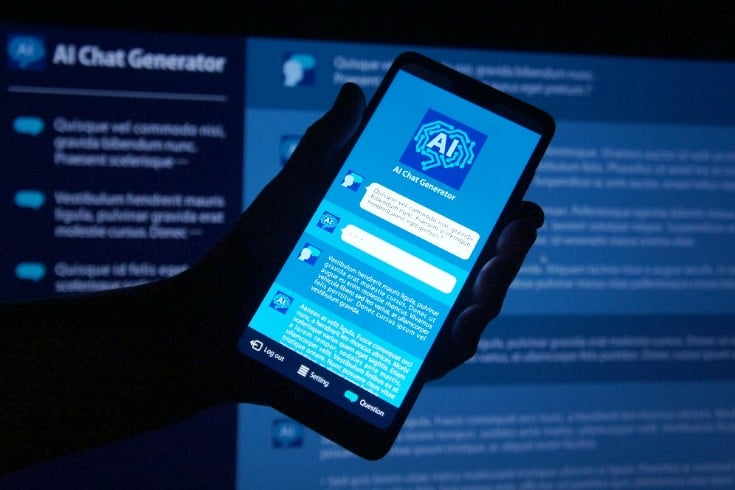暗号資産の最新改正:令和6年度・令和5年度税制改正が企業実務に与える影響と取るべき対応策

日本経済は、デジタル変革を国家戦略の中核に据え、Web3.0やブロックチェーン技術を活用したイノベーションの創出に注力しています。経済産業省(METI)も、このようなフロンティア分野の推進を積極的に後押ししており、特に税制の見直しは、国際的な競争力を確保するための必須の取り組みと位置づけられてきました。法人が暗号資産を事業に活用しようとする際、これまで最大の障壁となっていたのが、従来の法人税制における「期末時価評価課税」の原則でした。これは、暗号資産の売却による収益が実現していないにもかかわらず、未実現の含み益に対して課税が行われる仕組みであり、特に、長期的な事業戦略やエコシステム構築のために暗号資産を保有する企業にとって、予期せぬ多額の税負担と財務の不確実性を生じさせていました。
このイノベーション阻害要因を解消するため、政府は戦略的な税制改正に着手しました。まず、令和5年度(2023年)の税制改正において暗号資産の発行体(イシューア)の負担を軽減する措置が講じられ、さらに、続く令和6年度(2024年)の税制改正では、その適用除外の範囲が、一般事業会社を含む第三者保有の暗号資産にまで拡大されました。本稿では、これらの画期的な税制改正が企業実務に与える具体的な影響を、法令や官公庁の公開情報を根拠に詳述し、企業がこの税制優遇措置を享受するために不可欠となる実務上の対応策について解説します。
この記事の目次
日本のWeb3.0推進と暗号資産の法人税制改革の潮流

日本政府がWeb3.0戦略を推進する背景には、技術革新を阻害してきた税制上の課題を解決し、国際的な競争力を確保するという明確な意図があります。この章では、改正の必要性が生じた従来の税制の構造と、Web3.0政策の方向性を解説します。
従来の「期末時価評価課税」の原則
改正前の日本の法人税制においては、法人が保有する暗号資産は、原則として期末に時価評価を行い、その評価損益を損益に計上することが求められていました。これは、法人税法第61条第1項及び法人税法施行令第118条の7の規定に基づき、棚卸資産以外の資産の評価方法として時価法が適用されていたためです。暗号資産は市場価格の変動が激しいため、この時価評価課税は、企業が事業年度末に多額の含み益を計上した場合、実際の現金収入がないにもかかわらず納税義務が発生するという、大きなキャッシュフローリスクをもたらしました。
イノベーション阻害要因の構造
従来の時価評価課税の構造は、企業が暗号資産を長期的な戦略資産として保有することを強く抑制していました。法人が暗号資産を保有する主な目的は、ブロックチェーンエコシステムへの参画、将来のサービス提供の対価、またはガバナンスへの参加など、長期的な価値創出にあります。しかし、暗号資産の価格が上昇するたびに未実現の含み益に対して課税され、その納税のために他の資金源を充当したり、やむを得ず暗号資産の一部を売却したりする必要が生じていました。
この構造は、特に資金力が脆弱なWeb3.0スタートアップや、新たな技術活用を模索する一般企業の財務安定性を著しく損ない、結果として、企業の戦略的な暗号資産の活用を抑制し、日本の技術開発リソースがより税制上の優位性を持つ海外へ流出する一因となっていました。
令和5年度改正前に検討された時価評価の取り扱い
税制改正の議論が進む中で、暗号資産を用いた複雑な金融取引に関する税務処理の明確化も並行して進められてきました。例えば、令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)では、法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産を譲渡した場合の損益計上について、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までに種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、その時において買戻しをしたものとみなして損益相当額を計上する見直しを行うことが決定されています。この措置は、暗号資産のレンディングやデリバティブといった高度な取引が増加する状況に対応するためのものであり、税制が単なる資産保有だけでなく、暗号資産を介した事業活動全般にわたって適正化されつつあるという潮流を示しています。
転換点となった令和5年度税制改正:暗号資産発行法人の負担軽減
令和5年度税制改正は、法人税制の規制緩和に向けた第一歩であり、主に暗号資産の発行者、すなわちWeb3.0のコアビジネスを担う企業群の負担軽減に焦点を当てました。この改正の適用対象となったのは、法人が発行した暗号資産のうち、当該法人が継続して保有し、かつ短期売買目的でない一定の要件を満たすものです。
この改正の法令上の位置付けとして、法人税法施行令(法令)第118条の7の規定が見直されました。これにより、自家発行した暗号資産の評価方法が「原価法」等によることとされ、含み益課税が適用されない道筋が開かれました。結果として、発行企業は、将来のエコシステム活性化やインセンティブ付与のために自己発行トークンを長期的に保持する場合であっても、未実現の含み益に対する課税リスクを回避できるようになり、トークンエコノミクスの設計における税務上の懸念が大幅に軽減されました。
令和6年度税制改正の核心:第三者保有・市場暗号資産への適用拡大

令和5年度改正により発行体の負担は軽減されましたが、日本のWeb3.0経済圏の成長には、発行体以外の一般事業会社や投資家が安心して暗号資産を保有できる環境整備が不可欠でした。令和6年度(2024年)改正は、このニーズに応える核心的な措置であり、ここからその詳細を解説します。
法人による暗号資産保有のパラダイムシフト
令和5年度改正が発行体の「守り」であったとすれば、令和6年度(2024年)税制改正は、暗号資産の法人税制の規制緩和を一般企業にまで拡大する「攻め」の措置であり、日本のWeb3.0政策において極めて重要な意義を持ちます。この改正の最大のポイントは、発行法人以外の第三者法人が保有する暗号資産について、期末時価評価課税の対象外とする見直しが講じられた点です。
これにより、事業連携を目的とした戦略的なトークン投資を行う一般事業会社や、Web3.0関連プロジェクトに投資する企業が、未実現損益による財務リスクを負うことなく、長期的な視野で暗号資産を保有することが可能となりました。この改正は、多くの企業がデジタルアセットを本格的に事業戦略へ組み込むための決定的な転機となります。
改正の対象となる要件
第三者保有の暗号資産が時価評価課税の適用除外となるためには、以下の二点が主要な要件となります。
- 短期売買目的でないこと。
- 一定の市場暗号資産であること。
「市場暗号資産」とは、特定の要件を満たし、高い流動性を有する暗号資産を指します。重要なのは、これらの暗号資産の保有目的が投機的な短期売買ではなく、企業の長期的な事業目的と結びついていることを客観的に証明することです。
時価評価課税の適用除外を受けるための厳格な実務要件
「短期売買目的でない」という要件を税務当局に証明するためには、単に内部規定を定めるだけでは不十分であり、技術的および法的に、その資産が長期保有目的であることを裏付ける厳格な措置が要求されます。
規制当局の考え方では、税務上の適用除外を認めるためには、法人が保有する資産が投機目的ではなく、実際に長期保有の意図のもとにあり、容易に処分できない状態にあることを客観的な指標で示す必要があるとされています。そのため、法人がこの適用除外を希望する場合、その暗号資産に対して、物理的または技術的に資産の処分が制限されている状態を作り出すことが実務上義務付けられています。
具体的には、法人が適用除外の対象とする暗号資産は、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります 。
- 信託財産とする措置:当該暗号資産を信託財産とすること。
- 技術的措置:当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的な措置の内容を充足していること。
これらの技術的な措置や信託財産の措置に関する詳細な要件は、内閣府令(暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第1項第9号)及び、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)などの自主規制団体の規則(「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則第3条」)に詳細に定められています。企業は、これらの規則の細部を理解し、適用除外の要件を満たす措置を講じなければなりません。
また、適用除外を受けるためには、単に措置を講じるだけでなく、上記の技術的措置や信託財産の措置を講じたことを示す証明資料を添付し、税務当局に所定の届出書を提出する義務が生じます。この手続きは、企業の法務部門、経理部門、そして技術部門が密接に連携しなければ、適切に完遂することはできません。
法人税における暗号資産の期末時価評価課税の適用除外範囲の比較
令和5年度改正と令和6年度改正は、対象となる法人や暗号資産の性質において明確な違いがあり、企業がどの制度を利用できるかを正確に把握するために、その比較は不可欠です。
法人税における暗号資産の期末時価評価課税の適用除外範囲の比較は以下のとおりです。
| 項目 | 令和5年度改正(自家発行) | 令和6年度改正(第三者保有) |
| 対象となる法人 | 発行法人(トークンエコノミクスを主導する企業) | 発行法人以外の第三者法人(一般事業会社、投資会社など) |
| 対象となる暗号資産 | 自家発行した暗号資産 | 一定の市場暗号資産 |
| 評価除外の要件 | 継続して保有し、短期売買目的でないこと | 短期売買目的でないこと |
| 実務上の追加要件 | ――(主に意図と保有期間による) | 移転制限が付された暗号資産であること(技術的措置または信託財産) |
| 法令上の根拠 | 法人税法施行令第118条の7(改正) | 法人税法施行令等(さらなる改正) |
参考:財務省|令和6年度税制改正の大綱の概要
参考:国税庁|暗号資産の評価方法の見直し等
暗号資産を保有する企業が直面する実務上の課題と取るべき対応策
税制改正によって企業が暗号資産を保有する大きなメリットがもたらされましたが、その恩恵を享受するためには、企業側に厳格な対応が求められます。特に、暗号資産が短期売買目的でないことの証明や、適切な内部統制の構築は、法務・技術・経理部門が連携して取り組むべき専門性の高い実務課題となります。
税務会計上の論点と内部統制の構築
税制改正による時価評価課税の適用除外というメリットを享受するためには、その前提として、暗号資産の保有目的、経済的実態、そして適切な内部統制が整備されている必要があります。日本公認会計士協会(JICPA)がWeb3.0関連企業における監査受嘱上の課題として指摘しているように、取引の経済的合理性の理解、発行者と保有者の間の権利義務関係の特定、そして適切な会計処理の実施は、監査上の前提条件とされています。
この監査上の課題は、税務対応と密接に連動しています。JICPAが監査法人の観点から取引の経済合理性を検証することは、税務上の「短期売買目的でない」という要件の正当性を確認することに他なりません。したがって、税務上の適用除外の要件(移転制限)を満たすための措置を講じることは、同時に会計監査において当該資産が非短期売買目的資産として分類されることの正当性を財務報告の観点からも強化することに繋がります。企業は、税務対策、会計処理、および内部統制の構築を独立したプロセスとして捉えるのではなく、一体として進める必要があります。
短期売買目的の定義に関する社内ポリシーの策定
企業は、保有する暗号資産について、どの銘柄、どの数量を「短期売買目的でない」ものとして分類し、適用除外を適用するのかを明確に定義し、文書化する社内ポリシーを策定しなければなりません。
このポリシー策定においては、税務上のメリットだけでなく、経営戦略、投資ガイドライン、および資金計画との整合性を保つことが極めて重要です。また、暗号資産業界の市場環境は急速に変化するため、保有目的が変更される可能性も考慮に入れる必要があります。保有目的の変更は、時価評価への切り替えなど、税務上の重大な影響を伴う可能性があるため、変更の判断基準、手続き、およびそれに伴う税務上の影響をシミュレーションできる体制を事前に構築しておくことが求められます。
法務・技術部門主導による移転制限措置の実施と証明
令和6年度改正の恩恵を享受するために、最も専門的な知見と対応が求められるのが、技術的な移転制限措置の実施と、その証明資料の整備です。これは、法務、経理、技術の各部門が専門性を持ち寄り、共同で対応すべき課題です。
- 技術的要件の確認と措置の実施:
企業が採用しようとする技術的措置(例えば、特定のスマートコントラクトによるロックアップ、厳格なマルチシグネチャ管理、または専用のコールドウォレットにおける鍵の厳重な管理体制など)が、内閣府令や自主規制団体の規則が定める「移転制限」の定義を充足しているか否かを、法務部門と技術部門が共同で検証しなければなりません。特に、JVCEAの規則においては、信託財産とする措置、もしくは当該暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置の内容を充足していることが明確に要求されています。技術的な制限が、契約上の制限ではなく、ブロックチェーン上の検証可能な制限であることの担保が必要です。 - 証明資料の作成と提出:
適用除外の届出時に求められる「技術的措置の内容に関わる証明資料」は、単なる説明文書ではありません。これには、ブロックチェーン技術の詳細、採用したスマートコントラクトの構造とコード、マルチシグの運用フロー、およびそのガバナンスメカニズムが、どのように移転制限を実現しているかを示す詳細なエビデンスを含める必要があります。これらの資料は、税務調査や会計監査において、企業のコンプライアンス体制と長期保有の意思を客観的に証明するための、極めて重要な証拠となります。この文書化体制の構築と継続的な運用は、企業のコンプライアンス体制において最優先事項の一つとなります。
まとめ:暗号資産に関する内部統制は弁護士に相談を
令和5年度(2023年)及び令和6年度(2024年)の法人税制改正は、日本のWeb3.0産業の国際競争力を高め、法人による暗号資産の戦略的な保有・活用を促すための、極めて戦略的かつ重要な規制緩和措置です。特に、令和6年度改正により、発行体以外の第三者法人が保有する市場暗号資産が、厳格な要件のもとで期末時価評価課税の対象外となったことは、暗号資産を企業の事業ポートフォリオに組み込むための道を開くものです。
しかし、企業がこの改正の恩恵を享受するためには、従来の法人税法第61条に基づく時価評価課税の原則と、改正後の法人税法施行令等に基づく適用除外規定との違いを正確に理解し、その細部に厳格に準拠する必要があります。とりわけ、適用除外の要件である「短期売買目的でない」ことの客観的な証明として、内閣府令や自主規制団体の規則に基づき、技術的な「移転制限」措置を確実に講じ、その詳細な証明資料を整備し、税務当局に届け出ることが不可欠です。
企業には、法務、経理、技術の各部門が緊密に連携を取り、日本公認会計士協会(JICPA)が指摘する監査上の課題も念頭に置いた上で、保有目的の明確化と移転制限に関する強固な内部統制体制を構築することが強く求められます。これらの複雑かつ専門的な実務要件に確実に対応するためには、法令の細部解釈や具体的な技術的措置の妥当性について、専門的な知見を持つ法律事務所や税理士との緊密な連携を構築することが、コンプライアンスを確保しつつ、暗号資産の戦略的な活用を進める上での鍵となることが言えるでしょう。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。昨今、注目を集める暗号資産関連ビジネスは高度に専門的でリーガルチェックが必要です。当事務所は様々な法律の規制を踏まえた上で、現に開始したビジネス、開始しようとしたビジネスに関する法的リスクを分析し、可能な限りビジネスを止めることなく適法化を図ります。下記記事にて詳細を記載しております。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務