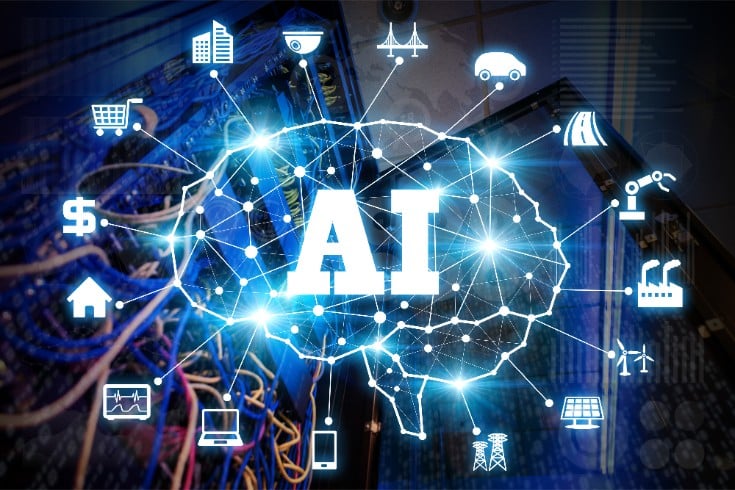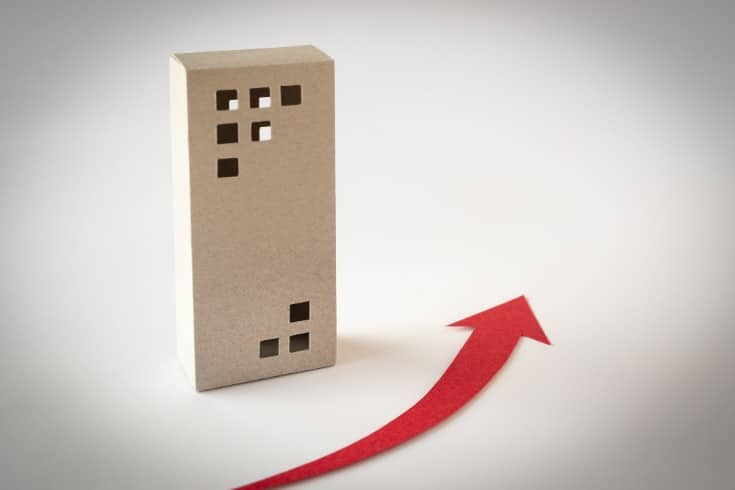【令和7年12月施行】スマホソフトウェア競争促進法とは?企業のとるべき対応策を解説

„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥„ÅØÁè扪£„ÅÆÊó•Êú¨ÁµåÊ∏à„Åä„Çà„Å≥ÂõΩÊ∞ëÁîüÊ¥ª„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅÂçò„Å™„ÇãÈÄö‰ø°Ê©üÂô®„ÇíË∂Ö„Åà„ÅüÁ§æ‰ºöÂü∫Áõ§„Å®„Åó„Ŷ„ÅÆÂΩπÂâ≤„ÇíÊãÖ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅ„Åù„ÅÆÂ੉æøÊÄß„ÅÆË£èÂÅ¥„Åß„ÅØ„ÄÅ„É¢„Éê„ǧ„É´OS„ÇÑ„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÂü∫ÂππÁöÑ„Å™„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Â∏ÇÂÝ¥„Åå„ÄÅÁâπÂÆöÂ∞ëÊï∞„ÅÆÊúâÂäõ„Å™‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´„Çà„ÇãÂØ°ÂçÝÁä∂ÊÖã„Å´„ÅÇ„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜÊßãÈÄÝÁöфř˙≤È°å„ÅåÂ≠òÂú®„Åó„Ŷ„Åç„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÜ„Åó„ÅüÁä∂Ê≥Å„ÅØ„ÄÅÊñ∞˶è‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅÆÂèÇÂÖ•„ÇíÂõ∞Èõ£„Å´„Åó„ÄÅÂÖ¨Ê≠£„Å™Á´∂‰∫â„ÇíÈòªÂÆ≥„Åô„Çã‰∏ÄÂõÝ„Å®ÊåáÊëò„Åï„Çå„Ŷ„Åç„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
„Åì„ÅÆË™≤È°å„Å´ÂØæÂøú„Åô„Åπ„Åè„Äʼnª§Âíå6Âπ¥6Êúà12Êó•„Å´„Äå„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥„Å´„Åä„ÅфŶÂà©ÁÅï„Çå„ÇãÁâπÂÆö„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Å´‰øÇ„ÇãÁ´∂‰∫â„ÅƉøÉÈÄ≤„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊ≥ïÂæã„ÄçÔºàÈÄöÁß∞Ôºö„Çπ„Éû„Éõ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Á´∂‰∫â‰øÉÈÄ≤Ê≥ïÔºâ„ÅåÊàêÁ´ã„Åó„ÄÅÂêåÊúà19Êó•„Å´ÂÖ¨Â∏É„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆÊñ∞„Åó„ÅÑÊ≥ïÂæã„ÅØ„Äʼn∏ÄÈÉ®„ÅÆ˶èÂÆö„ÇíÈô§„Åç„Äʼnª§Âíå7Âπ¥Ôºà2025Âπ¥Ôºâ12Êúà18Êó•„Åã„ÇâÂÖ®Èù¢ÁöÑ„Å´ÊñΩË°å„Åï„Çå„Çã‰∫àÂÆö„Åß„Åô„ÄÇÊú¨Ê≥ï„ÅØ„ÄÅ„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥„ÅÆ„Ç®„Ç≥„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„Å´„Åä„Åë„ÇãÂÖ¨Ê≠£„Åã„ŧËá™ÁřÁ´∂‰∫âÁí∞¢ɄÇíÊï¥ÂÇô„Åó„ÄŧöÊßò„Å™‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´„Çà„Çã„ǧ„Éé„Éô„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÇíÊ¥ªÊÄßÂåñ„Åï„Åõ„Çã„Åì„Å®„ÇíÁõÆÁöÑ„Å®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åù„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅÊúÄÁµÇÁöÑ„Å´„ÅØÊ∂àË≤ªËÄÖ„Åå„Çà„Çä§öÊßò„ÅßË≥™„ÅÆÈ´ò„Åфǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇíÈÅ∏Êäû„Åß„Åç„ÇãÂà©Áõä„Çí‰∫´Âèó„Åß„Åç„ÇãÁ§æ‰ºö„ÅÆÂÆüÁèæ„ÇíÁõÆÊåá„Åô„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ
この記事では、この新しいスマホソフトウェア競争促進法の内容と、企業のとるべき対応策について解説します。
この記事の目次
スマホソフトウェア競争促進法の概要
„Äå„Çπ„Éû„Éõ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Á´∂‰∫â‰øÉÈÄ≤Ê≥ï„Äç„Å®„ÅØ„ÄÅApple„ÇÑGoogle„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÂ∑®Â§ßIT‰ºÅÊ•≠„ÅåÊèê‰æõ„Åô„Çã„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥„ÅÆOS„ÇÑ„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„Å™„Å©„ÄÅ„Éá„Ç∏„Çø„É´Â∏ÇÂÝ¥„ÅÆÂü∫Áõ§Ôºà„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝÔºâ„Å´„Åä„Åë„ÇãÂÖ¨Ê≠£„Å™Á´∂‰∫â„Çí‰øÉ„Åô„Åü„ÇÅ„Å´Âà∂ÂÆö„Åï„Çå„ÅüÊñ∞„Åó„ÅÑÊ≥ïÂæã„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„Åì„Åß„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÆÊ≥ïÂæã„ÅÆʶÇ˶ńŴ„ŧ„ÅфŶËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
立法の背景と目的
„Çπ„Éû„Éõ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Á´∂‰∫â‰øÉÈÄ≤Ê≥ï„ÅåÂà∂ÂÆö„Åï„Çå„ÅüËÉåÊôØ„Å´„ÅØ„ÄÅÂæìÊù•„ÅÆÁ´∂‰∫âÊ≥ï„Åß„ÅÇ„ÇãÁã¨ÂçÝÁ¶ÅÊ≠¢Ê≥ï„ÅÝ„Åë„Åß„ÅØ„ÄÅÊÄ•ÈÄü„Ŵ§âÂåñ„Åô„Çã„Éá„Ç∏„Çø„É´Â∏ÇÂÝ¥„ÅÆË™≤È°å„Å´ËøÖÈÄü„Åã„ŧÂäπÊûúÁöÑ„Å´ÂØæÂøú„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅåÂõ∞Èõ£„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜÁÇπ„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÁã¨ÂçÝÁ¶ÅÊ≠¢Ê≥ï„ÅØ„ÄÅÁ´∂‰∫â„ÇíÂà∂Èôê„Åô„ÇãË°åÁÇ∫„ÅåË°å„Çè„Çå„ÅüÂæå„Å´„ÄÅ„Åù„ÅÆÈÅïÊ≥ïÊÄß„ÇíÂÄãÂà•„Å´Á´ãË®º„ÅóÊòØÊ≠£„ÇíʱDŽÇÅ„Çã„Äå‰∫ãÂæå˶èÂà∂„Äç„ÅÆ„Ç¢„Éó„É≠„ɺ„ÉÅ„ÇíÂèñ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅ„Éá„Ç∏„Çø„É´„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝÂ∏ÇÂÝ¥„Åß„ÅØ„ÄÅ„Éç„ÉÉ„Éà„É؄ɺ„ÇØÂäπÊûú„ÇÑ„Éá„ɺ„Çø„ÅÆÈõÜÁ©ç„Å´„Çà„Å£„Ŷ‰∏ÄÂ∫¶Á¢∫Á´ã„Åï„Çå„ÅüÂØ°ÂçÝÁä∂ÊÖã„Çí˶܄Åô„Åì„Å®„ÅØÊ•µ„ÇńŶÈõ£„Åó„Åè„ÄÅÁ´ãË®ºÊ¥ªÂãï„Å´Èï∑ÊôÇÈñì„Çí˶ńÅô„Çã‰∫ãÂæå˶èÂà∂„Åß„ÅØ„ÄÅÂ∏ÇÂÝ¥„ÅåÂõ∫ÂÆöÂåñ„Åó„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÑÊâãÈÅÖ„Çå„Å´„Å™„Çã„DZ„ɺ„Çπ„ÅåÂ∞ë„Å™„Åè„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„Åß„Åó„Åü„ÄÇ
„Åù„Åì„Åß„ÄÅ„Çπ„Éû„Éõ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Á´∂‰∫â‰øÉÈÄ≤Ê≥ï„Åß„ÅØ„ÄÅÁâπÂÆö„ÅÆÂ∏ÇÂÝ¥„Å´„Åä„ÅфŶº∑„ÅÑÂΩ±ÈüøÂäõ„ÇíÊåńŧ‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Çí„ÅÇ„Çâ„Åã„Åò„ÇÅÊåáÂÆö„Åó„ÄÅÁ´∂‰∫â„ÇíÈòªÂÆ≥„Åô„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„ÅåÈ´ò„ÅÑÁâπÂÆö„ÅÆË°åÁÇ∫È°ûÂûã„Çí‰∫ãÂâç„Å´Á¶ÅÊ≠¢„Åô„Çã„Äå‰∫ãÂâç˶èÂà∂„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÊñ∞„Åü„Å™ÊâãÊ≥ï„ÅåÂ∞éÂÖ•„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅÈÅïÂèçË°åÁÇ∫„Å´ÂØæ„Åó„ŶËøÖÈÄü„Åã„ŧÂäπÊûúÁöÑ„Å´‰ªãÂÖ•„Åó„ÄÅÂÖ¨Ê≠£„Å™Á´∂‰∫âÁí∞¢ɄÇíÁ∂≠ÊåÅ„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅåÂèØËÉΩ„Å´„Å™„Çã„Å®ÊúüÂæÖ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„ÅÆÊ≥ïÂæã„ÅÆÁ©∂Ê•µÁöÑ„Å™ÁõÆÁöÑ„ÅØ„ÄÅÂ∑®Â§ß„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„É݉∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å®„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Çфǵ„ɺ„Éì„ÇπÊèê‰æõ‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å®„ÅÆÈñì„ÅÆÂÖ¨Ê≠£„Å™Á´∂‰∫âÊù°‰ª∂„ÇíÁ¢∫‰øù„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄŧöÊßò„Å™‰∏ª‰Ωì„Å´„Çà„Çã„ǧ„Éé„Éô„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Åå‰øÉÈÄ≤„Åï„Çå„ÄÅÁµêÊûú„Å®„Åó„ŶÊ∂àË≤ªËÄÖ„Åå‰∫´Âèó„Åô„Çã„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÅÆË≥™„ÇÑÈÅ∏ÊäûËÇ¢„ÅåÂêë‰∏ä„Åô„Çã„ÄÅÂÅ•ÂÖ®„Å™„Ç®„Ç≥„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅÆÊßãÁØâ„ÇíÁõÆÊåá„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
規制の対象となる「特定ソフトウェア」と「指定事業者」
Êú¨Ê≥ï„Åå˶èÂà∂„ÅÆÂØæ˱°„Å®„Åô„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÄÅ„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥„ÅÆÂà©ÁŴ‰∏çÂèØʨ݄řÂü∫Áõ§„Å®„Å™„Çã4Á®ÆÈ°û„ÅÆ„ÄåÁâπÂÆö„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„Äç„Åß„Åô„ÄÇÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄÅ‚ëÝÂü∫Êú¨Âãï‰Ωú„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Ôºà„É¢„Éê„ǧ„É´OSÔºâ„ÄÅ‚ë°„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„Äł뢄Éñ„É©„Ƕ„Ç∂„ÄÅ‚ë£Ê§úÁ¥¢„Ç®„É≥„Ç∏„É≥„Åå„Åì„Çå„Å´Ë©≤ÂΩì„Åó„Åæ„Åô„ÄÇSNS„ÇÑ„Ç™„É≥„É©„ǧ„É≥„Ç∑„Éß„ÉÉ„Éî„É≥„Ç∞„É¢„ɺ„É´„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÂÄãÂà•„ÅÆ„Ç¢„Éó„É™„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Çфǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÅØ„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ4„ŧ„ÅÆ„ÅÑ„Åö„Çå„Åã„ÅÆÊ©üËÉΩ„ÇíÊèê‰æõ„Åó„Å™„ÅÑÈôê„Çä„ÄÅÁõ¥Êé•„ÅÆ˶èÂà∂ÂØæ˱°„Å®„ÅØ„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ
„Åù„Åó„Ŷ„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÁâπÂÆö„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÇíÊèê‰æõ„Åô„Çã‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅÆ„ÅÜ„Å°„ÄÅÁâπ„Å´Â∏ÇÂÝ¥„Å∏„ÅÆÂΩ±ÈüøÂäõ„Åå§߄Åç„Åщ∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÇíÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„Åå„ÄåÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Äç„Å®„Åó„ŶÊåáÂÆö„Åó„ÄÅ˶èÂà∂„ÇíÈÅ©ÁÅó„Åæ„Åô„ÄÇÊåáÂÆö„ÅÆÂü∫Ê∫ñ„Å®„Å™„Çã‰∫ãÊ•≠˶èÊ®°„ÅØÊîø‰ª§„ÅßÂÆö„ÇÅ„Çâ„Çå„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅÁèæÊôÇÁÇπ„Åß„ÅØ„ÄÅÁâπÂÆö„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÅÆÁ®ÆÈ°û„Åî„Å®„Å´„ÄÅÂõΩÂÜÖ„Å´„Åä„Åë„ÇãÊúàÈñì„ÅÆÂà©Áî®ËÄÖÊï∞„Åå4000‰∏á‰∫∫‰ª•‰∏ä„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„Åå‰∏Ąŧ„ÅÆÁõÆÂÆâ„Å®„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„ÅÆÊòéÁ¢∫„Å™Âü∫Ê∫ñ„Å´„Çà„Çä„ÄÅ˶èÂà∂„ÅÆÂØæ˱°„Å®„Å™„Çã‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅÆÁØÑÂõ≤„Åå‰∫àÊ∏¨ÂèØËÉΩ„Å®„Å™„Çä„ÄÅÊ≥ïÁöÑ„Å™ÂÆâÂÆöÊÄß„ÅåÁ¢∫‰øù„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÆÂü∫Ê∫ñ„Å´Âü∫„Å•„Åç‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÇíÂÄãÂà•„Å´ÊåáÂÆö„Åó„ÄÅÊåáÂÆö„Åï„Çå„Åü‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅØÊú¨Ê≥ï„ÅåÂÆö„ÇÅ„ÇãÂêÑÁ®Æ„ÅÆÁæ©Âãô„ÇíË≤Ý„ÅÜ„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
指定事業者として指定された企業
本法の規定に基づき、公正取引委員会は令和7年3月31日に、規制の対象となる「指定事業者」を正式に指定しました。指定されたのは以下の3社です。
- Apple Inc.:基本動作ソフトウェア(モバイルOS)、アプリストア、ブラウザ
- iTunesÊݙº艺öÁ§æÔºö„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢ÔºàAppleInc.„Å®ÂÖ±Âêå„ÅßÊèê‰æõÔºâ
- Google LLC.:基本動作ソフトウェア(モバイルOS)、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン
„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅAppleÁ§æ„ÅÆiOS„Å®AppStore„ÄÅGoogleÁ§æ„ÅÆAndroidOS„ÄÅGooglePlay„Çπ„Éà„Ç¢„ÄÅChrome„Éñ„É©„Ƕ„Ç∂„ÄÅGoogleʧúÁ¥¢„Å®„ÅÑ„Å£„Åü„ÄÅÊó•Êú¨„ÅÆ„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥Â∏ÇÂÝ¥„ÅßÂúßÂÄíÁöÑ„Å™„Ç∑„Çß„Ç¢„ÇíÊåńŧ„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Åå„ÄÅÊú¨Ê≥ï„ÅÆÁõ¥Êé•Áöфř˶èÂà∂‰∏ã„Å´ÂÖ•„Çã„Åì„Å®„ÅåÁ¢∫ÂÆö„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„Çâ„ÅƉºÅÊ•≠„ÅØ„ÄÅÊú¨Ê≥ï„ÅåÂÆö„ÇÅ„ÇãÁ¶ÅÊ≠¢‰∫ãÈÝÖ„Åä„Çà„Å≥ÈŵÂÆà‰∫ãÈÝÖ„Å´ÂØæÂøú„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„ÅƉΩìÂà∂ÊßãÁØâ„ÅåʱDŽÇÅ„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
ÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´Ë™≤„Åï„Çå„Çã„ÄåÁ¶ÅÊ≠¢‰∫ãÈÝÖ„Äç

Êú¨Ê≥ï„ÅƉ∏≠ÊÝ∏„Çí„Å™„Åô„ÅÆ„Åå„ÄÅÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅåË°å„Å£„Ŷ„ÅØ„Å™„Çâ„Å™„ÅÑË°åÁÇ∫„ÇíÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´ÂÆö„ÇÅ„Åü„ÄåÁ¶ÅÊ≠¢‰∫ãÈÝÖ„Äç„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆ˶èÂÆö„ÅØ„ÄÅ„Åì„Çå„Åæ„Åß„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„É݉∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅåÂà©Áî®Ë¶èÁ¥Ñ„Å™„Å©„ÇíÈÄö„Åò„Ŷ˰å„Å£„Ŷ„Åç„Åü„ÄÅÁ´∂‰∫â„ÇíÂà∂Èôê„Åô„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„ÅÆ„ÅÇ„ÇãË°åÁÇ∫„Å´Áõ¥Êé•ÁöÑ„Å™Âà∂Á¥Ñ„ÇíË™≤„Åô„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„Äljª•‰∏ã„Å´„ÄÅÊ≥ïÁ¨¨5Êù°„Åã„ÇâÁ¨¨9Êù°„Å´ÂÆö„ÇÅ„Çâ„Çå„Åü‰∏ªË¶Å„Å™Á¶ÅÊ≠¢‰∫ãÈÝÖ„ÇíËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
データの不当な使用の禁止(法第5条)
Ê≥ïÁ¨¨5Êù°„ÅØ„ÄÅÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Åå„Åù„ÅÆ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝÔºàÂü∫Êú¨Âãï‰Ωú„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÄÅ„Éñ„É©„Ƕ„Ç∂Ôºâ„ÅÆÈÅãÂñ∂„ÇíÈÄö„Åò„Ŷ„Äʼnªñ„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖÔºà„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å™„Å©Ôºâ„Åã„ÇâÂèñÂæó„Åó„ÅüÈùûÂÖ¨Èñã„ÅÆ„Éá„ɺ„Çø„Çí„ÄÅËᙄÇâ„ÅÆÁ´∂‰∫âÂÑ™‰ΩçÊÄß„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´‰∏çÂΩì„Å´Âà©ÁÅô„Çã„Åì„Å®„ÇíÁ¶ÅÊ≠¢„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÅÆÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Åå„ÄÅ„ÅÇ„Çã„ǵ„ɺ„Éâ„Éë„ɺ„ÉÜ„Ç£Ë£Ω„Ç¢„Éó„É™„ÅÆ£≤‰∏ä„ÇÑÂà©Áî®Áä∂Ê≥Å„Å´Èñ¢„Åô„ÇãË©≥Á¥∞„Å™„Éá„ɺ„Çø„ÇíÂàÜÊûê„Åó„ÄÅ„Åù„Çå„Å®Á´∂Âêà„Åô„ÇãËá™Á§æË£Ω„Ç¢„Éó„É™„ÇíÈñãÁô∫„ɪË≤©Â£≤„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„Å´„Åù„ÅÆ„Éá„ɺ„Çø„ÇíÂà©ÁÅô„ÇãË°åÁÇ∫„Åå„Åì„Çå„Å´Ë©≤ÂΩì„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„ÅÆ˶èÂÆö„ÅØ„ÄÅ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„É݉∫ãÊ•≠ËÄÖ„Åå„ÄåÂØ©ÂৄÄç„Å®„Äå„Éó„ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„Äç„Å®„ÅÑ„Å܉∫åÈáç„ÅÆÂΩπÂâ≤„ÇíÊåńŧ„Åì„Å®„ÅßÁîü„Åò„ÇãÂà©ÁõäÁõ∏ÂèçÂïèÈ°å„Å´ÂØæÂᶄÅô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝ„ÅØ„Äʼnªñ„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„Åå„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„ÇíË°å„ÅÜ„Åü„ÇÅ„ÅÆ„ÄåÂÝ¥„Äç„ÇíÊèê‰æõ„Åô„Çã‰∏ÄÊñπ„Åß„ÄÅËᙄÇâ„ÇÇ„Åù„ÅÆÂÝ¥„ÅßÁ´∂Âêà„Åô„Çã„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇíÊèê‰æõ„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åù„ÅÆÈöõ„ÄÅ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Å®„ÅÑ„ÅÜÁ´ãÂÝ¥„ÇíÂà©ÁÅó„ŶÂæó„ÅüÂÜÖÈÉ®ÊÉÖÂݱ„ÇíËá™Á§æ„ÅÆÂà©Áõä„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´‰Ωø„ÅÜ„Åì„Å®„ÅØ„ÄÅÂÖ¨Ê≠£„Å™Á´∂‰∫â„ÇíËëó„Åó„ÅèÊ≠™„ÇÅ„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÊú¨Êù°„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÜ„Åó„ÅüË°åÁÇ∫„ÇíÊòéÁ¢∫„Å´Á¶Å„Åò„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å™„Å©„ÅåÂÆâÂøÉ„Åó„Ŷ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„É݉∏ä„Å߉∫ãÊ•≠„Çí±ïÈñã„Åß„Åç„ÇãÁí∞¢ɄÇí‰øùË≠∑„Åô„Çã„Åì„Å®„ÇíÁõÆÁöÑ„Å®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
アプリストア・OS提供者の禁止行為(法第7条・第8条)
Ê≥ïÁ¨¨7Êù°„Åä„Çà„Å≥Á¨¨8Êù°„ÅØ„ÄÅÁâπ„Å´„É¢„Éê„ǧ„É´„Ç®„Ç≥„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅƉ∏≠ÊÝ∏„Çí„Å™„ÅôOS„Åä„Çà„Å≥„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÅÆÈÅãÂñ∂„Å´Èñ¢„Åó„Ŷ„Äŧö„Åè„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´„Å®„Å£„Ŷʕµ„ÇńŶÈáç˶ńřÁ¶ÅÊ≠¢Ë°åÁÇ∫„ÇíÂÆö„ÇńŶ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
まず、OS提供者は、自社が提供するアプリストア以外のサードパーティ製アプリストアの提供や利用を妨げてはならないとされています(法第7条第1号)。これは、これまで特定のOSにおいて事実上不可能であった、公式ストア以外からのアプリの導入(サイドローディング)を、安全性を確保した形で可能にすることを求めるものです。これにより、アプリの流通経路が多様化し、ストア間の競争が生まれることが期待されます。
ʨ°„Å´„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢ÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅØ„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÂÜÖ„Åß„ÅÆ„Éá„Ç∏„Çø„É´„Ç≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉÑ„Çфǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÅÆË≤©Â£≤„Å´„ÅÇ„Åü„Çä„ÄÅËá™Á§æ„ÅåÊèê‰æõ„Åô„ÇãÁâπÂÆö„ÅÆʱ∫Ê∏à„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÔºàË™≤Èáë„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÔºâ„ÅÆÂà©ÁÇíº∑Âà∂„Åó„Ŷ„ÅØ„Å™„Çä„Åæ„Åõ„ÇìÔºàÊ≥ïÁ¨¨8Êù°Á¨¨1Âè∑Ôºâ„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅØ„ÄÅ„Çà„ÇäÊâãÊï∞Êñô„ÅƉΩé„ÅѧñÈÉ®„ÅÆʱ∫Ê∏à„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇíÂ∞éÂÖ•„Åô„Çã„Å™„Å©„ÄÅʱ∫Ê∏àÊâãÊƵ„ÇíËá™ÁŴÈÅ∏Êäû„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØ„Äŧö„Åè„ÅÆÈñãÁô∫ËÄÖ„ÅåË≤ÝÊãÖ„Å´ÊÑü„Åò„Ŷ„ÅÑ„ÅüÈ´òÈ°ç„Å™ÊâãÊï∞Êñô„ÅÆÂïèÈ°å„Å´Áõ¥Êé•ÂØæÂᶄÅô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çä„Äʼn∫ãÊ•≠„ÅÆÂèéÁõäÊÄßÊîπÂñфŴ§߄Åç„ÅèÂØщ∏é„Åô„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åï„Çâ„Å´„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÂÜÖ„Åã„Çâ§ñÈÉ®„ÅƄǶ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„Éà„Å∏„ɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„ÇíË™òÂ∞é„Åó„ÄÅ„Åù„Åì„Åß„ÅÆÂïÜÂìÅË≥ºÂÖ•„ÇíÊ°àÂÜÖ„Åô„Çã„Åì„ŮԺà„ÅÑ„Çè„ÇÜ„Çã„Ç¢„É≥„Éńɪ„Çπ„ÉÜ„Ç¢„É™„É≥„Ç∞Ë°åÁÇ∫Ôºâ„ÇíÂà∂Èôê„Åô„Çã„Åì„Å®„ÇÇÁ¶ÅÊ≠¢„Åï„Çå„Åæ„ÅôÔºàÊ≥ïÁ¨¨8Êù°Á¨¨2Âè∑Ôºâ„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÂÜÖ„Åß„ÄåÂ֨ºè„ǵ„ǧ„Éà„Åã„Çâ„ÅÆË≥ºÂÖ•„Åß10%Ââ≤ºï„Äç„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÊÉÖÂݱ„ÇíÊèê‰æõ„Åó„ÄÅËá™Á§æ„ǵ„ǧ„Éà„Å∏„É™„É≥„ÇØ„ÇíË®≠ÁΩÆ„Åô„Çã„Åì„Å®„Çí„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝ„ÅÆ˶èÁ¥Ñ„ÅßÁ¶Å„Åò„Çã„Åì„Å®„ÅØ„ÄʼnªäÂæå„ÅØË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„Å™„Åè„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
このほかにも、OSの特定の機能(カメラやNFCなど)について、自社アプリと同等の性能でサードパーティ製アプリが利用することを妨げる行為(法第7条第2号)や、ブラウザアプリに対して自社製のブラウザエンジンの利用を強制する行為(法第8条第3号)も禁止されています。
検索エンジン提供者の禁止行為(法第9条)
法第9条は、検索エンジンにおける自己優遇(セルフ・プリファレンシング)を規制するものです。指定事業者である検索エンジン提供者は、検索結果の表示において、正当な理由なく、自社またはその子会社などが提供するサービスを、競合する他の事業者のサービスよりも優先的に取り扱ってはならないと定められています。
‰æã„Åà„Å∞„Äńɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„Åå‰∏ÄËà¨ÁöÑ„Å™ÂïÜÂìÅ„Çфǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇíʧúÁ¥¢„Åó„ÅüÈöõ„Å´„ÄÅʧúÁ¥¢ÁµêÊûú„ÅÆÊúĉ∏äÈÉ®„Å´Ëá™Á§æ„ÅÆ„Ç∑„Éß„ÉÉ„Éî„É≥„Ç∞„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇÑÊóÖË°å‰∫àÁ¥Ñ„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇíÁâπÂà•„Å™„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ÉÉ„Éà„ÅßË°®Á§∫„Åó„ÄÅÁ´∂Âêà‰ªñÁ§æ„ÅÆ„Ç™„ɺ„Ǩ„Éã„ÉÉ„Ç؄řʧúÁ¥¢ÁµêÊûú„Çí‰∏çÂΩì„Å´‰∏ã‰Ωç„Å´ËøΩ„ÅÑ„ÇÑ„Çã„Çà„Å܄ř˰åÁÇ∫„Åå„Åì„Çå„Å´Ë©≤ÂΩì„Åó„Åæ„Åô„ÄÇʧúÁ¥¢„Ç®„É≥„Ç∏„É≥„ÅØÊÉÖÂݱ„Å∏„ÅÆ„Ç¢„Ç؄Ǫ„Çπ„Å´„Åä„Åë„ÇãÈáç˶ńř„Ç≤„ɺ„Éà„Ƕ„Ç߄ǧ„Åß„ÅÇ„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Åù„ÅÆË°®Á§∫ÈÝ܉Ωç„Åå‰∏≠Á´ãÊÄß„Çíʨ݄Åç„ÄÅÈÅãÂñ∂ËÄÖ„ÅÆÈÉΩÂêà„ÅßÊ≠™„ÇÅ„Çâ„Çå„Çã„Åì„Å®„ÅØ„ÄÅÂÖ¨Ê≠£„Å™Á´∂‰∫â„ÇíÈòªÂÆ≥„Åó„ÄÅÊ∂àË≤ªËÄÖ„ÅÆÈÅ∏Êäû„ÇíË™§Ë™òÂ∞é„Åô„ÇãÊÅê„Çå„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÊú¨Êù°„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÜ„Åó„ÅüË°åÁÇ∫„Å´Ê≠ØÊ≠¢„ÇÅ„Çí„Åã„Åë„Çã„Åì„Å®„ÇíÁõÆÁöÑ„Å®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
正当化事由について
„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÁ¶ÅÊ≠¢‰∫ãÈÝÖ„ÅØÁµ∂ÂØæÁöÑ„Å™„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇÊú¨Ê≥ï„ÅØ„ÄÅÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅåÁâπÂÆö„ÅÆÁõÆÁöÑ„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´„ÄåÂøÖ˶ńřÊé™ÁΩÆ„Äç„Çí˨õ„Åò„Çã„Åì„Å®„Çí‰æã§ñÁöÑ„Å´Ë™ç„ÇńŶ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Çí„ÄåÊ≠£ÂΩìÂåñ‰∫ãÁÄç„Å®Â뺄Å≥„Åæ„Åô„ÄÇÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄÅ‚ë݄Ǫ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£„ÅÆÁ¢∫‰øù„ÄÅ‚ë°„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„ÅƉøùË≠∑„ÄÅ‚ë¢ÈùíÂ∞ëÂπ¥„ÅƉøùË≠∑„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÁõÆÁöÑ„ÅåÊåô„Åí„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
‰æã„Åà„Å∞„Äńǵ„ɺ„Éâ„Éë„ɺ„ÉÜ„Ç£Ë£Ω„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÅÆÂ∞éÂÖ•„ÇíË™ç„ÇÅ„Çã„Å´„ÅÇ„Åü„Çä„ÄÅ„Éû„É´„Ƕ„Çß„Ç¢„Å™„Å©„ÅÆËÑÖ®ńÅã„Çâ„ɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„Çí‰øùË≠∑„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„Å´„Äʼn∏ÄÂÆö„ÅƄǪ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£ÂØ©ÊüªÂü∫Ê∫ñ„ÇíË®≠„Åë„Çã„Åì„Å®„ÅØ„ÄÅÊ≠£ÂΩìÂåñ‰∫ãÁŮ„Åó„Ŷ˙ç„ÇÅ„Çâ„Çå„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅ„Åì„ÅÆ„ÄåÂøÖ˶ÅÊÄß„Äç„ÅÆÂà§Êñ≠„Åå„ÄÅÁ´∂‰∫â‰øÉÈÄ≤„Å®ÂÆâÂÖ®Á¢∫‰øù„ÅÆ„Éê„É©„É≥„Çπ„ÇíÂèñ„Çã‰∏ä„ÅßÊ•µ„ÇńŶÈáç˶ńŴ„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄljªäÂæå„ÄÅ„Åì„ÅÆÊ≠£ÂΩìÂåñ‰∫ãÁÅÆËߣÈáà„ÇíÂ∑°„Å£„Ŷ„ÄÅÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å®ÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„ÄÅ„ÅÇ„Çã„ÅÑ„Å؉ªñ„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å®„ÅÆÈñì„Åß˶ãËߣ„ÅÆÁõ∏ÈÅï„ÅåÁîü„Åò„ÄÅÊ≥ïÁöфř˴ñÁÇπ„Å®„Å™„ÇãÂÝ¥Èù¢„ÅåÊÉ≥ÂÆö„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
„Çπ„Éû„Éõ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Á´∂‰∫â‰øÉÈÄ≤Ê≥ï„Å´„Åä„Åë„ÇãÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Åå˨õ„Åö„Åπ„Åç„ÄåÈŵÂÆà‰∫ãÈÝÖ„Äç
Êú¨Ê≥ï„ÅØ„ÄÅÁ¶ÅÊ≠¢‰∫ãÈÝÖ„Å´ÂäÝ„Åà„Ŷ„ÄÅÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅåÁ©çÊ•µÁöфŴ˨õ„Åò„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çâ„Å™„ÅÑÊé™ÁΩÆ„ÄÅ„Åô„Å™„Çè„Å°„ÄåÈŵÂÆà‰∫ãÈÝÖ„Äç„ÇÇÂÆö„ÇńŶ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
その一つが、データの円滑な移転(データポータビリティ)を確保するための措置です(法第11条)。指定事業者は、利用者が自らのデータを他の事業者のサービスへ容易に移行できるよう、必要なツールやインターフェースを提供することが求められます。これにより、利用者が特定のサービスに縛られる「ロックイン効果」が緩和され、サービス間の乗り換えが容易になり、競争が促進されます。
„Åæ„Åü„ÄÅÊ®ôÊ∫ñË®≠ÂÆöÔºà„Éá„Éï„Ç©„É´„ÉàË®≠ÂÆöÔºâ„ÅƧâÊõ¥„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊé™ÁΩÆ„ÇÇÈáç˶ńřÈŵÂÆà‰∫ãÈÝÖ„Åß„ÅôÔºàÊ≥ïÁ¨¨12Êù°Ôºâ„ÄÇÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅØ„ÄÅ„Éñ„É©„Ƕ„Ç∂„ÇÑʧúÁ¥¢„Ç®„É≥„Ç∏„É≥„Å™„Å©„ÅÆ„Éá„Éï„Ç©„É´„ÉàË®≠ÂÆö„Çí„ÄÅÂà©Áî®ËÄÖ„ÅåÁ∞°Êòì„Ŵ§âÊõ¥„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄÅ„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥„ÅÆÂàùÊúüË®≠ÂÆöÊôÇ„Å™„Å©„Å´„ÄÅ˧áÊï∞„ÅÆÈÅ∏ÊäûËÇ¢„ÇíÊèêÁ§∫„Åô„ÇãÁîªÈù¢Ôºà„ÉÅ„É߄ǧ„Çπ„Çπ„ÇØ„É™„ɺ„É≥Ôºâ„ÇíË°®Á§∫„Åô„Çã„Å™„Å©„ÅÆÊé™ÁΩÆ„ÅåʱDŽÇÅ„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åï„Çâ„Å´„ÄÅÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅØ„ÄÅËᙄÇâ„ÅåÂèñÂæó„Åô„Çã„Éá„ɺ„Çø„ÅÆÁ®ÆÈ°û„ÇÑÂà©Áî®Êù°‰ª∂„Å™„Å©„Ç퉪ñ„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÇÑÂà©Áî®ËÄÖ„Å´ÈñãÁ§∫„Åô„ÇãÈÄèÊòéÊÄß„ÅÆÁ¢∫‰øùÔºàÊ≥ïÁ¨¨10Êù°Ôºâ„ÇÑ„ÄÅÊú¨Ê≥ï„ÅÆÈŵÂÆàÁä∂Ê≥Å„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÂݱÂëäÊõ∏„ÇíÊØéÂπ¥Â∫¶„ÄÅÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„Å´ÊèêÂá∫„Åô„ÇãÁæ©ÂãôÔºàÊ≥ïÁ¨¨14Êù°Ôºâ„ÇÇË≤Ý„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
スマホソフトウェア競争促進法がビジネスに与える影響

„Åì„ÅÆÊñ∞„Åó„ÅÑÊ≥ïÂæã„ÅØ„ÄÅ„Çπ„Éû„ɺ„Éà„Éï„Ç©„É≥„ÅÆ„Ç®„Ç≥„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„Å´Èñ¢„Çè„Çã§ö„Åè„ÅƉºÅÊ•≠„Å´„Å®„Å£„Ŷ„Äʼn∫ãÊ•≠Áí∞¢ɄÇíÊÝπÂ∫ï„Åã„Çâ§â„Åà„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„ÇíÁßò„ÇńŶ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØÂçò„Å™„Çã˶èÂà∂º∑Âåñ„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅÊñ∞„Åü„Å™„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„ÉÅ„É£„É≥„Çπ„ÅÆÂâµÂá∫„ÇíÊÑèÂë≥„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
アプリ開発・提供事業者への影響
„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÄÅÊú¨Ê≥ï„Åا߄Åç„Å™ËøΩ„ÅÑÈ¢®„Å®„Å™„Çã„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇÊúÄ„ÇÇÁõ¥Êé•ÁöÑ„Å™ÂΩ±Èüø„ÅØ„ÄÅÂèéÁõä„É¢„Éá„É´„ÅƧöÊßòÂåñ„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Åæ„Åߧö„Åè„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅåÊîØÊâï„Å£„Ŷ„Åç„Åü„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÅÆÊâãÊï∞ÊñôÔºà£≤‰∏ä„ÅÆ15%ÔΩû30%Ôºâ„Å´„ŧ„ÅфŶ„Äʼnª£Êõøʱ∫Ê∏à„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅÆÂ∞éÂÖ•„ÇÑËá™Á§æ„Ƕ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„Éà„Å∏„ÅÆË™òÂ∞é„ÅåÂèØËÉΩ„Å´„Å™„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅÊâãÊï∞ÊñôË≤ÝÊãÖ„Çí˪ΩÊ∏õ„Åó„ÄÅÂèéÁõäÊÄß„Çí§ßÂπÖ„Å´ÊîπÂñÑ„Åß„Åç„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åæ„Åü„Äńǵ„ɺ„Éâ„Éë„ɺ„ÉÜ„Ç£Ë£Ω„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„Å®„ÅÑ„ÅÜÊñ∞„Åü„řʵÅÈÄö„ÉÅ„É£„Éç„É´„ÅåÁîü„Åæ„Çå„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅ„Åì„Çå„Åæ„ÅßÂ֨ºè„Çπ„Éà„Ç¢„ÅÆÂé≥Êݺ„Å™ÂØ©ÊüªÂü∫Ê∫ñ„Åß„ÅØÂÖ¨Èñã„ÅåÈõ£„Åó„Åã„Å£„ÅüÁ®ÆÈ°û„ÅÆ„Ç¢„Éó„É™„ÇÑ„ÄÅÁâπÂÆö„ÅƄɶ„ɺ„Ç∂„ɺ±§„Å´ÁâπÂåñ„Åó„Åü„Éã„ÉÉ„ÉÅ„Å™„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÅåÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„Åã„ÇÇ„Åó„Çå„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä„ÄÅÊñ∞„Åü„Å™Â∏ÇÂÝ¥„ÅåÈñãÊãì„Åï„Çå„Äńɶ„ɺ„Ç∂„ɺÁç≤Âæó„ÅÆÈÅ∏ÊäûËÇ¢„ÅåÂ∫É„Åå„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åï„Çâ„Å´„ÄÅOSÊ©üËÉΩ„Å∏„ÅÆÂπ≥Á≠â„Å™„Ç¢„Ç؄Ǫ„Çπ„Åå‰øùË®º„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅÆÁ¥îÊ≠£„Ç¢„Éó„É™„ŮʩüËÉΩÈù¢„ÅßÂØæÁ≠â„Å´Á´∂‰∫â„Åß„Åç„Çã„ÄÅ„Çà„ÇäÈ´òÂ∫¶„ÅßÈù©Êñ∞ÁöÑ„Å™„Ç¢„Éó„É™„ÅÆÈñãÁô∫„ÇÇÊúüÂæÖ„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ
指定事業者以外の企業に生まれる新たなビジネスチャンス
Êú¨Ê≥ï„ÅÆÊñΩË°å„ÅØ„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„ÄÅ„Åù„ÅÆÂë®Ëæ∫Áî£Ê•≠„Å´„ÇÇÊñ∞„Åü„Å™Â∏ÇÂÝ¥„ÇíÁîü„ÅøÂá∫„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØ„ÄÅÊó¢Â≠ò„ÅÆÁã¨ÂçÝÁöÑ„Å™ÈÝòÂüü„ÅåËߣÊîæ„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„ÅßÁîü„Åæ„Çå„Çã„Ä剪£Êõø„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„Äç„Å®„ÄÅËߣÊîæ„Åï„Çå„ÅüÊ©üËÉΩ„ÇíÊ¥ªÁÅó„ŶÁîü„Åæ„Çå„Çã„ÄåÊñ∞„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Äç„Å®„ÅÑ„Å܉∫å„ŧ„ÅÆÂÅ¥Èù¢„Åã„ÇâÊçâ„Åà„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ
Áâπ„Ŵʱ∫Ê∏à„ǵ„ɺ„Éì„Çπ‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÅØ„ÄÅ„Åì„Çå„Åæ„ÅßÂ∑®Â§ß„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅåÁã¨ÂçÝ„Åó„Ŷ„Åç„Åü„Ç¢„Éó„É™ÂÜÖʱ∫Ê∏à„Å®„ÅÑ„ÅÜÂ∑®Â§ß„Å™Â∏ÇÂÝ¥„Å∏„ÅÆÂèÇÂÖ•Ê©ü‰ºö„ÅåÁîü„Åæ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´ÂØæ„Åó„Ŷ„ÄÅ„Çà„Çä‰Ωé„ÅÑÊâãÊï∞Êñô„ÄÅÂæåÊâï„ÅÑ„ÇÑÊöóÂè∑Ë≥áÁî£Ê±∫Ê∏à„Å®„ÅÑ„Å£„Åü§öÊßò„řʱ∫Ê∏àÊâãÊƵ„ÄÅAI„ÇíÊ¥ªÁÅó„ÅüÈ´òÂ∫¶„Å™‰∏çÊ≠£Ê§úÁü•Ê©üËÉΩ„Å™„Å©„ÇíÊèê‰æõ„Åô„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅÊñ∞„Åü„řȰßÂÆ¢„ÇíÁç≤Âæó„Åß„Åç„Çã„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇʱ∫Ê∏à„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÇíÂçò„Å™„Çã„Ç≥„Çπ„Éà„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄåÂèéÁõä„ÇíÊúħßÂåñ„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„ÅÆÊäïË≥á„Äç„Å®Êçâ„Åà„ÄÅÊà¶Áï•ÁöÑ„Å™„Éë„ɺ„Éà„Éä„ɺ„ÇíÈÅ∏„Å∂„Åì„Å®„ÅåÈáç˶ńŴ„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åæ„Åü„ÄÅOS„ÅÆÊ©üËÉΩ„Å∏„ÅÆ„Ç¢„Ç؄Ǫ„Çπ„ÅåÂπ≥Á≠âÂåñ„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅIoTÈÄ£Êê∫„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Å´„ÇÇÊñ∞„Åü„Å™ÂèØËÉΩÊÄß„ÅåÂ∫É„Åå„Çä„Åæ„Åô„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅ„Åì„Çå„Åæ„Åß„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝ„ÅƄǶ„Ç©„ɨ„ÉÉ„Éà„Ç¢„Éó„É™ÁµåÁŴÈôêÂÆö„Åï„Çå„Åå„Å°„ÅÝ„Å£„ÅüNFCÊ©üËÉΩ„ÅåËߣÊîæ„Åï„Çå„Çå„Å∞„ÄÅËá™Âãï˪ä„ÅÆ„Éá„Ç∏„Çø„É´„Ç≠„ɺ„ÄÅ„Ç™„Éï„Ç£„Çπ„ÅÆÂÖ•ÈÄÄÂƧÁÆ°ÁêÜ„Äʼn∫§ÈÄöÊ©üÈñ¢„ÅÆ„ÉńDZ„ÉÉ„Éà„ɨ„Çπ‰πó˪ä„ÄÅ„Éò„É´„Çπ„DZ„ǢʩüÂô®„Å®„ÅÆÁõ¥Êé•ÈÄ£Êê∫„Å®„ÅÑ„Å£„Åü„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„Çí„ÄŧöÊßò„Å™‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅåÊèê‰æõ„Åß„Åç„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åï„Çâ„Å´„ÄÅÂ∫ÉÂëäÂàÜÈáé„Åß„ÇǧâÂåñ„Åå‰∫àÊÉ≥„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝ„ÅåÊèê‰æõ„Åô„ÇãÂ∫ÉÂëäIDÔºàIDFA/GAIDÔºâ„Å´‰æùÂ≠ò„Åó„Å™„ÅÑ„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„Å´ÈÖçÊÖÆ„Åó„ÅüÊñ∞„Åü„Å™Â∫ÉÂëäÈÖç‰ø°„Éç„ÉÉ„Éà„É؄ɺ„ÇØ„ÇÑ„ÄńǺ„É≠„Éë„ɺ„ÉÜ„Ç£„Éá„ɺ„Çø„ÇíÊ¥ªÁÅó„ÅüIDË™çË®º„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å™„Å©„Å´„ÇÇ„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„ÉÅ„É£„É≥„Çπ„ÅåÂ∫É„Åå„Çã„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
スマホソフトウェア競争促進法に対して企業が準備すべきこと
この新法によるイノベーション創出に対して、企業には先見性を持って能動的に課題解決に取り組む姿勢が求められます。
Á¨¨‰∏Ä„Å´„ÄÅÊó¢Â≠ò„ÅÆ•ëÁ¥Ñ„ÅÆ˶ãÁõ¥„Åó„Åß„Åô„ÄÇ„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÅÆ„Éá„Éô„É≠„ÉÉ„Éë„ɺ˶èÁ¥Ñ„Å™„Å©„ÄÅ„Éó„É©„ÉÉ„Éà„Éï„Ç©„ɺ„É݉∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å®Á∑ÝÁµê„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã•ëÁ¥ÑÂÜÖÂÆπ„ÇíÁ≤æÊüª„Åó„ÄÅÊú¨Ê≥ï„ÅÆÊñΩË°å„Å´„Çà„Å£„ŶÁÑ°Âäπ„Å®„Å™„Çã„ÄÅ„ÅÇ„Çã„ÅÑ„ÅاâÊõ¥„ÅåÂøÖ˶ńŮ„Å™„ÇãÊù°ÈÝÖ„ÇíÁâπÂÆö„Åô„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
Á¨¨‰∫å„Å´„ÄÅÊñ∞„Åü„Å™„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„É¢„Éá„É´„ÅÆÊà¶Áï•ÁöÑʧúË®é„Åß„Åô„Äljª£Êõø„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„Åß„ÅÆÈÖç‰ø°„ÄŧñÈɮʱ∫Ê∏à„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅÆÂ∞éÂÖ•„ÄńǶ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„Éà„Åß„ÅÆÁõ¥Êé•Ë≤©Â£≤„Å™„Å©„ÄÅËߣÊîæ„Åï„Çå„ÇãÈÅ∏ÊäûËÇ¢„ÇíËá™Á§æ„ÅƉ∫ãÊ•≠Êà¶Áï•„Å´„Å©„ÅÜÁµÑ„ÅøË溄ÇÄ„Åã„ÄÅÊ≥ïÂãô„Äʼn∫ãÊ•≠„ÄÅÊäÄË°ì„ÅÆÂêÑÈÉ®ÈñÄ„ÅåÈÄ£Êê∫„Åó„ŶʧúË®é„ÇíÈñãÂßã„Åô„Åπ„Åç„Åß„Åô„ÄÇ
Á¨¨‰∏â„Å´„ÄÅ„Éá„É•„ɺ„Éá„Ç£„É™„Ç∏„Çß„É≥„Çπ„ÅÆÂæπÂ∫ï„Åß„Åô„ÄÇÊñ∞„Åü„Å´ÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„ǵ„ɺ„Éâ„Éë„ɺ„ÉÜ„Ç£Ë£Ω„ÅÆ„Ç¢„Éó„É™„Çπ„Éà„Ç¢„ÇÑʱ∫Ê∏à„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÇíÂà©ÁÅô„ÇãÈöõ„Å´„ÅØ„ÄÅ„Åù„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅƉø°ÈݺÊÄß„ÄńǪ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£ÂØæÁ≠ñ„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„Éù„É™„Ç∑„ɺ„Å™„Å©„ÇíÊÖéÈáç„Å´Ë©ï‰æ°„Åó„ÄÅËá™Á§æ„Åä„Çà„Å≥„ɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„Çí„É™„Çπ„ÇØ„Åã„ÇâÂÆà„Çã„Åü„ÇÅ„ÅÆÊ≥ïÂãô„ɪÊäÄË°ì‰∏°Èù¢„Åã„Çâ„ÅÆʧúË®º„Åå‰∏çÂèØʨ݄Åß„Åô„ÄÇ
„Åæ„Åü„ÄÅ„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å®„Åó„Ŷ„ÅØ„ÄÅÊú¨Ê≥ï„Å´„Çà„Å£„ŶÂæó„Çâ„Çå„ÇãÊñ∞„Åü„řʮ©Âà©„ÇíÊ≠£Á¢∫„Å´ÁêÜËߣ„Åó„ÄÅÈÅïÂèç„ÅåÁñë„Çè„Çå„ÇãË°åÁÇ∫„ÇíÁô∫˶ã„Åó„ÅüÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„Å∏Áî≥Âëä„Åô„ÇãÂà∂Â∫¶ÔºàÊ≥ïÁ¨¨15Êù°Ôºâ„ÅÆÊ¥ªÁÇÇ˶ñÈáé„Å´ÂÖ•„Çå„Çã„Åπ„Åç„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ
スマホソフトウェア競争促進法違反に対する措置と執行
Êú¨Ê≥ï„ÅÆÂÆüÂäπÊÄß„ÇíÊãÖ‰øù„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„Å´„Åغ∑Âäõ„Å™Âü∑Ë°åÊ®©Èôê„Åå‰∏é„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„ÅØ„ÄÅÊ≥ïÂæã„Å´ÈÅïÂèç„Åô„ÇãË°åÁÇ∫„ÅåË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„ÅüÂÝ¥Âêà„ÄÅ„Åù„ÅÆË°åÁÇ∫„ÅÆÂ∑ÆÊ≠¢„ÇÅ„ÇÑÊòØÊ≠£„ÇíÂëΩ„Åò„Çã„ÄåÊéíÈô§Êé™ÁΩÆÂëΩ‰ª§„Äç„ÇíÁô∫„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åï„Çâ„Å´„ÄÅÁâπ„Å´Èáç§߄řÈÅïÂèçË°åÁÇ∫„Å´ÂØæ„Åó„Ŷ„ÅØ„ÄÅÈáëÈä≠ÁöÑ„Å™Âà∂ˣńŮ„Åó„Ŷ„ÄåË™≤Âæ¥ÈáëÁ¥ç‰ªòÂëΩ‰ª§„Äç„ÅåÂá∫„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇË™≤Âæ¥Èáë„ÅÆÁÆóÂÆöÁéá„ÅØ„ÄÅÂéüÂâá„Å®„Åó„ŶÈÅïÂèçË°åÁÇ∫„Å´‰øÇ„ÇãÂØæ˱°ÂïÜÂìńɪ„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÅÆ£≤‰∏äÈ°ç„ÅÆ20%„Å®„ÄÅÈùûÂ∏∏„Å´È´ò„ÅèË®≠ÂÆö„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åï„Çâ„Å´„ÄÅÈÅéÂéª10Â𥉪•ÂÜÖ„Å´ÂêåÊßò„ÅÆÈÅïÂèçË°åÁÇ∫„ÇíÁπ∞„ÇäËøî„Åó„ÅüÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅ„Åù„ÅÆÁéá„ÅØ30%„Å´„Åæ„Åߺï„Åç‰∏ä„Åí„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆÊ•µ„ÇńŶȴò„ÅÑË™≤Âæ¥ÈáëÁéá„ÅØ„ÄÅÊåáÂÆö‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å´ÂØæ„Åó„Ŷ„ÄÅÊ≥ïÂæã„ÇíÈŵÂÆà„Åô„Çãº∑„ÅÑÂãïÊ©ü‰ªò„Åë„Çí‰∏é„Åà„Çã„Åì„Å®„ÇíÊÑèÂõ≥„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÂÖ¨Ê≠£ÂèñºïÂßîÂì°‰ºö„ÅØ„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÂëΩ‰ª§„ÇíÂá∫„Åô„Åü„ÇÅ„Å´„Äʼn∫ãÊ•≠ËÄÖ„Å∏„ÅÆÁ´ãÂ֕ʧúÊüª„ÇÑÈñ¢‰øÇËÄÖ„Å∏„ÅÆËÅ¥Âèñ„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüË™øÊüªÊ®©Èôê„ÇÇÊúâ„Åó„Ŷ„Åä„ÇäÔºàÊ≥ïÁ¨¨16Êù°Ôºâ„ÄÅÂé≥Êݺ„Å™Ê≥ïÂü∑Ë°å„ÅåÊúüÂæÖ„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
まとめ:スマホソフトウェア競争促進法を新たなビジネスチャンスに
„Äå„Çπ„Éû„Éõ„ÇΩ„Éï„Éà„Ƕ„Çß„Ç¢Á´∂‰∫â‰øÉÈÄ≤Ê≥ï„Äç„ÅØ„ÄÅÊó•Êú¨„ÅÆ„Éá„Ç∏„Çø„É´Â∏ÇÂÝ¥„Å´„Åä„Åë„ÇãÁ´∂‰∫âÊîøÁ≠ñ„ÅƧ߄Åç„ř˪¢ÊèõÁÇπ„Å®„Å™„ÇãÊ≥ïÂæã„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆÊ≥ïÂæã„ÅØ„ÄÅÂçò„Å´Â∑®Â§ßIT‰ºÅÊ•≠„Çí˶èÂà∂„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅÝ„Åë„ÅåÁõÆÁöÑ„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ„Åù„ÅÆÊú¨Ë≥™„ÅØ„ÄÅÁ°¨Áõ¥Âåñ„Åó„ÅüÂ∏ÇÂÝ¥ÊßãÈÄÝ„Å´È¢®Á©¥„ÇíÈñã„Åë„ÄÅ˶èÊ®°„ÅƧßÂ∞è„Å´„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅ„Åô„Åπ„Ŷ„ÅƉ∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÅåÂÖ¨Ê≠£„Å™„É´„ɺ„É´„ÅÆ„ÇÇ„Å®„ÅßËá™ÁŴÁ´∂‰∫â„Åó„Äńǧ„Éé„Éô„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÇíÂâµÂá∫„Åß„Åç„ÇãÁí∞¢ɄÇíÊï¥ÂÇô„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Ç¢„Éó„É™ÈñãÁô∫‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÇÑʱ∫Ê∏à‰∫ãÊ•≠ËÄÖ„ÄÅ„Åù„Åó„ŶÊñ∞„Åü„Å™„ǵ„ɺ„Éì„Çπ„ÅßÂ∏ÇÂÝ¥„Å´ÂèÇÂÖ•„Åó„Çà„ÅÜ„Å®„Åô„Çã„Çπ„Çø„ɺ„Éà„Ç¢„ÉÉ„Éó„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÄÅÊú¨Ê≥ï„ÅØ„Åì„Çå„Åæ„Åß„Å´„Å™„Åѧ߄Åç„Å™„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„ÉÅ„É£„É≥„Çπ„Çí„ÇÇ„Åü„Çâ„Åô„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅ„Åù„ÅÆÊ©ü‰ºö„ÇíÊúħßÈôê„Å´Ê¥ª„Åã„Åô„Åü„ÇÅ„Å´„ÅØ„ÄÅÊ≥ïÂæã„ÅÆË∂£Êó®„Å®ÂÖ∑‰ΩìÁöфř˶èÂæã„ÇíÊ∑±„ÅèÁêÜËߣ„Åó„ÄÅËá™Á§æ„ÅÆ„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„É¢„Éá„É´„ÇÑ•ëÁ¥ÑÈñ¢‰øÇ„ÄÅ„Ç≥„É≥„Éó„É©„ǧ„Ç¢„É≥„Çπ‰ΩìÂà∂„ÇíÊñ∞„Åü„Å™„É´„ɺ„É´„Å´Âêà„Çè„Åõ„ŶÊúÄÈÅ©Âåñ„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÅèÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„ÅÆÊñ∞„Åó„ÅÑÁ´∂‰∫âÁí∞¢ɄÅØ„ÄÅËá™Áî±Â∫¶„ÅåÈ´ò„Åæ„Çã‰∏ÄÊñπ„Åß„ÄńǪ„Ç≠„É•„É™„ÉÜ„Ç£„ÇÑ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰øùË≠∑„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÊñ∞„Åü„Å™„É™„Çπ„ÇØÁÆ°ÁêÜ„ÇÇʱDŽÇÅ„Çâ„Çå„Çã„ÄÅ„Çà„Çä˧áÈõë„Å™„ÇÇ„ÅÆ„Å®„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÜ„Åó„Åü§âÂåñ„ÅÆÊøÄ„Åó„ÅÑÊôljª£„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅÊ≥ïÁöÑ„Å™ÂÆâÂÖ®ÊÄß„ÇíÁ¢∫‰øù„Åó„Å™„Åå„Çâ„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„ÅÆÁ´∂‰∫âÂäõ„ÇíÈ´ò„ÇńŶ„ÅÑ„Åè„Åü„ÇÅ„Å´„ÅØ„ÄÅITÊ≥ïÂãô„Å®ÊúÄÊñ∞„ÅÆ„Éì„Ç∏„Éç„ÇπÂãïÂêë„ÅÆ„Åô„Åπ„Ŷ„Å´Á≤æÈÄö„Åó„ÅüÊ≥ïÁöфǵ„Éù„ɺ„Éà„Åå‰∏çÂèØʨ݄Åß„Åô„ÄÇ
当事務所による対策のご案内
„É¢„Éé„É™„ÇπÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„ÅØ„ÄÅIT„ÄÅÁâπ„Å´„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„Å®Ê≥ïÂæã„ÅƉ∏°Èù¢„Å´È´ò„ÅÑÂ∞ÇÈñÄÊÄß„ÇíÊúâ„Åô„ÇãÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„Åô„ÄÇÂΩì‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„ÅØ„ÄÅÊù±Ë®º‰∏äÂÝ¥‰ºÅÊ•≠„Åã„Çâ„Éô„É≥„ÉÅ„É£„ɺ‰ºÅÊ•≠„Åæ„Åß„ÄÅIT„ɪ„Éô„É≥„ÉÅ„É£„ɺ‰ºÅÊ•≠„Å™„Çâ„Åß„ÅØ„ÅÆÈ´òÂ∫¶„Å™ÁµåÂñ∂„ÅÆË™≤È°å„Å´ÂØæ„Åó„ŶÊ≥ïÂæãÈù¢„Åã„Çâ„ÅƄǵ„Éù„ɺ„Éà„ÇíË°å„Å£„Ŷ„Åä„Çä„Åæ„Åô„Älj∏ãË®òË®ò‰∫ã„Å´„Ŷ˩≥Á¥∞„ÇíË®ò˺â„Åó„Ŷ„Åä„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: IT・ベンチャー