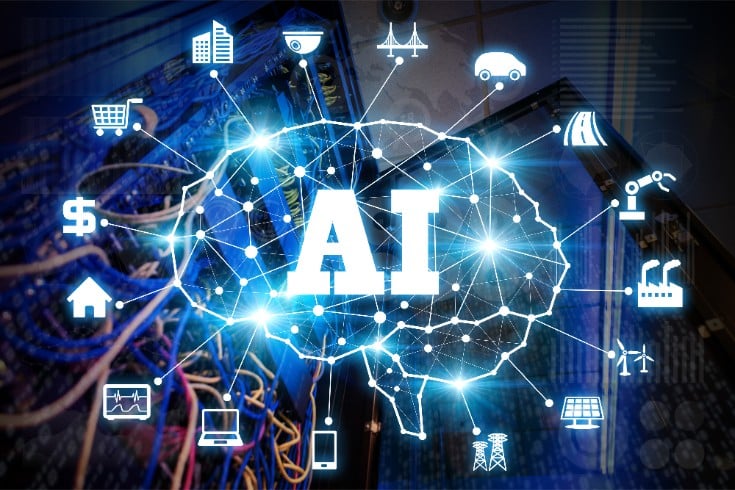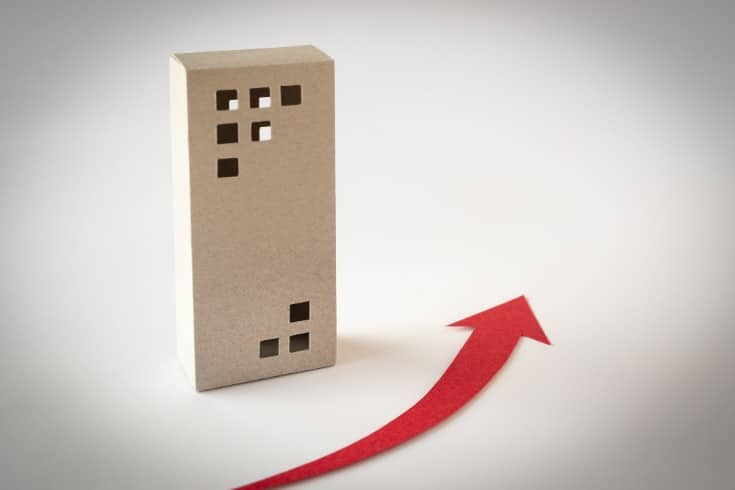ŃĆÉõ╗żÕÆī8Õ╣┤1µ£łµ¢ĮĶĪīŃĆæŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│ĢŃĆŹŃüīŃĆīõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│ĢŃĆŹŃüĖÕż¦µö╣µŁŻŃĆü5ŃüżŃü«õĖ╗Ķ”üµö╣µŁŻńé╣ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼

µĆźµ┐ĆŃü¬õ║║õ╗ČĶ▓╗ŃéäÕĤµØɵ¢ÖĶ▓╗ŃĆüŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝Ńé│Ńé╣ŃāłŃü«ķ½śķ©░Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüõ╝üµźŁķ¢ōÕÅ¢Õ╝ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõŠĪµĀ╝Ķ╗óÕ½üŃüīÕż¦ŃüŹŃü¬Ķ¬▓ķĪīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüåŃüŚŃü¤ńŖȵ│üŃéÆÕÅŚŃüæŃĆüÕģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃü©õĖŁÕ░Åõ╝üµźŁÕ║üŃü»ŃĆüńÖ║µ│©Õü┤Ńā╗ÕÅŚµ│©Õü┤ŃüīÕ»ŠńŁēŃü¬ń½ŗÕĀ┤Ńü¦õŠĪµĀ╝ŃéÆõ║żµĖēŃüŚŃéäŃüÖŃüÅŃü¬ŃéŗŃéłŃüåŃĆüŃéĄŃāŚŃā®ŃéżŃāüŃé¦Ńā╝Ńā│Õģ©õĮōŃü½ŃĆīµ¦ŗķĆĀńÜäŃü¬õŠĪµĀ╝Ķ╗óÕ½üŃĆŹŃéƵĀ╣õ╗śŃüŗŃüøŃéŗµ¢░Ńü¤Ńü¬õ╗ĢńĄäŃü┐Ńü«µĢ┤ÕéÖŃéÆķĆ▓ŃéüŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüØŃü«õĖĆńÆ░Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüõ╗żÕÆī8Õ╣┤’╝ł2026Õ╣┤’╝ē1µ£łŃü½Ńü»ŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│Ģ’╝łµŁŻÕ╝ÅÕÉŹń¦░’╝ÜõĖŗĶ½ŗõ╗Żķćæµö»µēĢķüģÕ╗ČńŁēķś▓µŁóµ│Ģ’╝ēŃĆŹŃüīÕż¦ŃüŹŃüŵö╣µŁŻŃüĢŃéīŃĆüµ│ĢÕŠŗŃü«µŁŻÕ╝ÅÕÉŹń¦░ŃééŃĆīĶŻĮķĆĀÕ¦öĶ©ŚńŁēŃü½õ┐éŃéŗõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗõ╗ŻķćæŃü«µö»µēĢŃü«ķüģÕ╗ČńŁēŃü«ķś▓µŁóŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗŃĆŹŃüĖŃü©Õżēµø┤ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü¦Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦Õ»ŠĶ▒ĪÕż¢ŃüĀŃüŻŃü¤ÕÅ¢Õ╝ĢķĪ×Õ×ŗŃéäŃāĢŃā¬Ńā╝Ńā®Ńā│Ńé╣Ńü«õ┐ØĶŁĘń»äÕø▓Ńü«µŗĪÕż¦ŃĆüµēŗÕĮóµēĢŃüäŃü«ÕĤÕēćń”üµŁóŃĆüĶĪīµö┐Ńü½ŃéłŃéŗķØóńÜäÕ¤ĘĶĪīŃü«Õ╝ĘÕī¢Ńü¬Ńü®ŃĆüõ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃééÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ŃüīÕż¦ŃüŹŃüäÕåģÕ«╣ŃüīÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüµö╣µŁŻµ│ĢŃü«õĖ╗Ķ”üŃāØŃéżŃā│ŃāłŃéƵĢ┤ńÉåŃüŚŃĆüõ┐ØĶŁĘÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃü©Õ¦öĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«ń½ŗÕĀ┤ŃüŗŃéēõĮĢŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗŃü«ŃüŗŃéÆŃĆüÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüīŃéÅŃüŗŃéŖŃéäŃüÖŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│ĢŃĆŹŃü©Ńü»
ŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│ĢŃĆŹŃü©Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ń¼¼1µØĪŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüŖŃéŖŃĆüŃĆīõĖŗĶ½ŗõ╗ŻķćæŃü«µö»µēĢķüģÕ╗ČńŁēŃéÆķś▓µŁóŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüĶ”¬õ║ŗµźŁĶĆģŃü«õĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆÕģ¼µŁŻŃü¬ŃéēŃüŚŃéüŃéŗŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüõĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü«Õł®ńøŖŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüŚŃĆüŃééŃüŻŃü”ÕøĮµ░æńĄīµĖłŃü«ÕüźÕģ©Ńü¬ńÖ║ķüöŃü½Õ»äõĖÄŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗŃĆŹµ│ĢÕŠŗŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│ĢŃĆŹŃü»ŃĆīńŗ¼ÕŹĀń”üµŁóµ│Ģ’╝łń¦üńÜäńŗ¼ÕŹĀŃü«ń”üµŁóÕÅŖŃü│Õģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ńó║õ┐ØŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗ’╝ēŃĆŹŃéÆĶŻ£Õ«īŃüÖŃéŗńē╣Õłźµ│ĢŃü©ŃüŚŃü”ÕłČÕ«ÜŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õĖŗĶ½ŗµ│ĢŃü©ńŗ¼ÕŹĀń”üµŁóµ│ĢŃü»ŃĆüŃüäŃüÜŃéīŃééÕģ¼µŁŻŃü¬ÕÅ¢Õ╝ĢŃü©Ķć¬ńö▒Ńü¬ń½Čõ║ēńÆ░ÕóāŃéÆÕ«łŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ķćŹĶ”üŃü¬µ│ĢÕŠŗŃü¦ŃĆüõĖŗĶ½ŗµ│ĢŃü»ŃĆüÕÅŚĶ©Ś’╝łõĖŗĶ½ŗ’╝ēõ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕ¦öĶ©Ś’╝łĶ”¬’╝ēõ║ŗµźŁĶĆģŃü«õĖŹÕĮōŃü¬ÕÅ¢ŃéŖµē▒ŃüäŃéÆĶ”ÅÕłČŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüõ╗żÕÆī8Õ╣┤’╝ł2026Õ╣┤’╝ēŃüŗŃéēµ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃéŗµö╣µŁŻµ│ĢŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃüØŃü«ń¼¼1µØĪŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃééŃĆīµłæŃüīÕøĮŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕāŹŃüŹµ¢╣Ńü«ÕżÜµ¦śÕī¢Ńü«ķĆ▓Õ▒ĢŃü½ķææŃü┐ŃĆüÕĆŗõ║║Ńüīõ║ŗµźŁĶĆģŃü©ŃüŚŃü”ÕÅŚĶ©ŚŃüŚŃü¤µźŁÕŗÖŃü½Õ«ēÕ«ÜńÜäŃü½ÕŠōõ║ŗŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗńÆ░ÕóāŃéƵĢ┤ÕéÖŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüńē╣Õ«ÜÕÅŚĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃü½µźŁÕŗÖÕ¦öĶ©ŚŃéÆŃüÖŃéŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüńē╣Õ«ÜÕÅŚĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃü«ńĄ”õ╗śŃü«ÕåģÕ«╣ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«õ║ŗķĀģŃü«µśÄńż║ŃéÆńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéŗńŁēŃü«µÄ¬ńĮ«ŃéÆĶ¼øŃüÜŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüńē╣Õ«ÜÕÅŚĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃü½õ┐éŃéŗÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ķü®µŁŻÕī¢ÕÅŖŃü│ńē╣Õ«ÜÕÅŚĶ©ŚµźŁÕŗÖÕŠōõ║ŗĶĆģŃü«Õ░▒µźŁńÆ░ÕóāŃü«µĢ┤ÕéÖŃéÆÕø│ŃéŖŃĆüŃééŃüŻŃü”ÕøĮµ░æńĄīµĖłŃü«ÕüźÕģ©Ńü¬ńÖ║Õ▒ĢŃü½Õ»äõĖÄŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗŃĆŹµ│ĢÕŠŗŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃüīµśÄĶ©śŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ÕÅ¢Õ╝ĢõĖŖŃü«ÕĢÅķĪīŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüµÖéõ╗ŻŃü«ÕżēÕī¢Ńü½Õ┐£ŃüśŃü¤µÄ¬ńĮ«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©Ńüīµö╣µŁŻŃü«ĶāīµÖ»Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ╗żÕÆī8Õ╣┤’╝ł2026Õ╣┤’╝ēŃü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃéŗµö╣µŁŻµ│ĢŃü»ŃĆüÕāŹŃüŹµ¢╣Ńü«ÕżÜµ¦śÕī¢Ńü©ŃüäŃüåµÖéõ╗ŻŃü«ÕżēÕī¢Ńü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéµö╣µŁŻµ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüÕĆŗõ║║õ║ŗµźŁõĖ╗Ńü¬Ńü®ŃüīÕ«ēÕ┐āŃüŚŃü”µźŁÕŗÖŃü½ÕÅ¢ŃéŖńĄäŃéüŃéŗńÆ░ÕóāŃéƵĢ┤ŃüłŃéŗŃüōŃü©Ńüīńø«ńÜäŃü¦ŃüéŃéŗŃü©µśÄńó║Ńü½ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵟ŁÕŗÖŃéÆÕ¦öĶ©ŚŃüÖŃéŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Õźæń┤äÕåģÕ«╣Ńü«µśÄńż║Ńü¬Ńü®ŃéÆńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ķü®µŁŻÕī¢Ńü©Õ░▒µźŁńÆ░ÕóāŃü«µĢ┤ÕéÖŃéÆÕø│ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÅéĶĆā’╝ÜÕģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝Ü’Į£õĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│Ģ’╝łÕÅ¢ķü®µ│Ģ’╝ēķ¢óõ┐é
µö╣µŁŻõĖŗĶ½ŗµ│Ģ’╝łõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│Ģ’╝ēŃü«5ŃüżŃü«ŃāØŃéżŃā│Ńāł

Ķ┐æÕ╣┤Ńü«µĆźµ┐ĆŃü¬ÕŖ┤ÕŗÖĶ▓╗Ńéäńē®õŠĪŃü«õĖŖµśćŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüŚŃĆüõ║ŗµźŁĶĆģķ¢ōŃü«ÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢ŃéÆÕø│ŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃü©õĖŁÕ░Åõ╝üµźŁÕ║üŃüīÕøĮõ╝ÜŃü½µÅÉÕć║ŃüŚŃü¤µö╣µŁŻµ│ĢµĪłŃüī2025Õ╣┤5µ£ł16µŚźŃü½ÕÅ»µ▒║Ńā╗µłÉń½ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«µö╣µŁŻŃü½ŃéłŃéŖŃĆü2026Õ╣┤1µ£ł1µŚźŃüŗŃéēŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│ĢŃĆŹŃü»ŃĆīõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│ĢŃĆŹŃü½ÕÉŹń¦░ŃüīÕżēŃéÅŃéŖŃĆüÕåģÕ«╣ŃééÕż¦Õ╣ģŃü½µö╣µŁŻŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗Ńü¬µö╣µŁŻńé╣Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«5ŃüżŃü¦ŃüÖŃĆé
- ÕŹöĶŁ░ŃéÆķü®ÕłćŃü½ĶĪīŃéÅŃü¬Ńüäõ╗ŻķćæķĪŹŃü«µ▒║Õ«ÜŃü«ń”üµŁó
- µēŗÕĮóµēĢńŁēŃü«ń”üµŁó
- ķüŗķĆüÕ¦öĶ©ŚŃü«Õ»ŠĶ▒ĪÕÅ¢Õ╝ĢŃüĖŃü«Ķ┐ĮÕŖĀ
- ÕŠōµźŁÕōĪÕ¤║µ║¢Ńü«Ķ┐ĮÕŖĀ
- ķØóńÜäÕ¤ĘĶĪīŃü«Õ╝ĘÕī¢
õ╗źõĖŗŃĆüÕÉäµö╣µŁŻńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃāØŃéżŃā│ŃāłŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ÕŹöĶŁ░ŃéÆķü®ÕłćŃü½ĶĪīŃéÅŃü¬Ńüäõ╗ŻķćæķĪŹŃü«µ▒║Õ«ÜŃü«ń”üµŁó
ÕĤµØɵ¢ÖĶ▓╗ŃéäŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝õŠĪµĀ╝ŃĆüÕŖ┤ÕŗÖĶ▓╗Ńü¬Ńü®ŃüīõĖŖµśćŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüńÖ║µ│©ĶĆģ’╝łĶ”¬õ║ŗµźŁĶĆģ’╝ēŃüīŃüØŃü«Ńé│Ńé╣ŃāłõĖŖµśćÕłåŃéÆÕÅ¢Õ╝ĢõŠĪµĀ╝Ńü½ÕÅŹµśĀŃüøŃüÜŃĆüÕŠōµØźŃü«õŠĪµĀ╝Ńü«ŃüŠŃüŠÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆńČÜŃüæŃüĢŃüøŃéŗŃü©ŃüäŃüåõŠĪµĀ╝µŹ«ŃüłńĮ«ŃüŹŃüīÕĢÅķĪīĶ”¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕĢÅķĪīŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµö╣µŁŻµ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüÕŹöĶŁ░ŃéÆķü®ÕłćŃü½ĶĪīŃéÅŃü¬ŃüäŃüŠŃüŠõĖƵ¢╣ńÜäŃü½õ╗ŻķćæķĪŹŃéƵ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆń”üµŁóŃüŚŃĆüõŠĪµĀ╝õ║żµĖēŃü«ķĆŵśÄµĆ¦Ńü©Õģ¼µŁŻµĆ¦ŃéÆÕ╝ĘÕī¢ŃüÖŃéŗĶ”ÅÕ«ÜŃéÆĶ©ŁŃüæŃüŠŃüŚŃü¤’╝łµö╣µŁŻµ│Ģń¼¼5µØĪ2ķĀģ4ÕÅĘ’╝ēŃĆé
ŃüōŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃüīĶ┐ĮÕŖĀŃüĢŃéīŃü¤ĶāīµÖ»Ńü½Ńü»ŃĆüÕŠōµØźŃü«ŃĆīĶ▓ĘŃüäŃü¤Ńü¤ŃüŹŃĆŹĶ”ÅÕłČŃüĀŃüæŃü¦Ńü»Õ»ŠÕ┐£ŃüīķøŻŃüŚŃüŗŃüŻŃü¤ÕĢÅķĪīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- ŃĆīĶ▓ĘŃüäŃü¤Ńü¤ŃüŹŃĆŹŃü«ń½ŗĶ©╝Ńü«ķøŻŃüŚŃüĢ’╝ÜÕŠōµØźŃü«Ķ▓ĘŃüäŃü¤Ńü¤ŃüŹĶ”ÅÕłČŃü¦Ńü»ŃĆüŃĆīķĆÜÕĖĖµö»µēĢŃéÅŃéīŃéŗÕ»ŠõŠĪ’╝łÕĖéÕĀ┤õŠĪµĀ╝’╝ēŃü½µ»öŃü╣ĶæŚŃüŚŃüÅõĮÄŃüäŃĆŹŃüōŃü©ŃéÆĶ©╝µśÄŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüńē╣µ│©ÕōüŃü¬Ńü®Ńü¦Ńü»ÕĖéÕĀ┤õŠĪµĀ╝Ńü«ń«ŚÕ«ÜŃüīķøŻŃüŚŃüÅŃĆüķüĢÕÅŹŃéÆń½ŗĶ©╝ŃüÖŃéŗŃāÅŃā╝ŃāēŃā½Ńüīķ½śŃüäŃü©ŃüäŃüåĶ¬▓ķĪīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- õ║żµĖēŃü«µ®¤õ╝ÜŃüĢŃüłõĖÄŃüłŃéēŃéīŃü¬ŃüäÕ«¤µģŗ’╝Üń½ŗÕĀ┤Ńü«Õ╝▒ŃüäÕÅŚµ│©ĶĆģŃü»ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢÕü£µŁóŃéƵüÉŃéīŃü”õŠĪµĀ╝õ║żµĖēŃéÆÕłćŃéŖÕć║ŃüÖŃüōŃü©Ķć¬õĮōŃüīÕø░ķøŻŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃü¤Ńü©Ńüłńö│ŃüŚÕģźŃéīŃü”ŃééŃĆüńÖ║µ│©ĶĆģŃü½ńäĪĶ”¢ŃüĢŃéīŃü¤ŃéŖŃĆüŃüŠŃü©ŃééŃü½ÕÅ¢ŃéŖÕÉłŃüŻŃü”ŃééŃéēŃüłŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃĆīķ¢ĆÕēŹµēĢŃüäŃĆŹŃüīµ©¬ĶĪīŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü»ŃĆüŃüōŃü«ŃĆīõ║żµĖēŃü«Ńé╣Ńé┐Ńā╝ŃāłŃā®ŃéżŃā│Ńü½ń½ŗŃü”Ńü¬ŃüäŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕĢÅķĪīŃéÆĶ¦ŻµČłŃüŚŃĆüÕ»ŠńŁēŃü¬ń½ŗÕĀ┤Ńü¦Ķ®▒ŃüŚÕÉłŃüäŃéÆĶĪīŃüåµ®¤õ╝ÜŃéƵ│ĢńÜäŃü½õ┐ØķÜ£ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃéĄŃāŚŃā®ŃéżŃāüŃé¦Ńā╝Ńā│Õģ©õĮōŃü¦Ńé│Ńé╣ŃāłõĖŖµśćÕłåŃéÆķü®ÕłćŃü½ÕłåµŗģŃüŚŃĆüõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃüīĶ│āõĖŖŃüÆŃü«ÕĤĶ│ćŃéÆńó║õ┐ØŃü¦ŃüŹŃéŗÕģ¼µŁŻŃü¬ÕÅ¢Õ╝ĢńÆ░ÕóāŃéƵĢ┤ŃüłŃéŗńŗÖŃüäŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µö╣µŁŻŃü½ŃéłŃéŖŃĆüńÖ║µ│©ĶĆģ’╝łÕ¦öĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģ’╝ēŃü»õ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬Õ»ŠÕ┐£ŃüīµĆźÕŗÖŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- õŠĪµĀ╝õ║żµĖēŃü½Õ┐£ŃüśŃéŗńżŠÕåģŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü«µĢ┤ÕéÖ’╝ÜĶ│╝Ķ▓Ęķā©ķ¢ĆŃéäÕ¢ČµźŁµŗģÕĮōĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüÕÅŚµ│©ĶĆģŃüŗŃéēŃü«õŠĪµĀ╝ÕŹöĶŁ░Ńü«Ķ”üĶ½ŗŃüīŃüéŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕ┐ģŃüÜÕ┐£ŃüśŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńżŠÕåģŃā½Ńā╝Ńā½Ńü©ŃüŚŃü”ÕŠ╣Õ║ĢŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- õŠĪµĀ╝µ▒║Õ«ÜŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ¬¼µśÄĶ▓¼õ╗╗Ńü«µ║¢ÕéÖ’╝ÜõŠĪµĀ╝ŃéƵŹ«ŃüłńĮ«ŃüÅŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»Õ╝ĢŃüŹõĖŗŃüÆŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«µĀ╣µŗĀŃü©Ńü¬ŃéŗŃāćŃā╝Ńé┐ŃéäÕ«óĶ”│ńÜäŃü¬µāģÕĀ▒ŃéƵ║¢ÕéÖŃüŚ’╝ÜńøĖµēŗŃü½Ķ¬¼µśÄŃü¦ŃüŹŃéŗõĮōÕłČŃéƵĢ┤ŃüłŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
- õ║żµĖēĶ©śķī▓Ńü«õ┐Øń«Ī’╝ÜŃāłŃā®Ńā¢Ńā½ŃéÆķü┐ŃüæŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃüäŃüżŃĆüĶ¬░ŃüīŃĆüŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ÕåģÕ«╣Ńü¦ÕŹöĶŁ░ŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤Ńü«ŃüŗŃéÆĶŁ░õ║ŗķī▓Ńü¬Ńü®Ńü¦Ķ©śķī▓Ńā╗õ┐Øń«ĪŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīµÄ©Õź©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
µēŗÕĮóµēĢńŁēŃü«ń”üµŁó
Õ¦öĶ©Śõ╗ŻķćæŃü«µö»µēĢµ£¤µŚźŃü»ŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦ķĆÜŃéŖ60µŚźõ╗źÕåģŃü©ŃüÖŃéŗŃā½Ńā╝Ńā½Ńü»ńČŁµīüŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü¦µ¢░Ńü¤Ńü½µö»µēĢµēŗµ«ĄŃüīÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ńÅŠķćæµēĢŃüäŃü½ķÖÉÕ«ÜŃüĢŃéīŃéŗńé╣ŃüīÕż¦ŃüŹŃü¬Õżēµø┤ńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆé
õ╗ŖÕø×Ńü«µ│Ģµö╣µŁŻŃü¦Ńü»ŃĆüÕÅŚµ│©ĶĆģ’╝łõĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģ’╝ēŃü«Ķ│ćķćæń╣░ŃéŖŃü«Ķ▓ĀµŗģŃéƵĀ╣µ£¼ńÜäŃü½Ķ¦ŻµČłŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕ¦öĶ©Śõ╗ŻķćæŃü«µö»µēĢŃüäµ¢╣µ│ĢŃüīÕÄ│µĀ╝Õī¢ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦ÕĢåµģŻń┐ÆŃü©ŃüŚŃü”µ«ŗŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ń┤äµØ¤µēŗÕĮóŃü¦Ńü«µö»µēĢŃüäŃüīÕģ©ķØóńÜäŃü½ń”üµŁóŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüķø╗ÕŁÉĶ©śķī▓Õ饵©®’╝łŃü¦ŃéōŃüĢŃüä’╝ēŃéäŃāĢŃéĪŃé»Ńé┐Ńā¬Ńā│Ńé░Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüµö»µēĢµ£¤µŚźŃüŠŃü¦Ńü½ńÅŠķćæÕī¢ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķøŻŃüŚŃüäŃééŃü«Ńü»ÕÉīµ¦śŃü½ń”üµŁóŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«µö╣µŁŻŃü«ĶāīµÖ»Ńü½Ńü»ŃĆüµēŗÕĮóµēĢŃüäŃüīÕÅŚµ│©ĶĆģŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ÕżÜŃüÅŃü«õĖŹÕł®ńøŖŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüŚŃü”ŃüŹŃü¤Õ«¤µģŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- Ķ│ćķćæń╣░ŃéŖŃü«µé¬Õī¢’╝ܵēŗÕĮóŃü»ńÅŠķćæÕī¢Ńü¦ŃüŹŃéŗŃüŠŃü¦Ńü«µ£¤ķ¢ō’╝łµö»µēĢŃéĄŃéżŃāł’╝ēŃüīÕ╣│ÕØć100µŚźÕēŹÕŠīŃü©ķØ×ÕĖĖŃü½ķĢĘŃüÅŃĆüÕÅŚµ│©ĶĆģŃü»ŃüØŃü«ķ¢ōŃĆüÕŻ▓õĖŖŃüīŃüéŃüŻŃü”ŃééµēŗÕģāŃü½ńÅŠķćæŃüīŃü¬ŃüäńŖȵģŗŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüńĄīÕ¢ČŃüīÕ£¦Ķ┐½ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- õĮÖÕłåŃü¬Ńé│Ńé╣ŃāłĶ▓Āµŗģ’╝ܵēŗÕĮóŃéƵ£¤µŚźÕēŹŃü½ńÅŠķćæÕī¢ŃüÖŃéŗŃü½Ńü»ŃĆüķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃü½µēŗµĢ░µ¢Ö’╝łÕē▓Õ╝Ģµ¢Ö’╝ēŃéƵö»µēĢŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«Ńé│Ńé╣ŃāłŃü»ÕÅŚµ│©ĶĆģŃüīõĖƵ¢╣ńÜäŃü½Ķ▓ĀµŗģŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- ń«ĪńÉåŃü«µēŗķ¢ōŃü©Ńā¬Ńé╣Ńé»’╝Üń┤ÖŃü«µēŗÕĮóŃü»ŃĆüń┤øÕż▒ŃéäńøŚķøŻŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŗŃü╗ŃüŗŃĆüŃüØŃü«õ┐Øń«ĪŃā╗ń«ĪńÉåŃü½Ńééµēŗķ¢ōŃü©Ńé│Ńé╣ŃāłŃüīŃüŗŃüŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- õĖŹÕģ¼Õ╣│Ńü¬Ķ▓ĀµŗģŃü«Ķ╗óÕ½ü’╝ÜńÖ║µ│©ĶĆģÕü┤Ńü»µö»µēĢŃüäŃéÆÕģłÕ╗ČŃü░ŃüŚŃü½ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü½ńäĪÕł®ÕŁÉŃü¦Ķ│ćķćæŃéÆĶ¬┐ķüöŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü©ÕÉīŃüśµü®µüĄŃéÆÕÅŚŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃü«Ķ▓ĀµŗģŃü»ŃüÖŃü╣Ńü”ÕÅŚµ│©ĶĆģŃü½µŖ╝ŃüŚõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃéīŃüŠŃü¦ŃééĶĪīµö┐µīćÕ░ÄŃü½ŃéłŃéŖµēŗÕĮóŃéĄŃéżŃāłŃü«ń¤ŁńĖ«Ńü¬Ńü®ŃüīķĆ▓ŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”µēŗÕĮóµģŻĶĪīŃüīµĀ╣Õ╝ĘŃüŵ«ŗŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃüåŃüŚŃü¤ńŖȵ│üŃéÆÕ«īÕģ©Ńü½Ķ¦ŻµČłŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü«µ│Ģµö╣µŁŻŃü¦ŃüżŃüäŃü½ÕĤÕēćńÅŠķćæµēĢŃüäŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃĆüÕÅŚµ│©ĶĆģŃü½Ķ▓ĀµŗģŃéÆÕ╝ĘŃüäŃéŗµö»µēĢŃüäµēŗµ«ĄŃüīń”üµŁóŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
õ┐ØĶŁĘŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü½ŃĆīńē╣Õ«ÜķüŗķĆüÕ¦öĶ©ŚŃĆŹŃéÆĶ┐ĮÕŖĀ
õ╗ŖÕø×Ńü«µ│Ģµö╣µŁŻŃü¦ŃĆüõ┐ØĶŁĘŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ń©«ķĪ×ŃüīµŗĪÕż¦ŃüĢŃéīŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü½ŃĆīńē╣Õ«ÜķüŗķĆüÕ¦öĶ©ŚŃĆŹŃüīÕŖĀŃéÅŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦Õ»ŠĶ▒ĪÕż¢ŃüĀŃüŻŃü¤ŃāłŃā®ŃāāŃé»ķüŗķĆüµźŁĶĆģŃü¬Ńü®ŃüīĶŹĘõĖ╗ŃüŗŃéēÕÅŚŃüæŃéŗķüŗķĆüÕ¦öĶ©ŚŃéƵ│ĢŃü«õ┐ØĶŁĘÕ»ŠĶ▒ĪŃü½ÕɽŃéüŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃĆüńē®µĄüµźŁńĢīŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ķü®µŁŻÕī¢ŃéÆÕø│ŃéŗŃü«Ńüīńø«ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃüŠŃü¦õĖŗĶ½ŗµ│ĢŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«4ŃüżŃü«ÕÅ¢Õ╝ĢķĪ×Õ×ŗŃü½ķÖÉŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- ĶŻĮķĆĀÕ¦öĶ©Ś
- õ┐«ńÉåÕ¦öĶ©Ś
- µāģÕĀ▒µłÉµ×£ńē®õĮ£µłÉÕ¦öĶ©Ś’╝łŃāŚŃāŁŃé░Ńā®ŃāĀŃĆüWebĶ©śõ║ŗŃĆüĶ©ŁĶ©łÕø│Ńü¬Ńü®’╝ē
- ÕĮ╣ÕŗÖµÅÉõŠøÕ¦öĶ©Ś’╝łŃāĪŃā│ŃāåŃāŖŃā│Ńé╣ŃĆüŃé│Ńā╝Ńā½Ńé╗Ńā│Ńé┐Ńā╝µźŁÕŗÖŃü¬Ńü®’╝ē
õ╗żÕÆī8Õ╣┤’╝ł2026Õ╣┤’╝ēŃüŗŃéēŃü»ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü½Ōæż ńē╣Õ«ÜķüŗķĆüÕ¦öĶ©ŚŃüīÕŖĀŃéÅŃéŖŃĆüÕÉłĶ©ł5ķĪ×Õ×ŗŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µö╣µŁŻŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕĆŗõ║║õ║ŗµźŁõĖ╗Ńü«ŃāēŃā®ŃéżŃāÉŃā╝ŃéäõĖŁÕ░ÅŃü«ķüŗķĆüõ╝ÜńżŠŃüīŃĆüÕż¦µēŗŃü«ĶŹĘõĖ╗ŃéäÕģāĶ½ŗŃüæŃü«ķüŗķĆüõ╝ÜńżŠŃüŗŃéēõĖŹÕĮōŃü¬ÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆÕ╝ĘŃüäŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃéÆķś▓ŃüÄŃĆüŃéłŃéŖÕģ¼µŁŻŃü¬Õźæń┤äŃéÆńĄÉŃü╣ŃéŗńÆ░ÕóāŃüīµĢ┤ÕéÖŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ķü®ńö©ń»äÕø▓Ńü½ŃĆīÕŠōµźŁÕōĪµĢ░ŃĆŹÕ¤║µ║¢ŃéÆĶ┐ĮÕŖĀ

ŃüōŃéīŃüŠŃü¦Ńü«õĖŗĶ½ŗµ│ĢŃü»ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆńÖ║µ│©ŃüÖŃéŗÕü┤’╝łĶ”¬õ║ŗµźŁĶĆģ’╝ēŃü©ÕÅŚµ│©ŃüÖŃéŗÕü┤’╝łõĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģ’╝ēŃü«Ķ│ćµ£¼ķćæŃü«Õż¦ŃüŹŃüĢŃüĀŃüæŃü¦ķü®ńö©Õ»ŠĶ▒ĪŃü½Ńü¬ŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃéÆÕłżµ¢ŁŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüōŃü«õ╗ĢńĄäŃü┐Ńü½Ńü»Õż¦ŃüŹŃü¬µŖ£Ńüæń®┤ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶ│ćµ£¼ķćæŃü»Õ░ÅŃüĢŃüÅŃü”ŃééŃĆüÕŻ▓õĖŖĶ”ŵ©ĪŃéäÕŠōµźŁÕōĪµĢ░ŃüīķØ×ÕĖĖŃü½ÕżÜŃüäŃĆīĶ║½Ķ╗ĮŃü¬Õż¦õ╝üµźŁŃĆŹŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüITµźŁńĢīŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣µźŁŃü¬Ńü®Ńü¦Ńü»ŃĆüÕż¦ŃüŹŃü¬Ķ│ćµ£¼ŃüīŃü¬ŃüÅŃü”ŃééÕżÜµĢ░Ńü«ÕŠōµźŁÕōĪŃéƵŖ▒ŃüłŃĆüõ║ŗµźŁŃéÆµĆźµŗĪÕż¦ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ╝üµźŁŃüīÕżÜŃüÅŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬õ╝üµźŁŃüīŃĆüĶ│ćµ£¼ķćæŃüīĶć¬ÕłåŃü¤ŃüĪŃéłŃéŖÕż¦ŃüŹŃüäõĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü½ńÖ║µ│©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕŠōµØźŃü«Ńā½Ńā╝Ńā½Ńü¦Ńü»õĖŗĶ½ŗµ│ĢŃü«Õ»ŠĶ▒ĪÕż¢Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃü«ńĄÉµ×£ŃĆüÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü½Ńü»ńÖ║µ│©ĶĆģÕü┤ŃüīÕ£¦ÕĆÆńÜäŃü½Õ╝ĘŃüäń½ŗÕĀ┤Ńü½ŃüéŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüõĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü»µ│ĢÕŠŗŃü¦õ┐ØĶŁĘŃüĢŃéīŃüÜŃĆüõĖŹÕĮōŃü¬ÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆÕ╝ĘŃüäŃéēŃéīŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
õ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü¦Ńü»ŃĆüÕŠōµØźŃü«ŃĆīĶ│ćµ£¼ķćæÕ¤║µ║¢ŃĆŹŃü½ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü½ŃĆīÕŠōµźŁÕōĪµĢ░Õ¤║µ║¢ŃĆŹŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüĶ│ćµ£¼ķćæŃüīÕ░ÅŃüĢŃüÅŃü”ŃééÕŠōµźŁÕōĪµĢ░ŃüīÕżÜŃüäõ║ŗµźŁĶĆģŃüīŃĆüÕŠōµźŁÕōĪµĢ░Ńü«Õ░æŃü¬Ńüäõ║ŗµźŁĶĆģŃü½ńÖ║µ│©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃééŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü½µ│ĢŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃĆÉÕģĘõĮōõŠŗŃĆæ
- Õ¦öĶ©ŚŃüÖŃéŗÕü┤: AńżŠ’╝łĶ│ćµ£¼ķćæ 5,000õĖćÕåå / ÕŠōµźŁÕōĪ 400õ║║’╝ē
- ÕÅŚĶ©ŚŃüÖŃéŗÕü┤: BńżŠ’╝łĶ│ćµ£¼ķćæ 8,000õĖćÕåå / ÕŠōµźŁÕōĪ 50õ║║’╝ē
’╝£ŃüōŃéīŃüŠŃü¦Ńü«Ńā½Ńā╝Ńā½’╝łĶ│ćµ£¼ķćæÕ¤║µ║¢Ńü«Ńü┐’╝ē’╝×
AńżŠŃü»BńżŠŃéłŃéŖŃééĶ│ćµ£¼ķćæŃüīÕ░ÅŃüĢŃüäŃü¤ŃéüŃĆüŃüōŃü«ÕÅ¢Õ╝ĢŃü»õĖŗĶ½ŗµ│ĢŃü«Õ»ŠĶ▒ĪÕż¢Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéAńżŠŃüīBńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ńäĪńÉåŃü¬Ķ”üµ▒éŃéÆŃüŚŃü”ŃééŃĆüBńżŠŃü»µ│ĢÕŠŗŃü¦õ┐ØĶŁĘŃüĢŃéīŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
’╝£ŃüōŃéīŃüŗŃéēŃü«µ¢░Ńā½Ńā╝Ńā½’╝łÕŠōµźŁÕōĪµĢ░Õ¤║µ║¢ŃéÆĶ┐ĮÕŖĀ’╝ē’╝×
AńżŠŃü»ÕŠōµźŁÕōĪµĢ░Ńüī300õ║║ŃéÆĶČģŃüłŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüBńżŠŃü«ÕŠōµźŁÕōĪµĢ░’╝ł300õ║║õ╗źõĖŗ’╝ēŃéłŃéŖŃééÕżÜŃüäŃü¤ŃéüŃĆüŃüōŃü«ÕÅ¢Õ╝ĢŃü»ŃĆīõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│ĢŃĆŹŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüBńżŠŃü»µ│ĢÕŠŗŃü¦õ┐ØĶŁĘŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü½ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪµĢ░Ńü©ŃüäŃüåµ¢░ŃüŚŃüäŃĆīŃééŃü«ŃüĢŃüŚŃĆŹŃéÆÕŖĀŃüłŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüĶ│ćµ£¼ķćæŃü«ķĪŹŃüĀŃüæŃü¦Ńü»µŹēŃüłŃüŹŃéīŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤õ╝üµźŁķ¢ōŃü«Õ«¤Ķ│¬ńÜäŃü¬ÕŖøķ¢óõ┐éŃéÆŃéłŃéŖµŁŻńó║Ńü½ÕÅŹµśĀŃü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ķØóńÜäÕ¤ĘĶĪīŃü«Õ╝ĘÕī¢
õ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü¦Ńü»ŃĆüŃĆīķØóńÜäÕ¤ĘĶĪīŃü«Õ╝ĘÕī¢ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåµ¢░ŃüŚŃüäõ╗ĢńĄäŃü┐ŃééÕ░ÄÕģźŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃĆīķØóńÜäÕ¤ĘĶĪīŃü«Õ╝ĘÕī¢ŃĆŹŃü©Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃüŠŃü¦õĖ╗Ńü½Õģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃü©õĖŁÕ░Åõ╝üµźŁÕ║üŃüīµŗģŃüŻŃü”ŃüŹŃü¤µ│ĢÕŠŗŃü«ńøŻńØŻõĮōÕłČŃéÆŃĆüõ╗¢Ńü«ń£üÕ║üŃééÕĘ╗ŃüŹĶŠ╝ŃéōŃü¦ÕżÜĶ¦ÆńÜäŃü½Õ║āŃüÆŃéŗŃüōŃü©ŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü¦ŃĆüÕÉ䵟ŁńĢīŃéƵēĆń«ĪŃüÖŃéŗõ║ŗµźŁµēĆń«ĪÕż¦Ķ毒╝łõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕ╗║Ķ©ŁµźŁŃü¬ŃéēÕøĮÕ£¤õ║żķĆÜÕż¦ĶćŻŃĆüķüŗĶ╝ĖµźŁŃü¬ŃéēÕøĮÕ£¤õ║żķĆÜÕż¦ĶćŻŃĆüITķ¢óķĆŻŃü¬ŃéēńĄīµĖłńöŻµźŁÕż¦ĶćŻŃü¬Ńü®’╝ēŃü½ŃééŃĆüµ│ĢÕŠŗŃéÆÕ¤ĘĶĪīŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«µ¢░Ńü¤Ńü¬µ©®ķÖÉŃüīõĖÄŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüµŗģÕĮōŃüÖŃéŗµźŁńĢīŃü«õ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬ŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- µīćÕ░ÄŃā╗ÕŖ®Ķ©Ć:’╝ܵŗģÕĮōµźŁńĢīŃü«Ķ”¬õ║ŗµźŁĶĆģ’╝łńÖ║µ│©ĶĆģ’╝ēŃüīµ│ĢÕŠŗŃü½ķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŗŃü©Ķ¬ŹŃéüŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«õ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”µīćÕ░ÄŃā╗ÕŖ®Ķ©ĆŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- Ķ¬┐µ¤╗ÕŹöÕŖø:’╝ÜÕģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃüīĶ¬┐µ¤╗ŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃü½ŃĆüõ║ŗµźŁµēĆń«ĪÕż¦ĶćŻŃééÕ┐ģĶ”üŃü¬ÕŹöÕŖøŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕłČÕ║”Ńü«Õ«¤ÕŖ╣µĆ¦ŃéÆķ½śŃéüŃĆüŃéłŃéŖÕżÜŃüÅŃü«õĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīńŗÖŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé
µö╣µŁŻõĖŗĶ½ŗµ│Ģ’╝łõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│Ģ’╝ēŃü«ńĮ░Õēć
õ╗ŖÕø×Ńü«µ│Ģµö╣µŁŻŃü»ŃĆüĶ”¬õ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃéłŃéŖõĖĆÕ▒żŃü«Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣’╝łµ│Ģõ╗żķüĄÕ«ł’╝ēŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«ńĮ░ÕēćŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃééńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃüÜŃĆüµö╣µŁŻÕŠīŃü«ŃĆīõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│ĢŃĆŹŃü¦ŃééŃĆüÕŠōµØźŃü«õĖŗĶ½ŗµ│ĢŃü©ÕÉīµ¦śŃü«ńĮ░ÕēćĶ”ÅÕ«ÜŃüīńČŁµīüŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüĶ”¬õ║ŗµźŁĶĆģŃü«õ╗ŻĶĪ©ĶĆģŃĆüõ╗ŻńÉåõ║║ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃü¬Ńü®ŃüīķüĢÕÅŹĶĪīńé║ŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«ĶĪīńé║ĶĆģŃü©µ│Ģõ║║Ńü«õĖĪµ¢╣ŃüīńĮ░ŃüøŃéēŃéīŃéŗŃĆīõĖĪńĮ░Ķ”ÅÕ«ÜŃĆŹŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ”¬õ║ŗµźŁĶĆģŃüīõĖŗĶ½ŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ▓ĘŃüäŃü¤Ńü¤ŃüŹŃĆüÕÅŚķĀśµŗÆÕÉ”ŃĆüõĖŹÕĮōŃü¬Ķ┐öÕōüŃĆüµö»µēĢķüģÕ╗ČŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ń”üµŁóĶĪīńé║ŃéÆĶĪīŃüäŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«Õģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃü½ŃéłŃéŗµś»µŁŻÕŗ¦ÕæŖŃü½ÕŠōŃéÅŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆü50õĖćÕååõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃüīń¦æŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«ń”üµŁóĶĪīńé║Ńü©Ńü»ÕłźŃü½ŃĆüÕģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃüīĶĪīŃüåµż£µ¤╗ŃéƵŗÆŃéōŃüĀŃéŖŃĆüÕ”©ŃüÆŃü¤ŃéŖŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ĶÖÜÕüĮŃü«ÕĀ▒ÕæŖŃéÆŃüŚŃü¤ŃéŖŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃééŃĆüÕÉīµ¦śŃü½ńĮ░ÕēćŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüõ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü¦Ńü»ŃĆüÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü½ńĮ░ÕēćŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü»ķ½śŃüŠŃüŻŃü¤Ńü©ĶĆāŃüłŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüØŃü«ńÉåńö▒Ńü«õĖĆŃüżŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüŃüŠŃüÜķüĢÕÅŹĶĪīńé║Ńü«ń»äÕø▓ŃüīµśÄńó║Õī¢Ńā╗µŗĪÕż¦ŃüĢŃéīŃü¤ńé╣ŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃüŠŃü¦Ńé░Ńā¼Ńā╝ŃéŠŃā╝Ńā│Ńü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃü¤ŃĆīÕŹöĶŁ░Ńü¬ŃüŹõŠĪµĀ╝µŹ«ŃüłńĮ«ŃüŹŃĆŹŃüīµśÄńó║Ńü½ŃĆīĶ▓ĘŃüäŃü¤Ńü¤ŃüŹŃĆŹŃü«õĖĆń©«Ńü©ŃüŚŃü”ń”üµŁóĶĪīńé║Ńü½ÕɽŃüŠŃéīŃü¤ŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃü½ŃéłŃéŗķüĢÕÅŹĶ¬ŹÕ«ÜŃüīÕ«╣µśōŃü½Ńü¬ŃéŖŃĆüµīćÕ░ÄŃéäÕŗ¦ÕæŖŃĆüŃüØŃüŚŃü”µ£ĆńĄéńÜäŃü½Ńü»ńĮ░ÕēćŃüĖŃü©ŃüżŃü¬ŃüīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüŠŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüńøŻńØŻõĮōÕłČŃüīÕ╝ĘÕī¢ŃüĢŃéīŃü¤ŃüōŃü©ŃééÕż¦ŃüŹŃü¬Ķ”üÕøĀŃü¦ŃüÖŃĆéÕģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃéäõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁÕ║üŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕÉäõ║ŗµźŁŃéƵēĆń«ĪŃüÖŃéŗń£üÕ║üŃü½ŃééµīćÕ░ÄŃā╗ÕŖ®Ķ©ĆŃü«µ©®ķÖÉŃüīõĖÄŃüłŃéēŃéīŃü¤ńĄÉµ×£ŃĆüŃéłŃéŖÕżÜŃüÅŃü«ŃĆīńø«ŃĆŹŃüīÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆńøŻĶ”¢ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃĆüķüĢÕÅŹĶĪīńé║ŃüīńÖ║Ķ”ŗŃüĢŃéīŃéäŃüÖŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Õģ¼µŁŻÕÅ¢Õ╝ĢÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃüŗŃéēÕŗ¦ÕæŖŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃü©ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ŃüØŃü«ÕåģÕ«╣’╝łķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤Ķ”¬õ║ŗµźŁĶĆģÕÉŹŃĆüķüĢÕÅŹõ║ŗÕ«¤Ńü«µ”éĶ”üŃü¬Ńü®’╝ēŃüīÕģ¼ĶĪ©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõ╝üµźŁÕÉŹŃüīÕģ¼ĶĪ©ŃüĢŃéīŃéīŃü░ŃĆü
- ŃĆīõĖŗĶ½ŗŃüæŃüäŃüśŃéüŃéÆŃüÖŃéŗõ╝üµźŁŃĆŹŃü©ŃüäŃüåŃāŹŃé¼ŃāåŃéŻŃā¢Ńü¬ŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃüīÕ║āŃüīŃéŗ
- ķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃéäÕÅ¢Õ╝ĢÕģłŃüŗŃéēŃü«õ┐Īńö©ŃüīõĮÄõĖŗŃüÖŃéŗ
- Õä¬ń¦ĆŃü¬õ║║µØÉŃü«µÄĪńö©ŃüīÕø░ķøŻŃü½Ńü¬Ńéŗ
Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃĆüõ║ŗµźŁŃü«ÕŁśńČÜŃü½ķ¢óŃéÅŃéŗµĘ▒Õł╗Ńü¬ŃāĆŃāĪŃā╝ŃéĖŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«Õģ¼ĶĪ©Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆķćŹŃüÅÕÅŚŃüæµŁóŃéüŃĆüńżŠÕåģŃü«ÕÅ¢Õ╝ĢõĮōÕłČŃéƵĢ┤ÕéÖŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝ܵö╣µŁŻõĖŗĶ½ŗµ│Ģ’╝łõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│Ģ’╝ēŃüĖŃü«Õ»ŠÕ┐£Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ńøĖĶ½ćŃéÆ
õ╗źõĖŖŃĆüŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│Ģ’╝łõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│Ģ’╝ēŃĆŹŃü«µö╣µŁŻńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõ┐ØĶŁĘÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃü©Õ¦öĶ©Śõ║ŗµźŁĶĆģŃü«Ķ”ÅÕłČŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüŃāØŃéżŃā│ŃāłŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õ╗ŖÕø×Ńü«µö╣µŁŻŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃü«Õ«¤ÕŗÖŃéäÕźæń┤äµøĖŃü«Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃééĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕøĮķÜøÕÅ¢Õ╝ĢŃü½ŃééõĖĆÕ«ÜŃü«µØĪõ╗ČŃü¦ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕ░éķ¢ĆńÜäŃü¬Õłżµ¢ŁŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
µö╣µŁŻŃĆīõĖŗĶ½ŗµ│Ģ’╝łõĖŁÕ░ÅÕÅŚĶ©ŚÕÅ¢Õ╝Ģķü®µŁŻÕī¢µ│Ģ’╝ēŃĆŹŃü½ŃüżŃüäŃü”õĖŹµśÄŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüĖńøĖĶ½ćŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆŃüŖŃüÖŃüÖŃéüŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃĆüńē╣Ńü½ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½ķ½śŃüäÕ░éķ¢ĆµĆ¦ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦Ńü»ŃĆüµØ▒Ķ©╝õĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃüŗŃéēŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝õ╝üµźŁŃüŠŃü¦ŃĆüŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬µĪłõ╗ČŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕźæń┤äµøĖŃü«õĮ£µłÉŃā╗Ńā¼ŃāōŃāźŃā╝ŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕźæń┤äµøĖŃü«õĮ£µłÉŃā╗Ńā¼ŃāōŃāźŃā╝ńŁēŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃéÆŃüöÕÅéńģ¦ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝õĖŗĶ½ŗµ│Ģ