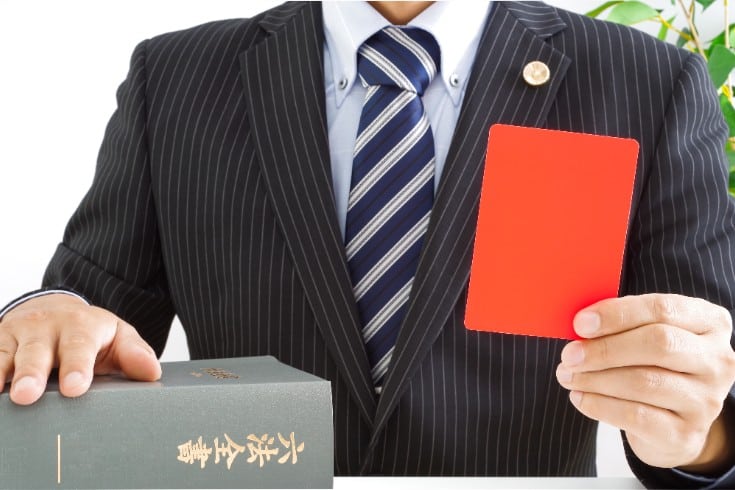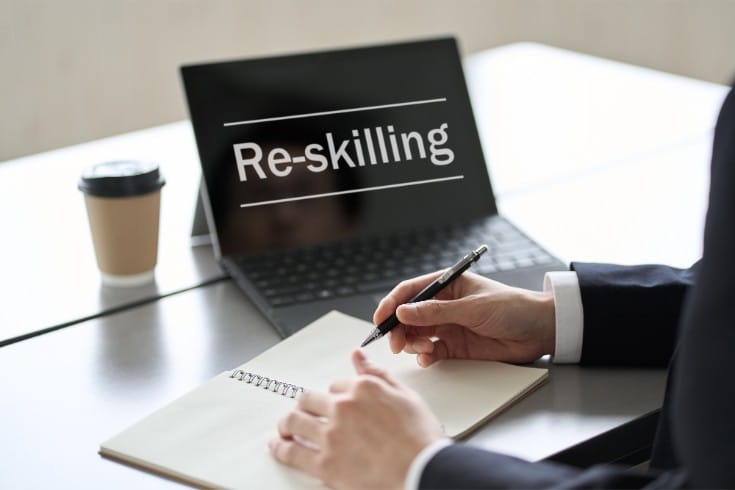人材開発支援助成金の定額制訓練(サブスクリプション型)に関する不正受給と対応

人材開発支援助成金は、企業が従業員の職業能力開発を計画的に支援する際に、その訓練費用や訓練期間中の賃金の一部を国が助成する制度です。特に、定額制訓練(サブスクリプション型)は、eラーニングなどを通じて多様な学習機会を柔軟に提供することを目的としており、多くの企業にとって人材育成の大きな後押しとなっています。この助成金は原則として返済不要であり、中小企業であれば訓練経費の最大75%が助成されるなど、そのメリットは大きいものと言えます。
しかし、この制度を悪用し、訓練機関を介した「キックバック」によって、企業が実質的に自己負担なしで訓練を受けるという不正受給が後を絶たず、深刻な社会問題となっています。会計検査院の調査では、2019年度から2023年度にかけて、人材開発支援助成金において1億円を超える不適切な受給が指摘されており、その多くがこのキックバックによるものでした。このような「実質無料」を謳う甘い誘惑が、企業を意図せず不正の片棒を担がせる危険性をはらんでいます。
本記事では、人材開発支援助成金の定額制訓練(サブスクリプション型)における不正受給、特にキックバック型不正受給に焦点を当て、その具体的な手口、なぜそれが不正とされるのか、発覚した場合に企業が直面する甚大なリスク、そして万が一不正に関与してしまった場合の対応について解説します。
この記事の目次
人材開発支援助成金(定額制訓練)の概要と支給要件

人材開発支援助成金の支給を受けるための最も重要な原則は、訓練に要した経費を「申請事業主が全て負担していること」です。この原則は、助成金が企業の自助努力を支援するものであり、実質的な費用負担なしに公的資金を受け取ることを許容しないという制度の趣旨によるものです。
定額制訓練は、労働者が多様な訓練を柔軟に選択・実施できるよう設計されたサブスクリプション型の研修サービスを対象としています。具体的には、eラーニングや同時双方向型の通信訓練がこれに含まれます。助成対象となる経費は、受講料や初期設定費用などのオプション経費です。助成率は、中小企業の場合、訓練経費の60%が助成され、さらに賃金要件や資格等手当要件を満たした場合には15%が加算され、最大75%の助成が可能です。定額制訓練では受講者1人あたりの限度額は設定されていませんが、人への投資促進コース全体として、1年度あたりの助成上限額は2,500万円と定められています。
助成金の支給を受けるためには、企業は「事業内職業能力開発計画」を作成し、「職業能力開発推進者」を選定します。この計画に基づき、「職業訓練実施計画届」を、訓練契約期間の開始日から遡って1ヶ月前までに労働局に提出しなければなりません。訓練は原則として労働時間内に行われ、対象となる雇用保険被保険者の従業員が受講し、その合計受講時間数が10時間以上である必要があります(ただし、終了した訓練の合計時間数は1人につき1時間以上)。訓練が完了したら、訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書と必要な書類を労働局に提出します。
キックバック型不正受給の具体的な手口と事例
人材開発支援助成金における不正受給は、制度の趣旨を逸脱し、公的資金を不当に取得する行為です。特に定額制訓練は、個々の訓練にかかる費用が明確になりにくいサブスクリプション型の特性を持つため、これを悪用したキックバック型の手口が報告されています。ここでは、具体的な事例で解説します。
キックバックの定義と不正受給とみなされる理由
前述したとおり、人材開発支援助成金の支給を受けるための最も重要な原則は、訓練に要した経費を「申請事業主が全て負担していること」です。この原則は、助成金が企業の自助努力を支援するものであり、実質的な費用負担なしに公的資金を受け取ることを許容しないという制度の趣旨によるものです。
キックバックとは、事業主が訓練実施機関(研修会社)に研修費用を支払い、その訓練実施機関またはその関連会社などから、支払った費用の一部が事業主に対して金銭的に還流される行為を指します。この還流は、「コンサルティング料」「キャッシュバック」「広告宣伝レビュー代」「受講者の感想提出への謝礼」など、さまざまな名目で行われています。また、ポイントやクーポン発行により、現金以外の方法で実質的な還流が行われるケースも存在します。
このようなキックバックは、助成金の基本要件である「事業主の全額負担」に明確に違反しており、ほぼ全てのケースで不正受給となります。そのため、教育訓練機関やその関連団体から、金銭の提供、費用の相殺、支払いの免除、融資、あるいは「広告宣伝レビュー」や「受講者の感想提出」などを名目とした金銭の授受があった場合など、実質的に訓練経費の返金が疑われる事案は、助成金の支給対象外と判断されます。この取り扱いは、過去の不正事例を受けて、2024年11月5日以降の職業訓練実施計画届からより明確に規定されることとなりました。当局は「形式」ではなく「実質」を重視して不正を判断しており、見かけ上の契約の名目ではなく、資金の流れ全体を精査して不正を摘発しています。
その他の不正受給の類型
キックバック以外にも、人材開発支援助成金では、架空研修や名義貸し、高額請求、虚偽申請、目的外利用、二重申請といった不正受給の手口が報告されています。これらの不正行為も、キックバックと同様に厳しく追及され、重いペナルティの対象となります。
不正受給が発覚する経路と厳格化する調査体制
助成金の不正受給は、さまざまな経路で発覚し、その摘発は年々厳格化されています。一度発覚すれば、企業に甚大な影響を及ぼすため、その経路を理解し、常に適正な運用を心がけることが重要です。
労働局による実地調査と書類チェック
最も一般的な発覚経路の一つが、労働局による実地調査です。労働局の審査官や監査官は、予告なしに事業所を訪問し、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿といった労働関係の書類を厳密に確認します。申請内容と実際の状況に矛盾がないか、例えば、休業した従業員として架空の人物が記載されていないか、休業中に業務を行っていなかったかなどを詳細に調べます。訓練日誌と出勤記録の照合も行われ、訓練日に有給休暇が取得されていないかといった矛盾点も確認されます。書類の改ざんや虚偽の記載は、帳簿の数字の食い違いとして必ず露呈するため、隠蔽することは不可能とされています。
内部告発の増加と通報窓口の整備
従業員や元従業員からの内部告発も、不正受給が発覚する主要な経路です。労働局のウェブサイトには、不正受給を告発するための専用投稿フォームが用意されており、匿名での通報も可能であるため、多くの情報が寄せられています。企業内で不正行為が行われている場合、従業員がその事実を認識し、関係機関に通報する可能性があります。これは、企業が内部統制を強化し、従業員が安心して不正を報告できる環境を整備することの重要性を示しています。
会計検査院による広範な調査と指摘
会計検査院は、公的資金の適正な執行を監視する独立機関であり、助成金の不正受給に対しても広範な調査を行います。会計検査院の調査は、特定の助成金に限定されず、過去の支給決定分についても遡って実施されます。
人材開発支援助成金においても、会計検査院は2019年度から2023年度までの支給決定分を対象に検査を行い、約3割にあたる32事業主(83件)、総額1億735万円が不正受給であると指摘しました。これらの不正の多くは、訓練実施機関から企業へのキックバックによる「実質無料」スキームが原因でした。会計検査院は、このような実質的な還流は、助成金の要件である「事業主の全額負担」を満たさないという判断に基づいて、厚生労働省に対して返還措置と制度見直しを要求しています。
他の助成金とのデータ照合と連携
複数の助成金制度を運用する中で、行政機関は申請内容のデータ照合を行い、重複や矛盾がないかを確認しています。例えば、同一の経費に対して複数の補助金や助成金を重複して申請・受給する「二重申請」は明確な不正行為とされています。異なる省庁や機関が管轄する助成金であっても、データ連携により不正が発覚する可能性は高まっています。また、不正受給に関与したコンサルタントが摘発された場合、その関与先が芋づる式に調査され、他の不正受給が発覚するケースも報告されています。
不正受給が企業にもたらすペナルティと影響

法的・経済的ペナルティ
不正受給が発覚した場合、企業には非常に厳しい法的・経済的ペナルティが科せられます。
不正に受給した助成金は、全額返還が命じられます。これに加え、返還額の2割に相当する違約金(加算金)と、不正受給日の翌日から返還完了までの年率3%の延滞金が請求されます。場合によっては、返還額が1.3倍以上になることもあります。
不正受給が決定された日から、原則として今後5年間、すべての雇用関係助成金(不正受給を行った以外の助成金を含む)の受給が停止されます。全額が返納されていない場合は、この停止期間が延長される可能性もあります。
特に悪質な不正行為は、刑法第246条の詐欺罪として刑事告発される可能性があります。詐欺罪が適用された場合、最大で10年以下の懲役が科される可能性があり、補助金等適正化法違反として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が併科されることもあります。
社会的信用の失墜と事業への悪影響
金銭的なペナルティに加えて、不正受給は企業の社会的信用を損なうことになります。
自主申告ではない不正受給が発覚し、支給取消額が100万円以上の場合、原則として事業主名、代表者名、事業所の所在地などが厚生労働省や都道府県労働局のウェブサイトで公表されます。この公表は長期にわたり不正の事実を知らしめることとなり、企業のブランドイメージやレピュテーションにダメージを与えます。
企業名が公表されることで、取引先からの信頼を失い、取引停止や契約解除に繋がることもあります。特に、コンプライアンス意識の欠如と判断されれば、金融機関からの評価が低下し、新たな融資や資金調達が困難になるなど、事業活動に広範な悪影響が及びます。
関係者(社会保険労務士・訓練実施機関)への連帯責任と罰則
不正受給の責任は、申請事業主だけでなく、不正行為を助言したり、積極的に関与したりした社会保険労務士や代理人、そして訓練実施機関にも及びます。
不正受給に関与した社会保険労務士や代理人は、事業主が負担すべき返還額(延滞金、2割の加算金を含む)について、事業主と連帯して返還義務を負います。不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金の申請が受理されなくなります。また、都道府県労働局や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトで、氏名や事業所名、不正の内容が公表されます。これは、専門家としての信用を失い、事業活動に大きな支障をきたすことになります。悪質なケースでは、社会保険労務士や訓練実施機関も詐欺罪などで刑事告発される可能性があります。
不適正・不正の疑いがある場合の自主申告と相談
万が一、自社が受給している助成金に不適正や不正の疑いがあると感じた場合は、速やかに自主申告を行うことが最も重要です。労働局が調査を行う前に自主申告を行い、迅速に全額を返還すれば、原則として事業主名の公表を免れる可能性があります。ただし、特に重大または悪質な場合はこの限りではありません。
自主申告を検討する際は、まず弁護士への相談を行うことを推奨します。法律の専門家である弁護士に相談することで、事実関係の整理、法的リスクの評価、複雑な手続である自主返還のサポート、そして詐欺罪による逮捕を回避するための弁護活動など、多岐にわたる支援を受けることができます。事案によっては、訓練機関に対する返金請求を行うべきケースもあります。
まとめ:人材開発支援助成金の不正受給については弁護士に相談を
人材開発支援助成金、特に定額制訓練は、企業が従業員の能力開発を促進し、生産性向上を図る上で極めて有効な国の支援策です。しかし、その柔軟な制度設計や高額な助成額は、同時に不正受給の誘因ともなり得ます。特に「実質無料」を謳うキックバック型の不正は、制度の根幹である「事業主の全額負担」原則を揺るがすものであり、会計検査院や労働局による厳格な調査の対象となっています。
企業がこの助成金を活用するにあたっては、制度の趣旨を深く理解し、公募要領や支給要件を遵守することが何よりも重要です。安易な「実質無料」の誘いに乗ることなく、研修内容の質と法令遵守を重視した信頼できる専門家や訓練実施機関を選定すべきです。
万が一、不適正や不正の疑いが生じた場合には、労働局や弁護士などの専門家に速やかに自主申告し、適切な対応を取ることが重要です。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT・ビジネスと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、ビジネスモデルや事業内容を深く理解した上で潜在的な法的リスクを洗い出し、リーガルサポートを行っております。補助金や助成金の不正受給に関連する業務に関しては、下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:補助金等の不正受給対応
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務