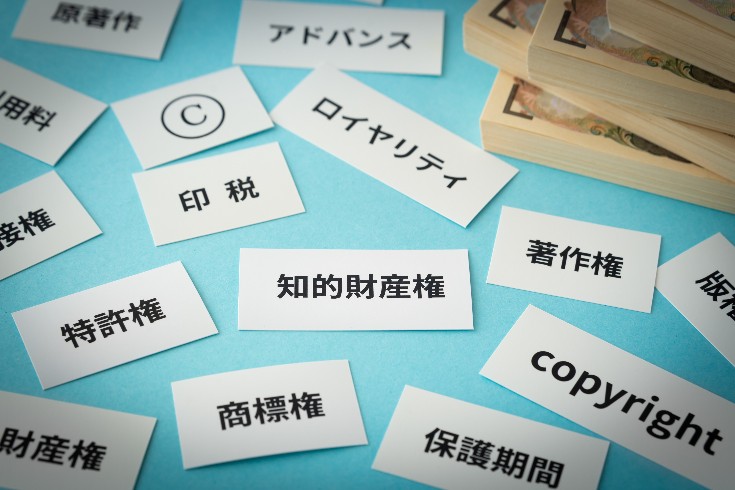【令和8年4月施行】「未管理著作物裁定制度」とは? 著作権法改正のポイントと企業実務への影響

日本政府は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や、国内の豊富な文化的資産を次世代に継承するためのデジタルアーカイブの構築を、国家的な重要課題として位置づけています。しかし、これらの取り組みの前に長らく立ちはだかってきたのが、著作権の権利処理という実務的な障壁です。
従来、著作権法には「著作権者不明」の著作物、いわゆる孤児著作物(Orphan Works)に対応するための裁定制度(著作権法第67条)が存在していました。しかし、実務上、より深刻な問題となっていたのは、権利者の所在は判明しているものの、連絡が取れない、あるいは連絡は取れても利用許諾の可否について返答が得られない「未管理」状態の著作物でした。これらは従来の制度ではカバーできず、多くのコンテンツが活用されないまま「眠っている」状態にありました。
こうした経済的・文化的停滞を解消し、DX時代に対応した円滑なコンテンツ利用を実現するため、「著作権法の一部を改正する法律」(令和5年法律第33号)が、令和5年(2023年)5月26日に公布されました。この改正法の中核をなすのが、新たに創設された「未管理著作物裁定制度」です。本制度は、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。この施行日は、制度の実務を担う「登録確認機関」の業務開始予定日とも一致しており、実際に本制度の利用申請を開始できる実務上のスタートラインとなります。
本制度は、従来の裁定制度では対応できなかった領域を包含するものであり、コンテンツ利用の可能性を大きく広げると同時に、権利者側の企業にも新たな権利管理体制を要求するものです。本記事では、新制度の概要と未管理著作物裁定制度の利用手続の流れについて詳細に解説します。
この記事の目次
令和5年著作物法改正と未管理著作物裁定制度創設の背景
今回の法改正は、社会的な要請に基づいて行われました。まず、本制度がいつから施行され、どのような背景で創設されたのか、その概要を確認します。
新制度の施行日:令和8年4月1日
本制度を含む改正著作権法(令和5年法律第33号)は、令和5年(2023年)5月26日に公布されました。同法の附則第1条本文において、主要部分の施行日は「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていました。
これを受け、令和7年(2025年)5月28日に公布された「著作権法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和7年政令第195号)により、本制度の施行日は令和8年(2026年)4月1日と正式に決定されました。
実務上も、本制度の申請窓口として文化庁に登録された公益社団法人著作権情報センター(CRIC)は、令和7年10月21日に登録を受け、その業務開始日を「2026年4月1日」と公表しています。したがって、企業が本制度の利用申請を開始できるのはこの日からとなります。
新制度創設の背景:DXと「眠れる著作物」の活用
新制度が創設された直接的な背景には、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に対応した著作権制度の整備が急務であったことが挙げられます。
文化庁の文化審議会著作権分科会がまとめた答申においても指摘されている通り、特に過去の映像、出版物、写真といったコンテンツをデジタルアーカイブ化する際や、新たなデジタルコンテンツを制作する際の権利処理の困難さが長年の課題となっていました。
権利者が不明であるか、判明していても連絡が取れない、あるいは連絡しても応答がないために、利用許諾が得られない著作物が大量に存在します。新制度の目的は、こうした「眠っている著作物」の活用を促進し、日本経済の活性化や文化的な資産の継承を図ることにあります。同時に、裁定制度を通じて利用者が補償金を供託する仕組みを設けることで、万が一権利者が見つかった場合に、その権利者への適切な対価還元を実現することも目的とされています。
従来の裁定制度(第67条)との決定的な違い

新制度の重要性を理解するためには、まず既存の制度がどのようなもので、なぜ改正が必要だったのかを知る必要があります。従来の裁定制度の課題と、新制度の対象範囲について解説します。
従来の「著作権者不明(Orphan Works)」制度の限界
著作権法には、従来から「著作権者不明等の場合における著作物の利用」を認める裁定制度が、第67条に規定されていました。
しかし、この第67条の制度が対象とするのは、あくまで「公表された著作物について、著作権者が不明であるとき、その他著作権者と連絡することができないとき」に限られていました。利用希望者は、著作権者を特定するために、公的記録の確認や関係団体への照会など、「相当な努力」を尽くしたことを証明する必要がありました。
この従来制度の最大の弱点は、実務上最も頻発する「著作権者は判明しているが、連絡をしても返事がない」というケースに対応できない点にありました。権利者が誰であるか(例えば、特定の企業や個人)が判明している以上、「著作権者不明」には該当しません。また、電子メールの送付や郵便物の送達が可能である以上、「連絡することができない」とも言えません。
結果として、権利者が意図的に利用許諾の問い合わせを「無視」している場合、利用希望者は法的に打つ手がなく、適法な利用を諦めざるを得ませんでした。この実務上のデッドロックが、新制度創設の直接的な契機となったと言えるでしょう。
新制度(第67条の3)の対象:「未管理公表著作物等」とは
今回の改正で新設されたのが、著作権法第67条の3に基づく「未管理著作物裁定制度」です。この制度は、従来制度が抱えていた前述の課題を正面から解決するものとなります。
本制度が対象とするのは、「未管理公表著作物等」と新たに定義された著作物です。これは、以下の2つの要件をいずれも満たす公表著作物等を指します。
- 集中管理されていないこと
著作権等管理事業者(JASRACやNexToneなど)によって集中管理されておらず、包括的な許諾を得ることができないこと。 - 利用の可否に係る意思が公表されていないこと
著作権者が、その著作物の利用許諾の可否(例えば「利用禁止」や「〇〇の条件で利用可」など)に関する意思を、インターネット等を通じて円滑に確認できる形で公表していないこと。
ここで注目すべきは、従来制度(第67条)が権利者の「所在」(不明・連絡不能)を要件としていたのに対し、新制度(第67条の3)は権利者の「意思」(不明・未公表)を要件としている点です。
これは、著作権実務における大きな転換を意味します。新制度の下では、著作権者が誰であるか明確に判明していても、その権利者が自社のウェブサイトなどでライセンスポリシーを公表しておらず、かつ個別の問い合わせに応答しない場合、その著作物は「未管理」として扱われ、裁定の対象となり得ます。これにより、従来制度では手詰まりとなっていた「判明しているが応答のない権利者」の著作物について、法的に利用できる道が初めて開かれることになります。
未管理著作物裁定制度の利用手続:申請から利用開始までの流れ
本制度を利用するにあたっては、定められた手順を正確に踏む必要があります。文化庁が定める告示やガイドラインに基づき、申請から利用開始までの具体的なステップを解説します。
ステップ1:利用者による「意思確認の措置」
利用希望者が新制度の裁定を申請するには、その前提として、「著作権者の意思を確認するための措置」を適切に講じたことを証明する必要があります。
この「措置」が、新制度における「相当な努力」に該当するプロセスとなります。具体的にどのような検索を何回行い、権利者への問い合わせ後、何日間応答がなければ「意思不明」とみなされるのか、その詳細は法律本体ではなく、下位の告示によって定められています。
企業が実務上、必ず参照しなければならないのは、「未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置等を定める件」(令和7年文化庁告示第6号)および、文化庁が公表する関連ガイドラインです。裁定申請が受理されるか否かは、この告示とガイドラインの要件を正確に満たしているかにかかっています。
ステップ2:「登録確認機関」への申請
利用希望者は、上記の「意思確認の措置」を講じた記録(検索履歴、メールの送信記録など)を添えて、裁定の申請を行います。この申請手続の簡素化・迅速化のため、改正法は文化庁長官の登録を受けた民間の「登録確認機関」が実務を担うことを認めています。
この登録確認機関として、文化庁は令和7年(2025年)10月21日付けで「公益社団法人著作権情報センター(CRIC)」を登録しました。
CRICの役割は、利用希望者からの申請の受付、申請者が「意思確認の措置」を適切に講じたかの要件確認、そして利用に際して利用者が供託すべき補償金額(通常の利用料相当額)の算出です。
参考:文化庁|指定補償金管理機関の指定・登録確認機関の登録の申請受付について
ステップ3:文化庁長官による裁定と補償金の供託
CRICによる要件確認と補償金額の算出を経て、最終的に文化庁長官が裁定を行います。
裁定が下りると、その事実(どの著作物が、どのような利用方法で、いつまで利用されるか)が公表されます。利用希望者は、CRICが算定した補償金を指定の機関(同じくCRICが「指定補償金管理機関」として指定されています)に供託することにより、裁定の範囲内で適法に著作物を利用する権利を得ます。
ただし、この利用権は永続的なものではありません。裁定によって認められる利用期間は、最大3年間に限定されます。
企業が取るべき実務対応:【利用者側】のリスクと対策
本制度は、コンテンツ利用の可能性を広げる一方で、利用する企業側には新たな法的リスク管理が求められます。どのような業界での活用が想定され、利用にあたってどのような点に注意すべきかを解説します。
影響を受ける業界と利用シーン
本制度の活用が特に期待されるのは、過去のコンテンツを扱うあらゆる業界です。文化庁が創設の背景として挙げているように、過去の作品(映像、書籍、写真、イラストなど)のデジタルアーカイブ化が、最も典型的な利用シーンとして想定されます。
具体的には、過去の放送ライブラリを活用したい放送局、過去の出版物を電子書籍化したい出版社、歴史的資料をデジタル展示したい美術館・博物館、そして一般ユーザーの投稿(UGC)の権利処理に課題を抱えるプラットフォーム事業者などが、本制度の主要な利用者となると考えられます。
裁定利用の法的リスク:権利者が現れた場合の対応
本制度を利用する企業が理解すべき最大の法的リスクは、この制度が利用者に永続的かつ絶対的な権利を与えるものではない、という点です。
裁定を受けて著作物を利用している期間中、あるいは利用後に、本来の著作権者から連絡が来る可能性があります。その場合、利用者はその後の利用継続について、権利者と直接交渉し、新たな許諾契約を結ぶ必要があります。
権利者は、文化庁に対し、裁定の取り消しを申し出ることができます。取り消しが認められた場合、利用者は(たとえ事業の途中であっても)当該著作物の利用を停止しなければならない可能性があります。また、権利者は、供託された補償金を受け取るか、あるいは補償金とは別に、過去の利用料を遡って請求することも法的に可能です。
このことから言えるのは、本制度の利用は「恒久的な権利確保」の手段ではなく、「時限的なリスクテイク」を可能にする手段として位置づけるべきだということです。利用者側の企業は、事業計画において、あらかじめ以下の3つのコストを「リスク・バジェット」として組み込んでおく経営判断が求められます。
- 裁定申請時に供託する「補償金」
- 権利者が現れた場合に、追加で支払う可能性のある「ライセンス料」
- 利用停止を余儀なくされた場合の「代替コンテンツ調達費用」や「事業計画変更コスト」
企業が取るべき実務対応:【権利者側】のリスクと対策

本制度の影響は、コンテンツを利用する側だけに留まりません。むしろ、自社で多くの知的財産を保有する「権利者側」の企業にとって、新たな管理体制の構築を迫るものとなります。権利者側が直面するリスクと、その具体的な予防策を解説します。
「未管理」とみなされる新たなリスク
本制度は、利用者側だけでなく、コンテンツを保有する権利者側の企業(出版社、新聞社、放送局、ゲーム会社、制作プロダクション、その他メーカー等)にとっても、極めて重大な影響を及ぼします。
従来、著作権法務において、権利者が利用許諾の問い合わせに「沈黙(返信しないこと)」することは、事実上の「拒絶(No)」を意味し、利用希望者はそれ以上進むことができませんでした。
しかし、新制度の施行により、この「沈黙」の法的な地位が根本から変わります。今後、権利者の「沈黙」は「拒絶」ではなく、「未管理(Unmanaged)」状態にあることの積極的な証拠として扱われかねません。その結果、権利者が認識しないうちに、自社の重要な知的財産が(補償金付きとはいえ)第三者によって時限的に利用されてしまう可能性が生じます。権利管理の「不作為」が、意図しないライセンスの発生に直結するリスクを内包することになったと言えます。
権利者側の具体的な予防策
権利者側の企業が取るべき対策は、自社が保有する著作物を、新制度の対象である「未管理公表著作物等」の定義に該当させないことです。そのための予防策は、大きく分けて2つあります。
予防策1(積極的防衛):利用許諾の意思を明示する
新制度の要件は「利用の可否に係る意思が公表されていない」ことです。したがって、最も簡単かつ強力な予防策は、自社の公式ウェブサイト、サービス利用規約、あるいは各コンテンツの公表ページにおいて、著作物の利用に関する意思(ポリシー)を明確に記載することです。
例えば、「当サイトのコンテンツの無断転載・複製を固く禁じます」「非営利目的に限り、当社の許諾なく利用可能です」「ライセンスに関するお問い合わせは、こちらのフォームからお願いします」といった意思表示を公にしておくだけで、その著作物は「意思が公表されている」ことになり、新制度の対象から外れます。
予防策2(受動的防衛):14日以内の応答体制構築
文化庁が公表したQ&Aによれば、利用希望者が「意思確認の措置」として権利者に問い合わせの連絡をした場合、権利者がその連絡から14日以内に「検討するから待ってほしい」といった何らかの応答(Reply)をするだけで、裁定手続はストップするとされています。14日以内に利用可否の「判断(Decision)」まで行う必要はなく、単なる「応答」で足りるという点は、権利者側の負担を軽減するために設けられた措置です。
この「14日ルール」は、権利者側企業にとって、新たなコンプライアンス上のベンチマークとなります。企業は、自社の著作権に関する問い合わせ窓口(例えば、ウェブサイト上のフォームや代表メールアドレス)が、最低でも14日間放置されることのないよう、社内の体制を早急に整備する必要があります。これまでEメールの確認を怠っていた、あるいはスパムフィルタによって重要な連絡が失われていた、といった事態が、自社の知的財産の意図しない利用に直結するリスクとなったからです。
まとめ:未管理著作物裁定制度については弁護士に相談を
本記事で詳述した通り、令和8年(2026年)4月1日から施行される「未管理著作物裁定制度」は、著作権法第67条の3に新たに追加される、コンテンツ利用のあり方を大きく変革する可能性を秘めた制度です。
この制度は、長らくデジタルアーカイブやDX推進の障壁となってきた「眠れる著作物」の活用に道を開くというポジティブな側面を持つ一方で、利用者側・権利者側双方の企業実務に、新たなコンプライアンス対応を強く求めるものでもあります。
コンテンツを利用したい企業(放送局、出版社、プラットフォーム事業者、広告代理店、メーカー等)にとって、この新しい裁定制度は、これまで権利処理がネックとなって諦めていた企画を実現するための、強力な法的ツールとなり得ます。過去の映像資料を用いたドキュメンタリー制作、古い学術文献のデジタルライブラリ化、あるいは他社の過去の製品デザインを参照した新商品の開発など、その可能性は多岐にわたります。
一方、コンテンツを保有する権利者側の企業(出版社、制作会社、IT企業、あるいは個人のクリエイターをマネジメントする事務所)にとっては、自社の知的財産が「利用意思不明」と判断され、意図しない形で利用されるリスクが新たに生じます。このリスクを回避するためには、自社の権利管理体制を根本から見直し、保有する各著作物に関する利用許諾の意思を対外的に明確化するという、戦略的な予防法務措置が求められます。
著作権法の改正への対応は、単なる法務部門の一タスクではなく、企業のコンテンツ戦略、ひいては競争力そのものに影響を与える経営課題です。本制度の活用や、本制度によるリスクへの対応に関しては、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、著作権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務