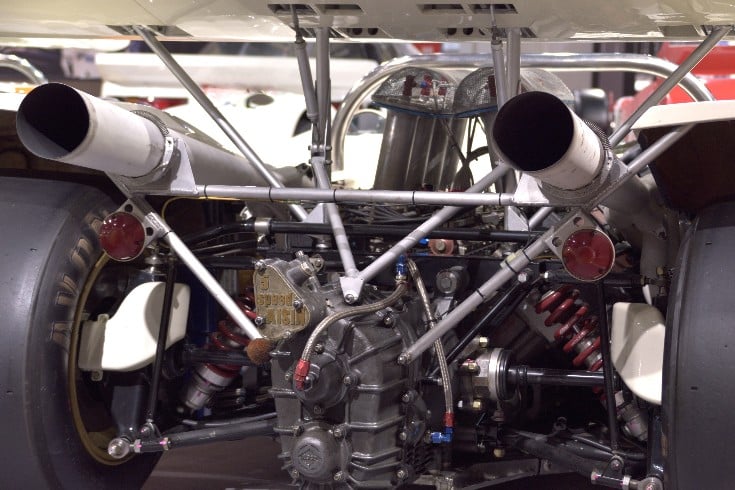„Āü„Ā£„ĀüśēįŚćĀcm„Āģ‚Äú„ÉÜ„Éľ„Éó‚ÄĚ„ĀĆśčõ„ĀĄ„Āü5šłá„ɶ„Éľ„É≠„ĀģÁĹįťáĎ‚ĒÄ‚ĒÄF1„Āę„ĀŅ„āčŚģČŚÖ®śČ蝆܄Ā®Ť¶ŹŚČáťĀčÁĒ®„ĀģŚģüťöõ

„āĻ„āŅ„Éľ„Éą3ŚąÜŚČć‚ÄĒ‚ÄĒ„Äā
F1„Āß„ĀĮ„Āď„ĀģÁü≠„ĀĄśôāťĖď„Āę„ÄĀ„ɨ„Éľ„āĻ„Āęśźļ„āŹ„āč10ŚźćšĽ•šłä„Āģ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĆšłÄśĖČ„ĀęťÄČ鼄Āó„ÄĀ„ā≤„Éľ„Éą„ĀĆťĖČ„Āė„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„āĆ„ĀĮŚģČŚÖ®„Āę„ɨ„Éľ„āĻ„āíŚü∑„ā䍰ƄĀÜ„Āü„āĀ„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™śČ蝆܄Āß„Āô„Äā
„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĘÉÁēĆ„āí„āŹ„Āö„Āč„ĀęŤ∂ä„Āą„ĀüšłÄś≠©„ĀĆ„ÄĀŤ≠įŤęĖ„āíŚĎľ„Ā∂„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„É©„ā§„Éź„Éę„Āģ„ɨ„Éľ„ā∑„É≥„āį„ÉĀ„Éľ„Ɇ„Āģ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĆ„ÄĀ„ā≥„Éľ„āĻŤĄá„Āꍮ≠„ĀĎ„āČ„āĆ„ĀüŚ£ĀÔľą„ÉĒ„ÉÉ„Éą„ā¶„ā©„Éľ„ÉęԾȄĀęŤ≤ľ„āČ„āĆ„Āü„ÄĆÁõģŚćį„ÉÜ„Éľ„Éó„Äć„āíŚČ•„ĀĆ„ĀĚ„ĀÜ„Ā®„Āó„Āü„Āģ„Āß„Āô„Äā„ĀĚ„ĀģÁĶźśěú„ÄĀťá挧߄Ā™„Éö„Éä„Éę„ÉÜ„ā£„ĀĆŤ™≤„Āõ„āČ„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„Āģť°ć„ÄĀ5šłá„ɶ„Éľ„É≠Ôľąśó•śú¨ŚÜÜ„ĀßÁīĄ900šłáŚÜÜԾȄÄā„Āď„ĀģšłÄšĽ∂„ĀĮ„ÄĀśĶ∑Ś§Ė„É°„Éá„ā£„āĘ„Āß„ÄĆ„ÉÜ„Éľ„Éó„ā≤„Éľ„ÉąÔľąTape-gateԾȚļ蚼∂„Äć„Ā®ŚĎľ„Āį„āĆ„ÄĀF1„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚģČŚÖ®śČ蝆܄Ā®„Éę„Éľ„ÉęťĀčÁĒ®„Āģ„Āā„āäśĖĻ„āíśĒĻ„āĀ„Ā¶ŚēŹ„ĀĄ„Āč„ĀĎ„āčŚáļśĚ•šļč„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āü„Ā£„ĀüśēįŚćĀcm„Āģ„ÉÜ„Éľ„Éó„ĀĆ„ÄĀ„Ā™„ĀúŚ§ß„Āć„Ā™ÁĹįťáĎ„Āł„Ā®„Ā§„Ā™„ĀĆ„Ā£„Ā¶„Āó„Āĺ„Ā£„Āü„Āģ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Āč„ÄāÁü•„āČ„āĆ„ĀĖ„āčF1„Éę„Éľ„Éę„āíŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„ɨ„ÉÉ„ÉČ„ÉĖ„Éę„Āģ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĆ„ÄĆÁõģŚćį„Äć„āíŚČ•„ĀĆ„ĀĚ„ĀÜ„Ā®‚Ķ

„Āď„Ā®„ĀģÁôļÁęĮ„ĀĮ„ÄĀ2025ŚĻī„āĘ„É°„É™„āęGP„ĀģśĪļŚčĚÁõīŚČć„Āģ„Āď„Ā®„Āß„Āó„Āü„Äā
„ÉÜ„ā≠„āĶ„āĻ„ÉĽ„ā™„Éľ„āĻ„ÉÜ„ā£„É≥„ĀģCircuit of the AmericasÔľąCOTAԾȄĀß„ĀĮ„ÄĀ„Éē„ā©„Éľ„É°„Éľ„ā∑„Éß„É≥„É©„ÉÉ„Éó„āíÁõģŚČć„Āę„Āó„Ā¶Á∑䌾Ķ„ĀĆťęė„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āô„Āß„Āę‚Äú3ŚąÜŚČć„ā∑„āį„Éä„Éę‚ÄĚ„ĀĆŚáļ„Āē„āĆ„ÄĀŚźĄ„ÉĀ„Éľ„Ɇ„Āģ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĮ„Éě„ā∑„É≥„ĀģśúÄÁĶā„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ„āíÁĶā„Āą„ÄĀťÄČ鼄āíŚßč„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ĀĚ„āď„Ā™„Ā™„Āč„ÄĀ„É©„ā§„Éź„Éę„ÉĀ„Éľ„Ɇ„Āß„Āā„āč„ɨ„ÉÉ„ÉČ„ÉĖ„Éę„Āģ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„Āģ„Ā≤„Ā®„āä„ĀĆ„ÄĀ2Áē™„āį„É™„ÉÉ„ÉČšĽėŤŅĎ„ĀęśąĽ„Ā£„Ā¶„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Äā
ŚĹľ„ĀģŤ¶ĖÁ∑ö„ĀģŚÖą„Āę„ĀĮ„ÄĀ„Éě„āĮ„É©„Éľ„ɨ„É≥„Āģ„É©„É≥„ÉČ„ÉĽ„Éé„É™„āĻťĀłśČč„Āģ„Éě„ā∑„É≥„ĀĆ„Äā„ĀĚ„Āģ„āį„É™„ÉÉ„ÉČšĹćÁĹģ„Āģ„ÉĒ„ÉÉ„Éą„ā¶„ā©„Éľ„ÉęŚĀī„Āę„ĀĮ„ÄĀŚįŹ„Āē„Ā™ÁõģŚćį„ÉÜ„Éľ„Éó„ĀĆŤ≤ľ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ÄāF1„ɨ„Éľ„āĶ„Éľ„ĀģŤ¶ĖÁēĆ„ĀĮťĚ쌳ł„ĀęÁč≠„ĀŹ„ÄĀ„Āó„Āį„Āó„Āį„ÉÜ„Éľ„Éó„āíÁõģŚćį„Ā®„Āó„Ā¶šĹŅ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„É©„ā§„Éź„Éę„Āģ„ɨ„ÉÉ„ÉČ„ÉĖ„ÉęŚĀī„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āí„ÄĆšłćťĀ©Śąá„Ā™Śćį„Äć„Ā®Ť¶č„Ā™„Āó„ÄĀŚČ•„ĀĆ„ĀĚ„ĀÜ„Ā®„Āó„Āü„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ°ĆÁāļ„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„Āô„Āß„Āę„Éē„ā©„Éľ„É°„Éľ„ā∑„Éß„É≥„É©„ÉÉ„ÉóÔľą„āĻ„āŅ„Éľ„ÉąŚČć„ĀģśļĖŚāôŤĶįŤ°ĆԾȄĀꌟτĀĎ„Ā¶„ÄĀ„ā≤„Éľ„ÉąťĖČťéĖšĹúś•≠„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀüśôāťĖĮ„Āß„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„āí„ÄĆ„ā≤„Éľ„Éą„ā¶„āß„ÉęÔľągate wellԾȄā®„É™„āĘ„Äć„ĀłŚÜćšĺĶŚÖ•„Āó„ÄĀ„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęÔľą„ā≥„Éľ„āĻšŅāŚď°ÔľČ„ĀģŚą∂ś≠Ę„ĀęŚĺď„āŹ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀFIA„ĀĮ„Āď„āĆ„āí„ÄĆŚģČŚÖ®„āíśźć„Ā™„ĀÜŤ°ĆÁāļ„Äć„Ā®Śą§śĖ≠„Āó„ÄĀÁĹįťáĎ5šłá„ɶ„Éľ„É≠Ôľą„ĀÜ„Ā°2.5šłá„ɶ„Éľ„É≠„ĀĮŚü∑Ť°ĆÁĆ∂šļąÔľČ„āíÁßĎ„Āô„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā
šĹē„ĀĆŤĶ∑„Āć„Āü„Āģ„ĀčÔľöšļčŚģüťĖĘšŅā„ĀģśēīÁźÜ
„Āď„Āď„ĀßšĹē„ĀĆŤĶ∑„Āć„Āü„Āģ„Āč„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀšļčŚģüťĖĘšŅā„āíśēīÁźÜ„Āó„Ā¶„ĀŅ„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā
Ť°ĆÁāļ„ĀģŚ†īśČÄ„Ā®„āŅ„ā§„Éü„É≥„āį
COTAÔľąCircuit of the AmericasԾȄĀģGate 1šĽėŤŅĎÔľą2Áē™„āį„É™„ÉÉ„ÉČ„ĀģŤŅĎŚāćԾȄÄā„Éē„ā©„Éľ„É°„Éľ„ā∑„Éß„É≥„É©„ÉÉ„Éó„ĀĆťĖčŚßč„Āē„āĆ„ÄĀ„ÉĒ„ÉÉ„ÉąŚĀī„ā≤„Éľ„Éą„ĀģťĖČťéĖšĹúś•≠„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčśúÄšł≠„Āę„ÄĀ„ɨ„ÉÉ„ÉČ„ÉĖ„Éę„Āģ„ÉĀ„Éľ„Ɇ„É°„É≥„Éź„Éľ„ĀĆ„ā≤„Éľ„Éą„ā¶„āß„Éę„ĀłŚÜćšĺĶŚÖ•„Äā„Éě„Éľ„ā∑„É£„Éę„ĀĮŚą∂ś≠Ę„ā퍩¶„ĀŅ„Āü„ĀĆ„ÄĀŚĹ≤„É°„É≥„Éź„Éľ„ĀĮŚŹćŚŅú„Āó„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Ā®Ť™ćŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ÄĆ„ÉÜ„Éľ„Éó„Äć„ĀģśČĪ„ĀĄ
„Éé„É™„āĻ„Āģ„āį„É™„ÉÉ„ÉČšĹćÁĹģŚźą„āŹ„ĀõÁĒ®„ĀģŚįŹ„Āē„Ā™„Éě„Éľ„āę„ÉľÔľą„ÉÜ„Éľ„ÉóԾȄĀĆ„ÉĒ„ÉÉ„Éą„ā¶„ā©„Éľ„ÉęŚĀī„ĀęŤ≤ľ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āíťô§ŚéĽ„Āó„āą„ĀÜ„Ā®„Āó„Āü„Ā®„ĀģŚ†ĪťĀď„ĀĆÁõłś¨°„Āé„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀÁĹįťáĎ„ĀĮ„ÉÜ„Éľ„Éó„ĀĚ„Āģ„āā„Āģ„Āł„ĀģŚĻ≤śłČ„āíÁõīśé•„ĀģÁźÜÁĒĪ„Ā®„ĀĮ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āõ„āďÔľą„ĀĚ„āā„ĀĚ„āāśėéśĖá„ĀßÁ¶Āś≠Ę„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄÔľČ„ÄāŚēŹť°Ć„ĀĮŚģČŚÖ®śČ蝆܄Āꌏć„Āó„ĀüŚÜćšĺĶŚÖ•„Āß„Āô„Äā
FIA„ĀĆšłč„Āó„ĀüŚá¶ŚąÜ
5šłá„ɶ„Éľ„É≠„ĀģÁĹįťáĎÔľąŚćäť°ć„ĀĮśĚ°šĽ∂šĽėŚĀúś≠ĘԾȄÄāťĀēŚŹćśĚ°ť†Ö„ĀĮŚõĹťöõ„āĻ„ÉĚ„Éľ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„ā≥„Éľ„ÉČÔľąISCÔľČ12.2.1(h)ÔľąŚģČŚÖ®„āíśźć„Ā™„ĀÜŤ°ĆÁāļÔľČ/ (i)ÔľąŚÖ¨ŚľŹśĆáÁ§ļ„Āł„ĀģšłćŚĺďԾȄÄā
„Ā©„ĀģŤ¶ŹŚČá„ĀęťĀēŚŹć„Āó„Āü„Āģ„ĀčÔľöśĚ°śĖá„Āß„ĀŅ„āč„ÄĆťÄÄŚéĽÁĺ©Śčô„Äć„Ā®„ÄĆśĆáÁ§ļťĀĶŚģą„Äć
F1„āĻ„ÉĚ„Éľ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„ÉĽ„ɨ„āģ„É•„ɨ„Éľ„ā∑„Éß„É≥Ôľą2025ÔľČ
- 3ŚąÜŚČć„ā∑„āį„Éä„ÉęÔľöŚźĄ„ÉĀ„Éľ„Ɇ„Āģ„āį„É™„ÉÉ„ÉČšłä„ĀģšļļŚď°„ĀĮśúÄŚ§ß16Śźć„Āꌹ∂ťôź„Äā
- 1ŚąÜŚČć„ā∑„āį„Éä„Éę„Äú15ÁßíÔľö„ā®„É≥„āł„É≥ŚßčŚčēŚĺĆ„ÄĀŚÖ®„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĮ15Áßí„ā∑„āį„Éä„Éę„Āĺ„Āß„Āę„āį„É™„ÉÉ„ÉČÔľą„Āä„āą„Ā≥Ť©≤ŚĹďśôā„Āģ„ÉĒ„ÉÉ„Éą„ɨ„Éľ„É≥„ÉĽ„Éē„ā°„āĻ„Éą„ɨ„Éľ„É≥ԾȄĀč„āČŚģĆŚÖ®ťÄČ鼄Äā
‚ÄĒ „Āď„āĆ„āČ„ĀĮÁ¨¨43.6„ÄĀ43.7śĚ°ÔľąśĪļŚčĚ„Āģ„āĻ„āŅ„Éľ„ÉąśČ蝆ÜÔľČÁ≠Č„Āęśė鍮ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
FIAŚõĹťöõ„āĻ„ÉĚ„Éľ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„ā≥„Éľ„ÉČÔľąISCÔľČ
- 12.2.1(h)/(i)ÔľöŚģČŚÖ®„āíśźć„Ā™„ĀÜŤ°ĆÁāļ„āĄťĖĘťÄ£„ā™„Éē„ā£„ā∑„É£„Éę„ĀģśĆáÁ§ļšłćŚĪ•Ť°Ć„āíťĀēŚŹć„Ā®„Āó„Ā¶ŚąóśĆô„Äā„ā≤„Éľ„ÉąťĖČťéĖšĹúś•≠„ĀģŚ¶®„Āí„ĀĮ„ÄĆunsafeÔľąŚćĪťôļԾȄÄć„Ā®Ť©ēšĺ°„Āē„āĆŚĺó„Āĺ„Āô„ÄāšĽäŚõě„ĀģŚÖ¨ŚľŹťĀēŚŹćŤ™ćŚģö„Āģś†Ļśč†„Āß„Āô„Äā
„ÄĆ„ÉÜ„Éľ„Éó„Äć„ĀĮťĀēŚŹć„Ā™„Āģ„ĀčÔľö„āį„ɨ„Éľ„ĀģÁ∑öŚľē„Āć
šĽäŚõě„ÄĀÁõģŚćį„ÉÜ„Éľ„Éó„ĀģŤ®≠ÁĹģŤá™šĹď„ĀĮŤ¶ŹŚČá„ĀęśėéśĖáÁ¶Āś≠Ę„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āü„āĀ„ÄĀŚć≥Śļß„ĀęťĀēŚŹć„Ā®„ĀĮ„Āē„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Āß„Āó„Āü„ÄāŚźĆśôā„Āę„ÄĀ„É©„ā§„Éź„Éę„ĀĆ„ĀĚ„āĆ„āíŚČ•„ĀĆ„Āô„Āď„Ā®„āíśėéśĖá„ĀßÁ¶Ā„Āė„ā荶ŹŚģö„āāŚ≠ėŚú®„Āó„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĆŚźĄ„É°„Éá„ā£„āĘ„ĀģŚÖĪťÄö„Āó„ĀüśēīÁźÜ„Āß„Āô„Äā
„āā„Ā£„Ā®„āā„ÄĀ„Āď„Āģ„āĪ„Éľ„āĻ„Āß„ĀĮŚČ•„ĀĆ„Āô„ÄĆŤ°ĆÁāļ„Äć„Āģśôā„Ā®Ś†īśČÄ„ĀĆÁ¶Ā„Āė„āČ„āĆ„āčÔľąÔľĚťÄÄŚéĽÁĺ©Śčô„ĀģŚĺĆ„ĀĮšłćŚŹĮԾȄĀü„āĀ„ÄĀŚģČŚÖ®śČ蝆܄Āꌏć„Āô„āčŚÜćšĺĶŚÖ•„ĀƌᶌąÜŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„āŹ„ĀĎ„Āß„Āô„Äā
ś≥ēŚčô„ÉĽťĀčÁĒ®„ĀģŤęĖÁāĻÔľöšĽäŚĺĆ„ÄĀ„Ā©„Āď„āíśėéÁĘļŚĆĖ„Āô„ĀĻ„Āć„Āč

ŚģČŚÖ®ŚĄ™ŚÖą„ĀģśČ蝆܄āí„āą„ā䌏ĮŤ¶ĖŚĆĖ
- ¬†„ā≤„Éľ„Éą„ā¶„āß„Éę„Ā™„Ā©ÁęčŚÖ•Áģ°ÁźÜ„ā®„É™„āĘ„ĀģŚģöÁĺ©„Ā®ťĖČťéĖ„āŅ„ā§„Éü„É≥„āį„āí„ÄĀ„ÉĀ„Éľ„ɆŚźĎ„ĀĎŤ≥áśĖô„āĄ„ā§„Éô„É≥„Éą„Éé„Éľ„Éą„Āߌõ≥Á§ļ„Āó„ÄĀÁĻį„āäŤŅĒ„ĀóŚĎ®Áü•„Āô„āč„Äā
Ś§ĖťÉ®„ÄĆŚüļśļĖÁČ©„ÄĆ„ĀģśČĪ„ĀĄ
- „ā¶„ā©„Éľ„Éęšłä„Āģ„Éě„Éľ„āę„ÉľÔľą„ÉÜ„Éľ„ÉóÁ≠ČԾȄāí„ÄĆšĹŅÁĒ®ŚŹĮ„ÉĽšłćŚŹĮ„Äć„ÄĆťô§ŚéĽŚŹĮ„ÉĽšłćŚŹĮ„Äć„ÄĆťô§ŚéĽŚŹĮŤÉĹ„Ā™śúüťôźÔľąťÄČ鼜ôāŚąĽ„Āĺ„ĀßԾȄÄć„Āģ„ĀĄ„Āö„āĆ„Āč„ĀßśėéśĖáŚĆĖ„Äā
- ¬†šĽĖÁ§ĺÁČ©„Āł„Āģśé•Ťß¶ÔľąŚĻ≤śłČԾȄĀęťĖĘ„Āô„ā蚳蹨śĚ°ť†ÖÔľąšĺčÔľö„ÄĆšĽĖ„ÉĀ„Éľ„Ɇ„ĀģŤ®≠ÁĹģÁČ©„Āł„Āģśé•Ťß¶Á¶Āś≠Ę„ÄĆԾȄāíŚģČŚÖ®śĚ°ť†Ö„Ā®Áīź„Ā•„ĀĎ„Ā¶ŤŅĹŤ®ė„Äā
‚ÄĽŚ†ĪťĀď„Āß„ĀĮ„ÉŹ„Éü„Éę„Éą„É≥„āāŤĽäšĹďŚĀī„Āę„ÉÜ„Éľ„Éó„āíÁĒ®„ĀĄ„āčšĺč„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āē„āĆ„ÄĀ„Éě„Éľ„ā≠„É≥„āįŤá™šĹď„ĀĮŚļÉ„ĀŹŤ°Ć„āŹ„āĆ„āčŚģüŚčô„Āß„Āô„ÄāŤ°ĆÁāļ„Āģ„ÄĆŚ†īśČÄ„Ā®śôāŚąĽ„Äć„ĀߌģČŚÖ®„Ā®ŚÖ¨ś≠£„āíśčÖšŅĚ„Āô„āč„Āģ„ĀĆÁŹĺŚģüÁöĄ„Āß„Āô„Äā
3. Śą∂Ť£Ā„ĀģŚĚ፰°
- ŚćĪťôļśÄß„ĀģÁ®čŚļ¶ÔľąťĖČťéĖšĹúś•≠„Āł„ĀģŚ¶®Śģ≥„ĀģśúČÁĄ°„ÄĀ„Éě„Éľ„ā∑„É£„Éę„ĀģŚą∂ś≠Ę„āíÁĄ°Ť¶Ė„Āó„ĀüŚļ¶Śźą„ĀĄÔľČ„ĀßÁĹįťáĎŚĻÖ„āí„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀꍟńĀ®„ĀóŤĺľ„āÄÔľąšĽäŚõě„Āģ„ÄĆŚćäť°ćŚü∑Ť°ĆÁĆ∂šļą„Äć„ĀĮ„ÄĀŚÜćÁôļťė≤ś≠Ę„āíšŅÉ„ĀôśäĎś≠ĘŤ®≠Ť®ą„Ā®„Āó„Ā¶Ś¶•ŚĹďԾȄÄā
ÁĶźŤęĖÔľö„āį„ɨ„Éľ„Ā™šļčśüĄ„āíśėéśĖáŚĆĖ„Āó„Ā¶Ť¶ŹŚą∂„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā
„ÄĆ„ÉÜ„Éľ„Éó„ā≤„Éľ„Éą„Äćšļ蚼∂„Āģśú¨Ť≥™„ĀĮ„ÄĆśČ蝆܄Äć„Ā®„ĀĄ„Āą„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„āį„É™„ÉÉ„ÉČťÄČ鼄ĀģŚé≥ś†ľťĀčÁĒ®„Ā®„ā™„Éē„ā£„ā∑„É£„ÉęśĆáÁ§ļ„ĀģŚĄ™Ť∂ä„ĀĮF1„ĀģŚģČŚÖ®śĖáŚĆĖ„Āģšł≠ś†ł„Āß„Āô„ÄāšĽäŚĺĆ„ĀĮ„ÄĀŚ§ĖťÉ®„Éě„Éľ„āę„Éľ„ĀģśČĪ„ĀĄ„ā팟ę„āÄťĀčÁĒ®„ĀģśėéÁĘļŚĆĖ„Ā®śēôŤā≤„ĀĆ„ÄĀŚģČŚÖ®„Ā®ŚÖ¨ś≠£„Āģšł°Áęč„ĀęŤ≥á„Āô„āč„ĀĮ„Āö„Āß„Āô„Äā
„Āā„ĀģśČč„Āď„ĀģśČč„ĀģŚ∑•Ś§ę„ĀĮF1„Āģť≠ÖŚäõ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀťÄČ鼌ĺĆ„ĀęśąĽ„āČ„Ā™„ĀĄ„ÉĽśĆáÁ§ļ„ĀęŚĺď„ĀÜ„Ā®„ĀĄ„ĀÜśúÄšĹéťôź„Āģ„É©„ā§„É≥„ĀĮ„ÄĀ„Ā©„āď„Ā™ťßÜ„ĀĎŚľē„Āć„āą„āä„āāŚĄ™ŚÖą„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
ŚĹďšļčŚčôśČÄ„Āę„āą„āčŚĮĺÁ≠Ė„Āģ„ĀĒś°ąŚÜÖ
„ÉĘ„Éé„É™„āĻś≥ēŚĺčšļčŚčôśČÄ„ĀĮ„ÄĀIT„ÄĀÁČĻ„Āę„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„Éą„Ā®ś≥ēŚĺč„Āģšł°ťĚĘ„Āęťęė„ĀĄŚįāťĖÄśÄß„āíśúČ„Āô„āčś≥ēŚĺčšļčŚčôśČÄ„Āß„Āô„ÄāŚĹďšļčŚčôśČÄ„Āß„ĀĮ„ÄĀśĚĪŤ®ľ„Éó„É©„ā§„ɆšłäŚ†īšľĀś•≠„Āč„āČ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„ÉľšľĀś•≠„Āĺ„Āß„ÄĀšļļšļč„ÉĽŚäīŚčôÁģ°ÁźÜ„Āę„Āä„ĀĎ„āč„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„āĄ„ÄĀ„Āē„Āĺ„ĀĖ„Āĺ„Ā™ś°ąšĽ∂„ĀęŚĮĺ„Āô„ā茕ĎÁīĄśõł„ĀģšĹúśąź„ÉĽ„ɨ„Éď„É•„ÉľÁ≠Č„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„Āä„āä„Āĺ„Āô„ÄāŤ©≥„Āó„ĀŹ„ĀĮ„ÄĀšłčŤ®ėŤ®ėšļč„āí„ĀĒŚŹāÁÖß„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô
„āŅ„āį: Formula1