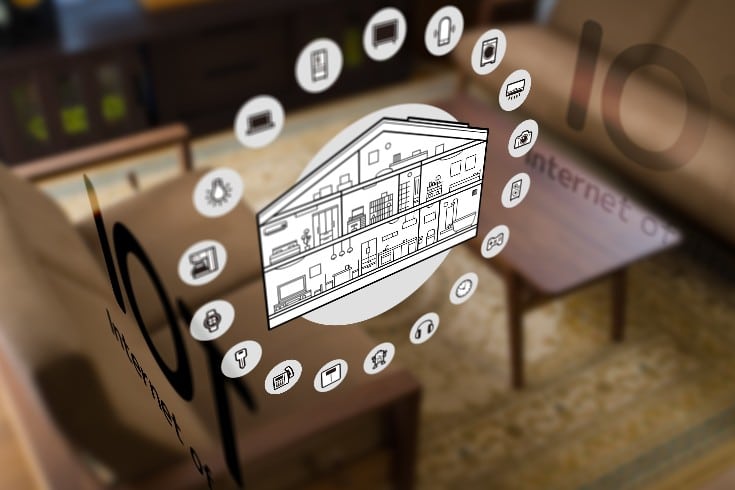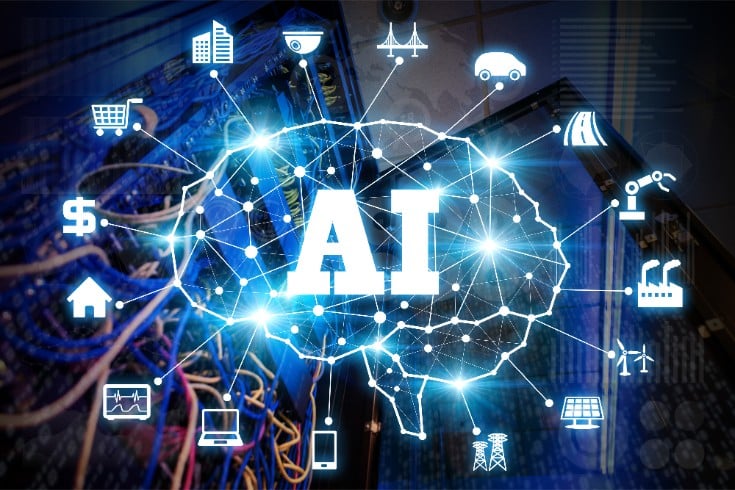リスキリング助成金のキックバックによる「実質無料」の不正受給と法的リスク
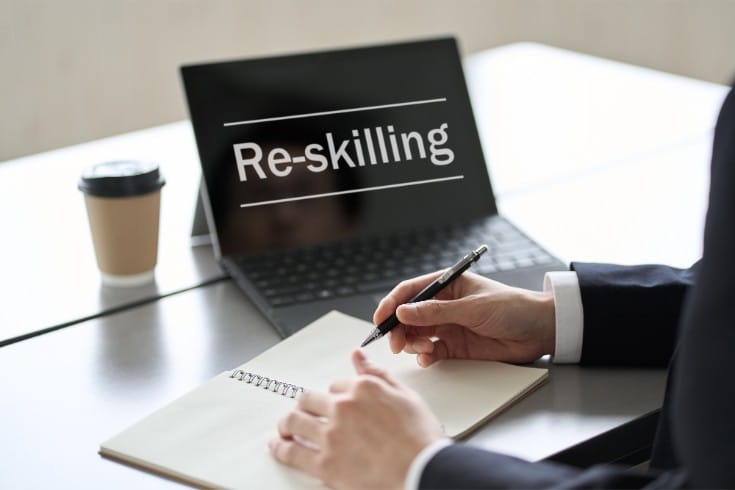
近年、企業の従業員育成や個人のスキルアップを支援する「リスキリング助成金」が注目を集めています。しかし、その一方で、この助成金を悪用した不正受給が横行しています。特に問題となっているのが、訓練機関と企業の間で交わされるキックバックによる不正受給です。
本記事では、このリスキリング助成金における、キックバックによる「実質無料」スキームに焦点を当て、それがなぜ不正受給とみなされるのか、発覚した場合に企業が直面する重大なリスク、そして、既にこうした「不正受給」を行ってしまった場合にどうしたらよいのかという点に関して、弁護士の視点から詳細に解説します。
この記事の目次
リスキリング助成金の意義と不正受給問題の背景
リスキリング助成金(人材開発支援助成金)は、企業が従業員のスキルアップや新たな事業展開に必要な人材育成を行う際に、その費用の一部を国が支援する重要な公的支援策です。この制度は、企業の競争力強化と従業員のキャリア形成を促進することを目的としており、雇用保険料を財源とする返済不要の資金として、企業にとって大きなメリットがあります。
しかし近年、この助成金制度を巡る不正受給が深刻な社会問題となっています。特に、訓練機関を介したキックバック(還流)による「実質無料」を謳う不正受給が会計検査院によって指摘されており、2019年から2023年度にかけて1億円を超える不適切な受給が確認されるなど、その件数と金額は看過できないレベルに達しています。
リスキリング助成金におけるキックバックと不正受給

キックバックの定義と「実質無料」スキーム
リスキリング助成金におけるキックバックとは、事業主が訓練実施機関(研修会社)に研修費用を支払った後、その訓練実施機関またはその関連団体から、支払った費用の一部が事業主に対して金銭的に還流される行為を指します 。
この還流は、「コンサルティング料」「キャッシュバック」「広告宣伝レビュー代」「受講者の感想提出への謝礼」など、さまざまな名目で行われることが特徴です。また、ポイントやクーポン発行により、現金以外の方法で実質的な還流が行われるケースもあります。これにより、事業主は研修費用を、実質的に無料・自己負担ゼロに抑えることができます。これが、いわゆる実質無料スキームです。
キックバックによる「実質無料」が不正受給となる理由
人材開発支援助成金は、「事業主が一度自社で研修費用を全額支払い、その負担した経費の一部を国が助成する制度」という大原則に基づいています。キックバックによる実質無料スキームは、この「事業主の全額負担」という助成金の基本要件に違反するものであり、不正受給とみなされます。
前述のとおり、多くの場合には形式的に別の名目が用意される訳ですが、例えば、「コンサルティング料」であれば「実体としてコンサルティング業務が提供されたのか」といった点が問題になります。そして、実質的に訓練費用が還流され、事業主の自己負担が軽減されている場合は、不正行為と判断されます。当局は「形式」ではなく「実質」を重視して不正を判断しており、見かけ上の契約だけでなく、資金の流れ全体を精査することで、不正を摘発しています。
不正受給の責任は事業主のみに留まりません。不正行為を助言したり、積極的に関与したりした代理人(社会保険労務士)や訓練実施機関も、ペナルティの対象となります。一部の助成金コンサルタントやITベンダーが、「実質無料」などの不自然な導入スキームを企業に持ちかけ、不正を主導するケースも報告されています。
キックバックによる「実質無料」型の不正受給の実例
2024年10月に公表された会計検査院の検査結果では、32事業主(83件)が不正受給であると指摘されました。「従業員の教育訓練風景の撮影や感想文の提出などで高額の謝礼を受け取る“キックバック”により、企業が自己負担なしで訓練を受けられる仕組み」、すなわち、いわゆる実質無料スキームが用いられており、「教育訓練機関への費用の支払いと近接した時期に、教育訓練機関から受講した企業に対して入金があり、実質的に企業が全額負担していない」状況を確認したとされています。
不正受給が発覚した場合の重いペナルティと企業への影響
金銭的ペナルティ:全額返還、延滞金、違約金
不正受給が判明した場合、企業は以下の金銭的ペナルティを負うことになります。これらの合計額は、当初受給した助成金を大きく上回る可能性があり、企業にとって甚大な経済的打撃となります。
- 助成金の全額返還:不正に受給した助成金は、その全額を国に返還しなければなりません。
- 延滞金:返還額には、不正受給日の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。厚生労働省管轄の助成金では年3%の延滞金が課されますが 、一部の補助金では年10.95%と非常に高率な延滞金が適用される場合もあり、返還が遅れるほど負担は増大します。
- 違約金(加算金):返還額に加えて、不正受給した額の2割に相当する違約金(加算金)も請求されます。
行政処分:企業名・代表者名の公表と助成金受給停止
金銭的ペナルティに加え、不正受給が発覚した企業には、その企業イメージと将来の事業活動に甚大な影響を与える行政処分が科されます。
- 企業名・代表者名・訓練機関名の公表:不正受給が発覚した場合、事業主名、代表者名、そして不正に関与した訓練実施機関名が、厚生労働省や都道府県労働局のウェブサイトなどで公表されます 。自主申告ではない不正受給事案については、例外なく事業主名等が公表されると明記されています。
- 社会的信用の失墜:企業名の公表により、長期間にわたって不正受給の事実が知れ渡ることになります 。これにより、金融機関からの評価低下、資金調達の困難化、取引先からの信用喪失など、事業の根幹を揺るがす事態に発展する可能性があります。
- 助成金受給停止:不正受給決定日から5年間、全ての雇用関係助成金の受給が停止されます 。全額が返納されていない場合は、この期間が延長されます。
実際問題として特に大きいのが、最後の項目、雇用関係助成金の5年間にわたる受給停止ではないでしょうか。リスキリング助成金に限らず、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など、雇用関係の全ての助成金が対象なので、会社の規模にもよりますが、影響が大きいものと言えます。
刑事告発の可能性:詐欺罪の適用と罰則
特に悪質な不正受給は、金銭的・行政的ペナルティに加えて、刑事告発の対象となる可能性があります。
- 詐欺罪の適用:「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、詐欺罪として「5年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」に処せられるか、または併科される可能性があります 。これは、企業だけでなく、不正行為に関与した個人が刑事罰の対象となることを意味します。
- 不正に関与した代理人・訓練実施機関へのペナルティ:事業主だけでなく、不正行為を行うことを助言した社会保険労務士や代理人、あるいは不正に関与した訓練実施機関も、詐欺罪の共犯になる可能性があります。
不正受給に心当たりがある場合の緊急対処法

もしリスキリング助成金の不正受給に心当たりがある場合、あるいは既に労働局からの調査が入っている場合、その対応は時間との勝負です。
最も重要な対応:自主申告のメリット
不正受給に心当たりがある場合、最も推奨されるのは、労働局による調査が入る前に「自主申告」を行うことです 。自主申告は、事態を悪化させずに解決に導くための極めて重要な第一歩となります。
自主申告を行うことには、以下のようなメリットがあります。
- 公表回避の可能性:労働局が調査を行う前に、不正・不適正な受給の全ての事実を申告し、迅速に全額返還すれば、原則として事業主名の公表を回避できる可能性があります 。
- 刑事告発回避の可能性:自主的な返還や、当局への誠意ある対応は、詐欺罪による逮捕や刑事告発を回避できる可能性を高めます 。
- 延滞金・違約金の軽減:自主申告によって早期に返還手続きを進めることで、延滞金が膨らむのを防ぐことができます。
ただ、自主申告は、単に労働局に連絡するだけでなく、事実関係の正確な把握、適切な書類の準備、労働局との専門的なやり取りなど、複雑なプロセスを伴います。
弁護士への早期相談
前述のような複雑なプロセスがある自主申告の際には、弁護士への相談が有用です。
- 法的なリスク評価と最適な対応策の立案:弁護士は、現在の状況が法的にどのようなリスク(詐欺罪の成否、ペナルティの種類と程度、関連法規の適用)を抱えているものなのかを評価し、自主申告の要否、その後の労働局や捜査機関への最適な対応策、示談交渉の可能性などを検討することができます。
- 労働局・捜査機関への対応支援と交渉:労働局や警察・検察といった捜査機関からの問い合わせ、立ち入り調査、聞き取り調査に対して、弁護士が代理人として対応を支援し、交渉を行います。これにより、不適切な発言や対応による事態の悪化を防ぎながら、冷静かつ誠意ある対応を行うことができます。
- 自主返還手続きの代行・サポート:弁護士は、自己申告の文書作成や、本人の代わりに自主返還手続きの対応を行うことができます。
- 精神的負担の軽減:不安を抱えた状態で一人で対応することの精神的負担は計り知れません。弁護士が伴走することで、法的な問題だけでなく、心理的な安心感を得られます。
問題を放置すればするほど、ペナルティが重くなり、企業へのダメージが拡大するリスクがあるため、初動の対応が極めて重要となります。
不正受給を未然に防ぐためのコンプライアンス体制構築
不正受給は、故意によるものだけでなく、制度の複雑さや知識不足、あるいは企業内の管理体制の不備から発生するケースも少なくありません。これを未然に防ぎ、企業の信頼性を維持するためには、不正受給問題に関する知識が不可欠です。
- 助成金制度の要件と趣旨の正確な理解:助成金は「返済不要」な資金であるものの、「自由に使えるお金」ではないことを認識することが重要です。「事業主の全額負担」という原則を理解し、実質的に自己負担がない状態は不正とみなされることを社内で周知する必要があります。
- 「実質無料」などの甘言に対する警戒と専門家への相談:「実質無料」「自己負担ゼロ」「100%受給保証」といった甘い言葉で勧誘してくる業者には乗らないことが肝要です。これらの勧誘は、キックバックを伴う不正受給につながる可能性が高いものと言えます。信頼できる専門家(弁護士、社会保険労務士など)へ自ら相談し、助言を求めるべきです。
- 外部専門家(弁護士・社会保険労務士)との継続的な連携:助成金申請代行は社会保険労務士の独占業務です。信頼できる社会保険労務士に依頼することで、申請の正確性を高め、不正リスクを低減できます。また、弁護士とは、コンプライアンス体制の構築 、リスクアセスメント 、そして万が一の不祥事発生時の危機管理について、継続的に連携することが望ましいです。
まとめ:リスキリング助成金の不正受給は弁護士に相談を
リスキリング助成金における、キックバックを用いた実質無料スキームは、助成金の基本要件である「事業主の全額負担」に違反する行為であり、不正受給とみなされます。不正受給が発覚した場合、企業は助成金の全額返還、高額な違約金と延滞金、企業名・代表者名の公表、5年間の助成金受給停止、そして悪質な場合には刑事告発といった、重いペナルティに直面します。
これらのリスクを回避・軽減するためには、不正受給に心当たりがある場合、あるいはその疑いが生じた場合、速やかに弁護士に相談し、対応を検討することが重要です。 弁護士は、自主申告のサポートを通じて企業名の公表や刑事告発のリスクを低減し、労働局や捜査機関との交渉、返還手続きの代行などのサポートを行うことができます。
当事務所は、リスキリング助成金を含む各種助成金の不正受給問題に対し、法的リスクの評価から自主申告のサポート、労働局や捜査機関への対応までの支援体制を有しています。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT・ビジネスと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、ビジネスモデルや事業内容を深く理解した上で潜在的な法的リスクを洗い出し、リーガルサポートを行っております。補助金や助成金の不正受給に関連する業務に関しては、下記記事にて詳細を記載しております。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務