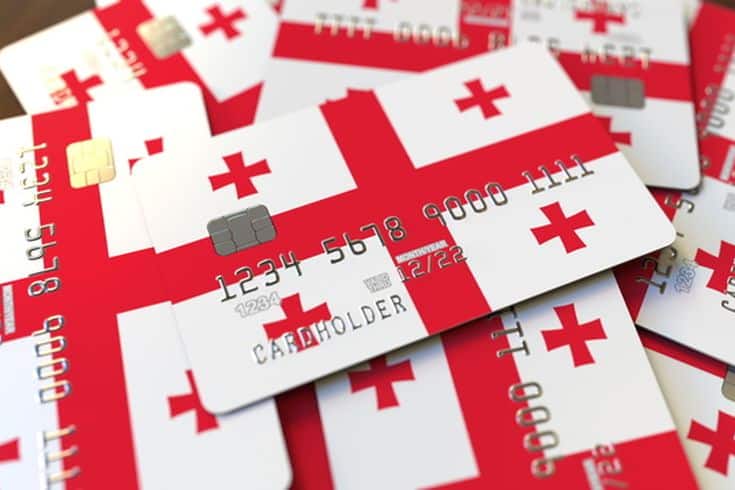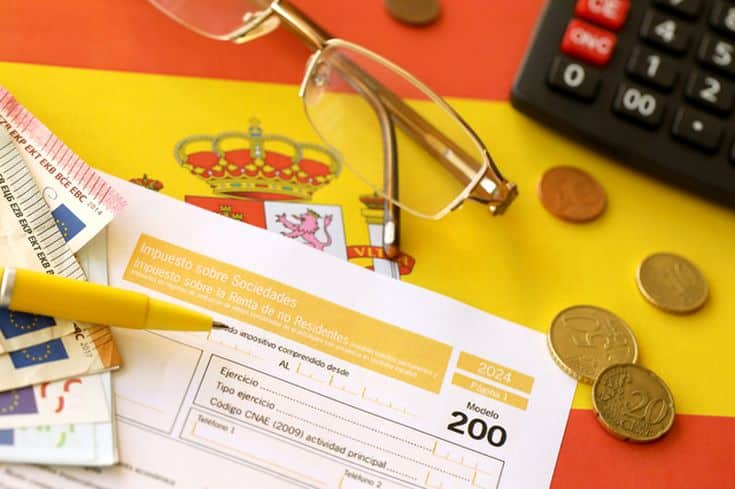гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒ®е®ҹеӢҷгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гҒӢгҒӨгҒҰгҖҢгӮ°гғ«гӮёгӮўгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒҜгҖҒгӮігғјгӮ«гӮөгӮ№ең°ж–№гҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҖҒ欧е·һгҒЁгӮўгӮёгӮўгҒ®зөҗзҜҖзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰең°ж”ҝеӯҰзҡ„гҒ«йҮҚиҰҒгҒӘдҪҚзҪ®гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢеӣҪгҒҜдё–з•ҢйҠҖиЎҢгҒ®гҖҢDoing BusinessгҖҚгғ©гғігӮӯгғігӮ°гҒ§дёҠдҪҚгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжүӢеҺҡгҒ„жҠ•иіҮ家дҝқиӯ·гҒЁз°Ўзҙ гҒӘиЎҢж”ҝжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иғҢжҷҜгҒ«гҖҒеӨ–еӣҪиіҮжң¬гҒ®иӘҳиҮҙгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«йҖІгӮҒгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®зөҢе–¶иҖ…гӮ„жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжіЁзӣ®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ«жёЎиҲӘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгғӘгғўгғјгғҲгҒ§дјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢзӮ№гӮ„гҖҒITдјҒжҘӯгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеј·еҠӣгҒӘзЁҺеҲ¶е„ӘйҒҮжҺӘзҪ®гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒ2021е№ҙгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹж–°гҖҢиө·жҘӯ家法гҖҚгҒ«гӮҲгӮӢEUжі•жә–жӢ гҒ®гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№еј·еҢ–гӮ„гҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®зЁҺеӢҷеҪ“еұҖгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢзөҢжёҲзҡ„е®ҹдҪ“пјҲSubstanceпјүгҖҚгҒ®еҺіж јгҒӘеҜ©жҹ»гҒӘгҒ©гҖҒйҖІеҮәгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜиЎЁйқўзҡ„гҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒжі•зҡ„гҒӘиҗҪгҒЁгҒ—з©ҙгӮ’ж…ҺйҮҚгҒ«жӨңиЁҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬зЁҝгҒ§гҒҜгҖҒжңҖж–°гҒ®жі•д»ӨгҒҠгӮҲгҒі2025е№ҙжҷӮзӮ№гҒ§гҒ®е®ҹеӢҷйҒӢз”ЁгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ§гҒ®дјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҖҒзЁҺеҲ¶гҖҒгҒҠгӮҲгҒіжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’дәӨгҒҲгҒӘгҒҢгӮүи©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒй…ҚеҪ“гӮ’иЎҢгҒҶгҒҫгҒ§жі•дәәзЁҺгҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгғ»гғўгғҮгғ«гҖҚгҒ®зЁҺеҲ¶гӮ„гҖҒITдјҒжҘӯгҒҢдә«еҸ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖҢгғҗгғјгғҒгғЈгғ«гӮҫгғјгғігҖҚгҒҠгӮҲгҒігҖҢеӣҪйҡӣдјҒжҘӯгӮ№гғҶгғјгӮҝгӮ№гҖҚгҒ®е…·дҪ“зҡ„иҰҒ件гҒЁгғӘгӮ№гӮҜгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гҒЁгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®з§ҹзЁҺжқЎзҙ„гҒ«еҹәгҒҘгҒҸиӘІзЁҺй–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©іиҝ°гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
2021е№ҙж”№жӯЈгӮёгғ§гғјгӮёгӮўдјҒжҘӯжі•гҒЁдјҡзӨҫеҪўж…ӢгҒ®йҒёжҠһ
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®дјҡзӨҫжі•еҲ¶гҒҜгҖҒй•·гӮүгҒҸ1994е№ҙгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢиө·жҘӯ家法пјҲLaw of Georgia on EntrepreneursпјүгҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸеҫӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒEUгҒЁгҒ®йҖЈеҗҲеҚ”е®ҡпјҲAssociation AgreementпјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҸжі•еҲ¶еәҰгҒ®иӘҝе’ҢгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒ2021е№ҙгҒ«жҠңжң¬зҡ„гҒӘж”№жӯЈгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж–°жі•гҒҜ2022е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгӮҲгӮҠж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®йҖҸжҳҺжҖ§еҗ‘дёҠгӮ„е°‘ж•°ж Әдё»жЁ©гҒ®еј·еҢ–гҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®дјҡзӨҫжі•гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгғүгӮӨгғ„жі•гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еј·гҒҸеҸ—гҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨ§йҷёжі•зі»гҒ®дҪ“зі»гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘжҰӮеҝөгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж—Ҙжң¬жі•гҒЁиҰӘе’ҢжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҒҢгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ«йҖІеҮәгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«еҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢдё»иҰҒгҒӘдәӢжҘӯеҪўж…ӢгҒҜгҖҒжңүйҷҗиІ¬д»»дјҡзӨҫпјҲLimited Liability CompanyпјҡLLCпјүгҒЁж ӘејҸдјҡзӨҫпјҲJoint Stock CompanyпјҡJSCпјүгҒ§гҒҷгҖӮе®ҹеӢҷдёҠгҖҒең§еҖ’зҡ„еӨҡж•°гҒ®дјҒжҘӯгҒҢLLCгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®жңҖеӨ§гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒLLCгҒ«гҒҜжңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘гҒ®иҰҒ件гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж–°жі•дёӢгҒ§гҒ®ж ӘејҸдјҡзӨҫпјҲJSCпјүгҒҜгҖҒиЁӯз«ӢжҷӮгҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ10дёҮгғ©гғӘпјҲ2025е№ҙжҷӮзӮ№гҒ®гғ¬гғјгғҲгҒ§зҙ„550дёҮеҶҶзӣёеҪ“пјүгҒ®жңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®иЁӯз«ӢгҒҠгӮҲгҒіз¶ӯжҢҒгҒ®гғҸгғјгғүгғ«гҒҢеј•гҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж—Ҙжң¬жі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҗҲеҗҢдјҡзӨҫгҒ«иҝ‘гҒ„еҪўж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢLLCгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж–°жі•гҒ§гҒҜгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№ж§ӢйҖ гҒҢгӮҲгӮҠеҺіж јеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒе®ҡж¬ҫеӨүжӣҙгӮ„зө„з№”еҶҚз·ЁгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйҮҚиҰҒдәӢй …гҒ®жұәиӯ°гҒ«гҒҜгҖҒиӯ°жұәжЁ©гҒ®75гғ‘гғјгӮ»гғігғҲд»ҘдёҠгҒ®иіӣжҲҗгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒе°‘ж•°ж Әдё»пјҲгғ‘гғјгғҲгғҠгғјпјүгҒ®дҝқиӯ·гҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒ2022е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙд»ҘеүҚгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹж—ўеӯҳгҒ®жі•дәәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж–°жі•гҒёгҒ®жә–жӢ пјҲе®ҡж¬ҫгҒ®жӣёгҒҚжҸӣгҒҲзӯүпјүгӮ’иЎҢгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®з§»иЎҢжңҹй–“гҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жңҹйҷҗгҒҜж•°еӣһгҒ®е»¶й•·гӮ’зөҢгҒҰгҖҒ2026е№ҙ4жңҲ1ж—ҘгҒҫгҒ§гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жңҹж—ҘгҒҫгҒ§гҒ«еҜҫеҝңгӮ’иЎҢгӮҸгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒжі•дәәзҷ»иЁҳгҒҢеҒңжӯўгҒ•гӮҢгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜжё…з®—жүӢз¶ҡгҒҚгҒ«з§»иЎҢгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж—ўеӯҳгҒ®гӮёгғ§гғјгӮёгӮўжі•дәәгӮ’дҝқжңүгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡLaw of Georgia on Entrepreneurs
https://matsne.gov.ge/en/document/view/5230186?publication=6
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒ®е®ҹеӢҷгҒЁйҒ йҡ”жүӢз¶ҡгҒҚ
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҡзӨҫиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®жңҖеӨ§гҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒзҷәиө·дәәгӮ„еҸ–з· еҪ№гҒҢзҸҫең°гҒ«иөҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒд»ЈзҗҶдәәгӮ’йҖҡгҒҳгҒҹе®Ңе…ЁгғӘгғўгғјгғҲгҒ§гҒ®иЁӯз«ӢгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪ家公е…ұзҷ»йҢІеәҒпјҲNAPRпјүгҒҢгғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒЁд»ЈзҗҶз”іи«ӢгӮ’еәғзҜ„гҒ«иӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒзҸҫең°гҒ®ејҒиӯ·еЈ«гӮ„гӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгҒ«иЁӯз«ӢжЁ©йҷҗгӮ’д»ҳдёҺгҒҷгӮӢ委任зҠ¶пјҲPower of AttorneyпјҡPoAпјүгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒЁгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒҜе…ұгҒ«гҖҢеӨ–еӣҪе…¬ж–ҮжӣёгҒ®иӘҚиЁјгӮ’дёҚиҰҒгҒЁгҒҷгӮӢжқЎзҙ„пјҲгғҸгғјгӮ°жқЎзҙ„пјүгҖҚгҒ®з· зөҗеӣҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ®е…¬иЁјеҪ№е ҙгҒ§е…¬иЁјдәәгҒ®иӘҚиЁјгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеӨ–еӢҷзңҒгҒ«гӮҲгӮӢгӮўгғқгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҰпјҲApostilleпјүд»ҳдёҺгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒқгҒ®ж–ҮжӣёгҒҜгӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪеҶ…гҒ§е…¬ж–ҮжӣёгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҠ№еҠӣгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жқұдә¬йғҪгӮ„еӨ§йҳӘеәңгҒӘгҒ©гҒ®дё»иҰҒгҒӘе…¬иЁјеҪ№е ҙгҒ§гҒҜгҖҒгғҜгғігӮ№гғҲгғғгғ—гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе…¬иЁјдәәгҒ®иӘҚиЁјгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гӮўгғқгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҰгҒ®еҸ–еҫ—гҒҢеҚіж—ҘгҒ§еҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡApostille (MOFA Japan)
https://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000416.html
зҸҫең°д»ЈзҗҶдәәгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮўгғқгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҰд»ҳгҒҚ委任зҠ¶гҒЁгҖҒе®ҡж¬ҫпјҲCharterпјүгҖҒгҒҠгӮҲгҒізҸҫең°гҒ§гҒ®жі•дәәзҷ»иЁҳдёҠгҒ®дҪҸжүҖпјҲLegal AddressпјүгҒ®дҪҝз”ЁеҗҢж„ҸжӣёгӮ’NAPRгҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжүӢз¶ҡгҒҚгҒҜйҖҡеёёгҖҒз”іи«ӢгҒ®зҝҢе–¶жҘӯж—ҘгҖҒиҝҪеҠ ж–ҷйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶзү№жҖҘз”іи«ӢгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°еҚіж—ҘпјҲеҗҢж—ҘпјүгҒ«е®ҢдәҶгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬жі•дәәгҒ®зҷ»иЁҳжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢйҖҡеёё1йҖұй–“гҒӢгӮү2йҖұй–“зЁӢеәҰиҰҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®иҝ…йҖҹжҖ§гҒҜйҡӣз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒзҷ»иЁҳдёҠгҒ®дҪҸжүҖгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢз§Ғжӣёз®ұгӮ„е®ҹдҪ“гҒ®гҒӘгҒ„дҪҸжүҖиІёгҒ—гӮөгғјгғ“гӮ№пјҲгғҗгғјгғҒгғЈгғ«гӮӘгғ•гӮЈгӮ№пјүгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҫҢиҝ°гҒҷгӮӢзЁҺеӢҷиӘҝжҹ»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе®ҹдҪ“жҖ§гҒ®ж¬ еҰӮгӮ’зҗҶз”ұгҒ«е…ҚзЁҺгӮ№гғҶгғјгӮҝгӮ№гҒҢеҗҰиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢдәӢдҫӢгҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒйғөдҫҝзү©гҒ®еҸ—й ҳгӮ„зү©зҗҶзҡ„гҒӘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢеҸҜиғҪгҒӘдҪҸжүҖгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе®ҹеӢҷдёҠжҺЁеҘЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®зЁҺеҲ¶гҒЁгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгғ»гғўгғҮгғ«
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®жі•дәәзЁҺеҲ¶гҒҜгҖҒ2017е№ҙгӮҲгӮҠе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹйҖҡз§°гҖҢгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгғ»гғўгғҮгғ«гҖҚгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжі•дәәгҒҢеҲ©зӣҠгӮ’иЁҲдёҠгҒ—гҒҹжұәз®—жңҹгҒ«гҒҜиӘІзЁҺгӮ’иЎҢгӮҸгҒҡгҖҒгҒқгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’ж Әдё»гҒёгҒ®й…ҚеҪ“пјҲгҒҫгҒҹгҒҜй…ҚеҪ“гҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢж”ҜеҮәпјүгҒЁгҒ—гҒҰеҲҶй…ҚгҒ—гҒҹжҷӮзӮ№гҒ§еҲқгӮҒгҒҰжі•дәәзЁҺгӮ’иӘІгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶд»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒй…ҚеҪ“йЎҚгӮ’0.85гҒ§йҷӨгҒ—гҒҹйҮ‘йЎҚгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ15гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒ®жі•дәәзЁҺгҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜе®ҹиіӘзҡ„гҒ«гҖҒй…ҚеҪ“йЎҚгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзҙ„17.65гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒ®зЁҺиІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬жі•дәәгҒҢеҲ©зӣҠгҒ®зҷәз”ҹгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«иӘІзЁҺпјҲзҷәз”ҹдё»зҫ©пјүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ§гҒҜеҲ©зӣҠгӮ’еҶ…йғЁз•ҷдҝқгҒ—гҖҒеҶҚжҠ•иіҮгҒ«еӣһгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҷҗгӮҠгҖҒжі•дәәзЁҺгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гӮ’з„ЎжңҹйҷҗгҒ«з№°гӮҠ延гҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгғ•гғӯгғјгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢгӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—дјҒжҘӯгӮ„гҖҒзҸҫең°гҒ§гҒ®дәӢжҘӯжӢЎеӨ§гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷдјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®й–“гҒ«гҒҜгҖҒ2021е№ҙгҒ«зҷәеҠ№гҒ—гҒҹгҖҢжүҖеҫ—гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢз§ҹзЁҺгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәҢйҮҚиӘІзЁҺгҒ®йҷӨеҺ»дёҰгҒігҒ«и„ұзЁҺеҸҠгҒіз§ҹзЁҺеӣһйҒҝгҒ®йҳІжӯўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж—Ҙжң¬еӣҪгҒЁгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒЁгҒ®й–“гҒ®жқЎзҙ„пјҲж—Ҙгғ»гӮёгғ§гғјгӮёгӮўз§ҹзЁҺжқЎзҙ„пјүгҖҚгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жқЎзҙ„гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўжі•дәәгҒҢж—Ҙжң¬еұ…дҪҸиҖ…пјҲжі•дәәгҒҫгҒҹгҒҜеҖӢдәәпјүгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰй…ҚеҪ“гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶйҡӣгҒ®жәҗжіүеҫҙеҸҺзЁҺзҺҮгҒҜгҖҒиӯ°жұәжЁ©гҒ®10гғ‘гғјгӮ»гғігғҲд»ҘдёҠгӮ’дҝқжңүгҒҷгӮӢиҰӘеӯҗдјҡзӨҫй–“гҒӘгҒ©гҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷе ҙеҗҲгҖҒеҫ“жқҘгҒ®жі•еҲ¶гӮҲгӮҠгӮӮдҪҺгҒ„5гғ‘гғјгӮ»гғігғҲпјҲгҒҫгҒҹгҒҜе…ҚзЁҺпјүгҒ«еҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪеҶ…жі•дёҠгҒ®й…ҚеҪ“жәҗжіүзЁҺзҺҮгӮӮ5гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз§ҹзЁҺжқЎзҙ„гҒ®йҒ©з”ЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе°ҶжқҘзҡ„гҒӘеӣҪеҶ…жі•гҒ®зЁҺзҺҮеј•гҒҚдёҠгҒ’гғӘгӮ№гӮҜгҒӢгӮүдҝқиӯ·гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гҒҢзўәдҝқгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡConvention between Japan and Georgia for the Elimination of Double Taxation
https://www.mofa.go.jp/files/100143488.pdf
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®ITдјҒжҘӯеҗ‘гҒ‘е„ӘйҒҮзЁҺеҲ¶гҒЁе®ҹдҪ“иҰҒ件гҒ®еҺіж јеҢ–

гӮёгғ§гғјгӮёгӮўйҖІеҮәгҒ®жңҖеӨ§гҒ®иӘҳеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒITгӮ»гӮҜгӮҝгғјгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеј·еҠӣгҒӘе„ӘйҒҮзЁҺеҲ¶гҒ§гҒҷгҖӮдё»гҒ«гҖҢгғҗгғјгғҒгғЈгғ«гӮҫгғјгғіпјҲVirtual Zone PersonпјҡVZPпјүгҖҚгҒЁгҖҢеӣҪйҡӣдјҒжҘӯпјҲInternational Company StatusпјҡICSпјүгҖҚгҒ®2гҒӨгҒ®гӮ№гғҶгғјгӮҝгӮ№гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғҗгғјгғҒгғЈгғ«гӮҫгғјгғігҒҜгҖҒITгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еӣҪеӨ–гҒ®йЎ§е®ўгҒ«жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдјҒжҘӯгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҲ©зӣҠгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжі•дәәзЁҺгҒҢе…ЁйЎҚе…ҚйҷӨпјҲ0гғ‘гғјгӮ»гғігғҲпјүгҒ•гӮҢгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиҝ‘е№ҙгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўжӯіе…ҘеәҒпјҲRevenue ServiceпјүгҒҜгҒ“гҒ®йҒ©з”ЁгҒ®еҜ©жҹ»гӮ’еҺіж јеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«2022е№ҙ12жңҲгҒ«зҷәиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢж–№жі•зҡ„жҢҮйҮқгҖҚд»ҘйҷҚгҖҒеҚҳгҒ«гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўй–ӢзҷәгӮ’иЎҢгҒҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪеҶ…гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢеҚҒеҲҶгҒӘзөҢжёҲзҡ„е®ҹдҪ“пјҲSubstanceпјүгҖҚгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪеҶ…гҒ§гҒ®йҒ©еҲҮгҒӘиіҮж јгӮ’жҢҒгҒӨеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®йӣҮз”ЁгӮ„гҖҒе®ҹйҡӣгҒ®жҘӯеӢҷйҒӮиЎҢгҒ®е®ҹзёҫгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒеӣҪйҡӣдјҒжҘӯгӮ№гғҶгғјгӮҝгӮ№пјҲICSпјүгҒҜгҖҒITгҒҠгӮҲгҒіжө·йҒӢжҘӯгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҖҒжі•дәәзЁҺзҺҮгӮ’5гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒ«и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒй…ҚеҪ“гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢжәҗжіүзЁҺгӮ’0гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҫ“жҘӯе“ЎгҒ®иіғйҮ‘гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢжүҖеҫ—зЁҺгӮ’йҖҡеёёгҒ®20гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒӢгӮү5гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒ«еј•гҒҚдёӢгҒ’гӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮICSгҒ®еҸ–еҫ—гҒ«гҒҜгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪеҶ…гҒҫгҒҹгҒҜжө·еӨ–гҒ®иҰӘдјҡзӨҫгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰ2е№ҙд»ҘдёҠгҒ®еҪ“и©ІдәӢжҘӯгҒ®е®ҹзёҫгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®ITдјҒжҘӯгҒҢеӯҗдјҡзӨҫгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒж—Ҙжң¬жң¬зӨҫгҒ®е®ҹзёҫгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгғҗгғјгғҒгғЈгғ«гӮҫгғјгғігҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰжі•дәәзЁҺгҒҜзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй…ҚеҪ“иӘІзЁҺгҒҢе…ҚйҷӨгҒ•гӮҢгӮӢзӮ№гӮ„иіғйҮ‘зЁҺгҒ®еӨ§е№…гҒӘеүҠжёӣеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гҖҒгҒқгҒ—гҒҰиҰҒ件гҒҢжҳҺзўәгҒ§жі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„зӮ№гҒӢгӮүгҖҒзө„з№”зҡ„гҒӘдәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’иЎҢгҒҶж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜICSгҒ®ж–№гҒҢжҺЁеҘЁгҒ•гӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йҮҚиҰҒгҒӘжіЁж„ҸзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®е„ӘйҒҮзЁҺеҲ¶гӮ’дә«еҸ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе®ҹдҪ“гҒ®дјҙгӮҸгҒӘгҒ„гҖҢгғҡгғјгғ‘гғјгӮ«гғігғ‘гғӢгғјгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ2025е№ҙзӯүгҒ®иҝ‘е№ҙгҒ®еҲӨдҫӢгӮ„зЁҺеӢҷзҙӣдәүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжӯіе…ҘеәҒгҒҜе®ҹдҪ“гҒ®гҒӘгҒ„дјҒжҘӯгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒйҒҺеҺ»гҒ«йҒЎгҒЈгҒҰе…ҚзЁҺжҺӘзҪ®гӮ’еҗҰиӘҚгҒ—гҖҒиҝҪеҫҙиӘІзЁҺгӮ’иЎҢгҒҶгӮұгғјгӮ№гҒҢж•ЈиҰӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўд»®жғігӮҫгғјгғіеұ…дҪҸиҖ…еҚ”дјҡпјҲGeorgian Virtual Zone Residents AssociationпјүгҒ®дјҡе“ЎдјҒжҘӯгҒҢй–ўдёҺгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒITдјҒжҘӯгҒҢеҚҒеҲҶгҒӘиіҮж јгӮ’жҢҒгҒӨеҫ“жҘӯе“ЎгӮ’зҸҫең°гҒ§йӣҮз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶз”ұгҒ«гҖҒй…ҚеҪ“гҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹжүҖеҫ—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҝҪеҫҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒжі•е»·гҒ§дәүгӮҸгӮҢгҒҹгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒе®ҹдҪ“иҰҒ件гҒ®и§ЈйҮҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҙҚзЁҺиҖ…еҒҙгҒ®дё»ејөгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢеҲӨжұәгӮ’дёӢгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзҙӣдәүгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒиЁӯз«ӢеҪ“еҲқгҒӢгӮүзү©зҗҶзҡ„гҒӘгӮӘгғ•гӮЈгӮ№гҒ®зўәдҝқгӮ„зҸҫең°гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ®йӣҮз”ЁгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе®ҹдҪ“еҪўжҲҗгҒёгҒ®жҠ•иіҮгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
еҸӮиҖғпјҡInternational Company Status (Revenue Service)
https://www.rs.ge/PersonsPreferentialTax-en?cat=2&tab=1
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®йҠҖиЎҢеҸЈеә§й–ӢиЁӯгҒЁйҮ‘иһҚе®ҹеӢҷгҒ®иӘІйЎҢ
жі•дәәиЁӯз«ӢиҮӘдҪ“гҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®йҠҖиЎҢеҸЈеә§й–ӢиЁӯгҒҜеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘгғҸгғјгғүгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®дё»иҰҒйҠҖиЎҢпјҲBank of GeorgiaгӮ„TBC BankгҒӘгҒ©пјүгҒҜгҖҒгғһгғҚгғјгғӯгғігғҖгғӘгғігӮ°еҜҫзӯ–пјҲAMLпјүгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүгҖҒйқһеұ…дҪҸиҖ…гҒҢеҮәиіҮгҒҷгӮӢжі•дәәгҒ®еҸЈеә§й–ӢиЁӯеҜ©жҹ»гӮ’еҺіж јеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеҸ–з· еҪ№гҒҢдёҖеәҰгӮӮзҸҫең°гӮ’иЁӘе•ҸгҒӣгҒҡгҒ«гғӘгғўгғјгғҲгҒ§жі•дәәеҸЈеә§гӮ’й–ӢиЁӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜжҘөгӮҒгҒҰеӣ°йӣЈгҒ§гҒҷгҖӮеҸЈеә§й–ӢиЁӯгҒ«гҒҜгҖҒеҸ–з· еҪ№гҒ®еҜҫйқўгҒ§гҒ®йқўи«ҮгҒ«еҠ гҒҲгҖҒдәӢжҘӯиЁҲз”»жӣёгҖҒеҸ–еј•е…ҲгҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„жӣёгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮӘгғ•гӮЈгӮ№иіғиІёеҘ‘зҙ„жӣёгҒӘгҒ©гҒ®жҸҗеҮәгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гӮӮгҖҢгӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪеҶ…гҒ§гҒ®зөҢжёҲзҡ„зөҗгҒігҒӨгҒҚгҖҚгҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ЈжӣҝжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒWiseпјҲж—§TransferWiseпјүгӮ„PayseraгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғ•гӮЈгғігғҶгғғгӮҜгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жі•дәәеҸЈеә§гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгғӘгғўгғјгғҲгҒ§гҒ®й–ӢиЁӯгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®еӣҪеә«пјҲTreasuryпјүгҒёгҒ®зҙҚзЁҺгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®зҙҚзЁҺгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҖҒеӣҪеҶ…йҠҖиЎҢгҒӢгӮүгҒ®йҖҒйҮ‘гӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҹзөұдёҖеӣҪеә«гӮігғјгғүпјҲдҫӢпјҡ101001000пјүгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжө·еӨ–йҖҒйҮ‘жүұгҒ„гҒЁгҒӘгӮӢгғ•гӮЈгғігғҶгғғгӮҜеҸЈеә§гҒӢгӮүгҒ®зҙҚзЁҺгҒ«гҒҜгҖҒд»Ід»ӢйҠҖиЎҢгҒ®зөҢз”ұгӮ„зү№еҲҘгҒӘйҖҒйҮ‘жүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзҙҚзЁҺгҒ®йҒ…延гӮ„зқҖйҮ‘дёҚжҳҺгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҖҒеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°зҸҫең°йҠҖиЎҢеҸЈеә§гҒ®й–ӢиЁӯгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҙӣдәүи§ЈжұәгҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰ
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ§гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзҙӣдәүгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰзҸҫең°гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҢз®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮгғҲгғ“гғӘгӮ·еёӮиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒҜе•ҶдәӢзҙӣдәүгӮ’е°Ӯй–ҖгҒЁгҒҷгӮӢйғЁй–ҖгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®дёҚи¶ігӮ„жЎҲ件гҒ®еў—еҠ гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҜ©зҗҶгҒ®йҒ…延гҒҢж…ўжҖ§зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚҳзҙ”гҒӘиЎҢж”ҝиЁҙиЁҹгӮ„е•ҶдәӢиЁҙиЁҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒ第дёҖеҜ©гҒ®еҲӨжұәгҒҢеҮәгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«ж•°е№ҙгӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮзҸҚгҒ—гҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢеҘ‘зҙ„жӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒзҙӣдәүи§ЈжұәжқЎй …гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӣҪйҡӣд»ІиЈҒпјҲArbitrationпјүгӮ’жҢҮе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгғӘгӮ№гӮҜз®ЎзҗҶгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒҜгҖҢеӨ–еӣҪд»ІиЈҒеҲӨж–ӯгҒ®жүҝиӘҚеҸҠгҒіеҹ·иЎҢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎзҙ„пјҲгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜжқЎзҙ„пјүгҖҚгҒ®еҠ зӣҹеӣҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒд»–еӣҪгҒ§дёӢгҒ•гӮҢгҒҹд»ІиЈҒеҲӨж–ӯгӮ’гӮёгғ§гғјгӮёгӮўеӣҪеҶ…гҒ§еҹ·иЎҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжі•зҡ„гҒ«дҝқиЁјгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ§гҒ®дјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒҜгҖҒжңҖдҪҺиіҮжң¬йҮ‘гҒ®дёҚиҰҒгҒӘLLCгҒЁгҒ„гҒҶжҹ”и»ҹгҒӘдјҡзӨҫеҪўж…ӢгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӢгӮўгғ»гғўгғҮгғ«гҒ«гӮҲгӮӢеҶҚжҠ•иіҮгҒ®дҝғйҖІгҖҒгҒқгҒ—гҒҰITдјҒжҘӯгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеј·еҠӣгҒӘзЁҺеҲ¶е„ӘйҒҮжҺӘзҪ®гҒӘгҒ©гҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨҡгҒҸгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒ2021е№ҙгҒ®жі•ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮӢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№иҰҒ件гҒ®еј·еҢ–гӮ„гҖҒзЁҺеӢҷеҪ“еұҖгҒ«гӮҲгӮӢе®ҹдҪ“иҰҒ件гҒ®еҺіж јгҒӘеҜ©жҹ»гҖҒйҠҖиЎҢеҸЈеә§й–ӢиЁӯгҒ®йӣЈжҳ“еәҰгҒӘгҒ©гҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®иӘІйЎҢгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҢгғҡгғјгғ‘гғјгӮ«гғігғ‘гғӢгғјгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢе®үжҳ“гҒӘзҜҖзЁҺгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘзЁҺеӢҷгғӘгӮ№гӮҜгӮ’дјҙгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҸҫең°гҒ§гҒ®йӣҮз”ЁгӮ„жӢ зӮ№еҪўжҲҗгӮ’дјҙгҒҶе®ҹиіӘзҡ„гҒӘгғ“гӮёгғҚгӮ№еұ•й–ӢгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҲ‘гҖ…гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮёгғ§гғјгӮёгӮўгҒ®жңҖж–°гҒ®жі•иҰҸеҲ¶гӮ„е®ҹеӢҷж…ЈиЎҢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®зҡҶж§ҳгҒ®зҸҫең°йҖІеҮәгӮ„жі•зҡ„иӘІйЎҢгҒ®и§ЈжұәгӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзҸҫең°гҒ®жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгӮ„е°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ®гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒиЁӯз«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒӢгӮүзЁҺеӢҷгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҖҒеҘ‘зҙ„жӣёдҪңжҲҗгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒеҶҶж»‘гҒӘдәӢжҘӯйҒӢе–¶гӮ’гҒҠжүӢдјқгҒ„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ