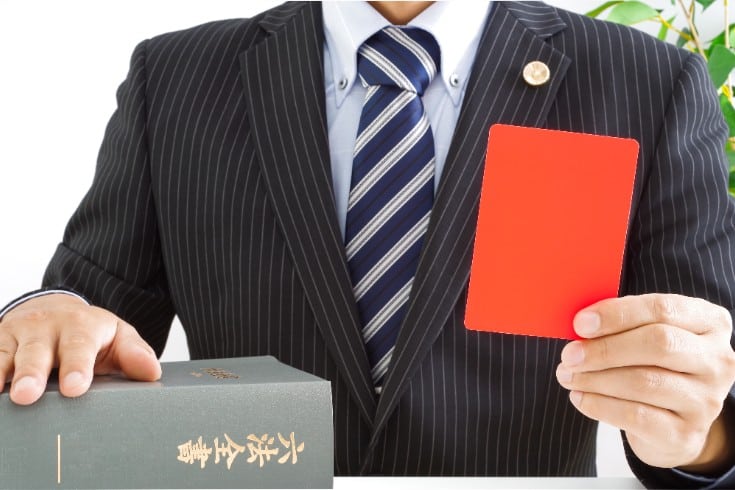人材開発支援助成金の不正受給問題から学ぶ自衛の方針

人材開発支援助成金は、企業のリスキリングや人材育成を支援する重要な公的制度です。しかし、その複雑性を悪用した不正受給が後を絶たず、深刻な社会問題となっています。特に、「実質無料」を謳うスキームは、「営業協力費」など、名目が何であろうと、実質的なキックバックを行う時点で不正受給と認定される可能性が非常に高いものと言えます。
本記事では、厚生労働省の労働局が人材開発支援助成金の不正受給に関与したとして社名を公表した実際の事案の分析を行います。そして、不正がもたらすリスクと、企業が自衛を行うためのポイントについて解説します。
例えば、労働局が訓練実施者の社名を公表する一方で、申請事業主側の社名が公表されないケースがあります。「それは何故なのか」という点は、今回の解説から学ぶべきことの一つです。
※2025年12月26日追記
本記事で紹介する事例の訓練実施者について、大規模な不正摘発が行われています。2025年12月以降の摘発に関しては下記記事で詳細に解説しています。
この記事の目次
助成金不正受給事案の概要と背景
不正に関与した助成金とは
本記事でご紹介する不正受給事案は、「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」に関わるものです。この助成金は、事業主が雇用する労働者に対し、職業に関連する知識や技能の取得を目的とした訓練を実施した場合に、その訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を国が助成する制度です。労働者の能力開発を促進し、企業の生産性向上を支援することを目的としています。
この助成金は、近年、新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置や、政府が掲げる「人への投資」加速化の流れで要件が緩和され、利用機会が拡大しました。制度の複雑性が増したことで、制度の隙間を狙う専門業者が、いわば「不正受給のコンサルタント」として参入する余地が生まれた可能性は否定できません。
助成金不正受給の具体的スキーム

「実質的負担」の要件
人材開発支援助成金は、申請事業主が訓練経費の「全額」を負担していることを支給の要件としています。これは、助成金が税金を原資とする公的資金であり、企業の自発的かつ実質的な投資努力を支援するという、制度本来の趣旨に基づくものです。事業主が訓練費用を負担していない、あるいはその費用が別の形で還流されている場合、助成金申請は要件を満たさないことになります。この「実質的負担」という要件が、本記事でご紹介する不正請求事案で紹介する不正スキームです。
「実質無料」スキームの構造
近年問題視されることが多いスキームが、いわゆる「実質無料」として構築されたスキームです。その具体的な仕組みは以下の通りです。
- 資金の補填:訓練実施者が、助成金の申請者である事業主に対し、「営業協力費」などの名目で、訓練経費と同額または一定割合の金額を支払います。
- 見せかけの費用負担:助成金申請事業主は、訓練実施者から補填された資金を原資として、形式上は自社で訓練経費を全額支払ったかのように装い、虚偽の申請を行います。
- 助成金の申請と分配:事業主は、この申請に基づいて助成金を受給し、その後、事業主が受け取った助成金の一部を、事前に交わされた覚書に基づき、訓練実施者が収受することになっています。
労働局により公開された情報によると、調査の結果、事業主へ支払われた「営業協力費」には、対価関係に立つ実質的な役務提供が認められず、名目上の契約が不正を隠蔽するための手段であったことが明らかになったケースがあります。このスキームは、事業主が自己負担なしで訓練を受講できる上に、一定の利益が残るというものでした。そして、この場合、事業主は訓練経費の「全額」を負担しているとは言えず、支給の要件を満たさないため、「不正受給」である、ということになります。
悪質な助成金不正受給の指南行為と法的問題
上記スキームが用いられた不正事案では、単に資金還流スキームが考案されただけにとどまりません。訓練実施者が申請事業主に対して助成金支給申請書の作成方法を指南し、さらに労働局から不正受給に関する調査を受けた際の対応方法についても指示を出していたとされています。
この指南行為は、不正の幇助という範疇を超えていると言えるでしょう。対応方法についての指示の詳細は公表されていませんが、例えば、「営業協力費(など実質的なキックバックの支払い)」に関して、対価関係に立つ実質的な役務提供があったと証言するように求める、といった指示を行う業者も存在する模様です。
助成金不正受給の全容
こうした不正は、訓練実施者の側が発案し、複数の申請事業主に持ちかける、という形で行われることが通常です。このため例えば、この場合の複数社の中の1社で従業員からの内部告発が行われ、行政が当該1社を調査し、組織的犯行の可能性が高いと判断し、他の申請事業主の事例に関しても横断的に調査を行う、といった形で、いわば「芋づる式」の調査が比較的容易に行われるものと思われます。
助成金不正受給の法的・経営的側面:リスクと罰則
刑事・民事上の法的責任
助成金の不正受給は、単なる行政上の問題ではなく、犯罪行為に該当する可能性があります。労働局を欺いて公的資金を不正に取得する行為は、刑法第246条の詐欺罪に問われる可能性が高いとされています。詐欺罪は「10年以下の懲役」と定められており、罰金刑が規定されていないため、起訴されると正式裁判となります。
この法的責任は、不正スキームを考案した訓練実施者と虚偽の申請を行った申請事業主の双方に及びます。
- 訓練実施者:不正を指南した訓練指導者は、単なる幇助にとどまらず、詐欺罪の共同正犯として問われる可能性があります。
- 申請事業主:申請事業主もまた、自らが虚偽の申請を行ったため、詐欺罪の共同正犯に問われるリスクがあります。
金銭的・行政的ペナルティ
不正受給が確定した場合、関与した企業には以下の複合的な重罰が科されます。これらは、訓練実施者と申請事業主、双方に科されるペナルティです。
| 詳細 | |
|---|---|
| 受給額の全額返還 | 不正に受給した金額の全額を返還する義務があります。 |
| 違約金(加算金) | 不正受給額の20%に相当する金額の納付を命じられます。 |
| 延滞金 | 不正受給日の翌日から返還完了までの年率10.95%の利息が課されます。返還が遅延するほど、企業の金銭的負担は加速度的に増加します。 |
| 助成金受給資格の剥奪 | 不正受給と判定された日から5年間、雇用関係助成金を含むすべての助成金の受給資格が剥奪されます。返還が完了しない場合は延長されます。 |
助成金申請事業主の社名が公表されない場合がある理由

社名の公表基準
「訓練実施者」として労働局から社名と代表者名が公表されるケースがある一方で、助成金を申請した事業主(企業)の社名が公表されないことがあります。
これは、社名の公表基準が「訓練実施者」と「申請事業主」で異なるためです。
- 訓練実施者:社会保険労務士や訓練実施機関など、不正に関与した指南役の場合、金額や返還の有無にかかわらず、原則として社名が公表されます。これは、不正の連鎖を断ち切るための厳しい措置です。
- 申請事業主の社名が公表されるのは、原則として労働局の調査により不正が発覚し、かつ支給決定取消額が100万円以上の場合に限られます。しかし、労働局による調査が入る前に事業主自らが自主申告を行い、速やかに全額を返還した場合、公表を免れる可能性があるとされています。申請事業主の社名が公表されない場合があるのは、これらの企業が自主申告という対応を取ったことが理由である可能性があります。
訓練実施者と申請事業主の潜在的な利害対立
このため、訓練実施者の社名がまだ公表されていない時点では、訓練実施者と申請事業主の間には、潜在的な利害対立があります。
- 訓練実施者:不正が発覚すると原則社名を公表されるので、自主申告という手段は基本的にない。申請事業主による自主申告を妨害し、「逃げ切る」ことを望む
- 申請事業主:適切な自主申告を行えば、社名を公表されずに済む可能性がある
訓練実施者から申請事業主に対し、「不正受給に関する調査を受けた際の対応方法についての指示」などが行われやすいのは、こうした構造によるものだと言えるでしょう。
まとめ:助成金に関するトラブルは弁護士に相談を
助成金制度の監査は、形式的な書類確認から、資金の流れや役務提供の実態を詳細に検証する「実質主義」へと移行していくと予測されます。会計検査院も、不正を防ぐための制度見直しを厚生労働省に要求しており、今後は異なる省庁間でデータが連携され、不正受給がより容易に発覚する体制が構築される可能性が高いと考えられます。
企業は、以下の予防策とリスク管理の重要性を認識する必要があります。
まず、事前の対策としては、コンプライアンス体制の強化と、専門家の選定基準の厳格化が必要でしょう。助成金申請に関わる担当者への教育を徹底し、申請書類の作成プロセスに内部監査を組み込むべきです。そして、助成金申請のサポートを外部に委託する場合、「簡単」「実質無料」といった甘い言葉に惑わされるべきではありません。
また、万が一、不正の疑いがある場合は、労働局の調査が入る前に速やかに自主申告を行うことが、法的・金銭的リスクを最小化する上で最も重要な手段となります。自主申告を行うことで、特に悪質な場合などの例外を除き、事業主名の公表を免れる可能性があります。
そして、その際には、訓練実施者から、不正受給に関する調査を受けた際の対応方法についての指示などを受けても、従うべきではありません。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、ビジネスモデルや事業内容を深く理解した上で潜在的な法的リスクを洗い出し、リーガルサポートを行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:補助金等の不正受給対応
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務