フランス共和国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

フランスは日本と同じく大陸法系に属し、法典を基礎とする点は共通していますが、その運用や解釈、特に公法と私法の明確な区別、ビジネス慣行に深く根差した契約法や労働法の詳細といった点において、日本法とは異なる重要な特徴があります。
また、近年、デジタル経済の発展に伴い、IT関連法制も急速に整備されており、電子商取引、データ保護、サイバーセキュリティ、デジタルサービスに関する規制は、EU全体の動向と密接に連携しつつ、独自の厳格な枠組みとなっています。
本記事では、フランス法制度の基本構造から、日本企業が特に留意すべき会社法、契約法、労働法といったビジネス関連法の主要なポイント、さらにはIT分野に特化した法規制の概要までを解説します。
この記事の目次
フランス法制度の基本構造と特徴
大陸法系の採用と法典主義
フランスは、ドイツなどと同様に「大陸法」を採用しており、その共通の起源は古代ローマ法にあります。特に、1804年に制定されたナポレオン民法典(Code civil)や1807年の商法典(Code de commerce)がその基礎を形成しています。これらの法典は、市民生活や商取引の基本的なルールを網羅的に定めており、法適用における一貫性と予測可能性を重視する法典主義の原則が貫かれています。
公法と私法の明確な区別
フランス法制度の顕著な特徴の一つは、公法と私法の明確な区別、そしてそれに対応する裁判所の二元構造です。私法(民法、商法など)に関する紛争は司法裁判所(Cour de cassationを頂点とする司法部門)が管轄し、行政活動に関する公法上の紛争は行政裁判所(Conseil d’Etatを頂点とする行政部門)が管轄します。行政裁判所は、国家や行政機関に対する訴えを管轄する専門家集団によって構成されています。
フランスにおける主要な会社形態

フランスでは、事業の規模、株主数、責任範囲、ガバナンスの柔軟性、税制などに応じて、様々な会社形態が選択可能です。
有限責任会社(SARL: Société à Responsabilité Limitée)
SARLは日本の有限会社に相当し、中小企業や家族経営に最も一般的な形態の一つです。出資者の責任は出資額に限定される有限責任であり、2名から100名までで設立可能です。株主が1名の場合は後述するEURLとなります。株主数が100名を超えた場合、SARLは1年以内に株主数を減らすか、株式会社(SA)に転換する必要があります。最低資本金の制限はなく、1ユーロから設立可能ですが、事業の信頼性を確保するためには、より多くの資本金が推奨されます。現金出資の場合、設立時に最低20%を払い込む必要があり、残りは5年以内に払い込むことができます。現物出資が3万ユーロを超える場合、または総資本金の半分以上を占める場合は、現物出資監査人の選任が義務付けられます。
経営は1名以上の自然人である「ジェラン(gérant)」が担い、法人がジェランとなることは認められていません。ジェランの任命、解任、権限、および株主の意思決定ルールは、フランス商法典によって厳格に定められています。株主総会はジェランの職務を補佐する役割を持ちます。
単純型株式会社(SAS: Société par Actions Simplifiée)
SASは日本の合同会社に近い形態であり 、その高い柔軟性からスタートアップや外国企業に最も人気のある法人形態です。出資者の責任は出資額に限定される有限責任であり、最低1名(SASU)から設立可能で、上限はありません。最低資本金は制限がなく、1ユーロから設立可能ですが、一般的には事業の信頼性のため、1,000ユーロ以上が推奨されます。現金出資の場合、設立時に最低50%を払い込む必要があり、残りは5年以内に払い込むことができます。
ガバナンスは非常に柔軟性が高く、定款(articles of association)により、株主の権利、意思決定プロセス、経営者の任命・解任など、組織構造を自由に定めることができます。これにより、非常に柔軟な経営体制を構築できます。社長(président)の選任が義務付けられますが、社長以外の機関を定款で定め、権限を定めることができます。社長は個人でも法人でもよく、外国の親会社をフランス子会社の社長に直接任命することも可能。取締役会や監査役会など、他の機関の設置は任意です。SASのガバナンスの柔軟性と株式譲渡の容易さは、スタートアップや外部投資を誘致したい企業にとって非常に魅力的です。
株式会社(SA: Société Anonyme)
SAは、大規模企業や上場を目指す企業向けの、より厳格な規制を持つ会社形態です。日本の株式会社に相当します。出資者の責任は出資額に限定される有限責任であり、非上場の場合は最低2名、上場の場合は最低7名以上が必要です。最低資本金は37,000ユーロと定められており、設立時に最低50%を払い込む必要があります。
ガバナンスは比較的厳格なルールが適用されます。単一型(Moniste)では取締役会(board of directors)と代表取締役(Directeur Général – DG)を置き、取締役会は3名から18名で構成され、会長(président)とDGを兼任することも可能。二層型(Dualiste)では経営委員会(management board)と監査役会(supervisory board)を置き、経営委員会は2名から5名(上場企業は7名)で構成され、監査役会が監督します。取締役は法人でもよいが、常駐代表者が必要であり、業務執行取締役は自然人である必要があります。必ず会計監査人(commissaire aux comptes)を設置する必要があります。上場企業や従業員500名以上(2020年には250名に引き下げ)で、売上高または資産が5,000万ユーロ以上の企業は、取締役会の男女比が40%以上である必要があります。SAは公開会社であり、規制市場への上場が可能であり、大規模な資金調達が可能で、高い信頼性を持つとされています。
その他の会社形態
フランスには、上記で詳述した主要な会社形態以外にも、特定の目的や事業構造に適した形態が存在します。
- 一人有限責任会社(EURL: Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée):EURLはSARLの単独株主版であり、個人事業主が有限責任で事業を行いたい場合に適しています。
- 一人単純型株式会社(SASU: Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle):SASUはSASの単独株主版であり、個人事業主が柔軟なガバナンス構造を望む場合に適しています。
- 個人事業主(EI: Entreprise Individuelle)およびマイクロアントルプルヌール(Micro-entreprise):EIは最もシンプルで設立が容易な事業形態であり、個人が独立して商業、手工業、自由業などの活動を行う場合に適しています。
- 支店(Branch):フランス国内での営業活動が可能でありながら独立した法人格を持たない
- 駐在員事務所(Liaison Office):商業活動を目的とせず市場調査や連絡拠点としての利用が主となる
- 合名会社(SNC: Société en Nom Collectif):全てのパートナーが無限責任を負う
- 合資会社(SCS: Société en Commandite Simple):無限責任を負う業務執行社員と有限責任を負う有限責任社員で構成される
- 株式合資会社(SCA: Société en Commandite par Actions):株式を発行し無限責任社員が経営を支配する
- 民事会社(SCI: Société Civile Immobilière):不動産の管理・賃貸を目的とする
フランスの商業法
フランスの商業法は、1807年の商法典(Code de commerce)にその基礎を持ち、その適用は「商行為」(acte de commerce)の客観的性質によって決定される「客観主義」を採用しています。これは、行為者の属性(商人であるか否か)ではなく、行為そのものが商行為に該当するかどうかで商業法の適用が決まるという考え方です。例えば、物品の転売目的での購入、動産の賃貸事業、製造業、運送業、銀行業などが商行為とされています(Code de commerce, Article L110-1, L110-2)。商行為に関する証拠は、法律に別段の定めがある場合を除き、あらゆる手段で証明できるとされています(Code de commerce, Article L110-3)。
日本の商法も商行為の概念を有しますが、フランスの「客観主義」の下では、たとえ一般の個人や非営利団体であっても、商行為を行えば商業法の適用を受ける可能性があります。そして、商行為の証明は「あらゆる手段で可能」とされています。
フランスの契約法
フランス契約法は、2016年の民法典改正によって大きく刷新され、現代のビジネス慣行に合わせた明確な規定が導入されました。
交渉段階からの「信義誠実の原則」と情報開示義務
フランス民法典第1104条は、「契約は、交渉、締結及び履行の各段階において、信義誠実に行われなければならない」と明文で規定しています。この原則に違反した場合、損害賠償だけでなく、契約の無効化につながる可能性もあります。
さらに、民法典第1112-1条は、広範な「情報開示義務」(devoir d’information)を定めています。「相手方の同意にとって決定的に重要な情報を知っている当事者は、その相手方が正当な理由でその情報を知らないか、または信頼している場合、その情報を開示しなければならない」とされています。この義務は、当事者間で制限または排除することができません。ただし、役務の価値評価に関する情報は、この情報開示義務の対象外と明記されています。この義務違反は、義務を負っていた当事者の責任を問われるだけでなく、契約の取消しにつながる可能性があります。
日本法においても、契約交渉における信義則上の義務や情報開示義務は判例法理で認められていますが、フランス法のように民法典に明文で広範に規定され、かつその義務を排除できない点は大きな相違です。
「予見可能性のない状況変化」と契約の再交渉(ハードシップ条項)
民法典第1195条は、「契約締結時に予見できなかった状況の変化により、当事者の一方にとってその義務の履行が著しく過重となった場合で、かつ当該当事者がそのリスクを負担することを受け入れていなかった場合、その当事者は相手方に契約の再交渉を求めることができる」と規定しています。再交渉中も義務の履行は継続しなければなりません。再交渉が拒否されたり不調に終わったりした場合、当事者は合意により契約を解除するか、共同で裁判所に契約の適合を求めることができます。合理的な期間内に合意に至らない場合、当事者の一方の請求により、裁判官が契約を改定するか、または解除することができます。この規定は2016年10月1日以降に締結された契約に適用され、当事者の合意によりその適用を排除または修正することが可能です。
日本法においても「事情変更の原則」は存在しますが、判例上その適用は極めて限定的であり、契約の拘束力(pacta sunt servanda)が強く維持される傾向にあります。これに対し、フランス法では、予見不可能な状況変化(ハードシップ)に対する契約の再交渉や裁判所による介入が明文で認められているため、契約の安定性に対する考え方が日本とは異なります。
「著しい不均衡」条項の無効
民法典第1171条は、「付合契約(contrat d’adhésion)において、交渉不能で、かつ当事者の一方によって事前に決定された条項のうち、契約当事者の権利義務に著しい不均衡を生じさせるものは、記載されなかったものとみなされる(無効となる)」と規定しています。この規定は、契約の主要目的や価格の妥当性には適用されません。この原則の適用は、一方の当事者が契約を交渉する機会がなかった「付合契約」に限定されています。
日本法では、消費者契約法に同様の不当条項規制がありますが、BtoB契約においては、原則として当事者間の合意が尊重され、このような「著しい不均衡」条項を直接無効とする明文規定は存在しません。フランス法におけるこの規定は、特にフランチャイズ契約やサプライヤー契約など、交渉力に大きな差があるBtoB取引において、優位な立場にある企業が作成した契約書の条項が、後になって無効とされるリスクを伴います。
フランスの労働法
フランスの労働法は、従業員の保護を重視する傾向が強く、雇用契約の締結から終了に至るまで、詳細かつ厳格な規制が設けられています。労働法典(Code du travail)は非常に包括的であり、個別の交渉の余地が少ない複雑な体系を有しています。
厳格な解雇規制と労働時間
フランスでは、従業員の解雇には「現実かつ重大な理由」(cause réelle et sérieuse)が必要です。個人的な理由による解雇は、この要件を満たす必要があります(Code du travail, Article L1232-1)。経済的理由による解雇の場合も、経済的困難、技術的変化、競争力維持の必要性、事業活動の停止といった具体的な理由が必要です(Code du travail, Article L1233-3)。経済的困難の判断基準として、売上や受注の減少期間が企業規模に応じて具体的に定められています。解雇手続きも厳格で、事前聴聞会、書面による解雇通知など、詳細な手順が義務付けられています。
フルタイム従業員の法定労働時間は週35時間と定められています(Code du travail, Article L3121-27)。また、週48時間、12週間の平均で週44時間、1日10時間を超えて労働させてはならないという上限規制も存在します。
合意解約(Rupture Conventionnelle)
解雇や自己都合退職とは異なる、労使双方の合意に基づく雇用契約の解除手続きとして「rupture conventionnelle」があります。これは特定の規制と条件に従って行われ、労働局の承認を必要とします。
この「rupture conventionnelle」は、紛争を避けるための有効な手段ですが、その手続きの複雑さや労働局の承認が必要な点は、日本の企業にとって新たなコンプライアンス上の課題となり得ます。
フランスのIT関連法概要
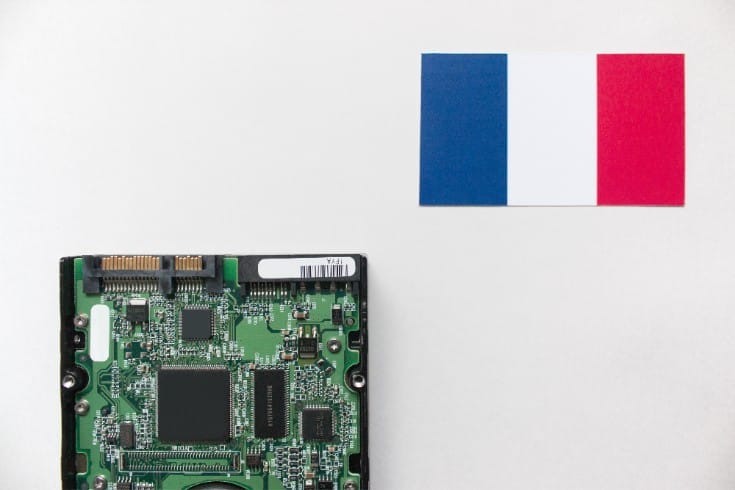
フランスのIT関連法制は、EUの指令や規則を国内法に転換する形で発展しており、デジタル経済の急速な進展に対応するための新たな規制が次々と導入されています。
電子商取引法
フランスの電子商取引は、EU法と国内法の双方によって規制されています。特に、電子商取引指令(Directive 2000/31/EC)は、フランス国内法である「デジタル経済における信頼に関する法律」(Law No. 2004-575, LCEN法)によって転換されています。
消費者保護の観点からは、消費法典(Code de la consommation)が適用され、特に通信販売における消費者の「撤回権」(droit de rétractation)が重要です。消費者は、オンライン契約締結後または商品受領後14日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます(Code de la consommation, Article L221-18)。電子商取引事業者は、企業情報、販売条件、価格、支払条件などの情報開示義務を負い、商品またはサービスは、契約締結後30日以内に遅滞なく提供されなければなりません。また、販売者は、注文から配送までの全過程における契約の適切な履行について、過失の有無にかかわらず責任を負う「当然の責任」(ipso jure liability)を負います(Code de la consommation, Article L221-15)。
EUの電子商取引指令に基づくフランスの法制度は、日本の電子商取引法と比較して、特に消費者保護が手厚いと言えます。14日間の撤回権は、日本のクーリングオフ制度よりも広範であり、返品・返金ポリシーの設計に大きな影響を与えます。また、販売者が配送チェーン全体にわたって「当然の責任」を負うことは、日本の企業がフランスでオンライン販売を行う際に、物流パートナー選定やリスク管理においてより厳格な基準を設ける必要があることを意味します。
データ保護法(個人情報保護)
フランスのデータ保護法は、1978年制定の「情報処理と自由に関する法律」(Loi Informatique et Libertés, Law No. 78-17)を中核とし、EUの一般データ保護規則(GDPR)の施行に伴い、その内容がGDPRに適合するよう大幅に改正・補完されています。
この法律は、フランス国内で個人データを処理するすべての企業や組織に適用され、フランスに拠点を置かない企業であっても、フランス市民に商品やサービスを提供する場合、またはフランス市民の個人データを処理する場合には適用されます。主要な原則として、同意(consent)、データ最小化(data minimization)、正確性(accuracy)、保存期間の制限(storage limitation)、セキュリティ(security)、透明性(transparency)、適法な処理根拠(lawful basis)、比例性(proportionality)などが挙げられます。個人データ主体には、アクセス権、訂正権、異議申立権、消去権(「忘れられる権利」)、処理制限権、データポータビリティ権、同意撤回権、死後のデータに関する指示権など、広範な権利が与えられています。データ保護に関する監督機関は、国家情報処理・自由委員会(CNIL: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)です。
日本の個人情報保護法も国際的な水準にありますが、GDPRとそれを補完するフランスのデータ保護法は、その適用範囲の広さ(域外適用)、同意の厳格性、データ主体の権利の広範さ、そして違反時の高額な制裁金において、日本の企業にとってより高いコンプライアンス水準を要求します。
サイバーセキュリティ法
フランスは、サイバー犯罪およびコンピュータ関連犯罪に関する広範な法的枠組みを採用しています。1988年の「コンピュータ詐欺に関する法律」(通称「ゴッドフラン法」)に始まり、刑法典第323-1条から323-7条に規定されているコンピュータデータおよびシステムに対する不正アクセス、データ妨害、システム妨害、デバイスの不正使用などの犯罪行為を定義しています。
「デジタル経済における信頼に関する法律」(LCEN法, Law No. 2004-575)など、多くの立法によってこの枠組みは発展してきました。刑事訴訟法も、捜索・差押え、通信傍受、データ復号化などの手続きを規定しています。情報システムのセキュリティを担当する機関は、国家情報システムセキュリティ庁(ANSSI: Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information)です。最近では、2024年5月21日の「デジタル空間の安全確保と規制を目的とする法律」(SREN法, Law No. 2024-449)により、サイバーセキュリティに関する新たな権限がANSSIに付与されています。また、EUのNIS 2指令を国内法に転換するための新たな法案も議論されています。
フランスのサイバーセキュリティ法制は、欧州の中でも特に包括的かつ先駆的であり、継続的に強化されています。
デジタルサービス法(SREN法)
2024年5月21日に公布された「デジタル空間の安全確保と規制を目的とする法律」(SREN法, Law No. 2024-449)は、フランスのデジタルサービス規制における最新の重要な動きです。この法律は、EUのデジタルサービス法(DSA)、データガバナンス法、データ法など、EUの主要なデジタル関連法規の規定にフランス法を適合させ、その国内執行を確保するためのものです。
EUのデジタルサービス法(Regulation (EU) 2022/2065)は、ソーシャルネットワーク、オンラインマーケットプレイス、アプリストアなどのオンラインプラットフォームや仲介サービスに適用されます。主な要件として、アルゴリズムの仕組みの開示、コンテンツモデレーション決定の理由説明、ターゲット広告に対する厳格な管理などが含まれます。特に、EU域内で月間4,500万人以上のユーザーを持つ「超大規模オンラインプラットフォーム」(VLOPs)には、より厳しい規則が課されます。
SREN法自体も、データ利他主義、クラウドサービスプロバイダー間の相互運用性義務、デジタルプラットフォームのサイバーセキュリティ認証、インフルエンサーの商業活動規制など、多岐にわたる側面をカバーしています。違反に対する罰金は、全世界年間売上高の最大6%に達する可能性があり、重大な違反が続く場合にはサービスの一時停止が命じられることもあります。また、オンラインでのヘイトスピーチ、ハラスメント、ディープフェイクなどに対する制裁も強化されています。
SREN法は、EUのデジタル市場戦略をフランスが積極的に国内法化する動きを象徴しており、特にオンラインプラットフォーム運営企業にとって、ビジネスモデルの根幹に関わる大きな影響を及ぼします。
まとめ
フランス市場への参入のためには、フランスの独特な法制度への適応が不可欠です。特に、大陸法系の基盤に立ちながらも、公法と私法の明確な区別、契約法における交渉段階からの信義誠実義務やハードシップ条項の明文化、労働法における厳格な解雇規制や週35時間労働制といった点は、日本法と大きく異なっています。
さらに、フランスには多くの会社形態があり、その選択も重要です。SARL、SAS、SAといった主要な法人形態から、個人事業主向けのEURLやSASUに至るまで、それぞれの形態が持つ責任範囲、ガバナンスの柔軟性、税制、社会保障制度の違いを理解した上で、最適な選択を行う必要があります。
また、電子商取引における手厚い消費者保護、GDPRを核とする厳格なデータ保護、そしてSREN法に代表されるデジタルサービスへの包括的な規制など、最近の法改正等への対応を行うことも必要となります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































