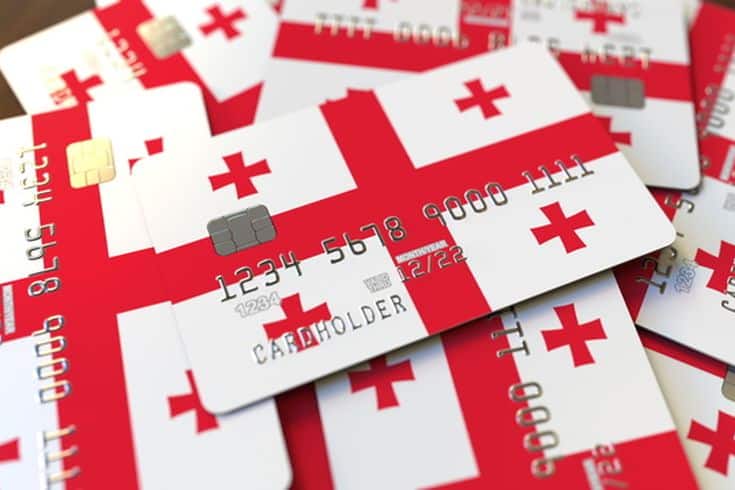ブラジルでの契約書作成時に問題となるの民法・契約法

ブラジル(正式名称、ブラジル連邦共和国)への事業展開を検討されている日本企業にとって、同国の法的環境、特に契約法への深い理解は、事業の成功を左右する重要な要素となります。
ブラジルの契約法は、民法典(Código Civil)に基づく大陸法系であり、契約の自由が原則とされつつも、信義誠実の原則や、日本法には見られない「契約の社会的機能の原則」といった独自の概念が存在します。この「契約の社会的機能の原則」は、過去に裁判所が契約に過度に介入する要因の一つと見なされてきましたが、2019年の法改正により「最小介入の原則」が明文化され、より当事者間の合意を尊重する方向へと変化しています。
特に、損害賠償においては、ブラジル法では「逸失利益」が直接的な損害の一種として扱われる傾向があり、日本法における予見可能性の原則とは異なる注意が必要です。また、ブラジルでは不可抗力に関する法典上の明文規定が存在するため、契約書においてその範囲を明確に定めることが重要となります。さらに、国際取引においては、ポルトガル語での「宣誓翻訳」が公的機関での法的手続きに不可欠であり、日本とは異なる厳格な言語要件が存在します。ブラジルは仲裁に友好的な法域であり、2015年の法改正で公共機関の仲裁利用が明確化されるなど、国際基準に準拠した紛争解決手段として広く利用されていますが、その執行には特有の厳格な手続きが求められます。
本記事では、契約の成立から紛争解決に至るまでの主要な論点を、日本法との比較を交えながら詳細に解説します。
なお、ブラジルの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ブラジル契約法の基本構造
ブラジル法は、その法体系において、フランス法やドイツ法の影響を受けた大陸法系に属し、民法典(Código Civil)は、契約の成立、有効性、履行、債務不履行などに関する包括的な原則を定めています。契約が法的に有効であるためには、ブラジル民法典第104条に基づき、当事者の行為能力、目的の適法性・可能性、そして法律で定められた形式を満たすことが必要です。
ブラジル契約法を理解する上で、まず日本法にも共通する信義誠実の原則(Princípio da Boa-fé)が重要となります。ブラジル民法典第422条は、「当事者は、契約の締結から履行に至るまで、信義誠実の原則に従って行動する義務を負う」と定めており、これは日本の民法第1条第2項の「信義則」とほぼ同様の概念です。この原則は、交渉段階から契約期間中、そして終了後までも、協力、情報提供、保護といった規範に従うことを要求するものです。
しかし、ブラジル法には、日本法とは一線を画す独自の原則が存在します。それが、ブラジル民法典第421条に規定される契約の社会的機能の原則(Função social do contrato)です。この原則は、契約が単に当事者間の自由な合意事項であるだけでなく、公序良俗の範囲を超えて、社会全体の利益に合致する必要があることを示しています。過去には、裁判所がこの原則を広範に適用し、経済変動により一方の当事者が過度な負担を負った場合に契約を修正・無効化する判例が多数見られました。これは、当事者の意思を尊重し、契約の拘束力(pacta sunt servanda)を重視する日本法とは根本的に異なるアプローチであり、ブラジルの法制度の不安定要因の一つであると指摘する研究もありました。
このような背景から、2019年の法改正(法律第13,874号)では、ブラジル民法典第421条の単独条項として「私的な契約関係においては、最小介入の原則と契約再検討の例外的原則が優先される」と明記されました。この改正は、過去の過度な司法介入に対する立法的な修正と見ることができますが、この原則自体が消滅したわけではありません。したがって、ブラジルでの事業展開を考える際には、自社のビジネスモデルや契約条件が社会的な公平性や公共の利益に照らして許容される範囲内にあるかを常に意識することが、法的安定性を確保する上で不可欠であると言えるでしょう。
ブラジルでの国際取引における契約言語と公証の重要性

ブラジルでの国際取引において、日本企業が特に注意すべき実務上の要件が、契約言語と公証手続きです。ブラジル法は、私的な契約が外国語で締結されることを原則として禁止していません。しかし、その契約がブラジル国内の裁判所や連邦・州の公的機関で証拠として提出される場合、宣誓翻訳(tradução juramentada)を添付することが法的に義務付けられています。
この宣誓翻訳は、単なる翻訳者による訳文では不十分です。ブラジルの商工会議所が実施する公的試験に合格し、登録された公認翻訳者(tradutor juramentado)による認証された翻訳文が不可欠となります。この翻訳文は、原文に含まれる印鑑、署名、その他のマークも含めて正確に記述される必要があります。
日本法では、裁判手続きにおいて外国語の文書を提出する際、通常は翻訳者を特定する必要はなく、提出者が翻訳文を添付すれば足りるとされています。これに対し、ブラジルでは、公的な資格を持つ専門家による翻訳が不可欠であり、この手続きは契約の法的有効性を担保する上で極めて重要な役割を果たします。ブラジル法が特定の形式(公証や宣誓翻訳)を契約の法的有効性に結び付けていることは、単なる言語的な問題以上の深い意味合いを持ちます。これは、ブラジルの法制度が形式主義的側面を強く持つことの表れであり、契約の信頼性を公的な手続きによって担保しようとする考えから来ていると言えるでしょう。
したがって、日本企業は、ブラジルでの契約書作成において、英語でのみ作成・署名し、そのままで十分だと考えるべきではありません。紛争が発生した場合に備え、契約書作成の段階から宣誓翻訳の必要性を視野に入れ、公証人による署名認証や領事館での認証など、ブラジル法が求める形式的な要件を確実に満たしておくことが、将来の法的手続きを円滑に進める上で不可欠なリスク管理となります。
ブラジルでの債務不履行時の損害賠償
ブラジル法における債務不履行時の損害賠償の範囲も、日本企業が注意すべき重要な論点です。ブラジル民法典第402条は、損害賠償の対象を「現実に生じた損害」(danos emergentes)と「逸失利益」(lucros cessantes)の二つのカテゴリーに分類しています。第403条は、損害賠償の対象は、債務不履行の「直接的かつ即座の結果」(por efeito dela direto e imediato)として生じた損害に限定されると定めています。
この条文の解釈から、ブラジル法では「逸失利益」が直接的な損害の一種として扱われる傾向にあります。ただし、逸失利益は推測ではなく、「客観的なデータと財務記録に基づき、具体的な証拠」をもって証明される必要があります。日本法では、通常損害と特別損害を区別し、後者の賠償には「予見可能性」という条件が付されますが、ブラジル法では、逸失利益も「直接的かつ即座の結果」であれば、通常損害と同様に扱われるという点で、賠償範囲がより広くなる可能性をはらんでいます。日本の商取引で一般的に用いられる「逸失利益や間接損害を賠償の範囲から除外する」といった条項は、ブラジル法下ではその効力が曖昧になる可能性があります。ブラジル法には「間接損害」や「結果的損害」の明確な法的定義がないため、契約書内でこれらの用語を明示的に定義し、賠償範囲を具体的に限定することが、予期せぬリスクを回避する上で極めて重要となります。
ブラジルでの不可抗力による責任免除と契約における特約
ブラジルでは、不可抗力(força maior)の概念が民法典に明文化されている点が、日本法との大きな違いです。ブラジル民法典第393条は、「債務者は、不可抗力または偶然の出来事によって生じた損害について、明示的に責任を負うことを約した場合を除き、責任を負わない」と明確に規定しています。この条文は、不可抗力や偶然の出来事を、「その効果を回避または防止することが不可能であった避けられない出来事」と定義しています。この規定が、契約に不可抗力条項が明記されていなくても適用される法定の「デフォルトルール」として機能することになるため、契約書においては、どのような事象を不可抗力と見なすか、あるいは見なさないか(例:ストライキ、公権力による処分、特定のパンデミックなど)、そして責任を負うか否かについて、詳細に記載しておいた方が望ましいと言えます。
ブラジルにおける国際紛争解決手段としての仲裁の優位性

ブラジルは、国際紛争解決手段としての仲裁に非常に友好的な法域です。ブラジル仲裁法(Lei nº 9.307/96)は、国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)のモデル法に準拠しており、国際基準に合致しています。また、2015年の改正により、公共機関も仲裁を利用できることが明文化され、ブラジルが仲裁を重視する姿勢は一層強固になりました。
さらに重要な点として、ブラジルは外国仲裁判断の承認と執行に関するニューヨーク条約を2002年に批准しており、これにより外国仲裁判断の国内での執行が法的に保障されています。ブラジル最高裁に相当するSuperior Court of Justice(STJ)は、外国仲裁判断の承認・執行について専属管轄を有し、過去の判例から見ても、その承認率は非常に高い水準にあります。
このことは、国際取引における日本の企業にとって大きな安心材料となります。しかし、その信頼性は、手続きの正確性を伴って初めて享受できるものです。STJはニューヨーク条約で定められた要件に加え、外国仲裁判断の承認を求める当事者に対し、裁定書、契約書、仲裁合意書、仲裁規則、裁定の確定証明書などの追加書類の提出を事実上求めています。これらの書類はすべて、ブラジル領事館による認証と宣誓翻訳が必要です。
このことから、ブラジルが仲裁を推進する姿勢と、国内の官僚的・形式主義的側面が共存していることがうかがえます。したがって、日本企業は、仲裁条項を盛り込む際には、単に仲裁地や仲裁機関を定めるだけでなく、将来的に外国仲裁判断をブラジルで執行する可能性を考慮し、求められるすべての書類と手続きを確実に履行しておく必要があります。これは、形式を軽視しがちな日本の実務とは異なる、ブラジルでの成功に不可欠な視点であると言えるでしょう。
まとめ
ブラジル法は、日本法と多くの共通点を持つ一方で、「契約の社会的機能の原則」や「逸失利益」の扱い、不可抗力に関する明文化された規定など、重要な点で異なる特徴を有しています。これらの違いを理解し、契約書に適切に反映させることは、ブラジルにおける事業リスクを低減する上で不可欠です。
特に、国際取引においては、ポルトガル語での宣誓翻訳や詳細な損害賠償・不可抗力条項の記載が、予期せぬリスクを回避する鍵となります。ブラジル法には「間接損害」や「結果的損害」の明確な定義がないため、契約書内でこれらの用語を明示的に定義することが、不確実性や紛争を避ける上で極めて重要です。また、ブラジルの商慣習には人間関係や信頼構築を重視する文化的な側面があり、交渉においては直接的な効率性だけでなく、より個人的なアプローチが求められることも理解しておくべきです。仲裁はブラジルにおける国際紛争解決の最も有効な手段ですが、外国仲裁判断の執行には裁定書や契約書、仲裁合意書など複数の書類が必要となり、これらの全てについて領事認証と宣誓翻訳が求められるため、形式的な要件を厳格に遵守することが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: 海外事業