イギリスの法体系であるコモン・ローの基礎

イギリスの法制度は、中世以来の判例の積み重ねによって形成された「コモン・ロー」(Common Law)をその根幹に置いています。これは、法典を主要な法源とする日本の「大陸法系」とは根本的に異なる特徴です。この違いは、単なる法文上の差異ではなく、法的思考、紛争解決の手法、そして契約実務に決定的な影響を及ぼします。この記事は、この本質的な相違点を体系的に解説し、日本企業がイギリスでのビジネス展開において直面する法的課題を乗り越えるための羅針盤となることを目指します。
本記事では、まずイギリス法の歴史的背景からその本質を紐解き、現代における主要な法源の階層と、その中核をなす判例の役割を詳述します。加えて、イギリスのEU離脱後に生じた近時の法改正動向にも触れ、ビジネス上の潜在的なリスクを指摘します。最後に、日本企業が特に留意すべき、コモン・ロー特有の契約実務上の重要ポイントと具体的な対応策について解説します。
なお、イギリスの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
イギリスのコモン・ローと大陸法の相違点
コモン・ローは、特定の法典に基づいて形成されたものではありません。その起源は1066年のノルマン征服に遡り、当時のイングランド王の裁判所が、地方ごとの慣習法を統一し、イングランド全域に共通する「common」な法として発展させてきた歴史的経緯を有しています。この歴史は、明治期にドイツやフランスの法典を継受して体系的な法制度を形成した日本とは対照的です。
日本の大陸法システムでは、民法や商法といった法典が主要な法源となり、裁判官の役割は、これらの法典を具体的な事件に当てはめて解釈し、適用することにあります。個々の裁判所の判決は、法典の解釈を示すものであり、法源そのものとは考えられていません。これに対し、コモン・ローシステムでは、個々の事件に対する裁判官の判決自体が新たな法を形成し、過去の判例(judicial precedent, case law)が将来の裁判官を拘束するという根本的な違いが存在します。
コモン・ローのこの「法典を持たない」(uncodified)という特性は、裁判官が法典を解釈するだけでなく、社会の変化や未曾有の事態に対して「法を創造する」役割を担うことを必然的に要求しました。このプロセスは、個々の事件の具体的な事実関係に即して法律を発展させるという、ボトムアップ型の法的思考を生み出したと言えます。この法的思考の根本的な違いが、ビジネス上の契約書作成時に当事者の意図を極めて詳細に記述する必要性や、判例を深く分析する重要性に直結しているのです。 このコモン・ローと日本法(大陸法)の核心的な相違点は、以下の表で整理することで、より明確に理解することができます。
| 日本法(大陸法) | イギリス法(コモン・ロー) | |
|---|---|---|
| 主要な法源 | 法典(民法、商法など)が中心 | 判例法(コモン・ロー、衡平法)が中心 |
| 判例の役割 | 法典の解釈・適用。厳格な拘束力は原則としてない。 | 判例自体が法源となり、上位裁判所の判決は下位裁判所を拘束する。 |
| 契約の成立要件 | 当事者の意思表示の合致のみで成立する。 (民法522条) | 約因(Consideration)の交換が原則として必須。 |
| 主な救済手段 | 損害賠償、特定履行など。 | 損害賠償が基本。衡平法に基づき特定履行などが認められる場合がある。 |
イギリス法源の階層と判例の役割
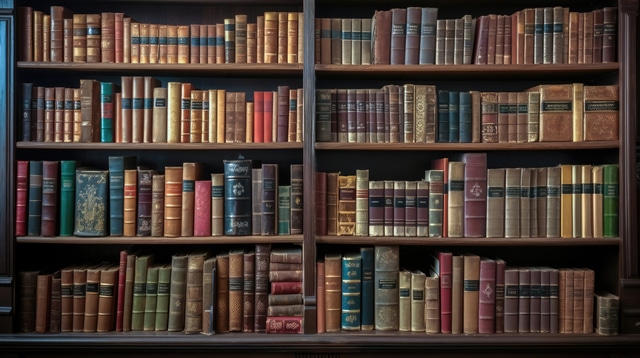
コモン・ローが歴史的基盤である一方、現代イギリス法において最も権威のある法源は、イギリス議会によって制定される「制定法」(Statutory Legislation)です。制定法はコモン・ローを修正したり、廃止したりする権限を持ち、法源の階層の最上位に位置します。この点は、日本の法体系において、法律が最高位の法源であることと共通しています。
コモン・ローの中核をなす原則は、「Stare Decisis」です。これはラテン語で「決定された事柄を支持する」を意味し、過去の判例が将来の裁判官を拘束するという先例拘束の原則を示しています。この原則により、上位裁判所の判決は下位裁判所を厳格に拘束し、法の一貫性と予測可能性を担保しています。イギリスの最高裁判所(The Supreme Court)は、2009年に設立された新しい機関ですが 、その判決はイングランドおよびウェールズのすべての下位裁判所を厳格に拘束します。
一見すると、厳格な先例拘束の原則は、コモン・ローが持つ柔軟性と矛盾するように感じられるかもしれません。しかし、イギリス法は判例の積み重ねによって法が発展する柔軟性と、厳格な「Stare Decisis」によって法の安定性を確保するという、二つの特性を両立させています。これは、裁判官が新しい事態に迅速に対応しつつ、法の予測可能性を担保するという、コモン・ローシステム独自の法的発展のメカニズムと言えます。
判例が法源となるコモン・ローシステムでは、判決の「Ratio Decidendi」(判決の論理的根拠)が真に法的拘束力を持つ要素となります。これは、日本の法体系における判例が法典の解釈に留まるのに対し、コモン・ローでは判決の論理的根拠自体が法となり、将来の裁判を拘束するという点で、判例の持つ「重み」が根本的に異なります。この違いを理解することは、イギリス法務の予見性を高める上で極めて重要です。
イギリスの制定法と判例法の相互関係
現代イギリス法において最も権威のある法源は制定法ですが、その制定プロセスは複数の段階に分かれています。制定法には、議会で審議され可決された「Acts of Parliament」(議会制定法)が含まれます。これは一次法令に分類され、社会の幅広い領域における大枠のルールを定めます。
一方で、Acts of Parliamentの下位法令として、政府大臣によって制定される「Statutory Instruments」(法定文書)があります。これらは二次法令に分類され、一次法令が定める大枠を補完し、詳細な規則や手続きを定める役割を担います。現代社会の複雑なニーズに対応するため、Statutory Instrumentsは毎年、Acts of Parliamentの2倍から5倍の量で制定されているという事実があります。
この状況は、法形成のプロセスが立法府(Parliament)から行政府(Government)へと大きくシフトしていることを示しています。これは、迅速かつ効率的に法を改正・制定する手段である一方で、十分な議会審議を経ずに重要な政策(例:税額控除の基準引き下げ)が法定されるリスクを伴う可能性を示唆しています。そのため、日本企業がイギリス法を調査する際には、ビジネスに関連する詳細な規制がStatutory Instrumentsに規定されている可能性を常に考慮する必要があるという、実務上の重要な示唆を得ることができます。
イギリスの法制度を巡る近時の動向
イギリスのEU離脱後、法制度は大きな転換期を迎えています。2018年欧州連合(離脱)法(European Union (Withdrawal) Act 2018)によって、「Retained EU Law」という概念が導入されました。これは、イギリスのEU離脱時に適用されていたEU法を、国内法として一時的に維持するための仕組みです。
その後、2023年EU法(廃止及び改革)法(Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023)により、「Retained EU Law」は「Assimilated Law」(同化法)と名称変更され、その法的性質が大きく変化しました。この法律の第7条は、イギリスの裁判所が従来のEU判例から逸脱する新たなテストを導入しており、裁判所がEU判例に拘束されず、より自由に判断を下せるようになりました。
この法律の改正は、短期間で多くの判例法が変更される事態を招き、法的安定性を損なう可能性を指摘する声も上がっています。特に雇用法や消費者保護法など、ビジネスに直結する分野において、長年確立されてきた権利が失われる可能性が懸念されています。これは、法的予測可能性を重視する日本企業にとって、法的リスクの増大を意味します。
なお、イギリスはEUを離脱した後も、欧州人権条約(European Convention on Human Rights)の締約国であり続けています。この条約はEUの枠組みとは別個の「欧州評議会」のものです。1998年人権法(Human Rights Act 1998)によって、条約で定められた人権(生存権や公正な裁判を受ける権利など)がイギリスの国内法に取り込まれており、イギリスの裁判所で人権侵害を訴えることが可能となっています。
イギリスのコモン・ローにおける契約実務の重要ポイント

コモン・ローシステムでは、法による介入が比較的少なく、当事者間の「契約自由の原則」が広範に認められています。このため、契約当事者は、その関係を律する「すべての条項」を契約書自体に詳細に記載する必要があり、結果として、イギリスの契約書は日本の契約書に比べて非常に長く、緻密になる傾向があります。
約因(Consideration)の概念
イギリス法における契約の成立には、日本法には存在しない「約因」(Consideration)の概念が不可欠です。約因とは、契約が有効に成立するために必要な「対価の交換」(quid pro quo)であり、金銭、物品、サービス、将来の約束など、何らかの価値のあるものでなければなりません。日本の民法第522条では、当事者の意思表示の合致のみで契約は有効に成立するのに対し、イギリス法では原則として約因のない無償契約(贈与など)は拘束力を持たないという、決定的な違いが存在します。このため、イギリス法準拠の契約を締結する際には、たとえ金銭のやり取りがなくても、約因が存在することを明確にする必要があります。
衡平法(Equity)と信義則
コモン・ローは歴史的に判例を重視し、厳格な法理に基づいて判断を行う傾向がありました。この硬直性を緩和し、個々の事情に応じた公平な解決を目指すために発展したのが「衡平法」(Equity)です。日本の民法第1条に規定される「信義誠実の原則」(信義則)と、衡平法の「公平性」や「柔軟な解決」を目指す姿勢には類似点があります。
しかし、両者の決定的な違いは、衡平法が具体的な救済手段を発達させた点にあります。コモン・ローが損害賠償を主な救済手段としてきたのに対し、金銭的な損害賠償だけでは不十分な場合に、裁判所が「特定履行」(Specific Performance)や「差止命令」(Injunction)といった特別な救済を命じることができるのが衡平法です。例えば、不動産のように代替不可能なものの売買契約では、損害賠償ではなく特定履行が認められるケースが多いとされています。
イギリスにおけるビジネス上のリスクと対応策
コモン・ローの特性を理解せずにイギリスでのビジネスを展開することは、予期せぬリスクを招く可能性があります。口頭での合意も有効な契約となり得ますが、その内容を証明することは極めて困難であるため、常に「書面での契約書」を使用することが最善の対策となります。また、一般的なテンプレートの利用は、個別のビジネス実態やリスクに合わせた条項が欠けているため、不十分な保護しか提供しない危険を伴います。
特に、コモン・ロー下では、契約書に責任制限条項がない場合、損害賠償額が契約の価値に縛られないため、潜在的な責任が無限に広がる可能性があります。このため、リスクを適切に管理するためには、以下の重要条項を契約書に含めることが不可欠です。
| 条項名 | 目的・機能 |
|---|---|
| 完全合意条項 (Entire Agreement Clause) | 契約書に記載された内容が当事者間の最終的かつ唯一の合意であることを確認する。これにより、過去の口頭でのやり取りや交渉過程での文書が法的拘束力を持たないことを明確にする。 |
| 責任制限条項 (Limitation of Liability) | 契約違反時の損害賠償額に上限を設けることで、潜在的に無制限な責任をコントロールし、予期せぬ巨額の賠償リスクを回避する。 |
| 不可抗力条項 (Force Majeure Clause) | 戦争、自然災害、疫病など、当事者の制御を超える事態が発生した場合に、契約上の義務を一時停止または解除できるようにする。 |
| 権利不放棄条項 (No Waiver Clause) | 契約不履行を一度見逃したとしても、その権利を将来にわたって放棄したとは解釈されないことを明確にする。これにより、一度の不履行を見逃したことで、将来の解除権などを失う事態を回避する。 |
日本企業が日本式の契約書(簡潔で、多くを法典や慣行に委ねる)をイギリスのビジネスパートナーに提示した場合、予期せぬ法的リスクに直面する可能性が極めて高いと言えます。イギリス法に特有のこれらの重要条項を盛り込むことは、単なる形式ではなく、リスク管理のための不可欠な戦略なのです。
まとめ
イギリスの法制度は、日本の法制度とは根本的に異なる思想と歴史的背景を持っています。それは、判例の積み重ねによって法が形成される「コモン・ロー」の柔軟性と、制定法が持つ明確な安定性、そして厳格な判例拘束の原則という、複数の要素が複雑に絡み合い、バランスを保つことで成り立っています。この複雑な法体系を正確に理解し、実務に反映させることが、日本企業がイギリスで円滑に事業を遂行し、法的リスクを最小限に抑えるための鍵となります。
特に、契約実務においては、日本法にない「約因」の概念を理解すること、そして口頭合意の危険性を認識し、コモン・ローの原則を前提とした緻密な契約書を作成することが極めて重要です。こうした契約書には、責任の範囲を明確にし、紛争を未然に防ぐための様々な条項を盛り込む必要があります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































