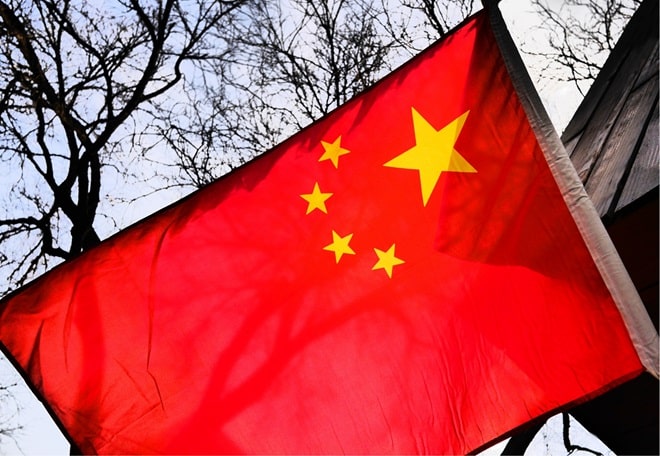ロシア連邦の労働法の解説

ロシアの労働法は、ロシア連邦労働法典(Трудовой кодекс Российской Федерации)によって包括的に規制されており、労働者の権利保護に極めて重点を置いた厳格な運用がなされます。
本記事では、雇用契約、労働時間、解雇といった主要なテーマに関して、有期雇用契約の厳格性、解雇の極めて高いハードル、そして最新の法改正がもたらす新たなリスクなどに焦点を当てて解説します。
なお、ロシア連邦の包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ロシアにおける雇用契約

ロシアにおける雇用関係は、ロシア連邦労働法典によって包括的に規制されています。最も重要な原則は、雇用契約は原則として無期雇用契約(бессрочный трудовой договор)であり、有期雇用契約(срочный трудовой договор)は特定の例外的な状況下でのみ許可されるという点です。これは、労働者にとって長期的な雇用の安定を法的に強く保障するものです。
有期雇用契約は、ロシア連邦労働法典第59条に列挙された、一時的な性質を持つ業務や特定の状況下でのみ締結が可能です。具体的な例としては、季節労働、最長2ヶ月の短期業務、病気による一時的な欠員補充などが挙げられます。有期雇用契約の期間は最長5年と定められていますが、この契約形態の利用は非常に限定的です。
日本の労働契約法では、有期雇用契約の締結が比較的広範囲に認められ、契約の反復更新も一般的な商慣行となっています。この点において、ロシア法との間には決定的な違いがあります。ロシア法では、雇用主が有期雇用契約を締結する際に、その法的根拠が労働法典に準拠していることを証明する責任を負うことになります。もし不適切な理由で締結されたと判断された場合、その契約は、無期雇用契約へと自動的に転換されるリスクが生じます。これは、事業の不確実性を考慮して安易に有期雇用契約を利用する日本企業にとって、予期せぬ法的・経済的負担を招く結果につながりかねません。無期雇用への転換は、将来的な解雇の困難性を高めるだけでなく、過去に遡って社会保険料の支払いを命じられる可能性も否定できません。
ロシアにおける試用期間と解雇手続き
雇用契約には、試用期間を設けることが可能ですが、これも法律によって厳格に規制されています。試用期間は通常3ヶ月以内と定められていますが、組織のトップマネージャーやチーフアカウンタントなど、特定の役職では6ヶ月まで延長が認められています。特筆すべきは、18歳未満の者や18ヶ月未満の子供を持つ女性など、試用期間を設定することができない特定のカテゴリーの従業員が存在する点です。これは日本法にはない、より強固な労働者保護の姿勢を示すものです。
試用期間中に従業員が不合格と判断された場合、雇用主は3日前の書面による通知で契約を解除できます。しかし、この通知には「不合格の理由」を具体的に明記しなければなりません。従業員は、この解雇が不当であるとして裁判所に異議を申し立てる権利を有しており、雇用主にはその理由の正当性を証明する責任が課されます。
ロシアにおける労働時間と休暇
ロシアの労働法は、労働者の健康と休息を保護するため、労働時間と休暇について非常に明確な規定を設けています。通常の労働時間は週40時間を超えてはならないと定められており、16歳未満は週24時間、16歳から18歳は週35時間など、特定の年齢層や属性に応じてより短い労働時間が義務付けられています。
時間外労働は原則として従業員の書面による同意が必要であり、年間120時間という厳格な上限が設定されています。これは、日本の法律よりも厳格な上限といえます。時間外労働、夜間労働、休日労働には割増賃金が適用され、特に時間外労働の場合、最初の2時間は150%、それ以降は200%以上の割増賃金が義務付けられています。年次有給休暇は最低28暦日と定められており、平均賃金が支払われます。これは、日本の法定年次有給休暇日数(勤続年数に応じて最大20日)と比較して、かなり多い日数となります。
| 項目 | ロシア労働法 | 日本労働法 |
| 雇用契約の原則 | 無期雇用 | 無期雇用・有期雇用 |
| 有期雇用契約 | 限定的(法典第59条に列挙) | 比較的広範囲 |
| 試用期間 | 通常3ヶ月(管理職6ヶ月) | 上限なし(就業規則による) |
| 年間時間外労働上限 | 120時間 | 360時間(特別条項によるものは720時間) |
| 時間外労働の割増賃金 | 最初の2時間150%、以降200% | 25%以上 |
| 最低年次有給休暇 | 28暦日 | 勤続年数に応じて最低10日 |
| 解雇の正当性要件 | 正当な理由必須(列挙主義的) | 解雇権濫用防止の法理(総合判断) |
ロシアにおける解雇

ロシア労働法典は、雇用契約の解除に「正当な理由(just cause)」を要求し、法律に明記された理由以外での解雇を認めません。この原則は、雇用主による恣意的な解雇を厳しく制限するものです。正当な理由の具体例としては、会社の清算、人員削減、従業員の規律違反、能力不足などが挙げられますが、これらの解雇事由は、それぞれ法律が定める煩雑な手続きを厳格に経なければなりません。
特に、能力不足を理由とする解雇は極めて困難です。提供された情報によると、ロシア法は従業員の「負の業務結果(poor performance)」を理由とする解雇を明示的に規定していません。したがって、単に「能力が低い」という理由で解雇することは極めて困難であり、企業にとっては「法律的な特殊作戦」とまで表現されるほど高いハードルとなります。これに対し、日本では人事評価制度に基づき、能力不足解雇が法的要件を満たせば認められる場合があります。この違いは、ロシアでは従業員のパフォーマンス改善を促すための厳格なプロセスや、能力を証明するための評価プロセスを事前に構築しておかなければ、解雇が事実上不可能であることを示唆します。日本企業は、採用段階から厳格な評価を行い、パフォーマンス管理計画(PIP)などを導入し、常に文書化を徹底するリスク管理が必須となります。
人員削減(downsizing)の場合でも、雇用主は解雇対象者を選定する「法的選定順序(statutory selection order)」に従う必要があります。雇用主は、生産性や資格がより高い従業員を優先的に保護しなければなりません。さらに、解雇対象者には、社内の代替職を提示する義務があり、また、2ヶ月前の書面による事前通知が義務付けられています。
近時のロシア労働法改正
ロシアの労働法は、国内および国際情勢の変化に迅速に対応し、常に改正が重ねられています。日本企業は、これらの最新動向を把握することが、予期せぬリスクを回避する上で不可欠です。
近年、ロシア政府は、企業が社会保障義務を回避するために、雇用関係を「独立請負人」や「業務委託」として偽装する慣行を強く問題視しています。これを防ぐため、明確な判断基準(個人で業務を行う、企業のコア業務である、雇用主が職場や備品を提供する等)を労働法典に明文化する法案が提案されています。この法案が施行されれば、日本の企業が慣行として利用する安易な業務委託契約が、後に雇用関係と再分類され、多額の税金や社会保険料の追徴金を支払うリスクが大幅に高まります。連邦労働監督庁(Rostrud)には、雇用契約への再分類を求めて訴訟を起こす権限が与えられることになります。
また、2022年9月以降、部分的軍事動員を受けて、動員された従業員の雇用契約を解除せず「停止」させる特別措置が導入されました。雇用主は、動員された従業員の雇用を維持する義務があり、その間、代替人員を期限付きで雇用することが可能です。動員された従業員が元の職場に復帰する権利も保障されており、雇用主が動員を理由に契約を終了させることは認められていません。
まとめ
本稿で解説したように、ロシアの労働法は、労働者保護を目的とした厳格な規制を多数含んでおり、日本の事業者は、安易な有期雇用契約の利用、日本の慣行に倣った長時間労働の強要、そして安易な解雇といった行為が、重大な法的リスクを招くことを認識しなければなりません。特に、解雇手続きの煩雑さや、業務委託契約が雇用関係と再分類されるリスクは、日本企業が事業計画を立てる上で最も注意すべき点です。これらのリスクは、単なる罰金に留まらず、従業員との紛争や企業の評判低下にもつながる可能性があります。
関連取扱分野:国際法務・ロシア連邦
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務