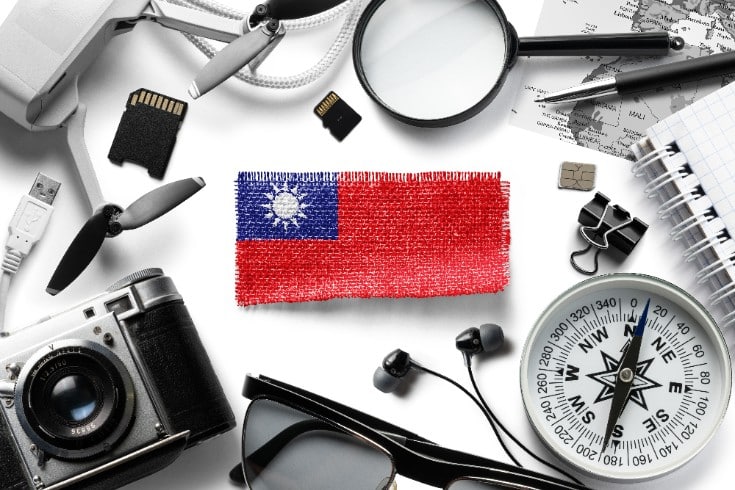„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģś≥ēŚĺč„ĀģŚÖ®šĹďŚÉŹ„Ā®„ĀĚ„Āģś¶āŤ¶Ā„ā팾ĀŤ≠∑Ś£ę„ĀĆŤß£Ť™¨

„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģÁĶĆśłą„Ā®„ā§„Éé„Éô„Éľ„ā∑„Éß„É≥„Āģśé®ťÄ≤Śäõ„ÄĀÁČĻ„ĀęITŚąÜťáé„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚÖąťÄ≤śÄß„Āč„āČ„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„Āģśó•śú¨šľĀś•≠„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶ť≠ÖŚäõÁöĄ„Ā™„Éď„āł„Éć„āĻŚĪēťĖčŚÖą„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀĆśé°ÁĒ®„Āô„ā茧ߝôłś≥ēÁ≥Ľ„Ā®„ĀĮś†Ļśú¨ÁöĄ„ĀęÁēį„Ā™„āč„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„ÉľÔľąŚą§šĺčś≥ēԾȄāíŚüļÁõ§„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™ś≥ēŚą∂Śļ¶„Ā®„ĀĚ„Āģś¶āŤ¶Ā„āí„ÄĀÁČĻ„ĀęITŚąÜťáé„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„āčś≥ēŤ¶ŹŚą∂„ĀęÁĄ¶ÁāĻ„āíŚĹď„Ā¶„Ā§„Ā§„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®„Āģťá捶Ā„Ā™ÁõłťĀēÁāĻ„Āę„āāŤß¶„āĆ„Ā™„ĀĆ„āČŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„ÄāšľöÁ§ĺŤ®≠Áęč„Āč„āČŚ•ĎÁīĄ„ÄĀťõáÁĒ®„ÄĀÁü•ÁöĄŤ≤°ÁĒ£„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑„āĄ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüITťĖĘťÄ£„ĀģŤ¶ŹŚą∂„ĀęŤá≥„āč„Āĺ„Āß„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„Āß„Āģ„Éď„āł„Éć„āĻŚĪēťĖč„ā휧úŤ®é„Āô„āčťöõ„ĀęŚēŹť°Ć„Ā®„Ā™„āčś≥ēŚĺč„āíÁ∂≤ÁĺÖÁöĄ„ĀęÁīĻšĽč„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„ā§„āģ„É™„āĻś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀģŚüļÁ§é
„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„ÄĀÁČĻ„Āę„ā§„É≥„āį„É©„É≥„ÉČŚŹä„Ā≥„ā¶„āß„Éľ„Éę„āļ„Āģ„ĀĚ„āĆ„ĀĮ„ÄĀšł≠šłĖšĽ•śĚ•„ĀģŚą§šĺč„ĀģÁ©ć„ĀŅťáć„Ā≠„Āę„āą„Ā£„Ā¶ŚĹĘśąź„Āē„āĆ„Āü„ÄĆ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„ÄćÔľąCommon LawԾȄāí„ĀĚ„Āģś†ĻŚĻĻ„ĀęÁĹģ„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀś≥ēŚÖł„āíšłĽŤ¶Ā„Ā™ś≥ēśļź„Ā®„Āô„āčśó•śú¨„Āģ„ÄĆŚ§ßťôłś≥ēÁ≥Ľ„Äć„Ā®„ĀĮś†Ļśú¨ÁöĄ„ĀęÁēį„Ā™„āčÁČĻŚĺī„Āß„Āô„Äā„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŤ£ĀŚą§Śģė„ĀģŚą§śĪļ„ĀĆśĖį„Āü„Ā™ś≥ē„āíŚĹĘśąź„Āó„ÄĀťĀéŚéĽ„ĀģŚą§šĺč„ĀĆŚįܜ̕„ĀģŤ£ĀŚą§Śģė„āíśčėśĚü„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĆStare Decisis„ÄćÔľąŚÖąšĺčśčėśĚü„ĀģŚéüŚČáԾȄĀĆś•Ķ„āĀ„Ā¶ťá捶Ā„Ā™ŚĹĻŚČ≤„āíśěú„Āü„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚéüŚČá„Āę„āą„āä„ÄĀšłäšĹćŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§śĪļ„ĀĮšłčšĹćŤ£ĀŚą§śČÄ„āíŚé≥ś†ľ„ĀęśčėśĚü„Āó„ÄĀś≥ē„ĀģšłÄŤ≤ęśÄß„Ā®šļąśł¨ŚŹĮŤÉĹśÄß„āíśčÖšŅĚ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨„ĀĮś≥ēŚÖł„ĀĆšł≠ŚŅÉ„Āß„Āā„āä„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§śĪļ„ĀĮšłĽ„Āęś≥ēŚÖł„āíŤß£ťáą„Āô„āč„āā„Āģ„Ā®ŤÄÉ„Āą„ā茧ߝôłś≥ē„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀęŚĪě„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āß„ĀĮ„ÄĀťĀéŚéĽ„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄŚą§śĪļŤá™šĹď„ĀĆś≥ēśļź„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚįܜ̕„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄ„āíśčėśĚü„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„Āß„ÄĀś≥ēÁöĄśÄĚŤÄÉ„Āģś†Ļśú¨ÁöĄ„Ā™ťĀē„ĀĄ„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āô„Äā
šłÄśĖĻ„Āß„ÄĀÁŹĺšĽ£„Āģ„ā§„āģ„É™„āĻś≥ē„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶śúÄ„āāś®©Ś®Ā„Āģ„Āā„āčś≥ēśļź„ĀĮ„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻŤ≠įšľö„Āę„āą„Ā£„Ā¶Śą∂Śģö„Āē„āĆ„āč„ÄĆŚą∂Śģöś≥ē„ÄćÔľąStatutory LegislationԾȄĀß„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„ĀĮ„ÄĀŤ≠įšľö„ĀߌĮ©Ť≠į„Āē„āĆŚŹĮśĪļ„Āē„āĆ„Āü„ÄĆActs of Parliament„ÄćÔľąŤ≠įšľöŚą∂Śģöś≥ēԾȄāĄ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģšłčšĹćś≥ēšĽ§„Ā®„Āó„Ā¶śĒŅŚļúŚ§ßŤá£„Āę„āą„Ā£„Ā¶Śą∂Śģö„Āē„āĆ„āč„ÄĆStatutory Instruments„ÄćÔľąś≥ēŚģöśĖáśõłÔľČ„Ā™„Ā©„ĀĆŚźę„Āĺ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚą∂Śģöś≥ē„ĀĮ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„āíšŅģś≠£„Āó„Āü„āä„ÄĀŚĽÉś≠Ę„Āó„Āü„āä„Āô„āčś®©ťôź„āíśĆĀ„Ā°„Āĺ„Āô„Äā„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģś≥ēśļź„ĀģťöéŚĪ§„ĀĮ„ÄĀŚą∂Śģöś≥ēÔľąšłÄś¨°ŚŹä„Ā≥šļĆś¨°ÔľČ„ÄĀ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„ÉľŚŹä„Ā≥Ť°°ŚĻ≥ś≥ēÔľąŚą§šĺčś≥ēԾȄÄĀŤ≠įšľöśÖ£ÁŅí„ÄĀšłÄŤą¨śÖ£ÁŅí„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ś®©Ś®Ā„Āā„āčśõłÁĪć„Āģť†Ü„Āßśßčśąź„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀĆś¨ßŚ∑ěťÄ£Śźą„āíťõĘŤĄĪ„Āó„ĀüŚĺĆ„āā„ÄĀ„ÄĆAssimilated Law„ÄćÔľąŚźĆŚĆĖś≥ē„ÄĀśóßRetained European Union LawԾȄĀ®„Āó„Ā¶šłÄťÉ®„ĀģEUś≥ē„ĀĆŚõĹŚÜÖś≥ē„Ā®„Āó„Ā¶Á∂≠śĆĀ„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ÄĆEuropean Convention on Human Rights„ÄćÔľąś¨ßŚ∑ěšļļś®©śĚ°ÁīĄÔľČ„ĀĆšļļś®©ś≥ē„Ā®„Āó„Ā¶ŚõĹŚÜÖś≥ē„ĀęÁĶĄ„ĀŅŤĺľ„Āĺ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„Āģ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀĮ„ÄĀťĀ©ŚŅúśÄß„Ā®śüĒŤĽüśÄß„Āꌥ™„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®Ť®Ä„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšłäšĹćŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆ„ÄĀÁ§ĺšľö„ĀģŚ§ČŚĆĖ„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ÄĀÁęčś≥ēŚļú„ĀģšĽčŚÖ•„āíŚĺÖ„Āü„Āö„ĀęťĀéŚéĽ„ĀģŚą§śĪļ„ā퍶܄Āô„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Āč„āČ„Āß„Āô„ÄāŚ§ßťôłś≥ē„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀģŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀšłĽ„ĀęÁęčś≥ē„Āę„āą„āčśĒĻś≠£„āíťÄö„Āė„Ā¶ś≥ē„ĀĆŚ§ČŚĆĖ„Āô„āč„Āģ„āíŚĺÖ„Āü„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāŚ§ßťôłś≥ē„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀŚą§šĺč„āíťÄö„Āė„Āüś≥ēŤß£ťáą„ĀģŚ§ČśõīÁ≠Č„ĀĮ„Āā
„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹§šĺč„ĀģśčėśĚüŚäõ„ĀĮ„ÄĀŤ£ĀŚą§Śģė„Āę„āą„āčÁõīśé•ÁöĄ„Ā™ś≥ēŚĹĘśąź„ĀģŚĹĻŚČ≤„ā퍙ć„āĀ„āč„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā
„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„ĀģśüĒŤĽüśÄß„Ā®ťĀ©ŚŅúśÄß„ĀĮ„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆšļąśúü„Āõ„Ā¨Áä∂ś≥Ā„ĀęŚĮĺŚá¶„Āß„Āć„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚą©ÁāĻ„ĀĆ„Āā„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀśėéÁĘļ„Ā™śĆáťáĚ„ĀģšłćŤ∂≥„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ™≤ť°Ć„āāšľī„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀŚ•ĎÁīĄśõłšĹúśąź„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģśĄŹŚõ≥„āíśėéÁĘļ„Āę„Āó„ÄĀ„É™„āĻ„āĮ„āíťĀ©Śąá„ĀęťÖ挹܄Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ÄĀŚą§šĺč„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„ĀüśĚ°ť†Ö„ĀģŤß£ťáą„āíšļąśł¨„Āó„ÄĀś•Ķ„āĀ„Ā¶ś≠£ÁĘļ„Ā™Ť®ėŤŅį„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄŚą∂Śļ¶„Āģś¶āŤ¶Ā
šłĽŤ¶Ā„Ā™śįĎšļčŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģťöéŚĪ§„ĀĮšĽ•šłč„ĀģťÄö„āä„Āß„Āô„Äā
„āę„ā¶„É≥„ÉÜ„ā£„ÉĽ„ā≥„Éľ„ÉąÔľąCounty CourtԾȄĀĮ„ÄĀśįĎšļčšļ蚼∂„ĀģŚ§ßťÉ®ŚąÜ„āíŚá¶ÁźÜ„Āô„āčÁ¨¨šłÄŚĮ©Ť£ĀŚą§śČÄ„Āß„Āô„ÄāŚįĎť°ćŤ®īŤ®üÔľąSmall Claims Track„ÄĀťÄöŚłł1šłá„ÉĚ„É≥„ÉČšĽ•šłč„ĀģŤęčśĪāԾȄÄĀÁį°śėīŤ®üÔľąFast Track„ÄĀ1šłá„ÉĚ„É≥„ÉČŤ∂Ö2.5šłá„ÉĚ„É≥„ÉČšĽ•šłč„ĀģŤęčśĪāԾȄÄĀšł≠ťĖīŤ®üÔľąIntermediate Track„ÄĀ2.5šłá„ÉĚ„É≥„ÉČŤ∂Ö10šłá„ÉĚ„É≥„ÉČšĽ•šłč„ĀģŤęčśĪāԾȄÄĀ„Āä„āą„Ā≥„āą„ā䍧áťõĎ„Ā™Ś§öť°ćŤ®īŤ®üÔľąMulti-track„ÄĀ10šłá„ÉĚ„É≥„ÉČŤ∂Ö„ĀģŤęčśĪāԾȄĀ™„Ā©„ÄĀŤęčśĪāť°ć„Ā®Ť§áťõĎśÄß„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶śßė„ÄÖ„Ā™Á®ģť°ě„Āģšļ蚼∂„āíśČĪ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ťęėÁ≠Čś≥ēťôĘÔľąHigh CourtԾȄĀĮ„ÄĀ„āą„ā䍧áťõĎ„Āßťęėť°ć„Ā™śįĎšļčšļ蚼∂„āíśČĪ„ĀÜŤ£ĀŚą§śČÄ„Āß„Āô„ÄāšłĽ„Āꌧߜ≥ēŚģėťÉ®ÔľąChancery DivisionԾȄÄĀÁéčŚļߝɮԾąKing‚Äôs Bench DivisionԾȄÄĀŚģ∂šļčťÉ®ÔľąFamily DivisionԾȄĀģ3„Ā§„ĀģťÉ®ťĖÄ„Āꌹ܄Āč„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚ§ßś≥ēŚģėťÉ®„ĀĮťĀļÁĒ£„ÄĀÁ†īÁĒ£„ÄĀŤĎóšĹúś®©„ÄĀŚúüŚúį„ĀģŚ£≤Ť≤∑„ÄĀśäĶŚĹďś®©„ÄĀÁČĻŤ®Ī„ÄĀŚēÜś®ô„Ā™„Ā©„ĀęťĖĘ„Āô„āčšļ蚼∂„āíśČĪ„ĀĄ„ÄĀÁéčŚļߝɮ„ĀĮšļļŤļę„ĀģŤá™ÁĒĪ„ĀģšĺĶŚģ≥Ôľąhabeas corpusԾȄÄĀŚŹłś≥ēŚĮ©śüĽ„ÄĀšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā™Ś•ĎÁīĄÁīõšļČ„Ā™„Ā©ŚĻÖŚļÉ„ĀĄśįĎšļčÁīõšļČ„āíśČĪ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāťęėť°ć„Ā™Ść†śúČŤęčśĪā„āĄšļļŤļęŚā∑Śģ≥ŤęčśĪā„Ā™„Ā©„ÄĀ„āę„ā¶„É≥„ÉÜ„ā£„ÉĽ„ā≥„Éľ„Éą„Āß„ĀĮśČĪ„Āą„Ā™„ĀĄšļ蚼∂„āāśčÖŚĹď„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŚģ∂šļčťÉ®„ĀĮśú™śąźŚĻīŚĺĆŤ¶č„ÄĀť§äŚ≠źÁłĀÁĶĄ„ÄĀŚ©öŚßĽťĖĘšŅā„ĀģŤ®īŤ®ü„Ā™„Ā©„āíśČĪ„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāťęėÁ≠Čś≥ēťôĘ„ĀĆŚ§ßś≥ēŚģėťÉ®„ÄĀÁéčŚļߝɮ„ÄĀŚģ∂šļčťÉ®„Āꌹ܄Āč„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚįāťĖÄśÄß„ĀģŚļ¶Śźą„ĀĄ„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
śéߍ®īťôĘÔľąCourt of AppealԾȄĀĮ„ÄĀ„āę„ā¶„É≥„ÉÜ„ā£„ÉĽ„ā≥„Éľ„Éą„Āĺ„Āü„ĀĮťęėÁ≠Čś≥ēťôĘ„ĀģŚą§śĪļ„ĀęŚĮĺ„Āô„āčśéߍ®ī„āíŚĮ©ÁźÜ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāťÄöŚłł3Śźć„ĀģŤ£ĀŚą§Śģė„Āę„āą„Ā£„Ā¶ŚĮ©ÁźÜ„Āē„āĆ„ÄĀ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©„Āģśéߍ®ī„Āę„ĀĮŤ®ĪŚŹĮ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā
śúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄÔľąSupreme CourtԾȄĀĮ„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģśúÄÁĶāŚĮ©Ť£ĀŚą§śČÄ„Āß„Āā„āä„ÄĀśįĎšļč„ÉĽŚąĎšļčšļ蚼∂„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĆś≥ēÁöĄ„Ā™ŤęĖÁāĻ„ÄćÔľąPoints of LawԾȄĀęťĖĘ„Āô„āčśéߍ®ī„āíŚĮ©ÁźÜ„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚÖ¨ŚÖĪ„Āģťá捶ĀśÄß„āíśĆĀ„Ā§ś≥ēÁöĄŚēŹť°Ć„ĀęÁĄ¶ÁāĻ„āíŚĹď„Ā¶„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻŚÖ®šĹď„Āģś≥ē„āíÁĶĪšłÄ„Āô„āčŚĹĻŚČ≤„āíśčÖ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā2009ŚĻī„Āę„ÉŹ„ā¶„āĻ„ÉĽ„ā™„ÉĖ„ÉĽ„É≠„Éľ„āļÔľąHouse of LordsԾȄĀꚼ£„āŹ„Ā£„Ā¶Ť®≠ÁĹģ„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀŚąĎšļčšļ蚼∂„āíšłĽ„ĀęśČĪ„ĀÜś≤ĽŚģČŚą§šļčŤ£ĀŚą§śČÄÔľąMagistrates‚Äô CourtsԾȄāā„ÄĀšłÄťÉ®„ĀģŚģ∂šļčšļ蚼∂„āĄŚúįśĖĻÁ®é„ĀģśĽěÁīć„Ā™„Ā©„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģśįĎšļčšļ蚼∂„āíśČĪ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„āĻ„ā≥„ÉÉ„Éą„É©„É≥„ÉČ„Ā®ŚĆó„āĘ„ā§„Éę„É©„É≥„ÉČ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„ā§„É≥„āį„É©„É≥„ÉČŚŹä„Ā≥„ā¶„āß„Éľ„Éę„āļ„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āčÁ訍ᙄĀģŤ£ĀŚą§śČÄŚą∂Śļ¶„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„ā§„āģ„É™„āĻšľöÁ§ĺś≥ē

„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģšľöÁ§ĺś≥ē„ĀĮ„ÄĀšłĽ„Āę„ÄĆCompanies Act 2006„ÄćÔľąšľöÁ§ĺś≥ē2006ŚĻīԾȄĀę„āą„Ā£„Ā¶ŚĆÖśč¨ÁöĄ„ĀꍶŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģś≥ēŚĺč„ĀĮ„ÄĀŚĺďśĚ•„ĀģšľöÁ§ĺś≥ē1985ŚĻī„ā팧ߌĻÖ„Āꌹ∑śĖį„Āô„āčŚĹĘ„Āߌą∂Śģö„Āē„āĆ„Āü„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā
šľöÁ§ĺŤ®≠Áęč„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšľöÁ§ĺś≥ē2006ŚĻī„Āę„āą„āäśČčÁ∂ö„Āć„ĀĆÁŹĺšĽ£ŚĆĖ„Āē„āĆ„ÄĀ„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éć„ÉÉ„ÉąÁĶĆÁĒĪ„Āß„ĀģŤ®≠Áęč„āāŚģĻśėď„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀšłÄšļļ„Āߌ֨ťĖčšľöÁ§ĺ„ā퍮≠Áęč„Āô„āč„Āď„Ā®„āāŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāšľöÁ§ĺ„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™śÜ≤ÁꆜĖáśõł„ĀĮ„ÄĆŚģöś¨ĺ„ÄćÔľąarticles of associationԾȄĀ®„Ā™„āä„ÄĀśĖįŤ®≠šľöÁ§ĺ„ĀģŚ†īŚźą„ÄĆŤ¶öśõł„ÄćÔľąmemorandumԾȄĀĮŚģöś¨ĺ„Ā®„Āó„Ā¶śČĪ„āŹ„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„ÄāšľöÁ§ĺ„ĀģŤ°ĆÁāļŤÉĹŚäõ„ĀĮ„ÄĀŚģöś¨ĺ„ĀęśėéÁ§ļÁöĄ„Ā™Śą∂ťôź„ĀĆ„Ā™„ĀĄťôź„āä„ÄĀÁĄ°Śą∂ťôź„Ā®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
ŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„ĀģÁĺ©Śčô„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀšľöÁ§ĺś≥ē2006ŚĻī„ĀĮ„ÄĀŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„Āä„āą„Ā≥Ť°°ŚĻ≥ś≥ēšłä„ĀģÁĺ©Śčô„āíśąźśĖáŚĆĖ„Āó„ÄĀšĽ•šłč„Āģ7„Ā§„Āģś≥ēŚģöÁĺ©Śčô„ā퍙≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨šłÄ„Āę„ÄĀś®©ťôźŚÜÖ„Āß„ĀģŤ°ĆŚčēÔľąs.171ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀŚģöś¨ĺ„āĄś†™šłĽ„ĀģśĪļŚģö„ĀęŚĺď„ĀÜÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨šļĆ„Āę„ÄĀšľöÁ§ĺ„ĀģśąźŚäü„ĀģšŅÉťÄ≤Ôľąs.172ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀś†™šłĽŚÖ®šĹď„ĀģŚą©Áõä„Āģ„Āü„āĀ„Āꍰƌčē„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆŤ™≤„Āõ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„ĀĮ„ÄĀťē∑śúüÁöĄ„Ā™ÁĶźśěú„ÄĀŚĺďś•≠Śď°„ĀģŚą©Áõä„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ɧ„Éľ„āĄť°ßŚģĘ„Ā®„ĀģťĖĘšŅā„ÄĀ„ā≥„Éü„É•„Éč„ÉÜ„ā£„āĄÁíįŚĘÉ„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„ÄĀťęė„ĀĄ„Éď„āł„Éć„āĻŤ°ĆŚčēŚüļśļĖ„ĀģÁ∂≠śĆĀ„ÄĀś†™šłĽťĖď„ĀģŚÖ¨ŚĻ≥śÄß„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüťĚěÁ∂≤ÁĺÖÁöĄ„Ā™Ť¶ĀÁī†„āíŤÄÉśÖģ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚźę„Āĺ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨šłČ„Āę„ÄĀÁč¨Áęč„Āó„ĀüŚą§śĖ≠„ĀģŤ°ĆšĹŅÔľąs.173ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀŤ£ĀťáŹ„ā팹∂ťôź„Āó„Ā™„ĀĄÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨Śõõ„Āę„ÄĀŚźąÁźÜÁöĄ„Ā™ś≥®śĄŹ„ÄĀśäÄŤÉĹ„ÄĀŚč§ŚčČ„Āē„ĀģŤ°ĆšĹŅÔľąs.174ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā™ŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„ĀĆŚźąÁźÜÁöĄ„ĀęśúüŚĺÖ„Āē„āĆ„āčÁü•Ť≠ė„ÄĀśäÄŤÉĹ„ÄĀÁĶĆť®ď„ĀģŚüļśļĖÔľąŚģĘŤ¶≥ÁöĄ„ÉÜ„āĻ„ɹԾȄĀ®„ÄĀŚĹ≤ŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„ĀģŚģüťöõ„ĀģÁü•Ť≠ė„ÄĀśäÄŤÉĹ„ÄĀÁĶĆť®ďÔľąšłĽŤ¶≥ÁöĄ„ÉÜ„āĻ„ɹԾȄĀģšł°śĖĻ„āíśļÄ„Āü„ĀôŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨šļĒ„Āę„ÄĀŚą©ÁõäÁõłŚŹć„ĀģŚõěťĀŅÔľąs.175ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀŚą©ÁõäÁõłŚŹć„āíťĀŅ„ĀĎ„āčÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀŚŹĖÁ∑†ŚĹĻšľö„Āĺ„Āü„ĀĮś†™šłĽ„ĀģśČŅŤ™ć„Āę„āą„ā茹©ÁõäÁõłŚŹć„ĀģŤ®ĪŚŹĮśĖĻś≥ē„ĀĆŚįéŚÖ•„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨ŚÖ≠„Āę„ÄĀÁ¨¨šłČŤÄÖ„Āč„āČ„ĀģŚą©Áõä„ĀģŚŹóť†ėÁ¶Āś≠ĘÔľąs.176ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀŚą©ÁõäÁõłŚŹć„āíÁĒü„Āė„Āē„Āõ„Ā™„ĀĄ„Ā®ŚźąÁźÜÁöĄ„Āꍶč„Ā™„Āē„āĆ„ā荼Ōĺģ„Ā™ŤīąÁ≠ĒŚďĀ„ĀĮŚŹóť†ėŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀśĖ፥ą„Āߍ©ēšĺ°„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨šłÉ„Āę„ÄĀšľöÁ§ĺ„Ā®„ĀģŚŹĖŚľē„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹©Śģ≥ťĖĘšŅā„ĀģÁĒ≥ŚĎäÔľąs.177ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀśŹźś°ą„Āē„āĆ„ĀüŚŹĖŚľē„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹©Śģ≥ťĖĘšŅā„āíÁĒ≥ŚĎä„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
šľöÁ§ĺś≥ē2006ŚĻī„ĀĮ„ÄĀśąźśĖáś≥ē„ĀģŚźĄŚõĹŚģ∂„Ā®ŚźĆśßė„Āę„ÄĀŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„ĀģÁĺ©Śčô„āíśąźśĖáŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„āā„Ā£„Ā®„āā„ÄĀšľöÁ§ĺś≥ē2006ŚĻī„ĀģšłÄŤą¨Áĺ©Śčô„ĀĮ„ÄĀŚą§šĺčś≥ēšłä„ĀģŚŹóŤ®óŤÄÖÁĺ©Śčô„āíśąźśĖáŚĆĖ„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Āā„āäÔľąs.170(3)(4)ԾȄÄĀŚ≠¶Ť™¨šłä„ĀĮ„ÄĆÁĺ©Śčô„ĀģŚÜÖŚģĻ„ĀĮŚģĆŚÖ®„ĀęÁ∂≤ÁĺÖ„Āē„āĆ„Āü„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚĺďŚČć„Āģ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„āĄŤ°°ŚĻ≥ś≥ēšłä„ĀģŚéüŚČá„ĀĆŚľē„ĀćÁ∂ö„Āćťá捶Ā„Ā™śĄŹŚĎ≥„āíśĆĀ„Ā§„Äć„Ā®Ťß£„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ā§„āģ„É™„āĻ„Āß„ĀĮ„ÄĀś≥ēšĽ§„ĀęśėéÁĘļ„Ā™Ť¶ŹŚģö„ĀĆ„Āā„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„ĀĮšĺĚÁĄ∂„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„ĀģÁĺ©Śčô„ĀģŤß£ťáą„ĀęŚĹĪťüŅ„āíšłé„Āą„ā茏ĮŤÉĹśÄß„Āģ„Āā„ā蜆ĻŚļē„Āę„Āā„āč„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„ĀģŚéüŚČá„Āę„āāÁēôśĄŹ„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀšľöÁ§ĺś≥ē2006ŚĻīÁ¨¨172śĚ°„ĀĮ„ÄĀŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„ĀĆ„ÄĆšľöÁ§ĺ„ĀģśąźŚäü„āíšŅÉťÄ≤„Āô„āč„ÄćÁĺ©Śčô„āíŤ≤†„ĀÜ„Ā®Ť¶ŹŚģö„Āó„ÄĀ„ĀĚ„Āģťöõ„ĀęŚĺďś•≠Śď°„ĀģŚą©Áõä„ÄĀ„ā≥„Éü„É•„Éč„ÉÜ„ā£„ÄĀÁíįŚĘÉ„ÄĀ„Éď„āł„Éć„āĻťĖĘšŅā„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüťĚěÁ∂≤ÁĺÖÁöĄ„Ā™Ť¶ĀÁī†„āíŤÄÉśÖģ„Āô„āč„Āď„Ā®„āíśėéÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀšłÄťÉ®„Āģś≥ēŚüü„āĄś≠īŚŹ≤ÁöĄŤß£ťáą„ĀßšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā†„Ā£„Āüś†™šłĽšł≠ŚŅÉšłĽÁĺ©„Āč„āČ„ÄĀ„āą„āäŚļÉÁĮĄ„Ā™„āĻ„ÉÜ„Éľ„āĮ„Éõ„Éę„ÉÄ„Éľ„āíŤÄÉśÖģ„Āô„āč„āĘ„Éó„É≠„Éľ„ÉĀ„Āł„ĀģÁ߼Ť°Ć„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ś†™šłĽ„Ā®„ĀģťĖĘšŅā„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšľöÁ§ĺś≥ē2006ŚĻī„ĀĮ„ÄĀś†™šłĽ„Ā®„ĀģťõĽŚ≠źÁöĄ„Ā™„ā≥„Éü„É•„Éč„āĪ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíŚģĻśėď„Āę„Āó„ÄĀťĚěŚÖ¨ťĖčšľöÁ§ĺ„Āę„Āä„ĀĎ„āčśõłťĚĘśĪļŤ≠į„ĀģŚÖ®šľöšłÄŤáīŤ¶ĀšĽ∂„ā팼ɜ≠Ę„Āó„ÄĀŚĻīś¨°ś†™šłĽÁ∑ŹšľöÔľąAGMԾȄĀģťĖčŚā¨Áĺ©Śčô„āíśí§ŚĽÉ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„ÄāšłäŚ†īšľöÁ§ĺ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚĻīś¨°Ś†ĪŚĎäśõł„Āę„Āä„ĀĎ„āčšļčś•≠„ɨ„Éď„É•„Éľ„ĀģŤŅŌ䆍¶ĀšĽ∂„āĄ„ÄĀś†™šłĽÁ∑Źšľö„ĀģÁĶźśěú„Āģ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„ÉąŚÖ¨ťĖčÁĺ©Śčô„Ā™„Ā©„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšľöÁ§ĺś≥ē„ĀĮ„ÄĀŚįŹŤ¶Źś®°„Ā™ťĚěŚÖ¨ťĖčšļčś•≠šĹď„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮśüĒŤĽü„Āꍮ≠Ť®ą„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ā蚳ĜĖĻ„Āß„ÄĀŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™ŚÖ¨ťĖčšľöÁ§ĺ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮ„āą„āäŚé≥ś†ľ„Ā™„ā¨„Éź„Éä„É≥„āĻ„Ā®ťÄŹśėéśÄß„ā퍙≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ā§„āģ„É™„āĻŚ•ĎÁīĄś≥ē„ĀģŚüļśú¨ŚéüŚČá
„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģŚ•ĎÁīĄś≥ē„ĀĮ„ÄĀ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„ĀģšľĚÁĶĪ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀśúČŚäĻ„Ā™Ś•ĎÁīĄ„āíśąźÁęč„Āē„Āõ„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„Āģ5„Ā§„ĀģŤ¶ĀÁī†„ĀĆśŹÉ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āö„ÄĀÁĒ≥Ťĺľ„ĀŅÔľąOfferԾȄĀ®śČŅŤęĺÔľąAcceptanceԾȄĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„ÄāšłÄśĖĻ„ĀģŚĹďšļčŤÄÖ„ĀĆśėéÁĘļ„Ā™ÁĒ≥Ťĺľ„ĀŅ„ā퍰ƄĀĄ„ÄĀšĽĖśĖĻ„ĀģŚĹďšļčŤÄÖ„ĀĆ„ĀĚ„ĀģÁĒ≥Ťĺľ„ĀŅ„āíśėéÁĘļ„ĀęśČŅŤęĺ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŚ•ĎÁīĄťĖĘšŅā„ĀĆťĖčŚßč„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāśČŅŤęĺ„ĀĮśõłťĚĘ„ÄĀŚŹ£ť†≠„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮŤ°ĆÁāļ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„āāŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Äā
ś¨°„Āę„ÄĀÁīĄŚõ†ÔľąConsiderationԾȄĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ā§„āģ„É™„āĻŚ•ĎÁīĄś≥ē„Āę„Āä„ĀĎ„āčśúÄ„āāťá捶Ā„Ā™ÁČĻŚĺī„ĀģšłÄ„Ā§„Āß„Āā„āä„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀģśĪļŚģöÁöĄ„Ā™ťĀē„ĀĄ„Āß„Āô„ÄāÁīĄŚõ†„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŚĮĺšĺ°„Ā®„Āó„Ā¶śĒĮśČē„āŹ„āĆ„āč„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮšļ§śŹõ„Āē„āĆ„āč„Äƚ尌ħ„Āā„āč„āā„Āģ„Äć„āíśĆá„Āó„Āĺ„Āô„ÄāťáĎťä≠„Āß„Āā„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁČ©ŚďĀ„ÄĀ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮ„ĀĚ„āĆ„āČ„ā휏źšĺõ„Āô„āčÁīĄśĚü„Āß„āāśßč„ĀĄ„Āĺ„Āõ„āď„ÄāÁīĄŚõ†„ĀĮ„ÄĆŚćĀŚąÜ„ÄćÔľąsufficientԾȄĀß„Āā„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ÄĆťĀ©Śąá„ÄćÔľąadequateԾȄĀß„Āā„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀŤ≤īťáć„Ā™Ť≤°ÁĒ£„ĀęŚĮĺ„Āô„āč1„ÉĚ„É≥„ÉČ„āĄ„ÄĀŤĪ°ŚĺīÁöĄ„Ā™„ÄĆ„ā≥„ā∑„Éß„ā¶„ĀģŚģü„ÄćÔľąpeppercornԾȄĀģ„āą„ĀÜ„Ā™ŚźćÁõģšłä„ĀģÁīĄŚõ†„Āß„āā„ÄĀś≥ēÁöĄ„Āę„ĀĮśúČŚäĻ„Ā™ÁīĄŚõ†„Ā®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāÁīĄŚõ†„ĀĆ„ÄĆťĀ©Śąá„Āß„Āā„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„ĀĆ„ÄĀŚćĀŚąÜ„Āß„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜś¶āŚŅĶ„Āß„Āô„Äā„Āü„Ā®„Āą„ÄĆŤ¶č„Āõ„Āč„ĀĎ„Äć„Āģ„āą„ĀÜ„Āꍶč„Āą„Ā¶„āā„ÄĀ„Āď„āĆ„Āę„āą„āäŚĹďšļčŤÄÖ„ĀĮ„ÄĀšļ§śŹõ„Āē„āĆ„āčšĺ°ŚÄ§„ĀĆśúÄŚįŹťôź„Āĺ„Āü„ĀĮŤĪ°ŚĺīÁöĄ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āāŚ•ĎÁīĄ„āíśčėśĚüŚäõ„Āģ„Āā„āč„āā„Āģ„Āę„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ÄāšľĀś•≠„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŚľ∑Śą∂Śäõ„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ÄĀŚźćÁõģšłä„ĀģśĒĮśČē„ĀĄ„Āĺ„Āü„ĀĮŚįŹ„Āē„Ā™Áõłšļí„ĀģÁīĄśĚü„ā팟ę„āĀ„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀÁīĄŚõ†„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„āíŚģĻśėď„ĀęśļÄ„Āü„Āô„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„ÉľÁČĻśúČ„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚģüŚčôÁöĄ„Ā™ŚĮĺŚŅúÁ≠Ė„Āß„Āô„Äā
Á¨¨Śõõ„Āę„ÄĀś≥ēÁöĄťĖĘšŅā„āíÁĮČ„ĀŹśĄŹśÄĚÔľąIntention to Create Legal RelationsԾȄĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚĹďšļčŤÄÖŚŹĆśĖĻ„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚźąśĄŹ„ĀĆś≥ēÁöĄ„ĀęśčėśĚüŚäõ„āíśĆĀ„Ā§„Āď„Ā®„ā휥ŹŚõ≥„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
śúÄŚĺĆ„Āę„ÄĀÁĘļŚģüśÄßÔľąCertaintyԾȄĀĆťá捶Ā„Āß„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģśĚ°ť†Ö„ĀĮśėéÁĘļ„Āß„Āā„āä„ÄĀśú¨Ť≥™ÁöĄ„Ā™śĚ°ť†Ö„ĀĆś¨†„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ā§„āģ„É™„āĻťõáÁĒ®ś≥ē
„ÄĆWorker„Äć„Ā®„ÄĆEmployee„Äć
„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģťõáÁĒ®ś≥ē„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģšłÄŚÖÉÁöĄ„Ā™„ÄĆŚäīŚÉćŤÄÖ„Äć„Āģś¶āŚŅĶ„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āä„ÄĀŚäīŚÉćŤÄÖšŅĚŤ≠∑„ĀģÁĮĄŚõ≤„ā퍧áśēį„Āģ„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ„Āꌹ܄ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšłĽ„Āę„ÄĆEmployee„ÄćÔľąŚĺďś•≠Śď°ÔľČ„Ā®„ÄĆWorker„ÄćÔľą„ÉĮ„Éľ„āę„ɾԾȄĀ®„ĀĄ„ĀÜšļĆ„Ā§„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™ŚģöÁĺ©„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆ„Āꚼėšłé„Āē„āĆ„āčś®©Śą©„ĀĆÁēį„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ÄĆWorker„ÄćÔľą„ÉĮ„Éľ„āę„ɾԾȄĀĮ„ÄĀ„ÄĆEmployment Rights Act 1996„ÄćÔľąťõáÁĒ®ś®©ś≥ē1996ŚĻīÔľČÁ¨¨230śĚ°„ĀߌģöÁĺ©„Āē„āĆ„ÄĀťõáÁĒ®Ś•ĎÁīĄ„āíśĆĀ„Ā§ŤÄÖ„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮŚÄčšļļÁöĄ„ĀęŚäīŚÉć„ā휏źšĺõ„Āó„ÄĀ„Āč„Ā§ť°ßŚģĘ„āĄ„āĮ„É©„ā§„āĘ„É≥„Éą„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄŤÄÖ„Ā®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āô„ĀĻ„Ā¶„ĀģŚĺďś•≠Śď°„ĀĮ„ÉĮ„Éľ„āę„Éľ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Āô„ĀĻ„Ā¶„Āģ„ÉĮ„Éľ„āę„Éľ„ĀĆŚĺďś•≠Śď°„Āß„Āā„āč„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„ÉĮ„Éľ„āę„Éľ„Āꚼėšłé„Āē„āĆ„āčś®©Śą©„Āę„ĀĮ„ÄĀśúÄšĹéŤ≥ÉťáĎÔľąNational Minimum Wage„ÄĀ21ś≠≥šĽ•šłä„ĀĮNational Living WageԾȄÄĀ28śó•ťĖď„Āģś≥ēŚģöśúČÁĶ¶šľĎśöá„ÄĀŚĻīťáĎŚą∂Śļ¶„Āł„ĀģŚä†ŚÖ•„ÄĀŚģČŚÖ®„Ā™ŚäīŚÉćÁíįŚĘÉÔľąHealth & Safety at Work Act 1974ԾȄÄĀŚ∑ģŚą•Á¶Āś≠ĘÔľąEquality Act 2010ԾȄÄĀŚäīŚÉćÁĶĄŚźą„Āģś®©Śą©„Ā™„Ā©„ĀĆŚźę„Āĺ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀťõáÁĒ®šŅĚťöúÔľąšłćŚĹďŤß£ťõá„Āč„āČ„ĀģšŅĚŤ≠∑ԾȄÄĀŤā≤ŚÖźšľĎśöá„ÄĀŤß£ťõáśČčŚĹď„Ā™„Ā©„ĀĮšĽėšłé„Āē„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„ÄāťęėŚŹéŚÖ•„ĀģťÖćÁģ°Ś∑•„Ā™„Ā©„ÄĀśļĖŤá™ŚĖ∂ś•≠ŤÄÖ„āā„Āď„Āģ„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ„Āꌟę„Āĺ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ÄĆEmployee„ÄćÔľąŚĺďś•≠Śď°ÔľČ„ĀĮ„ÄĀ„ÉĮ„Éľ„āę„Éľ„Āꚼėšłé„Āē„āĆ„āč„Āô„ĀĻ„Ā¶„Āģś®©Śą©„ĀęŚä†„Āą„ÄĀŤŅŌ䆄ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™ś®©Śą©„ĀĆšĽėšłé„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚĺďś•≠Śď°„Āꚼėšłé„Āē„āĆ„āčŤŅŌ䆄Āģś®©Śą©„Āę„ĀĮ„ÄĀťõáÁĒ®šŅĚťöú„ÄĀťÄÄŤĀ∑ťáĎ„ÄĀŤā≤ŚÖźšľĎśöá„ÄĀśõłťĚĘ„Āę„āą„āčťõáÁĒ®Ś•ĎÁīĄ„ÄĀŚÖ¨ś≠£„Ā™Ťß£ťõáŚČć„ĀģŚźąÁźÜÁöĄ„Ā™ťÄöÁü•„ÄĀŤß£ťõáśČčŚĹď„Ā™„Ā©„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚõĹśįĎšŅĚťôļśĖô„ĀģŤ≤†śčÖ„Ā®śČÄŚĺóÁ®é„ĀģÁīćÁ®éÁĺ©Śčô„āāŤ≤†„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚĺďś•≠Śď°„ĀģŚģöÁĺ©„ĀģŚą§śĖ≠„ĀĮ„ÄĀšłĽ„ĀęŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŤß£ťáą„ĀęŚßĒ„Ā≠„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ÄĆśĒĮťÖć„ÄćÔľącontrolԾȄÄĀ„ÄĆÁĶĪŚźą„ÄćÔľąintegrationԾȄÄĀ„ÄĆÁĶĆśłąÁöĄŚģüśÖč„ÄćÔľąeconomic realityԾȄÄĀ„ÄĆŚäīŚÉć„ĀęŚĮĺ„Āô„āčŤ≥ÉťáĎ„ĀģšłćŚŹĮś¨†„Ā™šļ§śŹõ„ÄćÔľąirreducible coreԾȄĀ®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤ¶ĀÁī†„ĀĆŤÄÉśÖģ„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģÁõłŚĮĺÁöĄ„Ā™šļ§śłČŚäõ„āāŤÄÉśÖģ„Āē„āĆ„ÄĀśõłťĚĘšłä„ĀģŚźąśĄŹ„ĀĆŚģüśÖč„ā팏ćśė†„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚźąśĄŹ„ĀĆÁĄ°Ť¶Ė„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
śó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀģśĮĒŤľÉ
śó•śú¨„ĀģťõáÁĒ®ś≥ē„ĀĮ„ÄĀšłĽ„Āę„ÄĆťõáÁĒ®šłĽ„Ā®Śĺďś•≠Śď°„ĀģťĖĘšŅā„Äć„āíŚĮĺŤĪ°„Ā®„Āó„ÄĀšľöÁ§ĺś≥ēšłä„ĀģŚĹĻŚď°„āĄÁč¨ÁęčŤęčŤ≤†šļļ„ĀĮŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶Śĺďś•≠Śď°„Ā®„ĀĮ„ĀŅ„Ā™„Āē„āĆ„Āö„ÄĀŚäīŚÉćś≥ē„ĀģšŅĚŤ≠∑„ā팏ó„ĀĎ„Āĺ„Āõ„āď„Äāśó•śú¨„Āę„ĀĮ„ÄĆAt Will„ÄćÔľąŤá™ÁĒĪŤß£ťõáԾȄĀģś¶āŚŅĶ„ĀĆ„Ā™„ĀŹ„ÄĀś≠£Ť¶ŹťõáÁĒ®„ĀģÁĶāšļÜ„ĀĮ„ÄĆŚģĘŤ¶≥ÁöĄ„ĀꌟąÁźÜÁöĄ„ĀßÁ§ĺšľöťÄöŚŅĶšłäÁõłŚĹď„Äć„Āß„Āā„āč„Ā®Śé≥ś†ľ„ĀęŤß£ťáą„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„ĀĮ„ÄĀ„Éē„Éę„āŅ„ā§„Ɇ„Āģś≠£Ť¶ŹŚĺďś•≠Śď°„Ā®ťĚěś≠£Ť¶ŹŚĺďś•≠Śď°„Ā®„ĀģťĖď„ĀģšłćŚźąÁźÜ„Ā™ŚĺÖťĀáŚ∑ģ„āíÁ¶Āś≠Ę„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģ„ÄĆEmployee„Äć„Ā®„ÄĆWorker„Äć„ĀģŚĆļŚą•„ĀĮ„ÄĀ„Āü„Ā®„ĀąŚģĆŚÖ®„Ā™Śĺďś•≠Śď°„Ā®„ĀŅ„Ā™„Āē„āĆ„Ā™„ĀĄŚÄčšļļ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀśúÄšĹéŤ≥ÉťáĎ„āĄśúČÁĶ¶šľĎśöá„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚüļśú¨ÁöĄ„Ā™ś®©Śą©„āíśĆĀ„Ā§„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚ§öŚĪ§ÁöĄ„Ā™šŅĚŤ≠∑„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„āíśßčÁĮČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšłÄśĖĻ„ÄĀśó•śú¨„ĀĮ„ÄĀšłĽ„Āę„ÄĆŚĺďś•≠Śď°„Äć„Ā®„ÄĆťĚěŚĺďś•≠Śď°„ÄćÔľąÁč¨ÁęčŤęčŤ≤†šļļ„āĄŚĹĻŚď°ÔľČ„ĀģšļĆŚÖÉÁöĄ„Ā™ŚĆļŚąÜ„ĀßťĀčÁĒ®„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀťĚěŚĺďś•≠Śď°„ĀĮŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ŚäīŚÉćś≥ē„ĀģšŅĚŤ≠∑ŚĮĺŤĪ°Ś§Ė„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀßšļļśĚź„āíťõáÁĒ®„Āô„āčśó•śú¨šľĀś•≠„ÄĀÁČĻ„ĀęśüĒŤĽü„Ā™Ś•ĎÁīĄŚĹĘśÖč„āĄ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Éô„Éľ„āĻ„ĀģŚĹĻŚČ≤„ĀßšļļśĚź„āíÁĘļšŅĚ„Āó„āą„ĀÜ„Ā®„Āô„ā茆īŚźą„ÄĀ„Āü„Ā®„ĀąÁč¨ÁęčŤęčŤ≤†šļļ„Ā®„Āó„Ā¶ťõáÁĒ®„Āô„ā蜥ŹŚõ≥„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚÄčšļļ„ĀĆ„ÄĆ„ÉĮ„Éľ„āę„Éľ„Äć„Ā®„ĀŅ„Ā™„Āē„āĆ„ÄĀťá捶Ā„Ā™ś≥ēŚģöś®©Śą©„āíśĆĀ„Ā§ŚŹĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Āď„Ā®„ā퍙ćŤ≠ė„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĀŚĺďś•≠Śď°/„ÉĮ„Éľ„āę„Éľ„ĀģŚúįšĹć„ā팹§śĖ≠„Āô„āčťöõ„Āę„ÄĀ„ÄĆÁĶĆśłąÁöĄŚģüśÖč„Äć„Ā®„ÄĆŚĹĘŚľŹ„āą„āä„āāŚģüŤ≥™„Äć„āíťá捶Ė„Āó„ÄĀÁõłšļí„ĀģšŅ°ť†ľťĖĘšŅā„āĄ„ÄĆšļ§śłČŚäõ„ĀģšłćŚĚ፰°„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤ¶ĀÁī†„āíŤÄÉśÖģ„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀśõłťĚĘšłä„ĀģŚ•ĎÁīĄ„Āß„ÄƍᙌĖ∂ś•≠ŤÄÖ„Äć„Ā®Ť®ėŤľČ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀŚģüťöõ„ĀģŚäīŚÉćŚģüśÖč„ĀĆťõáÁĒ®ťĖĘšŅā„āíÁ§ļŚĒÜ„Āô„ā茆īŚźą„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ®ėŤľČ„ĀĆÁĄ°Ť¶Ė„Āē„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀšľĀś•≠„ĀĮ„ÄĀŚćė„ĀꌕĎÁīĄšłä„ĀģŤā©śõł„Āć„ĀꝆľ„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„Āß„Āć„Āĺ„Āõ„āď„ÄāŚģüťöõ„Āę„Ā©„āĆ„Ā†„ĀĎ„ĀģśĆᜏģŚĎĹšĽ§„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„ÄĀšļčś•≠„Āł„ĀģÁĶĪŚźąŚļ¶Śźą„ĀĄ„ÄĀŚÄčšļļ„ĀģÁĶĆśłąÁöĄšĺĚŚ≠ėŚļ¶„ā팹ܜ쟄Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀ„Éē„É™„Éľ„É©„É≥„āĶ„Éľ„āĄ„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆŚäīŚÉćŤÄÖ„āíťõáÁĒ®„Āô„āčITšľĀś•≠„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶ÁČĻ„Āęťá捶Ā„Ā™ŤÄÉśÖģšļ蝆քĀß„Āô„Äā
„ā§„āģ„É™„āĻ„Āę„Āä„ĀĎ„āčITťĖĘťÄ£ś≥ēŚą∂Śļ¶

„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀĮ„ÄĀITŚąÜťáé„Āģ„Éď„āł„Éć„āĻŚĪēťĖč„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ÁČĻ„Āęťá捶Ā„Ā™„ÄĀ„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ÄĀťõĽŚ≠źŚēÜŚŹĖŚľē„ĀęťĖĘ„Āô„āčś≥ēŚą∂Śļ¶„āíśēīŚāô„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑
„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀEUťõĘŤĄĪ„Āęšľī„ĀĄ„ÄĀEUšłÄŤą¨„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑Ť¶ŹŚČáÔľąGDPRԾȄĀĆ„ÄĆUK GDPR„Äć„Ā®„Āó„Ā¶ŚõĹŚÜÖś≥ē„ĀꌏĖ„āäŤĺľ„Āĺ„āĆ„ÄĀ„ĀĚ„Āģšłä„Āß„ÄĆData Protection Act 2018„ÄćÔľą„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑ś≥ē2018ŚĻī„ÄĀDPA 2018ԾȄĀĆ„ÄĆUK GDPR„Äć„āíŤ£úŚģĆ„ÉĽšŅģś≠£„Āô„āčŚĹĘ„ĀßťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„āĶ„Éľ„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£
„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆComputer Misuse Act 1990„ÄćÔľą„ā≥„É≥„ÉĒ„É•„Éľ„āŅšłćś≠£šĹŅÁĒ®ś≥ē„ÄĀCMAԾȄĀĆ„ÉŹ„ÉÉ„ā≠„É≥„āį„āĄ„ā≥„É≥„ÉĒ„É•„Éľ„āŅ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āä„āą„Ā≥„Éá„Éľ„āŅ„Āł„Āģšłćś≠£„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„āíÁäĮÁĹ™„Ā®„Āô„āč„ā§„āģ„É™„āĻ„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™ś≥ēŚĺč„Āß„Āô„ÄāšłĽ„Ā™ÁäĮÁĹ™„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀšłćś≠£„āĘ„āĮ„āĽ„āĻÔľąÁ¨¨1śĚ°ÔľČ„ÄĀ„Āē„āČ„Ā™„āčÁäĮÁĹ™„āíÁäĮ„ĀôÁõģÁöĄ„Āß„Āģšłćś≠£„āĘ„āĮ„āĽ„āĻÔľąÁ¨¨2śĚ°ÔľČ„ÄĀ„ā≥„É≥„ÉĒ„É•„Éľ„āŅ„ĀģŚčēšĹú„ā팶®Śģ≥„Āô„āčšłćś≠£Ť°ĆÁāļÔľąÁ¨¨3śĚ°„ÄĀšĺč: DDoSśĒĽśíÉԾȄÄĀťá挧߄Ā™śźćŚģ≥„ā팾ē„ĀćŤĶ∑„Āď„Āôšłćś≠£Ť°ĆÁāļÔľąÁ¨¨3ZAśĚ°„ÄĀťá捶Ā„ā§„É≥„Éē„É©ŚĮĺŤĪ°ÔľČ„ÄĀšłćś≠£šĹŅÁĒ®ÁõģÁöĄ„ĀģÁČ©ŚďĀ„ĀģŤ£ĹťÄ†„ÉĽšĺõÁĶ¶„ÉĽŚŹĖŚĺóÔľąÁ¨¨3AśĚ°„ÄĀšĺč: „Éě„Éę„ā¶„āß„āĘԾȄĀ™„Ā©„ĀĆŤ¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Éď„āł„Éć„āĻ„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„āĶ„ā§„Éź„ÉľÁäĮÁĹ™ŤÄÖ„ā퍮īŤŅĹ„Āô„āčś≥ēÁöĄś†Ļśč†„ā휏źšĺõ„Āó„ÄĀšľĀś•≠„ĀĮŚĺďś•≠Śď°„ĀęŚĮĺ„Āô„āčśėéÁĘļ„Ā™„āĘ„āĮ„āĽ„āĻŚą∂ťôź„āíŚģöÁĺ©„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„ĀôÔľąÁ¨¨1śĚ°„ĀģÁäĮÁĹ™„ĀĮŚĺďś•≠Śď°„Āę„āāťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆŚĺó„āč„Āü„āĀԾȄÄāCMA„ĀģŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āč„ÄĆ„ā≥„É≥„ÉĒ„É•„Éľ„āŅŤ≥áśĖô„Äć„Āę„ĀĮŚÄčšļļ„Éá„Éľ„āŅ„ĀĆŚźę„Āĺ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„Āü„āĀ„ÄĀ„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑ś≥ē„Ā®„āāŚĮÜśé•„ĀęťĖĘťÄ£„Āó„Āĺ„Āô„ÄāÁĹįŚČá„ĀĮÁäĮÁĹ™„Āģťá挧ߜÄß„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶Áēį„Ā™„āä„ÄĀśúÄŚ§ß14ŚĻī„ĀģÁ¶ĀŚõļŚąĎ„Āĺ„Āü„ĀĮÁĶāŤļꌹĎÔľąťá挧߄Ā™śźćŚģ≥„ĀģŚ†īŚźąÔľČ„ÄĀ„Āä„āą„Ā≥ÁĄ°Śą∂ťôź„ĀģÁĹįťáĎ„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀ„ÄĆTelecommunications (Security) Act 2021„ÄćÔľąťõĽśįóťÄöšŅ°„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ś≥ē„ÄĀTSAԾȄĀĮ„ÄĀ„ÄĆCommunications Act 2003„ÄćÔľąťÄöšŅ°ś≥ē2003ŚĻīԾȄāíśĒĻś≠£„Āó„ÄĀŚÖ¨ŚÖĪ„ĀģťõĽŚ≠źťÄöšŅ°„Éć„ÉÉ„Éą„ÉĮ„Éľ„āĮ„Āä„āą„Ā≥„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ĀęŚĮĺ„Āô„ā茾∑ŚĆĖ„Āē„āĆ„Āü„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„āíŚįéŚÖ•„Āó„Āĺ„Āó„Āü„ÄāťÄöšŅ°„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄ„ÉľÔľąCSPsԾȄĀę„ĀĮ„ÄĀ„É™„āĻ„āĮ„ĀģÁČĻŚģö„ÉĽŤĽĹśłõ„ÄĀ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£šĺĶŚģ≥„Āł„ĀģśļĖŚāô„ÄĀśā™ŚĹĪťüŅ„Āģťė≤ś≠Ę„ÄĀ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ā§„É≥„ā∑„Éá„É≥„Éą„ĀģŚ†ĪŚĎä„Ā™„Ā©„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚŹéÁõä„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„Āü„ÉÜ„ā£„āĘŚą∂Ôľą„ÉÜ„ā£„āĘ1: 10ŚĄĄ„ÉĚ„É≥„ÉČšĽ•šłä„ÄĀ„ÉÜ„ā£„āĘ2: 5,000šłá„ÉĚ„É≥„ÉČšĽ•šłä10ŚĄĄ„ÉĚ„É≥„ÉČśú™śļÄ„ÄĀ„ÉÜ„ā£„āĘ3: 5,000šłá„ÉĚ„É≥„ÉČśú™śļÄԾȄĀĆťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Éď„āł„Éć„āĻ„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀťÄöšŅ°„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„Éó„É≠„Éź„ā§„ÉÄ„Éľ„ĀęÁõīśé•ÁöĄ„Ā™ŚĹĪťüŅ„āíšłé„Āą„āč„ĀĽ„Āč„ÄĀCSPs„Ā®ŚŹĖŚľē„Āģ„Āā„āčšľĀś•≠„āā„ÄĀ„āĶ„Éó„É©„ā§„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„Āģ„ɨ„āł„É™„ā®„É≥„āĻ„ĀęÁĄ¶ÁāĻ„āíŚĹď„Ā¶„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āč„Āü„āĀ„ÄĀťĖĘťÄ£„Āô„āčšĺõÁĶ¶Ś•ĎÁīĄ„ĀģŤ¶čÁõī„Āó„āíśĪā„āĀ„āČ„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāšłćťĀĶŚģą„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀOfcom„Āę„āą„Ā£„Ā¶1śó•„Āā„Āü„āäśúÄŚ§ß10šłá„ÉĚ„É≥„ÉČ„Āĺ„Āü„ĀĮŚĻīťĖéÁõä„Āģ10%„ĀģÁĹįťáĎ„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
ťõĽŚ≠źŚēÜŚŹĖŚľē„Āä„āą„Ā≥ťõĽŚ≠źťÄöšŅ°
ťõĽŚ≠źŚēÜŚŹĖŚľē„Āä„āą„Ā≥ťõĽŚ≠źťÄöšŅ°„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆPrivacy and Electronic Communications Regulations (PECR)„ÄćÔľą„Éó„É©„ā§„Éź„ā∑„ÉľŚŹä„Ā≥ťõĽŚ≠źťÄöšŅ°Ť¶ŹŚČáԾȄĀĆDPA 2018„Āä„āą„Ā≥UK GDPR„Ā®šł¶Ť°Ć„Āó„Ā¶ťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„ā荶ŹŚą∂„Āß„Āô„ÄāťõĽŚ≠ź„Éě„Éľ„āĪ„ÉÜ„ā£„É≥„āįÔľąťõĽŤ©Ī„ÄĀ„É°„Éľ„Éę„ÄĀ„ÉÜ„ā≠„āĻ„Éą„ÄĀFAXԾȄĀä„āą„Ā≥„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„Āģ„āĮ„ÉÉ„ā≠„Éľ„āĄť°ěšľľśäÄŤ°ď„ĀģšĹŅÁĒ®„ā퍶ŹŚą∂„Āó„ÄĀUK GDPR„ĀģŚźĆśĄŹŚüļśļĖ„ĀĆťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Éď„āł„Éć„āĻ„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀťõĽŚ≠źÁöĄ„Āę„Éě„Éľ„āĪ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„ā퍰ƄĀÜ„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„Āß„āĮ„ÉÉ„ā≠„Éľ„āíšĹŅÁĒ®„Āô„āč„Āô„ĀĻ„Ā¶„ĀģšľĀś•≠„ĀęťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„ÄĀśėéÁĘļ„Ā™„Éó„É©„ā§„Éź„ā∑„Éľ„ÉĚ„É™„ā∑„Éľ„Ā®„āĮ„ÉÉ„ā≠„Éľ„ÉĚ„É™„ā∑„Éľ„ĀģšĹúśąź„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāICOÔľąśÉÖŚ†Ī„ā≥„Éü„ÉÉ„ā∑„Éß„Éä„Éľ„ā™„Éē„ā£„āĻԾȄĀĮśúÄŚ§ß1750šłá„ÉĚ„É≥„ÉČ„Āĺ„Āü„ĀĮŚÖ®šłĖÁēĆŚ£≤šłäťęė„Āģ4ÔľÖ„Āģ„ĀĄ„Āö„āĆ„Āčťęė„ĀĄśĖĻ„ĀģÁĹįťáĎ„ā퍙≤„Āô„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„ÄĀŚŹĖÁ∑†ŚĹĻ„āāŤ≤¨šĽĽ„āíŚēŹ„āŹ„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖšŅĚŤ≠∑
„Āē„āČ„Āę„ÄĀ„ÄĆConsumer Rights Act 2015„ÄćÔľąś∂ąŤ≤ĽŤÄÖś®©Śą©ś≥ē2015ŚĻī„ÄĀCRA 2015ԾȄĀĮ„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģ„Āô„ĀĻ„Ā¶„ĀģšľĀś•≠„Āę„Āä„ĀĎ„āčś∂ąŤ≤ĽŤÄÖšŅĚŤ≠∑„ĀģŚüļÁõ§„Ā®„Ā™„āčś≥ēŚĺč„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥„Āß„ĀģÁČ©ŚďĀ„ÄĀ„Éá„āł„āŅ„Éę„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ÄĀ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ĀģŤ≤©Ś£≤„Āę„āāťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāšłĽŤ¶Ā„Ā™ś®©Śą©„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀÁČ©ŚďĀ„ĀĮśļÄŤ∂≥„Āģ„ĀĄ„ĀŹŚďĀŤ≥™„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„ÄĀŤ™¨śėéťÄö„āä„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„ÄĀśĄŹŚõ≥„Āē„āĆ„ĀüÁõģÁöĄ„ĀęťĀ©Śźą„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ÄĀ„Éá„āł„āŅ„Éę„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„āāŚźĆśßė„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„ÄĀ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ĀĮŚźąÁźÜÁöĄ„Ā™ś≥®śĄŹ„Ā®śäÄŤÉĹ„āí„āā„Ā£„Ā¶śŹźšĺõ„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Ā™„Ā©„ĀĆŤ¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ā™„É≥„É©„ā§„É≥Ť≤©Ś£≤„ĀģÁČĻŤ®ėšļ蝆քĀ®„Āó„Ā¶„ÄĀConsumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013„Āę„āą„āä„ÄĀ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©„Āģ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥Ť≥ľŚÖ•„Āę„ĀĮ14śó•ťĖď„Āģ„ā≠„É£„É≥„āĽ„ÉęśúüťĖďÔľą„āĮ„Éľ„É™„É≥„āį„ā™„ÉēśúüťĖďԾȄĀĆ„Āā„āä„ÄĀśėéÁĘļ„Ā™ŤŅĒťáĎŤ¶ĀšĽ∂Ôľą14śó•šĽ•ŚÜÖԾȄÄĀťö†„āĆ„ĀüśČčśēįśĖô„ĀģÁ¶Āś≠Ę„ÄĀťÄŹśėéśÄß„Āģ„Āā„ā茹©ÁĒ®Ť¶ŹÁīĄ„ÄĀ„āĘ„āĮ„āĽ„āĻŚŹĮŤÉĹ„Ā™„ā™„É≥„É©„ā§„É≥„ā∑„Éß„ÉÉ„Éó„Ā™„Ā©„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Éď„āł„Éć„āĻ„Āł„ĀģŚĹĪťüŅ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšľĀś•≠Śźć„ÄĀšĹŹśČÄ„ÄĀ„É°„Éľ„Éę„āĘ„ÉȄɨ„āĻ„ÄĀšľöÁ§ĺÁôĽťĆ≤Áē™ŚŹ∑„ÄĀVATÁē™ŚŹ∑„Ā™„Ā©„ĀģśėéÁĘļ„Ā™śÉÖŚ†ĪśŹźšĺõ„ÄĀšļčś•≠„Āꌟą„āŹ„Āõ„ĀüŚą©ÁĒ®Ť¶ŹÁīĄ„ÄĀťĀ©Śąá„Ā™ŤŅĒŚďĀ„ÉĽ„ā≠„É£„É≥„āĽ„Éę„Éó„É≠„āĽ„āĻ„ÄĀ„āĘ„āĮ„āĽ„āĻŚŹĮŤÉĹ„Ā™„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„ÄĀÁúüŚģüśÄß„Āģ„Āā„āč„Éě„Éľ„āĪ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāšłćťĀĶŚģą„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀś∂ąŤ≤ĽŤÄÖ„Āč„āČ„ĀģśźćŚģ≥Ť≥†ŚĄüŤęčśĪā„ÄĀ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„āĄŚŹĖŚľēśÖ£Ť°Ć„ĀģŚľ∑Śą∂ÁöĄ„Ā™Ś§Čśõī„ÄĀŤ©ēŚą§„ĀģśĮÄśźć„Ā™„Ā©„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
DPA 2018„ÄĀUK GDPR„ÄĀPECR„ÄĀCMA„ÄĀTSA„ÄĀCRA 2015„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüITťĖĘťÄ£ś≥ē„ĀĮŤ§áťõĎ„ĀęÁĶ°„ĀŅŚźą„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„ĀęPECR„ĀĮ„ÄĆ„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑ś≥ē„Ā®UK GDPR„Ā®šł¶Ť°Ć„Āó„Ā¶ťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„āč„Äć„Ā®„Āē„āĆ„ÄĀCMA„ĀĮ„ÄĆ„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑ś≥ē2018ŚĻī„Āä„āą„Ā≥šłÄŤą¨„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑Ť¶ŹŚČá„Ā®„Āč„Ā™„āä„Āģťá捧á„ĀĆ„Āā„āč„Äć„Ā®śė鍮ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšľĀś•≠„ĀĮ„Āď„āĆ„āČ„Āģś≥ēŚĺč„āíŚÄ茹•ÁöĄ„ĀęśČĪ„ĀÜ„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„Āā„āčś≥ēŚĺč„Āģšłč„Āß„ĀģŤ°ĆŚčēÔľąšĺč: PECR„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹ„Éě„Éľ„āĪ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„Āģ„Āü„āĀ„Āģ„Éá„Éľ„āŅŚŹéťõÜԾȄĀĆ„ÄĀšĽĖ„Āģś≥ēŚĺčÔľąšĺč: ŚÄčšļļ„Éá„Éľ„āŅ„ĀęťĖĘ„Āô„āčUK GDPR„ĀģŚéüŚČáԾȄĀę„āāśļĖśč†„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„āíÁĘļŤ™ć„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀÁ∂≤ÁĺÖÁöĄ„Ā™ŚĹĘ„Āß„Āģ„ā≥„É≥„Éó„É©„ā§„āĘ„É≥„āĻ„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ
„ā§„āģ„É™„āĻ„Āß„Āģ„Éď„āł„Éć„āĻŚĪēťĖč„Āģ„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āč„ā§„āģ„É™„āĻ„Āģś≥ēÁöĄśě†ÁĶĄ„ĀŅ„ÄĀÁČĻ„Āę„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„ĀģŚéüŚČá„Ā®Śą∂Śģöś≥ē„ĀģťĖĘšŅāśÄß„āíÁźÜŤß£„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„ÄāšľöÁ§ĺŤ®≠Áęč„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ÄĀťõáÁĒ®„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ITŚąÜťáé„ĀęÁČĻŚĆĖ„Āó„Āü„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑„āĄ„āĶ„ā§„Éź„Éľ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£„ÄĀťõĽŚ≠źŚēÜŚŹĖŚľē„ĀęťĖĘ„Āô„āčś≥ēŤ¶ŹŚą∂„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆ„ĀĆŤ§áťõĎ„ĀęÁĶ°„ĀŅŚźą„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀ„ā≥„ÉĘ„É≥„ÉĽ„É≠„Éľ„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹§šĺč„Āģťá捶ĀśÄß„āĄ„ÄĀÁīĄŚõ†„Āģś¶āŚŅĶ„ÄĀŚĺďś•≠Śď°„Ā®„ÉĮ„Éľ„āę„Éľ„ĀģŚĆļŚą•„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶Śé≥ś†ľ„Ā™„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑Ť¶ĀšĽ∂„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨šľĀś•≠„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶śĖį„Āü„Ā™Ť™≤ť°Ć„Ā®„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āď„āĆ„āČ„Āģś≥ēÁöĄŤ¶ĀÁāĻ„āíšļčŚČć„Āęśä䜏°„Āó„ÄĀťĀ©Śąá„Ā™ŚĮĺÁ≠Ė„ā퍨õ„Āė„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀšļąśúü„Āõ„Ā¨ś≥ēÁöĄ„É™„āĻ„āĮ„āíŚõěťĀŅ„Āó„ÄĀ„ā§„āģ„É™„āĻŚłāŚ†ī„Āß„Āģśąźťē∑„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô
„āŅ„āį: „ā§„āģ„É™„āĻśĶ∑Ś§Ėšļčś•≠