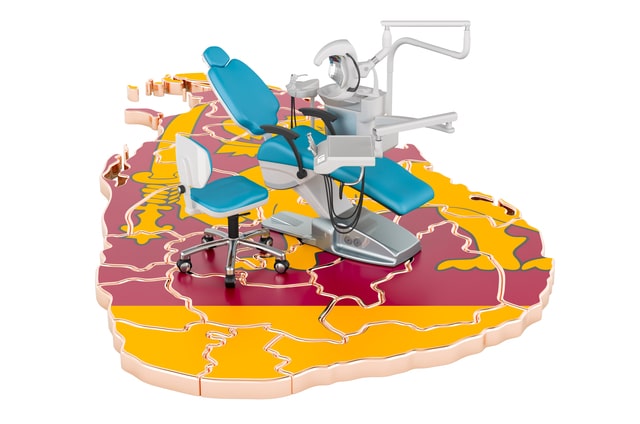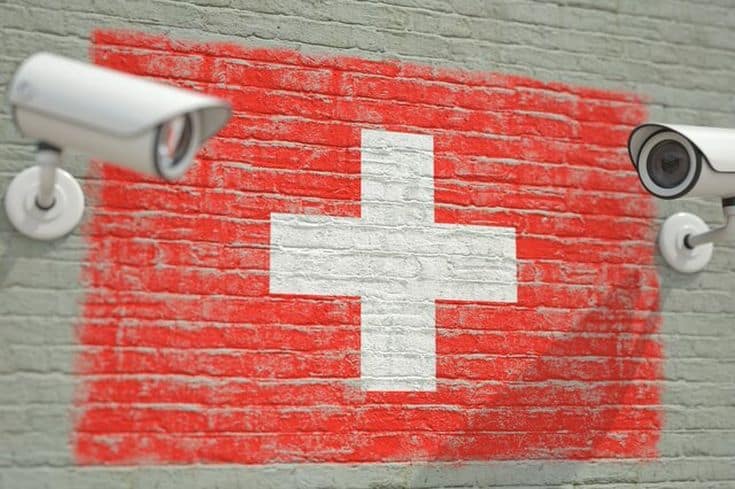ペルー共和国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

ペルー共和国は、南米大陸の西部に位置し、太平洋とアンデス山脈、アマゾンの広大なジャングルが織りなす多様な地理的特徴が、その経済構造に深く反映されています。古くから鉱業が経済の根幹をなし、現在でも銅、銀、金、亜鉛といった鉱物資源の生産において世界有数の地位を占めています。特に、カハマルカ近郊のヤナコチャ金鉱山のような大規模鉱山は、世界の主要な金の生産拠点の一つであり、鉱業は国家歳入に多大な貢献をしています。また、広大な海洋資源を活かした魚粉の輸出は1960年代から重要であり、近年ではコーヒーや綿花、アボカド、ブドウなどの高品質な農産物の輸出も盛んです。経済の多角化も進んでおり、近年は観光産業、金融サービス、電気通信といったサービスセクターが急速に成長し、労働人口の約60%を雇用しています。これらの産業の健全な発展は、ペルーの安定したマクロ経済環境と複数の自由貿易協定(FTA)に支えられています。
ペルーの法制度は、大陸法(civil law system)を基本とする大統領制の共和国です。その法体系は、日本と同じく成文法主義を根幹に据えており、企業法、労働法、契約法なども法典や法律によって明確に定められています。想定読者である日本の経営者や法務部員にとって、この大陸法という共通の法的背景は、英米法のような判例を重視する法体系とは異なり、比較的馴染みやすい枠組みであると言えます。しかし、細部においては、日本の法律には見られない独自の規定や、労働者保護を特に重視する原則など、重要な差異も存在します。
本記事では、ペルーでの事業展開を検討する上で不可欠な、これらの法律の全体像とその概要について解説します。
この記事の目次
ペルーの会社法と事業体の設立
このセクションでは、ペルーにおける会社設立の法的枠組みを、日本の法制度との比較を通じて詳細に解説します。
ペルーにおける主要な会社形態
ペルーの会社法は、「一般会社法(Ley General de Sociedades)」(Law N° 26887)によって包括的に規定されています。日本企業がペルーで事業活動を行う際、最も一般的に選択されるのは、有限責任が認められる株式会社(Sociedad Anónima)とその派生形態、あるいは有限責任会社(Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada)です。
株式会社(Sociedad Anónima – S.A.C., S.A.A.)は、日本の株式会社に最も近い形態です。株主は出資額を限度として責任を負い、その資本は株式によって構成されます。この形態には、事業規模や目的によってさらに細分化された種類があります。特に、小規模なビジネスや家族経営に適した閉鎖型株式会社(Sociedad Anónima Cerrada – S.A.C.)は、株主数が2名以上20名以下に制限されており、取締役会の設置が任意である点が大きな特徴です。一方、株式を公開して大規模な資金調達を行うことを目的とする公開型株式会社(Sociedad Anónima Abierta – S.A.A.)は、750名以上の株主を持つ場合や、株式の公募を行った場合、一定割合以上の株式が多数の株主に分散保有されている場合など、会社一般法上定められた条件のいずれかを満たすと該当します。
有限責任会社(Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)は、日本の合同会社に近い性質を持つ事業体です。この形態も構成員が2名以上20名以下で構成されますが、資本が株式ではなく「持ち分(participaciones)」に分割されるという点で異なります。これにより、株式譲渡の自由度が制限され、パートナーシップ型の事業に適しています。また、日本の法人がペルーに支店(Sucursal)を設立する場合、本社と同じ事業活動を行うことができ、独立した法人格は持たないものの、税務上は独立した納税主体として扱われます。これは、本社からの統制を維持しつつ事業を展開したい場合に適した選択肢です。
日本企業がペルーでの会社設立を検討する際に留意すべき重要な点は、株主・構成員の最低人数に関する要件です。日本の会社法では、2006年の会社法施行により、最低資本金制度が撤廃され、一人会社(株主が1名のみ)の設立が可能となりました。しかし、ペルーの会社法では、最も一般的な形態であるS.A.C.やS.R.L.の設立に最低2名の株主・構成員が要求されます。この前提は日本での事業経験を持つ経営者の感覚とは異なるため、ペルー進出を検討する際には、共同出資者を見つけるか、ペルー人または外国籍の代理人を株主として立てる(ノミニー・シェアホルダー)といった実務的対応が必要となります。この事実は、単独で事業をコントロールしたいと考える経営者にとって、設立段階での大きな障壁となり得るため、事前に正確な理解が不可欠です。
会社設立手続きのプロセス
ペルーでの会社設立は、複数の公的機関を通じた段階的なプロセスを経て行われます。まず、国立公的登記監督庁(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP)で商号の予約を行います。次に、会社の設立契約書となる定款(Minutes of Incorporation)を作成します。これには設立者、会社目的、機関設計などの詳細を記載し、弁護士の署名が必要です。
その後、会社名義の銀行口座を開設し、資本金を払い込みます。法律上の最低資本金は定められていませんが、実務上、銀行は特定の最低額(例:約4,300PEN)を要求する場合があります。株式の場合、額面価格の25%以上の払込が必要です。作成した定款は公証人(Notary Public)によって公証され、公的証書(public deed)としてSUNARPに登録されます。この登記をもって、会社が正式に設立されたと見なされます。最後に、国家税務監督庁(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT)から納税者番号(RUC)を取得し、事業活動が可能となります。
これらの手続きにおいて、外国籍の代表者の権限には特定の制限が課される可能性がある点に注意が必要です。SUNATのような特定の公的機関に対しては、外国籍の代表者の権限が制限される場合があります。このため、税務上の手続きや公的機関とのやり取りを円滑に進めるためには、ペルー在住の代理人(Peruvian proxy)を任命することが推奨されます。これは、外国投資を100%許可するというビジネスフレンドリーな姿勢と、国内の公的機関による管理を維持するという国家的な思惑の間のバランスを示しています。日本の経営者は、この「外国人所有は可能だが、実務は現地代理人が必要」という二段階の現実を理解した上で、体制を構築する必要があります。
ペルーと日本の主要会社形態の比較
ペルーと日本の会社形態は、その法的背景に共通性がある一方で、細部には重要な違いが存在します。事業展開を検討する上で、これらの差異を正確に把握することは、適切な事業体を選択する上で不可欠です。以下に、主要な会社形態の比較をまとめます。
| ペルーの閉鎖型株式会社(S.A.C.) | ペルーの有限責任会社(S.R.L.) | 日本の株式会社 | 日本の合同会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 法的根拠 | 一般会社法(Ley General de Sociedades) | 一般会社法 | 会社法 | 会社法 |
| 株主/社員の 最低・最大人数 | 最低2名、最大20名 | 最低2名、最大20名 | 最低1名 | 最低1名 |
| 責任形態 | 有限責任(出資額を限度) | 有限責任(出資額を限度) | 有限責任(出資額を限度) | 有限責任(出資額を限度) |
| 資本形態 | 株式 | 持ち分(participaciones) | 株式 | 持ち分 |
| 取締役会設置 | 任意 | 不要 | 必須(非公開会社は取締役1名) | 不要 |
| 代表者 | 総支配人(General Manager) | 1名以上の支配人(managers) | 代表取締役 | 業務執行社員 |
ペルー労働法の概要と雇用管理の留意点

このセクションでは、ペルーの労働法を深く掘り下げ、特に雇用終了時のリスク管理に焦点を当てます。
ペルー労働法の基本原則と特徴
ペルーの労働法は、1997年の「労働生産性・競争力法(Ley de Productividad y Competitividad Laboral – LPCL)」の統一法(Decreto Supremo N° 003-97-TR)を中核としています。この法律の最も重要な原則は、労働者保護主義です。これは、雇用者と労働者の間の構造的な不平等を是正することを目的としており、法律の解釈に疑義がある場合は労働者に有利に解釈されるという「in dubio pro operario」原則に象徴されます。
ペルー法では、労働契約は明示的に有期契約とされない限り、無期雇用契約であることが推定されます。この推定を覆すためには、有期雇用契約を明確に書面で締結し、その一時的な性質を客観的な理由(例:市場の需要増、新規事業立ち上げなど)によって正当化する必要があります。有期契約は最長5年間で、労働省への登録が義務付けられています。
一般的な試用期間は3ヶ月ですが、管理職や高度な技能を要する職務では最大6ヶ月、経営陣では最大1年まで延長が可能です。法定労働時間は、週48時間または1日8時間が最大値です。ペルー独自の重要な福利厚生として、7月と12月に支払われるボーナス(gratificación)があり、それぞれ1ヶ月分の給与に相当する額の支払いが義務付けられています。また、失業保険に類似した勤続期間補償金(Compensación por Tiempo de Servicios – CTS)の制度があり、雇用主は年に2回、従業員名義の銀行口座に積立を義務付けられています。
外国人労働者の雇用には厳格な規制があり、原則として、全従業員の20%以下、かつ総賃金総額の30%以下でなければなりません。これは、日本の外国人雇用政策と比較して非常に厳格な数値であり、駐在員を多数派遣して事業を立ち上げようとする日本企業にとって、大きな制約となり得ます。
解雇と雇用終了の法的枠組み
日本と同様、ペルーの労働者は安易な解雇から保護されています。雇用関係を終了させるためには、解雇に「公正な理由(just cause)」が存在しなければなりません。この公正な理由には、労働者の能力不足(勤務態度の著しい不良など)または重大な過失(不正行為、重大な不服従、刑事上の有罪判決など)が含まれます。
上記の公正な理由がないまま労働者を解雇した場合、それは「不当解雇」と見なされ、雇用主は労働者に対し、高額な補償金を支払う義務を負います。この補償金は、勤続年数1年につき月給の1.5ヶ月分と定められており、上限は月給12ヶ月分です。有期契約の場合でも、期間満了前に解雇した場合は、残存期間の月数に1.5ヶ月分を乗じた額を支払う必要があります。
ペルーの労働法は、一見すると日本の労働法と類似した部分が多いものの、その根底にある「労働者保護主義」の徹底ぶりと、不当解雇に対する補償金の計算方法が法律で明確に定められている点で、実務上のリスクが大きく異なります。日本の経営者は「解雇は難しい」という認識を持っているものの、そのリスクは通常、裁判所による解雇無効判決や和解金といった形で現れ、金額が明確でない場合が多いです。一方、ペルーでは、不当解雇が認定されると、法律で定められた計算式に基づき、最高で月給12ヶ月分という具体的な金額の支払い義務が発生します。この金銭的リスクの明確さと高額さは、日本企業にとって重大な経営上の考慮事項となります。したがって、ペルーで事業を行う際には、労働者の重大な過失を証明するための厳密な人事管理と、証拠を保全するプロセスが極めて重要となります。
ペルーと日本の雇用終了制度の比較
解雇は、特に人事制度や労務管理の文化が異なる国で事業を行う際の最大の関心事の一つです。以下の比較表を通じて、ペルーと日本の雇用終了制度の重要な差異を明確に示します。
| ペルー法 | 日本法 | 重要な差異と留意点 | |
|---|---|---|---|
| 解雇理由 | 「公正な理由」(just cause)が必須。能力不足、重大な過失など。 | 「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要。 | ペルー法は法律で具体的な理由が列挙されている。 |
| 解雇手続き | 重大な過失による解雇の場合、弁明機会付与の通知書を送付し、6日以上の弁明期間を与える。 | 法令上の明確な規定はないが、判例上、弁明機会の付与が求められる。 | ペルー法では、弁明機会の付与が法律で定められた明確な手続きとなっている。 |
| 不当解雇補償金 | 法律で明確に金額が規定されている。無期契約の場合、勤続年数1年につき月給の1.5ヶ月分(上限12ヶ月分)。有期契約の場合には、残存契約期間に応じて同率の補償。 | 法令上の明確な規定はなく、裁判所の判断により解雇無効や金銭和解となる。 | ペルーでは、不当解雇が認定されると、最高で月給12ヶ月分という高額かつ具体的な金額の支払い義務が発生する。この金銭的リスクは日本より明確かつ高額である。 |
| 法定ボーナス | 7月と12月に、それぞれ1ヶ月分の給与に相当するボーナスの支払いが義務。 | 法定の義務はない(賞与は任意)。 | ペルーでは、ボーナスが法定の義務であるため、労務費の計算に組み込む必要がある。 |
| 退職金制度 | 勤続期間補償金(CTS)の積立が義務付けられている。 | 法定の義務はない。 | 退職金に類似した制度が法的に義務付けられており、労務費として考慮が必要となる。 |
ペルーの契約法
ペルーの契約法は、民法(Código Civil)によって規定されています。この法体系は、日本法と同じく、契約の基本原則として「当事者の意思自治」と「pacta sunt servanda(約束は守られなければならない)」を尊重します。契約が有効に成立するためには、相互の合意、法的能力、そして合法的な目的が要件とされます。これらの成立要件は、日本の民法における要件と本質的に同じです。
鉱業分野における法規制

鉱業法制の概要
鉱業は、ペルー経済にとって非常に重要な産業です。そして、ペルーにおける鉱業活動は、鉱業全般法(Ley General de Minería)(Decreto Supremo N° 014-92-EM)によって厳格に管理されています。政府は、鉱業活動に必要な複数のコンセッション(concession)を付与しています。主なコンセッションには、鉱物資源の探査・採掘権を付与する鉱業コンセッション、選鉱・精錬権を付与する選鉱コンセッション、鉱物の輸送権を付与する輸送コンセッションなどがあります。これらのコンセッションは、鉱業活動を規制するだけでなく、環境保護や地域社会との関係構築も考慮して設計されています。
地表権と地下資源権の分離
日本法との最も重要な違いの一つは、ペルーでは土地の所有権(地表権)と、その地下に存在する鉱物資源の所有権(地下資源権)が法的に分離している点です。地下資源は、その地表の所有者に関わらず、国家が所有するものと見なされます。これは、鉱業コンセッションが「物権(real right)」であり、国家から探査・採掘の権利を付与されるものの、これは地表の所有権を意味しないという法的構造に由来します。
この法的構造は、鉱山開発を計画する日本企業にとって、予期せぬ問題を発生させる可能性があります。日本の法律では、土地の所有権はその土地の上下に及び、通常、地主が地下資源(温泉など)の所有権も有します。しかし、ペルーでは、たとえ地表の土地を所有していても、その地下にある鉱物資源は国家のものであるため、鉱山開発を行う事業者は、鉱業コンセッションを取得した後も、採掘活動に必要な施設(道路、パイプラインなど)を建設するために、地表の所有者から土地利用権(easement)を別途、補償金を支払って確保しなければなりません。さらに、鉱業活動を開始するためには、鉱業コンセッションの取得だけでなく、環境影響評価の承認(Declaración de Impacto Ambiental)や、関係する地域社会との事前協議など、複数の追加的要件をクリアする必要があります。この多段階のプロセスは、コンセッション取得から実際の事業開始までの期間を長期化させ、投資リスクを高める要因となり得ます。
まとめ
本記事では、ペルーへの事業展開を検討する日本企業の皆様に向け、会社設立、労働、契約、そして主要産業である鉱業における法制度の概略を解説しました。ペルーは、日本と共通の大陸法体系を持つ一方で、会社設立における株主要件、労働法における厳格な労働者保護原則と高額な不当解雇補償、そして鉱業における地表権と地下資源権の分離など、日本の法務感覚とは異なる重要な相違点が存在します。これらの差異を正確に理解し、適切に対応することが、ペルーでのビジネスを成功に導くための鍵となります。
関連取扱分野:
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務