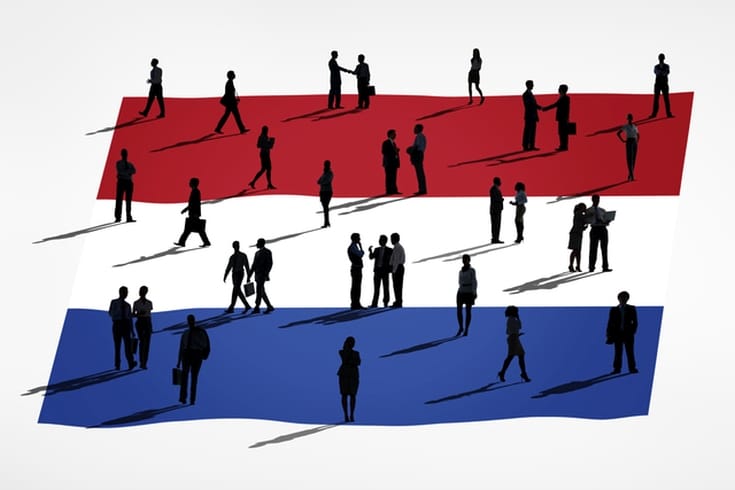Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü«Õģ©õĮōÕāÅŃü©ŃüØŃü«µ”éĶ”üŃéÆÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüīĶ¦ŻĶ¬¼

Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü»ŃĆüÕīŚµ¼¦Ńü«ń½ŗµå▓ÕÉøõĖ╗ÕøĮŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ń┤ä1.2ÕĆŹŃü«ķØóń®ŹŃéƵīüŃüżÕ║āÕż¦Ńü¬ÕøĮÕ£¤Ńü½ŃĆüń┤ä1,055õĖćõ║║Ńü«õ║║ÕÅŻŃéƵōüŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķ”¢ķāĮŃé╣ŃāłŃāāŃé»ŃāøŃā½ŃāĀŃü»ŃĆüŃéżŃāÄŃāÖŃā╝ŃéĘŃā¦Ńā│Ńü©µīüńČÜÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃéÆķćŹĶ”¢ŃüÖŃéŗŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ńÆ░ÕóāŃü«õĖŁÕ┐āÕ£░Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕżÜŃüÅŃü«µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīµ¢░Ńü¤Ńü¬ÕĖéÕĀ┤µ®¤õ╝ÜŃéƵ▒éŃéüŃü”µ│©ńø«ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃéƵłÉÕŖ¤ŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ńŗ¼ńē╣Ńü¬µ│ĢÕłČÕ║”Ńü©ÕĢåń┐ƵģŻŃéƵĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«Õģ©õĮōÕāÅŃéƵ”éĶ¬¼ŃüŚŃüżŃüżŃĆüńē╣Ńü½ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńü½ńø┤ńĄÉŃüÖŃéŗÕłåķćÄŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü¤ķÜøŃü«ńē╣ÕŠ┤ńÜäŃü¬ńøĖķüĢńé╣ŃéäķćŹĶ”üŃü¬ńĢÖµäÅńé╣ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«Õģ©õĮōÕāÅŃü©ÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”
µ│ĢõĮōń│╗Ńü«Õ¤║µ£¼ÕĤÕēćŃü©µ│Ģµ║É
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©ÕÉīµ¦śŃü½Õż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü«õ╝ØńĄ▒ŃéƵīüŃüżÕøĮŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüµłÉµ¢ćµ│ĢŃüīõĖ╗Ķ”üŃü¬µ│Ģµ║ÉŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŁÕ┐āńÜäŃü¬µ│Ģõ╗żķøåŃü»ŃĆüÕøĮõ╝Ü’╝łRiksdagen’╝ēŃüīÕłČÕ«ÜŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗ’╝łLaws’╝ēŃü©µö┐Õ║£’╝łRegeringen’╝ēŃüīÕłČÕ«ÜŃüÖŃéŗÕæĮõ╗ż’╝łOrdinances’╝ēŃü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃéŗŃĆÄSvensk F├ČrfattningssamlingŃĆÅ’╝łSFS’╝ēŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«SFSŃü»ŃĆü1925Õ╣┤õ╗źķÖŹŃĆüµ»ÄÕ╣┤õĮōń│╗ńÜäŃü½Õć║ńēłŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµ£Ćµ¢░ńēłŃü»ķø╗ÕŁÉńÜäŃü½Õģ¼ķ¢ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«µ│ĢÕŠŗÕ«ČŃüīŃĆīµ░æµ│ĢŃĆŹŃéäŃĆīÕĢåµ│ĢŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ńĄ▒õĖĆńÜäŃü¬µ│ĢÕģĖŃéÆÕ¤║ńżÄŃü©ŃüŚŃü”µ│ĢõĮōń│╗ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü½Ńü»ŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬Õīģµŗ¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕģĖŃü»ÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüØŃü«õ╗ŻŃéÅŃéŖŃü½ŃĆüŃĆīÕźæń┤äµ│ĢŃĆŹ’╝łSFS 1915:218’╝ēŃéäŃĆīÕŻ▓Ķ▓ʵ│ĢŃĆŹ’╝łSFS 1990:931’╝ēŃü¬Ńü®ŃĆüÕÉäÕłåķćÄŃéÆÕĆŗÕłźŃü½Ķ”ÅÕŠŗŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗŃüīÕżÜµĢ░ÕŁśÕ£©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µ¦ŗķĆĀŃü©ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń©«ķĪ×
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«ÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüõĖĆĶł¼ĶŻüÕłżµēĆŃĆüĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃĆüŃüŖŃéłŃü│Õ░éķ¢ĆĶŻüÕłżµēĆŃü«õĖēŃüżŃü½Õż¦ÕłźŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõĖĆĶł¼ĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüÕ£░µ¢╣ĶŻüÕłżµēĆ’╝łDistrict Courts’╝ēŃĆüµÄ¦Ķ©┤ĶŻüÕłżµēĆ’╝łCourts of Appeal’╝ēŃĆüŃüŖŃéłŃü│µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆ’╝łSupreme Court’╝ēŃü«õĖēÕ»®ÕłČŃü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣ńŁåŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüń¤źńÜäĶ▓ĪńöŻµ©®’╝łIPR’╝ēŃĆüń½Čõ║ēµ│ĢŃĆüŃā×Ńā╝Ńé▒ŃāåŃéŻŃā│Ńé░µ│ĢŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ńē╣Õ«ÜŃü«ÕłåķćÄŃéÆÕ░éķ¢ĆńÜäŃü½µē▒ŃüåĶŻüÕłżµēĆŃüīÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆé2016Õ╣┤Ńü½Ķ©Łń½ŗŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīńē╣Ķ©▒Ńā╗ÕĖéÕĀ┤ĶŻüÕłżµēĆŃĆŹ’╝łPatent and Market Court’╝ēŃü»ŃĆüńē╣Ķ©▒õŠĄÕ«│ŃüŖŃéłŃü│ńäĪÕŖ╣Ķ©┤Ķ©¤ŃéÆÕɽŃéĆŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«Õ░éķ¢ĆÕłåķćÄŃü½ŃüŖŃüæŃéŗń¼¼õĖĆÕ»®Ńü«ĶŻüÕłżń«ĪĶĮäŃéÆńŗ¼ÕŹĀńÜäŃü½µ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüŃé╣ŃāłŃāāŃé»ŃāøŃā½ŃāĀÕ£░µ¢╣ĶŻüÕłżµēĆŃü«Õ░éķ¢Ćķā©ķ¢ĆŃü©ŃüŚŃü”Ķ©ŁńĮ«ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµ│ĢńÜäŃü¬ĶŻüÕłżÕ«śŃü½ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüµŖĆĶĪōńÜäŃü¬ń¤źĶ”ŗŃéƵīüŃüżĶŻüÕłżÕ«śŃüīŃāæŃāŹŃā½ŃéƵ¦ŗµłÉŃüÖŃéŗńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆé
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«õ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃü©Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣

õ╝ÜńżŠÕĮóµģŗŃü«ķüĖµŖ×Ńü©Ķ©Łń½ŗµēŗńČÜŃüŹ
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü¦õ║ŗµźŁŃéÆĶĪīŃüåÕż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü»ŃĆüõĖ╗Ńü½µ£ēķÖÉĶ▓¼õ╗╗õ╝ÜńżŠ’╝łaktiebolagŃĆüAB’╝ēŃüŠŃü¤Ńü»µö»Õ║Ś’╝łFilial’╝ēŃü«ŃüäŃüÜŃéīŃüŗŃü«ÕĮóµģŗŃéÆķüĖµŖ×Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
- µ£ēķÖÉĶ▓¼õ╗╗õ╝ÜńżŠ’╝łAktiebolag’╝ē’╝Üńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ│Ģõ║║µĀ╝ŃéƵ£ēŃüŚŃĆüµĀ¬õĖ╗Ńü«µ│ĢńÜäĶ▓¼õ╗╗Ńü»Õć║Ķ│ćķĪŹŃü½ķÖÉÕ«ÜŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéµ£ĆõĮÄĶ│ćµ£¼ķćæŃü»25,000Ńé»ŃāŁŃā╝ŃāŖ’╝łń┤ä35õĖćÕåå’╝ēŃü©ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃü½µ£ĆõĮÄĶ│ćµ£¼ķćæŃü«Õ«ÜŃéüŃüīŃü¬ŃüäŃüōŃü©Ńü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”ŃééŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½õĮÄŃüäµ░┤µ║¢Ńü¦ŃüÖŃĆéĶ©Łń½ŗŃü½Ńü»ŃĆüńÅŠķćæŃüŠŃü¤Ńü»õ║ŗµźŁŃü½µ£ēńö©Ńü¬Ķ▓ĪńöŻŃéÆĶ│ćµ£¼ķćæŃü©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃĆüիܵ¼ŠŃü«õĮ£µłÉŃéäÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«õ╗╗ÕæĮŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéÕ╣┤µ¼ĪÕĀ▒ÕæŖµøĖŃü«õĮ£µłÉŃü©µÅÉÕć║ŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
- µö»Õ║Ś’╝łFilial’╝ē’╝ÜÕż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü«Õć║Õģłµ®¤ķ¢óŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃĆüµ│ĢńÜäĶ▓¼õ╗╗Ńü»ńø┤µÄźĶ”¬õ╝ÜńżŠŃüīĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶ│ćµ£¼ķćæŃü»õĖŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü«ńøŻµ¤╗µĖłŃü┐Õ╣┤µ¼ĪÕĀ▒ÕæŖµøĖŃü«µÅÉÕć║ŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠµ│Ģ’╝łSwedish Companies Act’╝ēŃü©ŃĆÄŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńā╗Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃā╗Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńā╗Ńé│Ńā╝ŃāēŃĆÅ’╝łSwedish Corporate Governance Code’╝ēŃüīõĖŁÕ┐āńÜäŃü¬µ×ĀńĄäŃü┐ŃéÆÕĮóµłÉŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüŃüōŃü«Ńé│Ńā╝ŃāēŃü»ŃĆīComply or ExplainŃĆŹ’╝łķüĄÕ«łŃüÖŃéŗŃüŗŃĆüĶ¬¼µśÄŃüøŃéł’╝ēŃü©ŃüäŃüåÕĤÕēćŃéƵÄ▓ŃüÆŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»ŃĆüõĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüŃé│Ńā╝ŃāēŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃéÆķüĄÕ«łŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéƵ▒éŃéüŃéŗõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüŃééŃüŚķüĄÕ«łŃüŚŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ńÉåńö▒Ńü©õ╗Żµø┐µÄ¬ńĮ«ŃéƵĀ¬õĖ╗ŃéäÕĖéÕĀ┤ÕÅéÕŖĀĶĆģŃü½µśÄńó║Ńü½Ķ¬¼µśÄŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗõ║īŃüżŃü«ķĪĢĶæŚŃü¬ńē╣ÕŠ┤ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖĆŃüżŃü»ŃĆüĶŁ░µ▒║µ©®ŃüīÕłČķÖÉŃüĢŃéīŃü¤õ║īķćŹŃé»Ńā®Ńé╣µĀ¬Õ╝ÅŃéÆÕ║āŃüÅÕł®ńö©ŃüŚŃĆüÕēĄµźŁÕ«ČŃéäÕ«ČµŚÅńĄīÕ¢ČŃü«µö»ķģŹµ©®ŃüīńČŁµīüŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗõ╝üµźŁŃüīÕżÜµĢ░ÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆéŃééŃüåõĖĆŃüżŃü»ŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģõ╗ŻĶĪ©ŃüīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü½ÕÅéÕŖĀŃüÖŃéŗŃĆīÕģ▒ÕÉīµ▒║Õ«ÜŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃĆŹŃüīµ│ĢńÜäŃü½ÕłČÕ║”Õī¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆéõĖĆĶł¼Ńü½õĖĆÕ«ÜĶ”ŵ©Ī’╝łõŠŗ’╝ÜÕ╣│ÕØć25õ║║õ╗źõĖŖķøćńö©ńŁē’╝ēŃü«Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüÕŖ┤ÕāŹńĄäÕÉłńŁēŃéÆķĆÜŃüśŃü”ÕŠōµźŁÕōĪõ╗ŻĶĪ©ŃüīķüĖõ╗╗ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃéÆÕɽŃéĆÕ╣ģÕ║āŃüäŃé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü«Õł®ńøŖŃéÆńĄīÕ¢ČÕłżµ¢ŁŃü½ÕÅŹµśĀŃüĢŃüøŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
µĄĘÕż¢ŃüŗŃéēŃü«Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│ŃüĖŃü«µŖĢĶ│ćĶ”ÅÕłČ
Õż¢ÕøĮńø┤µÄźµŖĢĶ│ćµ│Ģ’╝łFDI Act’╝ēŃü«µ”éĶ”ü
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü»ŃĆüķĢĘŃéēŃüÅÕż¢Ķ│ćŃü½Õ»øÕ«╣Ńü¬ÕøĮŃü©ŃüŚŃü”ń¤źŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü2023Õ╣┤12µ£ł1µŚźŃéłŃéŖŃĆüÕż¢ÕøĮńø┤µÄźµŖĢĶ│ćµ│Ģ’╝łFDI Act, Lag (2023:560) om granskning av utl├żndska direktinvesteringar’╝ēŃéƵ¢ĮĶĪīŃüŚŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü¬µŖĢĶ│ćÕ»®µ¤╗ÕłČÕ║”ŃéÆÕ░ÄÕģźŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«µ│ĢÕŠŗŃü«ńø«ńÜäŃü»ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«Õ«ēÕģ©õ┐ØķÜ£ŃĆüÕģ¼Ńü«Õ«ēÕģ©ŃĆüÕģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µ│ĢÕŠŗŃü»ŃĆüÕŹśŃü½Ķ╗Źõ║ŗķ¢óķĆŻŃü«õ║ŗµźŁŃéÆÕ»ŠĶ▒ĪŃü©ŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃĆīõ┐ØĶŁĘŃü½ÕĆżŃüÖŃéŗµ┤╗ÕŗĢŃĆŹ’╝łactivities worth protecting’╝ēŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«7ŃüżŃü«Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝ŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆé
- Õ¤║Õ╣╣ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣’╝ÜŃéżŃā│ŃāĢŃā®ŃĆüŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃĆüÕī╗ńÖéŃĆüķŻ¤ń│¦õŠøńĄ”ŃāüŃé¦Ńā╝Ńā│Ńü¬Ńü®ŃĆüÕżÜÕ▓ÉŃü½ŃéÅŃü¤ŃéŗńöŻµźŁŃĆé
- ÕøĮÕ«ČÕ«ēÕģ©õ┐ØķÜ£õĖŖŃü«µ®¤ÕŠ«Ńü¬µ┤╗ÕŗĢ’╝ÜĶ╗Źõ║ŗµ┤╗ÕŗĢŃĆüń®║µĖ»ŃĆüńÖ║ķø╗µēĆŃü¬Ńü®ŃĆé
- Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│ŃüŖŃéłŃü│EUŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ķćŹĶ”üŃü¬ÕĤµØɵ¢Ö
- µ®¤ÕŠ«Ńü¬ÕĆŗõ║║ŃāćŃā╝Ńé┐ŃüŠŃü¤Ńü»õĮŹńĮ«µāģÕĀ▒Ńü«Õć”ńÉå’╝ÜŃé»Ńā®Ńé”ŃāēŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣µÅÉõŠøĶĆģŃéäŃāćŃā╝Ńé┐Ńā¢ŃāŁŃā╝Ńé½Ńā╝Ńü¬Ńü®ŃüīÕɽŃüŠŃéīŃéŗŃĆé
- µ¢░ĶłłµŖĆĶĪōŃüŖŃéłŃü│ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«µł”ńĢźńÜäµŖĆĶĪō’╝ÜÕÄ¤ÕŁÉÕŖøµŖĆĶĪōŃĆüĶł¬ń®║ķø╗ÕŁÉµ®¤ÕÖ©ŃĆüŃéĮŃāĢŃāłŃé”Ńé¦ŃéóŃü¬Ńü®ŃĆé
- Ķ╗Źµ░æõĖĪńö©ĶŻĮÕōü
- Ķ╗Źõ║ŗĶŻģÕéÖÕōü
ńē╣Ńü½ńĢÖµäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆü4ńĢ¬ńø«Ńü«ŃĆīµ®¤ÕŠ«Ńü¬ÕĆŗõ║║ŃāćŃā╝Ńé┐ŃüŠŃü¤Ńü»õĮŹńĮ«µāģÕĀ▒Ńü«Õć”ńÉåŃĆŹŃüīõ┐ØĶŁĘÕ»ŠĶ▒ĪŃü½ÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆé
µŖĢĶ│ćÕ»®µ¤╗ŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü©ńĮ░Õēć
FDIµ│ĢŃü«ķü®ńö©Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗµŖĢĶ│ćÕ«ČŃü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«õ║ŗµźŁŃéÆĶĪīŃüåõ╝üµźŁŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ĶŁ░µ▒║µ©®Ńü«10%ŃĆü20%ŃĆü30%ŃĆü50’╝ģŃü¬Ńü®Ńü«µ«ĄķÜÄńÜäŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤ķ¢ŠÕĆżŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüµł”ńĢźńÜäĶŻĮÕōüńøŻńØŻÕ║ü’╝łInspektoratet f├Čr Strategiska Produkter, ISP’╝ēŃüĖŃü«õ║ŗÕēŹķĆÜń¤źńŠ®ÕŗÖŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ķĆÜń¤źńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüµŚźµ£¼ŃüŗŃéēŃü«µŖĢĶ│ćÕ«ČŃéÆÕɽŃéĆEUÕ¤¤Õż¢Ńü«µŖĢĶ│ćÕ«ČŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüEUÕ¤¤ÕåģŃüŖŃéłŃü│Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│ÕøĮÕåģŃü«µŖĢĶ│ćÕ«ČŃü½ŃééĶ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆé
ķĆÜń¤źÕŠīŃĆüISPŃü»25Õ¢ČµźŁµŚźõ╗źÕåģŃü½Õ»®µ¤╗ŃéÆÕ«īõ║åŃüŚŃĆüÕ┐ģĶ”üŃü½Õ┐£ŃüśŃü”3Ńāȵ£łõ╗źÕåģŃü«Ķ®│ń┤░Ķ¬┐µ¤╗’╝łŃāĢŃé¦Ńā╝Ńé║II’╝ēŃéÆķ¢ŗÕ¦ŗŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéĶ®│ń┤░Ķ¬┐µ¤╗Ńü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«ńŖȵ│üõĖŗŃü¦ŃüĢŃéēŃü½6Ńāȵ£łŃüŠŃü¦Õ╗ČķĢĘŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕ»®µ¤╗Ńü«ńĄÉµ×£ŃĆüµŖĢĶ│ćŃüīÕ«ēÕģ©õ┐ØķÜ£õĖŖŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüÖŃü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüISPŃü»µŖĢĶ│ćŃéƵē┐Ķ¬ŹŃüŚŃü¬ŃüäŃüŗŃĆüµØĪõ╗ČŃéÆõ╗śŃüÖŃüŗŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õ«īÕģ©Ńü½ń”üµŁóŃüÖŃéŗµ©®ķÖÉŃéƵ£ēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéķĆÜń¤źńŠ®ÕŗÖŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµ£ĆÕż¦1ÕääŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńā╗Ńé»ŃāŁŃā╝ŃāŖ’╝łń┤ä15ÕääÕåå’╝ēŃü«ĶĪīµö┐ńĮ░ķćæŃüīń¦æŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«Õ║āÕæŖĶ”ÅÕłČŃü©ŃĆÄŃā×Ńā╝Ńé▒ŃāåŃéŻŃā│Ńé░µģŻĶĪīµ│ĢŃĆÅ
µŚźµ£¼Ńü«µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü½Ńü»ŃĆÄŃā×Ńā╝Ńé▒ŃāåŃéŻŃā│Ńé░µģŻĶĪīµ│ĢŃĆÅ’╝łMarketing Practices Act’╝ēŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕÉīµ│ĢŃü»ŃĆüÕģ¼µŁŻŃü¬Ńā×Ńā╝Ńé▒ŃāåŃéŻŃā│Ńé░µģŻĶĪīŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃĆüõĖŹµŁŻŃĆüĶ¬żĶ¦ŻŃéƵŗøŃüÅŃĆüµö╗µÆāńÜäŃü¬Õ║āÕæŖŃéÆń”üµŁóŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢÕŠŗŃü»ŃĆüµČłĶ▓╗ĶĆģÕ║üŃü©µČłĶ▓╗ĶĆģŃé¬Ńā│Ńā¢Ńé║Ńā×Ńā│’╝łConsumer Ombudsman’╝ēŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ¤ĘĶĪīŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÉīµ│ĢŃü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬µ¦śŃĆģŃü¬õĖŹÕģ¼µŁŻŃü¬ÕĢåµģŻĶĪīŃéÆń”üµŁóŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
- ĶÖÜÕüĮÕ║āÕæŖŃéäĶ¬żĶ¦ŻŃéƵŗøŃüÅÕ║āÕæŖ’╝ÜĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕōüĶ│¬ŃĆüÕŖ╣ĶāĮŃĆüńē╣ÕŠ┤Ńü½ŃüżŃüäŃü”ĶÖÜÕüĮŃüŠŃü¤Ńü»Ķ¬żĶ¦ŻŃéƵŗøŃüÅõĖ╗Õ╝ĄŃéÆŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃĆé
- õĖŹÕĮōŃü¬õŠĪµĀ╝ĶĪ©ńż║’╝ÜĶ¬żĶ¦ŻŃéƵŗøŃüÅŃéłŃüåŃü¬ķ½śÕĆżŃüŗŃéēŃü«Õē▓Õ╝ĢĶĪ©ńż║ŃéäŃĆüŃāēŃā¬ŃāāŃāŚŃā╗ŃāŚŃā®ŃéżŃéĘŃā│Ńé░’╝łĶ│╝ÕģźµēŗńČÜŃüŹŃü«µ£ĆńĄéµ«ĄķÜÄŃü¦µ¢░Ńü¤Ńü¬ķØ×ķüĖµŖ×Õ╝ÅŃü«µ¢ÖķćæŃéÆĶ┐ĮÕŖĀŃüÖŃéŗŃüōŃü©’╝ēŃü¬Ńü®Ńü«µģŻĶĪīŃĆé
- µ¼║ń××ńÜäŃü¬Ńā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāĢŃé¦Ńā╝Ńé╣’╝łŃāĆŃā╝Ńé»ŃāæŃé┐Ńā╝Ńā│’╝ē’╝ÜÕüĮŃü«ŃĆīÕŻ▓ŃéŖÕłćŃéīķ¢ōĶ┐æŃĆŹĶĪ©ńż║ŃéäŃĆüŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ŃéŁŃāŻŃā│Ńé╗Ńā½ŃéÆÕø░ķøŻŃü½ŃüÖŃéŗŃéłŃüåŃü¬Ķ©ŁĶ©łŃü¬Ńü®ŃĆüµČłĶ▓╗ĶĆģŃü«µäŵĆص▒║Õ«ÜŃéƵōŹŃéŗŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāĢŃé¦Ńā╝Ńé╣ŃĆé
- Ńé╣ŃāåŃā½Ńé╣Ńā×Ńā╝Ńé▒ŃāåŃéŻŃā│Ńé░’╝ÜÕ║āÕæŖŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵśÄńó║Ńü½ŃüŚŃü¬ŃüäÕ║āÕæŖŃĆüõŠŗŃüłŃü░AIŃüīńö¤µłÉŃüŚŃü¤ĶŻĮÕōüŃā¼ŃāōŃāźŃā╝ŃéäŃĆüõ║║ķ¢ōŃü½ŃéłŃéŗŃā¼ŃāōŃāźŃā╝Ńü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Ķ¬żĶ¦ŻŃüĢŃüøŃéŗŃéłŃüåŃü¬Ńé│Ńā│ŃāåŃā│ŃāäŃĆ鵌źµ£¼Ńü«µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü¦ŃééŃé╣ŃāåŃā½Ńé╣Ńā×Ńā╝Ńé▒ŃāåŃéŻŃā│Ńé░ŃüīĶ”ÅÕłČŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü¦Ńü»ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüAIńö¤µłÉŃé│Ńā│ŃāåŃā│ŃāäŃü«ķĆŵśÄµĆ¦ńó║õ┐ØŃüīńē╣Ńü½µ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- µö╗µÆāńÜäŃé╗Ńā╝Ńā½Ńé╣’╝ܵȳĶ▓╗ĶĆģŃü½õĖŹÕĮōŃü¬Õ£¦ÕŖøŃéÆŃüŗŃüæŃü¤ŃéŖŃĆüÕ╝ĘÕłČńÜäŃü½Ķ│╝ÕģźŃüĢŃüøŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃé╗Ńā╝Ńā½Ńé╣µł”ĶĪōŃĆé
ńĢÖµäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│µČłĶ▓╗ĶĆģÕ║üŃü»µŚóÕŁśŃü«µČłĶ▓╗ĶĆģõ┐ØĶŁĘµ│ĢŃü«µ×ĀńĄäŃü┐ŃéÆAIŃü½Ńééķü®ńö©ŃüÖŃéŗµ¢╣ķćØŃéƵÄ▓ŃüÆŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüAIŃüīńö¤µłÉŃüŚŃü¤ĶŻĮÕōüŃā¼ŃāōŃāźŃā╝ŃéäÕ║āÕæŖŃé│Ńā│ŃāåŃā│ŃāäŃüīŃĆüõ║║ķ¢ōŃü½ŃéłŃéŗŃééŃü«Ńü©Ķ¬żĶ¦ŻŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«õ║ŗÕ«¤ŃéƵśÄńż║ŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÉīµ│ĢŃü»µö╣µŁŻµ│ĢŃüī2022Õ╣┤7µ£ł1µŚźŃü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃĆüķüĢÕÅŹŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüõ║ŗµźŁĶĆģŃü»ŃĆüķüĢµ│ĢŃü¬Ńā×Ńā╝Ńé▒ŃāåŃéŻŃā│Ńé░Ńü«ńČÖńČÜŃéÆń”üµŁóŃüÖŃéŗÕæĮõ╗żŃéäµāģÕĀ▒µÅÉõŠøÕæĮõ╗żńŁēŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«ÕæĮõ╗żŃü»ÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ķüĢÕÅŹµÖéŃü½µö»µēĢŃüåķ¢ōµÄźÕ╝ĘÕłČķćæ’╝łvite’╝ēŃéÆõ╝┤ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüõĖĆÕ«ÜŃü«ķüĢÕÅŹŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃüīÕĖéÕĀ┤µĘĘõ╣▒Ķ│”Ķ¬▓ķćæ’╝łmarknadsst├Črningsavgift’╝ēŃü«µö»µēĢŃüäŃéÆÕæĮŃüśŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«ķĪŹŃü»µ£ĆõĮÄ1õĖćSEKŃĆüõĖŖķÖÉŃü»ÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”õ║ŗµźŁĶĆģŃü«ÕŻ▓õĖŖķ½śŃü«µ£ĆÕż¦4%ŃĆüÕŻ▓õĖŖķ½śŃü«µāģÕĀ▒Ńüīµ¼ĀŃüæŃéŗńŁēŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»µ£ĆÕż¦200õĖćŃā”Ńā╝ŃāŁńøĖÕĮōķĪŹ’╝łSEKµÅøń«Ś’╝ēŃü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüÕÉīµ│ĢŃü»õĖĆÕ«ÜŃü«ķüĢÕÅŹŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüµČłĶ▓╗ĶĆģÕÅłŃü»õ╗¢Ńü«õ║ŗµźŁĶĆģŃü½ńö¤ŃüśŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½ŃüżŃüäŃü”µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ▓¼õ╗╗Ńüīńö¤ŃüśÕŠŚŃéŗŃüōŃü©ŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│ń©Äµ│ĢŃü«ńē╣ÕŠ┤
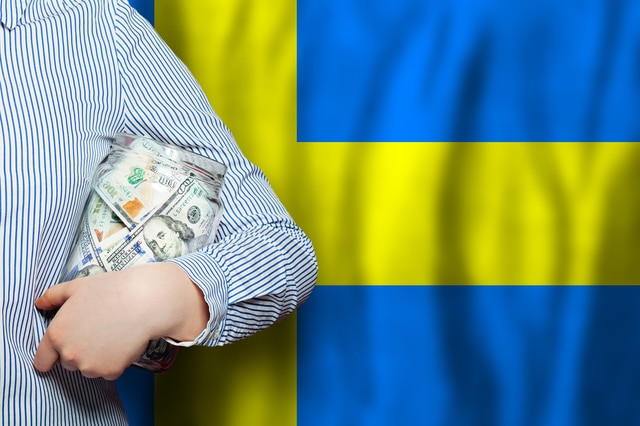
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«ń©ÄÕłČŃü»ŃĆüµ│Ģõ║║ń©ÄńÄćŃü«ń½Čõ║ēÕŖøŃü©ŃĆüõ║ŗµźŁÕåŹńĘ©ŃéÆõ┐āķĆ▓ŃüÖŃéŗÕä¬ķüćµÄ¬ńĮ«Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆé
µ│Ģõ║║ń©ÄÕłČ
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«µ│Ģõ║║µēĆÕŠŚń©ÄńÄćŃü»ŃĆü20.6%Ńü©ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│Ģõ║║Õ«¤ÕŖ╣ń©ÄńÄć’╝łń┤ä30%’╝ēŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”õĮÄŃüäµ░┤µ║¢Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü½ńÖ╗Ķ©śŃüĢŃéīŃü¤Õ▒ģõĮÅõ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Õģ©õĖ¢ńĢīŃü«µēĆÕŠŚŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ¬▓ń©ÄŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõĖƵ¢╣ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│ÕøĮÕåģŃü½µüÆõ╣ģńÜäµ¢ĮĶ©ŁŃéƵ£ēŃüÖŃéŗķØ×Õ▒ģõĮÅõ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│ÕøĮÕåģŃü¦ńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤µēĆÕŠŚŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«Ńü┐Ķ¬▓ń©ÄŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ń©ÄÕłČõĖŖŃü«Õä¬ķüćµÄ¬ńĮ«
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«ń©ÄÕłČŃü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Õä¬ķüćµÄ¬ńĮ«ŃéÆķĆÜŃüśŃü”ŃĆüÕŖ╣ńÄćńÜäŃü¬Ńé░Ńā½Ńā╝ŃāŚµ¦ŗķĆĀŃéƵö»µÅ┤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£ĆŃééķćŹĶ”üŃü¬Õä¬ķüćµÄ¬ńĮ«Ńü«õĖĆŃüżŃüīŃĆüķģŹÕĮōŃü«ķØ×Ķ¬▓ń©ÄÕłČÕ║”’╝łParticipation Exemption System’╝ēŃü¦ŃüÖŃĆéõ║ŗµźŁķ¢óķĆŻµĀ¬Õ╝ÅŃüŗŃéēÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃéŗķģŹÕĮōķćæŃéäŃĆüŃüØŃü«µĀ¬Õ╝ÅŃü«ÕŻ▓ÕŹ┤Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ńö¤ŃüśŃü¤ŃéŁŃāŻŃāöŃé┐Ńā½Ńé▓ŃéżŃā│Ńü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖÕĀ┤ÕÉłŃü½ķØ×Ķ¬▓ń©ÄŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüµīüµĀ¬õ╝ÜńżŠ’╝łŃāøŃā╝Ńā½ŃāćŃéŻŃā│Ńé░Ńé½Ńā│ŃāæŃāŗŃā╝’╝ēŃéÆŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü½Ķ©Łń½ŗŃüŚŃĆüŃé░Ńā½Ńā╝ŃāŚÕåģŃü¦Ńü«Ķ│ćķćæń¦╗ÕŗĢŃéäM&AŃéÆń©ÄÕŗÖõĖŖŃü«Ķ▓ĀµŗģŃü¬ŃüÅķĆ▓ŃéüŃü¤ŃüäŃü©ĶĆāŃüłŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüÕż¦ŃüŹŃü¬ŃāĪŃā¬ŃāāŃāłŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü½Ńü»Ńé┐ŃāāŃé»Ńé╣ŃāśŃéżŃā¢Ńā│Õ»ŠńŁ¢ń©ÄÕłČ’╝łCFC rules’╝ēŃééÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│õ╝üµźŁŃüīõĮÄĶ¬▓ń©ÄÕøĮŃü½µēĆÕ£©ŃüÖŃéŗÕż¢ÕøĮµ│Ģõ║║Ńü½25%õ╗źõĖŖŃü«Ķ│ćµ£¼ŃüŠŃü¤Ńü»ĶŁ░µ▒║µ©®ŃéÆńø┤µÄźńÜäŃüŠŃü¤Ńü»ķ¢ōµÄźńÜäŃü½õ┐ص£ēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü«ÕŖ┤ÕāŹµ│ĢŃü©ķøćńö©ķ¢óõ┐é
ńŗ¼ńē╣Ńü¬ÕŖ┤ÕāŹÕĖéÕĀ┤ŃāóŃāćŃā½
µŚźµ£¼Ńü½Ńü»ŃĆüµ£ĆõĮÄĶ│āķćæµ│ĢŃü½Õ¤║ŃüźŃüŵ│Ģիܵ£ĆõĮÄĶ│āķćæÕłČÕ║”ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü½Ńü»µ│ĢÕŠŗŃü¦Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤µ£ĆõĮÄĶ│āķćæŃü»ÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüØŃü«õ╗ŻŃéÅŃéŖŃü½ŃĆüĶ│āķćæŃéäÕŖ┤ÕāŹµÖéķ¢ōŃĆüõ╝æµÜćŃĆüķĆĆĶüĘķćæŃü¬Ńü®ŃĆüÕŖ┤ÕāŹµØĪõ╗ČŃü«Õż¦ķā©ÕłåŃü»ŃĆüķøćńö©ĶĆģÕøŻõĮōŃü©ÕŖ┤ÕāŹńĄäÕÉłŃü©Ńü«ķ¢ōŃü¦ńĘĀńĄÉŃüĢŃéīŃéŗŃĆīÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤ä’╝łkollektivavtal’╝ēŃĆŹŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«µźŁńĢīŃéäĶüĘń©«Ńü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃĆüķøćńö©ĶĆģŃü»ķøćńö©ĶĆģÕŹöõ╝ÜŃü½ÕŖĀÕģźŃüÖŃéŗŃüŗŃĆüÕŖ┤ÕāŹńĄäÕÉłŃü©ńø┤µÄźÕźæń┤äŃéÆńĄÉŃüČŃüōŃü©Ńü¦ŃüØŃü«ÕŹöń┤äŃü½µŗśµØ¤ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ÕŖ┤ÕāŹµ│Ģ’╝łEmployment Protection Act, LAS’╝ēŃü»ŃĆüķøćńö©Õźæń┤äŃü«Õ¤║µ£¼ńÜäŃü¬õ║ŗķĀģ’╝łĶ¦ŻķøćµÖéŃü«õ┐ØĶŁĘŃü¬Ńü®’╝ēŃéÆÕ«ÜŃéüŃĆüŃüØŃéīŃéÆÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃü©ÕĆŗÕłźŃü«ķøćńö©Õźæń┤äŃüīĶŻ£Õ«īŃüÖŃéŗµ¦ŗķĆĀŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ÕŖ┤ÕāŹµ│ĢŃüīÕŖ┤ÕāŹÕ¤║µ║¢µ│ĢŃéÆŃāÖŃā╝Ńé╣Ńü½ÕĆŗŃĆģŃü«Õźæń┤äŃüīĶŻ£Õ«īŃüÖŃéŗŃü«Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüńżŠõ╝ÜńÜäŃü¬ÕÉłµäÅŃü¦ŃüéŃéŗÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃüīõĖŁÕ┐āńÜäŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéƵףŃü¤ŃüÖŃĆüŃüäŃéÅŃéåŃéŗŃĆīńżŠõ╝ܵ░æõĖ╗õĖ╗ńŠ®ŃĆŹńÜäŃü¬ŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü½ķĆ▓Õć║ŃüÖŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü»ŃĆüÕŹśŃü½µ│ĢÕŠŗŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüĶć¬ńżŠŃü«õ║ŗµźŁÕłåķćÄŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃü«ÕåģÕ«╣ŃéƵŁŻńó║Ńü½µŖŖµÅĪŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ¦ŻķøćÕłČÕ║”
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüķøćńö©ĶĆģŃüīõĖƵ¢╣ńÜäŃü½ÕŠōµźŁÕōĪŃéÆĶ¦ŻķøćŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆīµŁŻÕĮōŃü¬ńÉåńö▒’╝łsakliga sk├żl’╝ēŃĆŹŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüõ║ŗµźŁõĖŖŃü«ńĄīµĖłńÜäńÉåńö▒’╝łõ║║ÕōĪµĢ┤ńÉå’╝ēŃüŠŃü¤Ńü»ÕŠōµźŁÕōĪŃü½ÕĖ░Ķ▓¼ŃüÖŃéŗÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬ńÉåńö▒’╝łõĖŹµŁŻĶĪīńé║ŃĆüÕŗżÕŗÖõĖŹĶē»Ńü¬Ńü®’╝ēŃü½ÕłåŃüæŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
õ║║ÕōĪµĢ┤ńÉåŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüńē╣Ńü½ķćŹĶ”üŃü¬ÕĤÕēćŃüīŃĆīLast in, first outŃĆŹ’╝łLIFO’╝ēŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«õ║ŗµźŁķā©ķ¢ĆŃü¦õ║║ÕōĪÕēŖµĖøŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕŗżńČÜÕ╣┤µĢ░Ńüīµ£ĆŃééń¤ŁŃüäÕŠōµźŁÕōĪŃüŗŃéēĶ¦ŻķøćŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕĤÕēćŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»ŃĆüÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃü½ŃéłŃüŻŃü”ķü®ńö©ŃüīÕżēµø┤ŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ¤║µ£¼ńÜäŃü½Ńü»ÕŗżńČÜÕ╣┤µĢ░ŃüīķĢĘŃüäÕŠōµźŁÕōĪŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
Ńé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü»ŃĆüÕ╝ĘÕŖøŃü¬ŃéżŃāÄŃāÖŃā╝ŃéĘŃā¦Ńā│Ńü©ńżŠõ╝ÜńÜäÕģ¼µŁŻŃéÆõĖĪń½ŗŃüĢŃüøŃéŗŃĆüńŗ¼Ķć¬Ńü«ķŁģÕŖøŃéƵ£ēŃüÖŃéŗŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ńÆ░ÕóāŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüÕż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü«µłÉµ¢ćµ│ĢŃéÆÕ¤║ńøżŃü©ŃüŚŃüżŃüżŃĆüÕłżõŠŗŃéäÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µ¤öĶ╗¤Ńü¬Ķ”üń┤ĀŃéÆÕÅ¢ŃéŖÕģźŃéīŃü¤ŃāÅŃéżŃā¢Ńā¬ŃāāŃāēŃü¬µ¦ŗķĆĀŃéƵ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣Ńü½ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃé╣Ńé”Ńé¦Ńā╝ŃāćŃā│Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃéƵłÉÕŖ¤ŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣ŃĆüõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕĖéÕĀ┤ÕÅéÕŖĀĶĆģŃüĖŃü«ŃĆīĶ¬¼µśÄĶ▓¼õ╗╗ŃĆŹŃéÆķćŹĶ”¢ŃüÖŃéŗŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ÕĤÕēćŃü©ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃüīńĄīÕ¢ČŃü½ÕÅéÕŖĀŃüÖŃéŗŃĆīÕģ▒ÕÉīµ▒║Õ«ÜŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃĆŹŃéäŃĆüµ│ĢÕŠŗŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃüīÕŖ┤ÕāŹµØĪõ╗ČŃéÆÕ«ÜŃéüŃéŗńŗ¼ńē╣Ńü¬ÕŖ┤ÕāŹÕĖéÕĀ┤ŃāóŃāćŃā½ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ