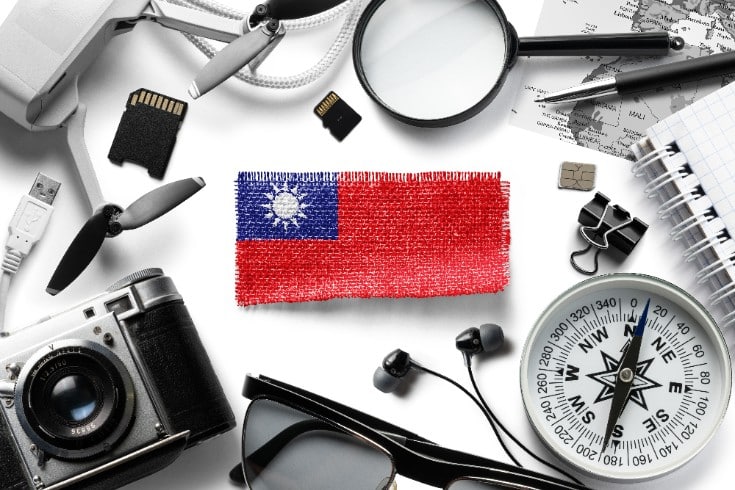ハンガリーでの契約書作成・交渉で問題となる民法・契約法

ハンガリーへの事業展開を検討する日本の経営者や法務担当者の皆様にとって、現地の契約法は事業の成否を左右する重要な要素です。ハンガリーの契約法は、日本法と共通の民法典(Act V of 2013)に根差す大陸法系に属しており、一見すると日本法と類似する部分が多く見られます。しかし、契約交渉の段階から課される「信義誠実義務」の厳格さや、特定の契約に適用される厳格な方式要件など、日本とは異なる重要な点が複数存在します。
本記事では、こうした日本法との異同に焦点を当て、ハンガリーにおける契約実務のリスクと機会を深く掘り下げて解説します。
なお、ハンガリーの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ハンガリー民法典の基礎
ハンガリーの契約法は、主に2014年3月15日に施行された新しい民法典(Act V of 2013)によって規律されています。この民法典は、私人の財産関係および人身関係を「相互依存の原則」と「平等の原則」に基づいて規定しており、その基本的な構造は日本法が属する大陸法系の体系と非常に類似しています。
その根幹にあるのは、日本法と共通の「契約自由の原則」です。これは、当事者が法律に違反しない限り、自由に契約内容を定めることができるという考え方です。契約は、当事者間の相互かつ全会一致の意思表示によって成立し、重要な事項について合意がなされる必要があります。この原則により、当事者は契約の相手方やその内容、形式を自由に選択することが可能となります。
ハンガリー法と日本法で異なる契約締結時の論点

口頭合意の有効性と書面化が必要な場合
ハンガリー法では、不動産売買など特定の類型を除き、口頭での合意でも契約が有効に成立します。これは、書面化が原則として契約成立の要件とされない点で日本法と共通の考え方です。口頭契約は法的拘束力を持ち、法廷での訴訟も可能とされています。しかし、口頭での合意は内容の立証が困難であるという実務上の課題は、日本と同様に存在します。
一方で、ハンガリーでは特定の種類の契約において、法律で厳格な書面化が義務付けられています。最も重要な例が不動産売買契約です。日本の不動産売買では、法律上は口頭でも契約は成立しますが、登記のためや実務上の慣習として書面が作成されます。これに対し、ハンガリーでは、不動産売買契約書は弁護士または公証人による副署(countersign)がなければ法的に無効となります。これは、契約の有効性そのものが形式に依存するという、日本法との決定的な違いであり、現地の弁護士を早期に関与させることの重要性を示しています。
また、雇用契約も書面で締結することが法律で義務付けられています。日本でも書面化が一般的ですが、ハンガリーでは書面での合意が雇用関係成立の要件とされています。ただし、法律が定める特殊な規定として、従業員のみが書面不在を30日以内に異議申し立てできるという点も注目に値します。
このように、ハンガリーの契約法は「口頭合意の有効性」という一般原則を掲げながらも、不動産や雇用といった事業上不可欠な分野では、厳格な書面化を義務付けています。
契約交渉における信義誠実義務と裁判所の介入
ハンガリー民法典第6編第62条は、当事者が契約締結前の交渉段階から、そして契約の成立と存続期間中、さらには終了時においても「信義と公平」に基づき行動し、相互に協力する義務を負うことが明記されています。この協力義務には、契約に影響を与えるすべての重要な状況について、互いに情報を提供することが含まれます。この義務を怠ることは「権利の濫用」と見なされる可能性があります。
日本の商習慣では、契約交渉は多くの場合、最終的な書面契約が締結されるまで法的拘束力を持たないと見なされがちです。しかし、ハンガリー法は、契約交渉そのものが法的な義務を伴うプロセスと捉える傾向が強いです。ハンガリー民法典には、契約交渉中の義務違反を原因とする「契約締結上の過失(culpa in contrahendo)」という概念が明文で導入されており、交渉が成立しなかった場合でも損害賠償責任が発生しうることが示されています。これは、交渉段階で当事者間に「信頼関係(relationship of trust and confidence)」が生じるとする考え方に基づくものです。
ハンガリーの裁判所は、当事者が交渉段階で信義誠実義務に違反した場合、その後の契約の有効性に対して積極的に介入することがあります。これは、日本の裁判所が一般的に交渉段階の義務違反を「不法行為」として損害賠償を命じるに留まるのとは対照的です。
その一例として、ハンガリー商工会議所付属仲裁裁判所が2005年に下した判決があります。この事案では、ある男性が銀行から80万フォリント(当時のレートで約3,250ユーロ)の融資を受ける際、友人を連帯保証人として説得しました。しかし、保証人となった女性は、幼い子供を一人で育てながら月収わずか7万フォリント(約284ユーロ)の収入しかなく、債務を返済する資力がない状況でした。男性が借金を返済できなくなったため、銀行が保証人に対して債務の履行を求めて提訴したのです。
仲裁裁判所は、この契約の有効性について、銀行が保証人の財政状況を十分に調査しなかったことを指摘しました。裁判所は、融資業務の本質的な原則として、銀行は融資相手とその保証人に返済能力があることを契約前に確認すべきであると述べました。その上で、保証人に返済を命じることは、彼女と子供の生活を成り立たなくさせ、「基本的な社会的および道徳的規範に反する」と判断しました。結果として、裁判所は保証契約全体を「善良な風俗に反する」として無効としました。この判決は、交渉段階での情報収集・確認義務が単なる努力義務ではなく、契約の有効性そのものを左右するほどに重い義務であることを示しています。
交渉相手に対し、重要な情報を意図的に秘匿したり、一方的な利益を追求したりする行為は、たとえ最終契約が締結されても、後に無効を訴えられるリスクとなります。日本企業は、交渉の初期段階から誠実な情報開示とデューデリジェンスを徹底し、信頼関係の構築を法的義務として捉える必要があります。
ハンガリーにおける契約内容の有効性と不当条項
契約当事者の行為能力
ハンガリー民法典第2編では、すべての人が行為能力を持つことが原則とされています。しかし、未成年者や後見人の下にある者には制限が課されます。18歳未満の者は未成年者とされ、14歳に達した「制限行為能力者」は、法定代理人の同意または追認なしには有効な法律行為を行えないことが一般的です。一方で、制限行為能力者であっても、少額の日常生活に関する契約や、自己の労働で得た収入に関する処分行為は、単独で行うことができます。
不当条項(Unfair Terms)と判例の動向
ハンガリー法では、特に消費者契約において、一方当事者に不利益をもたらす「不当条項」は無効と判断されることがあります。ハンガリーの裁判所は、不当性を職権で調査し、契約全体ではなく不当な条項のみを無効と判断する権限を持っている点が特徴的です。
ハンガリーの最高裁判所(Curia)は、法律の統一的な解釈を確保するため、下級裁判所を拘束する統一判決を下しています。これにより、裁判所による不当条項の判断には一定の基準がもたらされ、例えば不動産仲介手数料や保険契約における不当な条項など、具体的な事例を示唆する判例も蓄積されています。ハンガリーの民法典には、契約内容が「善良な風俗に反する」場合に無効となるという規定があり、これに加え、判例は、特に消費者や弱い立場の当事者を保護するために、裁判所が不当条項を積極的に無効化する権限を持っていることを示しています。
ハンガリーで消費者向けビジネスを展開する日本企業は、契約書内の条項がハンガリーで不当条項と判断されるリスクを考慮し、契約条項の作成において、現地の消費者保護法規だけでなく、裁判所の最新の判例動向にも注意を払う必要があります。
ハンガリーにおける契約の履行・不履行と終了
契約からの撤回・解除と賠償責任
ハンガリー法では、契約当事者は、一定の条件の下で契約から撤回(withdrawal)または終了(termination)する権利を持ちます。
なお、請負契約(works contract)においては、顧客はいつでも契約の履行開始前に撤回し、履行開始後はいつでも終了させることができます。そして、民法典第6編第249条第2項より、顧客が撤回・終了した場合、顧客は請負人に対し、請負代金の相応な部分を支払い、さらに損害を賠償する義務を負うことを明確に定めています。ただし、この賠償額は請負代金を超えることはありません。
契約不履行と損害賠償:日本法との比較
ハンガリー民法典は、契約不履行に対する法的責任を明確に定めています。契約違反によって相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務があります。ハンガリー法における契約違反の責任は「客観的責任(objective liability)」と称され、その免責は厳格な条件下でのみ認められます。具体的には、契約違反が、当事者の制御を超えた、契約締結時には予見不可能であった事由によって引き起こされたことを証明しなければなりません。これは、日本の債務不履行における「帰責事由」の考え方と類似しており、不可抗力などの特別な事情がない限り、損害賠償責任を負うという点で共通しています。
賠償の範囲は、契約の対象物自体に生じた損害、実際の損害、そして契約締結時に予見可能であった逸失利益にまで及びます。逸失利益の賠償責任が予見可能性によって制限されるという考え方は、日本の民法における損害賠償の範囲の規定(民法第416条)と一致しています。
契約の変更と「予見可能性」の原則
ハンガリー法では、契約締結後に予見不可能な状況の変化があった場合、契約内容を裁判所が修正することが認められる場合があります。これは、日本の民法が原則として当事者の合意による変更を前提とし、裁判所による変更を限定的にしか認めていない(いわゆる事情変更の原則)のと比較すると、より柔軟な運用がなされる可能性を示唆しています。ただし、ハンガリーの裁判所も、契約の修正は「例外的な状況」においてのみ可能であると判断する傾向にあります。インフレや需給変動といった通常のビジネスリスクは、予見不可能な事由とは見なされないことが一般的です。
まとめ
本稿で解説したように、ハンガリーの契約法は、日本法と根幹を同じくする大陸法系に属し、契約自由の原則を重視しています。しかし、その実務においては、日本法とは異なる重要な留意点が複数存在します。特に、契約交渉段階から厳格に課される信義誠実義務、不動産や雇用契約における厳格な方式要件、そして不当条項に対する裁判所の積極的な姿勢は、日本の商習慣とは異なるリスクを生む可能性があります。
こうした相違点を深く理解せずに事業を進めることは、予期せぬ法的トラブルにつながりかねません。ハンガリー市場へのスムーズな参入を実現するためには、現地の法律事務所や弁護士と連携し、現地の法規や商習慣に精通した専門家から、個別具体的な助言を得ることが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務