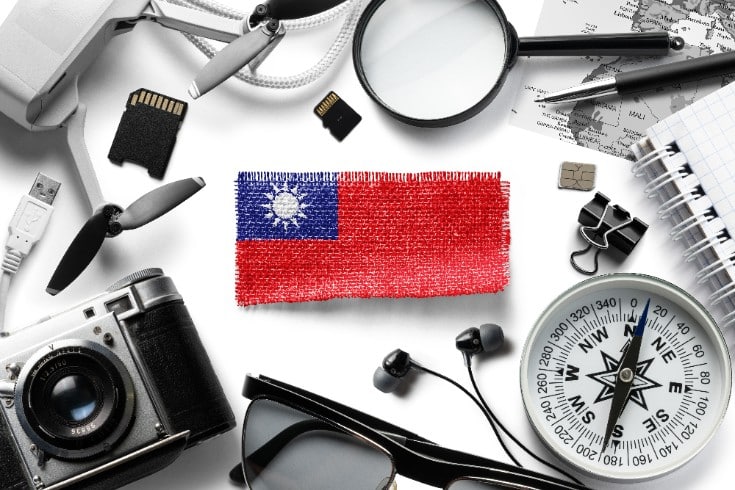アメリカで引き抜き防止の「ノーポーチ」協定が独禁法による規制を受ける理由

米国でのビジネス展開を検討する日本企業にとって、独占禁止法(Antitrust Law)は避けて通れない重要な法的リスクの一つです。特に近年、人材獲得に関する企業間の協定、いわゆる「ノーポ-チ協定」が、米国司法省(DOJ)および連邦取引委員会(FTC)によって厳格に規制され、重大な法的責任を問われる事例が増加しています。
ノーポ-チ協定とは、直訳すると「引き抜き防止協定」を意味し、通常、企業が競合他社の従業員を勧誘、採用、または引き抜かないと互いに合意する行為を指します。つまり、そうした人材獲得に関する企業間合意が、米国では、独占禁止法の重大な違反行為になる、という構造です。
米国法におけるノーポ-チ協定の規律は、日本法とは一線を画す「per se illegal(理由の如何を問わず違法)」という厳格な原則に基づいています。これは、協定が存在するだけで直ちに違法と判断され、その市場への悪影響を立証する必要がないことを意味します。
本記事では、この米国特有の法的原則の核心に迫り、過去の歴史的な判例から、近年のデジタルプラットフォームを介した情報共有に対する規制強化の動向までを網羅的に解説します。日本の法務部員や経営者の皆様が米国での予期せぬリスクを回避するための実践的な知見を提供します。
この記事の目次
ノーポ-チ協定と米国独禁法の「Per Se Illegal」原則
「ノーポ-チ協定」とシャーマン法第1条
ノーポ-チ協定とは、企業が競合他社の従業員や潜在的な労働者を勧誘、採用、または引き抜かないと合意する行為を指します。この協定は、必ずしも書面による明示的な合意である必要はなく、口頭での約束や、第三者を通じて形成された暗黙の了解も含まれ得ます。協定の内容も多岐にわたり、例えば「互いの従業員にコールドコール(見込み顧客への電話勧誘)をしない」といった緩やかな制限や、特定の従業員を採用する前に現在の雇用主から許可を得るという合意も、違法なノーポ-チ協定を構成する可能性があります。
米国独占禁止法では、ノーポ-チ協定は反トラスト法の根幹をなす「シャーマン法第1条」に違反するとされます。この法律は、取引を不当に制限するあらゆる契約や協定を不法と定めています。ノーポ-チ協定は、その反競争性が明白であると見なされるため、「per se illegal」という原則に基づき判断されます。これは、ラテン語の「per se(それ自体・本質的に)」と「illegal(違法)」を組み合わせた言葉で、協定の存在が確認されただけで直ちに違法とされること、つまり、協定が市場に与えた具体的な悪影響など、その他の要件を立証する必要がないことを意味します。また、被告が協定に「合理的理由」があったと主張することも、原則として認められません。この厳格な判断基準は、日本法における違法性判断とは根本的に異なり、日本企業が米国で事業を展開する際に直面する、予測不可能な法的リスクの最大の原因であると言えるでしょう。
労働市場における競争と反トラスト法
米国独占禁止法は、企業が消費者に商品やサービスを販売する市場だけでなく、従業員という労働力を獲得するための市場、すなわち「労働市場」も競争の対象であると明確に捉えています。労働市場における公正かつ自由な競争は、労働者のキャリアアップの機会を確保し、その能力に見合った公正な報酬が実現されることで、社会全体における人材の適材適所な配置を促進します。
この結果、人材を利用して供給される商品やサービスの水準が向上し、ひいては消費者の利益につながるという競争政策上の原則があります。ノーポ-チ協定は、労働者の自由な移動を阻害し、労働市場における競争を排除することで、健全な市場メカニズムに恒久的な損害を与える行為と評価されます。
米国シリコンバレー・ノーポ-チ協定事件

ノーポ-チ規制の歴史において、最も象徴的な事例として挙げられるのが、Apple、Google、Intel、Adobeといったシリコンバレーの主要企業が関与した事件です。本件は、これらの企業が互いの従業員を引き抜かないという密約を結んでいたとされるもので、スティーブ・ジョブズ(Apple共同創設者)とエリック・シュミット(元Google CEO)のようなトップエグゼクティブ間の電子メールのやり取りによって協定の存在が明らかになりました。裁判所は、これらの企業が「コールドコールをしない」といった緩やかな取り決めを含め、人材獲得競争を制限する一連の協定を締結していたと認定しました。
この事件は、まず米国司法省(DOJ)がこれらの企業に対してシャーマン法第1条違反で提訴しました。これに続き、協定によって不利益を被った従業員が、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所にて集団訴訟を提起しました。この訴訟は、2015年に最終的な和解合意に達しました。DOJによる調査の後、企業は協定を解消し、集団訴訟では総額4億ドルを超える和解金が従業員に支払われました。この事件は、労働市場も独占禁止法の厳格な適用対象であることを示した歴史的な転換点であり、企業が労働市場における競争を制限する行為に対して、政府による刑事・民事上の責任追及だけでなく、従業員からの巨額の損害賠償請求リスクがあることを明確に示しました。
| 事件名 | In re High-Tech Employee Antitrust Litigation |
| 当事者名 | 原告:元従業員(集団訴訟) 被告:Adobe Inc., Apple Inc., Google Inc., Intel Corporation, Intuit Inc., Pixar, Lucasfilm, Ltd. など |
| 裁判所 | U.S. District Court, Northern District of California |
| 判決年月日 | 2015年に最終和解合意 |
| 最終和解額 | 総額435million(Google,Apple,Intel,Adobeが415 million, Intuit, Lucasfilm, Pixarが$20 million) |
米国における人材獲得プロセスのデジタル化と規制強化
2025年の「労働者に関する事業活動のための新たな反トラストガイドライン」
米国の独占禁止法執行機関は、ノーポ-チ規制の姿勢を継続的に強化しています。米国司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)は、2016年に人事担当者向け反トラストガイダンスを発表し、ノーポ-チ協定や賃金固定協定が独占禁止法違反となり得ると警告しました。そして、2025年には「労働者に関する事業活動のための新たな反トラストガイドライン」を共同で発表し、規制の範囲をさらに拡大しています。この新しいガイドラインは、ノーポ-チや賃金固定協定を依然として「per se」原則の対象としています。
この新しいガイドラインが特に注視しているのは、デジタル化がもたらす新たな反競争行為です。従来の規制は企業間の直接的な合意を想定していましたが、現代のビジネスでは、人材獲得プロセスがデジタルプラットフォームや第三者ツールを通じて行われることが一般的です。新しいガイドラインは、企業が直接情報を共有しなくても、アルゴリズムや第三者のツールを通じて、競争上機密性の高い情報(賃金、雇用条件など)を間接的に共有することが、反競争的な効果を持つ場合に違法となり得ると明言しています。
アルゴリズムによる「共謀」のリスク
プラットフォームの設計やアルゴリズムの仕様が、意図せず企業間の暗黙の了解を助長し、事実上のノーポ-チ協定と評価される可能性があります。これは、複数の企業が同じプラットフォームやアルゴリズムに依存することで、賃金や雇用条件が自然と横並びになる「アルゴリズムによる共謀(Algorithmic Collusion)」というリスクを内包します。
具体的には、以下のような技術的な側面が問題視されます。
- 賃金情報の一元的管理と共有:競合する企業が、人材プラットフォームを通じて労働者の賃金や雇用条件などの機密情報を共有する仕組みです。たとえプラットフォームの利用規約で明示的に同意していなくても、システムが自動的にこれらの情報を集約・共有することで、企業間の賃金固定や競争抑制につながることがあります。
- アルゴリズムによる採用・賃金推奨:プラットフォームのアルゴリズムが、クライアント企業に対し、特定の賃金範囲や上限、あるいは他社のオファーを上回らないような採用条件を推奨するような設計です。これは、複数の企業が同じアルゴリズムに依存することで賃金水準が横並びになり、結果的に労働市場の競争が排除される可能性が高いと言えるでしょう。
- 候補者の自動的排除:プラットフォームの機能として、特定の競合他社の現役従業員を、採用候補者の検索結果やマッチングリストから自動的に排除する仕組みです。これは、企業間の「引き抜きを行わない」という合意を、システムが強制的に実行していると見なされる可能性があります。
さらに、新しいガイドラインは、伝統的なノーポ-チ協定だけでなく、以下のような行為も独占禁止法上の監視対象として明記しています。
- フランチャイズにおけるノーポ-チ協定:フランチャイザーとフランチャイズ加盟店の間、あるいは加盟店同士の間で、互いの従業員を引き抜かないと合意する行為は、たとえ垂直的な関係であっても「per se illegal」となる可能性があるとしています。
- 非競争協定(Non-Compete Agreements):従業員が退職後に競合他社で働くことを制限する非競争協定についても、労働者の移動を不当に制限し、競争を阻害するとして、個別のケースで独占禁止法違反として追及される可能性があると警告しています。
これらの例は、日本の経営者や法務部員が米国市場でビジネスを展開する際に、従来の商慣習や技術的な仕組みそのものに潜む法的リスクを認識する必要があるという重要な警告となります。
米国法と日本法との比較

日本の公正取引委員会(JFTC)や厚生労働省も、人材獲得に関する競争を独占禁止法の適用対象と捉えています。公正取引委員会は、2018年2月に発表した報告書「人材と競争政策に関する検討会」の中で、引き抜き防止協定(ノーポ-チ合意)について、原則として「不当な取引制限」または「不公正な取引方法」に該当する可能性が高いとしています。また、厚生労働省の報告書も、フリーランスや個人として働く者に対して、不当な不利益を与える行為が独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当し得ると指摘しています。
しかしながら、日本法では、上記の報告書が示すように、協定が「公正かつ自由な競争を実質的に制限する」ことや、企業が「優越的地位」にあるかどうかの個別的な判断を要する傾向があります。これは、米国の「per se illegal」のように、行為の存在だけで直ちに違法と判断されるわけではないという点で、根本的に異なります。この違いは、米国における法的リスクの厳格性と予測不能性を増大させます。協定に合理的な理由があったとしても、米国ではその弁明が認められない可能性が高いことから、日本の経営者が米国でのビジネス展開時に直面する最も重要な相違点であると言えます。
| 米国法(独占禁止法) | 日本法(独占禁止法) | |
|---|---|---|
| 原則的な判断基準 | 「Per Se Illegal」(行為の存在自体で違法) | 「合理の原則」または「不公正な取引方法」(競争を実質的に制限するか、優越的地位の濫用があるか) |
| 罰則の有無 | 刑事罰(企業・個人)と巨額の民事賠償が存在する | 行政処分(課徴金)や損害賠償、不当な取引制限には刑事罰も |
| 主要な法執行機関 | 司法省(DOJ)、連邦取引委員会(FTC) | 公正取引委員会(JFTC) |
| 適用範囲 | 伝統的な従業員に加え、独立請負人(independent contractor)も含む | 伝統的な労働者は原則対象外で、フリーランスなど「個人として働く者」が主な対象 |
まとめ
米国でのノーポ-チ規制は、日本での慣行や法的な考え方とは一線を画す厳格なものです。他社の人事担当者と人材に関する情報交換を行うこと、または口頭や暗黙的な合意であっても、その存在が明らかになれば、巨額の刑事罰や民事訴訟リスクに直面する可能性があります。特に、デジタルプラットフォームを介した情報共有や、一見無害に見えるサービス利用が、事実上のノーポ-チ協定と評価される可能性を深く認識すべきです。
日本企業が米国で事業を展開する際には、人材獲得に関する方針・規約を他社と協議することや、他社の人事担当者と不適切とみなされる可能性のある情報交換を行うことは、極めて重大なリスクを伴います。こうした複雑な法務課題への対応には、米国独占禁止法に関する専門的な知識と、日米の法制度の異同に関する深い理解が不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務