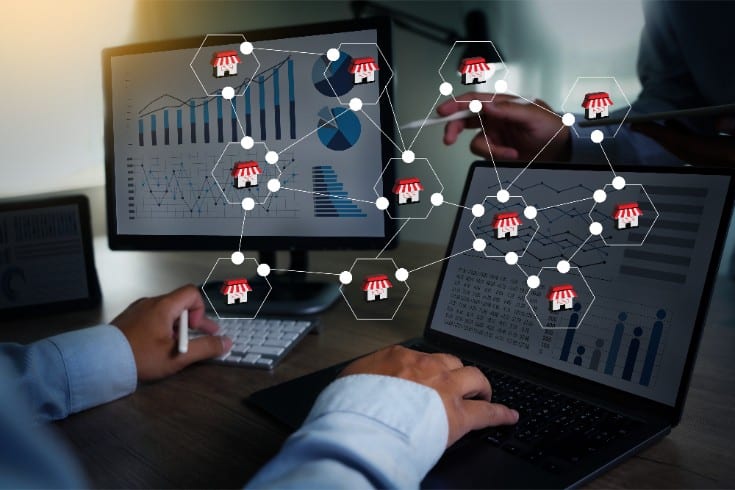オーストリア共和国の海外直接投資(FDI)に関する投資規制法(InvKG)とは

グローバルな経済安全保障の重要性が高まる中、欧州各国が外国直接投資(FDI)に対する審査を厳格化しています。オーストリアもその例外ではなく、2020年7月25日に発効した「投資規制法」(Investitionskontrollgesetz – InvKG)によって、国外からの投資に対する事前審査制度を大幅に強化しました。これは、オーストリアでのM&Aや事業投資を検討する上で、極めて重要な法的課題となっています。
本記事は、このInvKGの具体的な内容、特に日本の外為法(正式名称:外国為替及び外国貿易法)との重要な相違点、そして最新の判例から読み取れる実務上の注意点を詳細に解説するものです。本記事を通じて、InvKGが、日本の外為法における事前届出免除制度のような柔軟な運用は期待できないこと、そして取引完了前の承認を義務付ける「スタンドスティル義務」が厳格であり、違反には刑事罰を含む重い罰則が科されることをご理解いただければ幸いです。これらの規制の背景には、単なる経済活動の保護を超えた、より広範な「経済安全保障」の確保という強い政治的意思があり、この点を理解することが実務上のリスク管理において極めて重要となります。
なお、オーストリアの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
オーストリア投資規制法(InvKG)の背景と基本原則
オーストリアの投資規制法(InvKG)は、EU全体の外国直接投資(FDI)審査を強化する潮流に沿って導入されました。
この法律は、2020年7月25日に施行され、従来の外国貿易法(Foreign Trade Act 2011)に代わり、外国投資審査の枠組みを刷新するものです。この時期は、新型コロナウイルスのパンデミックが世界的に拡大し、各国が自国のサプライチェーン、特に医療関連の脆弱性を認識し始めた時期と重なります。この法律が「特に機密性の高い分野」として医薬品、ワクチン、医療機器分野の研究開発(R&D)を明示し、低い閾値を適用していることは、パンデミックが法改正の政治的背景に強く影響したことを示唆しています。これは、単なる法律のテクニカルな変更ではなく、国際情勢の変化に対応する強い政治的意思の表れと解釈すべきでしょう。
グローバルな危機が国内の重要産業(医療・技術)の脆弱性を露呈させ、その保護を目的とした法規制強化への政治的コンセンサスを形成したことで、単なる経済的な観点ではなく、安全保障の観点から外国投資を審査するという新しい潮流が生まれました。オーストリアの投資規制が、商業的な側面だけでなく、このような広範な「経済安全保障」の懸念を背景にしている点を理解することが重要です。
InvKGは、国の安全保障や公の秩序に脅威をもたらす可能性のある外国直接投資を審査するために導入されました。これは、EU機能条約第52条および第65条に規定された原則に基づいています。規制の対象となる投資行為は、以下のいずれかの行為です。議決権の取得(後述の閾値に達する場合)、支配的影響力(controlling influence)の取得、または事業の重要な資産(essential assets)の取得が該当します。
オーストリアで規制の適用対象となる投資の要件
InvKGが適用されるのは、以下の三つの要件がすべて満たされる場合です。
「外国投資家」の定義と実務上の注意点
InvKGにおける「外国投資家」とは、EU、欧州経済領域(EEA)、またはスイスに市民権、本店、または主要な事業拠点を有しない個人または法人を指します。
ここで特に注意すべきは、単に直接の投資家がこれらの地域内にいるかどうかだけでなく、その上位に位置する最終的な受益者(Ultimate Beneficial Owner:UBO)が第三国にいる場合も規制対象となるという点です。これは、投資ビークルを介した規制の迂回を防ぐための仕組みです。
例えば、投資スキームがオランダの特別目的会社(SPV)を介していても、そのSPVの最終的な親会社や議決権の過半数を保有する者が日本の企業である場合、オーストリア当局は垂直的に所有構造を遡り、日本の企業を「外国投資家」と認定し、InvKGの審査対象とします。この「垂直的な連鎖」の考え方は、日本の外為法と比較して厳格な側面であり、事前のデューデリジェンスにおいて、単に直接の投資主体だけでなく、グループ全体の所有構造が問題となることを示しています。
対象となる「オーストリア企業」
InvKGの対象となるのは、オーストリアに登記上の本店(seat)または中央管理拠点(central administration)を有する企業です。既存の企業や事業体の買収が対象となり、新たに事業を立ち上げるグリーンフィールド投資や、単なる支店の取得は規制対象外となります。
投資行為と議決権取得の閾値
InvKGが定める議決権取得の閾値は、対象企業の事業分野に応じて異なります。特に機密性の高い分野では、議決権の10%以上、25%以上、50%以上が対象となり 、その他の分野では、議決権の25%以上、50%以上が対象となります。
議決権の取得比率が10%に達した場合でも、その後25%や50%に引き上げられる場合、新たな届出義務が発生します。さらに、投資家が複数いる場合や、外国投資家が共同で議決権を行使する場合、その議決権は合算して計算されます。
一方で、小規模企業(マイクロ・エンタープライズ)には例外規定が設けられています。従業員数が10人未満、かつ年間売上高または年間貸借対照表合計額が200万ユーロ未満の零細企業やスタートアップ企業は、この規制の対象外となります。
オーストリアで審査対象となる「機密性の高い分野」の詳細
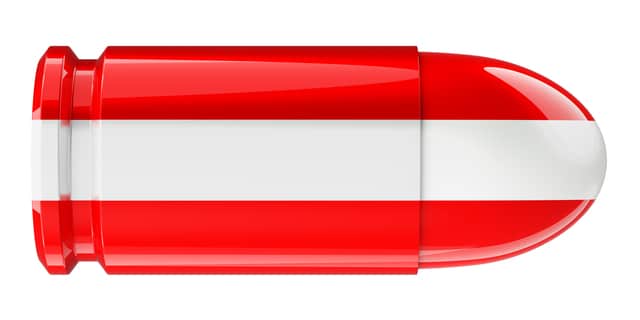
InvKGの附属書(Annex)は、審査対象となる事業分野を定めており、その重要性に応じて二つの区分に分かれています。
特に機密性の高い分野(附属書パート1)
以下の分野では、議決権比率が10%以上で審査対象となります。このリストは網羅的(exhaustive)です。
- 防衛関連品および技術
- 重要エネルギーインフラの運営
- 重要デジタルインフラの運営、特に5Gインフラ
- 水
- オーストリアのデータ主権を保証するシステムの運営
- 医薬品、ワクチン、医療機器、個人用防護具分野の研究開発
その他の分野(附属書パート2)
以下の分野では、議決権比率が25%以上で審査対象となります。このリストは例示的(non-exhaustive)であり、当局の裁量が広く認められます。
- エネルギー、情報技術、交通、健康、食料、通信、データ処理・保管、防衛など、重要インフラ
- 人工知能、ロボット工学、半導体、サイバーセキュリティ、量子技術、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなど、重要技術やデュアルユース品
- エネルギー、原材料、食料、医薬品等の重要資源の供給
- 個人データを含む機密情報へのアクセスまたはその管理能力
- メディアの自由と多様性
オーストリアにおける審査手続きの流れと実務上の注意点
InvKGに基づく審査は、取引のタイムラインと法的リスクに直接影響するため、その手続きを正確に理解しておく必要があります。
「無異議証明書」(Unbedenklichkeitsbescheinigung – UB)
審査の前提として、オーストリアのInvKGには「無異議証明書」(Unbedenklichkeitsbescheinigung – UB)という概念があります。これは、投資家が自らの取引がInvKGの規制対象に該当しないと判断した場合に、当局に対してその確認を求めるために申請するものです。日本の投資家にとって、これは「事前届出が不要な取引であることの確認」を求める手続きと理解できます。この申請は、たとえ取引が正式な承認を要しないと判断された場合でも、当局からの公式な確認を得て法的安全性を高めるための手段として利用されます。そして、当局がこの取引は審査対象であると判断した場合、この「無異議証明書」の申請は、法律上、正式な「承認申請」(Genehmigungsantrag)として扱われることになります。ただ、この「無異議証明書」の申請件数は、正式な承認申請よりも少ないという統計もあり、必ずしも活用されていない模様です。
申請義務と審査プロセス
申請義務は、主に取得側である外国投資家が負います。ただし、投資家が申請を怠った場合、対象企業にも届出義務が生じます。
取引完了前の承認取得義務(スタンドスティル義務)があり、承認が得られるまで取引を実行してはなりません。この義務に違反した場合、後述する刑事罰などの厳格な罰則が科されます。
審査プロセスは段階的です。まず、EUレベルでの協力メカニズムが開始され、他のEU加盟国や欧州委員会との情報共有が行われます。これには通常35暦日を要します。その後、オーストリア国内での予備審査が始まり、この期間は1ヶ月です。当局が安全保障上の懸念を抱くなど、さらに詳細な検討が必要と判断した場合、フェーズ2に進み、この期間はさらに2ヶ月を要します。標準的な審査期間でも合計で2〜3ヶ月かかることを考えると、M&A計画の初期段階からこの審査プロセスを組み込むことが不可欠です。日本の外為法と同様に、承認が得られるまでの期間は取引を凍結する形となり、これはM&Aのタイムラインに直接的な影響を及ぼします。
違反に対する厳格な罰則
承認なしに取引を完了させた場合(”gun jumping”)、その法律行為は暫定的に無効(provisionally invalid)となります。さらに、刑事罰として最高1年の禁固刑、悪質なケースでは最高3年の禁固刑が科される可能性があります。
当局は、事後的に取引に条件を課したり、取引の解消(unwinding)を命じることもできます。オーストリアの罰則は、日本の外為法違反における罰則(通常は行政罰や過料)と比較して、特に刑事罰の面で非常に厳格です。これは単なる法律違反ではなく、国の安全保障に対する脅威として扱われるという、オーストリア当局の強い姿勢の表れと言えるでしょう。
オーストリアと日本の法制度(外為法)の相違点
日本の外為法とオーストリアのInvKGは、国の安全保障を目的とした対内直接投資規制という点で共通していますが、その運用には重要な違いがあります。
事前届出免除制度の有無
日本の外為法には「事前届出免除制度」があり、外国投資家が役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないといった一定の基準を遵守する場合、事前届出が免除される場合があります。これは、一定の条件下で規制手続きの負担を軽減する柔軟な仕組みです。
一方で、オーストリアのInvKGには、このような広範な「行動基準に基づく事前届出免除制度」は存在しません。規制対象となる要件を満たした場合、審査は原則として強制的に行われます。唯一の例外は、従業員10人未満かつ年間売上高または貸借対照表合計額200万ユーロ未満の「マイクロ・エンタープライズ」に対するものです。この「免除制度の有無」は、日本の投資家が最も注意すべき点です。日本の制度に慣れていると、オーストリアでも同様の柔軟性があると誤解する可能性があります。しかし、オーストリアでは「該当すれば審査を受ける」という非常に厳格なルールが適用されるため、戦略の根本的な見直しが必要となります。
罰則の性質
日本の外為法では、違反に対して行政罰や罰金が科されます。一方、オーストリアのInvKGでは、取引の無効化や、最大3年の禁固刑という刑事罰までが規定されています。この厳格さは、オーストリア当局がこの規制を「経済的自由」よりも「国家の安全」を優先する、より強い政治的意志として位置付けていることを示唆しています。
オーストリアの最新判例と実務上の注意点
オーストリアのInvKGに関する初の司法判断が下されました。この判例は、手続きの厳格性と当局の裁量権の広さを示唆するものです。
連邦行政裁判所の初判例(GZ W177 2283132-1/2E)の解説
連邦行政裁判所(Bundesverwaltungsgericht – BVwG)、2024年1月25日判決の概要は以下の通りです。ある投資家が、議決権25%以上の株式取得について、当局に「無異議証明書」(Unbedenklichkeitsbescheinigung – UB)の申請を行いました。しかし、当局はこれをUB申請ではなく、取引が規制対象であるとして、正式な「承認申請」(Genehmigungsantrag)として取り扱う旨を通知しました。
投資家は、当局がUB申請を承認申請として扱ったことに不服を申し立てましたが、裁判所はこれを却下しました。その理由は、取引が最終的に承認されたため、申立人には不服を申し立てるための「負担」(Beschwer)がなかった、というものでした。
判例が示す教訓
この判決は、当局(連邦デジタル・経済省、BMAW)が申請書類を法的に再解釈し、より厳格な審査プロセスへと進める広範な裁量権を有していることが確認されました。この「法的擬制」(legal fiction)は、当局の権限の強さを明確に示しています。
当局が申請内容を法的に変更できるということは、投資家は、たとえ「無異議証明書」の申請という形で取引リスクを軽減しようとしても、当局の判断次第で、長期的な審査プロセスに引き込まれる可能性があること、そして取引が最終的に承認されれば、手続き上の問題について裁判所は関与しない可能性が高いことを示しています。
まとめ
オーストリアのInvKGは、欧州における経済安全保障の潮流を反映した、非常に厳格かつ広範な外国直接投資規制です。特に、議決権比率の低い閾値、日本の外為法にはない「事前届出免除制度」の不在、そして違反に対する刑事罰の存在は、日本の経営者や法務担当者が認識すべき最も重要な相違点です。この規制の存在は、オーストリアでのM&Aや事業投資が、単なる商業的判断だけでなく、厳格な法的・戦略的リスク評価を伴うことを意味します。
オーストリアでの投資案件を検討する際には、その対象企業がInvKGの定める「機密性の高い分野」に該当するかどうかを初期段階で慎重に評価し、専門家による法務デューデリジェンスを徹底的に実施する必要があります。取引完了前に当局の承認を得ることは、取引そのものの法的有効性を確保し、潜在的な刑事・民事上のリスクを回避するために不可欠なステップです。最新の判例は、オーストリアの投資審査が、当局の裁量と実質的な判断に大きく依存することを示しており、事前の法律専門家との緊密な連携と、当局との建設的なコミュニケーションの必要性を強く示していると言えるでしょう。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務