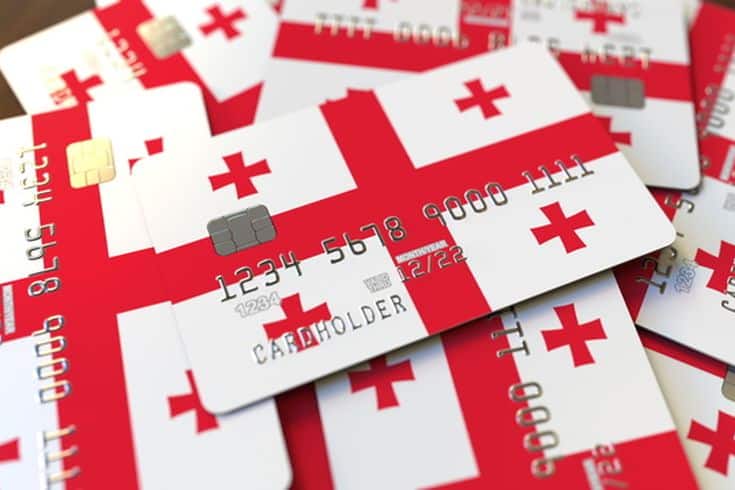ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«µ░æµ│ĢŃü©Õźæń┤äµøĖõĮ£µłÉŃü¦ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃéŗÕźæń┤äµ│ĢŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼

ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½ÕåģŃü¦Ńü«õ║ŗµźŁŃü¬Ńü®Ńü¦Õźæń┤äµøĖŃéÆõĮ£µłÉŃā╗õ┐«µŁŻŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«Õźæń┤äµ│ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗń¤źĶŁśŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«Õźæń┤äµ│ĢŃü»ŃĆüŃüŗŃüżŃü”ŃĆīÕźæń┤äµ│Ģ2056Õ╣┤’╝ł2000Õ╣┤’╝ēŃĆŹŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ”ÅÕŠŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü2017Õ╣┤Ńü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīÕøĮÕ«Čµ░æµ│ĢÕģĖ2074Õ╣┤’╝ł2017Õ╣┤’╝ēŃĆŹŃüīõĖ╗Ķ”üŃü¬µ│ĢńÜäµĀ╣µŗĀŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ░æµ│ĢÕģĖŃü»ŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«µ░æõ║ŗµ│ĢÕģ©õĮōŃéÆÕīģµŗ¼ńÜäŃü½µĢ┤ńÉåŃā╗ńĄ▒ÕÉłŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕźæń┤äŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ”ÅÕ«ÜŃééŃüØŃü«õĖĆķā©Ńü©ŃüŚŃü”ÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüµŚ¦Õźæń┤äµ│Ģ2056Õ╣┤Ńü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü©ÕøĮÕ«Čµ░æµ│ĢÕģĖ2074Õ╣┤Ńü½Ńü»ķĆŻńČܵƦŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüķüÄÕÄ╗Ńü«µ│ĢĶ¦ŻķćłŃéäÕłżõŠŗŃüīÕ╝ĢŃüŹńČÜŃüŹÕÅéńģ¦ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüäŃĆüŃü©Ķ©ĆŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü¦Ńü»ŃĆüĶź┐µÜ”Ńü©Ńü»ÕłźŃü½ŃāōŃé»Ńā®ŃāĀµÜ”Ńü©ŃüäŃüåńŗ¼Ķć¬Ńü«µÜ”ŃüīõĮ┐ŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃāōŃé»Ńā®ŃāĀµÜ”Ńü»ń┤ĆÕģāÕēŹ57Õ╣┤ŃéÆĶĄĘÕ╣┤Ńü©ŃüŚŃĆüĶź┐µÜ”Ńü«4µ£łÕŹŖŃü░ŃéƵ¢░Õ╣┤Ńü©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüĶź┐µÜ”2000Õ╣┤Ńü»ŃāōŃé»Ńā®ŃāĀµÜ”Ńü¦Ńü»2056Õ╣┤ÕÅłŃü»2057Õ╣┤Ńü¦ŃüÖŃĆéŃĆīÕźæń┤äµ│Ģ2056Õ╣┤’╝ł2000Õ╣┤’╝ēŃĆŹŃĆīÕøĮÕ«Čµ░æµ│ĢÕģĖ2074Õ╣┤’╝ł2017Õ╣┤’╝ēŃĆŹŃü©ŃüäŃüåĶĪ©Ķ©śŃü»ŃĆüŃüōŃü«ŃāōŃé»Ńā®ŃāĀµÜ”Ńü½ŃéłŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
Õźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü½ķ¢óŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©ÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüńö│ĶŠ╝Ńü┐Ńü©µē┐Ķ½ŠŃĆüķü®µ│ĢŃü¬ń┤äÕøĀ’╝łÕ»ŠõŠĪ’╝ēŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ĶāĮÕŖøŃĆüĶć¬ńö▒Ńü¬ÕÉīµäÅŃĆüķü®µ│ĢŃü¬ńø«ńÜäŃü©ŃüäŃüŻŃü¤Õ¤║µ£¼ńÜäŃü¬Ķ”üń┤ĀŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«Ķ”üń┤ĀŃüīµ¼ĀŃüæŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕźæń┤äŃü»ńäĪÕŖ╣ŃüŠŃü¤Ńü»ÕÅ¢µČłÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹŃüīµśÄńż║ńÜäŃü½Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗńé╣ŃéäŃĆüµśÄńż║ńÜäŃü¬ÕÉłµäÅŃüīŃü¬ŃüÅŃü©ŃééÕźæń┤äķ¢óõ┐éŃüīµłÉń½ŗŃüŚŃüåŃéŗŃĆīķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õźæń┤äŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ńĢ░Ńü¬ŃéŗÕĮóŃü¦Ķ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ŃāæŃā╝ŃéĮŃā│Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»ńē╣Ńü½µ│©µäÅŃéÆĶ”üŃüÖŃéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«µ░æµ│ĢŃü©Õźæń┤äµ│ĢŃü½ŃüżŃüäŃü”Õ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüīĶ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü«Õģ©õĮōÕāÅŃü©ŃüØŃü«µ”éĶ”üŃü½ķ¢óŃüŚŃü”Ńü»õ╗źõĖŗŃü«Ķ©śõ║ŗŃü¦Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü«Õģ©õĮōÕāÅŃü©ŃüØŃü«µ”éĶ”üŃéÆÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüīĶ¦ŻĶ¬¼
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
Õźæń┤äŃü«µłÉń½ŗĶ”üõ╗ČŃü©ŃĆīń┤äÕøĀŃĆŹ

ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ£ēÕŖ╣Ńü¬Õźæń┤äŃü«µłÉń½ŗŃü½Ńü»ŃĆüĶżćµĢ░Ńü«Õ¤║µ£¼ńÜäŃü¬Ķ”üń┤ĀŃüīÕ┐ģķĀłŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüńö│ĶŠ╝Ńü┐Ńü©µē┐Ķ½ŠŃĆüń┤äÕøĀŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ĶāĮÕŖøŃĆüĶć¬ńö▒Ńü¬ÕÉīµäÅŃĆüÕÉłµ│ĢńÜäŃü¬ńø«ńÜäŃĆüńó║Õ«¤µĆ¦ŃĆüµ│ĢńÜäŃü¬µŗśµØ¤µäŵĆØŃĆüŃüØŃüŚŃü”Õ▒źĶĪīÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü»µŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤䵳Éń½ŗĶ”üõ╗ČŃü©ÕżÜŃüÅŃü«ńé╣Ńü¦Õģ▒ķĆÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü¬Ńüäµ”éÕ┐ĄŃüīŃĆüŃĆīń┤äÕøĀ’╝łConsideration’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆéń┤äÕøĀŃü»ŃĆüķćæķŖŁŃĆüŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃĆüńē®ÕōüŃü¬Ńü®ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü¦õ║żµÅøŃüĢŃéīŃéŗõŠĪÕĆżŃüéŃéŗŃééŃü«ŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ķü®µ│ĢŃü¦ńÅŠÕ«¤ńÜäŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüķüĢµ│ĢŃüŠŃü¤Ńü»õĖŹķüōÕŠ│Ńü¬ĶĪīńé║ŃéÆÕɽŃüŠŃü¬ŃüäŃééŃü«Ńü¦Ńü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüń┤äÕøĀŃüīŃü¬ŃüäÕźæń┤äŃü»õĖĆĶł¼ńÜäŃü½ńäĪÕŖ╣Ńü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüÕźæń┤äµøĖõĮ£µłÉŃéäõ┐«µŁŻŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃü«ń┤äÕøĀŃéƵśÄńż║ŃüÖŃéŗĶ”üĶ½ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»Ķŗ▒ń▒│µ│ĢŃü½ńē╣ÕŠ┤ńÜäŃü¬µ”éÕ┐ĄŃü¦ŃüÖŃĆ鵌źµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»ÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ŃĆīń┤äÕøĀ’╝łconsideration’╝ēŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»ÕŁśÕ£©ŃüŚŃü¬ŃüäŃü¤Ńéü ŃĆüĶŗ▒ń▒│µ│Ģń│╗Ńü«ÕĮ▒ķ¤┐ŃüīÕ╝ĘŃüäŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃü©Ńü»ŃüōŃü«ńé╣Ńü¦ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Ńü«ŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹ
ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Õźæń┤äµ│ĢŃü«ńē╣ÕŠ┤Ńü«õĖĆŃüżŃü»ŃĆüŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐’╝łUndue Influence’╝ēŃĆŹŃüīŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«ÕŖøķ¢óõ┐éŃéäõ┐ĪķĀ╝ķ¢óõ┐éŃü«µ┐½ńö©ŃéÆķś▓ŃüÄŃĆüń£¤Ńü½Ķć¬ńö▒Ńü¬ÕÉīµäÅŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕźæń┤äŃü«µłÉń½ŗŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ķćŹĶ”üŃü¬Ķ”ÅÕ«ÜŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Õźæń┤äµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹŃü©Ńü»ŃĆüŃĆīõ╗¢ĶĆģŃü«ÕĮ▒ķ¤┐õĖŗŃü½ŃüéŃéŗŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃü«ĶĆģŃü«µäÅÕÉæŃü½ÕŠōķĀåŃü¬ĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬Õł®ńøŖŃéÆÕŠŚŃéŗµäÅÕø│ŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃü«ŃéłŃüåŃü¬Õł®ńøŖŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖµäÅÕø│ŃéÆŃééŃüŻŃü”ĶĪīõĮ┐ŃüĢŃéīŃéŗÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬õĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ÕÉīµäÅŃüīÕÅ¢ÕŠŚŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃü»ŃĆīÕÅ¢µČłÕÅ»ĶāĮ’╝łvoidable’╝ēŃĆŹŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕÅ¢µČłÕÅ»ĶāĮÕźæń┤äŃü©Ńü»ŃĆüĶó½Õ«│ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«Ķ½ŗµ▒éŃü½ŃéłŃéŖĶŻüÕłżµēĆŃüīńäĪÕŖ╣ŃéÆÕ«ŻĶ©ĆŃü¦ŃüŹŃéŗÕźæń┤äŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüĶó½Õ«│ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü»Õźæń┤äŃü«Ķ¦ŻķÖż’╝łrescission’╝ēŃéäÕĤńŖČÕø×ÕŠ®ŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüŃĆīĶć¬ńö▒Ńü¬ÕÉīµäÅŃĆŹŃüīÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü«Õ┐ģķĀłĶ”üń┤ĀŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕ╝ĘĶ┐½’╝łcoercion’╝ēŃĆüĶ®Éµ¼║’╝łfraud’╝ēŃĆüõĖŹÕ«¤ĶĪ©ńż║’╝łmisrepresentation’╝ēŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»õĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐’╝łundue influence’╝ēŃüīŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃüīµśÄńó║Ńü½µ▒éŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖƵ¢╣ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü»µśÄµ¢ćŃü¦Ķ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆ鵌źµ£¼µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüµäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü«ńæĢń¢ĄŃü©ŃüŚŃü”ŃĆīĶ®Éµ¼║’╝łµ░æµ│Ģ96µØĪ1ķĀģ’╝ēŃĆŹŃüŖŃéłŃü│ŃĆīÕ╝ĘĶ┐½’╝łµ░æµ│Ģ96µØĪ1ķĀģ’╝ēŃĆŹŃüīÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐Ńü½ŃéłŃéŗÕźæń┤äŃü»ŃĆüÕĆŗÕłźŃü«õ║ŗµĪłŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüĶ®Éµ¼║ŃéäÕ╝ĘĶ┐½Ńü«Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖŃüŗŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»Õģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚķüĢÕÅŹ’╝łµ░æµ│Ģ90µØĪ’╝ēŃü©ŃüŚŃü”ńäĪÕŖ╣Ńü©ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃüīŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹŃéÆńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”µśÄńż║ńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃüīŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«ÕŖøķ¢óõ┐éŃéäõ┐ĪķĀ╝ķ¢óõ┐éŃü«µ┐½ńö©Ńü½ŃéłŃéŗõĖŹÕģ¼Õ╣│Ńü¬Õźæń┤äŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéłŃéŖńø┤µÄźńÜäŃüŗŃüżÕ║āń»äŃü¬õ┐ØĶŁĘŃéÆõĖÄŃüłŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŗŃééŃü«ŃüĀŃü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü¦Ńü«Õźæń┤äõ║żµĖēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüńē╣Ńü½µö»ķģŹńÜäÕ£░õĮŹŃü½ŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃéäŃĆüńøĖµēŗµ¢╣Ńü©Ńü«ķ¢ōŃü½ńē╣ÕłźŃü¬ķ¢óõ┐éµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉł’╝łõŠŗ’╝Üõ╗ŻńÉåõ║║ŃĆüķøćńö©õĖ╗ŃĆüÕ«ČµŚÅķ¢óõ┐éŃü¬Ńü®’╝ēŃĆüÕźæń┤äńĘĀńĄÉŃü½Ķć│ŃéŗŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüńøĖµēŗµ¢╣Ńü«Ķć¬ńö▒Ńü¬µäŵĆØŃüīńó║õ┐ØŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃĆüŃéłŃéŖµģÄķćŹŃü½ńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
õ╗źõĖŗŃü½ŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃü©µŚźµ£¼µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü«µ»öĶ╝āŃéÆńż║ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
| ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒ | ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│Ģ’╝łÕøĮÕ«Čµ░æµ│ĢÕģĖ2074Õ╣┤ńŁē’╝ē | µŚźµ£¼µ│Ģ’╝łµ░æµ│Ģ’╝ē |
| õĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ | µśÄńż║ńÜäŃü½ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Õ«ÜńŠ®ŃĆéÕĮ▒ķ¤┐õĖŗŃü½ŃüéŃéŗĶĆģŃüĖŃü«ÕĆŗõ║║ńÜäÕł®ńøŖńø«ńÜäŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ĶĪīõĮ┐ | µśÄµ¢ćĶ”ÅÕ«ÜŃü¬ŃüŚŃĆéÕĆŗÕłźŃü«õ║ŗµĪłŃü¦Ķ®Éµ¼║ŃĆüÕ╝ĘĶ┐½ŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚķüĢÕÅŹŃü©ŃüŚŃü”µē▒ŃéÅŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ |
| Ķ®Éµ¼║ | ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”µśÄńż║ńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«Ü | µ░æµ│Ģ96µØĪ1ķĀģŃü½ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Ķ”ÅÕ«Ü |
| Õ╝ĘĶ┐½ | ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”µśÄńż║ńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«Ü | µ░æµ│Ģ96µØĪ1ķĀģŃü½ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Ķ”ÅÕ«Ü |
| õĖŹÕ«¤ĶĪ©ńż║ | ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”µśÄńż║ńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«Ü | ńø┤µÄźŃü«ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃüīŃĆüĶ®Éµ¼║Ńü½ÕɽŃüŠŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃéäķī»Ķ¬żŃü©ŃüŚŃü”µē▒ŃéÅŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŗ |
| ķī»Ķ¬ż | Õźæń┤äŃüīńäĪÕŖ╣Ńü©Ńü¬ŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŗ | µ░æµ│Ģ95µØĪŃü½ÕÅ¢µČłõ║ŗńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Ķ”ÅÕ«Ü |
ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Õźæń┤äµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õźæń┤äŃĆŹ
ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Õźæń┤äµ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüŃĆīķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õźæń┤ä’╝łIndirect contract’╝ēŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»ŃĆüµśÄńż║ńÜäŃü¬ÕÉłµäÅŃüīŃü¬ŃüÅŃü”ŃééŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«ĶĪīńé║ŃéäńŖȵ│üŃü½ŃéłŃüŻŃü”µ│ĢńÜäŃü¬ńŠ®ÕŗÖŃüīńö¤ŃüśŃéŗŃĆüŃüäŃéÅŃéåŃéŗŃĆīµ║¢Õźæń┤ä’╝łQuasi-contract’╝ēŃĆŹŃü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»ŃĆüµŚ¦ŃĆīÕźæń┤äµ│Ģ2056Õ╣┤ŃĆŹŃü«ń¼¼11µØĪŃü½µśÄńó║Ńü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüńÅŠĶĪīŃü«ŃĆīÕøĮÕ«Čµ░æµ│ĢÕģĖ2074Õ╣┤ŃĆŹŃü½ŃééÕ╝ĢŃüŹńČÖŃüīŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüäŃüōŃü©Ńüīńż║ÕöåŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«õĖ╗Ńü¬ńø«ńÜäŃü»ŃĆüõĖƵ¢╣Ńü«ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīõ╗¢µ¢╣Ńü«ńŖĀńē▓Ńü«ŃééŃü©Ńü½õĖŹÕĮōŃü½Õł®ńøŖŃéÆÕŠŚŃéŗŃüōŃü©ŃéÆķś▓ŃüÄŃĆüÕģ¼µŁŻŃéÆńČŁµīüŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Õźæń┤äµ│Ģ2056Õ╣┤ń¼¼11µØĪŃü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ńŖȵ│üŃü¦Õźæń┤äŃüīµłÉń½ŗŃüŚŃü¤Ńü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃü©Ķ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
- ńäĪĶāĮÕŖøĶĆģŃüŠŃü¤Ńü»µēČķżŖŃüĢŃéīŃéŗĶĆģŃüĖŃü«Õ┐ģķ£ĆÕōüŃü«µÅÉõŠø’╝ÜÕźæń┤äńĘĀńĄÉĶāĮÕŖøŃü«Ńü¬ŃüäĶĆģŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüØŃü«µēČķżŖŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃüØŃü«ńżŠõ╝ÜńÜäÕ£░õĮŹŃü½Ķ”ŗÕÉłŃüŻŃü¤Õ┐ģķ£ĆÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃüīµÅÉõŠøŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµÅÉõŠøĶĆģŃü»ŃüØŃü«Ķ▓╗ńö©ŃéÆÕÅŚńøŖĶĆģŃü«Ķ▓ĪńöŻŃüŗŃéēÕø×ÕÅÄŃüÖŃéŗµ©®Õł®ŃéƵ£ēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
- õ╗¢ĶĆģŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«õ╗ŻõĮŹÕ╝üµĖł’╝Üõ╗¢ĶĆģŃüīµö»µēĢŃüåŃü╣ŃüŹķćæķĪŹŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüŃüØŃü«µö»µēĢŃüäŃéäõĖŹµēĢŃüäŃü½Õł®Õ«│ķ¢óõ┐éŃü«ŃüéŃéŗĶĆģŃüīĶć¬Ńéēµö»µēĢŃüäŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«ĶĆģŃü»µ£¼µØźŃü«ńŠ®ÕŗÖĶĆģŃü«Ķ▓ĪńöŻŃüŗŃéēŃüØŃü«µö»µēĢŃüäŃéÆÕÅ¢ŃéŖµł╗ŃüÖµ©®Õł®ŃéƵ£ēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
- ńē®ÕōüŃüŠŃü¤Ńü»ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«µÅÉõŠøŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕ»ŠõŠĪ’╝ÜŃüéŃéŗĶĆģŃüīõ╗¢ĶĆģŃü½ńē®ÕōüŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüÕŖ┤ÕŗÖŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü¤ŃéŖŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«ńē®ÕōüŃéäÕŖ┤ÕŗÖŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗķü®ÕłćŃü¬Ķ▓╗ńö©ŃüŠŃü¤Ńü»ÕĀ▒ķģ¼Ńüīµö»µēĢŃéÅŃéīŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
- õ╗¢ĶĆģŃü«Ķ▓ĪńöŻŃü«ÕŹĀµ£ē’╝ÜŃüéŃéŗĶĆģŃüīõ╗¢ĶĆģŃü«Ķ▓ĪńöŻŃéƵ│ĢńÜäŃü½õ┐صīüŃü¦ŃüŹŃéŗÕĮóŃü¦ÕĆŗõ║║ńÜäŃü½ÕŹĀµ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Ķ▓ĪńöŻŃü»Õ»äĶ©Śńē®’╝łbailment property’╝ēŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- Ķ¬żŃüŻŃü”µö»µēĢŃéÅŃéīŃü¤ķćæķĪŹŃü«Ķ┐öķéä’╝ÜŃüéŃéŗĶĆģŃüīĶ¬żŃüŻŃü”õ╗¢ĶĆģŃü½µö»µēĢŃüŻŃü¤ķćæķĪŹŃü»ŃĆüĶ┐öķéäŃüĢŃéīŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
µŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»ŃĆüŃĆīķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õźæń┤äŃĆŹŃü©ŃüäŃüåńø┤µÄźŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüÕÉīµ¦śŃü«ńŖȵ│üŃü»ŃĆīõ║ŗÕŗÖń«ĪńÉå’╝łNegotiorum Gestio’╝ēŃĆŹŃüŖŃéłŃü│ŃĆīõĖŹÕĮōÕł®ÕŠŚ’╝łUnjust Enrichment’╝ēŃĆŹŃü«ÕĤÕēćŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ”ÅÕŠŗŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- õ║ŗÕŗÖń«ĪńÉå’╝łµ░æµ│Ģ697µØĪ’╝ē’╝ܵ│ĢńÜäŃü¬ńŠ®ÕŗÖŃü¬ŃüÅŃüŚŃü”õ╗¢õ║║Ńü«Ńü¤ŃéüŃü½õ║ŗÕŗÖŃü«ń«ĪńÉåŃéÆķ¢ŗÕ¦ŗŃüŚŃü¤ĶĆģ’╝łń«ĪńÉåĶĆģ’╝ēŃü»ŃĆüŃüØŃü«õ║ŗÕŗÖŃü«µĆ¦Ķ│¬Ńü½ÕŠōŃüäŃĆüµ£ĆŃééµ£¼õ║║Ńü«Õł®ńøŖŃü½ķü®ÕÉłŃüÖŃéŗµ¢╣µ│ĢŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüŃüØŃü«õ║ŗÕŗÖŃü«ń«ĪńÉå’╝łõ║ŗÕŗÖń«ĪńÉå’╝ēŃéÆŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéń«ĪńÉåĶĆģŃü»ŃĆüµ£¼õ║║Ńü«Ńü¤ŃéüŃü½µö»Õć║ŃüŚŃü¤Ķ▓╗ńö©ŃéäĶ▓ĀŃüŻŃü¤ÕéĄÕŗÖŃü½ŃüżŃüäŃü”Õä¤ķéäĶ½ŗµ▒鵩®ŃéƵ£ēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
- õĖŹÕĮōÕł®ÕŠŚ’╝łµ░æµ│Ģ703µØĪŃĆü704µØĪ’╝ē’╝ܵ│ĢÕŠŗõĖŖŃü«ÕĤÕøĀŃü¬ŃüÅõ╗¢õ║║Ńü«Ķ▓ĪńöŻŃüŠŃü¤Ńü»ÕŖ┤ÕŗÖŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õł®ńøŖŃéÆÕÅŚŃüæŃĆüŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃü½õ╗¢õ║║Ńü½µÉŹÕż▒ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüŚŃü¤ĶĆģ’╝łÕÅŚńøŖĶĆģ’╝ēŃü»ŃĆüŃüØŃü«Õł®ńøŖŃü«ÕŁśŃüÖŃéŗķÖÉÕ║”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃüōŃéīŃéÆĶ┐öķéäŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµé¬µäÅŃü«ÕÅŚńøŖĶĆģŃü»ŃĆüÕÅŚŃüæŃü¤Õł®ńøŖŃü½Õł®µü»ŃéÆõ╗śŃüŚŃü”Ķ┐öķéäŃüŚŃĆüŃüĢŃéēŃü½µÉŹÕ«│ŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃüØŃü«Ķ│ĀÕä¤Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Õźæń┤äķüĢÕÅŹµÖéŃü«µĢæµĖłµÄ¬ńĮ«Ńü©Õ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«ńĢÖµäÅńé╣

ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕźæń┤äķüĢÕÅŹŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕźæń┤äõĖŖŃü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ▒źĶĪīŃüŚŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õ▒źĶĪīŃüŚŃü¬Ńü䵌©ŃéÆķĆÜń¤źŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ŃüØŃü«ĶĪīÕŗĢŃéäµģŗÕ║”ŃüŗŃéēÕ▒źĶĪīĶāĮÕŖøŃüīŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃüīµśÄŃéēŃüŗŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ńÖ║ńö¤ŃüÖŃéŗŃü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬Õźæń┤äķüĢÕÅŹŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüĶó½Õ«│ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«µÉŹÕ«│ŃéÆÕø×ÕŠ®ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ĶżćµĢ░Ńü«µĢæµĖłµÄ¬ńĮ«ŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗Ńü¬µĢæµĖłµÄ¬ńĮ«Ńü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤ŃĆüńē╣Õ«ÜÕ▒źĶĪīŃĆüŃüØŃüŚŃü”Õźæń┤äĶ¦ŻķÖżŃüīĶ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃüÜŃĆüŃĆīµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕ䤒╝łCompensation/Damages’╝ēŃĆŹŃü»ŃĆüÕźæń┤äķüĢÕÅŹŃü½ŃéłŃéŖńö¤ŃüśŃü¤ńø┤µÄźńÜäŃüŗŃüżńÅŠÕ«¤Ńü«µÉŹÕż▒ŃüŠŃü¤Ńü»µÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüĶó½õŠĄÕ«│ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕÉłńÉåńÜäŃü¬ķćæķĪŹŃéÆĶ½ŗµ▒éŃü¦ŃüŹŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüķ¢ōµÄźńÜäŃüŠŃü¤Ńü»ķüĀķÜöńÜäŃü¬µÉŹÕż▒ŃéäµÉŹÕ«│Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Ķ½ŗµ▒éŃü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕźæń┤äŃü½õ║ŗÕēŹŃü½ÕÉłµäÅŃüĢŃéīŃü¤Ķ│ĀÕä¤ķĪŹ’╝łķüĢń┤äķćæ’╝ēŃüīÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«ń»äÕø▓ÕåģŃü¦ÕÉłńÉåńÜäŃü¬ķćæķĪŹŃéÆĶ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆé
µ¼ĪŃü½ŃĆüŃĆīńē╣Õ«ÜÕ▒źĶĪī’╝łSpecific Performance’╝ēŃĆŹŃü»ŃĆüķćæķŖŁńÜäĶŻ£Õä¤ŃüīĶó½õŠĄÕ«│ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«Ķó½ŃüŻŃü¤Õ«¤ķÜøŃü«µÉŹÕż▒ŃüŠŃü¤Ńü»µÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕÉłńÉåńÜäŃüŗŃüżÕŹüÕłåŃü¦Ńü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ńü½õ╗ŻŃüłŃü”Õźæń┤äŃü«ńē╣Õ«ÜÕ▒źĶĪīŃéÆĶ½ŗµ▒éŃü¦ŃüŹŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüķćæķŖŁŃü¦Ńü»õ╗Żµø┐Ńü¦ŃüŹŃü¬Ńüäńē╣ÕłźŃü¬ńē®ÕōüŃéäÕĮ╣ÕŗÖŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕźæń┤äŃü½ŃüŖŃüäŃü”ńē╣Ńü½ķćŹĶ”üŃü¬µĢæµĖłµēŗµ«ĄŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüńē╣Õ«ÜÕ▒źĶĪīŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü¬Ńüäńē╣Õ«ÜŃü«ńŖȵ│üŃééÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃü«ńøŻńØŻŃüīÕø░ķøŻŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕĆŗõ║║ńÜäÕĮ╣ÕŗÖÕźæń┤ä’╝łõŠŗ’╝Üńē╣Õ«ÜŃü«ŃéóŃā╝ŃāåŃéŻŃé╣ŃāłŃü½ŃéłŃéŗÕģ¼µ╝ö’╝ēŃĆüÕ▒źĶĪīŃüīńē®ńÉåńÜäŃü½õĖŹÕÅ»ĶāĮŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ŃüÖŃü¦Ńü½Õźæń┤äŃéÆńĀ┤µŻäŃüŚŃü¤Õü┤Ńüīńē╣Õ«ÜÕ▒źĶĪīŃéÆĶ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü¬Ńü®Ńü¦ŃüÖŃĆé
µ£ĆÕŠīŃü½ŃĆüŃĆīÕźæń┤äĶ¦ŻķÖż’╝łRescission’╝ēŃĆŹŃü»ŃĆüõĖƵ¢╣Ńü«ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ĶĪīńé║ŃüŠŃü¤Ńü»ĶĪīÕŗĢŃüīÕźæń┤äŃü«ķćŹÕż¦Ńü¬õĖŹÕ▒źĶĪīŃéÆńż║ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüõ╗¢µ¢╣Ńü«ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīķĆÜń¤źŃü½ŃéłŃéŖÕźæń┤äŃéÆĶ¦ŻķÖżŃüÖŃéŗµ©®Õł®ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕźæń┤äŃüīĶ¦ŻķÖżŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃĆüÕźæń┤äŃéÆńĄéõ║åŃüÖŃéŗÕĮōõ║ŗĶĆģŃü»Ķć¬ÕĘ▒Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ▒źĶĪīŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃü¬ŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü«µĢæµĖłµÄ¬ńĮ«Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äķüĢÕÅŹ’╝łÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪī’╝ēŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗµĢæµĖł’╝łµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ½ŗµ▒éŃĆüÕ▒źĶĪīĶ½ŗµ▒éŃĆüÕźæń┤äĶ¦ŻķÖż’╝ēŃü©Õ¤║µ£¼ńÜäŃü½Õģ▒ķĆÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ńü«ń»äÕø▓Ńüīńø┤µÄźµÉŹÕ«│Ńü½ķÖÉÕ«ÜŃüĢŃéīŃĆüńē╣ÕłźµÉŹÕ«│Ńü»õ║łĶ”ŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ķÖÉŃüŻŃü”Ķ│ĀÕä¤Õ»ŠĶ▒ĪŃü©ŃüÖŃéŗńé╣’╝łµ░æµ│Ģ416µØĪ’╝ēŃéäŃĆüķćæķŖŁĶ│ĀÕä¤ŃüīõĖŹÕŹüÕłåŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃü½ńē╣Õ«ÜÕ▒źĶĪīŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗ’╝łµ░æµ│Ģ414µØĪ’╝ēŃüīŃĆüÕĆŗõ║║ńÜäÕĮ╣ÕŗÖÕźæń┤äŃü¬Ńü®ńē╣Õ«ÜÕ▒źĶĪīŃüīÕø░ķøŻŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃü»ÕłČķÖÉŃüĢŃéīŃéŗńé╣ŃééÕģ▒ķĆÜŃü¦ŃüÖŃĆéŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü¦Ńü«Õźæń┤äµøĖõĮ£µłÉµÖéŃü½Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃéÆŃāÖŃā╝Ńé╣Ńā®ŃéżŃā│Ńü©ŃüŚŃü¤õĖŖŃü¦Ńü«õ║żµĖēŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃü¬ŃüŖŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü¦Ńü»µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ńü«Ķ½ŗµ▒éµÖéÕŖ╣Ńüī2Õ╣┤Ńü©µ»öĶ╝āńÜäń¤ŁŃüäŃü¤ŃéüŃĆüĶ┐ģķƤŃü¬Õ»ŠÕ┐£Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗńé╣Ńü½µ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü¦Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃéäŃĆüŃüØŃéīŃü½õ╝┤ŃüåÕźæń┤äµøĖŃü«õĮ£µłÉŃéäõ┐«µŁŻŃéÆĶĪīŃüåŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«Õźæń┤äµ│ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµĘ▒ŃüäńÉåĶ¦ŻŃü©ŃĆüŃüØŃéīŃü½õ╝┤Ńüåķü®ÕłćŃü¬µ│ĢńÜ䵳”ńĢźŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü½Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃéäŃĆüŃĆīķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õźæń┤äŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”µśÄńż║ńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüĢŃéīŃü¤µ║¢Õźæń┤äńÜäńŠ®ÕŗÖŃü«ķĪ×Õ×ŗŃü»ŃĆüõ║łµ£¤ŃüøŃü¼µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéƵŗøŃüÅÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüń┤░Õ┐āŃü«µ│©µäÅŃéƵēĢŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Õźæń┤äńĘĀńĄÉŃü½ķÜøŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«µ│ĢńÜäĶāĮÕŖøŃĆüĶć¬ńö▒Ńü¬ÕÉīµäÅŃü«µ£ēńäĪ’╝łńē╣Ńü½ŃĆīõĖŹÕĮōŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃĆŹŃü«µÄÆķÖż’╝ēŃĆüń┤äÕøĀŃü«ķü®µ│ĢµĆ¦Ńā╗µ£ēÕŖ╣µĆ¦ŃĆüÕźæń┤äńø«ńÜäŃü«ÕÉłµ│ĢµĆ¦Ńā╗Õ▒źĶĪīÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü¬Ńü®ŃĆüÕ¤║µ£¼ńÜäŃü¬Õźæń┤äĶ”üõ╗ČŃéÆÕŠ╣Õ║ĢńÜäŃü½ńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«ŃāćŃāźŃā╝ŃāćŃā¬ŃéĖŃé¦Ńā│Ńé╣ŃéƵĆĀŃéŗŃü©ŃĆüÕŠīŃĆģŃü«ń┤øõ║ēŃéäÕźæń┤äŃü«ńäĪÕŖ╣Õī¢Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤õ║ŗµģŗŃü½ńÖ║Õ▒ĢŃüÖŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńÅŠÕ£░Ńü¦µģŻń┐ÆńÜäŃü¬ÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆĶĪīŃüåÕĀ┤ÕÉłŃéäŃĆüńĘŖµĆźµÖéŃü«Õ»ŠÕ┐£ŃéÆĶ┐½ŃéēŃéīŃéŗÕĀ┤ķØóŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃééŃĆüŃĆīķ¢ōµÄźńÜäŃü¬Õźæń┤äŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃĆüµäÅÕø│ŃüøŃü¼µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃéÆĶ¬ŹĶŁśŃüŚŃĆüµģÄķćŹŃü½ĶĪīÕŗĢŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Õźæń┤äķüĢÕÅŹŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«µĢæµĖłµÄ¬ńĮ«Ńü»µŚźµ£¼µ│ĢŃü©ķĪ×õ╝╝ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«Ńü«ŃĆüŃāŹŃāæŃā╝Ńā½Ńü«ĶŻüÕłżÕłČÕ║”Ńéäõ╗Żµø┐ńÜäń┤øõ║ēĶ¦Żµ▒║’╝łADR’╝ēŃāĪŃé½ŃāŗŃé║ŃāĀ’╝łõ╗▓ĶŻüŃü¬Ńü®’╝ēŃü«Õł®ńö©ÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃĆüŃüØŃüŚŃü”Ķ©┤Ķ©¤Ńü«µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ō’╝ł2Õ╣┤’╝ēŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīŃĆüĶ┐ģķƤŃüŗŃüżÕŖ╣µ×£ńÜäŃü¬ń┤øõ║ēĶ¦Żµ▒║Ńü«Ńü¤ŃéüŃü½õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéńē╣Ńü½µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü«ń¤ŁŃüĢŃü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīń┤øõ║ēĶ¦Żµ▒║ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüĶ┐ģķƤŃü¬µäŵĆص▒║Õ«ÜŃü©ĶĪīÕŗĢŃéÆõ┐āŃüÖĶ”üÕøĀŃü©Ńü¬ŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ķ¢óķĆŻÕÅ¢µē▒ÕłåķćÄ’╝ÜÕøĮķÜøµ│ĢÕŗÖŃā╗µĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: ŃāŹŃāæŃā╝Ńā½µĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ