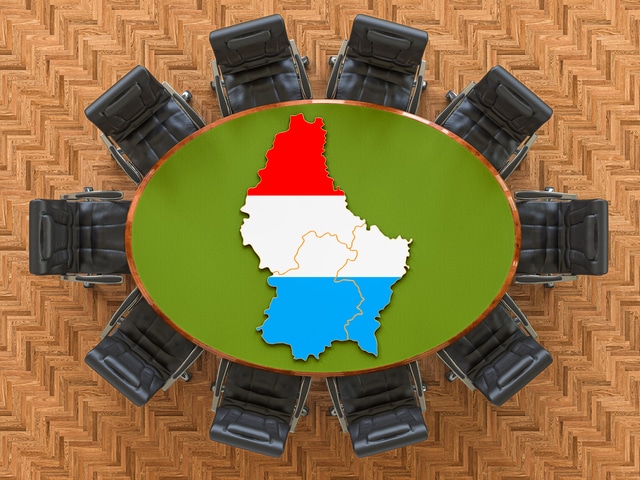タイ王国におけるノミニー(名義貸し)規制と2024年のプーケットノミニー事件

近年、タイでは、外国人事業法(Foreign Business Act, B.E. 2542)に基づくノミニー(Nominee、名義貸し)規制をめぐる法務環境が根本的に変化しています。これは、従来の事業慣行がもはや通用しない、「パラダイムシフト」と捉えるべきです。
タイでは、外国人が株式の過半数を支配する会社では、大部分の事業が許可制となります。この制約を受けることを避けるため、現地人に形式的に株式の過半数を持たせる、名義貸し(ノミニー)という手法があります。これは法的に「グレーゾーン」と言われていましたが、実際問題として、横行していました。
…と、ここまでを前提に、タイ当局は、近年、こうした外国投資構造を根絶するため、取締りを劇的に強化しています。法執行機関がデジタル技術を駆使し、司法機関が「形式」よりも「実態」を厳格に追求するという構造により、こうした「ノミニー」は、もはや「グレーゾーン」ではなく、現実的に刑事罰などが課せられる「犯罪行為」になっているのです。
本記事では、タイの外国人事業法(FBA)の基本原則から、当局が連携して行う最新の摘発手法、そして象徴的な裁判例である「プーケットノミニー事件」までを包括的に解説します。
なお、タイ王国の包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
タイ外国人事業法(FBA)の基本構造
外国人事業法(FBA)の概要
外国人事業法(Foreign Business Act, B.E. 2542, 1999)は、外国人がタイ国内で特定の事業を営むことを規制する主要な法律です。この法律は、外国投資を全面的に拒絶するのではなく、あくまでタイ国民がまだ競争力を持ち得ていない分野や、国家的に重要な分野を保護するための枠組みとして、後述する「外国人」が「特定の規制業種に関して」事業を行うことを規制しています。
「外国人」の定義と事業活動の制限
FBAにおいて「外国人」と定義される主体は多岐にわたります。タイ国籍を持たない個人や、タイ国外で登記された法人だけでなく、タイ国内で登記された法人であっても、以下の条件に該当すれば「外国人」と見なされます。
- 資本金の半分以上が、FBAが定義する「外国人」によって保有されている法人。
- 外国人の出資が、その法人の総資本の半分以上を占めている法人。
この「資本金の過半数」という定義から、ノミニー構造が広く利用されてきました。すなわち、外国人投資家は、形式上、タイ人株主が株式の過半数(51%以上)を保有する法人を設立することで、FBA上の「外国人」の定義を回避しようと試みてきたのです。
規制業種の三つのリスト
FBAは、「外国人」による事業活動を、その性質に応じて3つのリストに分類し、それぞれに異なる規制を課しています。
- リスト1:国家の安全保障や、伝統文化、天然資源に深く関わる事業が含まれ、原則として外国人が事業許可を取得することはできません。これには、報道、ラジオ・テレビ放送、米作、畜産、土地取引などが含まれます。
- リスト2:国の安全保障や文化、環境に影響を与える可能性のある事業が含まれ、事業を営むには、商務大臣の許可が必要です。
- リスト3:タイ国民がまだ外国人との競争に十分備えられていないと見なされる事業が含まれます。これには、会計、法律、建築、エンジニアリングなどのサービス業や、特定の建設業などが該当し、商務省事業開発局(DBD)の許可が必要です。
FBAに関する詳細は下記記事にてまとめています。
ノミニー規制の定義と認定基準

ノミニー(Nominee)とは
タイの法務環境において、ノミニーとは、法的な名義上の所有者(例:株主、取締役)として登記されているものの、実際には、実質的な経営権、経済的リスク、利益の享受権を持たず、外国人投資家のために名義を貸している個人または法人を指します。この定義は、書類上の形式ではなく、資金源や経営の実態といった「実質」によるものです。
そしてこの上で、FBA第36条は、外国人による規制業種への投資を間接的に幇助・支援する目的で、外国人のために株式を保有したり、名義を貸したりする行為を犯罪としています。
タイ司法の「実態」重視の姿勢
タイの司法は、ノミニーに関して、「形式(Form)よりも実質(Substance)を重視する」という考え方を、従前から示していました。2004年の最高裁判例(Supreme Court Decision No. 2975/2547)においても、裁判所は当事者間の「真の経済的結びつき」を重視すべきだと判断しています。
この長年の法理が、近年になってクローズアップされているのは、調査当局がその「実態」を調査・証明するための手段を飛躍的に向上させたことによります。デジタル技術の進歩により、資金源の不整合や経営への関与の欠如といった、これまで調査や証明が困難であった証拠が、容易に収集できるようになったのです。
調査当局が着目する「レッドフラグ」(危険信号)
タイの当局、特に商務省事業開発局(DBD)と特別捜査局(DSI)は、ノミニー構造を特定するために複数の「レッドフラグ」(危険信号)を監視していると言われています。
具体的には、例えば、株主構成に関して、外国人投資家の持分が規制の閾値である50%をわずかに下回る49.99%に集中している場合や、少数のタイ人が複数の企業で名義上の株主を務めている場合、さらに事業許可申請や当局の調査直前に株主構成が急に変更されている場合に、当局は疑念を抱くことがあるとされています。
資金源についても厳しくチェックされます。タイ人株主が自身の資本金拠出を銀行記録などで証明できない場合、あるいは株式の払込金が外国人からの送金や無利子「ローン」によって提供されている場合、さらには外国人からタイ人株主、そして会社へと資金が循環する不自然な流れが確認された場合などは、ノミニーと認定される可能性があります。
経営や運営の実態も重要な判断材料です。名義上のタイ人株主や取締役が経営会議に不参加であったり、事業内容や財務状況について当局の質問に答えられなかったりする場合、また外国人投資家が銀行口座の管理、契約締結、人事決定といったすべての主要な意思決定を行っている場合も、疑いの目が向けられます。外国人がすべての権利を委譲する包括的な委任状(Power of Attorney)が存在することも危険信号となります。
さらに、利益の配分も調査の対象です。タイ人株主が配当を一切受け取っていない、あるいは会社の利益が外国人への不自然な「サービス料」や「ローン返済」として計上されている場合も、ノミニー構造の存在を示す兆候とされます。
取締りの激化とプーケットノミニー事件
複数の省庁による連携強化
タイ当局は、商務省事業開発局(DBD)だけでなく、特別捜査局(DSI)、王立タイ警察、さらにはマネーロンダリング対策局(AMLO)が連携し、ノミニー構造に対する大規模な摘発キャンペーンを実施しています。
デジタル技術を活用した摘発手法
近年の取締りの最も特徴的な点は、テクノロジーの積極的な活用です。当局は、もはや書類の不備や匿名の通報だけに頼っていません。
- データクロスチェック:商務省事業開発局(DBD)は、企業登記情報(株主リスト、取締役、資本金)を歳入局(Revenue Department)の税務記録とリアルタイムで照合するシステムを運用しています。このシステムは、タイ人株主の納税記録に、その持ち株比率に見合った配当収入が計上されていないといった、資金の不整合を自動的に検出し、当局が捜査を開始するきっかけとなっています。
- Intelligence Business Analytics System (IBAS):2025年8月に本格稼働が予定されているこのシステムは、人工知能(AI)やアルゴリズムを用いて、複雑な企業ネットワークを分析します。このシステムは、複数の企業で同じタイ人名が株主として繰り返し登場するパターンなど、人間の目では見つけにくいノミニーの兆候を自動的に「レッドフラグ」として通知します。
これらの技術革新は、ノミニー構造のリスクを根本的に変えました。これまでは、「運悪く摘発される」という偶発的なリスクであったものが、今や「いつ摘発されてもおかしくない」という恒常的なリスクへと変質したことを意味します。
刑事法院判決 A. 2812/2567(プーケットノミニー事件)
2024年にプーケットで発生した大規模な摘発事件は、タイ当局の厳格な姿勢を象徴する出来事となりました。特別捜査局(DSI)は、外国人のためにノミニー会社の設立・斡旋に関与していた地元の法律・会計事務所の捜査に着手しました。この事務所は、約60社のノミニー会社にタイ人を名義上の取締役や株主として提供していたとされています。DSIの調査によると、捜査対象となった企業のうち44社が不動産業、8社が観光業、14社がその他のサービス業を営んでおり、不動産関連会社の資産は総額で4億4000万バーツに上ると推定されています。
そして、判決では、タイ人、外国人、タイ法人、外国法人を含む23人の被告が刑事法院によって有罪判決を受けました。逮捕された外国人の多くはロシア国籍の人物でした。
この判決は、ノミニー構造に関与した「全員」が処罰の対象となることを明確に示しました。裁判所は、外国人事業法(FBA)が「タイ人が外国人による規制業種の事業を支援・参加する行為」と、「外国人がそのタイ人にそのような行為を許可する行為」の両方を犯罪と定めていることから、名義を貸したタイ人だけでなく、実質的支配者である外国人、そしてノミニー構造の構築を支援した法律・会計事務所の関係者も同罪であるとしました。そして、被告人らは当初10年の懲役刑を言い渡されましたが、自白により5年に減刑され、2年間執行猶予、執行猶予期間中に1年間の保護観察期間、各被告に20万バーツの罰金となりました。
また、裁判所は、ノミニー構造を利用して事業を運営していた企業に対し、強制的な解散を命じました。摘発の対象となった事業は、主に不動産や観光関連でした。
この判決が示す最も重要な点は、裁判所が、名義上の株主構成や登記書類ではなく、「外国人投資家が資金を提供し、事業の意思決定を掌握していた」という「事業の実態」を厳しく評価したことです。この事件によって、外国人事業法違反が、単なる行政上の違反ではなく、刑罰を伴う重大な「犯罪行為」であるという認識が確立されました。
ノミニー規制違反の法的リスクと罰則
外国人事業法上の罰則
ノミニー行為に関与した外国人(実質的支配者)およびタイ人(名義貸し人)の両方が、FBA第36条および第37条に基づき刑事罰の対象となります。
- 刑事罰:3年以下の懲役刑。
- 罰金:10万バーツから100万バーツの罰金。
- 追加罰金:違反が継続する場合、1日あたり1万バーツから5万バーツの追加罰金が科せられます。
- 事業閉鎖:裁判所の命令により、事業の強制的な閉鎖と会社解散が命じられます。
マネーロンダリング防止法との関連と資産没収のリスク
ノミニー規制違反の法的リスクは、FBA上の罰則に留まりません。タイ当局は、マネーロンダリング防止法(AMLA)の改正を検討しており、ノミニー規制違反をマネーロンダリングの「原因犯罪」に分類しようとしています。この改正が実現すれば、マネーロンダリング対策局(AMLO)は、犯罪行為から得られたと見なされる資産を凍結・没収する権限を持つことになります。
これは、単なる罰金や懲役刑の増加にとどまらない、リスクの質的な変化を意味します。ノミニー構造を通じて取得された不動産(土地、建物)や銀行口座の資産が強制的に没収されるという壊滅的なリスクです。従来の「罰金を払えば済む」という認識が完全に無効化され、ノミニー制度はもはやビジネスリスクではなく、事業存続を脅かす破滅的なリスクとなります。
ノミニー行為に関与した第三者の責任
当局は、ノミニー構造の構築を支援した第三者、すなわち、法律家、会計士、ビジネス登録サービス提供者、税務アドバイザーなども積極的に捜査・起訴しています。これは、ノミニー制度を可能にしている「エコシステム」全体を破壊し、今後同様の不正行為が発生するのを防ぐという意志の表れでしょう。
先に解説したプーケットノミニー事件では、DSIは外国人向けにノミニー会社を設立・斡旋していた地元の法律・会計事務所を捜査し、最終的に複数の関係者を刑事訴追しました。同様に、バンコク近郊のサムットプラーカーン県では、中国人ビジネスマンにタイ人名義の会社を登録していた疑いで会計事務所が捜査され、タイ人51人と中国人21人が逮捕されるという事件も発生しています。この捜査では、15社のタイ人名義の会社の不正な設立が判明し、土地の権利証や会社印、事業関連書類などが押収されました。
合法的な事業進出のための選択肢と推奨事項

ノミニー制度はもはや持続可能な選択肢ではありません。タイでの事業展開を検討する日本企業は、以下の合法的な方法を検討すべきです。
- 外国人事業許可証(FBL)の取得:規制業種であっても、FBLを取得することで合法的に事業を運営できます。審査は厳格ですが、これが最も直接的で安全な道です。
- タイ投資委員会(BOI)の事業奨励制度の活用:BOIから投資奨励の認定を受けた企業は、外国人による100%出資が認められる場合があります。これは、技術移転や雇用創出といったタイ経済への貢献を前提としています。
- 米国との友好通商条約(Treaty of Amity)の適用:米国籍企業は、この条約により、一部の規制業種でタイ企業とほぼ同等の権利を享受できます。
- 真正なタイ人との合弁事業の構築:単なる名義貸しではなく、タイ人パートナーが真に資金を拠出し、経営に積極的に関与する「真正な」会社を構築することが不可欠です。
また、現時点で既にノミニー構造で事業を運営している企業は、早急に法的構造の見直しを行うべきです。専門家の協力を得て、合法的なスキームへの移行を検討することが、刑事罰や資産没収といったリスクを回避するために必要不可欠となっています。
まとめ
タイのノミニー規制は、長年の法的原則と最新のデジタル技術が融合することで、摘発能力が飛躍的に向上し、罰則も資産没収まで拡大するという、従来の常識を覆す変革期を迎えています。この新しい法務環境下では、安易なノミニー構造は「ビジネスリスク」ではなく、事業存続を脅かす「致命的なリスク」と考えるべきです。
日本人にとって重要なことは、タイの外国人事業法が日本の法制度とは異なる独自の規制体系を持つ一方で、その根底には「形式ではなく実質を問う」という普遍的な法理が存在する点です。タイでの事業展開においては、表面的な株主構成だけでなく、資金源、経営実態、そして利益配分といった「事業の実質」を透明化し、最初から合法的なスキームを構築することが重要です。
もはや、ノミニー制度に依存した事業モデルは持続可能ではありません。タイでのビジネスのためには、適切な専門家のサポートの下で、コンプライアンスを重視した透明性の高い事業運営を進めることが重要になっています。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務