гӮ№гӮӨгӮ№гҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰпјҲд»ҘдёӢгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№пјүгҒҜгҖҒй•·е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘгғ“гӮёгғҚгӮ№жҙ»еӢ•гҒ®дёӯеҝғең°гҖҒгҒҠгӮҲгҒідёӯз«Ӣзҡ„гҒӘзҙӣдәүи§ЈжұәгҒ®е ҙгҒЁгҒ—гҒҰдё–з•Ңзҡ„гҒӘең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҢж…ЈгӮҢиҰӘгҒ—гӮ“гҒ зөұдёҖзҡ„гҒӘеӣҪ家法дҪ“зі»гҒЁгҒҜж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢдәҢгҒӨгҒ®еҺҹеүҮгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢйҖЈйӮҰеҲ¶гҖҚгҒЁгҖҢеӨ§йҷёжі•е…ёдё»зҫ©гҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰж§ӢзҜүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®дёӢгҖҒжі•еҫӢгҒҜйҖЈйӮҰгҖҒ26гҒ®е·һпјҲгӮ«гғігғҲгғіпјүгҖҒгҒҠгӮҲгҒіеҹәзӨҺиҮӘжІ»дҪ“гҒ®дёүеұӨгҒ§еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒҢзөұдёҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе®ҹдҪ“жі•пјҲж°‘жі•е…ёгӮ„еӮөеӢҷжі•е…ёпјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜй«ҳгҒ„дәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒе·һгҒҢз®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жҢҒгҒӨеҲҶйҮҺгҖҒзү№гҒ«иЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе·һгҒ”гҒЁгҒ«з•°гҒӘгӮӢиҰҸеүҮгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢиӨҮйӣ‘гҒ•гӮ’жңүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮ№гӮӨгӮ№ж°‘жі•е…ёпјҲZGBпјүгҒЁеӮөеӢҷжі•е…ёпјҲORпјүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒЁе…ұйҖҡгҒ®гғ«гғјгғ„гӮ’жҢҒгҒӨгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒзү©жЁ©еӨүеӢ•гҒ®еҺҹеүҮгҒӘгҒ©гҖҒе•ҶеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғӘгӮ№гӮҜз®ЎзҗҶгҒ«зӣҙзөҗгҒҷгӮӢжұәе®ҡзҡ„гҒӘж§ӢйҖ зҡ„гҒӘзӣёйҒ•зӮ№гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжңҖй«ҳеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲBGerпјүгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰиӯ°дјҡгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ—гҒҹжі•еҫӢгҒ®йҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ©гӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰзү№з•°гҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬190жқЎпјүгҖӮ
жң¬зЁҝгҒ§гҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж—Ҙжң¬гҒ®зөҢе–¶иҖ…гҒҠгӮҲгҒіжі•еӢҷйғЁе“ЎгҒ®зҡҶж§ҳгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҰгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ®ж №е№№гӮ’гҒӘгҒҷгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж§ӢйҖ гӮ’и©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘе·®з•°гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҰгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®з•ҷж„ҸзӮ№гӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гӮ№гӮӨгӮ№жі•дҪ“зі»гҒ®ж №е№№гӮ’гҒӘгҒҷдәҢгҒӨгҒ®еҺҹеүҮпјҡйҖЈйӮҰеҲ¶гҒЁеӨ§йҷёжі•
йҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®ж§ӢйҖ гҒЁжі•жәҗгҒ®йҡҺеұӨжҖ§
гӮ№гӮӨгӮ№гҒҜгҖҒйҖЈйӮҰпјҲConfederationпјүгҒЁ26гҒ®е·һпјҲCantonпјүгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢйҖЈйӮҰеӣҪ家гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒҢжі•дҪ“зі»е…ЁдҪ“гҒ®йҡҺеұӨжҖ§гӮ’жұәе®ҡгҒҘгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйҖЈйӮҰжҶІжі•пјҲSR 101пјүгҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®жі•зҡ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖй«ҳгҒ®жі•жәҗгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®йҖЈйӮҰгҖҒе·һгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒ®жі•д»ӨгҒ«е„Әи¶ҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№гҒ®жЁ©йҷҗй…ҚеҲҶгҒҜгҖҢж®ӢдҪҷжЁ©йҷҗгҖҚгҒ®еҺҹеүҮгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬3жқЎгҒҜгҖҒе·һгҒ®дё»жЁ©гҒҢйҖЈйӮҰжҶІжі•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒе·һгҒҢе…ЁгҒҰгҒ®жЁ©еҲ©гӮ’иЎҢдҪҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒйҖЈйӮҰгҒ«жҳҺзўәгҒ«жЁ©йҷҗгҒҢд»ҳдёҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәӢй …пјҲдҫӢпјҡж°‘дәӢгҒ®е®ҹдҪ“жі•гҖҒеҲ‘жі•гҖҒйҖҡиІЁпјүгҒ®гҒҝгҒҢйҖЈйӮҰгҒ®з®ЎиҪ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ®дәӢй …гҒҜе·һгҒҢз®ЎиҪ„жЁ©гӮ’дҝқжҢҒгҒ—гҒҫгҒҷпјҲйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬42жқЎгҖҒ第43жқЎпјүгҖӮгҒ“гҒ®жЁ©йҷҗеҲҶз«ӢгҒ®дёӢгҒ§гҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒҜе·һжі•гӮ„е·һжҶІжі•гҒ«е„Әи¶ҠгҒ—гҒҫгҒҷпјҲйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬49жқЎпјүгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒдёӯеӨ®ж”ҝеәңгҒҢеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҢжі•еҫӢгҒ®зҜ„еӣІеҶ…гҒ§дәӢеӢҷгӮ’йҒӮиЎҢгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰпјҲең°ж–№иҮӘжІ»жі•пјүгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®е·һгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰгҒ«е§”иӯІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәӢй …гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®жҶІжі•гӮ’жңүгҒ—гҖҒз«Ӣжі•жЁ©гӮ’иЎҢдҪҝгҒҷгӮӢдё»жЁ©зҡ„гҒӘеӯҳеңЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®еҺҹеүҮгҒҜгҖҒзү№гҒ«е®ҹеӢҷзҡ„гҒӘеҒҙйқўгҒ§иӨҮйӣ‘гҒ•гӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж°‘дәӢгғ»еҲ‘дәӢгҒ®е®ҹдҪ“жі•гҒҜйҖЈйӮҰжі•гҒЁгҒ—гҒҰзөұдёҖгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁҙиЁҹиІ»з”ЁгӮ„дёҖйғЁгҒ®иЎҢж”ҝжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•иҰҸеҲ¶гҒҜе·һгҒ”гҒЁгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгҖҒгҒ©гҒ®е·һпјҲиЈҒеҲӨең°пјүгҒ§зҙӣдәүгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚиҰҸеүҮгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№ж°‘жі•е…ёпјҲZGBпјүгҒЁеӮөеӢҷжі•е…ёпјҲORпјүгҒ®ж§ӢйҖ
гӮ№гӮӨгӮ№гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„гӮ„гғ•гғ©гғігӮ№гҒ®жі•дҪ“зі»гҒӢгӮүеј·гҒ„еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹеӨ§йҷёжі•пјҲгӮ·гғ“гғ«гғӯгғјпјүгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«еұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯеҝғгӮ’гҒӘгҒҷгҒ®гҒҢгҖҒ1912е№ҙгҒ«зҷәеҠ№гҒ—гҒҹгӮ№гӮӨгӮ№ж°‘жі•е…ёпјҲZGBпјҡZivilgesetzbuchпјүгҒ§гҒҷгҖӮ
ZGBгҒҜгҖҒдәәжі•гҖҒ家ж—Ҹжі•гҖҒзӣёз¶ҡжі•гҖҒзү©жЁ©жі•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒеёӮж°‘й–“гҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘй–ўдҝӮгӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№еӮөеӢҷжі•е…ёпјҲORпјҡObligationenrechtпјүгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ZGBгҒ®гҖҢ第5йғЁгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰдёҖдҪ“зҡ„гҒ«дҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷ 4гҖӮORгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„жі•гҖҒдёҚжі•иЎҢзӮәжі•гҖҒдёҚеҪ“еҲ©еҫ—гҖҒе•ҶдәӢжі•гҖҒдјҡзӨҫжі•гҒӘгҒ©гҖҒеӮөжЁ©й–ўдҝӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеәғзҜ„гҒӘдәӢй …гӮ’з¶Ізҫ…гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•е…ёпјҲеӮөжЁ©з·ЁпјүгҒҠгӮҲгҒіе•Ҷжі•е…ёгҒ®дёҖйғЁгҒҢгӮ«гғҗгғјгҒҷгӮӢеҶ…е®№гӮ’еҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ZGBгҒЁORгҒҜгҖҒгҒқгҒ®и«–зҗҶзҡ„гҒӘдҪ“зі»жҖ§гҒЁжҳҺзўәгҒ§зҗҶи§ЈгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„иЁҳиҝ°гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒӢгӮүгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒ«гӮӮй«ҳгҒҸи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жі•е…ёгҒҜгҖҒгғҲгғ«гӮігӮ„гғҡгғ«гғјгҒ®жі•е…ёеҲ¶е®ҡгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒйҹ“еӣҪгҖҒеҸ°ж№ҫгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжқұгӮўгӮёгӮўи«ёеӣҪгҒ®жі•е…ёгҒ«гӮӮгҒқгҒ®еҪұйҹҝгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•е…ёгҒҜ1898е№ҙгҒ®еҲ¶е®ҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҲ¶е®ҡйҒҺзЁӢгҒ§еӨҡгҒҸгҒ®еӨ–еӣҪжі•е…ёгӮ’еҸӮз…§гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«еӨ§йҷёжі•дҪ“зі»гҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮ’е…ұжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬жі•гҒЁгӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘзӣёйҒ•зӮ№пјҡеҘ‘зҙ„гғ»зү©жЁ©еӨүеӢ•гҒ®еҺҹеүҮ
гӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒЁж—Ҙжң¬жі•гҒҢеӨ§йҷёжі•дҪ“зі»гҒ«еұһгҒ—гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е…ұйҖҡжҰӮеҝөгӮ’жҢҒгҒӨдёҖж–№гҒ§гҖҒзү№гҒ«е•ҶеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжұәе®ҡзҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгҖҢзү©жЁ©еӨүеӢ•гҖҚгҒ®еҺҹеүҮгҒ§гҒҷгҖӮ
еҘ‘зҙ„гҒ®гҖҢеӮөжЁ©зҡ„еҠ№еҠӣгҒ®гҒҝгҖҚгҒ®еҺҹеүҮгҒЁзү©жЁ©гҒ®еҲҶйӣўпјҲSeparation Principleпјү
гӮ№гӮӨгӮ№жі•пјҲORпјүгҒ®дёӢгҒ§гҒҜгҖҒеЈІиІ·еҘ‘зҙ„гҒӘгҒ©гҒ®еӮөжЁ©еҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ«е•Ҷе“ҒгҒ®еј•жёЎгҒ—гӮ„д»ЈйҮ‘ж”Ҝжү•гҒ„гҒ®зҫ©еӢҷпјҲеӮөжЁ©пјүгӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢгҒ«йҒҺгҒҺгҒҡгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®з· зөҗгҒ®гҒҝгҒ§гҒҜгҖҒжүҖжңүжЁ©гҒӘгҒ©гҒ®зү©жЁ©гҒҜ移転гҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
зү©жЁ©пјҲжүҖжңүжЁ©пјүгҒ®з§»и»ўгӮ’йҒ”жҲҗгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеӮөжЁ©еҘ‘зҙ„пјҲеҺҹеӣ иЎҢзӮәпјүгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ®еҗҲж„ҸгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«жЁ©еҲ©гӮ’移転гҒ•гҒӣгӮӢгҖҢзү©жЁ©зҡ„иЎҢзӮәгҖҚпјҲеҮҰеҲҶиЎҢзӮәпјүгҒҢиҰҒжұӮгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеӢ•з”ЈгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиІ·дё»гҒёгҒ®еј•жёЎгҒ—пјҲеҚ жңүгҒ®з§»и»ўпјүгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒзҷ»иЁҳгҒҢе®ҢдәҶгҒ—гҒҰеҲқгӮҒгҒҰжүҖжңүжЁ©гҒҢ移転гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒҜгҖҢеҲҶйӣўеҺҹеүҮпјҲSeparation PrincipleпјүгҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢзү©жЁ©зҡ„еҠ№еҠӣгҒ®ж¬ еҰӮпјҲNo Translative EffectпјүгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒ®ж„ҸжҖқиЎЁзӨәпјҲеЈІиІ·еҘ‘зҙ„гҒ®з· зөҗпјүгҒ®гҒҝгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзӣҙгҒЎгҒ«зү©жЁ©гҒҢ移転гҒҷгӮӢгҖҢж„ҸжҖқдё»зҫ©гҖҚгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲ民法第176жқЎпјүгҖӮзҷ»иЁҳгӮ„еј•жёЎгҒ—гҒҜгҖҒ第дёүиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҜҫжҠ—иҰҒ件пјҲ民法第177жқЎпјүгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§жүҖжңүжЁ©гҒҢ移転гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгҖҒзү№гҒ«еЈІдё»гҒҫгҒҹгҒҜиІ·дё»гҒ®еҖ’з”ЈпјҲз ҙз”ЈжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®й–Ӣе§ӢпјүгғӘгӮ№гӮҜгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹйҡӣгҒ«гҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®йҮҚеӨ§гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—д»ЈйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеј•жёЎгҒ—гӮ„зҷ»иЁҳгҒЁгҒ„гҒҶзү©жЁ©зҡ„иЎҢзӮәгҒҢе®ҢдәҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиІ·дё»гҒҜеҚҳгҒӘгӮӢдёҖиҲ¬еӮөжЁ©иҖ…гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒе•Ҷе“ҒгҒ®жүҖжңүжЁ©гӮ’дё»ејөгҒ—гҒҰзўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№жі•дәәгҒЁгҒ®еҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҘ‘зҙ„з· зөҗгҒЁжүҖжңү権移転гҒ®гҖҢзү©жЁ©зҡ„иЎҢзӮәгҖҚгҒ®еұҘиЎҢгӮ’еҺіеҜҶгҒ«з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ«жүҖжңүжЁ©з•ҷдҝқзү№зҙ„гӮ’жҳҺзўәгҒ«иЁӯгҒ‘гӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгғӘгӮ№гӮҜгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®зү№еҲҘгҒӘеҜҫзӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҒ®зөӮдәҶпјҡжҹ”и»ҹжҖ§гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®еҺіж јгҒӘеҹәжә–гҒЁгҒ®е·®з•°
гӮ№гӮӨгӮ№еӮөеӢҷжі•е…ёпјҲORпјүгҒҜгҖҒйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҒ®зөӮдәҶгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгӮӮиҰҸе®ҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҹәжң¬гҒҜеҘ‘зҙ„гҒ®дёҖиҲ¬еҺҹеүҮгҒ«еҫ“гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®еҠҙеғҚжі•еҲ¶гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰйӣҮз”ЁиӘҝж•ҙпјҲи§ЈйӣҮпјүгҒ®жҹ”и»ҹжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒ«гӮҲгӮӢйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҒ®и§ЈйҷӨпјҲи§ЈйӣҮпјүгҒҜгҖҒеҠҙеғҚеҘ‘зҙ„法第16жқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒгҖҢе®ўиҰізҡ„гҒ«еҗҲзҗҶзҡ„гҒӘзҗҶз”ұгӮ’ж¬ гҒҚгҖҒзӨҫдјҡйҖҡеҝөдёҠзӣёеҪ“гҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҚгҒҜгҖҒи§ЈйӣҮжЁ©гҒ®жҝ«з”ЁгҒЁгҒ—гҒҰз„ЎеҠ№гҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«дјҒжҘӯгҒҢзөҢжёҲзҡ„гҒӘзҗҶз”ұгҒ§дәәе“ЎеүҠжёӣгӮ’иЎҢгҒҶж•ҙзҗҶи§ЈйӣҮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гҖҢеӣӣиҰҒ件гҖҚгӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгӮ’еҺіж јгҒ«иҰҒжұӮгҒ—гҒҫгҒҷ 7гҖӮ
- дәәе“ЎеүҠжёӣгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§
- и§ЈйӣҮеӣһйҒҝеҠӘеҠӣзҫ©еӢҷгҒ®еұҘиЎҢгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§
- дәәйҒёгҒ®еҗҲзҗҶжҖ§
- жүӢз¶ҡгҒҚгҒ®зӣёеҪ“жҖ§
гҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒи§ЈйӣҮеӣһйҒҝеҠӘеҠӣзҫ©еӢҷгҒ®еұҘиЎҢпјҲдёҠиЁҳ2пјүгҒҜзү№гҒ«еҺіж јгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜж•ҙзҗҶи§ЈйӣҮгҒҜгҖҢжңҖеҫҢгҒ®жүӢж®өгҖҚгҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгҖҒйӣҮз”Ёдё»гҒҜи§ЈйӣҮгӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҒӮгӮүгӮҶгӮӢжүӢж®өгӮ’е°ҪгҒҸгҒҷзҫ©еӢҷгӮ’иІ гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒ®дёӢгҒ§гҒҜгҖҒгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“зӨҫдјҡзҡ„дҝқиӯ·гҒ®иҰҒзҙ гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲӨдҫӢжі•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҹ№гӮҸгӮҢгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®еҺіж јгҒӘгҖҢи§ЈйӣҮеӣһйҒҝеҠӘеҠӣзҫ©еӢҷгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй«ҳеәҰгҒ«иҰҸеҲ¶зҡ„гҒӘеҹәжә–гҒҜйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ§дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’иЎҢгҒҶдјҒжҘӯгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж„ҹиҰҡгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒзҸҫең°гҒ®ORгҒҠгӮҲгҒій–ўйҖЈеҠҙеғҚжі•гҒ®иҰҸе®ҡгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„жӣёгӮ„е°ұжҘӯиҰҸеүҮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒи§ЈйӣҮдәӢз”ұгҒЁжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’жҳҺзўәгҒӢгҒӨе…·дҪ“зҡ„гҒ«е®ҡзҫ©гҒ—гҖҒеҘ‘зҙ„гғҷгғјгӮ№гҒ§гҒ®з®ЎзҗҶгӮ’еҫ№еә•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®еӨҡеұӨж§ӢйҖ гҒЁйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®зү№з•°гҒӘеҪ№еүІ
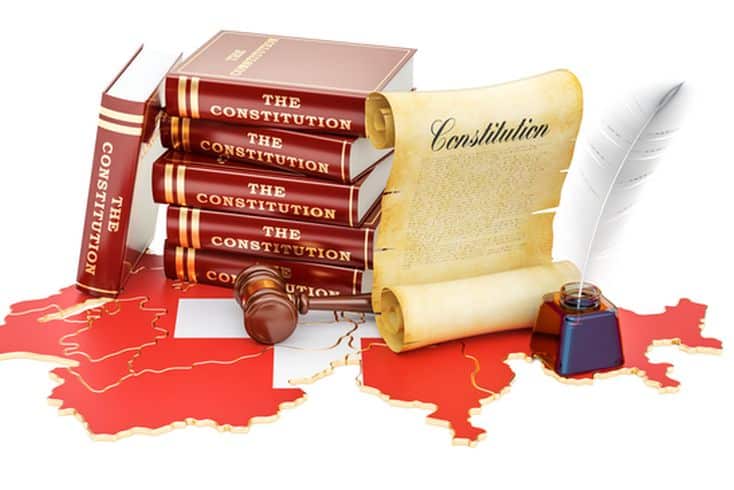
е·һиЈҒеҲӨжүҖгҒЁйҖЈйӮҰиЈҒеҲӨжүҖгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гҒ®еҲҶз«Ӣ
гӮ№гӮӨгӮ№гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰеҲ¶гӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҒҹеӨҡеұӨзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮеӨ§йғЁеҲҶгҒ®ж°‘дәӢгҒҠгӮҲгҒіеҲ‘дәӢдәӢ件гҒҜгҖҒе·һгғ¬гғҷгғ«гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз®ЎиҪ„гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҗ„е·һгҒ«гҒҜгҖҒ第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖгҒҠгӮҲгҒідёҠиЁҙеҜ©иЈҒеҲӨжүҖгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҖЈйӮҰгғ¬гғҷгғ«гҒ«гҒҜгҖҒжңҖй«ҳеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲBGerпјҡBundesgericht/Swiss Federal TribunalпјүгҒ®д»–гҒ«гҖҒ第дёҖеҜ©гҒ®йҖЈиҪ„иЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҒ—гҒҰд»ҘдёӢгҒ®дё»иҰҒгҒӘиЈҒеҲӨжүҖгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰеҲ‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖпјҲSwiss Federal Criminal CourtпјүпјҡйҖЈйӮҰгҒ®з®ЎиҪ„гҒ«еұһгҒҷгӮӢзү№е®ҡгҒ®еҲ‘дәӢдәӢ件пјҲдҫӢпјҡйҖЈйӮҰгғ¬гғҷгғ«гҒ®зө„з№”зҠҜзҪӘпјүгӮ’第дёҖеҜ©гҒЁгҒ—гҒҰеҜ©зҗҶгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖпјҲSwiss Federal Administrative CourtпјүпјҡйҖЈйӮҰиЎҢж”ҝж©ҹй–ўгҒ®жұәе®ҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдёҚжңҚз”ігҒ—з«ӢгҒҰгӮ’еҜ©зҗҶгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰзү№иЁұиЈҒеҲӨжүҖпјҲSwiss Federal Patent CourtпјүпјҡзҷәжҳҺзү№иЁұгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҙӣдәүгӮ’жүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲBGerпјүгҒҜгҖҒе·һгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ„йҖЈйӮҰдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҖзөӮеҜ©гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒҷ гҖӮBGerгҒ®дё»иҰҒгҒӘеҪ№еүІгҒҜгҖҒдәӢе®ҹй–ўдҝӮгӮ’еҶҚжӨңиЁјгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжі•зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒ®зөұдёҖзҡ„гҒӘйҒ©з”ЁгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ©гҒ®жұәе®ҡзҡ„гҒӘйҷҗе®ҡпјҡйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬190жқЎгҒ®еҺҹеүҮ
гӮ№гӮӨгӮ№гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒҢжңҖгӮӮж§ӢйҖ зҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒЁгҒ—гҒҰиӘҚиӯҳгҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒҜгҖҒйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲBGerпјүгҒ®жЁ©йҷҗгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲ¶зҙ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬190жқЎпјҲ Relevant Law/йҒ©з”Ёжі•иҰҸпјүгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®д»–гҒ®жі•йҒ©з”Ёж©ҹй–ўгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒЁеӣҪйҡӣжі•гҒ«еҫ“гҒҶпјҲArt. 190 Applicable Law. The Federal Supreme Court and the other authorities applying law shall follow the Federal Statutes and international law.пјүгҖӮ
гҒ“гҒ®иҰҸе®ҡгҒ®зөҗжһңгҖҒBGerгӮ’еҗ«гӮҖиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰиӯ°дјҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹйҖЈйӮҰжі•гҒҢжҶІжі•гҒ«йҒ•еҸҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҗҶз”ұгҒ§гҖҒгҒқгҒ®жі•еҫӢгҒ®йҒ©з”ЁгӮ’жӢ’еҗҰгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒз„ЎеҠ№гҒЁе®Је‘ҠгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮйҖЈйӮҰжі•гҒҜгҖҒжҶІжі•гҒ«йҒ©еҗҲгҒҷгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒжҶІжі•з¬¬81жқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжі•еҫӢгҖҒе‘Ҫд»ӨгҖҒиҰҸеүҮгҒӘгҒ©гҒҢжҶІжі•гҒ«йҒ©еҗҲгҒҷгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгӮ’жңҖзөӮзҡ„гҒ«жұәе®ҡгҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨгҖҢжҶІжі•гҒ®з•ӘдәәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№гҒ§еҸёжі•еҜ©жҹ»гҒҢйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдјқзөұзҡ„гҒӘзҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҒқгҒ®зӢ¬иҮӘгҒ®зӣҙжҺҘж°‘дё»еҲ¶гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҖЈйӮҰиӯ°дјҡгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ—гҒҹжі•еҫӢгҒҜгҖҒдёҖе®ҡж•°гҒ®еёӮж°‘гҒҢиҰҒжұӮгҒҷгӮҢгҒ°еӣҪж°‘жҠ•зҘЁпјҲгғ¬гғ•гӮЎгғ¬гғігғҖгғ пјүгҒ«д»ҳгҒ•гӮҢгҖҒеӣҪж°‘иҮӘиә«гҒҢгҒқгҒ®жі•еҫӢгҒ®жҳҜйқһгӮ’жұәе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еӣҪж°‘жҠ•зҘЁгҒҢгҖҒдәӢе®ҹдёҠгҒ®жҶІжі•еҜ©жҹ»гҒ®еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁи§ЈйҮҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒЁеӣҪйҡӣжі•гҒҢзҹӣзӣҫгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒBGerгҒҜйҖЈйӮҰжі•гҒ®йҒ©з”ЁгӮ’еҒңжӯўгҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жЁ©йҷҗиЎҢдҪҝгҒҜж…ҺйҮҚгҒ§гҒҷгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒиӯ°дјҡгҒҢеӣҪйҡӣжі•гӮ’ж„Ҹиӯҳзҡ„гҒ«йҒ•еҸҚгҒ—гҒҰжі•жЎҲгӮ’иө·иҚүгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒBGerгҒҢйҒ©з”ЁеҒңжӯўгӮ’жӢ’еҗҰгҒ—гҒҹеҲӨдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјҲSchubertеҲӨжұәпјҡBGE 99 Ib 39пјүгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲ¶зҙ„гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ§гҒ®гғӯгғ“гӮӨгғігӮ°гӮ„жі•зҡ„жҲҰз•ҘгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢдёҠгҒ§жұәе®ҡзҡ„гҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮйҖЈйӮҰиӯ°дјҡгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ—гҒҹйҖЈйӮҰгғ¬гғҷгғ«гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№жі•иҰҸпјҲдҫӢпјҡзЁҺеҲ¶гӮ„зӢ¬еҚ зҰҒжӯўжі•пјүгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж„ҹиҰҡгҒ§жҶІжі•дёҠгҒ®жЁ©еҲ©дҫөе®ігӮ’дё»ејөгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒқгҒ®з„ЎеҠ№еҢ–гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷжҲҰз•ҘгҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ§гҒҜжҺЎз”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжі•еҲ¶еәҰгҒ®еӨүжӣҙгӮ’жұӮгӮҒгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒз«Ӣжі•еәңпјҲйҖЈйӮҰиӯ°дјҡпјүгҒҫгҒҹгҒҜеӣҪж°‘жҠ•зҘЁгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдё»иҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№пјҲйҖЈйӮҰжі•гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ©пјү
| й …зӣ® | гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰ | ж—Ҙжң¬еӣҪ |
| ж №жӢ жқЎж–Ү | йҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬190жқЎпјҲ Relevant Lawпјү | ж—Ҙжң¬еӣҪжҶІжі•з¬¬81жқЎ |
| йҖЈйӮҰжі•гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ© | гҒӘгҒ—гҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜйҖЈйӮҰжі•гҒ«жӢҳжқҹгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ | гҒӮгӮҠгҖӮжі•еҫӢгҖҒе‘Ҫд»ӨгҖҒиҰҸеүҮгҒӘгҒ©гҒҢжҶІжі•гҒ«йҒ©еҗҲгҒҷгӮӢгҒӢеҜ©жҹ»гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ |
| жі•зҡ„зөұдёҖгҒ®жӢ…гҒ„жүӢ | BGerгҒҜжі•и§ЈйҮҲгҒ®зөұдёҖгӮ’жӢ…еҪ“гҖӮ | жңҖй«ҳиЈҒгҒҜжі•и§ЈйҮҲгҒ®зөұдёҖгҒЁжҶІжі•и§ЈйҮҲгӮ’жӢ…еҪ“гҖӮ |
| ж°‘дё»зҡ„гӮігғігғҲгғӯгғјгғ« | еӣҪж°‘жҠ•зҘЁпјҲгғ¬гғ•гӮЎгғ¬гғігғҖгғ пјүгҒҢеҜ©жҹ»гҒ®д»Јжӣҝж©ҹиғҪгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҖӮ | з«Ӣжі•еәңгҒ®гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҜгҖҒйҒёжҢҷгҒЁеҶҚеҸҜжұәгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«гӮҲгӮӢгҖӮ |
жҲҗж–Үжі•дёӯеҝғдё»зҫ©гҒЁеҲӨдҫӢжі•еҪўжҲҗгҒ®иһҚеҗҲ
гӮ№гӮӨгӮ№гҒҜеӨ§йҷёжі•дҪ“зі»гҒ«еұһгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжі•е…ёпјҲZGBгӮ„ORпјүгҒҢжі•жәҗгҒ®дёӯеҝғгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲBGerпјүгҒҜгҖҒжі•еҫӢгҒ«жҳҺзўәгҒӘиҰҸе®ҡгҒҢгҒӘгҒ„гҖҢжі•гҒ®ж¬ зјәпјҲгҒ‘гҒЈгҒ‘гӮ“пјүгҖҚгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҖҒеҲӨдҫӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰжі•гӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒжі•е…ёгҒ®дҪ“зі»жҖ§гӮ’дҝқгҒЎгҒӨгҒӨгҖҒеҖӢеҲҘе…·дҪ“зҡ„гҒӘдәӢжЎҲгӮ„зӨҫдјҡгҒ®еӨүеҢ–гҒ«жҹ”и»ҹгҒ«еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгҖҒеҲӨдҫӢжі•дё»зҫ©гҒ®иҰҒзҙ гӮ’иһҚеҗҲгҒ•гҒӣгҒҹжҹ”и»ҹгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒӢгӮүгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒ®е®ҹеӢҷзҡ„гҒӘйҒ©з”ЁзҜ„еӣІгӮ’жӯЈзўәгҒ«жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒZGBгӮ„ORгҒ®жқЎж–ҮзҹҘиӯҳгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒBGerгҒ®жңҖж–°гҒ®еҲӨдҫӢпјҲJurisprudenceпјүгӮ’з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«еҸӮз…§гҒ—гҖҒжҲҗж–Үжі•гҒ®и§ЈйҮҲгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҷәеұ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӣҪйҡӣе•ҶдәӢзҙӣдәүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒ®е„ӘдҪҚжҖ§гҒЁжңҖж–°еӢ•еҗ‘
гӮ№гӮӨгӮ№гҒҜгҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҒӘдёӯз«ӢжҖ§гҖҒзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹжі•гҒ®ж”Ҝй…ҚгҖҒгҒқгҒ—гҒҰй«ҳеәҰгҒӘе°Ӯй–ҖжҖ§гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘд»ІиЈҒең°гҒЁгҒ—гҒҰдё–з•Ңзҡ„гҒ«й«ҳгҒ„и©•дҫЎгӮ’еҫ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиҝ‘е№ҙгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒҜеӣҪеҶ…гҒ®иЁҙиЁҹеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘиҰҒжұӮгҒ«еҝңгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘиҝ‘д»ЈеҢ–гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°‘дәӢиЁҙиЁҹжі•пјҲZPOпјүж”№жӯЈпјҡеӣҪйҡӣгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒёгҒ®йҒ©еҝңпјҲ2025е№ҙ1жңҲпјү
гӮ№гӮӨгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒйҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гӮ’з·©е’ҢгҒ—гҖҒеҸёжі•жүӢз¶ҡгҒҚгҒ®зөұдёҖжҖ§гӮ’еӣігӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж°‘дәӢиЁҙиЁҹжі•е…ёпјҲZPOпјҡZivilprozessordnungпјүгҒҢйҖЈйӮҰжі•гҒЁгҒ—гҒҰеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҗ„е·һгҒҢдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰзӢ¬иҮӘгҒ®иҰҸеүҮгӮ’жҢҒгҒӨеҲҶйҮҺгҒҢж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ZPOгҒҢ2025е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«ж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®з°Ўзҙ еҢ–гҖҒиҝ…йҖҹеҢ–гҖҒгҒҠгӮҲгҒігӮігӮ№гғҲеҠ№зҺҮгҒ®ж”№е–„гҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
д»ҠеӣһгҒ®ж”№жӯЈгҒ§зү№гҒ«еӣҪйҡӣгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒд»ҘдёӢгҒ®зӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
- еӣҪйҡӣе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®иЁӯз«Ӣпјҡж”№жӯЈZPOгҒҜгҖҒеҗ„е·һгҒҢеӣҪйҡӣе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖпјҲInternational Commercial CourtsпјүгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’иӘҚгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- иЁҙиЁҹиЁҖиӘһгҒ®иӢұиӘһеҢ–пјҡеӣҪйҡӣе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®иЁӯз«ӢгҒ«дјҙгҒ„гҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘе•ҶжҘӯзҙӣдәүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®иЁҖиӘһгҒЁгҒ—гҒҰиӢұиӘһгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиЁұеҸҜгҒ•гӮҢгӮӢиҰӢиҫјгҒҝгҒ§гҒҷгҖӮ
- иЁҙиЁҹиІ»з”ЁгҒ®еҲ¶йҷҗпјҡиЁҙиЁҹгӮ’жҸҗиө·гҒҷгӮӢеҒҙгҒҢдәӢеүҚгҒ«ж”Ҝжү•гҒҶгҒ№гҒҚиЁҙиЁҹиІ»з”ЁгҒ®еүҚжү•йҮ‘пјҲAdvance on CostsпјүгҒҢгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢиЈҒеҲӨиІ»з”ЁгҒ®еҚҠеҲҶгҒҫгҒ§гҒ«еҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж”№жӯЈгҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒҢеӣҪйҡӣд»ІиЈҒгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёӯз«ӢжҖ§гҒЁеҠ№зҺҮжҖ§гҒ®еј·гҒҝгӮ’гҖҒеӣҪеҶ…гҒ®еӣҪйҡӣе•ҶдәӢиЁҙиЁҹгҒ«гӮӮжӢЎејөгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢжҳҺзўәгҒӘж„ҸжҖқгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«иӢұиӘһгҒ§гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮігғўгғігғӯгғјпјҲиӢұзұіжі•пјүгӮ’жә–жӢ жі•гҒЁгҒҷгӮӢеҘ‘зҙ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгӮ’зҙӣдәүи§Јжұәең°гҒЁгҒ—гҒҰйҒёжҠһгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®еҲ©дҫҝжҖ§гӮ’еӨ§е№…гҒ«й«ҳгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
йҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеӣҪйҡӣд»ІиЈҒеҲӨдҫӢгҒ®еҲҶжһҗ
BGerгҒҜгҖҒеӣҪйҡӣе•ҶдәӢд»ІиЈҒгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲӨдҫӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒгҒқгҒ®иҰӘд»ІиЈҒзҡ„гҒӘе§ҝеӢўгҒЁе®ҹеӢҷйҮҚиҰ–гҒ®ж…ӢеәҰгӮ’жҳҺзўәгҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҹ·иЎҢиҰҒ件гҒ®йқһеҪўејҸдё»зҫ©гҒ®еҺҹеүҮ
BGerгҒҜгҖҒеӣҪйҡӣд»ІиЈҒеҲӨж–ӯгҒ®жүҝиӘҚгғ»еҹ·иЎҢгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘе•ҶжҘӯеҸ–еј•гҒ®зҸҫе®ҹгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢжҹ”и»ҹгҒӘи§ЈйҮҲгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒд»ІиЈҒеҲӨж–ӯгҒ®жүҝиӘҚгҒЁеҹ·иЎҢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜжқЎзҙ„第IVжқЎ(1)(b)гҒҜгҖҒгҖҢд»ІиЈҒеҗҲж„ҸгҒ®еҺҹжң¬еҸҲгҒҜиӘҚ証謄жң¬гҖҚгҒ®жҸҗеҮәгӮ’иҰҒжұӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иҰҒ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒ2011е№ҙ10жңҲ10ж—ҘгҒ®еҲӨжұәпјҲдәӢ件з•ӘеҸ· 5A_427/2011пјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжқЎзҙ„гҒ®иҰҸе®ҡгӮ’йҒҺеәҰгҒ«еҪўејҸзҡ„гҒ«и§ЈйҮҲгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дәӢ件гҒ§гҒҜгҖҒд»ІиЈҒеҗҲж„ҸгҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹгғ—гғӯгғ•гӮ©гғјгғһгӮӨгғігғңгӮӨгӮ№гҒ®еҺҹжң¬гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒFAXгҒ§йҖҒдҝЎгҒ•гӮҢгҒҹгӮігғ”гғјгҒҢжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзӣёжүӢж–№еҪ“дәӢиҖ…гҒҢгҒқгҒ®зңҹжӯЈжҖ§гӮ’дәүгӮҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒBGerгҒҜеҹ·иЎҢгӮ’иӘҚгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹ 14гҖӮ
гҒ“гҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒBGerгҒҢжҠҖиЎ“зҡ„гҒӘжүӢз¶ҡиҰҒ件гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒеӣҪйҡӣе•ҶеҸ–еј•гҒ®иҝ…йҖҹгҒӘи§ЈжұәгҒЁгҖҒд»ІиЈҒеҲӨж–ӯгҒ®е®ҹеҠ№зҡ„гҒӘеҹ·иЎҢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’е„Әе…ҲгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№жі•гҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘиҖғгҒҲж–№гӮ’дҪ“зҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸёжі•еҹ·иЎҢи«ӢжұӮгҒ®жҳҺзўәжҖ§гҒ®иҰҒжұӮ
дёҖж–№гҖҒBGerгҒҜгҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®з°Ўзҙ еҢ–гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи«ӢжұӮеҶ…е®№гҒ®жҳҺзўәжҖ§гҒ«гҒҜеҺіж јгҒӘеҹәжә–гӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒ2025е№ҙ4жңҲ22ж—ҘгҒ®еҲӨжұәпјҲдәӢ件з•ӘеҸ· 4A_666/2024пјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҘ‘зҙ„дёҠгҒ®зӣЈжҹ»жЁ©пјҲAudit RightпјүгҒ®еҸёжі•еҹ·иЎҢгӮ’жұӮгӮҒгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒёгҒ®и«ӢжұӮгҒҜгҖҒжӯЈзўәгҒӢгҒӨйҷҗе®ҡзҡ„гҒ«ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁеј·иӘҝгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒжӣ–жҳ§гҒӘгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеәғзҜ„гҒӘжғ…е ұй–ӢзӨәгӮ’жұӮгӮҒгӮӢи«ӢжұӮгӮ’гҖҒиЁјжӢ еҸҺйӣҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гҖҢйҮЈгӮҠиЎҢзӮәгҖҚпјҲFishing ExpeditionsпјүгҒЁиҰӢгҒӘгҒ—гҒҰеҚҙдёӢгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲӨдҫӢгҒӢгӮүиЁҖгҒҲгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгғ©гӮӨгӮ»гғігӮөгғјгҒҢзӣЈжҹ»жЁ©гҒ®еҹ·иЎҢгӮ’жұӮгӮҒгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒжӨңжҹ»еҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢж–ҮжӣёгҖҒжңҹй–“гҖҒзҜ„еӣІгӮ’жҳҺзўәгҒ«зү№е®ҡгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҘ‘зҙ„дёҠгҒ®зҫ©еӢҷгҒ«й–ўйҖЈгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’з«ӢиЁјгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷ 15гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЁјжӢ еҸҺйӣҶгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢеҺіеҜҶгҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ§гҒ®иЁҙиЁҹжҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒз·»еҜҶгҒӘдәӢе®ҹиӘҚе®ҡгҒЁи«ӢжұӮеҶ…е®№гҒ®йҷҗе®ҡгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡгӮ№гӮӨгӮ№жі•еҲ¶еәҰгҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгғ“гӮёгғҚгӮ№дёҠгҒ®ж©ҹдјҡгҒЁгғӘгӮ№гӮҜ
гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒйҖЈйӮҰеҲ¶гҒ®иӨҮйӣ‘жҖ§гҒЁеӨ§йҷёжі•е…ёгҒ®дҪ“зі»зҡ„дҝЎй јжҖ§гҒҢиһҚеҗҲгҒ—гҒҹзӢ¬зү№гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгҒҢгҒ“гҒ®еӣҪгҒ§дәӢжҘӯгӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҖҒжі•зҡ„зҙӣдәүгҒ«зӣҙйқўгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®иҰҒзӮ№гҒ«з•ҷж„ҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҲҗеҠҹгҒ®йҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гӮӨгӮ№ж°‘жі•е…ёпјҲZGBпјүгҒҠгӮҲгҒіеӮөеӢҷжі•е…ёпјҲORпјүгҒҜгҖҒеӣҪйҡӣеҸ–еј•гҒ®жә–жӢ жі•гҒЁгҒ—гҒҰдҝЎй јгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзү©жЁ©еӨүеӢ•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢеӮөжЁ©зҡ„еҠ№еҠӣгҒ®гҒҝгҖҚгҒ®еҺҹеүҮпјҲеҲҶйӣўеҺҹеүҮпјүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢж„ҸжҖқдё»зҫ©гҖҚгҒЁгҒҜж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮҠгҖҒжүҖжңү権移転гҒ®зўәе®ҹжҖ§гӮ’жӢ…дҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҘ‘зҙ„дёҠгҒ®е·ҘеӨ«гҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲBGerпјүгҒҢйҖЈйӮҰжі•гҒ®зөұдёҖзҡ„йҒ©з”ЁгӮ’жӢ…гҒҶдёҖж–№гҒ§гҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ©гӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬190жқЎгҒ®еҲ¶зҙ„гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷжҲҰз•ҘгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҖҒз«Ӣжі•еәңгӮ’йҖҡгҒҳгҒҹеҜҫеҝңгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒBGerгҒҜеӣҪйҡӣе•ҶдәӢд»ІиЈҒгҒ®еҹ·иЎҢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйқһеҪўејҸзҡ„гҒӢгҒӨе®ҹеӢҷзҡ„гҒӘе§ҝеӢўгӮ’зӨәгҒ—гҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒҢдёӯз«Ӣзҡ„гҒӢгҒӨй«ҳеәҰгҒ«зҷәйҒ”гҒ—гҒҹзҙӣдәүи§Јжұәең°гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЈҸд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒ2025е№ҙ1жңҲж–ҪиЎҢгҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹжі•ж”№жӯЈгҒҜгҖҒеӣҪйҡӣе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®иЁӯз«ӢгӮ„иӢұиӘһгҒ§гҒ®иЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮ’й–ӢгҒҚгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ®еҸёжі•гӮӨгғігғ•гғ©гҒҢеӣҪйҡӣгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®иҰҒжұӮгҒ«з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҝңгҒҲгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢжҳҺзўәгҒӘиЁје·ҰгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гҒӘиӨҮйӣ‘гҒ•гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгғӘгӮ№гӮҜгғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮ№гӮӨгӮ№жі•еҲ¶еәҰгҒ®ж§ӢйҖ зҡ„зү№еҫҙгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®е®ҹеӢҷзҡ„гҒӘе·®з•°гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҖҒгҒҠе®ўж§ҳгҒ®гӮ№гӮӨгӮ№гҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ„еӣҪйҡӣзҙӣдәүи§ЈжұәгӮ’еј·еҠӣгҒ«гӮөгғқгғјгғҲгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гӮ№гӮӨгӮ№йҖЈйӮҰжө·еӨ–дәӢжҘӯ


































