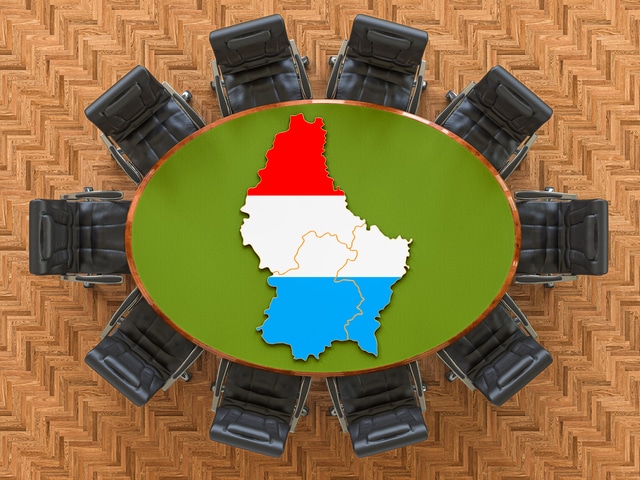гғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гғқгғјгғ©гғігғүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢгҒҳгҒҸеӨ§йҷёжі•пјҲгӮ·гғ“гғ«гғ»гғӯгғјпјүдҪ“зі»гҒ«еұһгҒҷгӮӢеӣҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжі•е…ёгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹжҲҗж–Үжі•дё»зҫ©гӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ§е…ұйҖҡзӮ№гӮӮеӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҶ…е®ҹгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒҜж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘзү№еҫҙгҒҢгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгӮ’зңӢйҒҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜдәҲжңҹгҒӣгҒ¬жі•зҡ„е•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжң¬зЁҝгҒ§гҒҜгҖҒзү№гҒ«гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҶгӮӢгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®ж ёеҝғйғЁеҲҶгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’дәӨгҒҲгҒӘгҒҢгӮүи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•дҪ“зі»гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзү№еҫҙгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жі•жәҗгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гҖҒзү№гҒ«еӣҪйҡӣжі•гҒЁеӣҪеҶ…жі•гҒ®й–ўдҝӮжҖ§гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ1997е№ҙгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹзҸҫиЎҢжҶІжі•гӮ’жңҖй«ҳжі•иҰҸгҒЁгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒҜ欧е·һйҖЈеҗҲпјҲEUпјүеҠ зӣҹеӣҪгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒEUжі•гҒҢеӣҪеҶ…жі•гҒ«е„Әе…ҲгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢEUжі•гҒ®е„ӘдҪҚгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҺҹеүҮгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҶІжі•з¬¬98жқЎгҒҢжқЎзҙ„гҒ®иӘ е®ҹгҒӘйҒөе®ҲгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒжқЎзҙ„гҒЁеӣҪеҶ…жі•гҒ®е„ӘеҠЈй–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҳҺзўәгҒӘйҡҺеұӨгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зӮ№гҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҫҢиҝ°гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒEUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҢгғқгғјгғ©гғігғүеӣҪеҶ…гҒ®еәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гӮ’EUжі•йҒ•еҸҚгҒЁгҒ—гҒҰз„ЎеҠ№гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹиҝ‘жҷӮгҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒҢгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®зҸҫе ҙгҒ«гҒ„гҒӢгҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷгҒӢгӮ’зӨәгҒҷеҘҪдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгҖҒеҸёжі•жЁ©гҒ®ж§ӢйҖ гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢеҚҳдёҖгҒ®гғ”гғ©гғҹгғғгғүж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЎгҖҒдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүдёҠе‘ҠгҒ•гӮҢгӮӢе…ЁгҒҰгҒ®дәӢ件гӮ’жңҖзөӮзҡ„гҒ«з®ЎиҪ„гҒ—гҖҒжі•еҫӢгҒҢжҶІжі•гҒ«йҒ•еҸҚгҒҷгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢйҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ©гӮӮжӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®еҸёжі•жЁ©гҒҜгҖҒжҶІжі•дёҠгҖҢиЈҒеҲӨжүҖпјҲsД…dyпјүгҖҚгҒЁгҖҢжі•е»·пјҲtrybunaЕӮyпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдәҢгҒӨгҒ®з•°гҒӘгӮӢзі»зөұгҒ«жҳҺзўәгҒ«еҲҶйӣўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж°‘дәӢгғ»еҲ‘дәӢдәӢ件гҒӘгҒ©гҒ®дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘиЁҙиЁҹгӮ’жүұгҒҶгҒ®гҒҜгҖҢиЈҒеҲӨжүҖгҖҚгҒ®зі»зөұгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®й ӮзӮ№гҒ«гҒҜжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢдҪҚзҪ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒгҖҢжі•е»·гҖҚгҒ®зі»зөұгҒ«гҒҜгҖҒжі•еҫӢгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’е°Ӯй–Җзҡ„гҒ«еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢжҶІжі•жі•е»·гӮ„гҖҒеӣҪ家гҒ®жңҖй«ҳе№№йғЁгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢејҫеҠҫиЈҒеҲӨгӮ’иЎҢгҒҶеӣҪ家法廷гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«жҶІжі•жі•е»·гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжҢҒгҒӨйҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ©гӮ’е°Ӯй–Җзҡ„гҒ«иЎҢдҪҝгҒҷгӮӢзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҲӨж–ӯгҒҜжі•еҫӢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’з„ЎеҠ№гҒ«гҒҷгӮӢеј·еҠӣгҒӘеҠ№жһңгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®дәҢе…ғзҡ„гҒӘеҸёжі•ж§ӢйҖ гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжі•д»ӨгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢз•°иӯ°з”ігҒ—з«ӢгҒҰгҒ®ж–№жі•гӮ„гҖҒгҒқгҒ®жңҖзөӮзҡ„гҒӘеҲӨж–ӯгҒҢдёӢгҒ•гӮҢгӮӢе ҙгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®еҸёжі•дҪ“зі»гҒ®зү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®ж ёеҝғйғЁеҲҶгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒзү№гҒ«гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢEUжі•гҒ®е„ӘдҪҚгҒ®еҺҹеүҮгҒЁеҸёжі•жЁ©гҒ®дәҢе…ғзҡ„ж§ӢйҖ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’дәӨгҒҲгҒӘгҒҢгӮүи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•жәҗгҒЁгҒқгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ
гғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒ1997е№ҙ4жңҲ2ж—ҘгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгғқгғјгғ©гғігғүе…ұе’ҢеӣҪжҶІжі•гӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢйҡҺеұӨж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•жәҗгҒҜгҖҒеӣҪж°‘е…ЁдҪ“гӮ’жі•зҡ„гҒ«жӢҳжқҹгҒҷгӮӢгҖҢжҷ®йҒҚзҡ„жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨжі•гҖҚгҒЁгҖҒзү№е®ҡгҒ®иЎҢж”ҝж©ҹй–ўеҶ…йғЁгҒ®гҒҝгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢгҖҢеҶ…йғЁжі•гҖҚгҒ«еӨ§еҲҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдәӢжҘӯжҙ»еӢ•гҒ«зӣҙжҺҘй–ўгӮҸгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеүҚиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢжҷ®йҒҚзҡ„жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨжі•гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еәҸеҲ—гҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮВ
- жҶІжі• (Konstytucja)пјҡеӣҪ家гҒ®жңҖй«ҳжі•иҰҸгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»–гҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жі•жәҗгҒҜжҶІжі•гҒ«йҒ©еҗҲгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжҶІжі•з¬¬8жқЎз¬¬1й …гҒҜгҖҒгҖҢжҶІжі•гҒҜгғқгғјгғ©гғігғүе…ұе’ҢеӣҪгҒ®жңҖй«ҳжі•иҰҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁжҳҺзўәгҒ«е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
- жү№еҮҶгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪйҡӣеҚ”е®ҡ (Ratyfikowane umowy miДҷdzynarodowe)пјҡиӯ°дјҡгҒҢеҲ¶е®ҡжі•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдәӢеүҚгҒ®жүҝиӘҚгӮ’дёҺгҒҲгҒҹдёҠгҒ§жү№еҮҶгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪйҡӣеҚ”е®ҡгҒҜгҖҒеӣҪеҶ…гҒ®еҲ¶е®ҡжі•гӮҲгӮҠгӮӮй«ҳгҒ„еҠ№еҠӣгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
- еҲ¶е®ҡжі• (Ustawa)пјҡз«Ӣжі•жЁ©гӮ’жҢҒгҒӨдәҢйҷўеҲ¶гҒ®иӯ°дјҡпјҲгӮ»гӮӨгғ пјҲдёӢйҷўпјүгҒЁгӮ»гғҠгғҲпјҲдёҠйҷўпјүпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгӮӢжі•еҫӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®еӣҪдјҡгҒҢеҲ¶е®ҡгҒҷгӮӢжі•еҫӢгҒ«зӣёеҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- зңҒд»Ө (RozporzД…dzenie)пјҡжҶІжі•гҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹзү№е®ҡгҒ®иЎҢж”ҝж©ҹй–ўпјҲеӨ§зөұй ҳгҖҒй–Јеғҡи©•иӯ°дјҡгҖҒйҰ–зӣёгҖҒеҗ„еӨ§иҮЈгҒӘгҒ©пјүгҒҢгҖҒеҲ¶е®ҡжі•гӮ’ж–ҪиЎҢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒқгҒ®еҲ¶е®ҡжі•гҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжҺҲжЁ©гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰзҷәд»ӨгҒҷгӮӢе‘Ҫд»ӨгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®ж”ҝд»ӨгӮ„зңҒд»ӨгҒ«дјјгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҝ…гҒҡдёҠдҪҚгҒ®еҲ¶е®ҡжі•гҒ«ж №жӢ гӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§ж—Ҙжң¬гҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁгҒ®жҜ”ијғгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжңҖгӮӮжіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚйҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гҒҜгҖҒжү№еҮҶгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪйҡӣеҚ”е®ҡгҒ®ең°дҪҚгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жҶІжі•з¬¬98жқЎз¬¬2й …гҒҜгҖҢж—Ҙжң¬еӣҪгҒҢз· зөҗгҒ—гҒҹжқЎзҙ„еҸҠгҒізўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪйҡӣжі•иҰҸгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’иӘ е®ҹгҒ«йҒөе®ҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁе®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжқЎзҙ„гҒЁеӣҪеҶ…жі•пјҲжі•еҫӢпјүгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒҢе„ӘдҪҚгҒҷгӮӢгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®жҳҺзўәгҒӘиҰҸе®ҡгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӯҰиӘ¬дёҠгӮӮиӯ°и«–гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғқгғјгғ©гғігғүжҶІжі•гҒҜгҖҒиӯ°дјҡгҒ®дәӢеүҚжүҝиӘҚгӮ’еҫ—гҒҰжү№еҮҶгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪйҡӣеҚ”е®ҡгҒҢгҖҒеӣҪеҶ…гҒ®еҲ¶е®ҡжі•пјҲUstawaпјүгҒЁжҠөи§ҰгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еӣҪйҡӣеҚ”е®ҡгҒҢе„Әе…ҲйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁжҳҺзўәгҒ«е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иҰҸе®ҡгҒҜгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒҢ1989е№ҙгҒ®ж°‘дё»еҢ–д»ҘйҷҚгҖҒиҘҝеҒҙи«ёеӣҪгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгӮ’ж·ұгӮҒгҖҒ欧е·һгҒ®дёҖе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘжі•зҡ„жһ зө„гҒҝгҒ«з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеӣҪ家жҲҰз•ҘгӮ’жі•еҲ¶еәҰгҒ®ж №е№№гҒ«жҚ®гҒҲгҒҹгҒ“гҒЁгҒ®зҸҫгӮҢгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«2004е№ҙгҒ®ж¬§е·һйҖЈеҗҲпјҲEUпјүеҠ зӣҹгӮ’иҰӢжҚ®гҒҲгҖҒEUжі•гҒЁгҒ„гҒҶе·ЁеӨ§гҒӘеӣҪйҡӣжі•зҡ„жһ зө„гҒҝгӮ’еӣҪеҶ…жі•дҪ“зі»гҒ«еҶҶж»‘гҒ«зө„гҒҝиҫјгӮҖгҒҹгӮҒгҒ®жҶІжі•дёҠгҒ®еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒҰиЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гғқгғјгғ©гғігғүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢEUжі•е„ӘдҪҚгҒ®еҺҹеүҮгҒЁгҒқгҒ®е®ҹеӢҷзҡ„еҪұйҹҝ
EUжі•гҒЁеӣҪеҶ…жі•дҪ“зі»гҒ®й–ўдҝӮ
еүҚиҝ°гҒ®жі•жәҗгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ§дәӢжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶдёҠгҒ§жңҖгӮӮе®ҹеӢҷзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒҢгҖҒ欧е·һйҖЈеҗҲпјҲEUпјүжі•гҒ®еӯҳеңЁгҒ§гҒҷгҖӮгғқгғјгғ©гғігғүгҒҜ2004е№ҙгҒ«EUгҒ«еҠ зӣҹгҒ—гҒҰд»ҘжқҘгҖҒEUжі•е…ЁдҪ“пјҲгӮўгӮӯгғ»гӮігғҹгғҘгғҺгғҶгғјгғ«пјүгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮEUжі•гҒ«гҒҜгҖҒеҠ зӣҹеӣҪгҒ§зӣҙжҺҘйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢиҰҸеүҮпјҲRegulationпјүгҖҚгҒЁгҖҒеҗ„еӣҪгҒҢеӣҪеҶ…жі•гӮ’ж•ҙеӮҷгҒ—гҒҰйҒ”жҲҗгҒҷгҒ№гҒҚзӣ®жЁҷгӮ’е®ҡгӮҒгӮӢгҖҢжҢҮд»ӨпјҲDirectiveпјүгҖҚгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®EUжі•гҒҜгҖҒEUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖпјҲCJEUпјүгҒ®еҲӨдҫӢжі•зҗҶгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢEUжі•гҒ®е„ӘдҪҚгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒеҠ зӣҹеӣҪгҒ®еӣҪеҶ…жі•пјҲжҶІжі•гӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒ«е„Әе…ҲгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁи§ЈгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒҜгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®еӣҪеҶ…жі•дҪ“зі»гҒЁзӣёгҒҫгҒЈгҒҰгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№з’°еўғгҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ競дәүжі•гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…дҝқиӯ·гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·пјҲGDPRпјүгҖҒз’°еўғеҹәжә–гҖҒиЈҪе“ҒгҒ®е®үе…ЁжҖ§гҒӘгҒ©гҖҒдәӢжҘӯжҙ»еӢ•гҒ®еӨҡгҒҸгҒ®еҒҙйқўгҒҢEUгғ¬гғҷгғ«гҒ§зөұдёҖгҒ•гӮҢгҒҹгғ«гғјгғ«гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸеҫӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүеӣҪеҶ…гҒ®жі•еҫӢгҒ®гҒҝгӮ’йҒөе®ҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒй–ўйҖЈгҒҷгӮӢEUжі•гҒ«йҒ•еҸҚгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгғӘгӮ№гӮҜгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
EUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгӮӢи–¬еұҖеәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒ®з„ЎеҠ№еҲӨж–ӯ
EUжі•гҒ®е„ӘдҪҚгҒҢгҖҒй•·е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹеӣҪеҶ…жі•гӮ’иҰҶгҒ—гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®еүҚжҸҗжқЎд»¶гӮ’ж №жң¬гҒӢгӮүеӨүгҒҲгҒҶгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷе…·дҪ“зҡ„гҒӘдәӢдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒи–¬еұҖгҒ®еәғе‘ҠиҰҸеҲ¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢEUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғқгғјгғ©гғігғүгҒ§гҒҜгҖҒ2012е№ҙгҒ«ж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҒҹеҢ»и–¬е“Ғжі•пјҲPrawo farmaceutyczneпјү第94aжқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒи–¬еұҖгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®жҙ»еӢ•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеәғе‘ҠгҒҢгҖҒжүҖеңЁең°гӮ„е–¶жҘӯжҷӮй–“гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ”гҒҸдёҖйғЁгҒ®жғ…е ұгӮ’йҷӨгҒҚгҖҒе…Ёйқўзҡ„гҒ«зҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮйҒ•еҸҚгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒжңҖеӨ§50,000гӮәгӮҰгӮ©гғҶгӮЈпјҲзҙ„12,000гғҰгғјгғӯпјүгҒ®зҪ°йҮ‘гҒҢ科гҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иҰҸеҲ¶гҒҜгҖҒеҢ»и–¬е“ҒгҒ®йҒҺеү°ж¶ҲиІ»гӮ’йҳІгҒҺгҖҒи–¬еүӨеё«гҒ®е°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзӢ¬з«ӢжҖ§гӮ’е®ҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе…¬иЎҶиЎӣз”ҹдёҠгҒ®зӣ®зҡ„гӮ’жҺІгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ欧е·һ委員дјҡгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®е…Ёйқўзҡ„гҒӘеәғе‘ҠзҰҒжӯўгҒҢEUжі•гҒ«йҒ•еҸҚгҒҷгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгӮ’зӣёжүӢеҸ–гӮҠEUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ«жҸҗиЁҙгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ欧е·һ委員дјҡгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иҰҸеҲ¶гҒҢгҖҒEUгҒ®еҹәжң¬жқЎзҙ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢEUгҒ®ж©ҹиғҪгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎзҙ„пјҲTFEUпјүгҖҚгҒҢдҝқйҡңгҒҷгӮӢгҖҢиЁӯз«ӢгҒ®иҮӘз”ұгҖҚпјҲ第49жқЎпјүгҒҠгӮҲгҒігҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣгҒ®иҮӘз”ұгҖҚпјҲ第56жқЎпјүгҖҒгҒӘгӮүгҒігҒ«йӣ»еӯҗе•ҶеҸ–еј•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҖҢEгӮігғһгғјгӮ№жҢҮд»ӨгҖҚпјҲ2000/31/ECпјүгҒ«йҒ•еҸҚгҒҷгӮӢгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2025е№ҙ6жңҲ19ж—ҘгҖҒEUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒдәӢ件з•ӘеҸ·C-200/24гҒ® 欧е·һ委員дјҡ еҜҫ гғқгғјгғ©гғігғү еҲӨжұәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒ欧е·һ委員дјҡгҒ®дё»ејөгӮ’е…Ёйқўзҡ„гҒ«иӘҚгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒе…¬иЎҶиЎӣз”ҹгҒ®дҝқиӯ·гҒҜжӯЈеҪ“гҒӘзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®иҰҸеҲ¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҖиҲ¬зҡ„гҒӢгҒӨзө¶еҜҫзҡ„гҒӘеәғе‘ҠзҰҒжӯўгҒҜгҖҒгҒқгҒ®зӣ®зҡ„гӮ’йҒ”жҲҗгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҢдёҚеқҮиЎЎгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғқгғјгғ©гғігғүгҒҜгҖҒгҒӘгҒңгӮҲгӮҠеҲ¶йҷҗзҡ„гҒ§гҒӘгҒ„д»–гҒ®жүӢж®өпјҲдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеәғе‘ҠеҶ…е®№гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҖ«зҗҶиҰҸе®ҡгҒ®е°Һе…ҘгҒӘгҒ©пјүгҒ§гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒӘгҒ®гҒӢгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«иЁјжҳҺгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒ®зөҗжһңгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒҜеӣҪеҶ…жі•гҒ§гҒӮгӮӢеҢ»и–¬е“Ғжі•гҒ®й–ўйҖЈиҰҸе®ҡгӮ’гҖҒEUжі•гҒ«йҒ©еҗҲгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶж”№жӯЈгҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгӮ’иІ гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дәӢдҫӢгҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲеӣҪеҶ…жі•гҒЁгҒ—гҒҰжңүеҠ№гҒ«жҲҗз«ӢгҒ—гҖҒй•·жңҹй–“йҒӢз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹиҰҸеҲ¶гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒEUжі•гҒЁгҒ®жҠөи§ҰгҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгӮҢгҒ°гҖҒEUгҒ®еҸёжі•еҲӨж–ӯгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒқгҒ®еҠ№еҠӣгҒҢиҰҶгҒ•гӮҢгҒҶгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҳҺзўәгҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғқгғјгғ©гғігғүеёӮе ҙгҒ«еҸӮе…ҘгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜгҖҒгғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°жҲҰз•ҘгӮ„гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№дҪ“еҲ¶гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒгғқгғјгғ©гғігғүеӣҪеҶ…жі•гҒЁEUжі•гҒ®дёЎж–№гӮ’дёҖдҪ“зҡ„гҒ«жӨңиЁҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒиҝ‘е№ҙгҖҒгҒ“гҒ®EUжі•е„ӘдҪҚгҒ®еҺҹеүҮгӮ’гӮҒгҒҗгӮҠгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүеӣҪеҶ…гҒ§жі•зҡ„гҒӘз·ҠејөгҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«гӮӮз•ҷж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ2021е№ҙ10жңҲ7ж—ҘгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жҶІжі•жі•е»·гҒҜгҖҒEUжқЎзҙ„гҒ®дёҖйғЁжқЎй …гҒҢгғқгғјгғ©гғігғүжҶІжі•гҒ«йҒ•еҸҚгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲӨж–ӯпјҲдәӢ件з•ӘеҸ· K 3/21пјүгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒEUгҒ®еҸёжі•еҲӨж–ӯгҒЁгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жңҖй«ҳжҶІжі•еҲӨж–ӯгҒЁгҒ®й–“гҒ«ж·ұеҲ»гҒӘеҜҫз«ӢгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжі•зҡ„гҒӘдёҚзўәе®ҹжҖ§гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҒҜгҖҒEUжі•гӮ’йҒөе®ҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҖе„Әе…ҲгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӣҪеҶ…гҒ®жі•ж”ҝжІ»зҡ„гҒӘеӢ•еҗ‘гҒҢгҖҒе°ҶжқҘзҡ„гҒ«иҰҸеҲ¶гҒ®и§ЈйҮҲгӮ„йҒӢз”ЁгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮеҝөй ӯгҒ«зҪ®гҒҸгҒ№гҒҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮВ
ж—Ҙжң¬гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгғқгғјгғ©гғігғүеҸёжі•жЁ©гҒ®дәҢе…ғзҡ„ж§ӢйҖ

гғқгғјгғ©гғігғүгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгҖҒгҒқгҒ®ж§ӢйҖ гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•жЁ©гҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢеҚҳдёҖгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гҒ®дёӢгҒ«гҖҒй«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҖҒең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҖҒ家еәӯиЈҒеҲӨжүҖгҖҒз°Ўжҳ“иЈҒеҲӨжүҖгҒҢдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зөұдёҖгҒ•гӮҢгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дёӯгҒ§гҖҒжҶІжі•йҒ©еҗҲжҖ§гҒ®еҲӨж–ӯгӮ’еҗ«гӮҖгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҸёжі•еҲӨж–ӯгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғқгғјгғ©гғігғүе…ұе’ҢеӣҪжҶІжі•з¬¬173жқЎгҒҜгҖҒгҖҢиЈҒеҲӨжүҖеҸҠгҒіжі•е»·гҒҜгҖҒеҲҶйӣўгҒ—гҒҹжЁ©еҠӣгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»–гҒ®жЁ©еҠӣйғЁй–ҖгҒӢгӮүзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҖҒеҸёжі•жЁ©гӮ’гҖҢиЈҒеҲӨжүҖпјҲsД…dyпјүгҖҚгҒЁгҖҢжі•е»·пјҲtrybunaЕӮyпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдәҢгҒӨгҒ®зі»зөұгҒ«жҳҺзўәгҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®дәҢе…ғзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зі»зөұгҒҢз•°гҒӘгӮӢзЁ®йЎһгҒ®жЁ©йҷҗгҒЁеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
| гғқгғјгғ©гғігғү | ж—Ҙжң¬ | |
|---|---|---|
| еҹәжң¬ж§ӢйҖ | дәҢе…ғзҡ„ж§ӢйҖ пјҡгҖҢиЈҒеҲӨжүҖ (sД…dy)гҖҚгҒЁгҖҢжі•е»· (trybunaЕӮy)гҖҚгҒ«еҲҶйӣў | еҚҳдёҖгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ |
| жңҖй«ҳеҸёжі•ж©ҹй–ў | жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖ (SД…d NajwyЕјszy) [дёҖиҲ¬гғ»и»ҚдәӢдәӢ件] еҸҠгҒіжңҖй«ҳиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖ (Naczelny SД…d Administracyjny) [иЎҢж”ҝдәӢ件] | жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖ [е…ЁгҒҰгҒ®дәӢ件гӮ’з®ЎиҪ„] |
| йҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ© | жҶІжі•жі•е»· (TrybunaЕӮ Konstytucyjny) гҒҢе°Ӯй–Җзҡ„гҒӢгҒӨжҺ’д»–зҡ„гҒ«з®ЎиҪ„ | жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢе…ЁгҒҰгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҢд»ҳйҡҸзҡ„гҒ«иЎҢдҪҝ |
| йҒ•жҶІеҲӨж–ӯгҒ®еҠ№еҠӣ | жі•еҫӢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’з„ЎеҠ№гҒЁгҒҷгӮӢжҷ®йҒҚзҡ„еҠ№еҠӣ (erga omnes) | еҪ“и©ІдәӢ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒ©з”ЁгӮ’жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢеҖӢеҲҘзҡ„еҠ№еҠӣ |
гҒ“гҒ®дәҢе…ғж§ӢйҖ гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒж¬ЎгҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зі»зөұгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢиЈҒеҲӨжүҖгҖҚгҒЁгҖҢжі•е»·гҖҚгҒ®еҪ№еүІгҒЁжЁ©йҷҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸиҰӢгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘдәӢ件гӮ’з®ЎиҪ„гҒҷгӮӢгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®гҖҢиЈҒеҲӨжүҖ (sД…dy)гҖҚ
гҖҢиЈҒеҲӨжүҖпјҲsД…dyпјүгҖҚгҒ®зі»зөұгҒҜгҖҒдјҒжҘӯжҙ»еӢ•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзҷәз”ҹгҒҷгӮӢж°‘дәӢгғ»е•ҶдәӢзҙӣдәүгӮ„иЎҢж”ҝгҒЁгҒ®дәүиЁҹгҒӘгҒ©гҖҒж—Ҙеёёзҡ„гҒӘжі•зҡ„е•ҸйЎҢгҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒҶеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зі»зөұгҒҜгҖҒдё»гҒ«жҷ®йҖҡиЈҒеҲӨжүҖгҖҒиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгӮҢгӮүгҒ®й ӮзӮ№гҒ«з«ӢгҒӨжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҷ®йҖҡиЈҒеҲӨжүҖ (sД…dy powszechne) гҒҜгҖҒж°‘дәӢгҖҒеҲ‘дәӢгҖҒеҠҙеғҚгҖҒ家ж—ҸдәӢ件гҒӘгҒ©гӮ’з®ЎиҪ„гҒҷгӮӢгҖҒеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®дёӯж ёгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨжүҖеҲ¶еәҰгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒеҜ©зҙҡеҲ¶еәҰгҒҢжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҖҡеёёгҒҜдёүеұӨж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- ең°еҢәиЈҒеҲӨжүҖ (sД…dy rejonowe)пјҡ第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжңҖгӮӮеӨҡгҒҸгҒ®дәӢ件гӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгӮ„з°Ўжҳ“иЈҒеҲӨжүҖгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖ (sД…dy okrДҷgowe)пјҡгӮҲгӮҠйҮҚеӨ§гҒӘдәӢ件гҒ®з¬¬дёҖеҜ©гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜең°еҢәиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҺ§иЁҙеҜ©гӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖпјҲ第дёҖеҜ©пјүгӮ„й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖпјҲжҺ§иЁҙеҜ©пјүгҒ®ж©ҹиғҪгҒ«иҝ‘гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
- жҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖ (sД…dy apelacyjne)пјҡең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒҢ第дёҖеҜ©гҒЁгҒ—гҒҰдёӢгҒ—гҒҹеҲӨжұәгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҺ§иЁҙеҜ©гӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒ«зӣёеҪ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢе•ҶдәӢдәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҜеӯҳеңЁгҒӣгҒҡгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҷ®йҖҡиЈҒеҲӨжүҖеҶ…гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹе•ҶдәӢйғЁгҒ§еҜ©зҗҶгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
иЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖ (sД…dy administracyjne) гҒҜгҖҒиЎҢж”ҝж©ҹй–ўгҒ®жұәе®ҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдёҚжңҚз”ігҒ—з«ӢгҒҰгҒӘгҒ©гҖҒе…¬жі•дёҠгҒ®зҙӣдәүгӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«жүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒзЁҺеӢҷеҪ“еұҖгҒӢгӮүгҒ®иӘІзЁҺеҮҰеҲҶгӮ„гҖҒиҰҸеҲ¶еҪ“еұҖгҒ«гӮҲгӮӢиЁұиӘҚеҸҜгҒ®жӢ’еҗҰгҒӘгҒ©гҖҒиЎҢж”ҝгҒ®иЎҢзӮәгҒ®йҒ©жі•жҖ§гӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зі»зөұгӮӮдәҢеҜ©еҲ¶гҒ§гҖҒ第дёҖеҜ©гҒ®зңҢиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҖҒгҒқгҒ®дёҠзҙҡеҜ©гҒ§гҒӮгӮӢжңҖй«ҳиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖ (Naczelny SД…d Administracyjny) гҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖ (SД…d NajwyЕјszy) гҒҜгҖҒжҷ®йҖҡиЈҒеҲӨжүҖгҒҠгӮҲгҒіи»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖпјҲи»ҚдәәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲ‘дәӢдәӢ件зӯүгӮ’з®ЎиҪ„пјүгҒ®жңҖдёҠзҙҡеҜ©гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®дё»гҒӘеҪ№еүІгҒҜгҖҒдёӢзҙҡеҜ©гҒ®еҲӨжұәгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҖзөӮзҡ„гҒӘеҲӨж–ӯпјҲз ҙжҜҖз”із«ӢгҒҰпјүгӮ’дёӢгҒҷгҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҲӨдҫӢгҒ®зөұдёҖжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжі•еҫӢгҒ®и§ЈйҮҲгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҢҮйҮқгӮ’зӨәгҒҷжұәиӯ°гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮжҶІжі•з¬¬183жқЎгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжҷ®йҖҡиЈҒеҲӨжүҖеҸҠгҒіи»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгӮ’зӣЈзқЈгҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨгҒЁе®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҸёжі•еҲӨж–ӯгҒ®дёҖиІ«жҖ§гӮ’дҝқгҒӨдёҠгҒ§дёӯеҝғзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№ж®ҠгҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®гҖҢжі•е»· (trybunaЕӮy)гҖҚ
гғқгғјгғ©гғігғүеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®дәҢе…ғж§ӢйҖ гӮ’зү№еҫҙгҒҘгҒ‘гӮӢгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®зі»зөұгҒҢгҖҒгҖҢжі•е»·пјҲtrybunaЕӮyпјүгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®й«ҳеәҰгҒӘж”ҝжІ»зҡ„гғ»жҶІжі•дёҠгҒ®е•ҸйЎҢгӮ’е°Ӯй–Җзҡ„гҒ«жүұгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹзү№еҲҘгҒӘеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҶІжі•жі•е»·гҒЁеӣҪ家法廷гҒ®дәҢгҒӨгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҶІжі•йҒ©еҗҲжҖ§гӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢжҶІжі•жі•е»·
жҶІжі•жі•е»· (TrybunaЕӮ Konstytucyjny) гҒҜгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжҘөгӮҒгҒҰгғҰгғӢгғјгӮҜгҒӢгҒӨеј·еҠӣгҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨж©ҹй–ўгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯж ёзҡ„гҒӘд»»еӢҷгҒҜгҖҒжҶІжі•з¬¬188жқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒеҲ¶е®ҡжі•гӮ„еӣҪйҡӣеҚ”е®ҡгҒҢжҶІжі•гҒ«йҒ©еҗҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®зӮ№гҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒҜжұәе®ҡзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒйҒ•жҶІеҜ©жҹ»жЁ©гҒҜзү№е®ҡгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘиЁҙиЁҹдәӢ件пјҲдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒжҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮиЁҙиЁҹгҒӘгҒ©пјүгҒ«д»ҳйҡҸгҒ—гҒҰгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢе…ЁгҒҰгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҢжі•еҫӢгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’еҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҲӨж–ӯгҒ®еҠ№еҠӣгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҒқгҒ®дәӢ件йҷҗгӮҠгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжі•еҫӢиҮӘдҪ“гӮ’зӣҙгҒЎгҒ«з„ЎеҠ№гҒ«гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дёҖж–№гҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жҶІжі•жі•е»·гҒҜгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘдәӢ件гҒӢгӮүйӣўгӮҢгҒҰгҖҒжі•еҫӢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’жҠҪиұЎзҡ„гҒ«еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮеӨ§зөұй ҳгӮ„дёҖе®ҡж•°гҒ®еӣҪдјҡиӯ°е“ЎгҒӘгҒ©гҒҢз”ігҒ—з«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжі•еҫӢгҒ®жңүеҠ№жҖ§гӮ’зӣҙжҺҘе•ҸгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒжҶІжі•жі•е»·гҒҢжі•еҫӢгӮ’йҒ•жҶІгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®еҲӨжұәгҒҜжңҖзөӮзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҷ®йҒҚзҡ„гҒӘжӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷпјҲerga omnesпјүгҖӮжҶІжі•з¬¬190жқЎз¬¬1й …гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®еҲӨжұәгҒҜе®ҳе ұгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹж—ҘгҒӢгӮүеҠ№еҠӣгӮ’з”ҹгҒҳгҖҒйҒ•жҶІгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹжі•еҫӢгҒ®жқЎй …гҒҜжі•дҪ“зі»гҒӢгӮүжҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒ2015е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒжҶІжі•жі•е»·гҒ®иЈҒеҲӨе®ҳгҒ®д»»е‘Ҫгғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гӮҒгҒҗгӮӢж”ҝжІ»зҡ„гҒӘеҜҫз«ӢгҒҢе…ҲйӢӯеҢ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®зӢ¬з«ӢжҖ§гӮ„жӯЈзөұжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӣҪеҶ…еӨ–гҒӢгӮүеӨҡгҒҸгҒ®жҮёеҝөгҒҢиЎЁжҳҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҠ¶жіҒгҒҜгҖҒжҶІжі•жі•е»·гҒ®еҲӨж–ӯгҒ®дәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гӮ’дҪҺдёӢгҒ•гҒӣгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•з§©еәҸе…ЁдҪ“гҒ«дёҚзўәе®ҹжҖ§гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҒҙйқўгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж”ҝжІ»зҡ„гғ»жі•зҡ„гҒӘиғҢжҷҜгӮӮзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮВ
ејҫеҠҫиЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’жҢҒгҒӨеӣҪ家法廷
гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®жі•е»·гҒ§гҒӮгӮӢеӣҪ家法廷 (TrybunaЕӮ Stanu) гҒҜгҖҒеӨ§зөұй ҳгӮ„й–ЈеғҡгҒӘгҒ©гҖҒеӣҪ家гҒ®жңҖй«ҳе№№йғЁгҒҢиҒ·еӢҷгҒ«й–ўйҖЈгҒ—гҒҰзҠҜгҒ—гҒҹжҶІжі•йҒ•еҸҚгӮ„жі•еҫӢйҒ•еҸҚгӮ’иЈҒгҒҸгҖҒгҒ„гӮҸгҒ°ејҫеҠҫиЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«й–Ӣе»·гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзЁҖгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҖҡеёёгҒ®дјҒжҘӯжҙ»еӢ•гҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷгҒ“гҒЁгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮВ
гҒҫгҒЁгӮҒ
жң¬зЁҝгҒ§гҒҜгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢдәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢзӣёйҒ•зӮ№гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгғқгғјгғ©гғігғүгҒҜж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢгҒҳеӨ§йҷёжі•зі»гҒ®еӣҪгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҜзңӢйҒҺгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зӢ¬иҮӘгҒ®зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
第дёҖгҒ«гҖҒжі•жәҗгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гҖҒгҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘EUжі•гҒ®е„ӘдҪҚгҒ®еҺҹеүҮгҒ§гҒҷгҖӮгғқгғјгғ©гғігғүжҶІжі•гҒҜгҖҒжү№еҮҶгҒ•гӮҢгҒҹеӣҪйҡӣеҚ”е®ҡгҒҢеӣҪеҶ…гҒ®еҲ¶е®ҡжі•гҒ«е„Әи¶ҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҳҺиЁҳгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠEUжі•гҒҢеӣҪеҶ…гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№иҰҸеҲ¶гҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒӢгҒӨеј·еҠӣгҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮEUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҢгғқгғјгғ©гғігғүгҒ®и–¬еұҖеәғе‘ҠгҒ®е…ЁйқўзҰҒжӯўгӮ’з„ЎеҠ№гҒЁгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒҢеҚҳгҒӘгӮӢзҗҶи«–гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдәӢжҘӯжҲҰз•ҘгҒ®еүҚжҸҗгӮ’иҰҶгҒ—гҒҶгӮӢзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғқгғјгғ©гғігғүгҒ§гғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’иЎҢгҒҶдёҠгҒ§гҒҜгҖҒеӣҪеҶ…жі•иҰҸгҒ®йҒөе®ҲгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒй–ўйҖЈгҒҷгӮӢEUгҒ®иҰҸеүҮгӮ„жҢҮд»ӨгҖҒгҒқгҒ—гҒҰEUеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢеӢ•еҗ‘гӮ’еёёгҒ«жіЁиҰ–гҒҷгӮӢиӨҮзңјзҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
第дәҢгҒ«гҖҒеҸёжі•жЁ©гҒ®дәҢе…ғзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҚҳдёҖзҡ„гҒӘеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒгғқгғјгғ©гғігғүгҒ§гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®ж°‘дәӢгғ»иЎҢж”ҝдәӢ件гӮ’жүұгҒҶгҖҢиЈҒеҲӨжүҖгҖҚгҒ®зі»зөұгҒЁгҖҒжі•еҫӢгҒ®жҶІжі•йҒ©еҗҲжҖ§гӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢгҖҢжі•е»·гҖҚгҒ®зі»зөұгҒҢдёҰз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒжі•еҫӢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’з„ЎеҠ№гҒ«гҒҷгӮӢеј·еҠӣгҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨжҶІжі•жі•е»·гҒ®еӯҳеңЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ«гҒҜгҒӘгҒ„зү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж©ҹй–ўгҒ®дёҖгҒӨгҒ®еҲӨж–ӯгҒҢгҖҒжҘӯз•Ңе…ЁдҪ“гҒ®жі•зҡ„жһ зө„гҒҝгӮ’дёҖеӨңгҒ«гҒ—гҒҰеӨүжӣҙгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’з§ҳгӮҒгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғқгғјгғ©гғігғүзү№жңүгҒ®дәӢжҘӯгғӘгӮ№гӮҜгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғқгғјгғ©гғігғүгҒ®жі•зҡ„з’°еўғгҒҜгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘжһ зө„гҒҝгҒЁеҜҶжҺҘгҒ«йҖЈжҗәгҒ—гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒеӣҪеҶ…гҒ§гҒҜзӢ¬иҮӘгҒ®жҶІжі•еҲӨж–ӯгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гӮ’жҢҒгҒӨгҖҒиӨҮйӣ‘гҒ§гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ