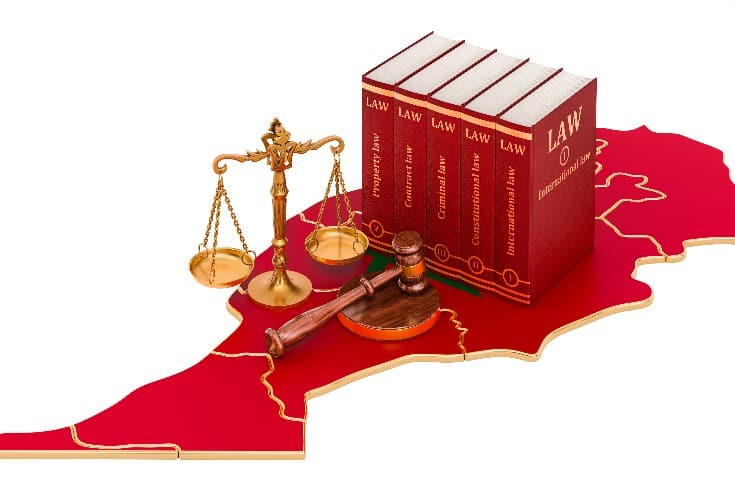台湾の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

台湾は、半導体産業を筆頭とするハイテク製造業が経済成長を牽引し、世界経済において重要な地位を占める先進的な市場です。国際通貨基金(IMF)の予測によれば、2024年には一人当たり名目GDPが日本を上回るとされており。過去10年間で名目GDPは約1.5倍に拡大し、特に2017年以降はスマートフォンやデータセンター、5G、IoT、AIといった新技術の進展に伴う半導体需要の急増が経済を加速させてきました。2023年には世界第16位の輸出国、第21位の輸入国となるなど、その貿易規模も注目に値します。
台湾の法制度は、その歴史的背景から日本と深い親和性を有しています。台湾の法制度は大陸法系に属し、特に近代日本の法制度とドイツ法の影響を強く受けて形成されました。中華民国政府が中国大陸で近代法典を編纂する際、ドイツをはじめとする西欧の近代法をモデルとし、日本の学者や実務家も招聘して各法典の起草作業を開始した経緯があります。第二次世界大戦後、中華民国政府が台湾を統治する際にこれらの法典が適用されたため、憲法を除けば、台湾の法制度全体が日本法と極めて類似していると評価されています。
本記事では、台湾の法律の全体像とその概要について詳しく解説します。
この記事の目次
台湾の法体系と司法制度の基礎
大陸法系の採用と日本法からの影響
台湾の法制度は、ドイツ法と近代日本法に起源を持つ大陸法系(Civil Law System)を基盤としています。これは、成文法を重視し、法典によって体系的に規定される特徴を持ちます。歴史的に、清朝末期の法制改革においてドイツ法や日本法が参考にされ、その成果が中華民国政府の基本法典制定に引き継がれた経緯があります。このため、台湾の法律用語にも日本と共通する点が多く見られます。
五権分立の憲法体制と日本の三権分立との比較
台湾の憲法(中華民国憲法、1947年公布)は、世界の多くの国が採用する三権分立(行政、立法、司法)とは異なり、孫文の「五権分立」思想に基づく「五院」(行政院、立法院、司法院、考試院、監察院)を採用しています。
- 行政院 (Executive Yuan): 日本の内閣に相当し、行政院長(首相に相当)が率いる最高行政機関です。
- 立法院 (Legislative Yuan): 最高の立法機関であり、法律案の議決、予算案の審議などを行う一院制の議会です。立法委員は直接選挙で選出され、任期は4年です。
- 司法院 (Judicial Yuan): 最高の司法機関であり、民事、刑事、行政訴訟の審判および公務員の懲戒を掌ります。特に、憲法解釈および法律・命令の統一解釈権を持つ大法官(Grand Justices)が設置されている点が日本の司法制度と異なります。
- 考試院 (Examination Yuan): 公務員の採用試験や人事管理を司る機関で、日本の人事院に相当します。
- 監察院 (Control Yuan): 公務員の監察、弾劾、国家政策の調査などを行う機関で、スウェーデンのオンブズマン制度に類似しています。
日本の三権分立に慣れた日本人にとって、台湾の「五権分立」は、政府機関の役割分担と権限範囲を理解する上で重要な違いとなります。また、日本の最高裁判所が違憲審査権を持つものの、具体的な事件の判決を通じて行うのと異なり、台湾では司法院の大法官が憲法解釈や法律・命令の統一解釈を専属的に行うことで、より集中的な憲法判断の機能を持っていると言えます。
裁判所の種類と構造
台湾の司法審理は、案件の性質により、普通裁判所、専門裁判所、行政裁判所、軍事裁判所に区分されます。
- 普通裁判所 (Common Courts): 民事および刑事事件を管轄し、原則として三級三審制(地方法院、高等法院、最高法院)を採用します。ただし、一部の小額案件や簡易な案件では二級二審制が採用されます。
- 行政裁判所 (Administrative Courts): 行政事件を管轄し、第一審の高等行政法院と終審の最高行政法院の二級二審制を採用します。
- 専門裁判所 (Specialized Courts): 特定の訴訟案件の性質に応じて設置されます。例として、知的財産案件を集中して管轄する智慧財産及商業法院(知的財産及び商業裁判所)があります。
- 軍事裁判所 (Military Courts): 現役軍人の特定の犯罪を管轄します(原則として、平時の軍事犯罪は普通裁判所において管轄)。
台湾の裁判所制度は、三審制を基本とする点で日本と類似していますが、普通裁判所と行政裁判所が明確に分離され、それぞれに最高裁判所が存在する「二元的な最高裁判所」構造を持つ点が特徴的です。
台湾の民法(契約法・不動産法)

契約法の基本原則と日本法との共通点
台湾の民法は1929年に制定され、主に1900年に施行されたドイツ民法を継受しており、日本の民法と全体的な構成や仕組みが類似しています。総則、債権、物権、親属、継承の5編から構成され、全1225条に及びます。契約の基本原則として、意思表示の解釈においては文言の字義通りの意味に拘泥せず、当事者の真意を追求する旨の規定があります。債務不履行に対する損害賠償請求権の原則や、信義則に基づく付随義務(通知、警告、協力、秘密保持、保護など)の考え方も、通説・実務上ドイツ法および日本法と同様に採用されています。
不動産物権の「登記発効主義」と日本法の「登記対抗主義」の相違点
台湾民法は、不動産物権の取得、設定、喪失、変更について、ドイツ法に倣い「登記発効主義」を採用しています。これは、登記を経なければその物権変動の効力が発生しないことを意味し、登記は単なる第三者対抗要件に留まらず、絶対的な効力を有します。これに対し、日本の民法は「登記対抗主義」を採用しており、登記がなくても物権変動の効力は発生するものの、第三者に対抗するためには登記が必要となります。
この「登記発効主義」は、日本企業が台湾で不動産取引を行う上で、最も重要な法的相違点の一つです。日本では登記がなくても売買契約自体は有効ですが、台湾では登記が完了するまで所有権移転の法的効力が発生しないため、登記手続きの完了が取引の成否に直結します。特に、売主が代金受領前に登記名義変更が行われ、買主が代金を支払わないリスクがあるという指摘もあります。台湾で不動産を購入する際には、代金決済と登記手続きの同時進行または厳格な連動を確保するための、より慎重なエスクロー(第三者預託)や決済スキームの導入が必要となるでしょう。
「家」制度の概要と日本旧民法との比較
台湾の民法には「家」に関する独立した章が設けられており、「家」は永続的な同居を目的とする親族の集団と定義され、家長が家事を管理します。この制度は、日本の旧民法における「戸主」制度と類似する点がありますが、台湾の家長の権限は日本の旧戸主と比較して大幅に制限されています。特定の事項(扶養料の決定、遺言執行者の報酬、口頭遺言の確認など)については、「親族会議」の開催が頻繁に義務付けられており、会議が成立しない場合や決議できない場合は、利害関係者が裁判所に申し立てて決定を求めることができます。
同性婚の合法化とその影響
2017年、台湾の司法院大法官は、民法が同性婚を認めないことが憲法の婚姻の自由と平等原則に違反すると判断しました。これを受け、2019年に「司法院釈字第748号解釈施行法」が公布され、同性間の永続的な結合が明文で合法化されました。これにより、台湾はアジアで初めて同性婚を法的に認めた国となりました。
台湾の会社法
台湾の会社法(公司法)は1929年に制定されましたが、その後頻繁に改正されており、直近では2018年8月1日に大きく改正されました。
会社の種類と外国企業の選択肢
会社は以下の表に示す4種類に分類されます。実務上、無限公司と両合公司はほとんど見られません。外国企業が現地法人を設立する際には、通常、股份有限公司(日本の株式会社に相当)の形態を選択します。有限公司も中小企業で一般的ですが、外国企業の子会社設立では股份有限公司が主流です。
| 無限公司 | 有限公司 | 両合公司 | 股份有限公司 | |
| 株主の最低人数 | 2人以上 | 1人以上 | 無限責任株主1人以上、有限責任株主1人以上 | 2人以上、または政府・法人株主1人 |
| 株主の責任範囲 | 連帯無限責任 | 出資額を限度とする有限責任 | 無限責任株主:連帯無限責任、有限責任株主:出資額を限度とする有限責任 | 引受株式の総額を限度とする有限責任 |
| 外国資本による利用 | 稀 | 中小企業で一般的 | 稀 | 主流 |
| 機関設計の柔軟性(単一法人株主の場合) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 取締役1-2名、取締役会・監査役不要 |
股份有限公司は、日本の「株式会社」に最も近い形態であり、統治構造や責任範囲が馴染みやすいと思われます。
単一株主会社の設立と機関設計の柔軟性
2018年改正会社法により、公開会社でない股份有限公司(非公開会社)は、単一の法人株主によって組織される場合、取締役を1名または2名とすることができ、取締役会および監査役の設置が不要となりました。これは、日本の単一株主会社(株式会社)では取締役会や監査役の設置が原則として必要であるのと異なる、柔軟な機関設計を可能にします。また、非公開会社では、定款に定めることにより株主総会をオンラインで開催することや、取締役会の決議を書面で行うことも可能となりました。
コーポレートガバナンスの規制
台湾のコーポレートガバナンスに関する規制は、会社法、証券取引法(SEA)、金融監督管理委員会(FSC)の関連規制、台湾証券取引所(TWSE)およびタイペイ・エクスチェンジ(TPEx)の規則(上場企業の企業統治ベストプラクティス原則など)で構成されます。会社法の下では、株式会社は取締役会、株主、監査役によって運営されます。取締役は会社に対して受託者責任(忠実義務、善管注意義務)を負い、会社の最善の利益のために行動する必要があり、利益相反が生じる場合、取締役は事実を開示し、投票を棄権しなければなりません。
上場企業に対しては、証券取引法により、独立取締役の導入(取締役会の5分の1以上、最低2名)、監査委員会および報酬委員会の設置義務、公認会計士による監査・認証要件、重要情報の開示義務、重要な資産の取得・処分手続き、内部統制の仕組みなどが厳格に規定されています。2023年6月30日以降、台湾のすべての上場企業は、ガバナンス関連法規およびベストプラクティスへの遵守を確保し、取締役の職務遂行を支援する最高ガバナンス責任者(CGO)を任命することが義務付けられています。さらに、2025年からは、すべての台湾上場企業(資本規模問わず)に対し、業界固有のESGリスク、パフォーマンス指標、気候関連開示を含む年次サステナビリティレポートを8月31日までに発行することが義務付けられます。
株主情報開示義務の強化
非公開会社は、財務諸表の公開が義務付けられていませんが、登録住所、事業範囲、会社状況、取締役リスト、資本金額などの基本的な企業情報は商業登記ウェブサイトを通じて公開されています。重要な変更(取締役の任命、資本変更、定款変更など)は15日以内に商業登記機関に報告する必要があります。
上場会社については、証券取引法により、公開会社の株式の5%以上を取得した株主は、FSCに報告し、公開発表を行う必要があります(2024年5月に従来の10%から引き下げられました)。また、総発行株式の1%に相当する保有株式が増減し、その結果保有比率が1%以上変動した場合も、FSCへの報告が必要となります。
台湾における海外資本からの投資規制

外国人投資許可(FIA)の原則とネガティブリスト
外国企業が台湾に現地法人を新設したり、既存の会社に投資(例:第三者割当増資の引受け)したりする際には、原則として経済部投資審議司(Investment Commission of the Ministry of Economic Affairs, 投審会)による外国人投資許可(FIA)を事前に取得する必要があります。ただし、公開市場を通じて台湾の上場会社に投資する場合(株式購入など)はFIAは不要で、代わりに「華僑及び外国人証券投資管理規則」に従い、証券取引所への登録や証券口座開設などが必要となります。
中国企業からの投資に対する特別な規制
中国企業による台湾への投資は、「大陸地区人民来台投資許可弁法」に基づき特別な許可が必要であり、投資可能な業種は「大陸地区人民来台投資業別項目」に属するもののみに限定されるポジティブリスト形式が採用されています。2012年までは段階的に規制緩和が進められましたが、2020年12月には、迂回投資を防ぐため、中国企業の定義、特に「第三地に投資する会社」の定義における資本額の割合の計算方法が改正され、階層ごとに算出する方式に変更されました。また、「実質的な支配力」の判断基準も拡大されました。
出資比率や土地所有に関する規制
会社法および外国人投資条例による出資比率や出資額に関する制限はなく、100%外国資本の設立も可能であるとされています。ただし、ラジオ・テレビ経営業や第一種電気通信業など、一部の業種には出資比率の制限があります。
土地所有については、外国人が自己使用、投資、または公益の目的で使用する場合に取得可能であり、その面積や場所は各自治体の法規に従う必要があります。ただし、台湾人が域外で同様の権利を享受できる場合に限り、当該外国の者も台湾で土地に関する権利を取得できるという「相互主義」の原則が適用されます。
台湾の海事法
台湾の海事法制は、大陸法系の伝統に基づきつつ、国際条約を国内法に取り入れた法体系となっており、海商法、船員法、海洋環境保護関連法制を主要な柱としています。経済が輸出依存型である台湾にとって、海上輸送は極めて重要なため、海事法制の健全な機能が重視されています。
海商法は、海上物品運送、共同海損、船舶衝突、船舶担保権などを規定しています。
- 海上物品運送契約: 運送人には、出航前および出航時に船舶が安全に航行する能力を持つこと(適航性)や、貨物倉が運送に適した状態であること(適載性)に注意し、必要な措置を講じる義務が課せられています。貨物の滅失、損傷、または遅延による損害賠償責任は、1梱包あたり666.67SDRまたは1kgあたり2SDRのいずれか高い金額が上限と定められており、これは国際的なハーグ・ヴィスビー規則に準拠しています。損害賠償請求権の時効は1年です。
- 共同海損: 航海中に共同の危険から財産を守るために行われた、意図的かつ合理的な処置によって生じた特別な犠牲や費用を、関係者がその利益の割合に応じて分担する制度です。
- 船舶衝突: 衝突後の船舶には、自船の安全が損なわれない範囲で相手船舶の救助に努め、現場に留まり情報を通知する義務があります。過失の軽重に応じて損害賠償責任が決定され、判定できない場合は等しく負担します。被害者は、加害船舶が台湾領海に入った際に抑留を申し立てることができます。
- 船舶担保権: 船舶抵当権と船舶先取特権があり、海難救助料や船員の給料などの債権を保護する目的で、船舶先取特権が船舶抵当権に優先すると定められています。
船員法は、船員の権益保護に特化した特別法であり、労働条件の最低基準を定めています。週の総労働時間が44時間を超えた場合は時間外労働とみなされ、残業代が支払われます。また、産休中や職務中の負傷による治療期間中の解雇は原則として禁止されており、雇用主には契約終了時に船員を雇用地へ護送する義務が課せられています。
海洋環境保護法制は、海洋汚染の防止と管理を目的とする「海洋汚染防止法」が中核です。総トン数150トン以上のタンカーや400トン以上のその他船舶の船主は、海洋汚染による賠償責任を担保するための強制保険の付保や保証の手配が義務付けられており、被害者は保険者や保証人に直接損害賠償を請求する権利を有します。
紛争解決に関しては、台湾の高雄地方裁判所に海事事件を専門に扱う部署が設置されており、専門性の高い紛争に迅速に対応できる体制が整っています。また、台湾はニューヨーク条約の締約国ではありませんが、仲裁法は同条約と同様の規定を持ち、外国の仲裁判断の承認・執行を可能にしています。日本と台湾の間に正式な外交関係がないため、訴訟書類の送達が困難な場合に仲裁は現実的な選択肢となり得ます。
台湾における広告規制
公平交易法による不当表示・不公正競争の禁止
台湾の公平交易法(Fair Trade Law, FTL)は、取引秩序と消費者利益の維持、自由かつ公正な競争の確保を目的とし、1992年に制定されました。FTLは、不当な再販売価格の制限、公正な競争を妨げる行為(特定の事業への供給・購入の断絶、不当な差別待遇、不当な低価格誘導、脅迫・利益誘導による価格競争の阻害など)、および事業の営業信用を損なう不実の陳述・散布などを禁止しています。この法律が、日本の景品表示法(不当表示)と独占禁止法(不公正な取引方法)の双方にまたがる広範な規制権限を持ちます。
虚偽・誤解を招く広告に対する規制と連帯責任
公平交易法第21条は、商品や広告における虚偽または誤解を招く表示・表象を禁止しており、価格、数量、品質、製造方法、用途、原産地など、取引決定に影響を与える事項に関する表示が対象となります。虚偽表示のある商品の販売、運送、輸出入も禁止されます。
特に重要なのは、広告代理業者、広告媒体業者、広告推薦者(インフルエンサーなど)は、知り得た状況下で誤解を招く広告を製作・設計・伝播・掲載した場合、広告主と連帯して損害賠償責任を負う点です。推薦者が著名な公衆人物、専門家、機関でない場合、連帯責任は受領報酬の10倍の範囲に限定されます。
台湾の広告規制は、虚偽・誤解を招く広告について、広告主だけでなく、広告代理店、媒体、さらにはインフルエンサーにまで連帯責任を課している点で、日本よりも広範かつ厳格な責任体系を持つと言えます。特にインフルエンサーマーケティングが盛んな現代において、日本企業が台湾でプロモーションを行う際には、単に広告内容の真実性だけでなく、広告に関わる全ての関係者(特にインフルエンサー)が適切なデューデリジェンスを行い、規制を遵守しているかを徹底的に確認する必要があるでしょう。これは、ブランドイメージの毀損や法的責任を回避するための重要なリスク管理事項となります。
台湾の個人情報保護法
個人情報保護法(PDPA)の基本原則と同意要件
台湾の個人情報保護法(Personal Data Protection Act, PDPA)は、個人データの保護を規定する主要な法律であり、その施行細則が詳細なガイドラインを提供します。
「個人データ」とは、自然人を直接的または間接的に識別するために使用される情報を指します。PDPAによると、個人データの収集、処理、使用にはデータ主体の同意が必要であり、収集、処理、使用は開示された特定の目的の必要な範囲内で行い、収集時にデータ主体に通知する必要があります。機密性の高い個人データの収集および処理は、特定の条件が満たされている場合を除き禁止されます。
台湾のPDPAは、個人データの定義、同意要件、目的制限、機微な個人データの取り扱いなどにおいて、EUのGDPR(一般データ保護規則)に類似した原則を採用しています。
個人情報保護委員会(PDPC)の設立と監督強化
2023年5月のPDPA改正により、個人情報保護委員会(Personal Information Protection Committee, PDPC)が主管機関として指定されました。これは、台湾憲法裁判所の判決(国家健康保険研究データベース事件)を受けて、独立したデータ保護メカニズムを確立し、個人情報とプライバシーの憲法上の権利を保護するためのものです。
PDPCは、データ侵害事件の報告を一元的に受け付け、迅速な調査と対応を促進します。また、個人データセキュリティ維持に関する規則を策定し、監査、検査、行政制裁の法的根拠を提供する役割を担います。公共部門では、データ保護責任者(DPO)の任命が義務付けられます。個人情報保護委員が発足し次第、民間部門への監督権限の移管が行われます。
越境データ移転の制限と実務上の留意点
PDPA第21条は、非政府組織が台湾外に個人データを移転することを、特定の状況下で禁止しています。これには、重要な国益に関わる場合、国際条約・協定で規定されている場合、受領国に適切な保護規制がないためにデータ主体の権利・利益を侵害する恐れがある場合、PDPAの適用を回避するために間接的な方法で移転される場合が含まれます。実務上、非政府組織は、個人データの国際移転を行う前に、それぞれの監督機関(各事業業種の主管当局)に合法性を確認することが推奨されます。
台湾の労働法

労働基準法の基本原則と近年の改正動向
台湾の労働法は、労働者保護に重点を置いた厳格な規制を有します。労働基準法は、労働条件の最低基準を定める基本法であり、これに違反する労働条件は無効となります。医師や外国人介護労働者などの一部例外を除き、国籍を問わずすべての労働者に適用されます。
労働基準法は、2017年と2018年に大きな改正が行われました。特に「一例一休」(週休二日制)の導入と調整、残業代の計算方法の変更、有給休暇の支給日数増加と買い取り義務化、残業時間の上限引き上げ、夜勤者の連続休息時間規定の緩和などが実施されました。
就業規則の作成義務と内容
台湾の労働基準法第70条および施行規則第37、38条によると、30人以上の労働者を雇用する会社は就業規則を作成し、30日以内に主務官庁に届け出なければなりません。また、それを事業場所内に公告し、印刷して各労働者に配布する必要があります。就業規則を修正したときも、同じく30日以内に主務官庁に届け出なければならず、主務官庁の承認を得ていない就業規則の修正は、その効力を有しません。この規定に違反した場合、2万~30万台湾元の過料が科される可能性があり、会社の規模・違反状況により45万台湾元までの過料が科されることもあります。
解雇規制の厳格性と種類
台湾において、労働者は労働基準法の保護を受けており、会社は法定の事由がなければ労働者を解雇することができません。台湾における解雇は、予告期間の有無によって大きく分けて労働基準法第11条、20条による「予告解雇」と労働基準法第12条による「即時解雇」の2種類があります。
- 予告解雇: 事業閉鎖、事業譲渡、事業損失、不可抗力による一時的な事業停止、事業性質変更に伴う人員削減、能力不足、会社再編・譲渡といった特定の法定事由がある場合にのみ許されます。勤続年数に応じた予告期間(3ヶ月以上1年未満:10日、1年以上3年未満:20日、3年以上:30日)が必要であり、予告期間を置かない場合はその期間分の賃金を支払う必要があります。
- 即時解雇: 労働者の重大な過失(契約時の虚偽申告、暴行、侮辱、秘密漏洩、無断欠勤など)がある場合に、予告期間や退職金なしで解雇が可能です。ただし、会社は事由を知ってから30日以内に解雇を行う必要があります。
台湾の解雇規制は、法定事由の限定と、解雇の種類に応じた厳格な手続き要件により、労働者保護が非常に手厚いのが特徴です。
外国人労働者の雇用規制と就労ビザ
台湾において外国人を雇用する基本法は雇用サービス法(就業服務法)の第5章です。原則として、外国人を雇用する際には、まず労働力発展署に就労許可を申請し、その後、外交部領事局に居留ビザを申請、当該外国人労働者が台湾に来台後15日以内に内政部移民署に居留証を申請する必要があります。
外国人が就労できる職種は、「専門・技術職」「外国投資企業の役員・管理者」「教師」「スポーツ選手・コーチ」「宗教・芸術・エンターテイメント職」「家事・介護ヘルパー」など、特定の分野に限定されています。また、一部の職種では最低賃金が適用されます。
まとめ
台湾の法制度は、その歴史的背景から日本の法制度と多くの共通点を持ち、大陸法系を基盤としながらも、独自の進化を遂げています。特に、五権分立の憲法体制や不動産物権の「登記発効主義」、同性婚の合法化といった点は、日本法との重要な相違点として、日本の経営者や法務部員が台湾でのビジネス展開を検討する上で深く理解すべき要素です。
会社法においては、単一法人株主の非公開会社に対する柔軟な機関設計や、コーポレートガバナンス規制の国際基準への積極的な整合性、株主情報開示義務の強化が注目されます。また、特に、広告代理業者、広告媒体業者、広告推薦者(インフルエンサーなど)が広告主と連帯して損害賠償責任を負うケースについて定めている広告規制も特徴的です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務