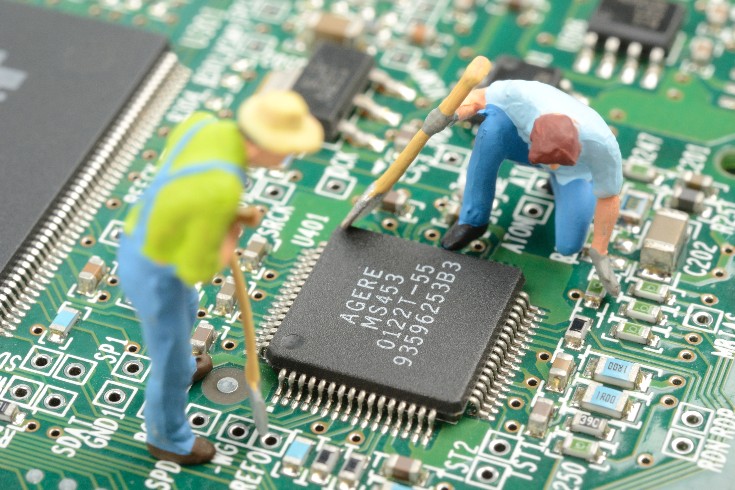µ│ĢÕŠŗńÜäĶ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃü┐Ńü¤ŃĆüŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕżēµø┤ń«ĪńÉåŃü«ĶĪīŃüäµ¢╣Ńü©Ńü»

ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃü¦Ńü»ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńüīõ║ŗÕēŹŃü½Ķ¬¼µśÄŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ÕåģÕ«╣ŃüīŃĆüõ╗Ģõ║ŗŃüīķĆ▓ŃéĆķüÄń©ŗŃü¦ÕŠīŃüŗŃéēÕżēµø┤ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃüīÕŠĆŃĆģŃü½ŃüŚŃü”ĶĄĘŃüōŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüõ╗Ģõ║ŗŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝Ńü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüõĖĆÕ║”ńĘĀńĄÉŃüŚŃü¤Õźæń┤äŃüŚŃü¤Õźæń┤äŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃĆüÕŠīŃüŗŃéēÕźæń┤äÕåģÕ«╣Ńü«Õżēµø┤Ńü½Õ┐£ŃüśŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīÕć║Ńü”ŃüÅŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃü¬ŃüŗŃü¬Ńüŗµā│Õ«ÜķĆÜŃéŖŃü½ķĆ▓ŃüŠŃü¬ŃüäŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃü©ŃüäŃüåŃééŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚµ│ĢńÜäŃü¬Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃĆüõ║ŗÕŠīŃü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃĆīÕżēµø┤ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåńÅŠĶ▒ĪŃéÆŃü®Ńüåµē▒ŃüŻŃü”ŃüäŃüÅŃü╣ŃüŹŃüŗŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃü»Ńü¬Ńü£õ║ŗÕŠīŃü¦ŃĆīÕżēµø┤ŃĆŹŃüĢŃéīŃéŗŃü«Ńüŗ
ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü»ŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝Ńü©Ńā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü«Õģ▒ÕÉīõĮ£µźŁ
ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü»õĖĆĶł¼ńÜäŃü½Ńü»ŃĆüõ╝üńö╗Ńā╗µÅɵĪłµ«ĄķÜÄŃéÆńĄīŃü”ŃĆüķ¢ŗńÖ║Ńü«Ķ”üõ╗ČŃüīÕ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃĆüÕźæń┤äŃüīńĘĀńĄÉŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”Õźæń┤äŃüīńĘĀńĄÉŃüĢŃéīŃü”õ╗źķÖŹŃü»ŃĆüÕÉäń©«Ķ©ŁĶ©łŃéÆńĄīŃü”ŃĆüĶ©ŁĶ©łķĆÜŃéŖŃü½Õ«¤ĶŻģŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃéŗÕĘźń©ŗŃéÆńĄéŃüłŃĆüµ£ĆÕŠīŃü½ŃāåŃé╣ŃāłŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ńĄéõ║åŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåµĄüŃéīŃéÆŃü¤Ńü®ŃéŗŃü«ŃüīõĖĆĶł¼ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüÕĘźń©ŗÕģ©õĮōŃü¦Ńü»ŃĆüõ╗Ģõ║ŗŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝ŃüīŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©ŃüŚŃü”Õ║āń»äŃü½ńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃüōŃü©Ńü»ŃééŃüĪŃéŹŃéōŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Õü┤Ńü½ŃééõĖĆÕ«ÜŃü«ÕŹöÕŖøńŠ®ÕŗÖŃüīĶ¬▓ŃüøŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüżŃüÅŃéŗŃü╣ŃüŹŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃüīµīüŃüŻŃü”ŃüŖŃüÅŃü╣ŃüŹµ®¤ĶāĮŃü«µ┤ŚŃüäÕć║ŃüŚ’╝ł’╝ØĶ”üõ╗ČÕ«ÜńŠ®’╝ēŃéäŃĆüńö╗ķØóÕü┤Ńü«Õż¢Ķ”│ŃéäµōŹõĮ£µä¤’╝ł’╝ØÕ¤║µ£¼Ķ©ŁĶ©ł’╝ēŃĆüŃüØŃüŚŃü”ŃĆüĶ”üõ╗ČķĆÜŃéŖŃü«ŃééŃü«ŃüīŃü¦ŃüŹŃü¤ŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü«ńó║Ķ¬Ź’╝ł’╝ØŃāåŃé╣ŃāłŃééŃüŚŃüÅŃü»µż£ÕÅÄ’╝ēŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ÕĘźń©ŗŃü¦Ńü»ńē╣Ńü½ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Õü┤Ńü«ÕŹöÕŖøŃüīķćŹĶ”üŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃü¬ŃüŖŃĆüŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃüīĶ▓ĀŃüŻŃü”ŃüäŃéŗńŠ®ÕŗÖŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«õĖĆĶł¼ńÜäŃü¬Ķ¦ŻĶ¬¼Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«Ķ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ŃüŚŃüŵē▒ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕŹöÕŖøńŠ®ÕŗÖŃü»ŃüéŃéīŃü®ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü»Ńü¬Ńü½ŃüŗŃü©Õżēµø┤ŃéƵ▒éŃéüŃü”ŃüÅŃéŗŃééŃü«
ŃüŚŃüŗŃüŚŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü¦ŃééŃü¬ŃüäŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃüīŃĆüÕĖĖŃü½Ķ©łńö╗µĆ¦ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃĆüŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü½Õ┐ģĶ”üŃü¬µāģÕĀ▒ŃéÆÕĖĖŃü½õĖŹĶČ│Ńü¬ŃüÅńČ▓ńŠģńÜäŃü½ŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝Ńü½õ╝ØŃüłŃüŹŃéīŃéŗŃüŗŃü©ŃüäŃüłŃü░ŃĆüŃüØŃüåŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéńÅŠÕ«¤Ńü½Ńü»ŃĆüń┤░ŃüŗŃüÅńĘ╗Õ»åŃü¬õĮ£µźŁŃü¦ŃüéŃéŗŃüīŃéåŃüłŃü½ŃĆüŃü®ŃüåŃüäŃüŻŃü¤õ║ŗÕ«¤ŃüīÕŠīÕĘźń©ŗŃü½ŃüŖŃüäŃü”µ▒║Õ«ÜńÜäŃü¬µäÅÕæ│ŃéƵīüŃüĪŃüåŃéŗŃüŗŃü¬Ńü®Ńü»Ńā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü½Ńééõ║łµĖ¼ŃüŚŃüłŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃééÕżÜŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüńÜ«ĶéēŃü½ŃééŃĆüķćŹĶ”üŃü¬õ║ŗÕ«¤Ńü╗Ńü®ÕŠīŃüŗŃéēÕ░ÅÕć║ŃüŚŃü½Õć║Ńü”ŃüÅŃéŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤õ║ŗµģŗŃü½ŃééŃü¬ŃéŖŃüŗŃüŁŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃüåŃüŚŃü¤õ║ŗµāģŃüŗŃéēŃĆüńÅŠÕ«¤Ńü«ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃü¦Ńü»ŃĆüŃĆīõĖŖµĄüÕĘźń©ŗŃüŗŃéēõĖŗµĄüÕĘźń©ŗŃüŠŃü¦õĖƵ░ŚķĆÜĶ▓½ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåŃü«ŃüīńÉåµā│Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüżŃüżŃééŃĆüõ║ŗÕŠīŃü¦µ¦śŃĆģŃü¬Õżēµø┤ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃüåŃéŗŃü©ŃüäŃüåµā│Õ«ÜŃü«ŃééŃü©ŃĆüŃĆīÕżēµø┤ń«ĪńÉåŃĆŹŃéÆŃüäŃüŗŃü½ŃüŚŃü”ĶĪīŃüåŃüŗŃü©ŃüäŃüåńé╣ŃüīķćŹĶ”üŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüÅŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
Õżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü©Ńü»

Õżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃüīńö©ŃüäŃéēŃéīŃéŗÕĀ┤ķØóŃü©Ńü»
Õżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü©Ńü»ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃüīŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüõ║ŗÕēŹŃü½ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤Ķ¬¼µśÄŃü«ÕåģÕ«╣ŃüŗŃéēŃĆüõ╗Ģµ¦śŃü«Õżēµø┤Ńéäµ®¤ĶāĮŃü«Ķ┐ĮÕŖĀŃéÆõŠØķĀ╝ŃüÖŃéŗķÜøŃü½ńö©ŃüäŃéŗµ¢ćµøĖŃü«ŃüōŃü©ŃéÆĶ©ĆŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕģłĶ┐░Ńü«ķĆÜŃéŖŃĆüĶ”üõ╗ČÕ«ÜńŠ®ŃéäÕ¤║µ£¼Ķ©ŁĶ©łŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃāĢŃé¦Ńā╝Ńé║Ńü¦ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃééŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝Ńü«µźŁÕŗÖŃü½Õ»ŠŃüŚÕŹöÕŖøŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«ÕĘźń©ŗŃü¦ÕŠīŃüŗŃéēńĢ░Ńü¬ŃéŗĶ”üµ£øŃéÆŃüéŃüÆŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü»Õ«¤ķÜøŃü½ŃééĶĄĘŃüōŃéŖŃüåŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
Õżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŗÕĀ┤ķØóŃü©ŃüŚŃü”õŠŗŃéÆŃüéŃüÆŃéŗŃü¬ŃéēŃĆüŃü¤Ńü©ŃüłŃü░ŃĆü
- Ķ”üõ╗ČÕ«ÜńŠ®ŃéäÕ¤║µ£¼Ķ©ŁĶ©łŃü¦µż£Ķ©ÄŃü½µ╝ÅŃéīŃüīŃüéŃéŖŃĆüõ║ŗÕŠīŃü¦µ®¤ĶāĮŃü«Ķ┐ĮÕŖĀŃéÆŃā¬Ńé»Ńé©Ńé╣ŃāłŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉł
- ķ¢ŗńÖ║Ńü«ķĆöõĖŁŃü¦ŃĆüõ║ŗµźŁŃü«µ¢╣ķćØŃü¬Ńü®Ńü½Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃĆüõ╗Ģµ¦śÕżēµø┤ŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŗÕĀ┤ÕÉł
Ńü¬Ńü®ŃüīĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüµ®¤ĶāĮŃü«Ķ┐ĮÕŖĀŃā╗õ╗Ģµ¦śŃü«Õżēµø┤Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤Ķ®▒ķĪīŃü½ķ¢óķĆŻŃüŚŃü”ŃüäŃüåŃü©ŃĆüõ╗Ģõ║ŗŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗÕü┤Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü¬Ńü½ŃéłŃéŖµ░ŚŃü½Ńü¬ŃéŗŃü«Ńü»ŃĆüĶ”ŗń®ŹŃéŖķćæķĪŹŃü«Õżēµø┤Ńüīµ│ĢÕŠŗõĖŖĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗŃü«ŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃüōŃü«ńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕłźĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ń┤░Ńü½Ķ¬¼µśÄŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃüåŃüŚŃü¤õ║ŗÕŠīńÜäŃü¬Ķ”ŗń®ŹŃéŖŃü«ÕóŚķĪŹŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃü½ŃĆüŃüØŃü«ÕåģÕ«╣Ńü«Ķ”ŗń®ŹŃéŖŃü«Õ”źÕĮōµĆ¦ŃéƵĩŃüŚķćÅŃéŗŃü¤ŃéüŃü«µĀ╣µŗĀŃü©Ńü¬ŃéŗŃü«ŃüīÕżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü¦ŃüÖŃĆéÕŠīŃü¦ÕóŚķĪŹŃüĢŃéīŃü¤Ķ”ŗń®ŹŃéŖŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”Ķ½ŗµ▒éŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃĆüńøĖµēŗµ¢╣Ńü©µÅēŃéüõ║ŗŃéÆĶĄĘŃüōŃüĢŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃü½Ńéé’╝łŃüŠŃü¤µÅēŃéüõ║ŗŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤ķÜøŃü½Ķć¬Ķ║½Ńü«Ķ©ĆŃüäÕłåŃü½Ķ¬¼ÕŠŚÕŖøŃéƵīüŃü¤ŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńéé’╝ēŃĆüÕżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü«õĮ£µłÉŃüīķćŹĶ”üŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé
Õżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü«Ķ©śĶ╝ēõ║ŗķĀģ
Ńü¦Ńü»ŃĆüµ│ĢÕŠŗõĖŖŃĆüÕżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃü╣ŃüŹõ║ŗķĀģŃü½Ńü»Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ŃééŃü«ŃüīŃüéŃéŗŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéÕżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃéÆÕł®ńö©ŃüŚŃü”ŃĆüõ╗Ģµ¦śÕżēµø┤Ńā╗µ®¤ĶāĮŃü«Ķ┐ĮÕŖĀŃü½Õ┐£ŃüśŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕźæń┤äŃü«õ╗ĢńĄäŃü┐Ńü»ŃüÖŃü¦Ńü½õĖĆĶł¼ńÜäŃü½ŃééÕ║āŃüÅĶ¬Źń¤źŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüńĄīńöŻń£üŃāóŃāćŃā½Õźæń┤äŃü¬Ńü®Ńü«ŃĆüÕ«śÕ║üŃüīńż║ŃüÖÕźæń┤äµØĪķĀģŃü«ķøøÕĮóŃéÆńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬õ║ŗķĀģŃéÆĶ©śķī▓Ńü©ŃüŚŃü”µ«ŗŃüÖŃü╣ŃüŹŃüŗŃüīµ”éŃüŁŃéÅŃüŗŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
’╝łÕżēµø┤ń«ĪńÉåµēŗńČÜ’╝ē
ń¼¼ 37 µØĪ ńö▓ÕÅłŃü»õ╣ÖŃü»ŃĆüńøĖµēŗµ¢╣ŃüŗŃéēń¼¼ 34 µØĪ’╝łŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀõ╗Ģµ¦śµøĖńŁēŃü«Õżēµø┤’╝ēŃĆüń¼¼ 35 µØĪ’╝łõĖŁķ¢ōĶ│ćµ¢ÖŃü«Ńā”Ńā╝ŃéČŃü½ŃéłŃéŗµē┐Ķ¬Ź’╝ēŃĆüń¼¼ 36 µØĪ’╝łµ£¬ńó║Õ«Üõ║ŗķĀģŃü«ÕÅ¢µē▒Ńüä’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕżēµø┤µÅɵĪłµøĖŃéÆÕÅŚķĀśŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕĮōĶ®▓ÕÅŚķĀśµŚźŃüŗŃéēŌŚŗµŚźõ╗źÕåģŃü½ŃĆüµ¼ĪŃü«õ║ŗķĀģŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü¤µøĖķØó’╝łõ╗źõĖŗŃĆīÕżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃĆŹŃü©ŃüäŃüåŃĆé’╝ēŃéÆńøĖµēŗµ¢╣Ńü½õ║żõ╗śŃüŚŃĆüńö▓ÕÅŖŃü│õ╣ÖŃü»ŃĆüń¼¼ 12 µØĪµēĆÕ«ÜŃü«ķĆŻńĄĪÕŹöĶŁ░õ╝ÜŃü½ŃüŖŃüäŃü”ÕĮōĶ®▓Õżēµø┤Ńü«ÕÅ»ÕÉ”Ńü½ŃüżŃüŹÕŹöĶŁ░ŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü©ŃüÖŃéŗŃĆé
ŌæĀ Õżēµø┤Ńü«ÕÉŹń¦░
ŌæĪ µÅɵĪłŃü«Ķ▓¼õ╗╗ĶĆģ
Ōæó Õ╣┤µ£łµŚź
ŌæŻ Õżēµø┤Ńü«ńÉåńö▒
Ōæż Õżēµø┤Ńü½õ┐éŃéŗõ╗Ģµ¦śŃéÆÕɽŃéĆÕżēµø┤Ńü«Ķ®│ń┤░õ║ŗķĀģ
Ōæź Õżēµø┤Ńü«Ńü¤ŃéüŃü½Ķ▓╗ńö©ŃéÆĶ”üŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃüØŃü«ķĪŹ
Ōæ” µż£Ķ©Äµ£¤ķ¢ōŃéÆÕɽŃéüŃü¤Õżēµø┤õĮ£µźŁŃü«Ńé╣Ńé▒ŃéĖŃāźŃā╝Ńā½
Ōæ¦ ŃüØŃü«õ╗¢Õżēµø┤Ńüīµ£¼Õźæń┤äÕÅŖŃü│ÕĆŗÕłźÕźæń┤äŃü«µØĪõ╗Č’╝łõĮ£µźŁµ£¤ķ¢ōÕÅłŃü»ń┤Źµ£¤ŃĆüÕ¦öĶ©Śµ¢ÖŃĆüÕźæń┤äµØĪķĀģńŁē’╝ēŃü½õĖÄŃüłŃéŗÕĮ▒ķ¤┐
ńø┤µÄźµØĪµ¢ćŃéÆĶ¬ŁŃéōŃü¦ŃĆüĶ©śĶ╝ēŃüīµÄ©Õź©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗķĀģńø«ŃéÆńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéīŃü░ŃĆüŃééŃüåŃüōŃéīõ╗źõĖŖŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼Ńü»õĖŹĶ”üŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéÕŠīŃü¦ŃĆīĶ©ĆŃüŻŃü¤Ńā╗Ķ©ĆŃéÅŃü¬ŃüäŃĆŹŃü«ÕĢÅķĪīŃü½ŃüŚŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüĶ®│ń┤░ŃüŗŃüżÕģĘõĮōńÜäŃü½Õżēµø┤Ńü«ńĄīńĘ»ŃéÆĶ©śķī▓ŃüÖŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃüåŃüŚŃü¤Ķ©śĶ╝ēõ║ŗķĀģŃéƵśÄĶ©śŃü«ŃüåŃüłŃĆüŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝Ńü©Ńā”Ńā╝ŃéČŃā╝ÕÅīµ¢╣Ńü«Ķ▓¼õ╗╗ĶĆģŃā╗µ▒║ĶŻüĶĆģŃü«ńĮ▓ÕÉŹŃü¬ŃüäŃüŚŃü»µŹ║ÕŹ░Ńü¬Ńü®Ńü©Ńé╗ŃāāŃāłŃü½Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüõĖćõĖĆĶŻüÕłżŃü½Ńü¬ŃéŗŃéłŃüåŃü¬ŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŹŃüåŃü©ŃééŃĆüĶ©╝µŗĀŃü©ŃüŚŃü”Õźæń┤äµøĖŃü©ÕÉīńŁēŃü«µäÅńŠ®ŃéÆŃééŃüżŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé
Õżēµø┤ń«ĪńÉåŃü½ķ¢óķĆŻŃüŚŃü”ń¤źŃüŻŃü”ŃüŖŃüÅŃü©Ķē»ŃüäŃüōŃü©

Õżēµø┤ń«ĪńÉåŃü»Õż¦µŖĄŃĆüĶ¬▓ķĪīń«ĪńÉåŃü©Ńé╗ŃāāŃāłŃü¦ĶĪīŃüåŃü╣ŃüŹŃééŃü«
Õżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗńÉåńö▒Ńü»ŃĆüÕżēµø┤Õ▒źµŁ┤ŃéÆń«ĪńÉåŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃéÆķüöµłÉŃü½Õ░ÄŃüÅŃüōŃü©’╝łŃüéŃéŗŃüäŃü»ŃĆüķüöµłÉŃü½Õ░ÄŃüæŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüõĖŹÕĮōŃü¬Ķ▓¼õ╗╗Ķ┐ĮÕÅŖŃéÆÕø×ķü┐ŃüÖŃéŗŃüōŃü©’╝ēŃü½ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüłŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüåŃüŚŃü¤ńø«ńÜäŃéÆķüöµłÉŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Õ«¤ÕŗÖõĖŖŃü»ŃĆüÕżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü«õĮ£µłÉŃü»ŃĆüĶ¬▓ķĪīń«ĪńÉåõĖĆĶ”¦ĶĪ©Ńü«õĮ£µłÉŃā╗µø┤µ¢░Ńü©Ńé╗ŃāāŃāłŃü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕżÜŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪŃĆüÕżēµø┤Õ▒źµŁ┤ŃéÆÕżēµø┤ń«ĪńÉåĶĪ©Ńü¦ń«ĪńÉåŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüŃüØŃü«ÕÉłµäÅŃüĢŃéīŃü¤Õżēµø┤ķĀģńø«Ńü»ŃĆüõ╗ŖÕŠīÕÅ¢ŃéŖńĄäŃéĆŃü╣ŃüŹĶ¬▓ķĪīŃü©ŃüŚŃü”Ķ¬▓ķĪīń«ĪńÉåõĖĆĶ”¦ĶĪ©Ńü«ķĀģńø«Ńü½ÕÅ¢ŃéŖĶŠ╝ŃüŠŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé
Õżēµø┤ÕŹöĶŁ░Ńü«ĶĪīŃüäµ¢╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃüéŃéÅŃüøŃü”Ķ”ÅÕ«ÜŃéÆŃüÖŃéŗŃü«ŃüīŃāÖŃé┐Ńā╝
Õżēµø┤ń«ĪńÉåŃü«ŃéäŃéŖµ¢╣ŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕżēµø┤Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕŹöĶŁ░Ńü«ĶĪīŃüäµ¢╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃĆüŃüéŃéÅŃüøŃü”Ķ”ÅÕ«ÜŃéÆĶ©ŁŃüæŃü”ŃüŖŃüÅŃü©ŃĆüÕżēµø┤Ńü«Õ»ŠÕ┐£ŃüīŃé╣ŃāĀŃā╝Ńé║Ńü½ŃüäŃüÅŃüōŃü©Ńüīµ£¤ÕŠģŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńé╣Ńü»ŃĆüńē╣Ńü½ŃéóŃéĖŃāŻŃéżŃā½ķ¢ŗńÖ║Ńü¬Ńü®ŃĆüõ║ŗÕŠīŃü½ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬Õżēµø┤ŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕēŹµÅÉŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗķ¢ŗńÖ║µēŗµ│ĢŃéƵÄĪńö©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüńē╣Ńü½ķćŹĶ”üŃü¬ńé╣Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃééŃĆüÕżēµø┤ń«ĪńÉåŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕŹöĶŁ░Ńü«Ķ”üĶ½ŗŃüīŃüéŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüńøĖµēŗµ¢╣ŃüīŃüäŃüżŃüŠŃü¦Ńü½ÕŹöĶŁ░Ńü½Õ┐£ŃüśŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¬Ńü«ŃüŗŃü¬Ńü®ŃéÆĶ”ÅÕ«ÜŃüÖŃéŗõŠŗŃü»ÕżÜŃüÅŃü┐ŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Õżēµø┤ÕŹöĶŁ░Ńü©Ķ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖ
õĖĪÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīõĖĆÕ║”ÕÉłµäÅŃüŚŃü¤Õźæń┤äŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõ║ŗÕŠīŃü¦ŃüØŃéīŃéÆÕżēµø┤ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüäŃéÅŃü░ŃüØŃéīŃü»µ¢░Ńü¤Ńü¬Õźæń┤äŃéÆńĘĀńĄÉŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü¦ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕźæń┤äŃüīÕĮōõ║║Ńü«Ķć¬ńö▒µäÅÕ┐ŚŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃüŗŃéēŃüÖŃéīŃü░ŃĆüÕĤÕēćĶ½¢Ńü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝ŃüīÕżēµø┤Õźæń┤äŃü½Õ┐£ŃüśŃéŗńŠ®ÕŗÖŃü»Ńü¬ŃüäŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüōŃüåŃüŚŃü¤µ©®Õł®Ńü«ķØóŃüīÕ╝ĘĶ¬┐ŃüĢŃéīŃüÖŃüÄŃéŗŃü©ŃĆüńÅŠÕ«¤ÕĢÅķĪīŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃüīÕååµ╗æŃü½ķĆ▓ŃüŠŃü¬ŃüÅŃü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃüīµćĖÕ┐ĄŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃééŃüéŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü»ŃéłŃüÅÕźæń┤äµøĖÕåģŃü½ŃĆüŃĆīÕżēµø┤Ńü«ÕŹöĶŁ░Ńü½Ķ¬ĀÕ«¤Ńü½Õ┐£ŃüśŃéŗńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃü¬ŃéŗŃééŃü«Ńü½ŃüżŃüäŃü”µśÄĶ©śŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃééÕżÜŃüÅŃĆüŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝ŃüīÕżēµø┤Ńü½Ķ¬ĀÕ«¤Ńü½Õ┐£ŃüśŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ½ŗµ▒éŃü¬Ńü®ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŗŃéłŃüåŃü¬Ķ©śĶ╝ēŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗõŠŗŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ©śĶ╝ēõŠŗŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüŃü¤Ńü©ŃüłŃü░õ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬µ¢ćõŠŗŃü¦ŃüÖ’╝łõ╗źõĖŗŃü½ŃĆüµØĪµ¢ćŃü«Ķ©śĶ╝ēõŠŗŃéƵÄ▓Ķ╝ēŃĆéńŗ¼ń½ŗĶĪīµö┐µ│Ģõ║║ µāģÕĀ▒Õć”ńÉåµÄ©ķĆ▓µ®¤µ¦ŗÕģ¼Õ╝ÅõĮ£µłÉŃü«ŃĆÄffÕ¤║µ£¼/ÕĆŗÕłźÕźæń┤äŃāóŃāćŃā½Ńü«Õ¤║µ£¼Õźæń┤äµøĖµĪłŃĆÅŃéłŃéŖÕ╝Ģńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝ēŃĆé
ń¼¼4µØĪ3ķĀģŃĆĆÕżēµø┤ÕŹöĶŁ░Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕżēµø┤Ńü«Õ»ŠĶ▒ĪŃĆüÕżēµø┤Ńü«ÕÅ»ÕÉ”ŃĆüÕżēµø┤Ńü½ŃéłŃéŗõ╗ŻķćæŃā╗ń┤Źµ£¤Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕĮ▒ķ¤┐ńŁēŃéƵż£Ķ©ÄŃüŚŃĆüÕżēµø┤ŃéÆĶĪīŃüåŃüŗŃü½ŃüżŃüäŃü”õĖĪÕĮōõ║ŗĶĆģŃü©ŃééĶ¬ĀÕ«¤Ńü½ÕŹöĶŁ░ŃüÖŃéŗŃĆé
Õżēµø┤µ¢╣µ│ĢŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ķ”ÅÕ«Ü
ÕģłĶ┐░Ńü«ķĆÜŃéŖŃĆüÕżēµø┤ŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃü½Ńü»ŃĆüķĆÉõĖĆÕżēµø┤Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕŹöĶŁ░ŃéÆķ¢ŗÕé¼ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü©ŃüŚŃü¤Ńü╗ŃüåŃüīŃĆüµ│ĢńÜäŃü½Ńü»ŃĆīÕ«ēÕģ©ŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüÕ░ÅĶ”ŵ©ĪŃü¬ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃü¦ŃüéŃéīŃü░ŃĆüŃéÅŃü¢ŃéÅŃü¢Õżēµø┤Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕŹöĶŁ░Ńü«ĶĪīŃüäµ¢╣ŃüŠŃü¦Õ«ÜŃéüŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåÕĀ┤ÕÉłŃééŃüéŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃüØŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüÕŹöĶŁ░Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ķ”ÅÕ«ÜŃéÆŃüŖŃüÅŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕŹöĶŁ░Ńü»Ńü¬ŃüÅŃü©ŃééÕżēµø┤ń«ĪńÉåµøĖŃü½Ńā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńā╗ŃāÖŃā│ŃāĆŃā╝ŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«Ķ▓¼õ╗╗ĶĆģŃü«ńĮ▓ÕÉŹŃā╗µŹ║ÕŹ░ŃéÆĶĪīŃüåŃü¬Ńü®Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüŃü»ŃüśŃéüŃü”Õżēµø┤ŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃéäŃéŖµ¢╣Ńü½ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕÅŻķĀŁŃü½ŃéłŃéŗÕÉłµäÅŃü«Ńü┐Ńü¦Õ«ēµśōŃü½Õżēµø┤Ńü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½ŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüÕżēµø┤ŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃü¤Ńü«ŃüŗÕÉ”ŃüŗŃüīŃü¬Ńü½ŃüŗŃü©µø¢µś¦Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüīŃüĪŃü¦ŃĆüÕŠīŃü¦Õż¦ŃüŹŃü¬ŃāłŃā®Ńā¢Ńā½Ńü½Ńü¬ŃéŗŃü©ŃüäŃüåµäÅÕæ│Ńü¦ŃééŃĆüµ¢ćµøĖń«ĪńÉåŃü»ÕŠ╣Õ║ĢŃüÖŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ŃééŃüŻŃü©ŃééŃĆüµ»ÄÕø×Õżēµø┤ń«ĪńÉåŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ÕłźķĆöµøĖķĪ×ŃéÆńö©µäÅŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüĢŃüłĶ▓ĀµŗģŃüīķćŹŃüÅŃĆüĶ橵®¤Õ┐£ÕżēŃü¬Õ»ŠÕ┐£ŃéÆĶĪīŃüåŃüōŃü©ŃéÆŃéłŃéŖķćŹĶ”¢ŃüŚŃü¤ŃüäŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŗŃüŗŃééŃüŚŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüØŃüåŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüõ╝ÜĶŁ░Ńü«ĶŁ░õ║ŗķī▓Ńü«Ńü¬ŃüŗŃü½Õżēµø┤Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗõ║ŗķĀģŃéÆŃāēŃéŁŃāźŃāĪŃā│ŃāłÕī¢ŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃü©ŃüäŃüåŃéäŃéŖµ¢╣Ńü½ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééõĖƵĪłŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķ¢ŗńÖ║Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╝ÜĶŁ░Ńü«ĶŁ░õ║ŗķī▓Ńü«µ«ŗŃüŚµ¢╣Ńü©ŃüäŃüåńé╣Ńü½ķ¢óŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«Ķ©śõ║ŗŃü¦Ķ®│ń┤░Ńü½Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
ķĀ╗ń╣üŃü½õ╗Ģµ¦śÕżēµø┤ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃéŗńÅŠÕĀ┤Ńü¦Ńü»Ńü¤ŃüŚŃüŗŃü½ŃĆüŃü¬Ńü½ŃüŗŃü©ŃāłŃā®Ńā¢Ńā½ŃéäµÅēŃéüõ║ŗŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü©ķÜŻŃéŖÕÉłŃéÅŃüøŃü½Ńü¬ŃéŖŃüīŃüĪŃü¦ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃüåŃüŚŃü¤Ķ橵®¤Õ┐£ÕżēŃüĢŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗńÅŠÕĀ┤Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüŃü¤ŃüĀÕøøĶ¦ÆÕøøķØóŃü½ŃĆīń«ĪńÉåŃü«ķćŹĶ”üµĆ¦ŃĆŹŃéÆÕ╝ĘĶ¬┐ŃüŚŃü”ŃééŃĆüńÅŠÕ«¤ńÜäŃü¬µ¢ĮńŁ¢ŃéÆĶ¼øŃüśŃéŗŃüōŃü©Ńü»ķøŻŃüŚŃüäŃüōŃü©ŃüīÕżÜŃüäŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé
ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńü½Ķ”üµ▒éŃüĢŃéīŃéŗŃé╣ŃāöŃā╝Ńāēµä¤Ńü©ŃĆüõĖćŃüīõĖĆŃü«õ║ŗµģŗŃüĖŃü«ÕéÖŃüłŃéÆŃüäŃüŗŃü½ŃüŚŃü”õĖĪń½ŗŃüŚŃü”ŃüäŃüÅŃü╣ŃüŹŃüŗŃü©ŃüäŃüåÕĢÅķĪīŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«ńŖȵ│üŃā╗ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃü«ÕåģÕ«╣Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Ńééµ£Ćķü®Ķ¦ŻŃüīńĢ░Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕżÜŃüäŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃéłŃüåŃü½µĆØŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆéµ£¼Ķ©śõ║ŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬ÕåģÕ«╣ŃéÆĶĖÅŃüŠŃüłŃüżŃüżŃééŃĆüõ╝ÜńżŠŃüöŃü©Ńā╗ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃüöŃü©Ńü½ŃĆüķü®ÕłćŃü¬ŃéäŃéŖµ¢╣ŃéÆÕÉäŃĆģµ©Īń┤óŃüŚŃü”ŃüäŃüÅÕ¦┐ÕŗóŃééķćŹĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŗŃééŃü«Ńü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé