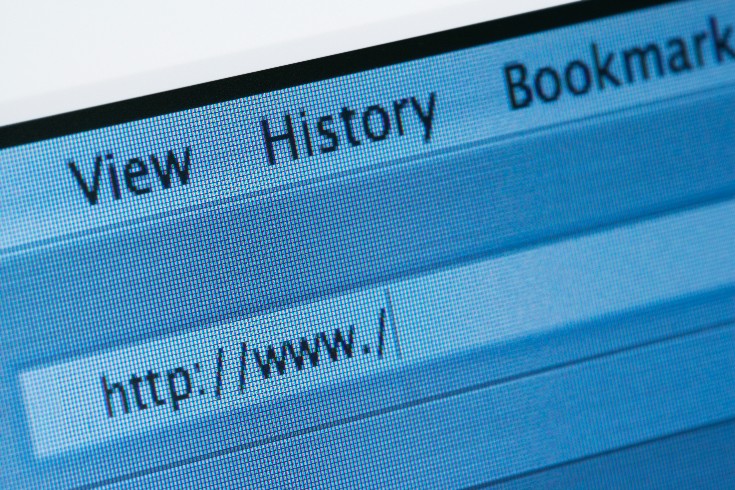م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ç™؛و³¨è€…مپ§مپ‚م‚‹مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپŒè² مپ†هچ”هٹ›ç¾©ه‹™مپ¨مپ¯

م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ن»•ن؛‹مپ¯م€پé–‹ç™؛مپ•م‚Œم‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپŒه¤§è¦ڈو¨،مپ§مپ‚م‚Œمپ°مپ‚م‚‹مپ»مپ©م€په¤ڑو•°مپ®ن؛؛و‰‹م‚„ه·¥و•°م‚’مپ‹مپ‘مپ¦è،Œمپ†ه؟…è¦پمپŒه‡؛مپ¦مپڈم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦مپمپ“مپ§مپ¯م€پé–‹ç™؛م‚’ه¼•مپچهڈ—مپ‘م‚‹مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛م‚’ç™؛و³¨مپ™م‚‹مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®هپ´مپ«م‚‚ن¸€ه®ڑمپ®هچ”هٹ›ç¾©ه‹™مپŒèھ²مپ›م‚‰م‚Œم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚
مپ“م‚Œمپ¯م€پé€ڑه¸¸مپ®هڈ—ç™؛و³¨é–¢ن؟‚مپ¨مپ¯ç•°مپھم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°ITم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ§مپ¯مپھمپڈم‚ھمƒ¼مƒ€مƒ¼مƒ،م‚¤مƒ‰مپ®م‚¹مƒ¼مƒ„مپ®ن½œوˆگم‚’م‚¹مƒ¼مƒ„ه±‹مپ«é ¼م‚€ه ´هگˆم€پç™؛و³¨è€…مپ§مپ‚م‚‹é،§ه®¢ï¼ˆمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼ï¼‰هپ´مپ¯م€پ特مپ«م€Œç¾©ه‹™م€چم‚’è² مپ„مپ¾مپ›م‚“م€‚م€Œç¾©ه‹™م€چم‚’è² مپ†مپ®مپ¯م€په°‚م‚‰هڈ—و³¨è€…مپ§مپ‚م‚‹م‚¹مƒ¼مƒ„ه±‹ï¼ˆمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼ï¼‰هپ´مپ§مپ™م€‚ه¤ڑو•°مپ®ن؛؛و‰‹م‚„ه·¥و•°مپŒه؟…è¦پمپھITم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ مپ‹م‚‰مپ“مپم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼م‚‚مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ«م€Œهچ”هٹ›م€چمپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹م€پمپ¨مپ„مپ†و§‹é€ مپ§مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼ن»»مپ›مپ§مپ¯و¸ˆمپ¾مپ•م‚Œمپھمپ„م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پç™؛و³¨è€…هپ´مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھو³•çڑ„義ه‹™مپŒمپ‚م‚‹مپ‹مپ«مپ¤مپ„مپ¦è§£èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ®ç›®و¬،
è‡ھ社مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ§مپ‚م‚‹ن»¥ن¸ٹم€پمپ™مپ¹مپ¦م€Œن¸¸وٹ•مپ’م€چمپ§مپ¯و¸ˆمپ¾مپ•م‚Œمپھمپ„
مپ²مپ¨مپ¤مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ§مپ‚مپ£مپ¦م‚‚م€پمپمپ“مپ«مپ¯ه¤ڑو•°مپ®ن؛؛مپ¨çµ„ç¹”مپŒé–¢ن¸ژمپ—مپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆمپŒه¤ڑمپ„م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚م‚³مƒ¼مƒ‡م‚£مƒ³م‚°وٹ€è،“مپ«é•·مپ‘مپںم‚¨مƒ³م‚¸مƒ‹م‚¢مƒ»مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒمپ¯م‚‚مپ،م‚چم‚“مپ®مپ“مپ¨م€پمپمپ†مپ—مپںن؛؛ه“،مپ®م‚¢م‚¦مƒˆمƒ—مƒƒمƒˆم‚’ن¸€مپ¤مپ®وˆگوœمپ«مپ¾مپ¨م‚پمپ‚مپ’م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچمƒ¼م‚¸مƒ£مƒ¼مپ®ه½¹ه‰²م‚‚é‡چè¦پمپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ—مپ‹مپ—م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپŒمپ©م‚Œمپ مپ‘é«کمپ„وٹ€è،“هٹ›مپ¨çµ„ç¹”هٹ›م‚’م‚‚مپ£مپ¦مپ—مپ¦م‚‚م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ مپ‘مپ®هٹ›مپ§م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپŒم‚„م‚ٹéپ‚مپ’م‚‰م‚Œم‚‹م‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپںمپ¨مپˆمپ°م€پمپمپ®ن¼ڑ社ه†…部مپ§مپ®مپ؟用مپ„م‚‰م‚Œم‚‹ç¤¾ه†…用èھم‚„م€پمپمپ®ن¼ڑ社مپ«ه›؛وœ‰مپ®و¥ه‹™çں¥èکمپ¨مپ„مپ£مپںم‚‚مپ®مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ®مپ؟مپ®ن¸€و–¹é€ڑè،Œمپ®هٹھهٹ›مپ§مپ¯çں¥م‚‹ç”±م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚ه¤§è¦ڈو¨،مپھم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®é–‹ç™؛مپ§مپ‚م‚Œمپ°مپ‚م‚‹مپ»مپ©م€پن¸€èˆ¬çڑ„مپھه‚¾هگ‘مپ¨مپ—مپ¦م€پمپمپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپŒو´»ç”¨مپ•م‚Œم‚‹ن¼ڑ社è‡ھن½“م‚‚ه¤ڑو•°مپ®ن؛؛مپ¨و¥ه‹™م‚’وٹ±مپˆمپںه¤§ن¼پو¥مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’é–‹ç™؛مپ®مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ®وˆگهٹںمپ«ه°ژمپڈمپںم‚پمپ«مپ¯م€په®ںمپ¯مƒ‘م‚½م‚³مƒ³ن»•ن؛‹ن»¥ه‰چمپ«م€پمپ“مپ†مپ—مپںمƒ“م‚¸مƒچم‚¹مƒم‚¸مƒƒم‚¯مپ®و•´çگ†مپ“مپمپŒه¤§مپچمپھم‚¦م‚§م‚¤مƒˆم‚’هچ م‚پمپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆم‚‚ه¤ڑمپ„م‚‚مپ®مپھمپ®مپ§مپ™م€‚
مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´م‚‚م€Œè‡ھهˆ†مپ¯ITوٹ€è،“مپ®ه°‚é–€ه®¶مپ§مپ¯مپھمپ„مپ‹م‚‰م€چمپ¨مپ„مپ†çگ†ç”±مپ§هڈ—مپ‘è؛«مپ«مپھم‚‹مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€پم‚€مپ—م‚چç©چو¥µçڑ„مپ«وƒ…ه ±وڈگن¾›م‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨مپ§م€پمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ®é€²è،ŒمپŒم‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپ«مپ„مپڈمپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚مپ“مپ®و„ڈه‘³مپ§مپ¯م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ«مپٹمپ„مپ¦مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپŒè² مپ£مپ¦مپ„م‚‹ه½¹ه‰²مپ¨مپ„مپ†مپ®مپ¯م€په®ںمپ¯و±؛مپ—مپ¦ه°ڈمپ•مپھم‚‚مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ®مپ§مپ™م€‚
هˆ¤ن¾‹م‚’è¸ڈمپ¾مپˆمپںمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ®هچ”هٹ›ç¾©ه‹™مپ¨مپ¯

مپ§مپ¯ه…·ن½“çڑ„مپ«م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ«مپٹمپ„مپ¦م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®هپ´مپŒè² مپ£مپ¦مپ„م‚‹هچ”هٹ›ç¾©ه‹™مپ¨مپ¯مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚مپ“مپ®ç‚¹مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پéپژهژ»مپ®هˆ¤ن¾‹مپ«ه¤ڑمپڈمپ®مƒ’مƒ³مƒˆمپŒو®‹مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
è£پهˆ¤مپ§مپ¯م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´ï¼ˆè¢«ه‘ٹ)مپ®ç´چوœںمپŒéپ…م‚Œمپںن»¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼ï¼ˆهژںه‘ٹ)مپ®و„ڈو€و±؛ه®ڑمپ®éپ…ه»¶ç‰مپŒمپ‚مپ£مپںمپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®é–‹ç™؛مپ«ه¯¾مپ™م‚‹هچ”هٹ›ç¾©ه‹™مپ®وœ‰ç„،مپŒن؛‰ç‚¹مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚مپ“مپ®ن»¶مپ«مپ¤مپچè£پهˆ¤و‰€مپ¯م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ®هچ”هٹ›ç¾©ه‹™éپ•هڈچم‚’مپ؟مپ¨م‚پم€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ®ه‚µه‹™ن¸چه±¥è،Œè²¬ن»»م‚’هگ¦ه®ڑمپ—مپ¾مپ—مپںم€‚(ه¥‘ç´„مپ®è§£é™¤مپ«é–¢مپ—مپ¦مپ¯èھچم‚پم‚‰م‚Œمپںم‚‚مپ®مپ®م€پمپ“مپ،م‚‰م‚‚ه…ه‰²مپ®éپژه¤±ç›¸و®؛مپŒèھچم‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚)
وœ¬ن»¶é›»ç®—م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛ه¥‘ç´„مپ¯ï¼Œمپ„م‚ڈم‚†م‚‹م‚ھمƒ¼مƒ€مƒ¼مƒ،م‚¤مƒ‰مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛ه¥‘ç´„مپ§مپ‚م‚‹مپ¨مپ“م‚چ,مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚ھمƒ¼مƒ€مƒ¼مƒ،م‚¤مƒ‰مپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛ه¥‘ç´„مپ§مپ¯ï¼Œهڈ—託者(مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼ï¼‰مپ®مپ؟مپ§مپ¯م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’ه®Œوˆگمپ•مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ¯مپ§مپچمپھمپ„مپ®مپ§مپ‚مپ£مپ¦ï¼Œه§”託者(مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼ï¼‰مپŒé–‹ç™؛éپژ程مپ«مپٹمپ„مپ¦ï¼Œه†…部مپ®و„ڈ見èھ؟و•´م‚’çڑ„ç¢؛مپ«è،Œمپ£مپ¦è¦‹è§£م‚’çµ±ن¸€مپ—مپںن¸ٹ,مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھو©ں能م‚’è¦پوœ›مپ™م‚‹مپ®مپ‹م‚’وکژç¢؛مپ«هڈ—託者مپ«ن¼مپˆï¼Œهڈ—託者مپ¨مپ¨م‚‚مپ«ï¼Œè¦پوœ›مپ™م‚‹و©ں能مپ«مپ¤مپ„مپ¦و¤œè¨ژمپ—مپ¦ï¼Œوœ€çµ‚çڑ„مپ«و©ں能م‚’و±؛ه®ڑمپ—,مپ•م‚‰مپ«ï¼Œç”»é¢م‚„ه¸³ç¥¨م‚’و±؛ه®ڑمپ—,وˆگوœç‰©مپ®و¤œهڈژم‚’مپ™م‚‹مپھمپ©مپ®ه½¹ه‰²م‚’هˆ†و‹…مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒه؟…è¦پمپ§مپ‚م‚‹م€‚
و±ن؛¬هœ°è£په¹³وˆگ16ه¹´ï¼“وœˆï¼‘ï¼گو—¥هˆ¤و±؛
وœ¬هˆ¤و±؛مپ¯م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپم‚Œè‡ھن½“مپŒمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ¨مپ®ه…±هگŒن½œو¥مپ§مپ‚م‚‹و—¨م‚’هˆ¤ç¤؛مپ™م‚‹مپ®مپ؟مپھم‚‰مپڑم€پم€Œه…·ن½“çڑ„مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھ点مپ«مپٹمپ„مپ¦هچ”هƒچمپ™مپ¹مپچمپھمپ®مپ‹م€چمپ¨مپ„مپ†ç‚¹مپ«مپ¤مپ„مپ¦è¨€وکژمپ—مپ¦مپ„م‚‹ç‚¹مپŒم€پéه¸¸مپ«ç¤؛ه”†مپ«ه¯Œم‚“مپ§مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپ«و€م‚ڈم‚Œمپ¾مپ™م€‚
試مپ؟مپ«ن¸ٹè¨کهˆ¤و±؛و–‡مپ®و–‡è¨€م‚’م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®IT用èھمپ«ç؟»è¨³مپ—مپ¦مپ؟مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
| وœ€çµ‚çڑ„مپ«و©ں能م‚’و±؛ه®ڑ・・・ →è¦پن»¶ه®ڑ義ï¼ڑمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھو©ں能م‚’ه‚™مپˆمپںم‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’ن½œم‚ٹمپںمپ„مپ‹مپ®وکژç¢؛هŒ– |
| ç”»é¢م‚„ه¸³ç¥¨م‚’و±؛ه®ڑ・・・ →هں؛وœ¬è¨è¨ˆï¼ڑç”»é¢م‚„ه¸³ç¥¨مپھمپ©م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ و“چن½œè€…مپ®è¦³ç‚¹مپ‹م‚‰مپ؟مپںم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ه¤–観مپ®è¨è¨ˆ |
| وˆگوœç‰©مپ®و¤œهڈژ・・・ →مƒ†م‚¹مƒˆم€€ï¼ڑن»•و§کé€ڑم‚ٹمپ®م‚‚مپ®مپŒن»•ن¸ٹمپŒمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’و¤œè¨¼مپ—م€پDBمƒ€مƒ³مƒ—مپھمپ©مپ®م‚¨مƒ“مƒ‡مƒ³م‚¹è³‡و–™مپ¨مپ¨م‚‚مپ«ç¢؛èھچمپ—م€پç´چه“پم‚’هڈ—مپ‘ن»کمپ‘م‚‹م€‚ |
مپ¨مپ„مپ£مپںه…·هگˆمپ«و•´çگ†مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ¯مپ„مپڑم‚Œم‚‚م€پITم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ه°‚é–€و€§مپŒمپ©م‚Œمپ»مپ©é«که؛¦مپ§مپ‚م‚چمپ†مپ¨م‚‚م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®هچ”هٹ›مپھمپ—مپ«هچک独مپ«مپھمپ—مپ†م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚و±‚م‚پمپ¦مپ„م‚‹و©ں能م‚„م€پç”»é¢مپ®مƒ¬م‚¤م‚¢م‚¦مƒˆمپŒمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹مپ‹مپ¯هں؛وœ¬çڑ„مپ«مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒوکژç¢؛هŒ–مپ™مپ¹مپچم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚ٹم€پمپ¾مپںو±‚م‚پمپںمپ¨مپٹم‚ٹمپ®م‚‚مپ®مپŒه®ںçڈ¾مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹هگ¦مپ‹م‚‚مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ«مپ—مپ‹ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¯مپ§مپچمپھمپ„مپ‹م‚‰مپ§مپ™م€‚ م€€
مپھمپٹم€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ«مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچم‚¸مƒ،مƒ³مƒˆç¾©ه‹™مپŒèھ²مپ›م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ¨هگŒمپکم‚ˆمپ†مپ«م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ«م‚‚هچ”هٹ›ç¾©ه‹™مپŒèھ²مپ›م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰مپ™م‚Œمپ°م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒن¸ٹè¨کمپ®م‚ˆمپ†مپھمƒ—مƒم‚»م‚¹مپ§هچ”هٹ›ç¾©ه‹™éپ•هڈچم‚’هƒچمپ‘م‚Œمپ°م€پ逆مپ«مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ‹م‚‰مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ«ه‚µه‹™ن¸چه±¥è،Œم‚„ن¸چو³•è،Œç‚؛مپ«هں؛مپ¥مپڈوگچه®³è³ ه„ںè«‹و±‚م‚’è،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ—مپ¾مپ†هڈ¯èƒ½و€§م‚‚مپ‚م‚‹مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ن؛‹ه¾Œمپ®ن»•و§که¤‰و›´مپ®مƒھم‚¯م‚¨م‚¹مƒˆمپ¯مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«è§£مپ•م‚Œم‚‹مپ®مپ‹

مپ¾مپںم€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپŒمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ¨مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ®ه…±هگŒن½œو¥مپ§مپ‚م‚‹ç‚¹م‚’ه‰چوڈگمپ¨مپ™م‚Œمپ°م€پمپ“مپ“مپ‹م‚‰مپ•م‚‰مپ«ç™؛ه±•çڑ„مپھè°è«–مپ¸مپ¨è©±مپ¯é€²م‚“مپ§مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚مپم‚Œمپ¯م€پم€Œمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒن؛‹ه¾Œçڑ„مپ«م€پو©ں能مپ®è؟½هٹ م‚„ن؟®و£م‚’ن¾é ¼مپ—م€پمپم‚Œمپ«م‚ˆمپ£مپ¦ç´چوœںمپ®م‚¯مƒھم‚¢مپŒه›°é›£مپ¨مپھمپ£مپںم‚ˆمپ†مپھه ´هگˆمپ¯م€پمپ¯مپںمپ—مپ¦èھ°مپ®è²¬ن»»مپ«مپھم‚‹مپ®مپ‹م€چمپ¨مپ„مپ£مپںه•ڈé،Œمپ§مپ™م€‚
م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ¯ن¸€èˆ¬çڑ„مپ«م€پè¦پن»¶ه®ڑ義مپ«ه§‹مپ¾م‚ٹم€پهں؛وœ¬è¨è¨ˆمƒ»è©³ç´°è¨è¨ˆمƒ»è£½é€ (مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ ه®ں装)مƒ»مƒ†م‚¹مƒˆمپ¨مپ„مپ£مپںé †ه؛ڈمپ§م€پو¥µهٹ›و‰‹وˆ»م‚ٹمپŒèµ·مپچم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«é€²م‚پمپ¦مپ„مپڈمپ“مپ¨م‚’ç›®وŒ‡مپ™م‚‚مپ®مپ§مپ™ï¼ˆن¸€èˆ¬çڑ„مپ«م‚¦م‚©مƒ¼م‚؟مƒ¼مƒ•م‚©مƒ¼مƒ«مƒ¢مƒ‡مƒ«مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹ï¼‰م€‚مپ—مپ‹مپ—مپھمپ«مپ‹مپ—م‚‰مپ®ن؛‹وƒ…مپ«م‚ˆم‚ٹم€په‰چه·¥ç¨‹مپ«ن¸چه‚™مپŒمپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپŒç™؛è¦ڑمپ™م‚‹مپ¨م€پمپھمپ«مپ‹مپ¨ه·¥ç¨‹مپ«و‰‹وˆ»م‚ٹمپŒç™؛ç”ںمپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚‚م€پçڈ¾ه®ںمپ«مپںمپ³مپںمپ³èµ·مپچم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚
مپ“مپ†مپ—مپںن؛‹و،ˆمپ«مپٹمپ„مپ¦م€پç´چوœںمپ«é–“مپ«هگˆم‚ڈمپھمپ‹مپ£مپںه ´هگˆمپ¯مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«è€ƒمپˆم‚‹مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚éپژهژ»مپ®هˆ¤ن¾‹م‚’èھمپ؟解مپڈمپ«م€پè؟½هٹ ن½œو¥مپŒç™؛ç”ںمپ—مپںم‚؟م‚¤مƒںمƒ³م‚°مپ«م‚ˆمپ£مپ¦çµگè«–مپ«ه·®ç•°مپŒمپ‚م‚‹م‚‚مپ®مپ¨è¦‹هڈ—مپ‘م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
è؟½هٹ ن½œو¥مپŒه¤–部è¨è¨ˆç‰مپ®ن»•و§کمپ®وکژç¢؛هŒ–م‚ˆم‚ٹه‰چمپ§مپ‚مپ£مپںه ´هگˆ
ه‰چوژ²مپ®هˆ¤ن¾‹مپ¯م€پهں؛وœ¬è¨è¨ˆن¸ï¼ˆمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ ه®ں装و®µéڑژم‚ˆم‚ٹم‚‚ه‰چ)مپ«مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ‹م‚‰هڈ—مپ‘مپںè؟½هٹ é–‹ç™؛مپ®ن¾é ¼مپŒمپ‚مپ£مپں点مپ«مپ¤مپچم€پمپمپ†مپ—مپںè¦پوœ›م‚’مپ‚مپ’م‚‹مپ“مپ¨è‡ھن½“مپ¯م€پمپ¨مپڈمپ«هچ”هٹ›ç¾©ه‹™éپ•هڈچمپ«مپ‚مپںم‚‹م‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپھمپ„و—¨م‚‚هگŒو™‚مپ«ç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ«ه¯¾مپ—,هں؛وœ¬è¨è¨ˆن½œو¥ن¸مپ«و§‹ç¯‰مپ™م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ«é–¢مپ™م‚‹و§کم€…مپھè¦پو±‚م‚’مپ™م‚‹مپ®مپ¯ï¼Œوœ¬ن»¶مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ه·¥ç¨‹مپ§مپ¯ه½“然مپ®مپ“مپ¨مپ§مپ‚م‚ٹ,مپ—مپ‹م‚‚,ه°‚é–€çڑ„çں¥èکمپ®مپھمپ„هژںه‘ٹمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ«مپٹمپ„مپ¦ï¼Œه½“該è¦پو±‚مپŒè؟½هٹ مپ®ه§”託و–™م‚„ç´چه…¥وœںé™گمپ®ه»¶وœںç‰م‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹ï¼Œن½œو¥ه·¥ç¨‹مپ«و”¯éڑœم‚’م‚‚مپںم‚‰مپ™م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹مپھمپ©م‚’,çڑ„ç¢؛مپ«هˆ¤و–مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¯ه›°é›£مپ§مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپ‹م‚‰ï¼Œهژںه‘ٹمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ«مپٹمپ„مپ¦ï¼Œè؟½هٹ مپ®ه§”託و–™م‚„ç´چه…¥وœںé™گمپ®ه»¶وœںç‰م‚’م‚‚مپںم‚‰مپ™è¦پو±‚م‚’è‡ھهˆ¶مپ™مپ¹مپچمپ§مپ‚مپ£مپںمپھمپ©مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚‚مپ§مپچمپھمپ„م€‚م‚€مپ—م‚چ,هژںه‘ٹمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒè؟½هٹ مپ®ه§”託و–™م‚„ç´چه…¥وœںé™گمپ®ه»¶وœںç‰م‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ™م‚‹è¦پو±‚م‚’مپ—مپںمپ®مپ§مپ‚م‚Œمپ°ï¼Œمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچمƒ¼م‚¸مƒ،مƒ³مƒˆç¾©ه‹™م‚’è² مپ†è¢«ه‘ٹمپ«مپٹمپ„مپ¦ï¼Œهژںه‘ٹمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ«مپمپ®و—¨ن¼مپˆمپ¦ï¼Œè¦پو±‚مپ®و’¤ه›م‚„ç´چه…¥وœںé™گمپ®ه»¶وœںç‰مپ«é–¢مپ™م‚‹هچ”è°م‚’و±‚م‚پم‚‹مپھمپ©مپ—,開ç™؛ن½œو¥مپ«و”¯éڑœمپŒç”ںمپکمپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«مپ™مپ¹مپچمپ§مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚
و±ن؛¬هœ°è£په¹³وˆگ16ه¹´ï¼“وœˆï¼‘ï¼گو—¥هˆ¤و±؛
ه½“該هˆ¤و±؛مپ§مپ¯م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ«م‚‚ن¸€ه®ڑمپ®هچ”هٹ›ç¾©ه‹™مپŒمپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚’肯ه®ڑمپ™م‚‹مپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€پو±؛مپ—مپ¦مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼è‡ھè؛«مپ¯م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ه°‚é–€ه®¶مپ§مپ¯مپھمپ„点م‚’و–ںé…Œمپ™مپ¹مپچو—¨مپŒهˆ¤ç¤؛مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚مپ™مپھم‚ڈمپ،م€پç™؛و³¨مپ™م‚‹مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ¯م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ه°‚é–€ه®¶مپ§م‚‚مپھمپ„ن»¥ن¸ٹم€پé–‹ç™؛مپ™م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ه†…ه®¹مپŒوکژç¢؛مپ«مپھم‚‹مپ¾مپ§مپ®وœںé–“مپ¯م€پ(ه ´هگˆمپ«م‚ˆمپ£مپںم‚‰ç™؛و³¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ•مپˆو…£م‚Œمپ¦مپٹم‚‰مپڑ)ه°ڈه‡؛مپ—مپ«مƒگمƒ©مƒگمƒ©مپ¨و³¨و–‡م‚’مپ¤مپ‘مپ¦مپڈم‚‹مپ“مپ¨مپ مپ£مپ¦مپ‚مپ£مپ¦مپٹمپ‹مپ—مپڈمپھمپ„مپ—م€پمپ¾مپ—مپ¦مپمپ®و³¨و–‡ه†…ه®¹مپŒç´چه…¥وœںé™گمپھمپ©مپ®è¦‹ç›´مپ—م‚’è¦پمپ™م‚‹ه ´هگˆمپ«م€Œمپمپ®مپ“مپ¨مپ«è‡ھهٹ›مپ§و°—مپŒمپ¤مپڈمپ¹مپچم€چمپھمپ©مپ¨مپ„مپ†مپ®مپ¯é…·مپ مپ¨مپ„مپ†è©±مپ مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
م‚‚مپ£مپ¨م‚‚م€پمپ“مپ“مپ§مپ®مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ®هپ´مپ«èھ²مپ›م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ç¾©ه‹™مپ¨مپ¯م€پمپ¤مپ¾م‚‹مپ¨مپ“م‚چç´چوœںمپ®ه»¶وœںç‰م‚’è¦پوœ›مپ—مپںم‚ٹ(م‚‚مپ—مپڈمپ¯م€پç´چوœںم‚’ه‹•مپ‹مپ›مپھمپ„مپھم‚‰م€پè؟½هٹ مپ®è¦پو±‚مپمپ®م‚‚مپ®م‚’هڈ–م‚ٹن¸‹مپ’م‚‹م‚ˆمپ†مپ«وڈگو،ˆمپ—مپںم‚ٹ)مپ¨مپ„مپ£مپںم‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپ®هٹھهٹ›م‚’وŒ‡مپ™م‚‚مپ®مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®è¦پو±‚م‚’مپ™مپ¹مپ¦هڈ—مپ‘ه…¥م‚Œمپںمپ†مپˆمپ§م€په½“هˆمپ®وœںو—¥é€ڑم‚ٹمپ«ç´چه“پمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¾مپ§مپ™مپ¹مپ¦ç¾©ه‹™مپ¨مپ—مپ¦هگ«م‚“مپ§م‚‹مپ¨مپ„مپ†و„ڈه‘³مپ§مپ¯مپھمپ„مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œم‚‹مپ®مپ§م€پمپ“مپ®ç‚¹مپ«مپ¯و³¨و„ڈمپŒه؟…è¦پمپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
è؟½هٹ ن½œو¥مپŒè£½é€ م‚„مƒ†م‚¹مƒˆه·¥ç¨‹مپ®ن»•و§کç¢؛ه®ڑم‚ˆم‚ٹم‚‚ه¾Œمپ§مپ‚مپ£مپںه ´هگˆ
ن¸ٹè¨کمپ®هˆ¤و±؛مپ®ه†…ه®¹م‚’è£ڈè؟”مپ›مپ°م€پن»•و§کم‚’مپ™مپ§مپ«ç¢؛ه®ڑمپ—終مپˆمپںه ´هگˆمپ®è؟½هٹ é–‹ç™؛مپ§مپ‚م‚Œمپ°مپ©م‚“مپھçµگè«–مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپںمپ‹م‚‚هگŒو™‚مپ«مپ‚م‚‹ç¨‹ه؛¦ن؛ˆو¸¬مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپمپ®ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پمپ“مپ†مپ—مپںè¦پو±‚مپ¯é€ڑم‚ٹمپ«مپڈمپڈمپھم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚مپںمپ—مپ‹مپ«م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ¨مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ§م€پé–‹ç™؛و¥ه‹™مپ«ه¯¾مپ™م‚‹çگ†è§£ه؛¦مپŒه¤§مپچمپڈé–‹مپچمپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†ç‚¹مپ¯م€پن»•و§کç¢؛ه®ڑمپ®ه‰چمپ م‚چمپ†مپŒه¾Œمپ م‚چمپ†مپŒه¤‰م‚ڈم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚
مپ—مپ‹مپ—م€پن»•و§کمپŒç¢؛ه®ڑمپ—مپںه¾Œمپ«و³¨و–‡ه†…ه®¹م‚’ه¤‰مپˆمپںم‚ٹè؟½هٹ مپ—مپںم‚ٹمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¯م€پن½œو¥مپ®م‚„م‚ٹç›´مپ—م‚’ه¼·مپ„م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒé«کمپ„م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚مپ“مپ†مپ—مپںه ´هگˆمپ«مپ¾مپ§ç™؛ç”ںمپ—مپںç´چوœںéپ…ه»¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پم€Œمپٹه®¢مپ•م‚“مپھمپ®مپ مپ‹م‚‰مپ‚م‚Œمپ“م‚Œè¦پوœ›م‚’مپ‚مپ’م‚‹مپ®مپ¯ه½“然م€چمپ¨و“پè·مپ™م‚‹مپ®مپ¯è‹¦مپ—مپ„ه ´هگˆمپŒه¤ڑمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚مپ•م‚‰مپ«مپ¯م€په¤ڑمپڈمپ®ن»•و§که¤‰و›´م‚„و©ں能è؟½هٹ مپŒن؛‹ه¾Œمپ§ç™؛ç”ںمپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ£مپںن؛‹و…‹مپ¯م€پمپم‚‚مپم‚‚ن؛‹ه‰چمپ«مپ™مپ§مپ«ه®Œن؛†مپ—مپ¦مپ„مپںمپ¯مپڑمپ®هں؛وœ¬è¨è¨ˆç‰مپ®ن¸ٹوµپه·¥ç¨‹مپ§م‚‚مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ®هچ”هٹ›ç¾©ه‹™éپ•هڈچمپŒمپ‚مپ£مپںمپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ‹مپ¨مپ„مپ†ç–‘ه•ڈم‚’م‚‚ç”ںمپکمپ•مپ›م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚
مپ“مپ†مپ—مپں点مپ‹م‚‰م‚‚م€پن»•و§کمپŒن¸€ه؛¦ç¢؛ه®ڑمپ—مپںه¾Œمپ«è،Œمپ£مپںن»•و§که¤‰و›´مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پمپم‚ŒمپŒهژںه› مپ®ç´چوœںéپ…ه»¶م‚’مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ®è²¬ن»»مپ¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¯çڈ¾ه®ںçڑ„مپ§مپ¯مپھمپ„مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚ه‰چوژ²مپ®هˆ¤و±؛و–‡مپ‹م‚‰مپ¯م€پمپمپ†مپ„مپ£مپںو„ڈه‘³هگˆمپ„م‚‚هگŒو™‚مپ«èھمپ؟هڈ–م‚‹مپ®مپŒه¦¥ه½“مپ¨مپ„مپ£مپںمپ¨مپ“م‚چمپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ¾مپںم€پمپ“مپ†مپ—مپںهˆ¤و–مپ¯م€په¥‘ç´„و›¸مپ مپ‘مپ§مپ¯مپھمپڈم€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®é€²وچ—مپ«هگˆم‚ڈمپ›مپںè°ن؛‹éŒ²مپھمپ©م‚‚証و‹ مپ¨مپ—مپ¦è،Œم‚ڈم‚Œم‚‹ه‚¾هگ‘مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚è°ن؛‹éŒ²مپ«é–¢مپ—مپ¦مپ¯ن¸‹è¨کè¨کن؛‹مپ«مپ¦è©³ç´°مپ«è§£èھ¬مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
関連è¨کن؛‹ï¼ڑو³•ه¾‹çڑ„観点مپ‹م‚‰مپ؟مپںم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ«مپٹمپ‘م‚‹è°ن؛‹éŒ²مپ®و®‹مپ—و–¹مپ¨مپ¯
مپ¾مپ¨م‚پï¼ڑè¦پن»¶ه®ڑ義مپŒمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®هپ´مپ®مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚’ه؟کم‚Œمپھمپ„مپ“مپ¨مپŒه¤§هˆ‡
è¦پن»¶ه®ڑ義مپ¯مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ®è…•مپ®è¦‹مپ›و‰€مپ§مپ‚م‚‹هڈچé¢م€پمپم‚‚مپم‚‚مپ¯مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®هپ´مپ®و¥ه‹™مپ§مپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚’و„ڈèکمپ—مپ¦مپٹمپڈمپ¹مپچمپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚مپم‚ŒمپŒè‡ھ社مپ§ç”¨مپ„م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ§مپ‚م‚‹ن»¥ن¸ٹم€پمپںمپ¨مپˆه¤–部مپ®ه°‚é–€ه®¶مپ®هٹ›م‚’ه€ںم‚ٹمپ¦ن½œم‚ٹن¸ٹمپ’م‚‹مپ®مپ مپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€په‰چوڈگمپ¨مپ—مپ¦è‡ھ社مپ®م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹مپŒهڈٹم‚“مپ§مپ„مپ¦مپ—مپ‹م‚‹مپ¹مپچé کهںںمپ§مپ‚م‚‹مپ¨و³•ه¾‹ن¸ٹمپ¯è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپŒé–‹ç™؛ه·¥ç¨‹مپ«هچ”هٹ›çڑ„مپ§مپھمپ„ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پمپںمپ¨مپˆمƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپŒç‚ژن¸ٹمپ—م‚ˆمپ†مپ¨م‚‚م€پè£پهˆ¤و‰€مپ¯مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ«م‚‚هژ³مپ—مپ„見解م‚’ç¤؛مپ—مپ¦مپڈم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒه¤§مپ„مپ«مپ‚م‚‹مپ®مپ مپ¨مپ„مپ†ç‚¹م‚’م€پمپ¾مپڑمپ¯èھچèکمپ—مپ¦مپٹمپڈمپ¹مپچمپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
م‚«مƒ†م‚´مƒھمƒ¼: ITمƒ»مƒ™مƒ³مƒپمƒ£مƒ¼مپ®ن¼پو¥و³•ه‹™