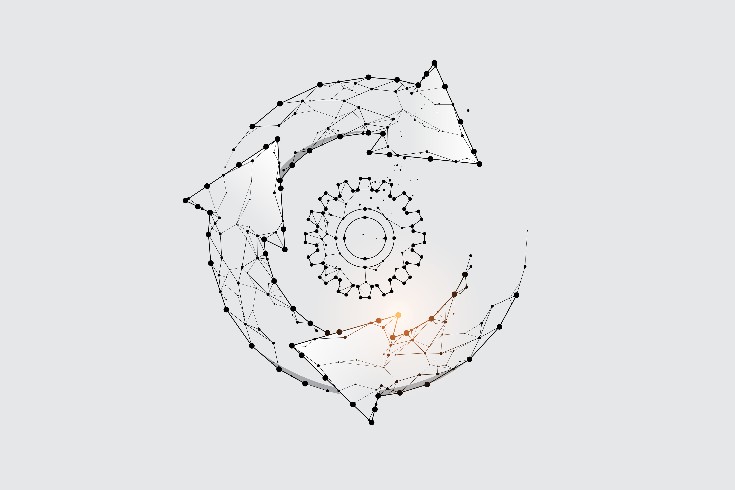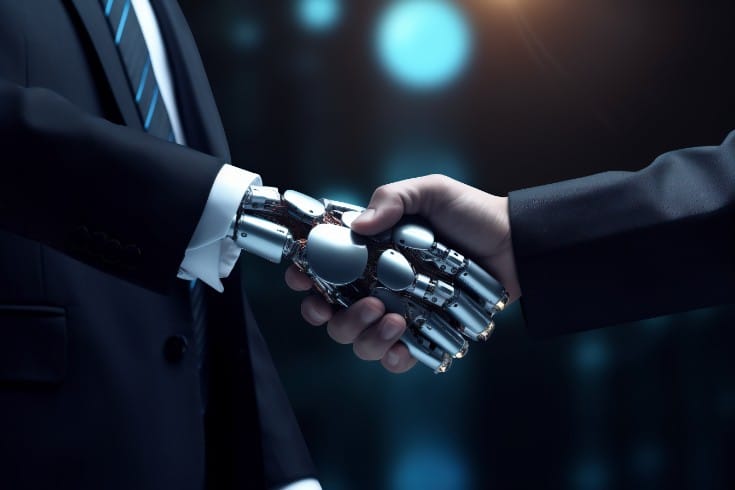„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āę„Āä„ĀĎ„ā茕ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„ĀģśĖĻś≥ē„Ā®„ĀĮ

„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀĮ„ÄĀťē∑„Āć„Āę„āŹ„Āü„āč„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Āß„Āā„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģťÄ≤Ť°Ć„ĀģťÄĒšł≠„Āß„ÄĆÁāéšłä„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüšļčśÖč„Āę„Ā™„āč„Āď„Ā®„āāŚĹďÁĄ∂śÉ≥Śģö„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āó„Ā¶„ÄĀ„ĀĄ„Ā§„āā„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Ā®„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆś≠©Ť™Ņ„ā팟ą„āŹ„Āõ„Ā¶„āĄ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀĎ„āč„Ā™„āČ„Ā®„āā„Āč„ĀŹ„ÄĀťÄĒšł≠„Āߌ•ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„Ā®„ĀĄ„ĀÜśČčśģĶ„ā휧úŤ®é„Āô„āčšļčśÖč„āāśÉ≥Śģö„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„ĀĻ„Āć„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„Āģ„ÄĆŤß£ťô§„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜś≥ēŚĺčšłä„Āģ„ā™„Éó„ā∑„Éß„É≥„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Ā®„ĀģťĖĘťÄ£„Āßťá捶Ā„Ā®„Ā™„āčÁāĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ťß£Ť™¨„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āć„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Ā®Ťß£ťô§„ĀģťĖĘšŅā„Ā®„ĀĮ
śįĎś≥ēšłä„ĀģŤß£ťô§„Ā®„ĀĮ„Ā™„Āę„Āč
śĒĻś≠£śįĎś≥ē„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„Āģ„ÄĆŤß£ťô§„Äć„ĀęťĖĘ„Āô„ā蚳蹨ÁöĄ„Ā™Ť¶ŹŚģö„ĀĮ„ÄĀÔľēÔľĒÔľźśĚ°„Āč„āČÔľēÔľĒÔľėśĚ°„Āĺ„Āß„ĀģśĚ°śĖá„Āߌģö„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚ•ĎÁīĄ„āíŤß£ťô§„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀšłÄŚļ¶Á∑†ÁĶź„Āē„āĆ„ĀüŚ•ĎÁīĄ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚäĻśěú„āíŚĺĆ„Āč„āČś∂ąśĽÖ„Āē„Āõ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Ā®„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Ā®„ĀĄ„ĀÜťĖĘšŅā„Āß„ĀĄ„ĀÜ„Ā™„āČ„Āį„ÄĀťÄöŚłł„ÄĀ„Ā≤„Ā®„Āü„Ā≥Ś•ĎÁīĄ„ĀĆÁ∑†ÁĶź„Āē„āĆ„āĆ„Āį„ÄĀ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Āę„āā„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„āíťĖčÁôļ„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆŤ™≤„Āõ„āČ„āĆ„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āę„āāŚ†ĪťÖ¨„ĀģśĒĮśČē„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁĺ©Śčô„ĀĆŤ™≤„Āõ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āó„Ā¶„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„āíŤ£ŹŤŅĒ„Āó„Āü„āā„Āģ„ĀĆ„ÄĀšł°ŤÄÖ„Āģ„ÄĆś®©Śą©„Äć„Ā®„āā„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„āā„Āó„Āď„āĆ„ĀĆŤß£ťô§„Āē„āĆ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āĆ„Āį„ÄĀšł°ŤÄÖ„ĀĆŤ≤†„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀüÁĺ©Śčô„ÉĽśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āüś®©Śą©„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀĆÁ∑†ÁĶź„Āē„āĆ„āčŚČć„ĀģÁä∂śÖč„ĀęśąĽ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀ„āā„Āó„Āĺ„Ā†ŚĪ•Ť°Ć„Āē„āĆ„Ā¶„Ā™„ĀĄťÉ®ŚąÜ„ĀģŚāĶŚčô„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀŚĪ•Ť°Ć„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆ„Ā™„ĀŹ„Ā™„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„āā„Ā°„āć„āď„Āģ„Āď„Ā®„ÄĀŚ•ĎÁīĄÁ∑†ÁĶźŚČć„ĀģÁä∂śÖč„āíŚüļśļĖ„Āę„Āó„Ā¶„ÄĀÁõłšļí„ĀęŚÖÉ„Ā©„Āä„āä„ĀģÁä∂śÖč„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹÁĺ©Śčô„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĆ„ÄĆŚéüÁä∂ŚõěŚĺ©Áĺ©Śčô„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā
„Ā™„Āä„ÄĀ„āā„ĀóŚźĆśôā„Āę„ÄĀśźćŚģ≥„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüšļčśÉÖ„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Āß„Āā„āĆ„Āį„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮŚą•ťÄĒśźćŚģ≥Ť≥†ŚĄü„ā퍰ƄĀÜ„Āď„Ā®„āāŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Äā
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļŚģüŚčô„Ā®Ťß£ťô§„Āģ„Āč„Āč„āŹ„āä
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„āí„ĀĮ„Āė„āĀ„Ā®„Āô„āč„Éď„āł„Éć„āĻ„Āĺ„āŹ„āä„Āģś≥ēŚĺčŚģüŚčô„Āꝶīśüď„ĀŅ„Āģ„Āā„āčšļļ„Āč„āČ„ĀŅ„āĆ„Āį„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„Āģ„ÄĆŤß£ťô§„Äć„Ā®„ĀĄ„Āą„Āį„ÄĀ„Āĺ„ĀöťÄ£śÉ≥„Āē„āĆ„āč„Āģ„ĀĮŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„Āģ„ĀĽ„ĀÜ„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀś≥ēŚĺčšłä„ĀĮ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„ĀģśĖ፥ą„Āęťôź„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀś†Ļśč†„Ā®„Ā™„āčśĚ°śĖá„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤß£ťô§„ĀģŚéüŚõ†„ĀĒ„Ā®„ĀęšļĆ„Ā§„Āģ„ÉĎ„āŅ„Éľ„É≥„Āꌧߌą•„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
ŚāĶŚčôšłćŚĪ•Ť°ĆÔľąŚĪ•Ť°ĆťĀÖśĽěԾȄāíÁźÜÁĒĪ„Ā®„Āô„ā茆īŚźą
ÔľąšĺčԾȄÉô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆŚĹĚÁīĄśĚü„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀüÁīćśúü„āíŤ∂ÖťĀé„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āę„āā„Āč„Āč„āŹ„āČ„Āö„ÄĀÁīćŚďĀ„ĀęŚŅú„Āė„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„Ā™„Ā©
śįĎś≥ē„ÄÄÁ¨¨šļĒÁôĺŚõõŚćĀšłÄśĚ°„ÄÄŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģšłÄśĖĻ„ĀĆ„ĀĚ„ĀģŚāĶŚčô„āíŚĪ•Ť°Ć„Āó„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀÁõłśČčśĖĻ„ĀĆÁõłŚĹď„ĀģśúüťĖď„āíŚģö„āĀ„Ā¶„ĀĚ„ĀģŚĪ•Ť°Ć„ĀģŚā¨ŚĎä„āí„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśúüťĖďŚÜÖ„ĀęŚĪ•Ť°Ć„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āć„ĀĮ„ÄĀÁõłśČčśĖĻ„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„āí„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Äā
ŤęčŤ≤†Ś•ĎÁīĄŚěč„Āģ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ÄĆŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģšłÄśĖĻ„Äć„Āß„Āā„āč„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆŤ≤†„ĀÜ„ÄĆŚāĶŚčô„Äć„Ā®„ĀĮ„ÄĀŤ¶ĀšĽ∂ŚģöÁĺ©ťÄö„āä„Āģ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„āíŚģĆśąź„Āē„Āõ„Ā¶ÁīćŚďĀ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀÁīćśúü„āíŚĺíťĀé„Āó„Āü„Āę„āā„Āč„Āč„āŹ„āČ„Āö„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆÁīćŚďĀ„ā퍰ƄāŹ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„Ā®„ĀĮ„ÄĀŤ®Ä„ĀĄśŹõ„Āą„āĆ„Āį„ÄĀÁīćśúü„Āĺ„Āß„Āę„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆšĽēšļč„āíŚģĆśąź„Āē„Āõ„Ā™„Āč„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„Āß„Āô„Äā„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆšĽēšļč„ĀģŚģĆśąź„Äć„Ā®„ĀĮ„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„ĀģŚ†īťĚĘ„Āß„ĀĮ„ÄĀŚÖ∑šĹďÁöĄ„Āę„ĀĮ„Ā©„ĀÜ„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Āč„Äā„Āď„ĀģÁāĻ„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮšłčŤ®ėŤ®ėšļč„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Ť©≥Áīį„ĀęŤß£Ť™¨„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ÁĎēÁĖĶśčÖšŅĚŤ≤¨šĽĽ„āíÁźÜÁĒĪ„Ā®„Āô„ā茆īŚźą
ÔľąšĺčԾȄÉô„É≥„ÉÄ„Éľ„Āč„āČÁīćŚďĀ„Āē„āĆ„Āü„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éź„āį„āĄ„Éá„Éľ„āŅ„ĀģšłćśēīŚźą„ĀĆŚ§ö„ĀŹ„ÄĀŚĺĆ„Āč„āČŚģüÁĒ®„ĀęťĀ©„Āē„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆ„āŹ„Āč„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„Ā™„Ā©
śįĎś≥ē„ÄÄÁ¨¨ŚÖ≠Áô嚳ȌćĀšļĒśĚ°„ÄÄšĽēšļč„ĀģÁõģÁöĄÁČ©„ĀęÁĎēÁĖĶ„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀ„ĀꌕĎÁīĄ„āí„Āó„ĀüÁõģÁöĄ„āíťĀĒ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āć„ĀĮ„ÄĀś≥®śĖáŤÄÖ„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„āí„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀŚĽļÁČ©„ĀĚ„ĀģšĽĖ„ĀģŚúüŚúį„ĀģŚ∑•šĹúÁČ©„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„Āď„Āģťôź„āä„Āß„Ā™„ĀĄ„Äā
„Ā™„Āä„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ¶≥ÁāĻ„Āč„āČ„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„Āß„Āā„āĆ„Āį„ÄĀ„Éô„É≥„ÉÄ„ÉľŚĀī„Āč„āČŚ•ĎÁīĄŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„ĀĆ„Ā™„Āē„āĆ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ĀĚ„ĀÜ„Āā„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāťÄöŚłł„ĀĮ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āč„āČ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„Ā™„Āē„āĆ„āč„āĪ„Éľ„āĻ„āíśÉ≥Śģö„Āó„Ā¶„Āä„ĀĎ„Āį„āą„ĀĄ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
ÁĎēÁĖĶśčÖšŅĚŤ≤¨šĽĽ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšłčŤ®ėŚą•Ť®ėšļč„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Ť©≥Áīį„Āꍙ¨śėé„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
Ťß£ťô§ťÄöÁü•śõł„Ā®„ĀĚ„āĆ„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„āčś≥ēŚĺčŚēŹť°Ć

Ťß£ťô§ťÄöÁü•śõł„Ā®„ĀĮ„ÄĀÔľąťÄöŚłł„ĀĮ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āč„āČ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶ÔľČŚ•ĎÁīĄ„āíŤß£ťô§„Āô„āčśó®„ā횾̄Āą„āč„Āü„āĀ„ĀģśĖáśõł„āí„Āē„Āó„Āĺ„Āô„ÄāśĚ°śĖá„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„Āģ„āā„Āģ„ā팏āÁÖß„Āô„āč„Ā®„āą„ĀĄ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
śįĎś≥ē„ÄÄÁ¨¨šļĒÁôĺŚõõŚćĀšłÄśĚ°„ÄÄŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģšłÄśĖĻ„ĀĆ„ĀĚ„ĀģŚāĶŚčô„āíŚĪ•Ť°Ć„Āó„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀÁõłśČčśĖĻ„ĀĆÁõłŚĹď„ĀģśúüťĖď„āíŚģö„āĀ„Ā¶„ĀĚ„ĀģŚĪ•Ť°Ć„ĀģŚā¨ŚĎä„āí„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśúüťĖďŚÜÖ„ĀęŚĪ•Ť°Ć„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āć„ĀĮ„ÄĀÁõłśČčśĖĻ„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„āí„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Äā
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āę„Āč„Āč„āŹ„āč„ÉČ„ā≠„É•„É°„É≥„Éą„Ā®„Āó„Ā¶„ĀŅ„ĀüŚ†īŚźą„Āę„ĀĮ„ÄĀŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ĀģÁČĻŚĺī„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀģŚÜÜśĽĎ„Ā™ťÄ≤Ť°Ć„āíÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„āíÁĶāšļÜ„Āē„Āõ„āč„Āü„āĀ„Āģ„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„āíśĆô„Āí„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀÁõīśé•ÁöĄ„ĀꚳČģö„Āģś≥ēŚĺčšłä„ĀģŚäĻśěú„āí„āā„Āü„āČ„Āô„Āď„Ā®„āíśúüŚĺÖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčśĖáśõł„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„āāŚ§ß„Āć„Ā™ÁČĻŚĺī„Āß„Āô„Äā
„Āó„Āč„Āó„ÄĀŚČćśé≤„ĀģśĚ°śĖá„ĀģťÄö„āä„ÄĀŚ•ĎÁīĄśõł„Ā™„Ā©„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āä„ÄĀÔľąšłÄŚģö„ĀģśĚ°šĽ∂„Āē„Āąśēī„Āą„ĀįԾȚłÄśĖĻ„Āč„āČ„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Āģ„ĀŅ„Āߍ∂≥„āä„āč„āā„Āģ„Āß„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āč„āČ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀęŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ĀĆśŹźÁ§ļ„Āē„āĆ„ā茆īŚźą„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ā팏óť†ė„Āó„Āü„Éô„É≥„ÉÄ„ÉľŚĀī„ĀģśčÖŚĹďŤÄÖ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ā퍙≠„āď„Āß„āā„ÄĀ„Ā©„ĀÜ„Āó„Ā¶Ś•ĎÁīĄ„ĀĆŤß£ťô§„Āē„āĆ„Āü„Āč„ĀĆ„āŹ„Āč„āČ„Ā™„ĀĄ„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚēŹť°Ć„ĀĆŤĶ∑„Āć„āč„Āď„Ā®„ĀĆśÉ≥Śģö„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀĮŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„āíšĹú„ā茆īŚźą„ÄĀ„ĀĚ„Āď„Āę„ĀĮŤß£ťô§„ĀģÁźÜÁĒĪ„āí„Ā©„Āď„Āĺ„ĀߌÖ∑šĹďÁöĄ„ĀęśĆáśĎė„Āô„ĀĻ„Āć„Ā™„Āģ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Āč„Äā
Ťß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ĀęŤß£ťô§„ĀģŚéüŚõ†„ĀĮśõł„ĀĄ„Ā¶„Āä„ĀŹ„ĀĻ„Āć„Āč
„Āď„ĀģÁāĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮťĀéŚéĽ„ĀģŤ£ĀŚą§šĺčÁ≠Č„āí„ĀŅ„āč„Āę„ÄĀŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ĀęŤß£ťô§„ĀģŚéüŚõ†„āíśė鍮ė„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚŅÖ„Āö„Āó„āāŤß£ťô§„ā퍰ƄĀÜ„Āü„āĀ„ĀęŚŅÖť†ą„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā®ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšłčŤ®ė„ĀꌾēÁĒ®„Āô„āčŤ£ĀŚą§šĺč„ĀĮ„ÄĀÁīćŚďĀ„Āē„āĆ„Āü„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀęšłćŚÖ∑Śźą„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČś≥ēŚĺčŚēŹť°Ć„ĀęÁôļŚĪē„Āó„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜšļčś°ą„Āß„Āô„Äā„ɶ„Éľ„ā∂„ÉľŚĀī„Āč„āČŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„ā퍰ƄĀÜťöõ„ÄĀ„Ā©„Āď„Āĺ„ĀßšłćŚÖ∑Śźą„ĀģŚÜÖŚģĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ŚÖ∑šĹďÁöĄ„Āęśä䜏°„Āó„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āíŚÖ∑šĹďÁöĄ„ĀęśĆáśĎė„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Āč„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„Āď„Ā®„ĀĆŚēŹť°Ć„Ā®„Ā™„Ā£„ĀüÁāĻ„Āę„Ā§„Āć„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮšĽ•šłč„Āģ„āą„ĀÜ„Āꌹ§Á§ļ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
Ťß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚŅÖ„Āö„Āó„āāŤß£ťô§ŚéüŚõ†„āíÁ§ļ„ĀôŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀŤ§áśēį„ĀģŤß£ťô§ŚéüŚõ†„Āę„āą„āčŤß£ťô§„āíŚćėšłÄ„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Āģ„Āß„Āā„āä„ÄĀŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Āę„Āā„Āü„Ā£„Ā¶„Āā„āčÁźÜÁĒĪ„āíśé≤„Āí„Ā¶„āā„ÄĀÁČĻ„Āę„ĀĚ„āĆšĽ•Ś§Ė„ĀģÁźÜÁĒĪ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ĀĮŤß£ťô§„Āó„Ā™„ĀĄśó®śėé„āČ„Āč„Āę„Āô„āč„Ā™„Ā©ÁČĻśģĶ„ĀģšļčśÉÖ„Āģ„Ā™„ĀĄťôź„āä„ÄĀŚĹ≤śĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„ĀĮ„ÄĀŤß£ťô§ŚĹďśôāŚ≠ėŚú®„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀüŚÖ®„Ā¶„ĀģÁźÜÁĒĪ„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀ„Āä„āą„ĀĚŚ•ĎÁīĄ„ā횳ČąáÁĶāšļÜ„Āē„Āõ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Āß„Āā„āč„Ā®ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„āč„Äā
śĚĪšļ¨ŚúįŚą§ŚĻ≥śąźÔľĎÔľĖŚĻīÔľĎÔľíśúąÔľíÔľíśó•
„ÄĆŤ§áśēį„ĀģŤß£ťô§ŚéüŚõ†„āíŚćėšłÄ„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĆŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŤ¶čŤß£„Āß„Āô„Äā„Ā§„Āĺ„āä„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŚĹďšļčŤÄÖ„ĀęŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚ„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Ā茟¶„Āč„ĀĆťá捶Ā„Ā™„Āģ„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ©≥Áīį„Ā™ŚéüŚõ†„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶šļčÁīį„Āč„ĀęśĆáśĎė„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā
„Āô„Ā™„āŹ„Ā°„ÄĀÁīćŚďĀ„Āē„āĆ„Āü„Ā®„ĀĮ„ĀĄ„Āą„ÄĀśú™ŚģĆśąź„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜśČĪ„ĀĄ„āí„Āô„ĀĻ„Āć„Ā™„Āģ„Āč„ÄĀťá挧߄Ā™ś¨†ťô•„ĀĆ„Āā„āč„Āü„āĀÁĎēÁĖĶśčÖšŅĚŤ≤¨šĽĽ„ĀģŚēŹť°Ć„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜśČĪ„ĀĄ„āí„Āô„ĀĻ„Āć„Ā™„Āģ„Āč„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüÁāĻ„Āĺ„Āß„ĀĮ„ÄĀŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„ĀģśģĶťöé„Āß„ĀĮŚēŹť°Ć„Āę„Āó„Ā™„ĀŹ„Ā¶„āā„āą„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŚĺģŚ¶ô„Ā™ŚēŹť°Ć„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮšłÄśó¶šłćŚēŹ„Āę„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀŚÖą„ĀęŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„āí„Āó„Ā¶„Āä„ĀĎ„Āį„ÄĀšłá„ĀĆšłÄŚĺĆ„ĀꍮīŤ®ü„Āę„Ā™„Ā£„Āü„āą„ĀÜ„Ā™Ś†īŚźą„Āß„āā„ÄĀŚĺĆ„Āč„āČŚĪ•Ť°ĆťĀÖśĽě„ÉĽÁĎēÁĖĶśčÖšŅĚŤ≤¨šĽĽ„Ā©„Ā°„āČ„āíŤß£ťô§„Āģś†Ļśč†„Ā®„Āó„Ā¶„āāšļČ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā
- śú™ŚģĆśąź„Āģ„āā„Āģ„ĀĆÁīćŚďĀ„Āē„āĆ„Āü„ÉĽ„ÉĽ„ÉĽ‚ÜíŚāĶŚčôšłćŚĪ•Ť°Ć
- ťá挧߄Ā™ś¨†ťô•„Āģ„Āā„āč„āā„Āģ„ĀĆÁīćŚďĀ„Āē„āĆ„Āü„ÉĽ„ÉĽ„ÉĽ‚ÜíÁĎēÁĖĶśčÖšŅĚŤ≤¨šĽĽ
ŚéüŚõ†„ā퍩≥Áīį„ĀęÁČĻŚģö„Āõ„Āö„Ā®„āā„ÄĀŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„ĀĮŤß£ťô§„ĀģśĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Ā®„Āó„Ā¶śúČŚäĻ„Āß„Āô„Äā
„āā„Ā£„Ā®„āā„ÄĀŤß£ťô§ŚéüŚõ†„āíŚÖ∑šĹďÁöĄ„ĀęśĆáśĎė„Āó„Āü„ĀÜ„Āą„ĀßŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ā휏źÁ§ļ„Āô„āč„ĀĽ„ĀÜ„ĀĆ„ÄĀšłášłÄ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Ā®„ĀģťĖď„Āß„ā≥„Éü„É•„Éč„āĪ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„ĀģŤ°Ć„ĀćťĀē„ĀĄ„āĄŤ™ćŤ≠ė„ĀęťĹüťĹ¨„ĀĆ„Āā„āč„āą„ĀÜ„Ā™Ś†īŚźą„Āß„āā„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āíśėé„āČ„Āč„Āę„Āß„Āć„āč„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„É°„É™„ÉÉ„Éą„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ā팏óť†ė„Āô„āčÁõłśČčśĖĻ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚéüŚõ†„ĀęśÄĚ„ĀĄŚĹď„Āü„āä„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Āß„Āā„āĆ„Āį„ÄĀŚĺĆ„Āč„āČÁīõšļČ„Āę„āā„Ā§„āĆ„āčŚŅÉťÖć„āāŚįŹ„Āē„ĀŹ„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶ŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťôź„āäŤß£ťô§ŚéüŚõ†„āíśėéÁĘļ„ĀꍮėŤľČ„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„ĀĽ„ĀÜ„ĀĆ„āą„ĀĄ„Āď„Ā®„āāšļčŚģü„Āß„Āô„Äā
„ÄĆÁõłŚĹď„Ā™śúüťĖď„Äć„āíŚģö„āĀ„ĀüŚā¨ŚĎä„Ā®„ĀĮ„Ā©„Āģ„ĀŹ„āČ„ĀĄ„ĀčÔľü

„Āĺ„Āü„ÄĀ„āā„ĀÜšłÄ„Ā§ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„āčÁāĻ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮśįĎś≥ēÔľēÔľĒԾϜ̰„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĀ„ÄĆ‚ÄĚÁõłŚĹď„Ā™śúüťĖď‚ÄĚ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĆ„Ā©„Āģ„ĀŹ„āČ„ĀĄ„Āģťē∑„Āē„Āč„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚēŹť°Ć„Āß„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„Āď„ĀģÁāĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„Āā„Āĺ„āäÁ•ěÁĶĆŤ≥™„ĀęŤÄÉ„Āą„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā®śÄĚ„āŹ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Ā™„Āú„Ā™„āČ„ÄĀŚā¨ŚĎä„ā퍰ƄĀÜ„Āĺ„Āß„ĀģśúüťĖď„Āę„ÄĆÁõłŚĹď„Ā™śúüťĖď„āíŚģö„āĀ„Ā¶„Äć„ĀĄ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀŚā¨ŚĎä„Āč„āČÁõłŚĹďśúüťĖď„ĀĆÁĶĆťĀé„Āó„Ā¶„ĀĄ„āĆ„Āį„ÄĀÁĶźśěúÁöĄ„ĀꌕĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„ĀĮŚŹĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āč„Āč„āČ„Āß„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚā¨ŚĎä„Āĺ„Āß„ĀģśúüťĖď„ĀĆ„ÄĆÁõłŚĹď„Ā™śúüťĖď„Äć„Āß„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀÁĶźśěúÁöĄ„ĀęÁõłŚĹď„Ā™śúüťĖď„ĀĆÁĶĆťĀé„Āó„ĀüśģĶťöé„Āߌ•ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„ĀĮŚŹĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚą§šĺčś≥ēšłä„āāśėéÁĘļ„Āę„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„āČ„Āß„Āô„Äā
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Ā≤„Ā®„Āü„Ā≥ŚĪ•Ť°ĆťĀÖśĽě„āĄÁĎēÁĖĶśčÖšŅĚŤ≤¨šĽĽ„ĀĆŚēŹť°Ć„Ā®„Ā™„āč„āą„ĀÜ„Ā™„ÄĆÁāéšłä„Äćšļčś°ą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆÁõłŚĹď„Ā™śúüťĖď„Äć„āíŚģö„āĀ„Ā¶Śā¨ŚĎä„ā퍰ƄĀ£„Āü„Ā®„Āď„āć„Āß„ÄĀÁīćŚďĀ„āĄÁĎēÁĖĶšŅģŤ£ú„ĀĆŚģĆšļÜ„Āô„ā茆īŚźą„ĀĮŚ§ö„ĀŹ„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüÁāĻ„ā퍳Ź„Āĺ„Āą„Ā¶„āā„ÄĀŚģüŚčôšłä„ÄĀ„ÄĆÁõłŚĹď„Ā™śúüťĖď„Äć„āí„āĀ„Āź„Ā£„Ā¶ś∑ĪŚąĽ„Ā™šļČ„ĀĄ„ĀĆŤĶ∑„Āć„āč„Āď„Ā®„ĀĮŤÄÉ„Āą„Āę„ĀŹ„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ŚĪ•Ť°ĆťĀÖŚĽ∂„Ā®„Ā™„āčŚģöÁĺ©„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚą•Ť®ėšļč„Āę„Ā¶Ť™¨śėé„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
Ťß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ĀģťÄöÁü•„ĀģśĖĻś≥ē„ĀĮÔľü
„Āĺ„ĀüŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł„ĀĮ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™śĖĻś≥ē„ĀßťÄöÁü•„Āô„āč„Āģ„ĀĆ„āą„ĀĄ„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀÁĶźśěúÁöĄ„ĀęťÄöÁü•„ĀĆŚąįťĀĒ„Āô„āč„Āģ„Āß„Āā„āĆ„ĀįÔľą„Āē„āČ„ĀꍮĄĀą„Āį„ÄĀÁĘļŚģü„ĀꌹįťĀĒ„Āó„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆŚĺĆ„Āč„āČÁę荮ľ„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Ā™śĖĻś≥ē„Āß„Āā„āĆ„ĀįԾȄĀ©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™śĖĻś≥ē„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āāŚēŹť°Ć„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā
„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀ„Āā„Āĺ„āäśČčÁ∂ö„ĀćťĚĘ„ĀģŚēŹť°Ć„ĀßÁ•ěÁĶĆŤ≥™„Āę„Ā™„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āü„Āó„Āč„ĀęŚģüŚčôšłä„ĀĮ„ÄĀŚĺĆ„Āč„āČ„ÄĆŤ®Ä„Ā£„Āü„ÉĽŤ®Ä„āŹ„Ā™„ĀĄ„Äć„ĀģŚēŹť°Ć„Ā®„Ā™„āč„Āď„Ā®„āíťĀŅ„ĀĎ„āč„Āü„āĀ„Āę„ÄĀŚÜÖŚģĻŤ®ľśėéťÉĶšĺŅ„Ā™„Ā©„Āģ„āĄ„āäśĖĻ„ĀĆŚ•Ĺ„Āĺ„āĆ„āčŚā匟τĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀÁõłśČč„ĀꌹįťĀĒ„Āó„Āü„Āď„Ā®„ĀĆÁĘļŤ™ć„Āß„Āć„āč„Āģ„Āß„Āā„āĆ„Āį„ÄĀFAX„āĄťõĽŚ≠ź„É°„Éľ„Éę„Ā™„Ā©„ĀģÁį°šĺŅ„Ā™„āĄ„āäśĖĻ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āāŚēŹť°Ć„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āü„Ā†ÁĶźŚĪÄ„ÄĀŤ£ĀŚą§„Ā™„Ā©„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āó„Āĺ„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆÁõłśČčśĖĻ„ĀꌹįťĀĒ„Āó„Āü„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ā퍮ľśėé„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„Āď„ĀģŤ¶≥ÁāĻ„ĀߌÜÖŚģĻŤ®ľśėé„ĀĆŚģČŚÖ®„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĮŤ®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĖ፥ą„Āęś≤Ņ„Ā£„Ā¶„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťô§„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āā„Āģ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀģśēīÁźÜ„ā퍰ƄĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŤß£ťô§„ĀģŤ°Ć„ĀĄśĖĻ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚģüŚčô„Āģ„Éé„ā¶„ÉŹ„ā¶„ĀĮ„āā„Ā°„āć„āď„Āģ„Āď„Ā®„ÄĀ„Āā„āŹ„Āõ„Ā¶ś≥ēŚĺčÁöĄ„ĀęśúČŚäĻ„Ā™śĄŹśÄĚŤ°®Á§ļ„Āģ„āĄ„āäśĖĻ„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„āāŚźę„āĀ„Ā¶ÁźÜŤß£„Āß„Āć„āĆ„Āį„ÄĀŚŅúÁĒ®„ĀģŚäĻ„Āć„āĄ„Āô„ĀĄÁü•Ť≠ė„Ā®„Ā™„āč„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Āč„Äā
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô
„āŅ„āį: „ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļśźćŚģ≥Ť≥†ŚĄüŤęčśĪāÁāéšłäÁĎēÁĖĶŤß£ťô§ťÄöÁü•śõł