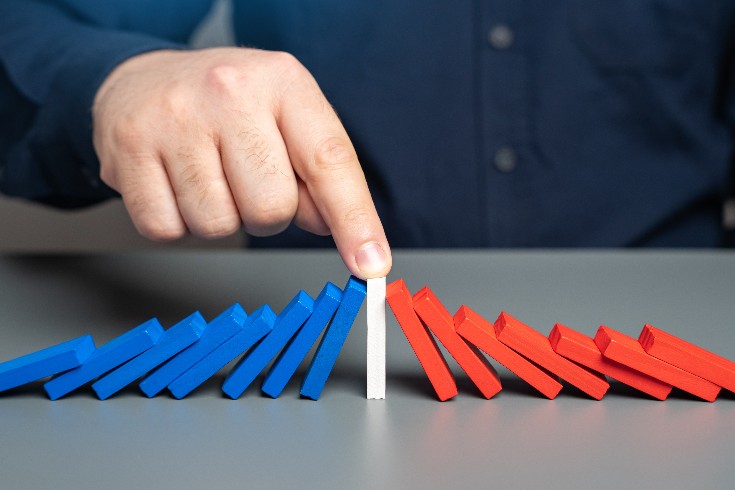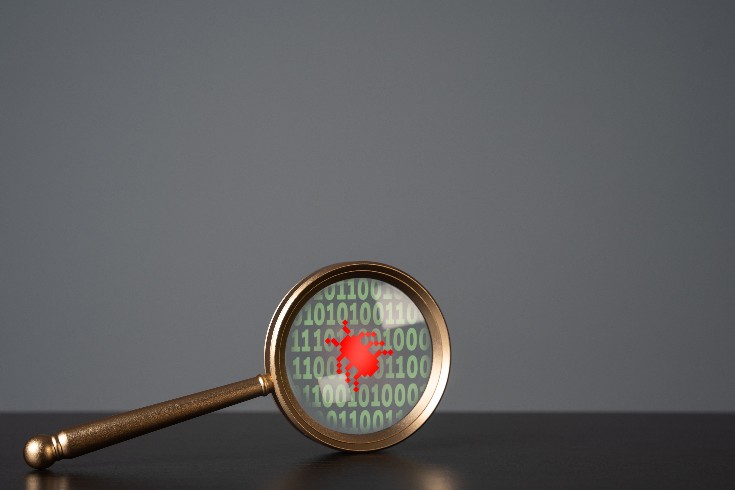гӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®д»•ж§ҳжӣёгҒ«гҒӘгҒ„ж©ҹиғҪгҒҜжі•еҫӢдёҠгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§е®ҹиЈ…гҒҷгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒӢ

дјҒжҘӯгҒ§з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢITгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’й–ӢзҷәгҒҷгӮӢгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҜеҺҹеүҮгҖҒдәҲгӮҒе®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҹд»•ж§ҳгҒ«жІҝгҒЈгҒҰдҪңгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—дёҖж–№гҒ§гҖҒгғҷгғігғҖгғјгҒҢгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰй–ӢзҷәжҘӯеӢҷгӮ’дёҖд»»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒд»•ж§ҳгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гӮ’ж©ҹжў°зҡ„гҒ«е®ҹиЈ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ гҒ‘гҒ§гӮҲгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ»гҒ©гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјеҒҙгҒ®жңҹеҫ…еәҰгҒҜдҪҺгҒҸгҒӘгҒ„гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢд»•ж§ҳжӣёгҒ«гҒҜиЁҳијүгҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒй–ӢзҷәгҒ®зӣ®зҡ„гҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰгҖҒе®ҹиЈ…гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮ’е®ҹиЈ…гҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгӮ’гҒ©гҒ“гҒҫгҒ§иІ гҒҶгҒ№гҒҚгҒӘгҒ®гҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
д»•ж§ҳгҒ«гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®е®ҹиЈ…гҒ«дјҙгҒҶжі•еҫӢе•ҸйЎҢ

гғҷгғігғҖгғјгҒ®жҘӯеӢҷгҒ«гҒҜиЈҒйҮҸгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢ
гӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒЁгҒ„гҒҶгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ«гҒҫгҒӨгӮҸгӮӢеҘ‘зҙ„гӮ„гҖҒгҒқгӮҢгҒ«д»ҳйҡҸгҒҷгӮӢзЁ®гҖ…гҒ®жі•еҫӢе•ҸйЎҢгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘзү№еҫҙгҒ«гҖҒд»•дәӢгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгғҷгғігғҖгғјгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘиЈҒйҮҸгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲзҫ©еӢҷгҒЁгҒҜ
гӮӮгҒЈгҒЁгӮӮгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒ„гҒҶгҖҢиЈҒйҮҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ й–Ӣзҷәе·ҘзЁӢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮгҒ„гҒҲгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҗ„е·ҘзЁӢгӮ’жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҖҒзҙ°гҒӢгҒ„гӮҝгӮ№гӮҜгҒёгҒ®жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гӮ’йҖІгӮҒгҒҹеҫҢгҒ«гҒҜгҖҒеҚҳзҙ”гҒӘдҪңжҘӯгҒ«иҝ‘гҒ„д»•дәӢгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒҜгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиӘІйЎҢгҒ®зҙ°еҲҶеҢ–гҒ®еүҚгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎдёҠжөҒе·ҘзЁӢгҒ®жҘӯеӢҷгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘиЈҒйҮҸгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒӘгҒ—гҒ«гҒҜжҘӯеӢҷгҒ®йҒӮиЎҢгҒҢеӣ°йӣЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдёҠжөҒе·ҘзЁӢгҒ»гҒ©еҘ‘зҙ„йЎһеһӢгҒЁгҒ—гҒҰжә–委任гҒ«гӮҲгҒҸйҰҙжҹ“гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„зҗҶз”ұгӮӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹзӮ№гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ§гҒ®и«ӢиІ еҘ‘зҙ„гҒЁжә–委任еҘ‘зҙ„гҒ®еҢәеҲҘгҒЁйҒ•гҒ„
иЈҒйҮҸгҒҜгҖҒеҺіж јгҒӘй–Ӣзҷәе·ҘзЁӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§зҷәжҸ®гҒҷгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’й–ӢзҷәгҒҷгӮӢгғҷгғігғҖгғјгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘиЈҒйҮҸгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҖҢгҒӘгҒ—еҙ©гҒ—гҖҚзҡ„гҒ«гӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲиҰҒжңӣгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҫҢгҒ®е·ҘзЁӢгҒ«з”ҡеӨ§гҒӘиў«е®ігӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒІгҒЁгҒӨгҒ®ITгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҖҒзҙ°гҒӢгҒ„йғЁе“ҒгҒ®йӣҶгҒҫгӮҠгҒ§жҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгӮҶгҒҲгҒ«гҖҒеӨ–иҰідёҠгӮҸгҒҡгҒӢгҒӘеӨүжӣҙгҒ«гҒҷгҒҺгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒй–ӢзҷәиҖ…еҒҙгҒӢгӮүгҒҝгҒҰеӨ§е№…гҒӘе·Ҙж•°гҒ®еӨүжӣҙгҒҢиҰҒгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®д»•ж§ҳеӨүжӣҙгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ«й–ўгҒ—гҖҒеӨүжӣҙзҠ¶жіҒгҒ®з®ЎзҗҶгҒ®д»•ж–№гӮ’жі•еҫӢзҡ„гҒӘиҰізӮ№гҒӢгӮүиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹиЁҳдәӢгҒ«гҒҜд»ҘдёӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ®иЁҳдәӢгҒҜеӨүжӣҙз®ЎзҗҶгҒ®д»•ж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҠҖиЎ“иҖ…гҒӢгӮүгҒҝгҒҰд»•ж§ҳгҒ®еӨүжӣҙгҒҢгҒ©гӮҢгҒ»гҒ©жҘӯеӢҷгҒ«еӨҡеӨ§гҒӘеҪұйҹҝгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮӮдҪөгҒӣгҒҰи«–гҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡжі•еҫӢзҡ„иҰізӮ№гҒӢгӮүгҒҝгҒҹгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӨүжӣҙз®ЎзҗҶгҒ®иЎҢгҒ„ж–№гҒЁгҒҜ
д»•ж§ҳгҒ«гҒЁгӮүгӮҸгӮҢгҒҡгҖҒе°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰгҒӘгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ«гҒӢ
гӮ·гӮ№гғҶгғ й–Ӣзҷәгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’еҶҶж»‘гҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒй–ӢзҷәгҒ®иҰҒ件гӮ’дәҲгӮҒе®ҡзҫ©гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«жІҝгҒЈгҒҰиЁҲз”»зҡ„гҒ«йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒдәӢеүҚгҒ«е®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҹиҰҒ件гҒ«жІҝгҒЈгҒҰгҖҒгҒҹгҒ иЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰеҚҒеҲҶгҒ«еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒӣгҒӘгҒ„е ҙйқўгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮёгғ¬гғігғһгҒ®гҒӘгҒӢгҖҒгҖҢд»•ж§ҳгҒ«зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒе®ҹиЈ…гҒҷгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒЁгҒҜгҒӘгҒ«гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒҢйЎ•еңЁеҢ–гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жі•еҫӢдёҠгҒ®зҫ©еӢҷгҒҜгҖҒд»•ж§ҳжӣёгӮ„еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®гҖҢи¶Јж—ЁгҖҚгҒ«жІҝгҒЈгҒҰжұәгҒҫгӮӢ
е®ҹиЈ…гҒҷгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒ®еҶ…е®№гҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲеҘ‘зҙ„жӣёгғ»д»•ж§ҳжӣёгҒ«иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгҒқгӮҢгӮүеҘ‘зҙ„жӣёгғ»д»•ж§ҳжӣёгҒ®иЁҳијүдәӢй …гҒ®гҖҢи¶Јж—ЁгҖҚгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҖҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹе‘ігӮ„ж„ҸеӣігӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҸ–гӮҠжұәгӮҒгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒӢгӮүжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ«гҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢиЈҒеҲӨдҫӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«иҰӢгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүе®ҹиЈ…зҫ©еӢҷгҒҢеҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹиЈҒеҲӨдҫӢгҖҖ
д»ҘдёӢгҒ«еј•з”ЁгҒҷгӮӢиЈҒеҲӨдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒгғҷгғігғҖгғјгҒҢй–ӢзҷәгҒ—гҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒӨгҒҚгҖҒд»®зЁјеғҚгҒҫгҒ§йҖІгӮ“гҒ гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘж©ҹиғҪгҒҢи¶ігӮҠгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁеҘ‘зҙ„гҒ®и§ЈйҷӨгӮ’жұӮгӮҒгҒҰдәүгҒ„гҒ«зҷәеұ•гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒЁдё»ејөгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҢгғҮгғјгӮҝгҒ®иҮӘеӢ•жӣҙж–°ж©ҹиғҪгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜжң¬д»¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дё»иҰҒгҒӘгӮ»гғјгғ«гӮ№гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгӮӢж—ЁгҒҢдё»ејөгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҒ“гҒ®е®ҹиЈ…зҫ©еӢҷгӮ’иӘҚгӮҒгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
дёҠиЁҳиӘҚе®ҡгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒжң¬д»¶еҘ‘зҙ„жӣёдёҰгҒігҒ«еҹәжң¬иЁӯиЁҲжӣёеҸҠгҒіи©ізҙ°иЁӯиЁҲжӣёгҒ«гҒҜгҖҒв‘ўж©ҹиғҪгҒҢжң¬д»¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й–ӢзҷәеҜҫиұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷиЁҳијүгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
еҺҹе‘ҠгҒҜгҖҒв‘ўж©ҹиғҪгҒҢиў«е‘ҠгҒ®еҺҹе‘ҠгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжң¬д»¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®дё»иҰҒгҒӘгӮ»гғјгғ«гӮ№гғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӘгҒ©гҒЁдё»ејөгҒ—гҖҒеҗҢж©ҹиғҪгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’еј·иӘҝгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дё»ејөгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®ж—ЁгҒҢжң¬д»¶еҘ‘зҙ„жӣёзӯүгҒ«жҳҺиЁҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҒеҗҢж©ҹиғҪгҒ®й–ӢзҷәгҒҢеҗҲж„ҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒҜиҖғгҒҲйӣЈгҒ„гҖӮ
жқұдә¬ең°еҲӨе№іжҲҗ21е№ҙ2жңҲ18ж—Ҙ
еҪ“и©ІеҲӨжұәгҒҜгҒҹгҒ—гҒӢгҒ«гӮ·гғігғ—гғ«гҒ«зөҗи«–гҒ гҒ‘гӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгҖҢиЁӯиЁҲжӣёгҒ«иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜдҪңгӮүгҒӘгҒҸгҒҰиүҜгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮҲгӮҠжӯЈзўәгҒ«гҒ„гҒҶгҒӘгӮүгҖҒиЁӯиЁҲжӣёгҒ«иЁҳијүгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҪўејҸзҡ„гҒӘдәӢе®ҹгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®иЁӯиЁҲжӣёгғ»еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®иЁҳијүгҒ®гҖҢи¶Јж—ЁгҖҚгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹеҲӨж–ӯгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҖҢиЁӯиЁҲжӣёгӮ„еҘ‘зҙ„жӣёгҒ«иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹзҗҶз”ұгӮ’иҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠгҒқгҒ®иЁҳијүгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢеҗҲж„ҸгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢеҰҘеҪ“гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮе®ҹиЈ…зҫ©еӢҷгҒҢиӮҜе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹиЈҒеҲӨдҫӢ
дёҖж–№гҖҒгҒҹгҒЁгҒҲеҘ‘зҙ„жӣёгӮ„д»•ж§ҳжӣёгҒ«иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒе®ҹиЈ…гҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒ№гҒҚгҒЁгҒ—гҒҹиЈҒеҲӨдҫӢгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ«еј•з”ЁгҒҷгӮӢиЈҒеҲӨдҫӢгҒҜгҖҒи–¬еүӨгҒ®жңҚз”ЁжӯҙгӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й–ӢзҷәгҒ«гҒӨгҒҚгҖҒж—ўеӯҳгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӢгӮүж–°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒёгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒ®з§»иЎҢгӮ’иЎҢгҒҲгҒҡгҖҒж–°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®жҙ»з”ЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҒ«гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјеҒҙгҒҢеҘ‘зҙ„гҒ®и§ЈйҷӨгӮ’иЎҢгҒӘгҒЈгҒҹдәӢжЎҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҷгғігғҖгғјеҒҙгҒҜгғҮгғјгӮҝ移иЎҢгҒҫгҒ§гҒҜжҘӯеӢҷзҜ„еӣІеӨ–гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰдәүгҒ„гҒ«зҷәеұ•гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж–°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й–ӢзҷәгҒ«гҒҜгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҖҒж—ўеӯҳгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®ж’Өе»ғгҒЁгҖҒгғҮгғјгӮҝгҒ®з§»иЎҢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдҪңжҘӯгӮ’дјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжҘӯеӢҷгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ„гҖҒгҒқгӮҢгҒ«д»ҳйҡҸгҒҷгӮӢжі•еҫӢе•ҸйЎҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®иЁҳдәӢгҒ§гӮӮи©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гӮ’иЎҢгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ§гҒ®ж—§гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӢгӮүгҒ®з§»иЎҢгҒ«дјҙгҒҶжі•еҫӢе•ҸйЎҢ
ж—ўеӯҳгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜж—ўгҒ«пј•дёҮдәәгӮ’и¶…гҒҲгӮӢжӮЈиҖ…гғҮгғјгӮҝгҒҢдҝқеӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҺҹе‘ҠгҒҜпјҢгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰдәӢеӢҷгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’еӣігҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒжӮЈиҖ…гғҮгғјгӮҝгӮ’ж—ўеӯҳгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӢгӮүжң¬д»¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«з§»иЎҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒи–¬еұҖгҒ§гҒ®иӘҝеүӨжҘӯеӢҷгҒ«ж”ҜйҡңгӮ’жқҘгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜжҳҺзҷҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҺҹе‘Ҡд»ЈиЎЁиҖ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҪ“然гҒ«гҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒжң¬д»¶еҘ‘зҙ„з· зөҗеүҚгҒ«гҖҒеҺҹе‘Ҡд»ЈиЎЁиҖ…гҒҢгҖҒиў«е‘Ҡд»ЈиЎЁиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғҮгғјгӮҝ移иЎҢгҒ®еҸҜеҗҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиіӘе•ҸгӮ’гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҜиў«е‘Ҡд»ЈиЎЁиҖ…гӮӮиҮӘиӘҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚпјҲдёӯз•ҘпјүгҖҒеҺҹе‘Ҡд»ЈиЎЁиҖ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒпј•дёҮдәәгӮ’и¶…гҒҲгӮӢжӮЈиҖ…гғҮгғјгӮҝгҒ«гҒӨгҒҚжүӢе…ҘеҠӣгӮ’гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰжң¬д»¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…ҘгӮ’жұәж–ӯгҒ—гҒҹгҒЁгҒҜеҲ°еә•иҖғгҒҲйӣЈгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҠиЁҳ(1)гӮӨгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҖҒиў«е‘ҠгҒҜгҖҒж—ўеӯҳгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®и–¬жӯҙгғҮгғјгӮҝгӮ’жң¬д»¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«з§»иЎҢгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’зҙҷгҒ«еҚ°еҲ·гҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’пј°пјӨпјҰгғ•гӮЎгӮӨгғ«гҒ«еҸ–гӮҠиҫјгӮҖгҒӘгҒ©гҒ®еҮҰзҗҶгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжң¬д»¶еҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгғҮгғјгӮҝ移иЎҢгҒҢеүҚжҸҗгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«гҖҒиў«е‘ҠгҒҢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжүӢй–“гҒ®гҒӢгҒӢгӮӢдҪңжҘӯгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒЁгҒҜеҲ°еә•иҖғгҒҲйӣЈгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жқұдә¬ең°еҲӨе№іжҲҗ22е№ҙ11жңҲ18ж—Ҙ
гҒ“гҒ“гҒ§гӮӮйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®зӣ®зҡ„гӮ„гҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ®иЁҳијүдәӢй …гҒ®гҖҢи¶Јж—ЁгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒ—гӮӮгғҮгғјгӮҝгҒ®з§»иЎҢгӮ’жҘӯеӢҷгҒ®зҜ„еӣІеӨ–гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§дёЎеҪ“дәӢиҖ…гҒҢеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹгҒЁгҒӘгӮҢгҒ°гҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгғ»гғҷгғігғҖгғјгҒЁгӮӮгҒ«дёҚиҮӘ然гҒӘж„ҸеӣігӮ’гӮӮгҒЈгҒҰеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢзӮ№гӮ’иЈҒеҲӨжүҖгӮ’жҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҜиҶЁеӨ§гҒӘйҮҸгҒ®жүӢдҪңжҘӯгӮ’еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгғҷгғігғҖгғјгӮӮд»ҘеҫҢгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®жҘӯеӢҷгҒ«ж”ҜйҡңгӮ’гҒҚгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гӮ’зҹҘгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ«иҮЁгӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰйқһеҗҲзҗҶгҒӘи©ұгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
дёЎеҲӨжұәгҒӢгӮүгӮҸгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒҜ
гғҮгғјгӮҝ移иЎҢгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгғ»д»•ж§ҳжӣёгҒ«иЁҳијүгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮе®ҹиЈ…гҒ®зҫ©еӢҷгҒҢиӮҜе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгғҮгғјгӮҝгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒз”»йқўдёҠгҒ®еӨ–иҰігҒ«гҒӮгӮүгӮҸгӮҢгҒӘгҒ„дәӢй …гҒ®и©ұгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮй–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеүҚж®өгҒ®гҖҢеҝ…й Ҳж©ҹиғҪгҒ®ж¬ иҗҪгҖҚгҒҜгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®з”»йқўгғ»еӨ–иҰігҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒ«гҒӮгӮүгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®зҙ дәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒд»•ж§ҳжӣёгҒ®иЁҳијүжјҸгӮҢгӮ’зҷәиҰӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҒ•гҒ»гҒ©еӣ°йӣЈгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҸҚйқўгғҮгғјгӮҝ移иЎҢгҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®зҙ дәәгҒ«гҒҜгҒқгҒ®е·ҘзЁӢгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ„гҖҒжҘӯеӢҷгҒ®йӣЈжҳ“еәҰгӮ„е·Ҙж•°гҒӘгҒ©гҒҢиӘҚиӯҳгҒ—гҒҘгӮүгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгӮҶгҒҲгҖҒгғҷгғігғҖгғјеҒҙгҒҢе°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰеҶҶж»‘гҒ«еҸ–гӮҠд»•еҲҮгӮӢгҒ№гҒҚдәӢй …гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжүұгӮҸгӮҢгӮ„гҒҷгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢжғ…гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒд»•ж§ҳжӣёгӮ„еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®иЁҳијүжјҸгӮҢгҒҜгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®гҖҢеҚ”еҠӣзҫ©еӢҷгҖҚгҒЁгӮӮеҜҶжҺҘгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢе•ҸйЎҢгҒ гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢеҘ‘зҙ„гҒ®з· зөҗгғ»д»•ж§ҳжӣёгҒ®дҪңжҲҗгҒ«гӮҖгҒ‘гҒҰгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҖҢеҚ”еҠӣзҫ©еӢҷгҖҚгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮгӮ·гӮ№гғҶгғ й–Ӣзҷәгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгҒҢжһңгҒҹгҒҷгҒ№гҒҚжі•зҡ„зҫ©еӢҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®е…ЁиҲ¬зҡ„гҒӘи§ЈиӘ¬гҒҜд»ҘдёӢгҒ®иЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©ігҒ—гҒҸжүұгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®зҷәжіЁиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгғҰгғјгӮ¶гғјеҒҙгҒҢиІ гҒҶеҚ”еҠӣзҫ©еӢҷгҒЁгҒҜ
дёҠгҒ®иЁҳдәӢгӮӮдҪөгҒӣгҒҰзўәиӘҚгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒз”»йқўгғ»еҝ…й Ҳж©ҹиғҪгҒ®жҙ—гҒ„еҮәгҒ—гҒӘгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҰгғјгӮ¶гғјеҒҙгҒ®еҚ”еҠӣгҒ®иҰҒи«ӢгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„й ҳеҹҹгҒЁгҖҒгғҮгғјгӮҝ移иЎҢгҒ®жӨңиЁҺжјҸгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒи©ұгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮиҮӘгҒҡгҒЁзҙҚеҫ—гҒҢгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
д»•ж§ҳжӣёгҒ«гҒӘгҒ„й–ӢзҷәгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢе ұй…¬гҒҜгҒ©гҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢ
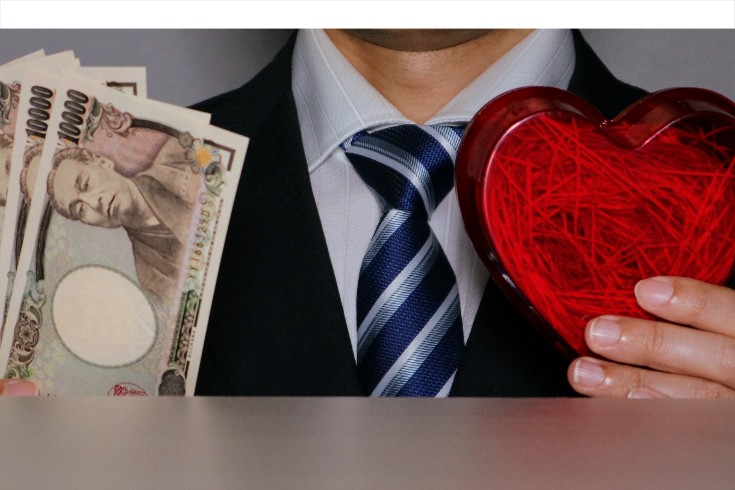
гҒҫгҒҹжң¬иЁҳдәӢгҒ®и©ұйЎҢгҒ«й–ўйҖЈгҒ—гҒҰдҪөгҒӣгҒҰж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒд»•ж§ҳжӣёгҒ«гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’дҪңгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҖҒдёҠд№—гҒӣгҒ—гҒҹе ұй…¬и«ӢжұӮгҒҜжі•еҫӢдёҠиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮе ұй…¬гҒ®дёҠд№—гҒӣгҒ®еҸҜеҗҰгҒЁгҖҒеҸҜиғҪгҒӘе ҙеҗҲгҒ®иҰӢз©ҚгӮӮгӮҠйҮ‘йЎҚгҒ®иЁҲз®—ж–№жі•гҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®иЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡгӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ®иҰӢз©ҚгӮҠйҮ‘йЎҚгҒ®дәӢеҫҢеў—йЎҚгҒҜеҸҜиғҪгҒӢ
дёҠгҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒе ұй…¬гҒЁеҜҫдҫЎй–ўдҝӮгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹжҘӯеӢҷзҜ„еӣІгӮ’дёҠеӣһгӮӢжҘӯеӢҷгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒӢеҗҰгҒӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢж—ЁгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒжң¬иЁҳдәӢгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ§гҒ„гҒҶгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеҪ“еҲқгҒ®д»•ж§ҳгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ®й–ӢзҷәпјҲжң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒ„гҒҶгҒӘгӮүгҖҒеҗҰе®ҡдҫӢгҒ®ж–№пјүгҒ®й–ӢзҷәгҒ«гҖҒгғҷгғігғҖгғјгҒҢеҝңгҒҳгҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜиҝҪеҠ гҒ®е ұй…¬и«ӢжұӮгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒгҖҖ
гӮ·гӮ№гғҶгғ й–ӢзҷәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғҷгғігғҖгғјгҒҢгҒӘгҒҷгҒ№гҒҚеҪ№еүІгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢдёҖйқўгҒ§гҒҜеҘ‘зҙ„жӣёгӮ„д»•ж§ҳжӣёгҒ®еҶ…е®№гҒ«жІҝгҒЈгҒҰжұәгҒҫгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰй«ҳеәҰгҒӘдҝЎй јгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«жҘӯеӢҷгӮ’д»»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®е®ҹж…ӢгҒҜеҪўејҸгҒӮгӮҠгҒҚгҒ§жұәгҒҫгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҶ…е®ҹгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжі•еҫӢгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷзӮ№гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гӮ·гӮ№гғҶгғ й–Ӣзҷә