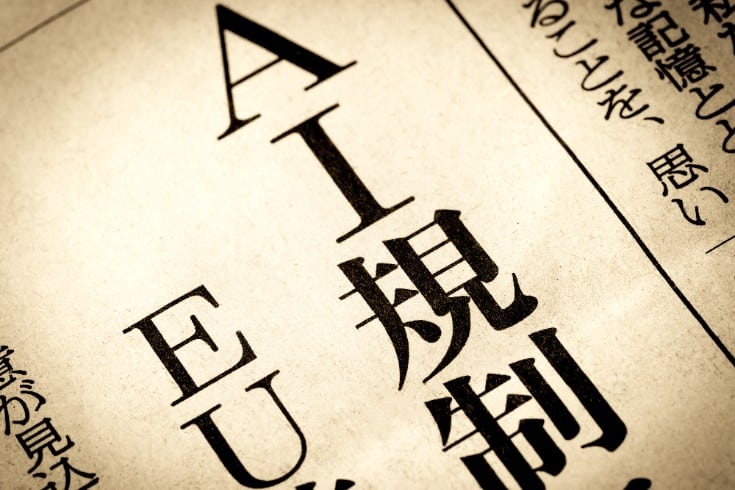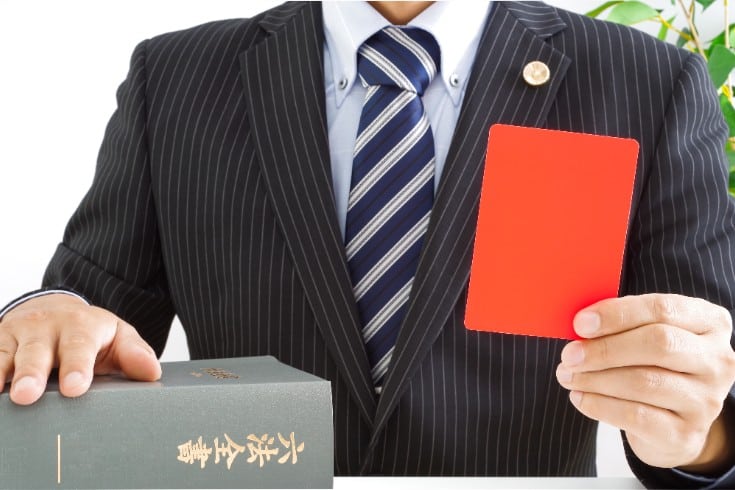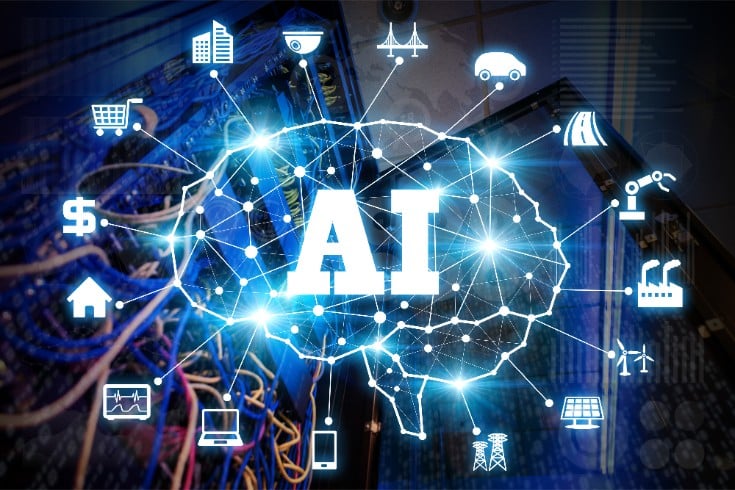プロンプトに著作権はあるのか?AI時代の知的財産権を徹底解説

生成AIの技術は急速に進化し、文章や画像、プログラムコードまで自動生成できる時代となりました。ChatGPTやPerplexity、Midjourneyなどの多種多様なAIツールがビジネスでも広く導入される中、「AIにどのような指示を出すか」というプロンプトが、成果物の質を大きく左右しています。
生成された画像や文章に著作権が発生するのはイメージしやすいと思います。では、AIに出力内容や形式を指示する「プロンプト」には著作権はあるのでしょうか。
本記事では、AIのプロンプトと著作権の関係について、現行法に基づきつつ、企業や法務部門、開発者が押さえておくべき知識を徹底解説します。
この記事の目次
著作権とは?生成AI時代にも重要な法的基盤
著作権の意義は著作者の権利を保護し、同時に著作物の公正な利用を確保することにあります。これにより、文化の発展に貢献することを目的としています。
では著作権法が定める「著作物」とは一体なんなのでしょうか。
著作権法における「著作物」の定義
著作権法上、著作物と認められれば、著作者には「著作権」が与えられます。では一体どのようなものが「著作物」に該当するのでしょうか。
著作権法第2条第1項第1号では、著作物を以下のように定義しています。
「1.思想又は感情を 2. 創作的に 3. 表現したものであつて、 4.文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
著作権が発生するためには上記の4つの要件が必要と言われています。
著作権の4つの要件とその具体例
条件1:思想または感情が含まれていること
この要件は厳格なものではなく、人間の「考え」や「気持ち」のような主観的要素が含まれていれば足りるとされています。ただし、単なる事実の羅列や客観的なデータだけでは、「思想又は感情」に該当しないとされ、著作物とはみなされません。
条件2:創作的な表現であること
「創作性」とは、高度な芸術性を意味するものではありません。作者の個性や工夫が何らかの形で反映されていればこの条件は満たされると解されています。一方で、語句を短く組み合わせただけの定型文や、表現にほとんど選択肢がないようなケースでは、創作性が認められにくく、著作物とは判断されないことが多いです。
条件3:「表現されたものである」こと
表現の手段は紙や画面上の文章だけでなく、音声による発話や口述も含まれます。重要なのは、それが実際に外部に示された「表現」である点で、アイデアそのものや発想の段階にとどまる内容は、著作権の保護対象にはなりません。たとえ優れたアイデアであっても、アイディア自体は著作権の保護対象にはなりません。
条件4:文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
著作物とされる対象は、文芸、学術、美術、音楽といった範疇に属するものである必要がありますが、これは必ずしも限定的なカテゴリではありません。たとえば、設計図やプログラムなども、創作性が認められれば著作物に含まれると考えられています。
上記の4つが要件であることから、「頑張って」といったありふれた短いフレーズや、天気予報の数字データなどの事実の羅列、単なるアイデアや手法には著作権は発生しません。
上記の著作物の条件は原則プロンプトにも当てはまります。例えば、「猫の写真を生成せよ」という発想自体は保護されませんし、「猫の写真を生成せよ」という指示文は単なる短いフレーズにも思えます。この指示文の表現に創作性があるかどうかが争点になります。
プロンプトとは?その意味と役割

生成AIを利用するには、「プロンプト」が必要になります。ここでは、まずそのプロンプトについて解説します。
プロンプトの意味と種類
プロンプトとは、生成AIに対して「こういうものを作ってほしい」と指示する入力文のことです。例えば下記のプロンプトを見てみましょう。
- ショートプロンプト:単純な命令文(例:「美しい風景の写真を生成せよ」)
- ロングプロンプト:AIへの指示を詳細に規定した命令文(例:「青空が広がる秋の高原に立つ一軒家を、油絵風で描いてください」)
条件・文体などを詳細に指定したプロンプトと、そうでないプロンプトでは出力される結果に大きな差が生じます。
プロンプトの設計はノウハウの塊
企業や個人が成果物の質を上げるために研究を重ねた「プロンプト設計」は、単なる指示文ではなく、知的資産になりつつあります。
プロンプトの設計は「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれ、AIの出力結果を左右するほど大きな影響を及ぼします。複雑なプロンプトではときには1000文字を超えることもあることから、著作権や知的財産権の議論に発展する背景となっています。
では、プロンプトには著作権は発生するのでしょうか。
なお、生成AIによって出力された成果物に著作権があるのか、という論点については、下記記事を参照ください。
関連記事:生成系AIの文章に著作権は生まれるか ChatGPT等の自然言語処理AIと著作権を解説
プロンプトに著作権はあるのか?行政や立法府の見解

生成AIで望み通りの出力を得るにはプロンプトが鍵となります。そのプロンプトと著作権について、執筆時点で公表されている行政や立法府の見解を紹介します。
創作性が認められるプロンプトには著作権が発生する可能性
プロンプトが著作物に該当するかどうかのポイントは、以下の3点に集約されます。
- 表現であるか(単なるアイデアや事実ではないか)
- 創作性があるか(ありふれた表現でないか)
- 人間によって制作されたか
1について、2023年の文化庁の見解では「生成 AI に対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該 AI 生成物に著作物性は認められない」と示されました。
また、2の創作性については”創作的寄与”という言葉を用いたうえで、「創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えられる。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しない」との見解を示しました。
また、2023年の国会答弁でも「プロンプトが一般的な名詞の組み合わせだけであれば創作性がなく、著作物と認められない可能性がある」と同様の指摘がなされています。
一方で、「プロンプトエンジニアリングにつきましては、AIに対する指示などの命令に関する手法や技術と捉えますと、その内容が技術で表現されるものでなければ著作物には含まれません」としていることから、技術として表現されており、詳細な指示や命令を含む場合には創造性が認められるケースもあるとしています。
ただ「最終的には司法において判断されることになる」と答弁を締めくくっており、法整備や判例などが追いついていないのが現状です。
関連記事:生成AIと著作権の関係で押さえておくべき考え方とは?
海外の事例やガイドライン
米国著作権局(U.S. Copyright Office)は、AIが生成した出力に著作権を認めるかは、ケースバイケースでの分析が必要であるとされています。人間の関与が明確でない場合、著作物と認められないという立場です。
一方、英国やEUでは、共同著作や職務著作の概念もあり、企業活動の中でプロンプトを作成した場合の取扱いにも一定の柔軟性があります。
日本での実務上の対応
現在のところ、日本ではプロンプトに対して個別の判例はまだありません。しかし「創作的な表現」と評価されるものであれば、理論的には著作権の保護を受ける可能性があります。企業では生成AIの導入に際して、「知的財産」として社内ガイドラインを設けることが必要になるかもしれません。
実務における注意点と対策
プロンプトに著作権が認められる可能性が残っている以上、知的財産に準じる形式で運用・管理する必要があります。下記の点に留意しておくとよいでしょう。
- プロンプトと生成物の関係を明確にして記録
誰が何のためにどのようなプロンプトを使ったのかを記録しておくことで、万一の法的紛争時に備えることができます。 - 成果物の使用範囲を定めた契約書を作成
生成物を第三者に提供する場合、著作権があるか否かにかかわらず、契約書で利用範囲を明確にしておくことが重要です。 - プロンプトと生成物をセットで管理
企業にとってプロンプトはノウハウであり、生成物は成果です。この2つを分けて考えず、一体で管理することが推奨されます。
実務で押さえるべきリスクと対策(盗用・共有・ライセンス)

既に業務に生成AIを取り入れている企業も多いでしょう。ここでは、プロンプトに著作権が認められる可能性があることを配慮して、具体的に検討すべきリスクと対策について解説します。
プロンプトの盗用は法的に問題となるか?
プロンプトに創作性のある表現が認められれば、当該プロンプトは著作物です。無断使用は著作権侵害となる可能性があります。
昨今では、SNSを通して、AIのプロンプトを商用利用しているユーザーも見受けられますが、それが他社のプロンプトだった場合、使用差し止めや損害賠償を請求されることもありえます。特に、企業が開発したロジックやテンプレートが含まれたプロンプトは、機密情報としても扱われるべきです。
社内ガイドラインの策定と法務部との連携
企業では以下のような対応が有効です:
- プロンプト作成・使用時のガイドラインを作成
- 社員に対する著作権・知財教育を実施
- 法務・知財部門による定期レビュー
このようなルール整備により、生成AI利用時の法的リスクを最小化できます。
まとめ:生成AIについては専門家に相談を
生成AIを使った業務が当たり前になる中、プロンプトには著作権が発生する余地があります。特に、プロンプトに創作性があれば、著作権によって保護される可能性があることを認識しておきましょう。
特に商用利用する場合には注意が必要です。企業活動の中では、プロンプトと生成物のセットで利用範囲と責任を明確にし、契約や規程でコントロールすることが大切です。
加えて、企業内ではガイドラインの策定など、知的財産に関しての対策を講じることが必要です。知的財産に関しては高度に専門性が必要とされる問題です。特に生成AIやプロンプトについては、判例や法整備が追いついていません。ぜひ一度専門家に相談したほうがいいでしょう。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。AIビジネスには多くの法的リスクが伴い、AIに関する法的問題に精通した弁護士のサポートが必要不可欠です。当事務所は、AIに精通した弁護士とエンジニア等のチームで、ChatGPTを含むAIビジネスに対して、契約書作成、ビジネスモデルの適法性検討、知的財産権の保護、プライバシー対応など、高度な法的サポートを提供しています。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:AI(ChatGPT等)法務
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務