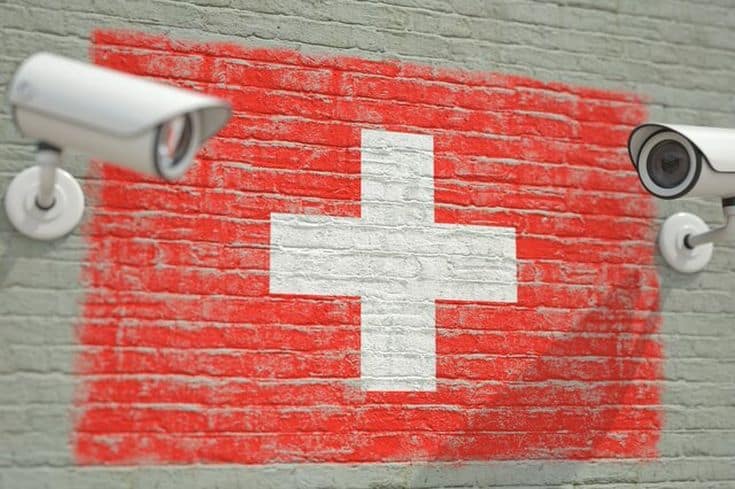フランス共和国の法体系と司法制度を弁護士が解説

フランスは、ドイツなどと同様に、古代ローマ法に端を発する大陸法(シヴィル・ロー)を基盤としています。この共通の起源は、日本民法がフランス法の影響を受け、その後ドイツ法の影響を深く受けた経緯を理解する上で重要です。
ただ、フランス法は、日本と同じ「大陸法」という共通の起源を持ちながらも、ビジネスに直接影響を及ぼす顕著な相違点を内包しています。特に、ナポレオン法典を基礎とする「法典主義」と、日本には存在しない「公法・私法の二元構造」は、フランスで事業を行う日本企業も理解しておくべき重要なポイントです。
本記事では、このフランス法体系を理解する上で核となる「法典主義」と「公法・私法の二元構造」について、その歴史的背景と現代的な意義を解説します。
なお、フランスの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
フランス法の起源と大陸法体系の核心
フランス法体系の歴史的背景
フランスの法体系を理解するためには、まずその歴史的背景と、根幹をなす「法典主義」の原則を把握することが不可欠です。
フランス法の基礎を形成したのは、1804年に制定されたナポレオン民法典(Code civil)と、1807年の商法典(Code de commerce)です。これらの法典は、市民生活や商取引の基本的なルールを網羅的に規定することを目的としており、現在も多くの条文が有効であり、その後の法改正の基盤であり続けています。ナポレオン民法典は「第1編:人」、「第2編:財産及び所有権の各種変更」、「第3編:財産を取得する各種の方法」の3部構成からなり、その体系的な規定は法の「アクセシビリティと明解性」という憲法上の価値に資するものとされています。
この体系の顕著な特徴が「法典主義」です。これは、法律の解釈・適用において、成文法である法典を最も重要な法源とする考え方です。この原則は、法解釈の一貫性と予測可能性を高めることを目指しています。
成文法と判例法の関係
フランス法は成文法を第一の法源とする一方で、実際の運用においては最高裁判所の「判例」(jurisprudence)が大きな役割を果たしています。例えば近年でも、労働法における非競業義務条項や、新型コロナウイルス感染症下の商業テナントにおける賃料支払い義務といった重要な法的論点に関する多くの具体的なルールは、最高裁判所(Cour de cassation)による判例によって確立・解釈されてきました。
この状況は、成文法典を重視する「法典主義」という言葉の厳密な意味と一見矛盾するように見えますが、ここにこそフランス法を理解する上で重要な要素があります。フランスの最高裁判所は、判例を通じて法解釈の統一を図る役割を担っており、その判断は下級審を事実上拘束する強い影響力を持ちます。判例は、社会や経済の変化に対応するため、条文の適用に留まらず、具体的な法的ルールを形成する事実上の法源として機能しています。これらは、日本と基本的に同じ構造となります。
フランスの公法・私法の二元構造
フランスの司法制度を理解する上で、日本の法体系と最も異なる点が、公法と私法の明確な区別、そしてそれに対応する「裁判所の二元構造」です。フランス法は、私人間の関係を規律する「私法」と、国家・行政機関の活動や、これらと私人との関係を規律する「公法」を厳格に区別するsumma divisio(最大の区分)という考え方を採用しています。
この二元構造は、フランス革命後の「司法裁判所が行政に干渉することを防ぐ」という歴史的経緯から生まれました。この原則に基づき、フランスの司法制度は、私人間の紛争を扱う「司法裁判所」(ordre judiciaire)と、行政に関する紛争を扱う「行政裁判所」(ordre administratif)の、二つの独立した法体系に分かれています。
この結果、行政との紛争(例:許認可、税金、入札)は、通常の裁判所とは全く異なる、専門化された行政裁判所の管轄となります。この違いは単に手続き的なものに留まりません。行政裁判所は、行政の論理と文化を深く理解した専門家(多くが国立行政学院ENAの卒業生)で構成されています。この特殊な専門性より、行政に対する訴えがより迅速かつ効果的に処理されるという利点がある一方で、その判断基準や手続きが通常の民事・商事紛争とは大きく異なるという側面もあります。
フランス司法制度の構造
二つの最高裁判所
フランスの二元構造を具体的に示すのが、二つの独立した最高裁判所を持つ司法制度の階層です。
司法裁判所の階層 私法上の紛争(民事・商事・刑事)は、第一審としてtribunal judiciaire(一般裁判所)、conseil de prud’hommes(労働審判所)、tribunal de commerce(商事裁判所)などが管轄します。これらの判決に対しては、cour d’appel(控訴院)に控訴することができます。そして、司法裁判所の頂点には、Cour de cassation(破棄院)が位置します。
行政裁判所の階層 公法上の紛争は、第一審としてtribunal administratif(行政裁判所)が管轄し、cour administrative d’appel(行政控訴院)に控訴することができます。行政裁判所の頂点には、Conseil d’État(国務院)が位置します。
そして、フランスのCour de cassationやConseil d’Étatは、事実関係を再審理する「第三審」ではなく、下級審の裁判官が法律を正しく適用したか(vice de formeやerreur de droit)のみを審査する「破棄院」としての役割を担っています。
権限分配法廷(Tribunal des conflits)
この二元構造の隙間を埋める特別な裁判所として、Tribunal des conflits(権限分配法廷)が存在します。司法裁判所と行政裁判所のどちらが管轄権を持つかについて紛争が生じた場合、この法廷が最終的な判断を下します。この法廷は、両裁判所の判事から同数ずつ選出された人員で構成されており、管轄権の衝突(conflit positif)や、両者がともに管轄権がないと判断した場合(conflit négatif)に、最終的な判断を下します。
この特異な裁判所の存在自体が、フランスの二元構造が単なる理論ではなく、実務上厳格に運用されていることの何よりの証拠です。
権限分配法廷によるブランコ判決
権限分配法廷が下した最も代表的な判決が、1873年2月8日の「ブランコ判決」です。
この事件は、政府が運営するタバコ製造工場の従業員が操る台車に轢かれて負傷したアニエス・ブランコという5歳の少女の損害賠償請求に端を発します。アニエスの父親は、民法に基づき司法裁判所に提訴しましたが、この訴訟は公役務(公共サービス)の活動に起因するものであり、国家に民法を適用できるかが問題となりました。
これに対し、権限分配法廷は、国家の公役務活動から生じる損害に対する責任は、民法典の原則ではなく、「公役務の必要性」に応じて変動する特別な規則によって規律されるべきだと判示しました。そして、その「特別な規則」を適用する権限は、行政裁判所にあると結論づけました。
この判決は、以下の2個の点で、フランスの行政法の基礎を築いたものでした。
- 国家責任の確立:従来、国家は公権力の行使による損害に責任を負わないという「国家無責任原則」が支配的でしたが、ブランコ判決はこれを覆し、国家も責任を負うべきであることを明確にしました。
- 行政法の自律性:国家の活動は公共の利益を目的とするため、私人間の関係を規律する民法とは異なる独自の法体系(行政法)によって統治されるべきであるという考え方を確立しました。
この判決により、国家の公役務活動に関する紛争は、行政裁判所の管轄に属することが決定的となりました。ただし、その後の法改正や判例によって、この原則は修正・発展しています。例えば、1921年のSociété commerciale de l’Ouest africain判決では、民間企業と同様に商業的に運営される「産業・商業的公役務」の紛争は司法裁判所の管轄とされました。また、1957年の法律により、ブランコ判決の事案と類似した「公用車両」による損害の紛争は、今日では司法裁判所が管轄することになっています。
ブランコ判決は、その具体的な適用範囲は時代とともに変化しましたが、公法と私法の明確な区分と、行政法の自律性という二元的な司法制度の核心を確立した点で、現在も重要な判例として位置づけられています。
まとめ
フランスの法体系は、ナポレオン法典に遡る確固たる成文法を基礎としながらも、判例が動的に法を形成・解釈する側面を持ち、また、公法と私法の二元構造という日本にはない独特なシステムを維持しています。これらの特性を深く理解し、近年の企業ガバナンスや労働法の変革、そして電子商取引における消費者保護といった分野の動向を正確に把握することは、フランスでの事業活動における法的リスクを管理する上で不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務