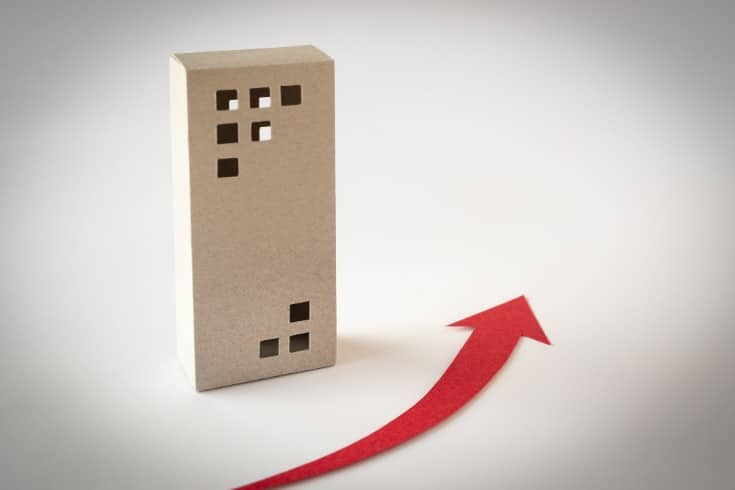IT導入補助金のキックバックによる「実質無料」の不正受給と法的リスク
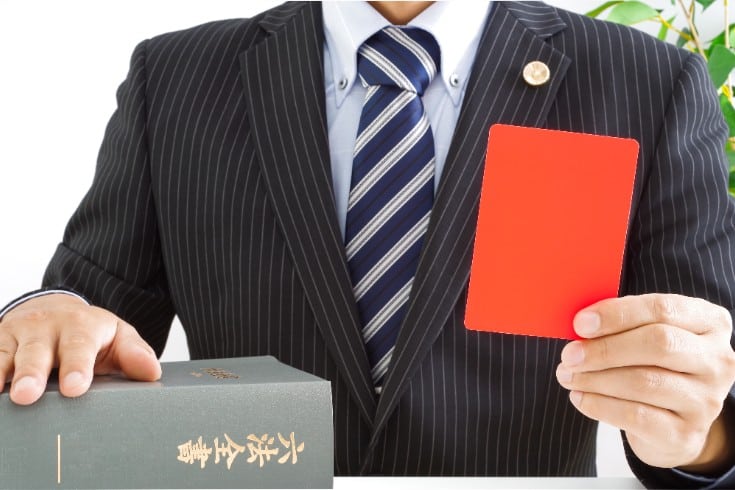
IT導入補助金は、中小企業がITツールを導入し、生産性向上を図ることを支援する国の重要な制度です。デジタル化推進の波に乗る企業にとって、この補助金は事業成長の大きな後押しとなり得ます。しかし、近年、この公的資金を悪用した不正受給が社会問題化しており、特に「キックバック」と呼ばれる手口を用いた、「実質無料」スキームによる不正が顕著に増加しています。会計検査院の調査によれば、IT導入補助金において、キックバックを用いた実質無料スキームなどによる1.4億円以上の不正受給が指摘されており、これは調査対象となった445案件のうち41件、30事業主体で確認されています。
本記事では、IT導入補助金における不正受給、特にキックバックや「実質無料スキーム」の実態、その発覚経路とペナルティを解説します。そして、万が一不正受給に心当たりがある場合、またはそれに巻き込まれた可能性がある場合の自己申告についても解説します。
この記事の目次
IT導入補助金におけるキックバックによる実質無料スキームとは

IT導入補助金のキックバックによる「実質無料」と不正受給
不正受給とは、「偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすること」と定義されます。これは、単なる誤りや不注意とは異なり、意図的な欺罔行為を伴うものです。
補助金や助成金は国民の税金を原資とする公的資金であり、その適正な執行が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金等適正化法)によって厳しく求められています。この法律に違反する行為は、犯罪として扱われます。
近年、特に問題視されているのが「キックバック」を用いた「実質無料スキーム」による不正受給です。IT導入補助金におけるキックバックとは、IT導入支援事業者やその関係会社から中小企業などへ資金が還流される行為を指し、「実質無料スキーム」とは、これによって中小企業の自己負担額が減額または無償になる、あるいは自己負担額を上回る不当な利益を得ることができると謳う手口をいいます。典型的なスキームとしては、IT導入支援事業者が「実質ゼロ円で導入できます」「キャッシュバック」「100%受給保証」などと、不自然な導入スキームや甘言を持ちかけ、ITツールの販売先を開拓するケースが多発しています。具体的には、会計ソフトの購入費用を後日、IT導入支援事業者もしくは第三者から返金される、または営業先への紹介料と称して、IT導入支援事業者もしくは第三者から「紹介料やコンサル料等」を受け取る、といった手口が報告されています。これらの行為は、実質的には補助金制度の趣旨を逸脱した不正行為です。
補助金制度の根幹にあるのは、「事業主が一度自社でITツール導入費用を全額支払い、その負担した経費の一部を国が助成する」という大原則です。キックバックや、それを用いた実質無料スキームは、この原則に明確に違反します。「代理人に任せていた」「自分は知らなかった」といった主張は、代表者の責任逃れとして原則として認められません 。企業は、たとえ第三者(IT導入支援事業者、コンサルタントなど)が不正を主導したり関与したりした場合でも、最終的な責任は申請事業者、特にその代表者に帰属するという厳格な原則が適用されることを理解する必要があります。
参考:IT導入補助金2025
キックバックを用いた実質無料スキームによる不正受給の実例
会計検査院の調査では、IT導入補助金において、15社のITベンダーがキックバックによる実質無料スキームに関与し、1978事業(補助金交付額58億2891万円相当)に上る不正が確認されています。これらのIT導入支援事業者は、協賛金や実態を伴わない紹介料などの名目で資金を還流させていました。
会計検査院の報告書や関連情報から確認できる、キックバックによる実質無料スキームが違法と判断された具体的な事例には、例えば、以下のようなものがあります。
- ECサイト、クラウド型の会計ソフトなどのITツールが導入したあと、協賛金や実態を伴わない紹介料などの名目で資金が還流され、自己負担額が減額または無償になっていた事例
- ITツールの導入後、「採択されれば紹介料もお支払いします」という提案を受け、紹介料名目で資金が還流されていた事例
- ITツールの導入後、「顧客紹介料」「コンサル料返金」などの名目で資金が還流され、自己負担ゼロどころか、180万円の利益を得る構図になっていた事例
補助金の不正受給が発覚する経路と背景
補助金事務局や会計検査院は、補助金交付後も厳格な調査を実施します。事業実施中または事業終了後に、会計検査院や事務局が事業所に立ち入り、ITツールが事業計画の目的に従って活用されているか、帳簿書類や証憑が適切に保管されているかなどを確認します。IT導入補助金においても、会計検査院が約10万社のうち376社445案件を抽出し、利用実態などを検査した結果、キックバックなど1.4億円超の不正受給が発覚しました。検査では、申請にあった設備やシステムが実装されていない、決算書や口座履歴の精査からキックバックや、それを用いた実質無料スキームが発見されるといった具体的な状況が確認されています。中小機構や事務局は、警察からの捜査関係事項照会やコールセンターへの通報から不正の疑義を把握していたにもかかわらず、会計検査院の調査で不正が多数判明するまで立ち入り調査を一度も実施していなかったことが指摘されています。この指摘を受け、IT導入支援事業者の登録取り消しや、中小企業への自主返還手続きの呼びかけが行われています。
不正受給の発覚経路として、内部告発も強力な要因です。従業員が不正を察知し、労働局や関係機関に通報することで不正が発覚するケースは少なくありません。情報提供者のプライバシーは十分に配慮される体制が整っているため、従業員が通報しやすい環境が整備されています。
IT導入支援事業者などの悪質な業者が不正行為で摘発された場合、その業者と取引があった他の企業も芋づる式に調査対象となることもあります。
補助金不正受給のペナルティ
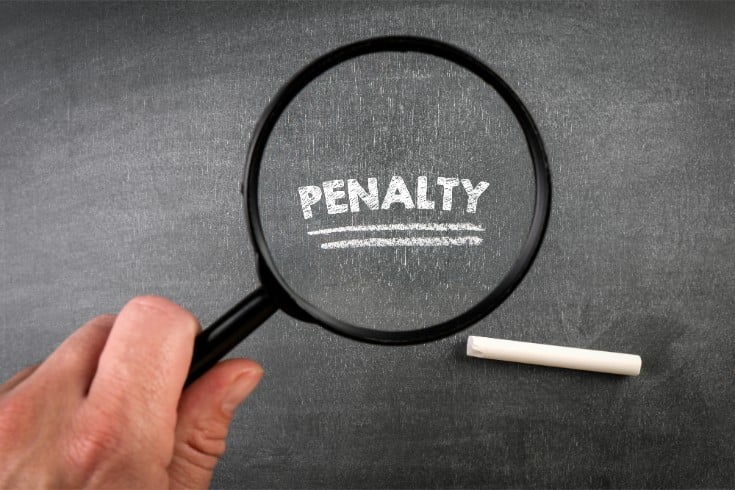
不正受給が判明した場合、企業は以下の経済的負担を負うことになります。
まず、不正に受給した補助金は、その全額を国に返還しなければなりません。これは、不正発生日を含む期間以降の全額が対象となります。次に、返還額の20%に相当する加算金(違約金)が追加で課せられます。これにより、返還総額は受給額の1.2倍に膨れ上がります。さらに、不正受給日の翌日から返還が完了する日まで、年率3%または年10.95%の延滞金が発生し続けます。IT導入補助金においては、年10.95%の高額な延滞金が課されることが明記されています。
金銭的ペナルティに加え、不正受給が発覚した企業には、行政処分が科されます。不正受給が発覚し、自主申告ではない場合、事業主名、代表者名、訓練機関名などが公表されます。特に支給決定取消等を行った額が100万円以上の場合は、原則として公表対象となります。これにより、長期間にわたって不正受給の事実が知れ渡ることとなります。
また、補助金の指定業者から除外されるというのも、大きなデメリットです。不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金を含む全ての補助金、助成金の受給資格を失います。雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など、雇用関係の全ての助成金が対象となるため、企業によっては深刻な悪影響となります。また、全額返納されていない場合は、この期間が延長されます。
特に悪質な不正受給は、金銭的、行政的ペナルティに加えて、刑事告発の対象となる可能性があります。悪質な不正受給は、刑法第246条に定める詐欺罪に問われる可能性があります。詐欺罪の場合、10年以下の拘禁刑(懲役)が科される可能性があります。また、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金等適正化法)に基づき、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
不正受給では、申請事業者のみならず、その不正に関与した第三者にも厳しいペナルティが科せられます。社会保険労務士や代理人、訓練実施機関、IT導入支援事業者などが不正受給に関与していた場合、事業主と同等の責任を負うことになります。具体的には、事業主と連帯して返還義務を負い、事業所名などが公表され、5年間の助成金申請受理停止などの措置が取られます。IT導入支援事業者については、登録取消が行われ、補助金ウェブサイトで公表されます。
補助金不正受給を未然に防ぐための対策とコンプライアンス強化
不正受給は、一度発生すると企業に甚大なダメージを与えます。そのため、未然に防ぐための対策と、強固なコンプライアンス体制の構築が不可欠です。
補助金、助成金の要項や制度趣旨は、自社で詳細に確認することが最も基本的な対策です。社外の「労働局に確認した」などの情報を鵜呑みにせず、信頼できる専門家へ自ら相談し、不明点を解消することが重要であり、外部の情報を盲信せず、自らの責任で制度を深く理解することが求められます 。申請の手引きをしっかりと確認し、辞退届などの提出漏れを防ぐことも、適正な運用には不可欠です。
「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」「100%受給保証」といった勧誘は、不正行為の可能性が極めて高いものと考えざるを得ません。このような甘い言葉で近づいてくる研修会社やコンサルタントは、不正受給という犯罪につながり、最悪の場合、会社を倒産の危機に追い込む可能性があります。契約を急かしたり、質問に対して曖昧な回答しかしない業者、申請代行を行うのに社会保険労務士の資格を持っていない業者(社会保険労務士法により、雇用関係助成金の申請代行は社労士の独占業務とされています)には特に注意が必要です。
自社での申請が難しい場合や、複雑な判断が必要な場合は、信用できる専門家(弁護士、社会保険労務士、認定支援機関など)を利用することが、不正リスクを避ける上で極めて有効です。
弁護士への早期相談と自己申告の重要性

また、既に不正受給を行ってしまったという事実を認識した場合は、労働局や補助金事務局による調査が開始される前に自主申告を行うべきです。労働局が調査を行う前に不正、不適正な受給の全ての事実を申告し、迅速に全額返還することで、事業主名の公表を原則として行わないという方針が示されているからです。
これは、企業の信用力やブランドイメージを維持し、取引先や顧客からの信頼失墜を防ぐ上で極めて重要です。意図しない不正受給であった場合でも、自主返還の手続きを行うことで、加算金や延滞金といった経済的ペナルティを軽減し、事業継続への影響を最小限に抑えることができます。ただし、不正の態様、手段、組織性などから判断して特に重大または悪質と認められる場合は、自主申告であっても非公表とならない場合がある点には留意が必要です。
弁護士は、不正受給に関する問題に直面した企業に対し、さまざまなサポートを行うことができます。まず、不正に申請したときの資料等を弁護士がチェックし、何が、どのように、どの程度不正受給に該当しうるのか、事実関係を正確に調査することになります。その上で、自己申告の文書作成や、本人の代わりに自主返還手続きの対応を行います。労働局や補助金事務局への自主申告に際し、面談への同行、当局からの資料提供依頼への対応、書面内容のチェック、修正協議など、当局とのやり取りを代行、支援します。
まとめ:IT導入補助金の不正受給は弁護士に相談を
IT導入補助金は、中小企業の生産性向上とデジタル化を推進するための重要な国の支援策であり、その適正な活用は企業の持続的な成長に不可欠です。しかし、キックバックによる実質無料スキームをはじめとする不正受給は、公的資金の悪用であり、発覚した場合には企業に甚大な経済的損失、社会的な信用の失墜、そして刑事罰という取り返しのつかないリスクをもたらします。
もし、不正受給に心当たりがある、またはその可能性を疑う場合は、速やかに弁護士に相談し、自己申告を行うことが、企業名の公表回避や刑事罰の軽減など、最も賢明な対応策です。早期の弁護士への相談は、法的なリスクを正確に把握し、当局との適切な交渉を通じて、事態の収拾を図るために重要であるといえます。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT・ビジネスと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証プライム上場企業からベンチャー企業まで、ビジネスモデルや事業内容を深く理解した上で潜在的な法的リスクを洗い出し、リーガルサポートを行っております。補助金や助成金の不正受給に関連する業務に関しては、下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:補助金・助成金の不正受給対応
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務