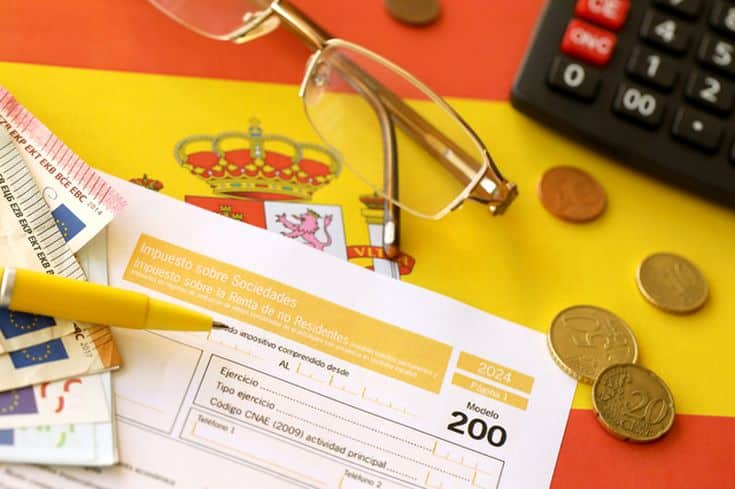マルタ共和国の労働法と解雇法理、労働紛争

マルタ共和国の労働法の基盤は、主に「Employment and Industrial Relations Act(雇用・労使関係法)」に定められており、これは日本の労働基準法や労働契約法に相当し、最低限の労働条件から紛争解決に至るまで、労使双方の権利と義務を定めるものです。また、この法令は、EUの基本的な権利憲章(EU Charter of Fundamental Rights)に準拠しています。
ただ、成文法による日本の法体系とは異なり、マルタの法律は、重要な概念が明確に定義されておらず、英国のコモン・ロー(判例法)や過去の法廷判例の解釈に大きく依存する場面があり、単に法令だけを読んでも全貌を理解しにくい場合があります。
本記事では、マルタの労働法制、その法的枠組や監督機関、雇用契約の種類や解雇法理、労働条件、手当、および各種休暇制度、労働紛争について解説します。
この記事の目次
マルタ労働法の枠組と監督機関の役割
マルタ共和国にて、雇用・労使関係法の執行と労使関係の監督を担う主要な行政機関が、産業・雇用関係局(Department of Industrial and Employment Relations, DIER)です。DIERは、労使双方にガイダンスや支援を提供し、契約内容や労働条件に関する幅広い事項について助言するだけでなく、不公正な労働慣行に関する苦情を調査し、調停サービスを提供しています。
実際に、2024年には、DIERのカスタマーケア部門が数万件の問い合わせに対応し、1,202件のケースを調査した結果、和解を通じて160万ユーロ以上の未払い賃金を回収したというデータがあります。
日本でも、労働基準監督署などの労働行政機関が同様の指導や監督を行いますが、DIERのデータからは、マルタでは労使紛争が日常的に発生し、当局が積極的に介入していることが覗えます。マルタで事業を行う場合、日本の慣習のように「労働基準監督署の指導を待つ」といった受動的な姿勢ではなく、DIERとの円滑なコミュニケーション体制を構築することが、リスク管理上、極めて重要であると言えるでしょう。
マルタにおける雇用契約の種類と試用期間

マルタにおける雇用契約は、日本と同様に無期雇用契約(Indefinite Contract)と有期雇用契約(Fixed-term Contract)に大別されます。有期雇用契約は、最長で4年まで更新が可能であり、その後は原則として無期契約に移行すると定められています。
特に留意すべきは、試用期間(Probationary Period)における法的枠組の特殊性です。日本では、試用期間は期間満了後の本採用を前提とするもので、この期間中の解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が厳しく求められます。これに対し、マルタ法における試用期間は、労使双方が「理由を付すことなく、いつでも」雇用関係を終了できる期間として定められています。ただし、労働組合活動や妊娠・出産、差別的取扱いなど、法令上禁止される事由を理由とする解雇は、試用期間中であっても不当解雇となり得る点に注意が必要です。特に新規事業立ち上げ時など、現地の従業員の能力や適性を慎重に評価したい企業は、この「試用期間」を利用し、法的リスクを抑えつつ人材を確保することができるでしょう。ただし、1ヶ月以上勤務した従業員に対しては、雇用を終了させる側が1週間の事前通知を行う必要があります。
マルタにおける雇用関係の終了
解雇事由:「正当かつ十分な理由」(Good and Sufficient Cause)
マルタにおいて、無期雇用契約の試用期間終了後の解雇には、「正当かつ十分な理由」(good and sufficient cause)が必要です。しかし、日本の労働契約法第16条が定める「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない」解雇は無効とする原則とは異なり、マルタ法は「何が正当かつ十分な理由であるか」について明確な定義を与えていません。これは、マルタの法律が英国のコモン・ロー(判例法)の影響を強く受けていることによるものです。有効な解雇事由を判断するには、過去のインダストリアル・トリビューナル(後述)や裁判所の判例を詳細に分析する必要があり、専門家の助言が不可欠になるでしょう。
整理解雇時の「最終入社者優先」(Last-In-First-Out)原則
日本の整理解雇が「人員削減の必要性」「解雇回避努力義務」「被解雇者選定の合理性」「手続の相当性」という「4要件」を総合的に考慮するのに対し、マルタ法は異なる原則に基づいています。マルタでは、整理解雇(Redundancy)は原則として「最終入社者優先」(Last-In-First-Out, LIFO)のルールに従わなければなりません。
これは、同一職種内で最も遅く入社した従業員から順に解雇するという原則です。このルールは、日本法の「被解雇者選定の合理性」とは全く異なる考え方です。日本の企業が、貢献度やスキルに基づいて解雇対象者を選定する可能性があるのに対し、マルタでは勤続年数が主要な判断基準となります。これは、マルタの労働法が従業員の長期的な安定雇用を重視することによるものです。したがって、マルタで事業再編や人員削減を行う際には、日本の企業が考えるような「リストラ」の論理は通用しません。最も有能で、事業の将来に不可欠な人材であっても、入社時期が最も新しければ解雇対象となり得ます。このリスクを回避するためには、整理解雇の必要性を証明する「リストラクチャリング計画」の策定や、可能な場合は代替職の提供など、LIFOルールを適用する前の段階で慎重な対応が求められます。
さらに、「整理解雇」自体も「正当かつ十分な理由」と同様に、法令上の明確な定義がありません。経済的困難、組織再編、技術変更などがその理由となり得るものの、その正当性は個々のケースで判断されることになります。
有期雇用契約の早期終了に伴うペナルティ
有期雇用契約を期間満了前に終了させた場合、正当かつ十分な理由がない限り、雇用を終了させた側は、もう一方の当事者に対して、残存期間に本来支払われるべき賃金の「半額」を支払う義務があります。これは日本の労働法には存在しない、明確な違約金規定です。日本では、契約期間中の自己都合退職や、解雇が無効とされた場合の損害賠償請求はありますが、このように法定されたペナルティは一般的ではありません。
解雇予告期間と退職金
無期雇用契約において、解雇予告期間は勤続年数に応じて、1週間から最大12週間までと定められています。マルタ法には、法定の解雇予告期間分の賃金(またはそれに代わる手当)を超える「退職金」(severance pay)の支払いを義務付ける規定は原則としてありません。
マルタにおける労働条件、手当、および各種休暇制度
法定最低賃金と年2回のボーナス
マルタの法定最低賃金は、年齢に応じて定められています。2025年1月1日時点での18歳以上のフルタイム従業員の最低週給は€221.78です。さらに、日本の賞与制度とは異なる重要な特徴として、マルタ法には、全てのフルタイム従業員に年間€512.46のボーナスを、四半期ごとに分割して支払うことが義務付けられています。これは法律で定められた必須の手当であり、日本企業の賞与の考え方とは根本的に異なるものです。
労働時間・残業・休憩
マルタの標準労働時間は、業界ごとに定められた「賃金規制命令」(Wage Regulation Orders, WROs)によって異なりますが、通常、週40時間を超える労働は残業と見なされます。残業手当は、通常の時間給の150%以上で支払われることが一般的です。また、従業員は、1日6時間を超える労働に対して少なくとも15分の休憩が義務付けられており、毎日の休息時間として11時間の連続した時間、週ごとの休息時間として少なくとも24時間の連続した時間を受ける権利があります。
各種法定休暇
マルタの従業員は、年間「4週間と32時間」(合計192時間)の有給休暇が付与されます。日本の「日数」で付与される休暇とは異なり、時間で管理されることが特徴です。また、病気休暇(Sick Leave)として年間「2労働週分」の休暇があり、全額賃金が支払われますが、社会保障法に基づく疾病手当に相当する額が控除される仕組みになっています。この他にも、親権休暇(Parental Leave)、弔事休暇(Bereavement Leave)、出産休暇(Maternity Leave)など、日本と同様に複数の種類の休暇制度が存在します。
マルタにおけるインダストリアル・トリビューナルによる労働紛争の解決

マルタにおける労働紛争の解決において、極めて重要な役割を担うのが「インダストリアル・トリビューナル(Industrial Tribunal)」です。これは、雇用関連の特定の紛争について排他的な管轄権を持つ法的な裁定機関であり、その決定は法廷の判決と同等の拘束力を持ちます。
トリビューナルの構成と権限
インダストリアル・トリビューナルの構成は、取り扱う紛争の性質によって異なります。例えば、不当解雇の申し立てを扱う場合は、議長(Chairperson)1名のみで構成されます。一方、労働争議(Industrial Dispute)を扱う場合は、議長1名に加え、労働者と使用者それぞれの利益を代表する委員が1名ずつ、計3名で構成されます。日本の労働審判制度が裁判官と労働審判員で構成されるのと似ていますが、マルタでは紛争の性質に応じて構成が変わることが特徴です。
トリビューナルは、不当解雇の申し立てのほか、差別、ハラスメント、報復行為、そして有期雇用契約の期間内終了に伴う金銭的請求など、多岐にわたる雇用関連の紛争を扱います。また、労働契約違反を扱う権限もありますが、その場合、申し立ては通常の裁判所に行われることになります。
紛争解決の手続きと時効
不当解雇の申し立てを含むトリビューナルへの申し立ては、書面による事実関係の記述を含む書類(referral)を、違反行為があったとされる日から「4ヶ月以内」に、マルタ裁判所内のトリビューナル登録局に提出する必要があります。
救済措置:補償金と原職復帰命令
インダストリアル・トリビューナルは、不当解雇の申し立てが正当であると判断した場合、主に2つの救済措置を命じることができます。一つは「補償金」の支払い命令、もう一つは「原職復帰または再雇用」の命令です。
補償金の額は、不当に解雇された従業員が被った実際の損害や損失、その年齢、スキル、再就職の可能性といった様々な状況を考慮して決定されます。これは、日本の裁判所が不当解雇に対して支払いを命じる逸失利益や慰謝料に相当するものです。
原職復帰または再雇用命令は、従業員が特に復帰を求め、トリビューナルがそれを現実的かつ公正であると判断した場合に発令されます。しかし、この命令は、特別な信頼関係が求められる経営・管理職(managerial or executive post)の従業員に対しては発令されないという特別な規定があります。この点は、日本の法律にはない、マルタ法特有の規定です。
決定の拘束力と控訴
インダストリアル・トリビューナルの裁定や決定は、当事者双方を法的に拘束し、原則として1年以内に一方的に見直しを求めることはできません。また、トリビューナルの決定に対しては、事実関係に関する異議申立ては認められず、「法律上の争点(a point of law)」に限って、決定から12日以内に控訴裁判所へ控訴することが可能です。つまり、トリビューナルが事実認定の最終的な権限を有し、控訴審は法的な解釈の誤りなどを審査する役割を担う、という制度です。
まとめ
| 日本の労働法 | マルタ労働法 | |
|---|---|---|
| 試用期間中の解雇 | 解雇権濫用として厳格に制限される。 | 理由を付す必要がないが、1ヶ月超の勤務者には1週間の事前通知が必要。 |
| 解雇事由(正当性の判断) | 客観的・合理的な理由と社会通念上の相当性が求められる。 | 「正当かつ十分な理由」が法令に定義されておらず、判例法に依存する。 |
| 整理解雇の要件 | 4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性)が考慮される。 | 原則として「最終入社者優先」(LIFO)原則に従う。 |
| 有期雇用契約の早期終了 | 法令上の違約金規定は一般的ではない。 | 終了させた側が、残存期間の賃金の半額を支払う明確な義務がある。 |
| 退職金制度 | 法定の解雇予告手当を超える退職金の支払いは義務付けられていない。 | 従業員の期待する退職金制度が存在しない可能性がある。 |
| 不当解雇の訴え時効 | 明確な時効期間は定められていない。 | インダストリアル・トリビューナルへの申し立て期限は解雇日から4ヶ月以内。 |
マルタの労働法は、成文法主義の日本とは異なり、判例法の影響を強く受けています。特に、「正当かつ十分な理由」や「整理解雇」といった主要な概念が法令に明確に定義されていないため、過去の判例からその法的解釈を検討することが不可欠となります。
さらに、整理解雇における「最終入社者優先」原則や、有期雇用契約の早期終了に伴う明確なペナルティなど、日本の労働法には見られない特有のルールが多数存在します。また、DIERという活発な行政機関の存在や、不当解雇の申し立て期限が4ヶ月と短いことから、マルタでの労務管理においては、予防的なコンプライアンスの徹底と、問題発生時の迅速な対応が極めて重要となります。
関連取扱分野:国際法務・マルタ共和国
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務