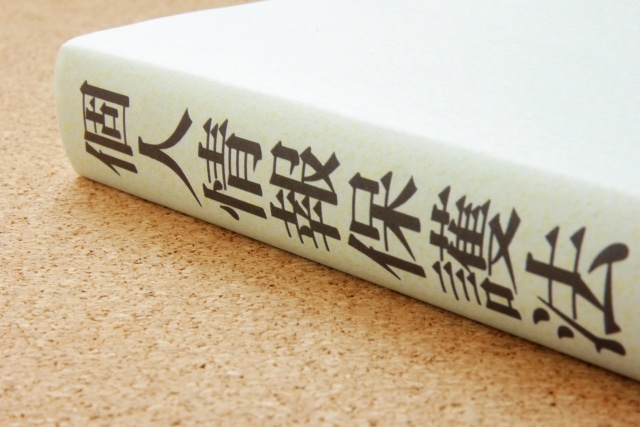õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü©Ńü»’╝¤ķüĄÕ«łŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦Ńü«ŃāØŃéżŃā│ŃāłŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼
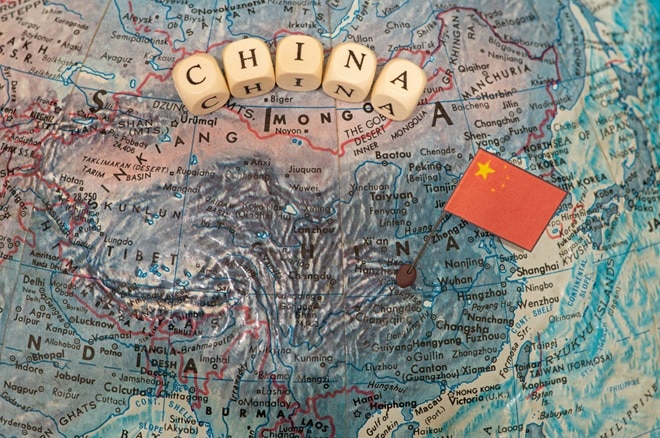
ÕĖØÕøĮŃāćŃā╝Ńé┐ŃāÉŃā│Ńé»Ńü«ŃĆīńē╣Õłźõ╝üńö╗’╝ܵŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«ŃĆīõĖŁÕøĮķĆ▓Õć║ŃĆŹÕŗĢÕÉæĶ¬┐µ¤╗’╝ł2024Õ╣┤’╝ēŃĆŹŃü½ŃéłŃéŗŃü©ŃĆüõĖŁÕøĮŃü½ķĆ▓Õć║ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü»ŃĆü1õĖć3,034ńżŠŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŁÕøĮŃü½ķ¢óķĆŻŃüÖŃéŗŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ╝üµźŁŃü»ŃĆüŃüØŃéīŃéłŃéŖÕżÜŃüäŃü©ŃüäŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéõĖŁÕøĮŃü¦Ńü»ŃĆü2017Õ╣┤Ńü½ŃĆīõĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃĆŹŃüīµ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõĖŁÕøĮŃü¦ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü¬µ│ĢÕŠŗŃü½ÕēćŃüŚŃü¤Ķ”ÅÕ«ÜŃü«µö╣Õ«ÜŃéäµŖĆĶĪōńÜäŃü¬õ┐ØĶŁĘµÄ¬ńĮ«ŃéÆĶĪīŃéÅŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüōŃü«ŃĆīõĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃĆŹŃüīŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬µ│ĢÕŠŗŃü¬Ńü«ŃüŗŃéÅŃüŗŃéēŃü¬Ńüäµ¢╣ŃéäŃĆüĶć¬ńżŠŃüīŃü©ŃéŗŃü╣ŃüŹÕ»ŠÕ┐£ŃüīŃéÅŃüŗŃéēŃü¬Ńüäµ¢╣ŃééŃüäŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé
ŃüØŃüōŃü¦µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüõĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«µ”éĶ”üŃéäĶ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃĆüÕÅ¢ŃéŗŃü╣ŃüŹÕ»ŠńŁ¢Ńü¬Ńü®ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõĖŁÕøĮŃü¦ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃā╗õ╗ŖÕŠīķĆ▓Õć║ŃéÆĶĆāŃüłŃü”ŃüäŃéŗµ¢╣Ńü»ŃĆüŃü£Ńü▓ÕÅéĶĆāŃü½ŃüŚŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«µ”éĶ”ü

õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│Ģ’╝łńĮæń╗£Õ«ēÕģ©µ│Ģ’╝ēŃü©Ńü»ŃĆü2017Õ╣┤6µ£łŃü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü¤õĖŁÕøĮŃü«µ│ĢÕŠŗŃü¦ŃüÖŃĆéµ│ĢÕŠŗŃü«ńø«ńÜäŃü»ŃĆüń¼¼1µØĪŃü½Ńü”õ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
- ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»Ńü«Õ«ēÕģ©ŃéÆõ┐ØķÜ£ŃüÖŃéŗ
- ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝ń®║ķ¢ōŃü«õĖ╗µ©®ŃĆüÕøĮŃü«Õ«ēÕģ©ŃĆüÕģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖŃéÆÕ«łŃéŗ
- ÕøĮµ░æŃĆüµ│Ģõ║║ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«ÕøŻõĮōŃü«µŁŻÕĮōŃü¬µ©®Õł®Õł®ńøŖŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüÖŃéŗ
- ńĄīµĖłŃā╗ńżŠõ╝ÜŃü«µāģÕĀ▒Õī¢Ńü«ńÖ║Õ▒ĢŃéÆõ┐āķĆ▓ŃüÖŃéŗ
ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»Ńü©Ńü»ŃĆüŃĆīŃé│Ńā│ŃāöŃāźŃā╝Ńé┐Ńā╗ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«µāģÕĀ▒ń½»µ£½ŃüŖŃéłŃü│ķ¢óķĆŻĶ©ŁÕéÖŃü½ŃéłŃéŖµ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃĆüõĖĆÕ«ÜŃü«Ńā½Ńā╝Ńā½ŃéäŃāŚŃāŁŃé░Ńā®ŃāĀŃü½ÕŠōŃüŻŃü”µāģÕĀ▒ŃéÆÕÅÄķøåŃĆüõ┐ØÕŁśŃĆüõ╝ØķĆüŃĆüõ║żµÅøŃĆüÕć”ńÉåŃüÖŃéŗŃééŃü«’╝łń¼¼76µØĪ’╝ēŃĆŹŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃüĀŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃéżŃā│ŃāłŃā®ŃāŹŃāāŃāł’╝łõ╝üµźŁÕåģŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»’╝ēŃééÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü»ŃĆüEUõĖĆĶł¼ŃāćŃā╝Ńé┐õ┐ØĶŁĘĶ”ÅÕēć’╝łGDPR’╝ēŃé䵌źµ£¼Ńü«ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒õ┐ØĶŁĘµ│ĢŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüŃĆīÕĆŗõ║║ŃéäńĄäń╣öµāģÕĀ▒Ńü«õ┐ØĶŁĘŃĆŹŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃĆīõĖŁÕøĮÕøĮÕ«ČŃü«Õ«ēÕģ©ŃéäÕģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖŃü«õ┐ØĶŁĘŃĆŹŃéÆŃééńø«ńÜäŃü½ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆéµ│ĢÕŠŗŃü¦Ńü»ŃĆüÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬Ńéŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘŃü«Õ«¤µ¢ĮŃéäŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ńü«ķüĄÕ«łŃĆüµ©®Õł®ńŠ®ÕŗÖŃü«µśÄńó║Õī¢Ńü¬Ńü®ŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃü½ķ¢óŃüŚŃü”Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü½Ńü»ŃĆüõ╗¢Ńü½ŃééõĖŁÕøĮŃāćŃā╝Ńé┐Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃĆīõĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃĆŹŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«Ķ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜõĖŁÕøĮŃāćŃā╝Ńé┐Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü©Ńü»’╝¤µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīÕÅ¢ŃéŗŃü╣ŃüŹÕ»ŠńŁ¢ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«Ķ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒Ī

µŚźµ£¼Ńü«õ╝üµźŁŃüīõĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗŃü«Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- õĖŁÕøĮÕåģŃü¦µāģÕĀ▒Ńü«ÕÅ¢ŃéŖµē▒ŃüäŃüīŃüéŃéŗ
- õĖŁÕøĮŃüŗŃéēµŚźµ£¼ŃüĖµāģÕĀ▒ŃéÆń¦╗Ķ╗óŃüÖŃéŗ
µŗĀńé╣ŃüīµŚźµ£¼Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüõĖŖĶ©śŃü½ÕĮōŃü”Ńü»ŃüŠŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüĶ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪĶĆģŃü½Ńü»ŃĆüŃĆīŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃĆŹŃĆīķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁŃü«ķüŗÕ¢ČĶĆģŃĆŹŃü¬Ńü®ŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü©Ńü»ŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»Ńü«µēƵ£ēŃā╗ń«ĪńÉåĶĆģŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃéƵÅÉõŠøŃüÖŃéŗĶĆģŃü«ŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆé
ķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁŃü«ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü©Ńü»ŃĆüµÉŹÕ«│ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«Õ«ēÕģ©ŃéÆĶäģŃüŗŃüÖÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü«ŃüéŃéŗÕłåķćÄ’╝łŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃéäķüŗĶ╝ĖŃĆüķćæĶ׏ŃĆüÕģ¼Õģ▒ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü¬Ńü®’╝ēŃü¦ŃĆüńĀ┤µÉŹŃéäŃāćŃā╝Ńé┐µ╝ŵ┤®Ńü¬Ńü®Ńü½ŃéłŃéŖÕøĮÕ«ČÕ«ēÕģ©õ┐ØķÜ£ŃĆüÕøĮµ░æńö¤µ┤╗ŃĆüÕģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖŃéÆĶæŚŃüŚŃüÅµÉŹŃü¬ŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü«ŃüéŃéŗĶ©ŁÕéÖŃéÆķüŗÕ¢ČŃüÖŃéŗĶĆģŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«ÕåģÕ«╣

õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬ńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
- ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃü«ńŁēń┤ÜĶ©ŁńĮ«
- ÕøĮŃü«Õ╝ĘÕłČńÜ䵩ֵ║¢ŃüĖŃü«ķü®ÕÉł
- Õ«¤ÕÉŹńÖ╗ķī▓Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗ
- ķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁķüŗÕ¢ČĶĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖ
- ń«ĪńÉåŃā╗Ńā¼Ńé╣ŃāØŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃü«µ¦ŗń»ē
ŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«Ķ®│ń┤░ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃü«ńŁēń┤ÜĶ©ŁńĮ«
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«ń¼¼21µØĪŃü½Ńü”ŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃüīķĀåÕ«łŃüÖŃü╣ŃüŹŃĆīńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘÕłČÕ║”ŃĆŹŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüõĖŁÕøĮÕøĮÕåģŃü¦ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ŃéƵēƵ£ēŃüÖŃéŗõ╝üµźŁŃéäńĄäń╣öŃü»ŃĆüńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘĶ¬ŹĶ©╝Ńü«ÕÅ¢ÕŠŚŃüīÕ┐ģĶ”üŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘÕłČÕ║”Ńü©Ńü»ŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻń«ĪńÉåõĮōÕłČŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕģ¼ńÜäŃü¬Ķ®ĢõŠĪÕłČÕ║”Ńü¦ŃüÖŃĆéÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬Ńéŗń»äÕø▓Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ŃéżŃā│ŃāĢŃā®
- IoT
- ńöŻµźŁńö©ÕłČÕŠĪŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀ
- Õż¦Ķ”ŵ©ĪŃü¬ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃéĄŃéżŃāłŃā╗ŃāćŃā╝Ńé┐Ńé╗Ńā│Ńé┐Ńā╝
- Õģ¼Õģ▒ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃāŚŃā®ŃāāŃāłŃāĢŃé®Ńā╝ŃāĀ
ńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘÕłČÕ║”Ńü¦Ńü»ŃĆüµāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃüīµÉŹÕŻŖŃüŚŃü¤Ńü©ŃüŹŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ń»äÕø▓ŃéäµÉŹÕ«│Ķ”ŵ©ĪŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«5ŃüżŃü«ńŁēń┤ÜŃü½ÕłåķĪ×ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
| Õ«óõĮōŃüīÕÅŚŃüæŃéŗµÉŹÕ«│Ńü«ń©ŗÕ║” | |||
| õĖĆĶł¼ńÜäŃü¬µÉŹÕ«│ | µĘ▒Õł╗Ńü¬µÉŹÕ«│ | ńē╣Ńü½µĘ▒Õł╗Ńü¬µÉŹÕ«│ | |
| ÕøĮµ░æŃüŖŃéłŃü│µ│Ģõ║║Ńü¬Ńü® | ń¼¼1ń┤Ü | ń¼¼2ń┤Ü | ń¼¼3ń┤Ü |
| ńżŠõ╝Üń¦®Õ║ÅŃā╗Õģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖ | ń¼¼2ń┤Ü | ń¼¼3ń┤Ü | ń¼¼4ń┤Ü |
| ÕøĮÕ«ČŃü«Õ«ēÕģ© | ń¼¼3ń┤Ü | ń¼¼4ń┤Ü | ń¼¼5ń┤Ü |
ŃüŠŃü¤ŃĆüńŁēń┤ÜŃüöŃü©Ńü«Õ«ÜńŠ®Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖŃü¦ŃüÖŃĆé
| ńŁēń┤Ü | Õ«ÜńŠ® |
| ń¼¼1ń┤Ü | ńĀ┤ÕŻŖŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüķ¢óõ┐éŃüÖŃéŗÕģ¼µ░æŃĆüµ│Ģõ║║ŃĆüŃüØŃü«õ╗¢ńĄäń╣öŃü«ÕÉłµ│ĢńÜäŃü¬µ©®Õł®Ńā╗Õł®µ©®ŃüīµÉŹŃü¬ŃéÅŃéīŃéŗŃüīŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«Õ«ēÕģ©ŃéäńżŠõ╝Üń¦®Õ║ÅŃĆüÕģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖŃü½Ńü»ÕĮ▒ķ¤┐Ńü«Ńü¬ŃüäõĖĆĶł¼ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé» |
| ń¼¼2ń┤Ü | ńĀ┤ÕŻŖŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüķ¢óõ┐éŃüÖŃéŗÕģ¼µ░æŃéäµ│Ģõ║║ŃĆüŃüØŃü«õ╗¢ńĄäń╣öŃü«ÕÉłµ│ĢńÜäŃü¬µ©®Õł®Ńā╗Õł®ńøŖŃü½ķćŹÕż¦Ńü¬µÉŹÕ«│Ńüīńö¤ŃüśŃéŗŃĆéŃüŠŃü¤Ńü»ŃĆüńżŠõ╝Üń¦®Õ║ÅŃü©Õģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖŃü½ÕŹ▒Õ«│ŃüīŃééŃü¤ŃéēŃüĢŃéīŃéŗŃüīŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«Õ«ēÕģ©Ńü½ÕĮ▒ķ¤┐Ńü«Ńü¬ŃüäõĖĆĶł¼ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé» |
| ń¼¼3ń┤Ü | ńĀ┤ÕŻŖŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüķ¢óõ┐éŃüÖŃéŗÕģ¼µ░æŃĆüµ│Ģõ║║ŃĆüŃüØŃü«õ╗¢ńĄäń╣öŃü«ÕÉłµ│ĢńÜäŃü¬µ©®Õł®Ńā╗Õł®µ©®Ńü½ķØ×ÕĖĖŃü½ķćŹÕż¦Ńü¬µÉŹÕ«│ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤Ńü»ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«Õ«ēÕģ©Ńü½ÕŹ▒Õ«│Ńüīńö¤ŃüśŃéŗķćŹĶ”üŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé» |
| ń¼¼4ń┤Ü | ńĀ┤ÕŻŖŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüńżŠõ╝Üń¦®Õ║ÅŃā╗Õģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖŃéÆĶæŚŃüŚŃüÅµÉŹŃü¬ŃüåŃĆéŃüŠŃü¤Ńü»ŃĆüÕøĮÕ«ČÕ«ēÕģ©Ńü½ķØ×ÕĖĖŃü½ķćŹĶ”üŃü¬µÉŹÕ«│ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüÖńē╣Ńü½ķćŹĶ”üŃü¬ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé» |
| ń¼¼5ń┤Ü | ńĀ┤ÕŻŖŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«Õ«ēÕģ©Ńü½ķØ×ÕĖĖŃü½ķćŹÕż¦Ńü¬µÉŹÕ«│ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüÖµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé» |
ŃüōŃü«ÕłåķĪ×ŃüöŃü©Ńü½ŃĆüķüĄÕ«łŃüÖŃü╣ŃüŹµāģÕĀ▒Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃü«Õ¤║µ║¢ŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü»ń¼¼2ń┤Üõ╗źõĖŖŃĆüķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü»ń¼¼3ń┤Üõ╗źõĖŖŃü«ńŁēń┤ÜŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃü«ŃüīõĖĆĶł¼ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆé
ńŁēń┤ÜÕÅ¢ÕŠŚŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕĮōÕ▒ĆŃü½ńŁēń┤ÜŃü«Ķć¬õĖ╗ńö│Ķ½ŗŃéÆŃüŚŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµ£ĆńĄéńÜäŃü½Ńü»Õģ¼Õ«ēķā©ŃüŗŃéēŃü«ÕÉłµäÅŃéÆÕŠŚŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘÕłČÕ║”Ńü¦Ńü»ŃĆüń¼¼2ń┤Üõ╗źõĖŖŃü»Ķ®ĢõŠĪµ®¤ķ¢óŃü½ŃéłŃéŗĶ®ĢõŠĪŃéÆÕÅŚŃüæŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘÕłČÕ║”Ńü½ķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗŃü©ńĮ░ķćæŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗµüÉŃéīŃüīŃüéŃéŗŃü¤Ńéüµ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕøĮŃü«Õ╝ĘÕłČńÜ䵩ֵ║¢ŃüĖŃü«ķü®ÕÉł
ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłĶŻĮÕōüŃüŖŃéłŃü│ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«µÅÉõŠøĶĆģŃüīµÅÉõŠøŃüÖŃéŗŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü»ŃĆüÕøĮŃü«Õ╝ĘÕłČńÜ䵩ֵ║¢Ńü½µ║¢µŗĀŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łń¼¼22µØĪ’╝ēŃĆéµÅÉõŠøĶĆģŃü»ŃĆüµé¬µäÅŃü«ŃüéŃéŗŃāŚŃāŁŃé░Ńā®ŃāĀŃéÆĶ©ŁńĮ«ŃüŚŃü”Ńü»Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü½µ¼ĀķÖźŃéäĶäåÕ╝▒µĆ¦ŃĆüŃüØŃü«õ╗¢Ńü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńÖ║Ķ”ŗŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüńø┤ŃüĪŃü½µÄ¬ńĮ«ŃéÆĶ¼øŃüśŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü½ÕæŖń¤źŃā╗ķ¢óõ┐éń«ĪĶĮäÕĮōÕ▒ĆŃü½ÕĀ▒ÕæŖŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
2021Õ╣┤9µ£łŃü½Ńü»ŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃéÆÕ»ŠĶ▒ĪŃü©ŃüŚŃü¤ŃĆīŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłĶŻĮÕōüŃé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻĶäåÕ╝▒µĆ¦ń«ĪńÉåĶ”ÅÕ«Ü’╝łńĮæń╗£õ║¦ÕōüÕ«ēÕģ©µ╝ŵ┤×ń«ĪńÉåĶ¦äÕ«Ü’╝ēŃĆŹŃüīµ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ŃĆüŃüōŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃééÕÅéńģ¦ŃüŚŃĆüÕ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Õ«¤ÕÉŹńÖ╗ķī▓Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗ
ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ń黵ğńČÜŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃĆüÕø║Õ«Üķø╗Ķ®▒Ńā╗µÉ║ÕĖ»ķø╗Ķ®▒Ńü«ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ń黵ğńČܵēŗńČÜŃüŹŃĆüµāģÕĀ▒Õģ▒µ£ēŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃĆüŃéżŃā│Ńé╣Ńé┐Ńā│ŃāłŃāĪŃāāŃé╗Ńā╝ŃéĖŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü¬Ńü®ŃéÆŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü½µÅÉõŠøŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝Ńü«Õ«¤ÕÉŹńÖ╗ķī▓ŃéÆŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃüīÕ«¤ÕÉŹńÖ╗ķī▓ŃéÆŃüŚŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”Ńü»Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü»ŃĆüŃā”Ńā╝ŃéČŃā╝ŃüīńÖ║õ┐ĪŃüÖŃéŗµāģÕĀ▒Ńüīµ│ĢÕŠŗŃéÆńŖ»ŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüŗŃéÆÕ»®ĶŁ░ŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁķüŗÕ¢ČĶĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖ
ķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁŃü«ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü»ŃĆüŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü½Ķ¬▓ŃüĢŃéīŃü¤Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻÕ»ŠńŁ¢ŃéÆĶĪīŃüåŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬Õ»ŠńŁ¢ŃééÕ┐ģĶ”üŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
- ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃéäŃāćŃā╝Ńé┐ŃāÖŃā╝Ńé╣Ńü«Õ«Üµ£¤ńÜäŃü¬ŃāÉŃāāŃé»ŃéóŃāāŃāŚŃéÆÕÅ¢Ńéŗ
- Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃéżŃā│ŃéĘŃāćŃā│ŃāłŃüĖŃü«Õ»ŠÕ┐£Ķ©łńö╗Ńü«ńŁ¢Õ«Ü
- Õ╣┤Õ║”Õ«ēÕģ©Ķ®ĢõŠĪ
- ŃāćŃā╝Ńé┐ŃāŁŃā╝Ńé½Ńā®ŃéżŃé╝Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│
ŃāćŃā╝Ńé┐ŃāŁŃā╝Ńé½Ńā®ŃéżŃé╝Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│’╝ÜŃāćŃā╝Ńé┐Ńüīńö¤µłÉŃüĢŃéīŃü¤ÕøĮŃü«ÕøĮÕóāÕåģŃü¦ŃāćŃā╝Ńé┐ŃéÆõ┐ØÕŁśŃā╗Õć”ńÉåŃüÖŃéŗŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü«ŃüōŃü©
2021Õ╣┤9µ£łŃü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁÕ«ēÕģ©õ┐ØĶŁĘµØĪõŠŗŃĆŹŃü¦Ńü»ŃĆüķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁŃü«ń«ĪńÉåŃĆüĶ¬ŹÕ«ÜŃĆüķüŗÕ¢ČĶĆģŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü¬Ńü®ŃéÆŃüĢŃéēŃü½ÕģĘõĮōńÜäŃü½Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃüōŃüĪŃéēŃééÕÅéńģ¦ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ń«ĪńÉåŃā╗Ńā¼Ńé╣ŃāØŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃü«µ¦ŗń»ē
ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü½µ▒éŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«Ńü½Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖ’╝łń¼¼21µØĪ’╝ēŃĆé
- Õ«ēÕģ©ń«ĪńÉåÕłČÕ║”ŃéäµōŹõĮ£Ķ”Åń©ŗŃü«ÕłČÕ«Ü
- ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»Ńü«Õ«ēÕģ©Ķ▓¼õ╗╗ĶĆģŃü«ńó║Õ«Ü
- Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃéżŃā│ŃéĘŃāćŃā│ŃāłŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃā¼Ńé╣ŃāØŃā│Ńé╣Ķ©łńö╗Ńü«ń½ŗµĪłŃā╗µŖĆĶĪōńÜäµÄ¬ńĮ«Ńü«µĢ┤ÕéÖ
- ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»Ńü«ńøŻĶ”¢µŖĆĶĪōŃü«Õ░ÄÕģźŃĆüŃāŁŃé░Ńü«õ┐ØÕŁś’╝łÕ░æŃü¬ŃüÅŃü©Ńéé6ŃāĄµ£ł’╝ē
- ŃāćŃā╝Ńé┐ÕłåķĪ×ŃĆüķćŹĶ”üŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«ŃāÉŃāāŃé»ŃéóŃāāŃāŚŃā╗µÜŚÕÅĘÕī¢Ńü¬Ńü®Ńü«õ┐ØĶŁĘµÄ¬ńĮ«
ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«Ķ”ÅÕ«Ü

ńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘÕłČÕ║”Ńü¦µ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗŃé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻĶ”üõ╗ČŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµś»µŁŻÕæĮõ╗żŃü©ĶŁ”ÕæŖŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕæĮõ╗żŃéƵŗÆÕÉ”ŃĆüŃééŃüŚŃüÅŃü»ŃāŹŃāāŃāłŃā»Ńā╝Ńé»Ńü«Õ«ēÕģ©ŃéÆĶäģŃüŗŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆü1õĖćÕģāõ╗źõĖŖ10õĖćÕģāõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃéƵö»µēĢŃéÅŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüńø┤µÄźŃü«Ķ▓¼õ╗╗ĶĆģŃü½Ńü»ŃĆü5ÕŹāÕģāõ╗źõĖŖ5õĖćÕģāõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüµé¬µäÅŃü«ŃüéŃéŗŃāŚŃāŁŃé░Ńā®ŃāĀŃéÆĶ©ŁńĮ«ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃéäĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«µ¼ĀķÖźŃéäŃé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃāøŃā╝Ńā½Ńü¬Ńü®Ńü«Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”µÄ¬ńĮ«ŃéÆĶ¼øŃüśŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü¬Ńü®Ńü½Ńé鵜»µŁŻÕæĮõ╗żŃü©ĶŁ”ÕæŖŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃĆüŃüØŃéīŃéƵŗÆÕÉ”ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»ńĮ░ķćæŃü«µö»µēĢŃüäŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ķüĢÕÅŹŃü«ÕåģÕ«╣Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ńĮ░ķćæŃü«ķćæķĪŹŃü»ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüŃé”Ńé¦Ńā¢ŃéĄŃéżŃāłŃü«ķ¢ēķÄ¢ŃéäÕ¢ČµźŁĶ©▒ÕÅ»Ńü«µŖ╣µČłŃĆüķ¢ŗµźŁµźŁÕŗÖŃü«Õü£µŁóŃü¬Ńü®ŃéÆÕæĮŃüśŃéēŃéīŃéŗµüÉŃéīŃééŃüéŃéŗŃü¤Ńéüµ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéķüÄÕÄ╗Ńü½Ńü»ŃĆüķüĢÕÅŹŃü½ŃéłŃéŖńĮ░ķćæÕć”ńĮ░ŃĆüµŗģÕĮōĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüńĄéĶ║½Ńü½ŃéÅŃü¤ŃéŖÕÉīµźŁŃüĖŃü«ÕŠōõ║ŗŃéÆń”üµŁóŃüĢŃéīŃü¤Ńé▒Ńā╝Ńé╣ŃééŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃüĖŃü«Õ»ŠńŁ¢Ńü»µ¼ĀŃüŗŃüøŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīÕÅ¢ŃéŗŃü╣ŃüŹŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢÕ»ŠńŁ¢

õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü»ĶżćķøæŃü¬Ńü¤ŃéüŃĆüõĮĢŃüŗŃéēµēŗŃéÆŃüżŃüæŃü”ŃüäŃüäŃüŗŃéÅŃüŗŃéēŃü¬Ńüäµ¢╣ŃééŃüäŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīÕÅ¢ŃéŗŃü╣ŃüŹÕ»ŠńŁ¢ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķā©ķ¢ĆŃéäDXķ¢óķĆŻķā©ķ¢ĆŃü©Ńü«ķĆŻµÉ║ŃüÖŃéŗõĮōÕłČŃéƵĢ┤ŃüłŃéŗ
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüķüŗńö©ŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü«µ¦ŗń»ēŃéäÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒ń«ĪńÉåĶ”ÅÕ«ÜŃü«ńŁ¢Õ«ÜŃā╗Ķ┐ĮÕŖĀŃü¬Ńü®ŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘÕłČÕ║”Ńü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüĶć¬ńżŠŃü«ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”µŖĆĶĪōńÜäŃü¬µÄ¬ńĮ«Ńüīµ¼ĀŃüŗŃüøŃüŠŃüøŃéōŃĆé
µ│ĢÕŗÖŃéäńĘÅÕŗÖķā©ķ¢ĆŃü¬Ńü®ŃüīÕĆŗŃĆģŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüµāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķā©ķ¢ĆŃéäDXķ¢óķĆŻķā©ķ¢ĆŃü©ŃééķĆŻµÉ║ŃüÖŃéŗõĮōÕłČŃéƵĢ┤ŃüłŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Ķć¬ńżŠŃüīõ┐ص£ēŃüÖŃéŗÕÉäŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃüīŃü®Ńü«ńŁēń┤ÜŃü½ÕÉłĶć┤ŃüÖŃéŗŃüŗŃéÆÕłżÕ«ÜŃüÖŃéŗ
ŃüŠŃüÜŃĆüĶć¬ńżŠŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü«ńŁēń┤ÜÕłżÕ«ÜŃéÆŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«ńŁēń┤ÜŃü½ÕÉłŃéÅŃüøŃĆüÕÉäķā©ķ¢ĆŃü¦ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃü½ÕēćŃüŻŃü¤Õ»ŠÕ┐£ŃéÆŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéµ│ĢÕŗÖŃéäńĘÅÕŗÖŃĆüŃā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåķā©ķ¢ĆŃü¦Ńü»ŃĆüµ│ĢŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗĶ”ÅÕ«ÜŃéäķüŗńö©Ńü«Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃéäµö╣Õ«ÜŃĆüµāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃā╗DXķ¢óķĆŻķā©ķ¢ĆŃü¦Ńü»ŃĆüµŖĆĶĪōķØóŃü¦Ńü«Õ»ŠÕ┐£ŃüīÕ┐ģĶ”üŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü«Õ»ŠÕ┐£Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µ│ĢÕŗÖŃéäńĘÅÕŗÖŃĆüŃā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåķā©ķ¢Ć
ńŁēń┤ÜŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗķĀģŃü©Ķć¬ńżŠŃü«ń«ĪńÉåńŖȵ│üŃĆüµāģÕĀ▒Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻõĮōÕłČŃéƵ»öĶ╝āŃüŚŃĆüĶ”ÅÕ«ÜŃü«Ķ┐ĮÕŖĀŃéäķüŗńö©õĮōÕłČŃü«Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃéÆŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃüŗŃéƵż£Ķ©ÄŃüŚŃĆüÕłČÕ║”Ńü«µĢ┤ÕéÖŃéäµö╣µŁŻŃü¬Ńü®ŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ńŁēń┤ÜŃüīń¼¼2ń┤Üõ╗źõĖŖŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕĮōÕ▒ĆŃüĖŃü«Õ▒ŖŃüæÕć║ŃééĶĪīŃéÅŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéĶć¬ńżŠŃüīķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁķüŗÕ¢ČĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüń¼¼3ń┤Üõ╗źõĖŖŃü«ńŁēń┤Üõ┐ØĶŁĘĶ¬ŹĶ©╝ÕÅ¢ÕŠŚŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüŃāćŃā╝Ńé┐ŃāŁŃā╝Ńé½Ńā®ŃéżŃé╝Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│Ķ”ÅÕłČŃüĖŃü«Õ»ŠÕ┐£ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃüĖŃü«Õ«Üµ£¤ńÜäŃü¬µāģÕĀ▒Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻŃü«µĢÖĶé▓Ńā╗µŖĆĶĪōŃāłŃā¼Ńā╝ŃāŗŃā│Ńé░Ńü¬Ńü®ŃéÆĶĪīŃéÅŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü¬Ńü®ŃĆüÕ»ŠÕ┐£ŃüÖŃü╣ŃüŹõ║ŗķĀģŃüīÕżÜŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®µ¢ĮĶ©ŁķüŗÕ¢ČĶĆģŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüķĪ¦ÕĢÅÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü¬Ńü®Ńü©ńøĖĶ½ćŃüŚŃĆüÕ»ŠÕ┐£µ¢╣ķćØŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüŖŃüÅŃü©Õ«ēÕ┐āŃü¦ŃüÖŃĆé
Ķ┐æÕ╣┤ŃĆüõĖŁÕøĮŃü¦Ńü»Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻķ¢óķĆŻŃü«ÕłČÕ║”ŃüīńČÜŃĆģŃü©µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüŃā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåķā©ķ¢ĆŃü¦Ńü»ŃĆüµ¢░ŃüŚŃüäĶ”ÅÕłČŃü½ÕÉłŃéÅŃüøŃü¤Ńā¬Ńé╣Ńé»Õ»ŠÕ┐£ŃüīÕ┐ģĶ”üŃü½Ńü¬ŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
µāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃā╗DXķ¢óķĆŻķā©ķ¢Ć
µāģÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀķā©ŃéäDXķ¢óķĆŻķā©ķ¢ĆŃü¦Ńü»ŃĆüńŁēń┤ÜŃü½ÕÉłŃéÅŃüøŃü¤Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻõ┐ØĶŁĘµÄ¬ńĮ«Ńü«ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀÕ░ÄÕģźŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃüÜŃü»ŃĆüĶć¬ńżŠŃü«µŚóÕŁśŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü«Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻõ┐ØĶŁĘµÄ¬ńĮ«ŃéƵĢ┤ńÉåŃüŚŃĆüõĖŹĶČ│ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü½ÕŹ│ŃüŚŃü¤ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃéÆńĄäŃü┐ĶŠ╝Ńü┐ŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│Ģõ╗źÕż¢Ńü½ŃééŃĆüŃāćŃā╝Ńé┐ŃāŁŃā╝Ńé½Ńā®ŃéżŃé╝Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│Ķ”ÅÕłČŃéäĶČŖÕóāÕłČķÖÉŃĆüŃé¼ŃāÉŃāĪŃā│ŃāłŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ńü¬Ńü®Ńü½ŃééÕ»ŠÕ┐£ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéõĖŁÕøĮÕøĮÕż¢ŃüĖŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ŃāćŃā╝Ńé┐ŃéÆĶ╗óķĆüŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü«ŃüŗŃéƵŖŖµÅĪŃüŚŃĆüĶć¬ńżŠŃü«ŃāćŃā╝Ńé┐ÕÅ¢ÕŠŚŃéäõ┐Øń«ĪŃü«ńŖȵ│üŃéÆĶ”ŗńø┤ŃüÖÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüĶ”ÅÕ«ÜŃü«µö╣Õ«ÜŃüĀŃüæŃü½ńĢÖŃüŠŃéēŃüÜŃĆüµŖĆĶĪōńÜäŃü¬õ┐ØĶŁĘµÄ¬ńĮ«ŃéÆĶĪīŃéÅŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃĆüÕ»ŠÕ┐£ķā©ńĮ▓Ńü«ķĆŻµÉ║Ńüīµ¼ĀŃüŗŃüøŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü©ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«ĶČŖÕóāń¦╗Ķ╗óĶ”ÅÕłČŃü«ńĘ®ÕÆī’╝ł2024Õ╣┤3µ£ł’╝ē
õĖŁÕøĮŃü¦ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ŃéÆÕ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«ĶČŖÕóāń¦╗Ķ╗óĶ”ÅÕłČŃü»ķĢĘÕ╣┤Ńü«µćĖµĪłõ║ŗķĀģŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé2017Õ╣┤Ńü«ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│Ģµ¢ĮĶĪīõ╗źķÖŹŃĆüÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ķ”ÅÕłČŃü½ŃéłŃéŖÕżÜŃüÅŃü«õ╝üµźŁŃüīÕ»ŠÕ┐£Ńü½Ķŗ”µģ«ŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü2024Õ╣┤3µ£łŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬Ķ╗óµÅøńé╣ŃéÆĶ┐ÄŃüłŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õĖŁÕøĮµö┐Õ║£Ńü»ńĄīµĖłµ┤╗µĆ¦Õī¢Ńü©Õż¢Ķ│ćĶ¬śĶć┤Ńü«Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēĶ”ÅÕłČńĘ®ÕÆīŃü½ĶĖÅŃü┐ÕłćŃéŖŃĆüõ╝üµźŁŃü«Ķ▓ĀµŗģŃéÆÕż¦Õ╣ģŃü½Ķ╗ĮµĖøŃüÖŃéŗµ¢░Ńü¤Ńü¬Ķ”ÅÕ«ÜŃéÆÕ░ÄÕģźŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüÕģ©Ńü”Ńü«Ńé▒Ńā╝Ńé╣Ńü¦Ķ”ÅÕłČŃüīńĘ®ÕÆīŃüĢŃéīŃü¤ŃéÅŃüæŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕøĮÕ«ČÕ«ēÕģ©ŃéäķćŹĶ”üŃéżŃā│ŃāĢŃā®Ńü½ķ¢óŃéÅŃéŗÕłåķćÄŃü¦Ńü»õŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”ÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ķ”ÅÕłČŃüīńČŁµīüŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüĶ”ÅÕłČńĘ®ÕÆīŃü«µ”éĶ”üŃü©ŃĆüńĘ®ÕÆīŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃü¬ŃüäŃé▒Ńā╝Ńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗķ¢óķĆŻµ│Ģõ╗żŃü«µ”éĶ”ü
õĖŁÕøĮŃü»2017Õ╣┤Ńü½ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃéƵ¢ĮĶĪīŃüŚŃĆüŃāćŃā╝Ńé┐ĶČŖÕóāń¦╗Ķ╗óŃü½ÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ķ”ÅÕłČŃéÆĶ©ŁŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéķćŹĶ”üŃāćŃā╝Ńé┐Ńü»Õ«ēÕģ©Ķ®ĢõŠĪŃüīÕ┐ģķĀłŃü¦ŃĆüÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒ŃééÕ«ēÕģ©Ķ®ĢõŠĪŃā╗Ķ¬ŹĶ©╝ÕÅ¢ÕŠŚŃā╗µ©Öµ║¢Õźæń┤äŃü«ŃüäŃüÜŃéīŃüŗŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
2024Õ╣┤3µ£ł22µŚźŃĆüÕøĮÕ«ČŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłµāģÕĀ▒Õ╝üÕģ¼Õ«żŃü»ŃĆīŃāćŃā╝Ńé┐ĶČŖÕóāµĄüÕŗĢŃü«õ┐āķĆ▓Ńü©Ķ”Åń»äŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ”ÅÕ«ÜŃĆŹŃéÆÕģ¼ÕĖāŃā╗µ¢ĮĶĪīŃüŚŃĆüĶ”ÅÕłČŃéÆÕż¦Õ╣ģńĘ®ÕÆīŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńĄīµĖłµłÉķĢĘŃü©Õż¢Ķ│ćĶ¬śĶć┤ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü¤µÄ¬ńĮ«Ńü¦ŃüÖŃĆé
µ¢░Ķ”ÅÕ«ÜŃü«õĖ╗Ńü¬ńĘ®ÕÆīÕåģÕ«╣Ńü»õ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖŃü¦ŃüÖŃĆé
- ÕøĮķÜøĶ▓┐µśōŃĆüĶČŖÕóāķģŹķĆüŃĆüÕŁ”ĶĪōÕŹöÕŖøńŁēŃü¦ÕÅÄķøåŃüĢŃéīŃü¤ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü¦ŃĆüÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒Ńā╗ķćŹĶ”üŃāćŃā╝Ńé┐ŃéÆÕɽŃüŠŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü»Õ¤¤Õż¢ń¦╗Ķ╗óŃü«ÕēŹµÅɵØĪõ╗ČÕģŹķÖż
- µ│Ģõ╗żŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕŖ┤ÕāŹń«ĪńÉåŃü«Ńü¤ŃéüŃü«ÕŠōµźŁÕōĪÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒Ńü«Õ¤¤Õż¢µÅÉõŠøŃüīÕģŹķÖż’╝łŃé░ŃāŁŃā╝ŃāÉŃā½õ╝üµźŁŃü«Ķ▓ĀµŗģĶ╗ĮµĖø’╝ē
- õĖĆĶł¼õ╝üµźŁŃü«Õ╣┤ķ¢ō10õĖćõ║║µ£¬µ║ĆŃü«ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒Õ¤¤Õż¢µÅÉõŠøŃü»ÕēŹµÅɵØĪõ╗ČÕģŹķÖż
- ķćŹĶ”üŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«Õłżµ¢ŁÕ¤║µ║¢µśÄńó║Õī¢’╝łķ¢óķĆŻķā©ķ¢ĆŃüŗŃéēµśÄńó║Ńü½µīćÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüæŃéīŃü░Õ«ēÕģ©Ķ®ĢõŠĪõĖŹĶ”ü’╝ē
ŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõĖŁÕøĮŃü¦ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ŃéÆĶĪīŃüåõ╝üµźŁŃü«ŃāćŃā╝Ńé┐ĶČŖÕóāń¦╗Ķ╗óŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ▓ĀµŗģŃüīÕż¦Õ╣ģŃü½Ķ╗ĮµĖøŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ķ”ÅÕłČńĘ®ÕÆīŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃü¬ŃüäŃé▒Ńā╝Ńé╣
µ¢░Ķ”ÅÕ«ÜŃü½ŃéłŃéŗńĘ®ÕÆīµÄ¬ńĮ«Ńü½Ńééķ¢óŃéÅŃéēŃüÜŃĆüķćŹĶ”üŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«Õ¤¤Õż¢ń¦╗Ķ╗óŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»õŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”ÕĮōÕ▒ĆŃü½ŃéłŃéŗÕ«ēÕģ©Ķ®ĢõŠĪŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕ╣┤ķ¢ōń┤»Ķ©ł100õĖćõ║║õ╗źõĖŖŃü«ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒Ńéä1õĖćõ║║õ╗źõĖŖŃü«µ®¤ÕŠ«Ńü¬ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒ŃéÆÕ¤¤Õż¢µÅÉõŠøŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃééŃĆüÕŠōµØźķĆÜŃéŖÕ«ēÕģ©Ķ®ĢõŠĪŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Õ╣┤ķ¢ōń┤»Ķ©ł10õĖćõ║║õ╗źõĖŖ100õĖćõ║║µ£¬µ║ĆŃü«ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒ŃéäÕ╣┤ķ¢ō1õĖćõ║║µ£¬µ║ĆŃü«µ®¤ÕŠ«Ńü¬ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒ŃéÆÕ¤¤Õż¢µÅÉõŠøŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒ĶČŖÕóāµ©Öµ║¢Õźæń┤äŃü«ńĘĀńĄÉŃā╗Õ▒ŖÕć║ŃüŠŃü¤Ńü»ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒õ┐ØĶŁĘĶ¬ŹĶ©╝Ńü«ÕÅ¢ÕŠŚŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ķćŹĶ”üµāģÕĀ▒ŃéżŃā│ŃāĢŃā®ķüŗÕ¢ČĶĆģŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµ¢░Ķ”ÅÕ«ÜŃü«ńĘ®ÕÆīµÄ¬ńĮ«Ńü«ķü®ńö©ń»äÕø▓ŃüīķÖÉÕ«ÜńÜäŃü¦ŃüÖŃĆéķø╗ÕŖøŃĆüķĆÜõ┐ĪŃĆüķćæĶ׏ŃĆüõ║żķĆÜńŁēŃü«ķćŹĶ”üŃéżŃā│ŃāĢŃā®õ║ŗµźŁĶĆģŃü»Õ╝ĢŃüŹńČÜŃüŹÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õ«ēÕģ©Ķ®ĢõŠĪŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ”ÅÕłČńĘ®ÕÆīŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃééŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ńČÖńČÜŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- ÕĆŗõ║║ŃüĖŃü«õ║ŗÕēŹÕæŖń¤źŃü©ÕĆŗÕłźÕÉīµäÅŃü«ÕÅ¢ÕŠŚ
- ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒õ┐ØĶŁĘÕĮ▒ķ¤┐Ķ®ĢõŠĪŃü«Õ«¤µ¢Į
- ŃāćŃā╝Ńé┐Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻÕ»ŠńŁ¢Ńü«Õ«¤µ¢Į
- ķü®ÕłćŃü¬Ķ©śķī▓ń«ĪńÉåŃü©õ┐ØÕŁśŃĆĆŃü¬Ńü®
õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü«Ķ”ÅÕłČõĮōń│╗Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕøĮÕ«ČÕ«ēÕģ©ŃéäķćŹĶ”üŃéżŃā│ŃāĢŃā®Ńü½ķ¢óŃéÅŃéŗÕłåķćÄŃü¦Ńü»ÕŠōµØźŃü«ÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ķ”ÅÕłČŃüīńČŁµīüŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╝üµźŁŃü»Ķć¬ńżŠŃü«õ║ŗµźŁńē╣µĆ¦Ńü©ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«µĆ¦Ķ│¬ŃéƵģÄķćŹŃü½Ķ®ĢõŠĪŃüŚŃü¤õĖŖŃü¦ķü®ÕłćŃü¬Õ»ŠÕ┐£ŃéÆÕÅ¢ŃéēŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝ÜõĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢÕ»ŠÕ┐£Ńü»Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü½ŃüöńøĖĶ½ćŃéÆ

õĖŁÕøĮŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü©Ńü»ŃĆüõĖŁÕøĮŃü«ÕøĮÕ«ČÕ«ēÕģ©õ┐ØķÜ£Ńü«Ńü¤ŃéüŃü½ŃüżŃüÅŃéēŃéīŃü¤ÕłČÕ║”Ńü¦ŃüÖŃĆéŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüµ│ĢÕŗÖķā©ŃéäńĘÅÕŗÖķā©Ńü½ŃéłŃéŗĶ”ÅÕ«ÜŃü«µö╣Õ«ÜŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüµŖĆĶĪōńÜäŃü¬õ┐ØĶŁĘµÄ¬ńĮ«Ńü¬Ńü®ŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃ鯵│ĢŃüīµ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü”õ╗źķÖŹŃĆüŃĆīŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłĶŻĮÕōüŃé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻĶäåÕ╝▒µĆ¦ń«ĪńÉåĶ”ÅÕ«ÜŃĆŹŃéäŃĆīŃéĄŃéżŃāÉŃā╝Ńé╗ŃéŁŃāźŃā¬ŃāåŃéŻÕ»®µ¤╗Õ╝üµ│Ģ’╝łÕøĮÕ«ČÕ«ēÕģ©Õ»®µ¤╗ÕłČÕ║”ŃéÆÕģĘõĮōÕī¢ŃüÖŃéŗÕłČÕ║”’╝ēŃĆŹŃü¬Ńü®ŃĆüŃāćŃā╝Ńé┐Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗŃüīńČÜŃĆģŃü©ÕłČÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗŃü©ńĮ░ķćæŃéäŃé”Ńé¦Ńā¢ŃéĄŃéżŃāłŃü«ķ¢ēķÄ¢ŃĆüÕ¢ČµźŁĶ©▒ÕÅ»Ńü«µŖ╣µČłŃü¬Ńü®Ńü«ĶĪīµö┐Õć”ÕłåŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗµüÉŃéīŃüīŃüéŃéŗŃü¤Ńéüµ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéõĖŁÕøĮŃü¦õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃā╗õ╗ŖÕŠīõ║łÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüõĖŁÕøĮŃü«µ│ĢÕŠŗŃü½Ķ®│ŃüŚŃüäÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüĖńøĖĶ½ćŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆŃüŖŃüÖŃüÖŃéüŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃā╗ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃā╗ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńü½Õ╝ĘŃü┐ŃéƵīüŃüżµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéõĖŁÕøĮŃéäŃéóŃāĪŃā¬Ńé½ŃĆüEUĶ½ĖÕøĮŃü¬Ńü®õĖ¢ńĢīÕÉäÕøĮŃü«µĪłõ╗ČŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵥ĘÕż¢Ńü¦ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńüīõ╝┤ŃüåŃü¤ŃéüŃĆüńĄīķ©ōĶ▒ŖÕ»īŃü¬Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ŃéłŃéŗŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃüīµ¼ĀŃüŗŃüøŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«µ│ĢÕŠŗŃéäĶ”ÅÕłČŃü½ń▓ŠķĆÜŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüõĖ¢ńĢīÕÉäÕøĮŃü«µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü©ķĆŻµÉ║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü«ÕÅ¢µē▒ÕłåķćÄ’╝ÜÕøĮķÜøµ│ĢÕŗÖŃā╗µĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: õĖŁÕøĮÕøĮķÜøµ│ĢÕŗÖµĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ