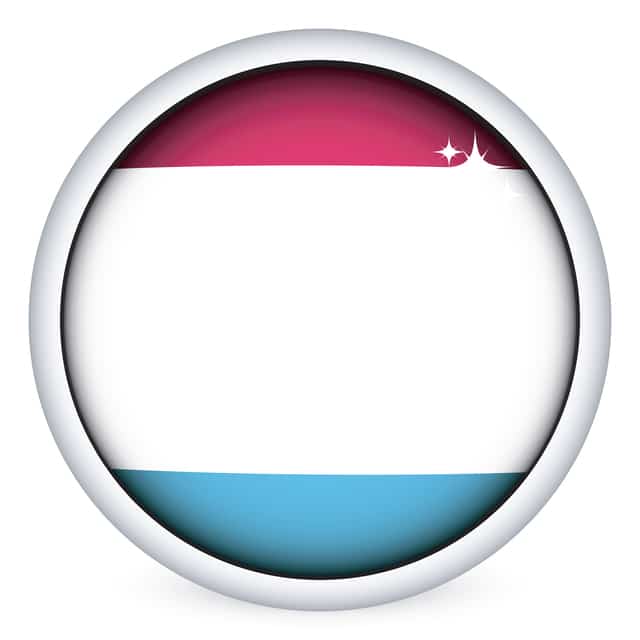„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģśįĎś≥ē„ÉĽŚ•ĎÁīĄś≥ē„ā팾ĀŤ≠∑Ś£ę„ĀĆŤß£Ť™¨

„ÄĆťõĽŚ≠źŚõĹŚģ∂„Äć„Ā®„Āó„Ā¶šłĖÁēĆÁöĄ„ĀęÁü•„āČ„āĆ„āč„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘŚÖĪŚíĆŚõĹÔľąšĽ•šłč„ÄĆ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ÄćԾȄÄā„ĀĚ„ĀģŚÖąťÄ≤ÁöĄ„Ā™„Éá„āł„āŅ„ÉęÁ§ĺšľö„ĀģŚüļÁõ§„āíśĒĮ„Āą„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀĆ„ÄĀśüĒŤĽü„Āč„Ā§ŚźąÁźÜÁöĄ„Ā™ś≥ēšĹďÁ≥Ľ„Āß„Āô„Äā„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„Āß„Āģ„Éď„āł„Éć„āĻŚĪēťĖč„ā휧úŤ®é„Āē„āĆ„āčśó•śú¨„ĀģÁĶĆŚĖ∂ŤÄÖ„āĄś≥ēŚčôśčÖŚĹďŤÄÖ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„ÄĀÁŹĺŚúį„Āß„ĀģŚ•ĎÁīĄŚģüŚčô„Āģś†ĻŚĻĻ„āí„Ā™„Āô„ÄĆśįĎś≥ē„ÉĽŚ•ĎÁīĄś≥ē„Äć„ĀģÁźÜŤß£„ĀĮ„ÄĀťĀŅ„ĀĎ„Ā¶ťÄö„āĆ„Ā™„ĀĄťá捶Ā„Ā™Ť™≤ť°Ć„Āß„Āô„Äā
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģŚ•ĎÁīĄś≥ē„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™ś†Ļśč†„ĀĮ„ÄĀ2002ŚĻī„ĀęśĖĹŤ°Ć„Āē„āĆ„Āü„ÄĆŚāĶŚčôś≥ēÁ∑ŹŤęĖ (Law of Obligations Act„ÄĀšĽ•šłč„ÄĆLOA„Äć)„Äć„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģś≥ēŚĺč„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģśąźÁęč„Āč„āČŚĪ•Ť°Ć„ÄĀťĀēŚŹć„ÄĀśēĎśłąśé™ÁĹģ„ĀęŤá≥„āč„Āĺ„Āß„āíŚĆÖśč¨ÁöĄ„ĀꍶŹŚĺč„Āô„āč„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘÁßĀś≥ē„Āģšł≠ś†ł„Ā®„Ā™„āčś≥ēŚÖł„Āß„Āô„ÄāLOA„ĀĮ„ÄĀ„Éá„āł„āŅ„ÉęÁĶĆśłą„Āģ„ÉÄ„ā§„Éä„Éü„āļ„Ɇ„ĀęŚĮĺŚŅú„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„ÄĀEUśĆᚼ§„āĄŚõĹťöõÁöĄ„Ā™ŚéüŚČáÔľąUNIDROITŚõĹťöõŚēÜšļ茕ĎÁīĄŚéüŚČá„Ā™„Ā©ÔľČ„āíŤČ≤śŅÉ„ĀŹŚŹćśė†„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚéüŚČá„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„ĀüśüĒŤĽü„Ā™„āĘ„Éó„É≠„Éľ„ÉĀ„āíÁČĻŚĺī„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ÁČĻ„Āęťá捶Ā„Ā™„Āģ„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„Ā®„āāŚÖĪťÄö„Āô„āč„ÄĆšľĀś•≠ťĖĖŚľēÔľąB2BԾȄÄć„Ā®„ÄĆś∂ąŤ≤ĽŤÄÖŚŹĖŚľēÔľąB2CԾȄÄć„ĀģŚĆļŚą•„Āß„Āô„ÄāB2BŚ•ĎÁīĄ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮŚĹďšļčŤÄÖťĖď„ĀģŚ•ĎÁīĄ„ĀģŤá™ÁĒĪ„ĀĆŚļÉ„ĀŹŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„ā蚳ĜĖĻ„ÄĀB2CŚ•ĎÁīĄ„Āß„ĀĮŚé≥ś†ľ„Ā™ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖšŅĚŤ≠∑Ť¶ŹŚČá„ĀĆťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„Āß„Āģ„Éď„āł„Éć„āĻŚĪēťĖč„Āꚳ挏Įś¨†„Ā™LOA„ĀģŚüļśú¨śßčťÄ†„āíŤß£Ť™¨„Āô„āč„Ā®„Ā®„āā„Āę„ÄĀśó•śú¨„ĀģÁĶĆŚĖ∂ŤÄÖ„āĄś≥ēŚčôśčÖŚĹďŤÄÖ„ĀĆÁČĻ„Āęś≥®śĄŹ„Āô„ĀĻ„Āć„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®„Āģťá捶Ā„Ā™ÁõłťĀēÁāĻ„ĀęÁĄ¶ÁāĻ„āíŚĹď„Ā¶„Ā¶Ťß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀŚ•ĎÁīĄŤß£ťô§„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„āĄ„ÄĀB2BŚ•ĎÁīĄ„Āę„Āä„ĀĎ„āčšłćŚÖ¨ś≠£śĚ°ť†Ö„ĀģśČĪ„ĀĄ„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āč„āĘ„Éó„É≠„Éľ„ÉĀ„ĀĆŚŹĖ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚģüŚčôšłä„ÄĀś•Ķ„āĀ„Ā¶ťá捶Ā„Āß„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘś≥ē„ĀģŤß£ťáą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶śĪļŚģöÁöĄ„Ā™ŚĹĻŚČ≤„āíśěú„Āü„Āô**„ÄĆŤ™†Śģü„ĀģŚéüŚČá„Äć„Ā®„ÄĆŚźąÁźÜśÄß„ĀģŚéüŚČá„Äć**„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™Śą§šĺč„āíšļ§„Āą„Ā™„ĀĆ„āČ„ĀĚ„ĀģŚģüśÖč„ĀęŤŅę„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘŚ•ĎÁīĄś≥ē„ĀģŚüļÁõ§„ÄĆŚāĶŚčôś≥ēÁ∑ŹŤęĖÔľąLOAԾȄÄć
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģśįĎś≥ē„ÉĽŚ•ĎÁīĄś≥ē„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚ§ö„ĀŹ„ĀĆ2002ŚĻī7śúą1śó•„ĀęśĖĹŤ°Ć„Āē„āĆ„Āü„ÄĆŚāĶŚčôś≥ēÁ∑ŹŤęĖÔľąLOA„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘŤ™ěÔľöV√Ķla√ĶigusseadusԾȄÄć„ĀęťõÜÁīĄ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģś≥ēŚÖł„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„Āč„āČÁĒü„Āė„āčŚāĶŚčôťĖĘšŅā„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀšłćś≥ēŤ°ĆÁāļ„āĄšłćŚĹ©Śĺó„Ā™„Ā©„ÄĀŚāĶŚčôÔľąObligationԾȌ֮Ťą¨„ā퍶ŹŚĺč„Āô„āčŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™ś≥ēŚĺč„Āß„Āô„Äā
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀĮEUŚä†ÁõüŚõĹ„Āß„Āā„āč„Āü„āĀ„ÄĀLOA„ĀĮEU„ĀģŚźĄÁ®ģśĆᚼ§ÔľąÁČĻ„Āęś∂ąŤ≤ĽŤÄÖšŅĚŤ≠∑śĆᚼ§„āĄťõĽŚ≠źŚēÜŚŹĖŚľēśĆᚼ§„Ā™„Ā©ÔľČ„ĀģŚÜÖŚģĻ„āíŚõĹŚÜÖś≥ēŚĆĖ„Āô„āčŚĹĻŚČ≤„āāśčÖ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśßčťÄ†„ĀĮ„ÉČ„ā§„ÉĄśįĎś≥ē„Ā™„Ā©„ĀģŚ§ßťôłś≥ē„ĀģŚľ∑„ĀĄŚĹĪťüŅ„ā팏ó„ĀĎ„Ā§„Ā§„āā„ÄĀŚõĹťöõÁöĄ„Ā™ŚŹĖŚľēŚģüŚčô„āĄ„ā≥„ÉĘ„É≥„É≠„Éľ„ĀģŤ¶ĀÁī†„āāŚŹĖ„āäŚÖ•„āĆ„Āü„ÄĀŤŅĎšĽ£ÁöĄ„Āč„Ā§śüĒŤĽü„Ā™ŚÜÖŚģĻ„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„Āģś≥ēŚĺč„ĀĮ„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģŚÖ¨ŚľŹś≥ēšĽ§„Éá„Éľ„āŅ„Éô„Éľ„āĻ„Āß„Āā„āč„ÄĆRiigi Teataja„Äć„Āę„Ā¶„ÄĀśúÄśĖį„ĀģŤčĪŤ®≥ÁČą„āíťĖ≤Ť¶ß„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Äā
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„Āę„Āä„ĀĎ„ā茕ĎÁīĄ„ĀģŤá™ÁĒĪ„Ā®Śé≥ś†ľ„Ā™ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖšŅĚŤ≠∑ÔľąB2B„Ā®B2CÔľČ
LOA„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģŚĪěśÄß„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶Áēį„Ā™„ā荶ŹŚĺč„ā퍮≠„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
B2BÔľąšľĀś•≠ťĖďԾȌ•ĎÁīĄ„Āę„Āä„ĀĎ„ā茕ĎÁīĄ„ĀģŤá™ÁĒĪ
šľĀś•≠ťĖď„ĀģŚŹĖŚľēÔľąB2BԾȄĀę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĆŚ•ĎÁīĄŤá™ÁĒĪ„ĀģŚéüŚČáÔľąPrinciple of Party AutonomyԾȄÄćÔľąLOA ¬ß 5ԾȄĀĆŚļÉ„ĀŹťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚĹďšļčŤÄÖ„ĀĮ„ÄĀś≥ēŚĺč„ĀģšĽĽśĄŹŤ¶ŹŚģöÔľąŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģŚźąśĄŹ„ĀĆ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„ĀęťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„ā荶ŹŚģöԾȄĀ®Áēį„Ā™„āčŚÜÖŚģĻ„āí„ÄĀŤá™ÁĒĪ„ĀꌕĎÁīĄ„Āߌģö„āĀ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā
„Āü„Ā†„Āó„ÄĀ„Āď„ĀģŤá™ÁĒĪ„āāÁĄ°Śą∂ťôź„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀś≥ēŚĺč„ĀģŚľ∑Ť°ĆŤ¶ŹŚģö„āĄ„ÄĀŚÖ¨ŚļŹŤČĮšŅóÔľągood morals or public orderԾȄĀꌏć„Āô„ā茟ąśĄŹÔľąśįĎś≥ēÁ∑ŹŚČáś≥ē ¬ß 86ԾȄĀĮÁĄ°ŚäĻ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
B2CÔľąś∂ąŤ≤ĽŤÄÖԾȌ•ĎÁīĄ„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚé≥ś†ľ„Ā™šŅĚŤ≠∑
šłÄśĖĻ„ÄĀšļčś•≠ŤÄÖ„Ā®ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖ„Ā®„ĀģťĖď„ĀģŚŹĖŚľēÔľąB2CԾȄĀę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀLOA„ĀĮEUś≥ē„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀś•Ķ„āĀ„Ā¶Śé≥ś†ľ„Ā™ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖšŅĚŤ≠∑Ť¶ŹŚģö„āíÁĹģ„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀšļčś•≠ŤÄÖ„ĀĆšłÄśĖĻÁöĄ„ĀęśļĖŚāô„Āó„Āüś®ôśļĖÁīĄś¨ĺÔľąStandard TermsԾȄĀģšĹŅÁĒ®„Āę„ĀĮŚľ∑„ĀĄŤ¶ŹŚą∂„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖ„ĀęŤĎó„Āó„ĀŹšłćŚą©„Ā™śĚ°ť†Ö„āĄ„ÄĀŤ™†Śģü„ĀģŚéüŚČá„Āꌏć„Āó„Ā¶ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖ„Āģś®©Śą©„Ā®Áĺ©Śčô„ĀģťĖď„Āęťá挧߄Ā™šłćŚĚ፰°„āíÁĒü„Āė„Āē„Āõ„āčśĚ°ť†Ö„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆšłćŚÖ¨ś≠£ÔľąunfairԾȄÄć„Ā™„āā„Āģ„Ā®„Āó„Ā¶ÁĄ°ŚäĻ„Ā®„Āē„āĆ„Āĺ„ĀôÔľąLOA ¬ß 42ԾȄÄā„Āď„ĀģÁāĻ„ĀĮśó•śú¨„Āģś∂ąŤ≤ĽŤÄÖŚ•ĎÁīĄś≥ē„Ā®ť°ěšľľ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘś≥ēÔľą„Ā≤„ĀĄ„Ā¶„ĀĮEUś≥ēԾȄĀģšŅĚŤ≠∑„ĀģÁĮĄŚõ≤„ĀĮ„ÄĀ„Āó„Āį„Āó„Āįśó•śú¨ś≥ē„āą„āä„āāŚļÉÁĮĄ„Āč„Ā§Śľ∑Śäõ„Āß„Āā„āč„Āü„āĀś≥®śĄŹ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā
śó•śú¨ś≥ēŚčô„ĀĆśäľ„Āē„Āą„āč„ĀĻ„Āć„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘŚ•ĎÁīĄś≥ē„Āģťá捶ĀÁõłťĀēÁāĻ
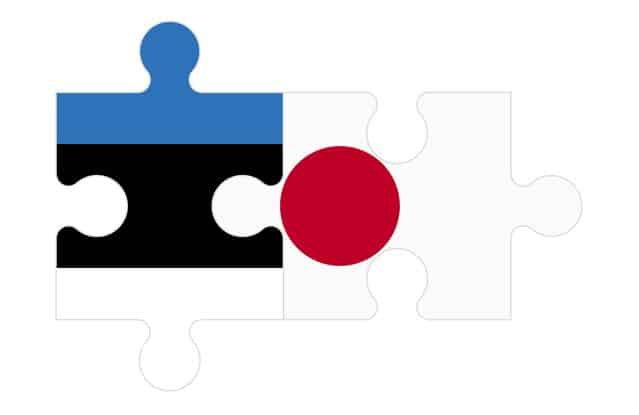
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģŚ•ĎÁīĄś≥ē„ĀĮŚ§ßťôłś≥ēÁ≥Ľ„Āß„Āā„āä„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®Ś§ö„ĀŹ„ĀģŚÖĪťÄöÁāĻ„āíśĆĀ„Ā°„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀŚģüŚčôšłä„ÄĀśĪļŚģöÁöĄ„Ā™ťĀē„ĀĄ„āíÁĒü„āÄŚŹĮŤÉĹśÄß„Āģ„Āā„āčÁõłťĀēÁāĻ„āāŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ÁõłťĀēÁāĻ‚φԾöŚ•ĎÁīĄŤß£ťô§„ĀģŤ¶ĀšĽ∂„Ā®„Āó„Ā¶„Āģ„ÄĆťá挧߄Ā™ťĀēŚŹć„Äć
śó•śú¨šľĀś•≠„ĀĆ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘšľĀś•≠„Ā®Ś•ĎÁīĄ„āíÁ∑†ÁĶź„Āô„āčťöõ„ÄĀśúÄ„āāś≥®śĄŹ„Āô„ĀĻ„ĀćÁāĻ„Āģ„Ā≤„Ā®„Ā§„ĀĆ„ÄĀŚ•ĎÁīĄťĀēŚŹćÔľąŚāĶŚčôšłćŚĪ•Ť°ĆԾȄĀĆ„Āā„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„ĀģŚ•ĎÁīĄŤß£ťô§ÔľąWithdrawal from contractԾȄĀģŤ¶ĀšĽ∂„Āß„Āô„Äā
śó•śú¨„ĀģśįĎś≥ē„Āß„ĀĮ„ÄĀ2020ŚĻī„ĀģśĒĻś≠£ŚĺĆ„ÄĀÁõłśČčśĖĻ„ĀęŚāĶŚčôšłćŚĪ•Ť°Ć„ĀĆ„Āā„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ÁõłŚĹď„ĀģśúüťĖď„āíŚģö„āĀ„Ā¶ŚĪ•Ť°Ć„āíŚā¨ŚĎä„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśúüťĖďŚÜÖ„ĀęŚĪ•Ť°Ć„ĀĆ„Ā™„ĀĎ„āĆ„ĀįŚ•ĎÁīĄ„āíŤß£ťô§„Āß„Āć„Āĺ„ĀôÔľąśó•śú¨śįĎś≥ēÁ¨¨541śĚ°ÔľČ„Äā„Āď„Āģťöõ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģťĀēŚŹć„ĀĆ„ÄĆťá挧߄Äć„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„Āĺ„Āß„ĀĮŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶Ť¶ĀśĪā„Āē„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā
„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘś≥ē„Āß„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄŤß£ťô§„ĀģŚČ朏źśĚ°šĽ∂„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ÁõłśČčśĖĻ„Āę„āą„āčťá挧߄Ā™Ś•ĎÁīĄťĀēŚŹćÔľąFundamental breach of contractԾȄÄć„ĀĆ„Āā„āč„Āď„Ā®„ĀĆŤ¶ĀśĪā„Āē„āĆ„Āĺ„ĀôÔľąLOA ¬ß 116 (1)ԾȄÄā
LOA § 116 (1)
A party may withdraw from a contract if the other party has committed a fundamental breach of a contractual obligation.
ÔľąŤ®≥ÔľöŚĹďšļčŤÄÖ„ĀĮ„ÄĀÁõłśČčśĖĻ„ĀĆŚ•ĎÁīĄšłä„ĀģÁĺ©Śčô„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ťá挧߄Ā™ťĀēŚŹć„āíÁäĮ„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„āíŤß£ťô§„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„ÄāÔľČ
šĹē„ĀĆ„ÄĆťá挧߄Ā™ťĀēŚŹć„Äć„Āę„Āā„Āü„āč„Āč„ĀĮ„ÄĀLOA ¬ß 116 (2) „ĀęŚÖ∑šĹďÁöĄ„ĀꌹóśĆô„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀťĀēŚŹć„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ś•ĎÁīĄ„ĀģÁõģÁöĄ„ĀĆťĀĒśąź„Āß„Āć„Ā™„ĀŹ„Ā™„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„āĄ„ÄĀŚģö„āĀ„āČ„āĆ„ĀüŤŅŌ䆄ĀģŚĪ•Ť°ĆśúüťĖďÔľąśó•śú¨„ĀģŚā¨ŚĎä„ĀęÁõłŚĹďԾȄāíÁĶĆťĀé„Āó„Ā¶„āāŚĪ•Ť°Ć„Āó„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„Ā™„Ā©„ĀĆ„Āď„āĆ„Āꍩ≤ŚĹď„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģťĀē„ĀĄ„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŤĽĹŚĺģ„Ā™„Ä挕ĎÁīĄťĀēŚŹć„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āüťöõ„ÄĀśó•śú¨ś≥ēŚčô„ĀģśĄüŤ¶ö„Āß„ĀĮŤß£ťô§ŚŹĮŤÉĹ„Ā®ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„Ā¶„āā„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘś≥ēšłä„Āß„ĀĮŤß£ťô§„ĀĆŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„Ā™„ĀĄ„É™„āĻ„āĮ„ĀĆ„Āā„āč„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŚ•ĎÁīĄśõłšĹúśąźśôā„Āę„ĀĮ„ÄĀ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ś†īŚźą„Āę„ÄĆťá挧߄Ā™ťĀēŚŹć„Äć„Ā®„ĀŅ„Ā™„Āô„Āģ„ĀčÔľąšĺč„Āą„Āį„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģÁĺ©ŚčôťĀēŚŹć„āíŤá™ŚčēÁöĄ„Āęťá挧߄Ā™ťĀēŚŹć„Ā®„ĀŅ„Ā™„ĀôśĚ°ť†Ö„Ā™„Ā©ÔľČ„āíśėéÁĘļ„ĀęŚģöÁĺ©„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀÁīõšļČšļąťė≤„ĀģŤ¶≥ÁāĻ„Āč„āČś•Ķ„āĀ„Ā¶ťá捶Ā„Āß„Āô„Äā
ÁõłťĀēÁāĻ‚Ď°ÔľöB2BŚ•ĎÁīĄ„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĆšłćŚÖ¨ś≠£śĚ°ť†Ö„Äć„ĀģŚŹłś≥ēŚĮ©śüĽ
„āā„ĀÜšłÄ„Ā§„Āģťá捶Ā„Ā™ÁõłťĀēÁāĻ„ĀĮ„ÄĀś®ôśļĖÁīĄś¨ĺÔľąStandard TermsԾȄĀęťĖĘ„Āô„ā荶ŹŚĺč„Āß„Āô„Äāśó•śú¨ś≥ē„Āß„āā2020ŚĻīśĒĻś≠£„ĀߌģöŚěčÁīĄś¨ĺÔľąśįĎś≥ēÁ¨¨548śĚ°„Āģ2ԾȄĀęťĖĘ„Āô„ā荶ŹŚģö„ĀĆśĖįŤ®≠„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ¶ŹŚĺč„ĀĮšłĽ„Āę„ÄĀšłćśĄŹśČď„Ā°śĚ°ť†Ö„āĄšłÄśĖĻÁöĄ„ĀęšłćŚĹď„Ā™śĚ°ť†Ö„Āģ„ÄĆÁĶĄŚÖ•„āĆÔľąŚ•ĎÁīĄŚÜÖŚģĻ„Ā®„Āô„āč„Āď„Ā®ÔľČ„Äć„āí„ā≥„É≥„Éą„É≠„Éľ„Éę„Āô„āčÁāĻ„ĀęšłĽÁúľ„ĀĆÁĹģ„Āč„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘś≥ēÔľąLOA ¬ß 42ԾȄāā„ÄĀś∂ąŤ≤ĽŤÄÖŚ•ĎÁīĄÔľąB2CԾȄĀę„Āä„ĀĄ„Ā¶šłćŚÖ¨ś≠£„Ā™ś®ôśļĖÁīĄś¨ĺ„āíÁĄ°ŚäĻ„Ā®Śģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāś≥®Áõģ„Āô„ĀĻ„Āć„ĀĮ„ÄĀ„Āď„Āģ„ÄĆšłćŚÖ¨ś≠£śÄß„Äć„Āģ„ā≥„É≥„Éą„É≠„Éľ„Éę„ĀĆ„ÄĀŚą§šĺč„āíťÄö„Āė„Ā¶B2BŚ•ĎÁīĄ„Āę„āāŚŹä„Ā≥Śĺó„āčÁāĻ„Āß„Āô„Äā
„Āď„ĀģÁāĻ„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘśúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄÔľąRiigikohusԾȄĀĮ„ÄĀšļčś°ąÁē™ŚŹ∑ 3-2-1-139-14Ôľą2015ŚĻī1śúą19śó•Śą§śĪļԾȄĀę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀťá捶Ā„Ā™Śą§śĖ≠„āíÁ§ļ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āď„Āģšļčś°ą„ĀßśúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĀB2BŚ•ĎÁīĄ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶šĹŅÁĒ®„Āē„āĆ„Āüś®ôśļĖÁīĄś¨ĺ„ĀĆ„ÄĀÁõłśČčśĖĻŚĹďšļčŤÄÖÔľą„Āď„ĀģŚ†īŚźą„ĀĮšļčś•≠ŤÄÖԾȄĀę„Ā®„Ā£„Ā¶ŤĎó„Āó„ĀŹšłćŚÖ¨ś≠£ÔľąunfairԾȄĀß„Āā„āčÁĖĎ„ĀĄ„ĀĆÁĒü„Āė„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀ„ĀĚ„Āģś®ôśļĖÁīĄś¨ĺ„ā휏źÁ§ļ„Āó„ĀüŚĹďšļčŤÄÖÔľąśĚ°ť†Ö„ĀģśĀ©śĀĶ„ā팏ó„ĀĎ„āčŚĀīԾȄĀĆ„ÄĀ„ÄĆ„ĀĚ„ĀģśĚ°ť†Ö„ĀĆŚĹ≤ŚŹĖŚľē„ĀģśĖ፥ą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶šłćŚÖ¨ś≠£„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„Äć„āíÁę荮ľ„Āô„āčŤ≤¨šĽĽ„āíŤ≤†„ĀÜ„ÄĀ„Ā®Śą§Á§ļ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀB2BŚ•ĎÁīĄ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀŚäõťĖĘšŅā„ĀęŚ∑ģ„ĀĆ„Āā„ā茆īŚźą„āĄ„ÄĀšłÄśĖĻ„ĀęŤĎó„Āó„ĀŹšłćŚą©Áõä„Ā™ŚÜÖŚģĻ„ĀĆś®ôśļĖÁīĄś¨ĺ„Ā®„Āó„Ā¶ÁĶĄ„ĀŅŤĺľ„Āĺ„āĆ„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆ„ĀĚ„ĀģśĚ°ť†Ö„ĀģŚÜÖŚģĻ„Āę„Āĺ„ĀߍłŹ„ĀŅŤĺľ„āď„ĀßÁĄ°ŚäĻ„Ā®Śą§śĖ≠„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„āą„āä„āāťęė„ĀĄ„Āď„Ā®„āíÁ§ļŚĒÜ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘšľĀś•≠„Āč„āČśŹźÁ§ļ„Āē„āĆ„ĀüŚ•ĎÁīĄśõł„āí„ɨ„Éď„É•„Éľ„Āô„āčťöõ„ĀĮ„ÄĀ„Āü„Ā®„ĀąB2BŚŹĖŚľē„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀšłÄśĖĻÁöĄ„Āꚳ挹©„Ā™śĚ°ť†Ö„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āč„ÄĀ„āą„āäśÖéťáć„ĀęÁĘļŤ™ć„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘś≥ēŤß£ťáą„ĀģťćĶÔľö„ÄĆŤ™†Śģü„ĀģŚéüŚČá„Äć„Ā®„ÄĆŚźąÁźÜśÄß„ĀģŚéüŚČá„Äć
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģLOA„āíÁźÜŤß£„Āô„āčšłä„Āßś¨†„Āč„Āõ„Ā™„ĀĄ„Āģ„ĀĆ„ÄĀś≥ēŤß£ťáą„āĄŚ•ĎÁīĄ„ĀģŚĪ•Ť°Ć„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶śúÄ„āāťá捶Ā„Ā™śĆáťáĚ„Ā®„Ā™„āčšļĆ„Ā§„ĀģšłÄŤą¨ŚéüŚČá„Āß„Āô„Äā
Ť™†Śģü„ĀģŚéüŚČá (Principle of Good Faith)
LOAÁ¨¨6śĚ°Ôľą¬ß 6ԾȄĀĮ„ÄĀ„ÄĆŤ™†Śģü„ĀģŚéüŚČá„Äć„āíŚģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„ĀĆŚćė„ĀꌕĎÁīĄśĚ°ť†Ö„ĀģśĖ፮ĄĀęŚĺď„ĀÜ„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀšļí„ĀĄ„Āģś®©Śą©„Ā®Śą©Áõä„āíŚįäťáć„Āó„Ā¶Ť°ĆŚčē„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘÁßĀś≥ē„Āģś†Ļśú¨ŚéüŚČá„Āß„Āô„Äā
LOA § 6 (1)
Obligees and obligors shall act in good faith in their relations with one another.
ÔľąŤ®≥ÔľöŚāĶś®©ŤÄÖ„Ā®ŚāĶŚčôŤÄÖ„ĀĮ„ÄĀÁõłšļí„ĀģťĖĘšŅā„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Ť™†Śģü„Āꍰƌčē„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„ÄāÔľČ
„Āď„ĀģŚéüŚČá„ĀĮ„ÄĀŚćė„Ā™„āčŚä™ŚäõÁõģś®ô„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāLOAÁ¨¨14śĚ°„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄÁ∑†ÁĶźŚČć„Āģšļ§śłČśģĶťöé„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„ĀĮŤ™†Śģü„ĀģŚéüŚČá„ĀęŚĺď„ĀÜÁĺ©Śčô„āíŤ≤†„ĀÜ„Ā®Śģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘśúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§šĺčÔľąšĺčÔľöšļčś°ąÁē™ŚŹ∑ 3-2-1-89-06„ÄĀ3-2-1-168-14ԾȄĀß„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄÁ∑†ÁĶź„ĀģÁúü„ĀģśĄŹŚõ≥„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āę„āā„Āč„Āč„āŹ„āČ„Āöšļ§śłČ„āíÁ∂ö„ĀĎ„Āü„āä„ÄĀŚźąÁźÜÁöĄ„Ā™ÁźÜÁĒĪ„Ā™„ĀŹšłÄśĖĻÁöĄ„Āęšļ§śłČ„āíśČď„Ā°Śąá„Ā£„Āü„āä„Āô„ā荰ĆÁāļ„ĀĮ„ÄĀ„Āď„Āģ„ÄĆŤ™†Śģü„ĀģŚéüŚČá„ÄćťĀēŚŹć„Āę„Āā„Āü„āč„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀśźćŚģ≥Ť≥†ŚĄüŤ≤¨šĽĽ„ĀĆŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ŚźąÁźÜśÄß„ĀģŚéüŚČá (Principle of Reasonableness)
LOAÁ¨¨7śĚ°Ôľą¬ß 7ԾȄĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚźąÁźÜśÄß„ĀģŚéüŚČá„Äć„āíŚģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģÁä∂ś≥Āšłč„Āß„ÄĆśÖéťáć„Āč„Ā§ŚźąÁźÜÁöĄ„Ā™šļļÔľąa careful and reasonable personԾȄÄć„ĀĆťÄöŚłł„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Āꍰƌčē„Āô„āč„Āč„āíŚüļśļĖ„Āę„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģŤ°ĆÁāļ„āĄŚ•ĎÁīĄ„ĀģŤß£ťáą„ā퍰ƄĀÜ„ĀĻ„Āć„Ā®„Āô„āčŚéüŚČá„Āß„Āô„Äā
Ś•ĎÁīĄśõł„Āęśė鍮ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄšļ蝆քāĄ„ÄĀŚĪ•Ť°Ć„ĀģŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™śĖĻś≥ē„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶šļČ„ĀĄ„ĀĆÁĒü„Āė„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„Āď„Āģ„ÄĆŚźąÁźÜśÄß„Äć„āíŚüļśļĖ„Āꌹ§śĖ≠„Āó„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀŚ•ĎÁīĄťĀēŚŹć„ĀĆ„Āā„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„ĀꍶĀśĪā„Āē„āĆ„āčťÄöÁü•śúüťĖď„āĄ„ÄĀśźćŚģ≥„ĀģÁĮĄŚõ≤„ÄĀŚČćŤŅį„Āģ„ÄĆťá挧߄Ā™ťĀēŚŹć„Äć„ĀģŚą§śĖ≠„Ā™„Ā©„ÄĀś≥ē„Āģ„Āā„āČ„āÜ„ā茆īťĚĘ„Āß„Āď„Āģ„ÄĆŚźąÁźÜśÄß„Äć„Āģ„Éē„ā£„Éę„āŅ„Éľ„ĀĆťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀÔľö„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„Éď„āł„Éć„āĻśąźŚäü„ĀģťćĶ„ĀĮÁŹĺŚúįś≥ē„Āģś≠£ÁĘļ„Ā™ÁźÜŤß£
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģśįĎś≥ē„ÉĽŚ•ĎÁīĄś≥ē„Āģś†ĻŚĻĻ„Āß„Āā„āč„ÄĆŚāĶŚčôś≥ēÁ∑ŹŤęĖÔľąLOAԾȄÄć„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚüļśú¨śßčťÄ†„Ā®„ÄĀśó•śú¨šľĀś•≠„ĀĆÁČĻ„Āęś≥®śĄŹ„Āô„ĀĻ„Āćśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀģÁõłťĀēÁāĻ„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
Ť®ėšļč„ĀģŤ¶ĀÁāĻ„āí„Āĺ„Ā®„āĀ„āč„Ā®„ÄĀšĽ•šłč„ĀģťÄö„āä„Āß„Āô„Äā
- „ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀģŚ•ĎÁīĄś≥ē„ĀĮ„ÄĀ2002ŚĻīśĖĹŤ°Ć„Āģ„ÄĆŚāĶŚčôś≥ēÁ∑ŹŤęĖÔľąLOAԾȄÄć„ĀęťõÜÁīĄ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā
- B2BŚ•ĎÁīĄ„Āß„ĀĮŚ•ĎÁīĄ„ĀģŤá™ÁĒĪ„ĀĆŚļÉ„ĀŹŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„āč„ĀĆ„ÄĀB2CŚ•ĎÁīĄ„Āß„ĀĮŚé≥ś†ľ„Ā™ś∂ąŤ≤ĽŤÄÖšŅĚŤ≠∑„ĀĆťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„āč„Äā
- „Äźśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀģÁõłťĀēÁāĻ‚φ„ÄĎ Ś•ĎÁīĄŤß£ťô§„Āę„ĀĮ„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĆťá挧߄Ā™Ś•ĎÁīĄťĀēŚŹć„ÄćÔľąLOA ¬ß 116ԾȄĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āā„āä„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„āą„āä„āāŤ¶ĀšĽ∂„ĀĆŚé≥ś†ľ„Āß„Āā„āč„Äā
- „Äźśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀģÁõłťĀēÁāĻ‚Ď°„ÄĎ B2BŚ•ĎÁīĄ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀś®ôśļĖÁīĄś¨ĺ„ĀĆŤĎó„Āó„ĀŹšłćŚÖ¨ś≠£„Ā™Ś†īŚźą„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆ„ĀĚ„ĀģŚäĻŚäõ„ā팟¶Śģö„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģÁę荮ľŤ≤¨šĽĽ„ĀƜ̰ť†ÖśŹźÁ§ļŚĀī„Āę„Āā„āč„Ā®„Āó„ĀüśúÄťęėŤ£ĀŚą§šĺčÔľą3-2-1-139-14ԾȄĀĆŚ≠ėŚú®„Āô„āč„Äā
- ŚÖ®„Ā¶„Āģś≥ēŤß£ťáą„ĀģŚüļÁ§é„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ„ÄĆŤ™†Śģü„ĀģŚéüŚČá„ÄćÔľąLOA ¬ß 6ԾȄĀ®„ÄĆŚźąÁźÜśÄß„ĀģŚéüŚČá„ÄćÔľąLOA ¬ß 7ԾȄĀĆś•Ķ„āĀ„Ā¶Śľ∑Śäõ„Ā™śĆáťáĚ„Ā®„Āó„Ā¶ś©üŤÉĹ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚ•ĎÁīĄšļ§śłČśģĶťöé„Āč„āČťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„āč„Äā
„Éá„āł„āŅ„ÉęŚÖąťÄ≤ŚõĹ„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģś≥ēšĹďÁ≥Ľ„āā„Āĺ„Āü„ÄĀŚõĹťöõś®ôśļĖ„ā팏Ė„āäŚÖ•„āĆ„ĀüŚźąÁźÜÁöĄ„Āč„Ā§śüĒŤĽü„Ā™„āā„Āģ„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśüĒŤĽüśÄß„ĀĮ„ÄĆŤ™†Śģü„Äć„Āč„Ā§„ÄĆŚźąÁźÜÁöĄ„Äć„Ā™Ť°ĆŚčē„āíŚĹďšļčŤÄÖ„Āꌾ∑„ĀŹśĪā„āĀ„āč„āā„Āģ„Āß„Āā„āä„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āč„āĘ„Éó„É≠„Éľ„ÉĀ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„ā茆īťĚĘ„āāŚįĎ„Ā™„ĀŹ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā
„ā®„āĻ„Éą„Éč„āĘ„Āß„Āģ„Éď„āł„Éć„āĻŚĪēťĖč„ÄĀÁŹĺŚúįšľĀś•≠„Ā®„ĀģŚ•ĎÁīĄšļ§śłČ„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮŚ•ĎÁīĄśõł„Āģ„ɨ„Éď„É•„Éľ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„Āģś≥ēÁöĄ„Ā™ÁõłťĀēÁāĻ„āíś≠£ÁĘļ„Āęśä䜏°„Āó„ÄĀ„É™„āĻ„āĮ„āíÁģ°ÁźÜ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„ÄāÁŹĺŚúį„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„āĄŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™Ś•ĎÁīĄśĚ°ť†Ö„ĀģŤß£ťáą„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĒšłćśėé„Ā™ÁāĻ„āĄśáłŚŅĶ„ĀĆ„ĀĒ„ĀĖ„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„āČ„ÄĀŚĹďšļčŚčôśČÄ„Āß„āā„āĶ„ÉĚ„Éľ„Éą„ĀĄ„Āü„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô