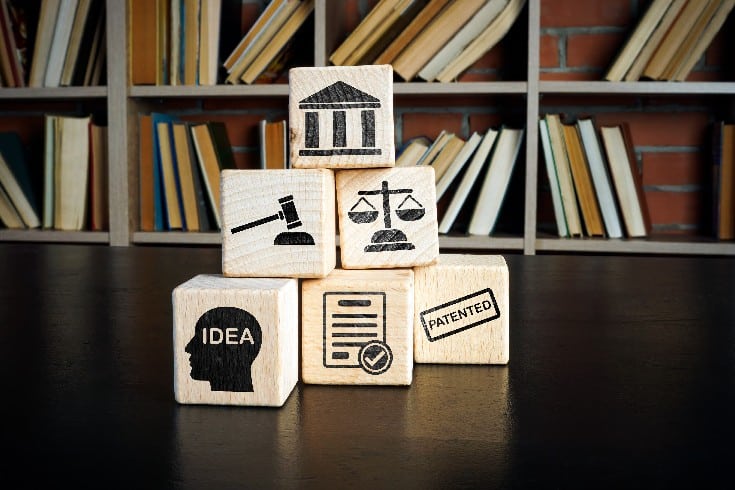õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Ńü»’╝¤Õł®ńö©µ©®Ńü«ń»äÕø▓ŃéäÕłżõŠŗŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼
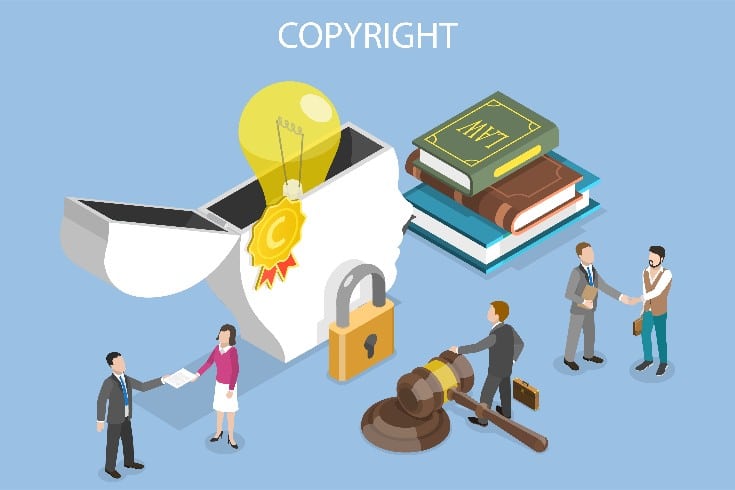
ń¦üŃü¤ŃüĪŃü«Õæ©ŃéŖŃü½Ńü»ŃĆüÕ░ÅĶ¬¼ŃéäŃā×Ńā│Ńé¼ŃéÆÕĤõĮ£Ńü©ŃüŚŃü”µśĀÕāÅÕī¢ŃüŚŃü¤ŃāåŃā¼ŃāōŃāēŃā®Ńā×Ńé䵜Āńö╗ŃüīŃüéŃüĄŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüéŃéŗĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆŃĆīÕĤõĮ£ŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”µ¢░ŃüŚŃüÅÕēĄõĮ£ŃüĢŃéīŃü¤õĮ£ÕōüŃü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Õæ╝Ńü░ŃéīŃüŠŃüÖŃĆéĶ┐æÕ╣┤Ńü¦Ńü»ŃĆüSNSŃéÆķĆÜŃüśŃü”ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«ŃéóŃāŗŃāĪŃéäŃā×Ńā│Ńé¼ńŁēŃéÆõĖ╗ķĪīŃü©ŃüŚŃü¤ŃüäŃéÅŃéåŃéŗŃāĢŃéĪŃā│ŃéóŃā╝ŃāłŃü¬Ńü®Ńü«õ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£Ńééµ┤╗ńÖ║Ńü½ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗŃāłŃā®Ńā¢Ńā½ŃééÕżÜŃüÅńö¤ŃüśŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü»ŃĆüÕĤõĮ£ŃéÆÕ¤║Ńü½ŃüŚŃü”µ¢░Ńü¤Ńü¬ÕēĄõĮ£ĶĪīńé║ŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃéŗńé╣Ńü¦ŃĆüµ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃüīĶżćķøæŃü½Ńü¬ŃéŖŃéäŃüÖŃüÅŃĆüÕēĄõĮ£Ńā╗Õł®ńö©Ńü½ķÜøŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗµŁŻńó║Ńü¬ńÉåĶ¦ŻŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüØŃüōŃü¦ŃĆüµ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüÕłżõŠŗŃü©Ńü©ŃééŃü½Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Ńü»

ĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Õ«ÜńŠ®ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃĆĆĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆń┐╗Ķ©│ŃüŚŃĆüńĘ©µø▓ŃüŚŃĆüĶŗźŃüŚŃüÅŃü»ÕżēÕĮóŃüŚŃĆüÕÅłŃü»ĶäÜĶē▓ŃüŚŃĆüµśĀńö╗Õī¢ŃüŚŃĆüŃüØŃü«õ╗¢ń┐╗µĪłŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŖÕēĄõĮ£ŃüŚŃü¤ĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆŃüäŃüåŃĆé
ĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģń¼¼2µØĪń¼¼1ķĀģń¼¼11ÕÅĘ
ŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪŃĆüŃĆīĶæŚõĮ£ńē®ŃĆŹŃéÆŃĆīń┐╗µĪłńŁēŃĆŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŖµ¢░Ńü¤Ńü½ÕēĄõĮ£ŃüĢŃéīŃü¤ĶæŚõĮ£ńē®Ńüīõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü¦ŃüÖŃĆé
õĖĆŃüżõĖĆŃüżķĀåńĢ¬Ńü½Ķ”ŗŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ŃĆīĶæŚõĮ£ńē®ŃĆŹŃü©Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢõĖŖŃĆüŃĆīµĆصā│ÕÅłŃü»µä¤µāģŃéÆÕēĄõĮ£ńÜäŃü½ĶĪ©ńÅŠŃüŚŃü¤ŃééŃü«ŃĆŹŃü©Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łń¼¼2µØĪń¼¼1ķĀģń¼¼1ÕÅĘ’╝ēŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕ░ÅĶ¬¼Ńéäµ╝½ńö╗ŃĆüķ¤│µźĮŃé䵜Āńö╗ńŁēŃĆüŃüØŃü«ń»äÕø▓Ńü»ÕżÜÕ▓ÉŃü½µĖĪŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüØŃüŚŃü”ŃĆīń┐╗µĪłŃĆŹŃü©Ńü»ŃĆüÕłżõŠŗõĖŖŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Ķ¦ŻŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ń┐╗µĪłŌĆ”Ńü©Ńü»’╝īµŚóÕŁśŃü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü½õŠØµŗĀŃüŚ’╝īŃüŗŃüż’╝īŃüØŃü«ĶĪ©ńÅŠõĖŖŃü«µ£¼Ķ│¬ńÜäŃü¬ńē╣ÕŠ┤Ńü«ÕÉīõĖƵƦŃéÆńČŁµīüŃüŚŃüżŃüż’╝īÕģĘõĮōńÜäĶĪ©ńÅŠŃü½õ┐«µŁŻ’╝īÕóŚµĖø’╝īÕżēµø┤ńŁēŃéÆÕŖĀŃüłŃü”’╝īµ¢░Ńü¤Ńü½µĆصā│ÕÅłŃü»µä¤µāģŃéÆÕēĄõĮ£ńÜäŃü½ĶĪ©ńÅŠŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŖ’╝īŃüōŃéīŃü½µÄźŃüÖŃéŗĶĆģŃüīµŚóÕŁśŃü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶĪ©ńÅŠõĖŖŃü«µ£¼Ķ│¬ńÜäŃü¬ńē╣ÕŠ┤ŃéÆńø┤µÄźµä¤ÕŠŚŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü«Ńü¦ŃüŹŃéŗÕłźŃü«ĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃéÆŃüäŃüåŃĆé
µ£ĆÕłżÕ╣│µłÉ13Õ╣┤6µ£ł28µŚź µ░æķøå55ÕĘ╗4ÕÅĘ837ķĀü’╝łµ▒¤ÕĘ«Ķ┐ĮÕłåõ║ŗõ╗Č’╝ē
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õ«ÜńŠ®Ńü¦ÕłŚµīÖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗń┐╗Ķ©│ŃéäńĘ©µø▓ńŁēŃü«ĶĪīńé║Ńü»ŃĆüķĆÜÕĖĖŃĆüõĖŖĶ©śµĆ¦Ķ│¬ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüŗŃéēŃĆüŃĆīń┐╗µĪłŃĆŹŃü«ÕģĖÕ×ŗõŠŗŃéÆÕłŚµīÖŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
ķćŹĶ”üŃü¬ńé╣Ńü»ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü½ÕēĄõĮ£ńÜäŃü¬ĶĪ©ńÅŠŃéÆõ╗śõĖÄŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüŗÕÉ”ŃüŗŃü¦ŃüÖŃĆéµ¢░Ńü¤Ńü½ÕēĄõĮ£ńÜäŃü¬ĶĪ©ńÅŠŃéÆõ╗śõĖÄŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃéēŃüōŃüØŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäŃĆīĶæŚõĮ£ńē®ŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”õ┐ØĶŁĘŃüĢŃéīŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé
ķĆåŃüŗŃéēĶ©ĆŃüłŃü░ŃĆüÕŹśŃü½ÕĤĶæŚõĮ£ńē®ŃéƵ©ĪÕĆŻ’╝łĶżćĶŻĮ’╝ēŃüŚŃü¤Ńü½ŃüÖŃüÄŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü½ÕēĄõĮ£ńÜäŃü¬ĶĪ©ńÅŠŃéÆõ╗śõĖÄŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½Ńü»ÕĮōŃü¤ŃéŖŃüŠŃüøŃéō’╝łŃüōŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶżćĶŻĮµ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖ’╝ēŃĆé
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«õŠŗ

õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ÕĮōŃü¤ŃéŗÕģĘõĮōõŠŗŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüÕ░ÅĶ¬¼ŃéäŃā×Ńā│Ńé¼ńŁēŃéƵśĀÕāÅÕī¢ŃüŚŃü¤ŃéóŃāŗŃāĪŃé䵜Āńö╗Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤ÕĢåµźŁńÜäŃü¬ŃééŃü«ŃüŗŃéēŃĆüõĖĆĶł¼õ║║ŃüīŃĆüŃéóŃāŗŃāĪŃéäŃā×Ńā│Ńé¼ńŁēŃü«ŃéŁŃāŻŃā®Ńé»Ńé┐Ńā╝ŃéÆõĖ╗ķĪīŃü©ŃüŚŃü¬ŃüīŃéēŃĆüÕĮōĶ®▓ÕĤõĮ£ÕōüŃü«µ¢ćĶäłŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗõ╗╗µäÅŃü«ńŖȵ│üĶ©ŁÕ«ÜŃü«ŃééŃü©Ńü¦Ńé¬Ńā¬ŃéĖŃāŖŃā½Ńü«õĮ£Õōü’╝łŃüäŃéÅŃéåŃéŗŃĆīŃāĢŃéĪŃā│ŃéóŃā╝ŃāłŃĆŹńŁē’╝ēŃéÆÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗŃéłŃüåŃü¬ĶČŻÕæ│ńÜäŃü¬ŃééŃü«ŃüŠŃü¦ŃĆüõŠŗŃéƵīÖŃüÆŃéīŃü░ŃéŁŃā¬ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüńē╣Ńü½Ķ┐æÕ╣┤ŃĆüÕŠīĶĆģŃü«ŃéłŃüåŃü¬ÕĆŗõ║║Ńü½ŃéłŃéŗõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ÕēĄõĮ£’╝łõĖĆĶł¼ńÜäŃü½ŃĆīõ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£ŃĆŹŃü©Ķ©ĆŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆé’╝ēŃü»ŃĆüSNSŃü«ńÖ║Õ▒ĢŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕŠōµØźŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗµ│ĢńÜäÕĢÅķĪīŃéÆńö¤ŃüśŃüĢŃüøŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪŃĆüń┤öń▓ŗŃü½ĶČŻÕæ│Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüń¦üńÜäŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗõ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®õĖŖŃééõŠŗÕż¢ńÜäŃü½õ┐ØĶŁĘŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗ’╝ł30µØĪŃĆü47µØĪŃü«’╝¢’╝ēŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüń¦üńÜäÕł®ńö©Ńü«ń»äÕø▓ŃéÆĶČģŃüłŃü¤Õł®ńö©ĶĪīńé║Ńü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗõ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£ÕÅŖŃü│ŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖÕēĄõĮ£ŃüĢŃéīŃü¤õĮ£ÕōüŃéÆSNSŃü½µŖĢń©┐ŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®’╝łń┐╗µĪłµ©®Ńā╗Õģ¼ĶĪ©µ©®’╝ēŃü«õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüSNSŃü½µŖĢń©┐ŃüĢŃéīŃéŗõ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£õĮ£ÕōüŃü«ÕżÜŃüÅŃü»ŃĆüÕ░æŃü¬ŃüÅŃü©Ńééµ│ĢńÜäŃü½Ńü»ĶæŚõĮ£µ©®ŃéÆõŠĄÕ«│ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃééŃü«Ńü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖ’╝łÕŠīĶ┐░Ńü«Ńü©ŃüŖŃéŖŃĆüõ║ŗÕ«¤õĖŖĶ©▒Õ«╣ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü½ŃüÖŃüÄŃü¬ŃüäŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīŃü╗Ńü©ŃéōŃü®Ńü¦ŃüÖ’╝ēŃĆé
ŃüØŃüōŃü¦ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüŚŃĆüŃüōŃéīŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»ŃĆüÕĖĖŃü½ÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®ĶĆģŃü©Ńü«µ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃü½µ│©µäÅŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ¼Īń½ĀŃü¦Ńü»ŃĆüÕģĘõĮōõŠŗŃü©ÕłżõŠŗŃéÆŃééŃü©Ńü½ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ĶĆģŃü©ÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Õł®ńö©µ©®

õŠŗŃüłŃü░ŃĆüXŃüĢŃéōŃüīĶŗ▒Ķ¬×Ńü¦µøĖŃüäŃü¤Õ░ÅĶ¬¼ŃéÆYŃüĢŃéōŃüīµŚźµ£¼Ķ¬×Ńü½ń┐╗Ķ©│ŃüŚŃü”Õć║ńēłŃüŚŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕĤõĮ£ĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗXŃüĢŃéōŃü»ÕĮōĶ®▓Õ░ÅĶ¬¼Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü©ŃüŚŃü”ĶæŚõĮ£µ©®ŃéƵ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéYŃüĢŃéōŃüīÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗµŚźµ£¼Ķ¬×ńēłŃü«Õ░ÅĶ¬¼Ńü»ŃĆüÕĤõĮ£ÕōüŃü¦ŃüéŃéŗXŃüĢŃéōŃü«Õ░ÅĶ¬¼’╝łŃĆīĶæŚõĮ£ńē®ŃĆŹ’╝ēŃéÆŃĆīń┐╗Ķ©│ŃĆŹŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ÕĮōŃü¤ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¦Ńü»ŃĆüYŃüĢŃéōŃüīÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗµŚźµ£¼Ķ¬×ńēłŃü«Õ░ÅĶ¬¼Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüXŃüĢŃéōŃü©YŃüĢŃéōŃü»ŃĆüŃüØŃéīŃü×ŃéīŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬µ©®Õł®ŃéƵ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé
ŃĆīÕēĄõĮ£ŃĆŹŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ©®Õł®ķ¢óõ┐é
ÕēŹµÅÉŃü©ŃüŚŃü”µ│©µäÅŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü«Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ÕĮōŃü¤ŃéŗŃüŗŃéēŃü©ŃüäŃüŻŃü”ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®ŃéÆńäĪĶ”¢ŃüŚŃü”ŃéłŃüäŃéÅŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆé
ÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü½Ńü»ŃĆüÕĮōńäČŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«ĶæŚõĮ£µ©®ŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüØŃüōŃü½Ńü»ŃĆīń┐╗µĪłµ©®ŃĆŹ’╝łń¼¼27µØĪ’╝ēŃüīÕɽŃüŠŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüżŃüŠŃéŖŃĆüµ£¼µØźŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü»ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®ŃéÆõŠĄÕ«│ŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆķü®µ│ĢŃü½ÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗŃü½Ńü»ŃĆüÕ¤║µ£¼ńÜäŃü½Ńü»ÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®ĶĆģŃü«Ķ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃĆüŃü©ŃüäŃüåŃü«ŃüīĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü«Ńā½Ńā╝Ńā½Ńü¦ŃüÖŃĆé
õĖŖĶ©śõ║ŗõŠŗŃü¦Ńü»ŃĆüÕēŹµÅÉŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüYŃüĢŃéōŃüīXŃüĢŃéōŃüŗŃéēŃĆüXŃüĢŃéōŃü«Õ░ÅĶ¬¼ŃéÆń┐╗Ķ©│ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüæŃéīŃü░ŃĆüń┐╗Ķ©│ŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ķć¬õĮōŃüīĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖ’╝łŃü¬ŃüŖŃĆüÕēĄõĮ£ĶĪīńé║ŃüīķüĢµ│ĢŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü»µłÉń½ŗŃüÖŃéŗŃü©Ķ¦ŻŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝ēŃĆé
ŃĆīÕł®ńö©ŃĆŹŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ©®Õł®ķ¢óõ┐é
Ńü¦Ńü»ŃĆüÕēĄõĮ£ĶĪīńé║Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ÕĤĶæŚõĮ£µ©®ĶĆģŃüŗŃéēĶ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüķü®µ│ĢŃü½ÕēĄõĮ£ŃüŚŃü¤õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗķÜøŃü«µ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃü»Ńü®ŃüåŃü¬ŃéŗŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé
ŃüŠŃüÜŃĆüĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü½Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õł®ńö©Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬µśÄµ¢ćŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü»ŃĆüÕĮōĶ®▓õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õł®ńö©Ńü½ķ¢óŃüŚŃĆüŃüōŃü«µ¼ŠŃü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüÖŃéŗµ©®Õł®Ńü¦ÕĮōĶ®▓õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃüīµ£ēŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü©ÕÉīõĖĆŃü«ń©«ķĪ×Ńü«µ©®Õł®ŃéÆÕ░éµ£ēŃüÖŃéŗŃĆé
ĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģń¼¼28µØĪ’╝łõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õł®ńö©Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®’╝ē
Ķ”üŃüÖŃéŗŃü½ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü©ŃĆīÕÉīõĖĆŃü«ń©«ķĪ×Ńü«µ©®Õł®ŃĆŹŃéƵ£ēŃüÖŃéŗŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńü¦Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃüīµ£ēŃüÖŃéŗµ©®Õł®Ńü©Ńü»õĮĢŃüŗŃüīÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃü«ńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ÕłżõŠŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®ń»äÕø▓
µ╝½ńö╗ŃĆīPOPEYEŃĆŹŃü½ŃüżŃüäŃü”ĶæŚõĮ£µ©®ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗÕĤÕæŖõ╝ÜńżŠŃéēŃüīŃĆīŃāØŃāæŃéżŃĆŹŃĆüŃĆīPOPEYEŃĆŹŃü«µ¢ćÕŁŚŃü©õ║║ńē®ÕāÅŃü«Õø│µ¤äŃéÆõ╗śŃüŚŃü¤ŃāŹŃé»Ńé┐ŃéżŃéÆĶ▓®ÕŻ▓ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤Ķó½ÕæŖõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüĶ▓®ÕŻ▓Ńü«ÕĘ«µŁóÕÅŖŃü│µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ńü¬Ńü®ŃéƵ▒éŃéüŃü¤õ║ŗõŠŗŃü»ŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃüŠŃü¦õ║ēŃéÅŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
Õłżµ▒║µ¢ćŃü¦Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢõĖŖŃü«Ķ½¢ńé╣Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüķćŹĶ”üŃü¬Õłżńż║ŃüīĶżćµĢ░ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃüōŃü¦Ńü»õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õł®ńö©Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗń«ćµēĆŃü½ńä”ńé╣ŃéÆÕĮōŃü”Ńü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃüÜŃĆüµ£¼õ╗ČŃü¦ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õĖĆĶ®▒Õ«īńĄÉÕ×ŗŃü«ķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«µłÉÕÉ”Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆü
ķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕŠīńČÜŃü«µ╝½ńö╗Ńü»ŃĆüÕģłĶĪīŃüÖŃéŗµ╝½ńö╗Ńü©Õ¤║µ£¼ńÜäŃü¬ńÖ║µā│ŃĆüĶ©ŁÕ«ÜŃü«Ńü╗ŃüŗŃĆüõĖ╗õ║║Õģ¼ŃéÆÕ¦ŗŃéüŃü©ŃüÖŃéŗõĖ╗Ķ”üŃü¬ńÖ╗ÕĀ┤õ║║ńē®Ńü«Õ«╣Ķ▓īŃĆüµĆ¦µĀ╝ńŁēŃü«ńē╣ÕŠ┤ŃéÆÕÉīŃüśŃüÅŃüŚŃĆüŃüōŃéīŃü½µ¢░Ńü¤Ńü¬ńŁŗµøĖŃéÆõ╗śŃüÖŃéŗŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüµ¢░Ńü¤Ńü¬ńÖ╗ÕĀ┤õ║║ńē®ŃéÆĶ┐ĮÕŖĀŃüÖŃéŗŃü¬Ńü®ŃüŚŃü”õĮ£µłÉŃüĢŃéīŃéŗŃü«ŃüīķĆÜÕĖĖŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃĆüŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüÕŠīńČÜŃü«µ╝½ńö╗Ńü»ŃĆüÕģłĶĪīŃüÖŃéŗµ╝½ńö╗ŃéÆń┐╗µĪłŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃüŗŃéēŃĆüÕģłĶĪīŃüÖŃéŗµ╝½ńö╗ŃéÆÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü©ŃüÖŃéŗõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Ķ¦ŻŃüĢŃéīŃéŗŃĆé
µ£ĆÕłżÕ╣│µłÉ9Õ╣┤7µ£ł17µŚź µ░æķøå51ÕĘ╗6ÕÅĘ2714ķĀü ’╝łŃāØŃāæŃéżŃāŹŃé»Ńé┐Ńéżõ║ŗõ╗Č’╝ē
Ńü©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüżŃüŠŃéŖŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü»õ╗¢õ║║Ńü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü¦ŃüéŃéŗÕ┐ģĶ”üŃü»Ńü¬ŃüÅŃĆüĶć¬ÕłåŃü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü«õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃüīµłÉń½ŗŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüåŃéŗŃĆüŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüØŃü«õĖŖŃü¦ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®ń»äÕø▓Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Õłżńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ŃüŖŃüäŃü”µ¢░Ńü¤Ńü½õ╗śõĖÄŃüĢŃéīŃü¤ÕēĄõĮ£ńÜäķā©ÕłåŃü«Ńü┐Ńü½ŃüżŃüäŃü”ńö¤ŃüśŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Õģ▒ķĆÜŃüŚŃüØŃü«Õ«¤Ķ│¬ŃéÆÕÉīŃüśŃüÅŃüÖŃéŗķā©ÕłåŃü½Ńü»ńö¤ŃüśŃü¬ŃüäŃü©Ķ¦ŻŃüÖŃéŗŃü«ŃüīńøĖÕĮōŃü¦ŃüéŃéŗŃĆéŃüæŃüĀŃüŚŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃüīÕĤĶæŚõĮ£ńē®ŃüŗŃéēńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤ÕłźÕĆŗŃü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü©ŃüŚŃü”ĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢõĖŖŃü«õ┐ØĶŁĘŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃü«Ńü»ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü½µ¢░Ńü¤Ńü¬ÕēĄõĮ£ńÜäĶ”üń┤ĀŃüīõ╗śõĖÄŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüŃü¦ŃüéŃüŻŃü”’╝łĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģń¼¼2µØĪ1ķĀģ11ÕÅĘ’╝ēŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ŃüåŃüĪÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Õģ▒ķĆÜŃüÖŃéŗķā©ÕłåŃü»ŃĆüõĮĢŃéēµ¢░Ńü¤Ńü¬ÕēĄõĮ£ńÜäĶ”üń┤ĀŃéÆÕɽŃéĆŃééŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕłźÕĆŗŃü«ĶæŚõĮ£ńē®Ńü©ŃüŚŃü”õ┐ØĶŁĘŃüÖŃü╣ŃüŹńÉåńö▒ŃüīŃü¬ŃüäŃüŗŃéēŃü¦ŃüéŃéŗŃĆé
µ£ĆÕłżÕ╣│µłÉ9Õ╣┤7µ£ł17µŚź µ░æķøå51ÕĘ╗6ÕÅĘ2714ķĀü ’╝łŃāØŃāæŃéżŃāŹŃé»Ńé┐Ńéżõ║ŗõ╗Č’╝ē
ŃüżŃüŠŃéŖŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®Ńü»ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕēĄõĮ£µĆ¦Ńüīõ╗śõĖÄŃüĢŃéīŃü¤ķā©ÕłåŃü«Ńü┐Ńü½ńö¤ŃüśŃéŗŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃéīõ╗źÕż¢Ńü«ÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü©Õģ▒ķĆÜŃüÖŃéŗķā©ÕłåŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®Ńü«Ńü┐ŃüīÕÅŖŃüČŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜŃéŁŃāŻŃā®Ńé»Ńé┐Ńā╝Ńü«ŃāæŃā¢Ńā¬ŃéĘŃāåŃ鯵©®ŃéäÕÉäń©«ń¤źńÜäĶ▓ĪńöŻµ©®Ńü«ķ¢óõ┐éŃü©Ńü»’╝¤
ÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®ń»äÕø▓
ķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗ŃĆīŃéŁŃāŻŃā│ŃāćŃéŻŃā╗ŃéŁŃāŻŃā│ŃāćŃéŻŃĆŹŃü«Ńé╣ŃāłŃā╝Ńā¬Ńā╝ÕĤń©┐ŃéÆÕ░ÅĶ¬¼ÕĮóÕ╝ÅŃü¦Õ¤ĘńŁåŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ÕĤõĮ£ĶĆģŃüīŃĆüÕĮōĶ®▓ÕĤń©┐Ńü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”µ╝½ńö╗Ńü«Õ¤ĘńŁåŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¤µ╝½ńö╗Õ«ČŃĆüÕÅŖŃü│ŃĆüµ╝½ńö╗Õ«ČŃüŗŃéēĶżćĶŻĮŃü«Ķ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü”ŃüäŃü¤õ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüµ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü»Õģ▒ÕÉīĶæŚõĮ£ńē®Ńü¬ŃüäŃüŚÕĤõĮ£Ńü«õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ŃüéŃü¤ŃéŗŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü«õĖĆķā©Ńü¦ŃüéŃéŗŃé│Ńā×ńĄĄŃĆüĶĪ©ń┤ÖńĄĄŃĆüŃā¬ŃāłŃé░Ńā®ŃāĢŃéäńĄĄŃü»ŃüīŃüŹ’╝łµ£¼õ╗ČÕĤńö╗’╝ēŃü«õĮ£µłÉŃā╗ĶżćĶŻĮŃā╗ķģŹÕĖāŃü«ÕĘ«µŁóŃéƵ▒éŃéüŃü¤õ║ŗõŠŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«õ║ŗõŠŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃé│Ńā×ńĄĄńŁēŃü«ĶżćĶŻĮŃü½ŃüżŃüäŃü”µ╝½ńö╗Õ«ČŃüŗŃéēŃüŚŃüŗÕł®ńö©Ķ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü”ŃüŖŃéēŃüÜŃĆüÕĤõĮ£ĶĆģŃüŗŃéēŃü«Õł®ńö©Ķ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüØŃééŃüØŃééµ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü½ÕĤõĮ£ĶĆģŃü«ĶæŚõĮ£µ©®ŃüīÕÅŖŃéōŃü¦ŃüäŃéŗ’╝łõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ÕĮōŃü¤Ńéŗ’╝ēŃü«ŃüŗŃĆüÕÅŖŃéōŃü¦ŃüäŃéŗŃü©ŃüŚŃü”ÕĤõĮ£ĶĆģŃüŗŃéēŃü«Õł®ńö©Ķ©▒Ķ½ŠŃééÕłźķĆöÕ┐ģĶ”üŃüŗÕÉ”ŃüŗŃüīÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüŃüŠŃü¦õ║ēŃéÅŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ£Ćķ½śĶŻüŃü»ŃĆüŃüŠŃüÜŃĆüµ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü»ÕĤõĮ£Õ░ÅĶ¬¼Ńü«õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ÕĮōŃü¤ŃéŗŃüŗÕÉ”ŃüŗŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Õłżńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤
µ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü»’╝īĶó½õĖŖÕæŖõ║║ŃüīÕÉäÕø×ŃüöŃü©Ńü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬Ńé╣ŃāłŃā╝Ńā¬Ńā╝ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüŚ’╝īŃüōŃéīŃéÆ’╝ö’╝É’╝ÉÕŁŚĶ®░ŃéüÕĤń©┐ńö©ń┤Ö’╝ō’╝ɵ×ÜŃüŗŃéē’╝Ģ’╝ɵ×Üń©ŗÕ║”Ńü«Õ░ÅĶ¬¼ÕĮóÕ╝ÅŃü«ÕĤń©┐Ńü½ŃüŚ’╝īõĖŖÕæŖõ║║Ńü½ŃüŖŃüäŃü”’╝īµ╝½ńö╗Õī¢Ńü½ÕĮōŃü¤ŃüŻŃü”õĮ┐ńö©Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃü©µĆØŃéÅŃéīŃéŗķā©ÕłåŃéÆķÖżŃüŹ’╝īŃüŖŃüŖŃéĆŃüŁŃüØŃü«ÕĤń©┐Ńü½õŠØµŗĀŃüŚŃü”µ╝½ńö╗ŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåµēŗķĀåŃéÆń╣░ŃéŖĶ┐öŃüÖŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŖÕłČõĮ£ŃüĢŃéīŃü¤Ńü©ŃüäŃüåŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆéŃüōŃü«õ║ŗÕ«¤Ńü½ŃéłŃéīŃü░’╝īµ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü»Ķó½õĖŖÕæŖõ║║õĮ£µłÉŃü«ÕĤń©┐ŃéÆÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü©ŃüÖŃéŗõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃüŗŃéē’╝īĶó½õĖŖÕæŖõ║║Ńü»’╝īµ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü½ŃüżŃüäŃü”ÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü©ŃüäŃüåŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŗŃĆé
µ£ĆÕłżÕ╣│µłÉ13 Õ╣┤10µ£ł25µŚź ÕłżµÖé1767ÕÅĘ115ķĀü’╝łŃéŁŃāŻŃā│ŃāćŃéŻŃéŁŃāŻŃā│ŃāćŃéŻõ║ŗõ╗Č’╝ē
ńČÜŃüæŃü”ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½Õłżńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüØŃüŚŃü”’╝īõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü¦ŃüéŃéŗµ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü«Õł®ńö©Ńü½ķ¢óŃüŚ’╝īÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗĶó½õĖŖÕæŖõ║║Ńü»µ£¼õ╗ČķĆŻĶ╝ēµ╝½ńö╗Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗõĖŖÕæŖõ║║Ńüīµ£ēŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü©ÕÉīõĖĆŃü«ń©«ķĪ×Ńü«µ©®Õł®ŃéÆÕ░éµ£ēŃüŚ’╝īõĖŖÕæŖõ║║’╝łõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģ’╝ēŃü«µ©®Õł®Ńü©Ķó½õĖŖÕæŖõ║║’╝łÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģ’╝ēŃü«µ©®Õł®Ńü©ŃüīõĮĄÕŁśŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŗŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃéē’╝īõĖŖÕæŖõ║║Ńü«µ©®Õł®Ńü»õĖŖÕæŖõ║║Ńü©Ķó½õĖŖÕæŖõ║║Ńü«ÕÉłµäÅŃü½ŃéłŃéēŃü¬ŃüæŃéīŃü░ĶĪīõĮ┐ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃü©Ķ¦ŻŃüĢŃéīŃéŗŃĆé
ÕÉīõĖŖ
ŃüżŃüŠŃéŖŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃüīńŗ¼Ķć¬Ńü½ÕēĄõĮ£ŃüŚŃü¤ķā©ÕłåŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®Ńü©ÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®Ńüīńŗ¼ń½ŗŃü½õĮĄÕŁśŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆüŃü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆé
ńŗ¼ń½ŗŃü½õĮĄÕŁśŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ╗źõĖŖŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃüŗŃéēÕł®ńö©Ķ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü”ŃüäŃéīŃü░õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®Ńü«õŠĄÕ«│Ńü½Ńü»Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃüīŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃüŗŃéēŃü«Õł®ńö©Ķ©▒Ķ½ŠŃüīŃü¬ŃüäķÖÉŃéŖŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®ŃéÆõŠĄÕ«│ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŗŃĆüŃü©ŃüäŃüåŃéÅŃüæŃü¦ŃüÖŃĆé
õ╗źõĖŖŃü«ÕłżõŠŗŃéÆĶĖÅŃüŠŃüłŃü”ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü©õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü½µĢ┤ńÉåŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
- ÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®’╝ÜÕĤĶæŚõĮ£ńē®’╝ŗõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«Õģ©ķā©
- õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µ©®Õł®’╝Üõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ÕēĄõĮ£ķā©ÕłåŃü«Ńü┐
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗķÜøŃü«µ│©µäÅńé╣

õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®ĶĆģŃü«µ©®Õł®ŃéÆķü®ÕłćŃü½Õ░ŖķćŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéõ║ŗÕ«¤õĖŖŃü«Ķ©▒Õ«╣ŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüµ│ĢńÜäŃü¬Ķ©▒Ķ½ŠŃü¬ŃüÅõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗŃü«Ńü»ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½Ńü¬ŃéŗŃüŖŃüØŃéīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╗źõĖŗŃü¦Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆķü®µ│ĢŃü½ÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Õ┐ģĶ”üŃü¬ńó║Ķ¬Źõ║ŗķĀģŃü©µēŗńČÜŃüŹŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¬¼µśÄŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£Ńé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│Ńü«ńó║Ķ¬Ź
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕēĄõĮ£ŃüÖŃéŗÕēŹŃü½ŃĆüŃüŠŃüÜńó║Ķ¬ŹŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»õ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£Ńé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│Ńü«µ£ēńäĪŃü¦ŃüÖŃĆéńÅŠÕ£©ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«µ©®Õł®ĶĆģŃüīõ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£ŃéÆõ║ŗÕ«¤õĖŖĶ©▒Õ«╣ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńŖȵ│üŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµ│ĢńÜäŃü¬Ķ©▒Ķ½ŠŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃüōŃü©Ńü½µ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
µ©®Õł®ĶĆģŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüŃüéŃéēŃüŗŃüśŃéüõ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£Ńé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│ŃéÆÕģ¼ĶĪ©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«ń»äÕø▓ÕåģŃü¦Ńü«Õł®ńö©Ńü¦ŃüéŃéīŃü░µ│ĢńÜäŃü½ŃééĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü»Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│ŃüīÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕåģÕ«╣ŃéÆÕŹüÕłåńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤µØĪõ╗ČŃéÆķüĄÕ«łŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕÅéĶĆā’╝Ühololive õ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£Ńé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│
ÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®ńó║Ķ¬Ź
µ¼ĪŃü½ńó║Ķ¬ŹŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£µ©®ńŖȵ│üŃü¦ŃüÖŃĆéĶæŚõĮ£µ©®Ńü½Ńü»õ┐ØĶŁĘµ£¤ķ¢ōŃüīŃüéŃéŖŃĆüĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«µŁ╗ÕŠī70Õ╣┤ŃéÆńĄīķüÄŃüÖŃéŗŃü©µ©®Õł®ŃüīµČłµ╗ģŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüŃü¤Ńü©ŃüłÕĤĶæŚõĮ£ńē®Ńü«õ┐ØĶŁĘµ£¤ķ¢ōŃüīńĄéõ║åŃüŚŃü”ŃüäŃü”ŃééŃĆüŃüØŃü«õĮ£ÕōüŃéÆÕ¤║Ńü½ŃüŚŃü¤ń┐╗Ķ©│ŃéäńĘ©µø▓Ńü¬Ńü®Ńü«õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«µ©®Õł®ŃüīõŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”ÕŁśńČÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüÕēĄõĮ£ŃüŚŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃüīŃĆīÕēĄõĮ£µĆ¦ŃĆŹŃü«Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃééķćŹĶ”üŃü¬ńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéÕŹśŃü¬Ńéŗµ©ĪÕåÖŃéäĶ╗ĮÕŠ«Ńü¬µö╣ÕżēŃü»õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü©ŃüŚŃü”Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü¬ŃüäÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗńé╣Ńü½µ│©µäÅŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
µ©®Õł®ĶĆģŃü©Ńü«õ║żµĖēŃā╗Õźæń┤ä
Ńé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│ŃüīŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃéäŃĆüŃé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│Ńü«ń»äÕø▓ŃéÆĶČģŃüłŃéŗÕł®ńö©ŃéÆĶĪīŃüåÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüµ©®Õł®ĶĆģŃü©Ńü«õ║żµĖēŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŠŃüܵ©®Õł®ĶĆģŃéÆńē╣Õ«ÜŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüÕć║ńēłńżŠŃéäĶæŚõĮ£µ©®ń«ĪńÉåÕøŻõĮōŃüīń¬ōÕÅŻŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃééÕżÜŃüäŃü¦ŃüÖŃĆ鵩®Õł®ĶĆģŃüīńē╣Õ«ÜŃü¦ŃüŹŃü¤ŃéēŃĆüÕģĘõĮōńÜäŃü¬Õł®ńö©µØĪõ╗ČŃü½ŃüżŃüäŃü”ÕŹöĶŁ░ŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ķÜøŃĆüÕł®ńö©ÕĮóµģŗŃü©Õ»ŠõŠĪŃĆüµ©®Õł®Ńü«ÕÅ¢µē▒ŃüäŃü¬Ńü®Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ®│ń┤░Ńü¬µØĪõ╗ČŃéƵśÄńó║Ńü½ŃüŚŃĆüÕ┐ģŃüܵøĖķØóŃü¦Ńü«Õźæń┤äŃü©ŃüŚŃü”µ«ŗŃüÖŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéÕÅŻķĀŁŃü¦Ńü«ÕÉłµäÅŃüĀŃüæŃü¦Ńü»ŃĆüÕŠīŃü½µā│Õ«ÜÕż¢Ńü«Õł®ńö©ÕłČķÖÉŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤ŃéŖŃĆüĶ┐ĮÕŖĀŃü«Õł®ńö©µ¢ÖŃéÆĶ½ŗµ▒éŃüĢŃéīŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃü¦ŃüÖŃĆé
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗķÜøŃü«µ│©µäÅńé╣

õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü©õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü«ÕÅīµ¢╣Ńü«µ©®Õł®Ńüīķ¢óõ┐éŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéõĖƵ¢╣Ńü«Ķ©▒Ķ½ŠŃüĀŃüæŃü¦Ńü»ķü®µ│ĢŃü¬Õł®ńö©Ńü©Ńü»Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüäŃü¤ŃéüŃĆüµģÄķćŹŃü¬µ©®Õł®Õć”ńÉåŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéõ╗źõĖŗŃü¦Ńü»ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆķü®µ│ĢŃü½Õł®ńö©ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Õ┐ģĶ”üŃü¬ńó║Ķ¬Źõ║ŗķĀģŃü©µēŗńČÜŃüŹŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¬¼µśÄŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃü«ńó║Ķ¬Ź
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®ŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗķÜøŃü»ŃĆüĶżćµĢ░Ńü«µ©®Õł®ŃüīķćŹÕ▒żńÜäŃü½ÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃü»õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Õģ©õĮōŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”µ©®Õł®ŃéƵīüŃüĪŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃü»µ¢░Ńü¤Ńü½ÕēĄõĮ£ŃüŚŃü¤ķā©ÕłåŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ńü┐µ©®Õł®ŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕł®ńö©Ńü½Ńü»ÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”õĖĪĶĆģŃüŗŃéēŃü«Ķ©▒Ķ½ŠŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
Õł®ńö©Ķ©▒Ķ½ŠŃü«ÕÅ¢ÕŠŚ
Õł®ńö©Ķ©▒Ķ½ŠŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüÖŃéŗķÜøŃü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®µ│Ģń¼¼28µØĪŃü½ŃéłŃéŖÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃüŗŃéēŃü©ŃĆüõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģŃüŗŃéēŃü«Ķ©▒Ķ½ŠŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéÕł®ńö©ńø«ńÜäŃéäń»äÕø▓ŃéƵśÄńó║Ńü½ŃüŚŃü¤Õźæń┤äµØĪõ╗ČŃéÆĶ©ŁÕ«ÜŃüŚŃĆüÕ░åµØźŃü«Õł®ńö©ÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃééĶĆāµģ«ŃüŚŃü¤Ķ©▒Ķ½ŠµØĪõ╗ČŃéÆÕ«ÜŃéüŃéŗŃüōŃü©Ńüīµ£øŃüŠŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé
Õł®ńö©µÖéŃü«µ│©µäÅõ║ŗķĀģ
Õ«¤ķÜøŃü«Õł®ńö©Ńü½ķÜøŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüĶ©▒Ķ½ŠŃüĢŃéīŃü¤Õł®ńö©ń»äÕø▓ŃéÆÕÄ│Õ«łŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕĤĶæŚõĮ£ĶĆģŃā╗õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ĶæŚõĮ£ĶĆģõĖĪµ¢╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ķü®ÕłćŃü¬Ńé»Ńā¼ŃéĖŃāāŃāłĶĪ©Ķ©śŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńČÖńČÜńÜäŃü¬Õł®ńö©Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüµ©®Õł®ķ¢óõ┐éŃü«Õżēµø┤Ńü½µ│©µäÅŃéƵēĢŃüäŃĆüÕł®ńö©ńŖȵ│üŃü«Ķ©śķī▓ŃéÆķü®ÕłćŃü½õ┐Øń«ĪŃüÖŃéŗŃü«ŃééķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝Üõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ŃāłŃā®Ńā¢Ńā½Ńü»Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ńøĖĶ½ćŃéÆ
õ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü«ÕēĄõĮ£Ńā╗Õł®ńö©Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®µ│ĢŃü«µŁŻńó║Ńü¬ńÉåĶ¦ŻŃü©ķü®ÕłćŃü¬Õ»ŠÕ┐£ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéĶ©▒Ķ½ŠŃéÆÕŠŚŃü”ŃüäŃü¬Ńüäõ║īµ¼ĪÕēĄõĮ£Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüń¦üńÜäÕł®ńö©Ńü«ń»äÕø▓ŃéÆĶČģŃüłŃü¤Õł®ńö©ŃéäÕģ¼ķ¢ŗŃü»ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµģÄķćŹŃü¬Õ»ŠÕ┐£Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ĶæŚõĮ£µ©®õŠĄÕ«│Ńü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃüŗÕÉ”ŃüŗŃü«Õłżµ¢ŁŃü»Õ░éķ¢ĆńÜäŃü¦ÕŠ«Õ”ÖŃü¬Ńé▒Ńā╝Ńé╣ŃééÕżÜŃüäŃü¤ŃéüŃĆüĶæŚõĮ£µ©®ŃéÆÕ░éķ¢ĆŃü©ŃüÖŃéŗÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüĖŃü«ńøĖĶ½ćŃéÆŃüŖŃüÖŃüÖŃéüŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõ║īµ¼ĪńÜäĶæŚõĮ£ńē®Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕĢÅķĪīŃéƵ£¬ńäČŃü½ķś▓ŃüÄŃĆüķü®ÕłćŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéīŃü░ŃĆüÕēĄõĮ£µ┤╗ÕŗĢŃéÆÕ«ēÕģ©Ńü½ńČÖńČÜŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃĆüńē╣Ńü½ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½ķ½śŃüäÕ░éķ¢ĆµĆ¦ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéĶ┐æÕ╣┤ŃĆüĶæŚõĮ£µ©®ŃéÆŃéüŃüÉŃéŗń¤źńÜäĶ▓ĪńöŻµ©®Ńü»µ│©ńø«ŃéÆķøåŃéüŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»Ńü«Õ┐ģĶ”üµĆ¦Ńü»ŃüŠŃüÖŃüŠŃüÖÕóŚÕŖĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦Ńü»ń¤źńÜäĶ▓ĪńöŻŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗŃéĮŃā¬ŃāźŃā╝ŃéĘŃā¦Ńā│µÅÉõŠøŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ń┤░ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü«ÕÅ¢µē▒ÕłåķćÄ’╝ÜITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ŃāóŃāćŃā½Ńü«ķü®µ│ĢÕī¢ń¤źńÜäĶ▓ĪńöŻµ©®ĶæŚõĮ£µ©®