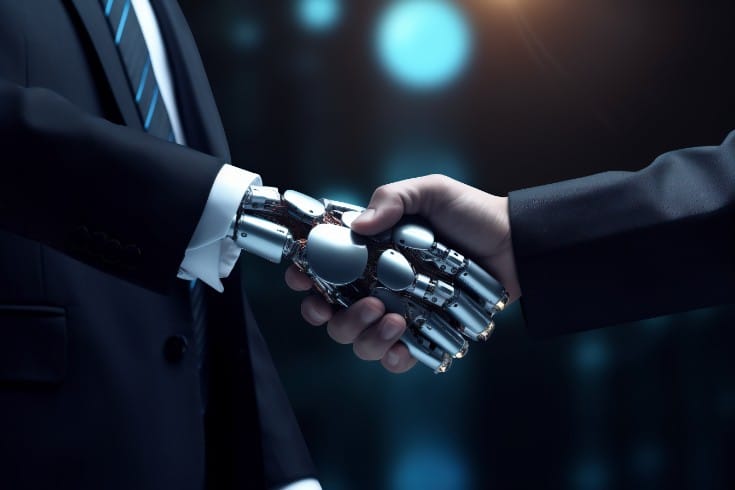実用新案権とは?特許権との違いを分かりやすく解説

「ペットボトルのキャップ」や「布団叩き」「朱肉不要の印鑑(通称:シャチハタ)」、この3つに共通すること、それは「実用新案権」として法的な保護を受けている点です。実用新案権とは、日常的によく目にする知的財産権のひとつで、分かりやすく言えば「ちょっとした発明」です。特筆すべき発展的な技術がなくても、新しく作り出した特徴があれば、実用新案の対象になります。
この記事では、実用新案権とはいったいどのようなものなのかを解説します。
この記事の目次
実用新案権と特許権

先程「ちょっとした発明」と言いましたが、実用新案権の専門的な定義としては「自然法則を利用した技術的思想の創作に対して認められる権利」とあります。特許権にも類似しているようにも見えますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
実用新案権と特許権の最も大きな違いは、実用新案権には発明としての新しさや進歩性が、特許権ほどには求められないことです。
実用新案法(定義)
第2条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
特許法(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2つの違いは、実用新案権は特許権ほどの高度さを必要としないという点にもあり、だから実用新案法では、「発明」ではなく、「考案」とされています。アイデアや工夫をもとに生み出した創作という点では同じでも、誰も開発することのできなかった技術というほどではない、発明と呼ぶには革新的・技術的な発展があるわけではない創作を保護するのが実用新案権なのです。
また、実用新案権の保護対象は実用新案法第3条より、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限られています。特許権で見られる方法の考案、物の製造方法の考案は実用新案登録されません。ソフトウェアや化学物質等も同様であって、これらの保護を求める場合には、特許出願する必要があります。
実用新案権とは
特許権を取得するうえでの最大の難関は審査です。発明としての要件(自然法則を利用している・再現が難しく、高度な創作であるなど)と、特許としての要件(産業に利用可能である・進歩性があるなど)の両方を兼ね備えていなければ審査の対象とさえなりません。
実用新案権と無審査登録主義
一方、特許とは異なり、実用新案は無審査登録主義をとっています。実用新案登録出願においては、実体的な内容が審査されることはなく、登録申請の書類などに不備がなければ、半年ほどで特許庁が管理する特許原簿に実用新案権の設定登録がされます。
実用新案を登録出願する際には、出願手続とともに最初の3年分の登録料(年金)を特許庁に納付します。実用新案権は、特許原簿への登録によって発生し、登録実用新案の内容を公示する登録実用新案公報(実用新案掲載公報)が特許庁より発行されます。
この実用新案権は出願日から満10年経過をもって満了します。ただし、登録料を特許庁に納付し続けないと、権利が消滅します。
有効な実用新案権は、有効な特許権と同等の効力を発揮します。つまり、実用新案権者は、(非営利目的の事業を含む)業として登録実用新案(実用新案登録を受けた考案)を実施する権利を専有します。また、実用新案権者は、登録実用新案を実施する権利を他者に許諾(ライセンス)したり、譲渡したりできます。
実用新案権のメリット

実用新案権と特許権は、どちらも新しい技術を保護するための権利ですが、その内容には大きな違いがあります。
特許権は、非常に厳格な審査を経て登録されます。そのため、一度権利が認められれば、その保護は非常に強力です。万が一、他社があなたの技術を模倣した場合でも、裁判などで権利を主張し、十分な保護を受けることができます。しかし、特許権の審査には時間と費用がかかるというデメリットもあります。
一方、実用新案権は、特許権のような厳格な審査がありません。そのため、比較的簡単かつスピーディーに登録できるのが最大のメリットです。新しいアイデアをいち早く形にしたい場合や、費用を抑えたい場合に有効な選択肢となります。
ただし、審査がない分、実用新案権は特許権に比べて保護が限定的である点に注意が必要です。いざという時に権利を行使するためには、別途、技術評価を請求するなど、手続きが必要になることがあります。
また、実用新案の出願から3年以内であれば、同じ内容の創作について特許に切り替えて出願をすることができます。その場合は実用新案の出願時にさかのぼり、特許出願をしたこととみなされます。「特許の申請には時間がかかるから、とりあえず権利の保護のみしておきたい」というようなケースでは、先に登録が簡単な実用新案を申請しておいて、準備が整った時点で特許出願をする、といった手段も可能です。
実用新案権のデメリット

実用新案権は、登録が簡単である一方、デメリットといえる面もあります。例えば、特許権の保護期間が20年なのに対して、実用新案権の保護期間は10年と半分の短さになっています。
実用新案権は、特許権のように事前の厳しい審査がないため、その有効性について疑問が生じることがあります。そのため、もしあなたが実用新案権を持っていて、他の人があなたの技術を無断で使用している場合に、その行為をやめさせたり(差し止め)、損害の賠償を求めたりする際には、少し手間がかかります。
具体的には、まず特許庁長官に申請し、「実用新案技術評価書」という書類を作成してもらう必要があります。この評価書は、あなたの実用新案が本当に有効かどうかを専門の審査官が判断した結果がまとめられたものです。この評価書を相手方に提示し、警告することで初めて、差し止めや損害賠償の請求に進むことができます。
このように、特許権と比べると、実用新案権の場合は権利を行使するまでに多くの手続きが必要になるというデメリットを理解しておきましょう。
実用新案は、無審査で登録されるため、後から「実はこの権利は有効ではなかった」という問題(無効理由)が見つかる可能性が、特許権に比べて高くなります。
もし、あなたが誰かから実用新案権を侵害していると警告を受けた場合、その実用新案に無効理由があると思われるなら、その旨を相手に伝えられます。さらに、無効審判を請求して、その審判で「この実用新案権は無効である」という決定(無効審決)が確定すれば、その実用新案権は最初から存在しなかったことになります。
実用新案権者が相手方に警告しまたは権利を行使した場合において、実用新案登録を無効とする審決が確定したときには、実用新案権者は、警告または権利行使によって相手方に与えた損害を賠償する責任を負います。ただし、実用新案権の有効性を否定しない見解の実用新案技術評価書に基づいて警告または権利行使をしたときや、相当の注意を払った上で警告または権利行使をしたときには、損害賠償責任は発生しません。
これは特許権の行使の際にはないリスクであり、実用新案登録出願または実用新案権の行使にあたり予め承知しておくべき事項です。
実用新案権の侵害
実用新案権の侵害は、特許権侵害と同様に「直接侵害」と「間接侵害」に大別されます。直接侵害はさらに「文言侵害」と「均等侵害」に分けられます。
文言侵害とは、対象製品が実用新案の構成要件をすべて満たしている場合に成立する侵害です。登録された実用新案の内容と完全に一致する製品を無断で製造・販売すると文言侵害となりますが、構成要件を一つでも欠いていれば侵害は成立しません。
しかし、構成要件の一部が異なっていても、実質的に同じ技術的範囲内であれば侵害となる場合があります。これが「均等論」による均等侵害です。均等侵害が認められるためには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 異なる部分が考案の本質的部分ではないこと。
- その部分を置き換えても同じ目的や効果が得られること
- 製造時にその置き換えを専門家が容易に思いつけること
- 対象製品が出願時の公知技術と同一でないこと
- 出願手続きで意識的に除外されたものでないこと
一方、間接侵害は、直接侵害には該当しなくても、侵害を誘発する可能性が極めて高い行為です。例えば、侵害品にのみ使用される専用部品を供給する行為などがこれに当たります。このような行為は、直接的な侵害ではなくても、実用新案権の保護の観点から侵害行為として扱われます。
関連記事:特許権侵害の判断基準は?判例を解説
実用新案権を巡る裁判例

実用新案権の侵害が争われた代表的な事例として「足先支持パッド事件」があります。
足先支持パッド事件は、スポーツ用品メーカーである原告会社が「足先支持パッド」の実用新案権を保有していました。被告会社は、もともと原告から商品を仕入れて販売する取引関係にありました。しかし、その後取引を中止し、独自に類似商品を開発して販売を始めました。
原告会社は、被告会社の商品が自社の実用新案権を侵害していると主張し、製造・販売の差し止めと既存商品の廃棄を求めて訴訟を起こしています。このような元取引先による模倣品の製造・販売は、実用新案権の侵害でよく見られるトラブルです。
文言侵害について
裁判では、原告の実用新案「足先支持パッド」が持つ7つの構成要件と被告商品を詳細に比較しました。
①足指の付け根部の下側に嵌め込み、
②柔軟で弾性を有する素材の
③足先支持パッドであって、
④足裏における触球部の上辺から少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置させる水平部と、
⑤少なくとも第2指と第3指との間、第3指と第4指との間、第4指と小指との間にそれぞれ入り込む第1、第2および第3凸状部とからなり、
⑥パッド水平部の上面および3個のパッド凸状部の両側面は、各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し、
⑦少なくとも第1および第2凸状部が高さ方向に長く延びることにより、第1と第2凸状部間および第2と第3凸状部間は半円形側面になり、第2指と第3指との間および第3指と第4指との間で足裏に保持される足先支持パッド。
構成要件は、足指の付け根に装着する柔軟な素材のパッドで、足指の間に入り込む凸状の突起部分があり、足裏にフィットする形状などが細かく定められていました。
裁判所が被告商品を検証した結果、7つの構成要件のうち5つ(①②③⑤⑦)は満たしていることが確認されています。しかし、残り2つの要件(④水平部の配置範囲と⑥湾曲形状の一部)については満たしていないと判断されました。
実用新案権の文言侵害が成立するためには、すべての構成要件を満たさなければなりません。そのため、2つの要件を満たしていない被告商品については、文言侵害は認められませんでした。
均等侵害について

文言侵害は否定されましたが、裁判所は「均等論」に基づいて侵害の有無の検討を行い、被告商品と原告の実用新案との相違点(構成要件④と⑥)について、次のように判断しています。
まず、相違点は製品の本質的な部分ではないと認定しました。つまり、足先支持パッドとしての基本的な機能に影響しない部分だということです。
次に、相違があっても製品の効果は同じであることを確認しました。被告商品の構成でも、原告の実用新案と同じように足をサポートする効果が得られるということです。また、このような置き換えは、専門家であれば容易に思いつくレベルのものだと判断しました。
最後の2つの要件について、被告側は「公知技術から容易に作れるもの」や「意図的に除外されたもの」であることを証明できませんでした。
以上の理由から、裁判所は被告商品が原告の実用新案と実質的に同等であり、均等侵害に当たると認定しています。つまり、完全に同じでなくても、実質的に同じ技術範囲に含まれるため侵害になるとの判断です。
そして、被告の侵害行為により原告会社に生じた損害額については、
実用新案法29条1項は、実用新案権又は専用実施権侵害の場合に、侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡数量に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる旨規定するところ、「単位数量当たりの利益額」とは、製品の販売価格から製造原価等その製造販売に追加的に要した費用を控除した額(限界利益)と解するのが相当である。
大阪地方裁判所2016年3月17日判決
として、原告会社の損害額1億4790万6617円と弁護士費用1500万円、合計1億6290万6617円の支払いと、商品の製造、譲渡等の禁止を命じました。
原告会社から商品を仕入れて販売していた会社が自社で開発した侵害商品を販売するというのは、他の商品についても見られる事例であり、実用新案権においては、ありがちなトラブルと言えます。
関連記事:特許・商標・著作権などの知的財産権侵害リスクとその対策とは
実用新案権が侵害された場合の対応
実用新案権が侵害された場合、権利者は差止請求や損害賠償請求などの法的措置を取ることができますが、特許権とは異なる重要な手続きがあります。
まず、権利行使の前に必ず実用新案技術評価書を特許庁から取得し、侵害者に警告を行う必要があります(実用新案法第29条の2)。この手続きを経なければ、差止めや損害賠償の請求はできません。
差止請求により、侵害品の製造・販売の停止や既存製品の廃棄を求めることができ、模倣品の流通を防げます。損害賠償請求については、特許権の場合と異なり「過失の推定」が適用されないため、権利者側が侵害者の故意・過失を立証する必要があります。これは権利者にとって大きな負担となるため、十分な証拠収集が不可欠です。
実際の事例では、足先支持パット事件のように1億円を超える損害賠償が認められたケースがある一方、目隠しシール事件のように権利の無効を理由に請求が認められなかったケースもあります。そのため、権利行使を検討する際は、知的財産権に精通した弁護士に相談し、権利の有効性評価をはじめ、総合的な検討を行うことが重要です。
まとめ:実用新案権侵害への適切な対応が重要
実用新案権の侵害は、直接的な模倣だけでなく、均等侵害や間接侵害といった形で発生することもあります。
実用新案は、特許の対象となる「発明」と比較して、より実用的な考案を保護するものです。そのため、特許とは異なる種類の権利侵害が問題となる場合もあります。しかし、どのようなケースであっても、専門家が適切な対応を行うことで、これらの侵害行為に対して効果的に対抗することが可能です。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。近年、実用新案権をめぐる知的財産権は注目を集めており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所では知的財産に関するソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:IT・ベンチャーの企業法務
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: ビジネスモデルの適法化知的財産権