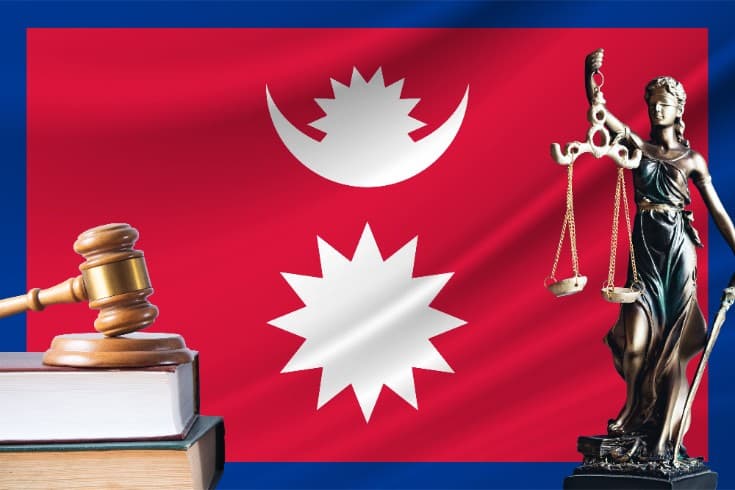ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃüīÕ«ÜŃéüŃéŗŃé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣

Õ£░õĖŁµĄĘŃü½µĄ«ŃüŗŃüČÕ│ČÕøĮŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü»ŃĆüµ¼¦ÕĘ×ķĆŻÕÉł’╝łEU’╝ēÕŖĀńø¤ÕøĮŃü©ŃüŚŃü”Ńü«Õ«ēÕ«ÜµĆ¦ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ÕøĮķÜøńÜäŃü½ķŁģÕŖøńÜäŃü¬ń©ÄÕłČŃéÆĶāīµÖ»Ńü½ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«Ńé░ŃāŁŃā╝ŃāÉŃā½õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”õ║ŗµźŁµŗĀńé╣Ńü©ŃüŚŃü”Ńü«õŠĪÕĆżŃéÆķ½śŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃüīµ¼¦ÕĘ×ŃĆüõĖŁµØ▒ŃĆüŃéóŃāĢŃā¬Ńé½ÕĖéÕĀ┤ŃüĖŃü«Ńé▓Ńā╝ŃāłŃé”Ńé¦ŃéżŃü©ŃüŚŃü”ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣ŃüĖŃü«ķĆ▓Õć║ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗķÜøŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü©Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü«µ×ĀńĄäŃü┐ŃéƵĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüõ║ŗµźŁŃü«µłÉÕŖ¤Ńü½õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü»ŃĆüõĖ╗Ńü½Ķŗ▒ÕøĮŃü«1948Õ╣┤õ╝ÜńżŠµ│ĢŃéÆÕ¤║ńżÄŃü©ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüĶŗ▒ń▒│µ│Ģ’╝łŃé│ŃāóŃā│ŃāŁŃā╝’╝ēŃü«õ╝ØńĄ▒Ńü½µĀ╣ÕĘ«ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃü»ŃĆüµłÉµ¢ćµ│ĢŃéƵ│ĢõĮōń│╗Ńü«õĖŁÕ┐āŃü½µŹ«ŃüłŃéŗµŚźµ£¼Ńü«Õż¦ķÖĖµ│Ģ’╝łŃéĘŃāōŃā½ŃāŁŃā╝’╝ēŃü©Ńü»µĀ╣µ£¼ńÜäŃü¬µĆصā│ŃüīńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüµ│Ģõ╗żŃü«Ķ¦ŻķćłŃü½ŃüŖŃüäŃü”ÕłżõŠŗŃüīķćŹĶ”üŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéƵףŃü¤ŃüÖŃü©ŃüäŃüåńē╣ÕŠ┤ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü«ķüĢŃüäŃüīŃĆüõ╝ÜńżŠķüŗÕ¢ČŃü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬Õ«¤ÕŗÖŃĆüńē╣Ńü½ńĄīÕ¢ČķÖŻŃü«Ķ▓¼õ╗╗ŃéäµäŵĆص▒║Õ«ÜŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīµģŻŃéīĶ”¬ŃüŚŃéōŃüĀµģŻĶĪīŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗµ¦śŃĆģŃü¬Õü┤ķØóŃéÆńö¤Ńü┐Õć║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╝ÜńżŠŃü«Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©ÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüµŚźÕĖĖńÜäŃü¬µźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃéƵŗģŃüåŃĆīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃĆŹŃü©ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µ£Ćķ½śµäŵĆص▒║իܵ®¤ķ¢óŃü¦ŃüéŃéŗŃĆīµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃĆŹŃü©ŃüäŃüåõ║īŃüżŃü«õĖ╗Ķ”üŃü¬µ®¤ķ¢óŃü½ŃéłŃüŻŃü”µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«ķüŗÕ¢ČŃéƵö»ŃüłŃéŗÕĮ╣ĶüĘŃéäŃā½Ńā╝Ńā½Ńü½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ▓ĀŃüåŃĆīĶ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖ’╝łFiduciary Duties’╝ēŃĆŹŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīĶ▓ĀŃüåÕ¢äń«Īµ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃéäÕ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃü©ķĪ×õ╝╝ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃéäķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«µ│ĢńÜäĶ┐ĮÕÅŖŃü«ŃüéŃéŖµ¢╣Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüĶŗ▒ń▒│µ│Ģńē╣µ£ēŃü«ÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ķ¦ŻķćłŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü¦Ńü»Õģ©Ńü”Ńü«õ╝ÜńżŠŃü½ŃĆīõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣’╝łCompany Secretary’╝ēŃĆŹŃü«Ķ©ŁńĮ«Ńüīµ│ĢÕŠŗŃü¦ńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüōŃü«ÕĮ╣ĶüĘŃüīõ╝ÜńżŠŃü«µ│ĢÕŗÖŃā╗ńĘÅÕŗÖŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ŃéÆõĖĆÕģāńÜäŃü½µŗģŃüåŃü©ŃüäŃüåńé╣ŃééŃĆüµŚźµ£¼Ńü½Ńü»Ńü¬ŃüäŃā”ŃāŗŃā╝Ńé»Ńü¬ÕłČÕ║”Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü½ŃüŖŃüæŃéŗńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░Ńü«ÕÅ»µ▒║Ķ”üõ╗ČŃüīµŚźµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃéłŃéŖŃééÕÄ│µĀ╝Ńü½Ķ©ŁÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéäŃĆüõ╝ÜĶ©łÕ¤║µ║¢Ńü©ŃüŚŃü”ÕøĮķÜøĶ▓ĪÕŗÖÕĀ▒ÕæŖÕ¤║µ║¢’╝łIFRS’╝ēŃü«ķü®ńö©ŃüīÕģ©ńżŠŃü½ńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║ŃéÆĶ©Łń½ŗŃā╗ķüŗÕ¢ČŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüÕ«¤ÕŗÖńÜäŃü½µźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬Ķ½¢ńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼ń©┐Ńü¦Ńü»ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╝ÜńżŠķüŗÕ¢ČŃü©Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü«µ│ĢńÜäµ×ĀńĄäŃü┐Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüńē╣Ńü½µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīõ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ńĢÖµäÅŃüÖŃü╣ŃüŹķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣Ńü½ńä”ńé╣ŃéÆÕĮōŃü”Ńü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü«Õ¤║ńżÄŃü©Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü«µ×ĀńĄäŃü┐
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╝ÜńżŠµ│ĢÕŗÖŃü«µĀ╣Õ╣╣ŃéÆŃü¬ŃüÖµ│ĢÕŠŗŃü»ŃĆüŃĆīõ╝ÜńżŠµ│Ģ’╝łThe Companies Law, Cap. 113’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢÕŠŗŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Ķ©Łń½ŗŃüŗŃéēķüŗÕ¢ČŃĆüń«ĪńÉåŃĆüŃüØŃüŚŃü”µĖģń«ŚŃü½Ķć│ŃéŗŃüŠŃü¦Ńü«Ńā®ŃéżŃāĢŃéĄŃéżŃé»Ńā½Õģ©Ķł¼ŃéÆÕīģµŗ¼ńÜäŃü½Ķ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü¦õ║ŗµźŁŃéÆĶĪīŃüåŃüÖŃü╣Ńü”Ńü«õ╝ÜńżŠŃüīµ║¢µŗĀŃüÖŃü╣ŃüŹÕ¤║µ£¼µ│ĢÕģĖŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠµ│ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕģ¼Õ╝ÅŃü¬µāģÕĀ▒Ńü»ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«ÕĢåµźŁńÖ╗Ķ©śŃü¬Ńü®ŃéÆń«ĪĶĮäŃüÖŃéŗŃĆīõ╝ÜńżŠńÖ╗Ķ©śŃā╗ń¤źńÜäĶ▓ĪńöŻÕ║ü’╝łDepartment of Registrar of Companies and Intellectual Property’╝ēŃĆŹŃü«Ńé”Ńé¦Ńā¢ŃéĄŃéżŃāłŃü¦ńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÅéĶĆā’╝Üõ╝ÜńżŠńÖ╗Ķ©śŃā╗ń¤źńÜäĶ▓ĪńöŻÕ║ü
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüŃüōŃü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü©ŃĆüÕĆŗŃĆģŃü«õ╝ÜńżŠŃü«ŃĆīµå▓µ│ĢŃĆŹŃü©ŃééŃüäŃüłŃéŗõ║īŃüżŃü«Õ¤║µ£¼Õ«Üµ¼ŠŃĆüŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪŃĆīÕ¤║µ£¼Õ«Üµ¼Š’╝łMemorandum of Association’╝ēŃĆŹŃü©ŃĆīõ╗śÕ▒×իܵ¼Š’╝łArticles of Association’╝ēŃĆŹŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ķüŗÕ¢ČŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕ¤║µ£¼Õ«Üµ¼ŠŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«ÕĢåÕÅĘŃĆüµĀ¬õĖ╗Ńü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü«ń»äÕø▓ŃĆüµÄłµ©®Ķ│ćµ£¼ķćæŃü¬Ńü®ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Õ»ŠÕż¢ńÜäŃü¬Õ¤║µ£¼õ║ŗķĀģŃéÆÕ«ÜŃéüŃéŗµ¢ćµøĖŃü¦ŃüÖŃĆéõĖƵ¢╣ŃĆüõ╗śÕ▒×իܵ¼ŠŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃéäµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü«ķüŗÕ¢ČµēŗńČÜŃüŹŃĆüÕĮ╣ÕōĪŃü«ķüĖõ╗╗µ¢╣µ│ĢŃĆüµĀ¬Õ╝ÅĶŁ▓µĖĪŃü«Ńā½Ńā╝Ńā½Ńü¬Ńü®ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Õåģķā©ńÜäŃü¬ķüŗÕ¢ČĶ”ÅÕēćŃéÆĶ®│ń┤░Ńü½Õ«ÜŃéüŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠµ│ĢŃü»ŃĆüŃüōŃü«õ╗śÕ▒×իܵ¼ŠŃü«ŃāóŃāćŃā½Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüń¼¼õĖĆķÖäÕēćŃü«AĶĪ©’╝łTable A of the First Schedule’╝ēŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕżÜŃüÅŃü«õ╝ÜńżŠŃüīŃüōŃéīŃéÆķøøÕĮóŃü©ŃüŚŃü”Ķć¬ńżŠŃü«õ╗śÕ▒×իܵ¼ŠŃéÆõĮ£µłÉŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü«µ│Ģõ╗żŃüŖŃéłŃü│իܵ¼ŠŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü»õĖ╗Ńü½õ║īŃüżŃü«µ®¤ķ¢óŃü½ŃéłŃüŻŃü”µŗģŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõĖĆŃüżŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µŚźÕĖĖńÜäŃü¬ńĄīÕ¢ČŃü©µźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃéƵŗģÕĮōŃüÖŃéŗŃĆīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü’╝łBoard of Directors’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃééŃüåõĖĆŃüżŃüīŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µēƵ£ēĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗµĀ¬õĖ╗Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃĆüիܵ¼ŠÕżēµø┤ŃéäÕĮ╣ÕōĪķüĖõ╗╗Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤õ╝ÜńżŠŃü«µĀ╣Õ╣╣Ńü½ķ¢óŃéÅŃéŗķćŹĶ”üõ║ŗķĀģŃéƵ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗµ£Ćķ½śµäŵĆص▒║իܵ®¤ķ¢óŃü¦ŃüéŃéŗŃĆīµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝Ü’╝łGeneral Meeting of Shareholders’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«õ║īÕ▒żµ¦ŗķĆĀŃü»µŚźµ£¼Ńü«µĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠÕłČÕ║”Ńü©Õģ▒ķĆÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕēŹĶ┐░Ńü«ķĆÜŃéŖŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü»Ķŗ▒ń▒│µ│ĢŃéÆÕ¤║ńżÄŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµ│Ģõ╗żŃü«µØĪµ¢ćĶ¦ŻķćłŃü½ŃüéŃü¤ŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüķüÄÕÄ╗Ńü«ĶŻüÕłżµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕłżõŠŗŃüīµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬µäÅÕæ│ŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠµ│ĢCap. 113Ńü«µØĪµ¢ćŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃéīŃéēŃüīÕ«¤ķÜøŃü«ĶŻüÕłżŃü¦Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü½Ķ¦ŻķćłŃā╗ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃü¤ŃüŗŃü©ŃüäŃüåÕłżõŠŗµ│Ģ’╝łŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃāŁŃā╝’╝ēŃü«ń¤źĶŁśŃüīŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü©Ķ▓¼õ╗╗
Ķ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖ’╝łFiduciary Duties’╝ēŃü«µ”éÕ┐Ą
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü«õĖŗŃü¦ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»õ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Õ║āń»äŃü¬ŃĆīĶ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖ’╝łFiduciary Duties’╝ēŃĆŹŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīõ╝ÜńżŠŃü«ÕÅŚĶ©ŚĶĆģ’╝łtrustee’╝ēŃüŠŃü¤Ńü»õ╗ŻńÉåõ║║’╝łagent’╝ēŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃéƵ£ĆÕż¦Õī¢ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ĶĪīÕŗĢŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåŃĆüĶŗ▒ń▒│µ│ĢŃü«õ┐ĪĶ¬Źķ¢óõ┐éŃüŗŃéēµ┤Šńö¤ŃüŚŃü¤µźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬µ”éÕ┐ĄŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ķ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µ£ĆÕ¢äŃü«Õł®ńøŖŃü«Ńü¤ŃéüŃü½Ķ¬ĀÕ«¤Ńü½’╝łbona fide’╝ēĶĪīÕŗĢŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃĆüÕł®ńøŖńøĖÕÅŹŃéÆÕø×ķü┐ŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃĆüŃüØŃüŚŃü”õĖÄŃüłŃéēŃéīŃü¤µ©®ķÖÉŃéÆŃüØŃü«ńø«ńÜäŃü«ń»äÕø▓ÕåģŃü¦Ńü«Ńü┐ĶĪīõĮ┐ŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃü¬Ńü®ŃĆüĶżćµĢ░Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃüŗŃéēµ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ŃĆīÕ¢äń«Īµ│©µäÅńŠ®ÕŗÖ’╝łÕ¢äĶē»Ńü¬Ńéŗń«ĪńÉåĶĆģŃü«µ│©µäÅńŠ®ÕŗÖ’╝ēŃĆŹŃéäŃĆīÕ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃü©ŃĆüŃüØŃü«ńø«µīćŃüÖŃü©ŃüōŃéŹŃü»ķĪ×õ╝╝ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«µ│ĢńÜäÕ¤║ńøżŃü½Ńü»ķüĢŃüäŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃüīµ░æµ│ĢõĖŖŃü«Õ¦öõ╗╗Õźæń┤äŃü«ÕĤÕēćŃüŗŃéēÕ░ÄŃüŗŃéīŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«Ķ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüÕÅŚĶ©ŚĶĆģŃüīÕÅŚńøŖĶĆģŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶĪīÕŗĢŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåĶĪĪÕ╣│µ│Ģ’╝łEquity’╝ēõĖŖŃü«ÕÄ│µĀ╝Ńü¬õ┐ĪĶ¬Źķ¢óõ┐éŃü«ÕĤÕēćŃü½ńö▒µØźŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕł®ńøŖńøĖÕÅŹŃü«ńŖȵ│üŃü¬Ńü®Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õłżµ¢ŁŃüīŃü¬ŃüĢŃéīŃéŗÕéŠÕÉæŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬Õł®ńøŖŃüīõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃü©Õ»Šń½ŗŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīÕ░æŃüŚŃü¦ŃééŃüéŃéŗńŖȵ│üŃéÆķü┐ŃüæŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃüÜŃĆüŃééŃüŚŃüØŃü«ŃéłŃüåŃü¬ńŖȵ│üŃü½ķÖźŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«õ║ŗÕ«¤ŃéÆõ╝ÜńżŠŃü½ķ¢ŗńż║ŃüŚŃĆüµē┐Ķ¬ŹŃéÆÕŠŚŃéŗŃü¬Ńü®Ńü«µēŗńČÜŃüŹŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©ķćŹĶ”üÕłżõŠŗ
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃüīµ£ĆŃééµ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹńé╣Ńü«õĖĆŃüżŃü»ŃĆüŃĆīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüĶ¬░Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃü«ŃüŗŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕĢÅŃüäŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńŁöŃüłŃü¦ŃüÖŃĆéńĄÉĶ½¢ŃüŗŃéēĶ©ĆŃüłŃü░ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Ķ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüµ│ĢńÜäŃü½Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü©ŃüäŃüåńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ│Ģõ║║µĀ╝Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü«Ńü┐Ķ▓ĀŃüåŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕĆŗŃĆģŃü«µĀ¬õĖ╗ŃéäŃĆüµĀ¬õĖ╗Õģ©õĮōŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ńø┤µÄźńÜäŃü½Ķ▓ĀŃüåŃééŃü«Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«ÕłżõŠŗµ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”õĖĆĶ▓½ŃüŚŃü”ńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ŃüōŃü«ńé╣ŃéƵśÄńó║Ńü½ńż║ŃüŚŃü¤ķćŹĶ”üŃü¬ÕłżõŠŗŃüīŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃüī2015Õ╣┤2µ£ł5µŚźŃü½õĖŗŃüŚŃü¤Wail Abuljebain v. Unetec-United Engineering and Technical Consultants et al, Civil Appeal 182/2009 õ║ŗõ╗ČŃü«Õłżµ▒║Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«õ║ŗõ╗ČŃü¦Ńü»ŃĆüŃüéŃéŗµĀ¬õĖ╗ŃüīŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü¦ŃüéŃéŗõ╗¢Ńü«µĀ¬õĖ╗Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃü«õĮ┐ķĆöŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ¬¼µśÄŃéƵ▒éŃéüŃéŗĶ©┤ŃüłŃéÆńø┤µÄźµÅÉĶĄĘŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¼¼õĖĆÕ»®Ńü«Õ£░µ¢╣ĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃüōŃü«Ķ©┤ŃüłŃéÆĶ¬ŹŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃüōŃéīŃéÆĶ”åŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ£Ćķ½śĶŻüŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü»õ╝ÜńżŠĶć¬õĮōŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ▓ĀŃéÅŃéīŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬Ķ©┤ŃüłŃü»õ╝ÜńżŠĶć¬Ķ║½Ńü«Õł®ńøŖŃü«Ńü¤ŃéüŃü½µÅÉĶĄĘŃüĢŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüķĆÜÕĖĖŃü»õ╝ÜńżŠŃüīÕĤÕæŖŃü©Ńü¬ŃéŗŃüŗŃĆüŃüØŃéīŃüīµ£¤ÕŠģŃü¦ŃüŹŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»µĀ¬õĖ╗Ńüīõ╝ÜńżŠŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶĪīŃüåŃĆīµ┤Šńö¤Ķ©┤Ķ©¤’╝łderivative action’╝ēŃĆŹŃü«ÕĮóÕ╝ÅŃéÆŃü©ŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃü©Õłżńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüĢŃéēŃü½Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüŃĆīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠĶć¬õĮōŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«µĀ¬õĖ╗ŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ķ¢óķĆŻõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃüØŃü«ŃéłŃüåŃü¬ńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃééŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃĆŹŃü©µśÄńó║Ńü½Ķ┐░Ńü╣Ńü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕłżõŠŗŃüīńż║ŃüÖµ│ĢÕĤÕēćŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃüŗŃéēŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü½µ┤ŠķüŻŃüĢŃéīŃü¤ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬ńż║ÕöåŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«õ╝üµźŁµ¢ćÕī¢Ńü¦Ńü»ŃĆüÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü«µäÅÕÉæŃü½µ▓┐ŃüŻŃü”ĶĪīÕŗĢŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕĮōńäČĶ”¢ŃüĢŃéīŃüīŃüĪŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣µ│ĢŃü«õĖŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ń¼¼õĖĆŃü«µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüŃüéŃüÅŃüŠŃü¦ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃéÆÕ«łŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╗«Ńü½ŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃü½Ńü»Ńü¬ŃéŗŃééŃü«Ńü«ŃĆüÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃéÆÕ«│ŃüÖŃéŗŃéłŃüåŃü¬ÕÅ¢Õ╝Ģ’╝łõŠŗŃüłŃü░ŃĆüõĖŹÕĮōŃü½Õ«ēõŠĪŃü¬õŠĪµĀ╝Ńü¦Ńü«ĶŻĮÕōüõŠøńĄ”Ńéäķ½śķĪŹŃü¬Ńā×ŃāŹŃéĖŃāĪŃā│ŃāłŃāĢŃéŻŃā╝Ńü«µö»µēĢŃüäŃü¬Ńü®’╝ēŃéÆĶ”¬õ╝ÜńżŠŃüŗŃéēµīćńż║ŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃéīŃü½ÕŠōŃüåŃü©ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖķüĢÕÅŹŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ÕĆŗõ║║ŃüīÕŁÉõ╝ÜńżŠŃéäŃüØŃü«Õ饵©®ĶĆģŃüŗŃéēµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤ŃéÆĶ½ŗµ▒éŃüĢŃéīŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆĶ▓ĀŃüåŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü«µīćńż║Ńü©ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃüīńøĖÕÅŹŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣µ│ĢŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃéÆÕä¬ÕģłŃüÖŃéŗÕłżµ¢ŁŃéÆõĖŗŃüÖµ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆÕŹüÕłåŃü½Ķ¬ŹĶŁśŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣’╝łCompany Secretary’╝ēŃü«ÕĮ╣Õē▓
Ķ©ŁńĮ«ńŠ®ÕŗÖŃü©µ│ĢńÜäÕ£░õĮŹ
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃüīÕ«ÜŃéüŃéŗŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃü«õĖŁŃü¦ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”µ£ĆŃééķ”┤µ¤ōŃü┐ŃüīĶ¢äŃüÅŃĆüŃüŗŃüżķćŹĶ”üŃü¬Ńü«ŃüīŃĆīõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣’╝łCompany Secretary’╝ēŃĆŹŃü«ÕŁśÕ£©Ńü¦ŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼171µØĪ’╝łSection 171 of the Companies Law, Cap. 113’╝ēŃü»ŃĆüÕģ©Ńü”Ńü«ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣õ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣ŃéÆ1ÕÉŹ’╝łŃüŠŃü¤Ńü»1ńżŠ’╝ēõ╗╗ÕæĮŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Ķ”ŵ©ĪŃéäõ║ŗµźŁÕåģÕ«╣Ńü½ķ¢óŃéÅŃéēŃü¬ŃüäńĄČÕ»ŠńÜäŃü¬Ķ”üõ╗ČŃü¦ŃüÖŃĆé┬Ā
õ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣Ńü½Ńü»ŃĆüµ│ĢÕŠŗõĖŖŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«Õ░éķ¢ĆĶ│ćµĀ╝Ńü»Ķ”üµ▒éŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆü18µŁ│õ╗źõĖŖŃü¦ŃüéŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüŃüØŃü«ĶüĘÕŗÖŃü«µĆ¦Ķ│¬õĖŖŃĆüõ╝ÜńżŠµ│ĢŃéäķ¢óķĆŻµ│ĢĶ”ÅŃü½ń▓ŠķĆÜŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü½µ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéķĆÜÕĖĖŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü½ŃéłŃüŻŃü”õ╗╗ÕæĮŃüĢŃéīŃĆüŃüØŃü«õ╗╗µ£¤ŃéäÕĀ▒ķģ¼ŃééÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃüīµ▒║Õ«ÜŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéķćŹĶ”üŃü¬ńé╣Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüī1ÕÉŹŃü«Ńü┐Ńü«ÕĀ┤ÕÉł’╝łÕŹśńŗ¼µĀ¬õĖ╗Ńü«ń¦üõ╝ÜńżŠŃéÆķÖżŃüÅ’╝ēŃĆüŃüØŃü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńüīõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣ŃéÆÕģ╝õ╗╗ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃüÜŃĆüÕĮ╣Õē▓Ńü«ÕłåķøóŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüµźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃü©Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ńøŻńØŻŃü«µ®¤ĶāĮŃüīõĖĆÕ«Üń©ŗÕ║”ŃĆüÕłåķøóŃüĢŃéīŃéŗõ╗ĢńĄäŃü┐Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ĶüĘÕŗÖÕåģÕ«╣Ńü©µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½ŃüŖŃüæŃéŗńøĖÕĮōµ®¤ĶāĮŃü©Ńü«ķüĢŃüä
õ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣Ńü«ĶüĘÕŗÖŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«ń«ĪńÉåńÜäŃā╗µ│ĢńÜäµēŗńČÜŃüŹŃü«ķüĄÕ«łŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½ķøåń┤äŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬ĶüĘÕŗÖÕåģÕ«╣Ńü»ÕżÜÕ▓ÉŃü½ŃéÅŃü¤ŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõĖ╗Ķ”üŃü¬ŃééŃü«Ńü©ŃüŚŃü”õ╗źõĖŗŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- µ│ĢÕ«ÜńÖ╗Ķ©śń░┐Ńü«ń«ĪńÉå’╝ܵĀ¬õĖ╗ÕÉŹń░┐ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńā╗ń¦śµøĖÕĮ╣ÕÉŹń░┐ŃĆüµŗģõ┐ص©®Ķ©ŁÕ«ÜńÖ╗Ķ©śń░┐Ńü¬Ńü®ŃĆüõ╝ÜńżŠµ│ĢŃü¦Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤ÕÉäń©«ńÖ╗Ķ©śń░┐ŃéƵŁŻńó║Ńü½õĮ£µłÉŃā╗õ┐Øń«ĪŃüÖŃéŗŃĆé
- õ╝ÜńżŠńÖ╗Ķ©śµēĆŃüĖŃü«µ│ĢիܵøĖķĪ×Ńü«µÅÉÕć║’╝ܵ»ÄÕ╣┤ŃĆüÕ╣┤µ¼ĪÕĀ▒ÕæŖµøĖ’╝łAnnual Return, Form HE32’╝ēŃéÆĶ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©Ńü©Õģ▒Ńü½õ╝ÜńżŠńÖ╗Ķ©śµēĆŃüĖµÅÉÕć║ŃüÖŃéŗŃü╗ŃüŗŃĆüÕĮ╣ÕōĪÕżēµø┤Ńéäµ£¼Õ║ŚµēĆÕ£©Õ£░Õżēµø┤Ńü¬Ńü®Ńü«ķÜøŃü½Õ┐ģĶ”üŃü¬ÕÉäń©«Õ▒ŖÕć║ŃéÆķüģµ╗×Ńü¬ŃüÅĶĪīŃüåŃĆé
- ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃā╗µĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü«ķüŗÕ¢Čµö»µÅ┤’╝Üõ╝ÜĶŁ░Ńü«µŗøķøåķĆÜń¤źŃü«ńÖ║ķĆüŃĆüĶŁ░õ║ŗķĆ▓ĶĪīŃü«ĶŻ£ÕŖ®ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ĶŁ░õ║ŗķī▓Ńü«õĮ£µłÉŃā╗õ┐Øń«ĪŃéÆĶĪīŃüåŃĆé
- õ╝ÜńżŠµ¢ćµøĖŃü«Ķ¬ŹĶ©╝’╝Üõ╝ÜńżŠŃü«Õģ¼Õ╝ŵ¢ćµøĖŃéäĶŁ░õ║ŗķī▓Ńüīń£¤µŁŻŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ©╝µśÄŃüŚŃĆüõ╝ÜńżŠÕŹ░’╝łCommon Seal’╝ēŃü«ķü®µŁŻŃü¬ń«ĪńÉåŃā╗õĮ┐ńö©ŃéÆńøŻńØŻŃüÖŃéŗŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü«ĶüĘÕŗÖŃü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüķĆÜÕĖĖŃĆüĶżćµĢ░Ńü«ķā©ńĮ▓Ńü½ŃüŠŃü¤ŃüīŃüŻŃü”Õć”ńÉåŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüńÖ╗Ķ©śķ¢óķĆŻµźŁÕŗÖŃéäµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜķüŗÕ¢ČŃü»ńĘÅÕŗÖķā©ŃüīŃĆüÕźæń┤äµøĖń«ĪńÉåŃéäŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ķüĄÕ«łŃü»µ│ĢÕŗÖķā©ŃüīŃĆüŃüØŃüŚŃü”ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«ĶŁ░õ║ŗķī▓õĮ£µłÉŃü»ńĄīÕ¢Čõ╝üńö╗Õ«żŃéäÕĮ╣ÕōĪń¦śµøĖŃüīµŗģÕĮōŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ÕĮóŃüīõĖĆĶł¼ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü¦Ńü»ŃüōŃéīŃéēŃü«ķćŹĶ”üŃü¬Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣µ®¤ĶāĮŃüīŃĆīõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåõĖĆŃüżŃü«µ│ĢÕ«ÜÕĮ╣ĶüĘŃü½ķøåń┤äŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µ│ĢńÜäŃā╗ĶĪīµö┐ńÜäńŠ®ÕŗÖŃü«Õ▒źĶĪīŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ▓¼õ╗╗Ńü«µēĆÕ£©ŃéƵśÄńó║Õī¢ŃüŚŃĆüŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ķüĄÕ«łŃéÆÕŠ╣Õ║ĢŃüĢŃüøŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣Ńü»ÕŹśŃü¬Ńéŗõ║ŗÕŗÖµŗģÕĮōĶĆģŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü½ŃüŖŃüäŃü”õĖŁÕ┐āńÜäŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéƵŗģŃüåŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ńā╗Ńé¬ŃāĢŃéŻŃéĄŃā╝Ńü©ŃüŚŃü”Ńü«Õü┤ķØóŃéÆÕ╝ĘŃüŵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆ鵥ĘÕż¢ŃüŗŃéēŃü«µŖĢĶ│ćÕ«ČŃüīŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½õ╝ÜńżŠŃéÆĶ©Łń½ŗŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃéäõ╝ÜĶ©łõ║ŗÕŗÖµēĆŃĆüõ┐ĪĶ©Śõ╝ÜńżŠŃü¬Ńü®ŃüīÕ░éķ¢ĆńÜäŃü¬ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü©ŃüŚŃü”õ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣ŃéÆÕ╝ĢŃüŹÕÅŚŃüæŃéŗŃüōŃü©ŃüīõĖĆĶł¼ńÜäŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüķü®ÕłćŃü¬Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃéÆķüĖõ╗╗ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃĆüÕååµ╗æŃü¬õ╝ÜńżŠķüŗÕ¢ČŃü«ķŹĄŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü©µ▒║ĶŁ░Ķ”üõ╗Č

ńĘÅõ╝ÜŃü«ń©«ķĪ×Ńü©µŗøķøå
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü»ŃĆüõĖ╗Ńü½ŃĆīÕ╣┤µ¼ĪµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝Ü’╝łAnnual General Meeting, AGM’╝ēŃĆŹŃü©ŃĆīĶ橵ÖéµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝Ü’╝łExtraordinary General Meeting, EGM’╝ēŃĆŹŃü«õ║īń©«ķĪ×Ńü½ÕłåŃüæŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Õ╣┤µ¼ĪµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝Ü’╝łAGM’╝ēŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕÉŹŃü«ķĆÜŃéŖµ»ÄÕ╣┤ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃéŗիܵÖéńĘÅõ╝ÜŃü¦ŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠµ│ĢŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Ķ©Łń½ŗŃüŗŃéē18Ńāȵ£łõ╗źÕåģŃü½µ£ĆÕłØŃü«AGMŃéÆķ¢ŗÕé¼ŃüŚŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü»ÕēŹÕø×Ńü«AGMŃüŗŃéē15Ńāȵ£łŃéÆĶČģŃüłŃü¬Ńüäķ¢ōķÜöŃü¦µ»ÄÕ╣┤ķ¢ŗÕé¼ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéAGMŃü«µŗøķøåŃü½Ńü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”µ£ĆõĮÄ21µŚźķ¢ōŃü«ķĆÜń¤źµ£¤ķ¢ōŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
õĖƵ¢╣ŃĆüĶ橵ÖéµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝Ü’╝łEGM’╝ēŃü»ŃĆüAGMõ╗źÕż¢Ńü½ķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃéŗÕģ©Ńü”Ńü«µĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃéäŃĆüõĖĆÕ«ÜÕē▓ÕÉłõ╗źõĖŖŃü«µĀ¬Õ╝ÅŃéÆõ┐ص£ēŃüÖŃéŗµĀ¬õĖ╗ŃüŗŃéēŃü«Ķ½ŗµ▒éŃüīŃüéŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½µŗøķøåŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
µÖ«ķĆܵ▒║ĶŁ░Ńü©ńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░
µĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü¦Ńü«µäŵĆص▒║Õ«ÜŃü»ŃĆüŃĆīµ▒║ĶŁ░’╝łResolution’╝ēŃĆŹŃü½ŃéłŃüŻŃü”ĶĪīŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüµ▒║ĶŁ░Ńü«ń©«ķĪ×Ńü©ŃüŚŃü”õĖ╗Ńü½ŃĆīµÖ«ķĆܵ▒║ĶŁ░’╝łOrdinary Resolution’╝ēŃĆŹŃü©ŃĆīńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░’╝łSpecial Resolution’╝ēŃĆŹŃüīÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µÖ«ķĆܵ▒║ĶŁ░Ńü»ŃĆüĶŁ░µ▒║µ©®ŃéÆĶĪīõĮ┐Ńü¦ŃüŹŃéŗµĀ¬õĖ╗Ńü«µŖĢŃüśŃü¤ńź©µĢ░Ńü«ķüÄÕŹŖµĢ░’╝ł50%ĶČģ’╝ēŃü«Ķ│øµłÉŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕÅ»µ▒║ŃüĢŃéīŃéŗµ▒║ĶŁ░Ńü¦ŃüÖŃĆéÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃéäńøŻµ¤╗ÕĮ╣Ńü«ķüĖõ╗╗ŃĆüķģŹÕĮōŃü«µē┐Ķ¬ŹŃü¬Ńü®ŃĆüµ»öĶ╝āńÜ䵌źÕĖĖńÜäŃü¬ķćŹĶ”üõ║ŗķĀģŃüīŃüōŃü«µÖ«ķĆܵ▒║ĶŁ░Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µ▒║Õ«ÜŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µĀ╣Õ╣╣Ńü½ķ¢óŃéÅŃéŗńē╣Ńü½ķćŹĶ”üŃü¬õ║ŗķĀģŃéƵ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ńö©ŃüäŃéēŃéīŃéŗŃĆüŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü¬Ķ”üõ╗ČŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃü¤µ▒║ĶŁ░Ńü¦ŃüÖŃĆéńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░ŃéÆÕÅ»µ▒║ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüĶŁ░µ▒║µ©®ŃéÆĶĪīõĮ┐Ńü¦ŃüŹŃéŗµĀ¬õĖ╗Ńü«µŖĢŃüśŃü¤ńź©µĢ░Ńü«4ÕłåŃü«3’╝ł75%’╝ēõ╗źõĖŖŃü«Ķ│øµłÉŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüµŗøķøåķĆÜń¤źŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüŃüØŃü«ĶŁ░µĪłŃüīńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░Ńü©ŃüŚŃü”µÅɵĪłŃüĢŃéīŃéŗµŚ©ŃéƵśÄĶ©śŃüŚŃĆüŃüŗŃüżµ£ĆõĮÄ21µŚźķ¢ōŃü«ķĆÜń¤źµ£¤ķ¢ōŃéÆĶ©ŁŃüæŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ╝ÜńżŠńÖ╗Ķ©śµēĆŃü«Ńé¼ŃéżŃāĆŃā│Ńé╣Ńü½ŃéłŃéīŃü░ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬õ║ŗķĀģŃü½Ńü»ńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░ŃüīĶ”üµ▒éŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- Õ¤║µ£¼Õ«Üµ¼ŠŃüŠŃü¤Ńü»õ╗śÕ▒×իܵ¼ŠŃü«Õżēµø┤
- ÕĢåÕÅĘŃü«Õżēµø┤
- Ķ│ćµ£¼ķćæŃü«µĖøÕ░æ’╝łÕłźķĆöŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃü«µē┐Ķ¬ŹŃééÕ┐ģĶ”ü’╝ē
- õ╝ÜńżŠŃü«õ╗╗µäŵĖģń«Ś
ŃüōŃüōŃü¦µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīµ│©ńø«ŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüŃüōŃü«ÕÅ»µ▒║Ķ”üõ╗ČŃü«ķüĢŃüäŃü¦ŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüիܵ¼ŠÕżēµø┤ŃéäÕÉłõĮĄŃĆüõ╝ÜńżŠĶ¦ŻµĢŻŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ķćŹĶ”üõ║ŗķĀģŃü«µ▒║ĶŁ░’╝łńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░’╝ēŃü½Ńü»ŃĆüĶŁ░µ▒║µ©®ŃéÆĶĪīõĮ┐Ńü¦ŃüŹŃéŗµĀ¬õĖ╗Ńü«ĶŁ░µ▒║µ©®Ńü«ķüÄÕŹŖµĢ░ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµĀ¬õĖ╗ŃüīÕć║ÕĖŁŃüŚŃĆüÕć║ÕĖŁŃüŚŃü¤µĀ¬õĖ╗Ńü«ĶŁ░µ▒║µ©®Ńü«3ÕłåŃü«2’╝łń┤ä66.7%’╝ēõ╗źõĖŖŃü«Ķ│øµłÉŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣µ│ĢŃü«75%Ńü©ŃüäŃüåĶ”üõ╗ČŃü»ŃĆüŃüōŃéīŃéłŃéŖŃééŃüŗŃü¬ŃéŖķ½śŃüäŃāÅŃā╝ŃāēŃā½Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«ķüĢŃüäŃü»ŃĆüńē╣Ńü½ÕÉłÕ╝üõ║ŗµźŁ’╝łŃéĖŃā¦ŃéżŃā│ŃāłŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝’╝ēŃü«ńĄäµłÉŃü½ŃüŖŃüäŃü”ķćŹĶ”üŃü¬µł”ńĢźńÜäµäÅÕæ│ŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆéŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü¦Ńü»ŃĆü25%ĶČģŃü«ĶŁ░µ▒║µ©®ŃéÆõ┐ص£ēŃüÖŃéŗÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Õ«Üµ¼ŠÕżēµø┤ŃéäĶ¦ŻµĢŻŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µĀ╣µ£¼ńÜäŃü¬µäŵĆص▒║Õ«ÜŃéÆÕŹśńŗ¼Ńü¦ķś╗µŁóŃüÖŃéŗŃĆīµŗÆÕÉ”µ©®ŃĆŹŃéƵīüŃüżŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«µä¤Ķ”ÜŃü¦3ÕłåŃü«1õ╗źõĖŖŃü«Õć║Ķ│ćµ»öńÄćŃéÆńó║õ┐ØŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░µŗÆÕÉ”µ©®ŃéƵīüŃü”Ńü¬ŃüäŃü©ĶĆāŃüłŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüµäÅÕø│ŃüøŃüÜŃüŚŃü”ńøĖµēŗµ¢╣Ńü½Õ╝ĘŃüäŃé│Ńā│ŃāłŃāŁŃā╝Ńā½µ©®ŃéÆõĖÄŃüłŃü”ŃüŚŃüŠŃüåÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüµĀ¬õĖ╗ķ¢ōÕźæń┤äŃü¬Ńü®ŃéÆĶ©ŁĶ©łŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»ŃĆüŃüōŃü«75%Ńü©ŃüäŃüåÕ¤║µ║¢ŃéÆÕēŹµÅÉŃü©ŃüŚŃü¤ŃāæŃā»Ńā╝ŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«õ║żµĖēŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
Õ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü«õ┐ØĶŁĘŃü©Ķ┐æµÖéŃü«ÕłżõŠŗ
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü»ŃĆüÕżÜµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗Ńü½ŃéłŃéŗµ©®ÕŖøŃü«µ┐½ńö©ŃüŗŃéēÕ░æµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗ŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃééĶ©ŁŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«õĖŁÕ┐āŃü©Ńü¬ŃéŗŃü«ŃüīŃĆüõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼202µØĪ’╝łSection 202 of the Companies Law, Cap. 113’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅŃĆīÕ£¦Ķ┐½ĶĪīńé║’╝łOppression’╝ēŃĆŹŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗµĢæµĖłńö│ń½ŗŃü”Ńü«ÕłČÕ║”Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«ńĄīÕ¢ČŃüīÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Õ£¦Ķ┐½ńÜäŃā╗õĖŹÕģ¼µŁŻŃü¬µ¢╣µ│ĢŃü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©ĶĆāŃüłŃéŗµĀ¬õĖ╗ŃüīŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”õ╝ÜńżŠŃü«µĖģń«ŚŃéäŃĆüÕżÜµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗Ńü½ŃéłŃéŗĶć¬ÕĘ▒Ńü«µĀ¬Õ╝ÅŃü«Ķ▓ĘÕÅ¢ÕæĮõ╗żŃü¬Ńü®ŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗÕłČÕ║”Ńü¦ŃüÖŃĆé┬Ā
ŃüōŃü«Õ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗õ┐ØĶŁĘŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµēŗńČÜŃüŹŃü«µśÄńó║Õī¢Ńü½Õ»äõĖÄŃüÖŃéŗŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½µ¢░ŃüŚŃüäÕłżõŠŗŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé2024Õ╣┤7µ£ł12µŚźŃü½ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õĖŖĶ©┤ĶŻüÕłżµēĆŃüīõĖŗŃüŚŃü¤ŃĆüFAIR CHAMPIONS MERIDIAN LTD ńżŠŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗõ║ŗõ╗ČŃü«Õłżµ▒║Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«õ║ŗõ╗ČŃü¦Ńü»ŃĆüÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńüīõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼202µØĪŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüÕżÜµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗Ńü½ŃéłŃéŗÕ£¦Ķ┐½ĶĪīńé║ŃéÆńÉåńö▒Ńü©ŃüŚŃü”õ╝ÜńżŠŃü«µĖģń«ŚŃüŠŃü¤Ńü»µĀ¬Õ╝ÅŃü«Ķ▓ĘÕÅ¢ŃéƵ▒éŃéüŃéŗńö│ń½ŗŃü”ŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüĶó½ÕæŖŃü¦ŃüéŃéŗÕżÜµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗Õü┤Ńü»ŃĆüÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü«ńö│ń½ŗŃü”Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńĢ░ĶŁ░ńö│ń½ŗŃü«µēŗńČÜŃüŹŃü«õĖŁŃü¦ŃĆüķĆåŃü½Õ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗŃĆīÕÅŹĶ©┤’╝łCounterclaim’╝ēŃĆŹŃéƵÅÉĶĄĘŃüŚŃéłŃüåŃü©Ķ®”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé┬Ā
õĖŖĶ©┤ĶŻüÕłżµēĆŃü»ń¼¼õĖĆÕ»®Ńü«Õłżµ¢ŁŃéƵö»µīüŃüŚŃĆüÕ£¦Ķ┐½ĶĪīńé║Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ©┤Ķ©¤µēŗńČÜŃüŹŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüĶó½ÕæŖ’╝łÕżÜµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗’╝ēŃüīńĢ░ĶŁ░ńö│ń½ŗŃü½õ╗śķÜÅŃüŚŃü”ÕÅŹĶ©┤ŃéƵÅÉĶĄĘŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ķ©▒ŃüĢŃéīŃü¬ŃüäŃü©Ńü«Õłżµ¢ŁŃéÆõĖŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłżµ▒║Ńü½ŃéłŃéīŃü░ŃĆüÕżÜµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗ŃüīõĮĢŃéēŃüŗŃü«Ķ½ŗµ▒éŃéÆĶĪīŃüäŃü¤ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü«ńö│ń½ŗŃü”Ńü©Ńü»ÕłźŃü½ŃĆüńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ¢░Ńü¤Ńü¬ńö│ń½ŗŃü”ŃéÆĶć¬ŃéēµÅÉĶĄĘŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕżÜµĢ░µ┤ŠµĀ¬õĖ╗ŃüīÕÅŹĶ©┤Ńü©ŃüäŃüåµēŗńČÜŃüŹŃéÆÕł®ńö©ŃüŚŃü”ŃĆüÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗ŃüŗŃéēŃü«µŁŻÕĮōŃü¬ńö│ń½ŗŃü”ŃéÆķüģÕ╗ČŃüĢŃüøŃü¤ŃéŖŃĆüĶżćķøæÕī¢ŃüĢŃüøŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆķś▓ŃüÉÕŖ╣µ×£ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«2024Õ╣┤Ńü«ÕłżõŠŗŃü»ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«ÕÅĖµ│ĢŃüīÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü«µ©®Õł®õ┐ØĶŁĘŃéÆÕ«¤ÕŖ╣ńÜäŃü½µ®¤ĶāĮŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü«µśÄńó║Ńü¬µēŗńČÜŃüŹńÜäķüōńŁŗŃéÆķćŹĶ”¢ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½µŖĢĶ│ćŃüÖŃéŗÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüŃüØŃü«µ©®Õł®Ńüīµ│ĢńÜäŃü½Õ╝ĘŃüÅõ┐ØĶŁĘŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüÖÕźĮõŠŗŃü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜĶ©łŃā╗ńøŻµ¤╗ÕłČÕ║”Ńü©IFRSŃü«Õ╝ĘÕłČķü®ńö©
ÕøĮķÜøĶ▓ĪÕŗÖÕĀ▒ÕæŖÕ¤║µ║¢’╝łIFRS’╝ēŃü«Õ╝ĘÕłČķü®ńö©
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜĶ©łÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗµ£ĆÕż¦Ńü«ńē╣ÕŠ┤Ńü»ŃĆüÕøĮķÜøĶ▓ĪÕŗÖÕĀ▒ÕæŖÕ¤║µ║¢’╝łInternational Financial Reporting Standards, IFRS’╝ēŃü«ķü®ńö©Ńüīµ│ĢÕŠŗŃü½ŃéłŃüŻŃü”ńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠµ│ĢCap. 113Ńü»ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü¦ńÖ╗Ķ©śŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕģ©Ńü”Ńü«õ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃüØŃü«Ķ”ŵ©ĪŃéäõĖŖÕĀ┤Ńā╗ķØ×õĖŖÕĀ┤Ńü«ÕłźŃéÆÕĢÅŃéÅŃüÜŃĆüEUŃüīµÄĪµŖ×ŃüŚŃü¤IFRSŃü½µ║¢µŗĀŃüŚŃü”Ķ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©ŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ”üµ▒éŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Õģ©Ńü”Ńü«õ╝ÜńżŠŃü«Ķ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©Ńü»ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Õģ¼Ķ¬Źõ╝ÜĶ©łÕŻ½ÕŹöõ╝Ü’╝łICPAC’╝ēŃü½ńÖ╗ķī▓ŃüĢŃéīŃü¤ÕģŹĶ©▒ŃéƵīüŃüżńøŻµ¤╗õ║║Ńü½ŃéłŃéŗńøŻµ¤╗ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆü2023Õ╣┤1µ£ł1µŚźõ╗źķÖŹŃĆüń┤öÕŻ▓õĖŖķ½śŃüī20õĖćŃā”Ńā╝ŃāŁõ╗źõĖŗŃĆüŃüŗŃüżńĘÅĶ│ćńöŻŃüī50õĖćŃā”Ńā╝ŃāŁõ╗źõĖŗŃü©ŃüäŃüåÕ¤║µ║¢ŃéÆ2Õ╣┤ķĆŻńČÜŃü¦µ║ĆŃü¤ŃüÖÕ░ÅĶ”ŵ©Īõ╝ÜńżŠŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµ│ĢÕ«ÜńøŻµ¤╗Ńü½õ╗ŻŃüłŃü”ŃĆüŃéłŃéŖń░ĪµśōńÜäŃü¬ŃĆīŃā¼ŃāōŃāźŃā╝’╝łReview Engagement’╝ēŃĆŹŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃüōŃü©ŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüōŃü«ÕģŹķÖżĶ”ÅÕ«ÜŃü½Ķ®▓ÕĮōŃüŚŃü¬ŃüäķÖÉŃéŖŃĆüÕģ©Ńü”Ńü«õ╝ÜńżŠŃüīIFRSŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅŃāĢŃā½Ńé╣Ńé│Ńā╝ŃāŚŃü«ńøŻµ¤╗ŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ķĆŻńĄÉµ▒║ń«ŚŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕ«¤ÕŗÖńÜäÕĮ▒ķ¤┐
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü½ŃüŖŃüæŃéŗIFRSŃü«Õ╝ĘÕłČķü®ńö©Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃüīķĆŻńĄÉĶ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©ŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗķÜøŃü½ŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«ÕżÜŃüÅŃü«õ╝üµźŁŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü¦õĖĆĶł¼Ńü½Õģ¼µŁŻÕ”źÕĮōŃü©Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü¤õ╝ÜĶ©łÕ¤║µ║¢’╝łJapanese GAAP, J-GAAP’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”µ▒║ń«ŚŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüJ-GAAPŃü©IFRSŃü©Ńü«ķ¢ōŃü½Ńü»õ╝ÜĶ©łÕć”ńÉåŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗķćŹĶ”üŃü¬ÕĘ«ńĢ░ŃüīĶżćµĢ░ÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«õ╝ÜĶ©łÕ¤║µ║¢Ńü¦Ńü»ŃĆüµĄĘÕż¢ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Ķ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©ŃéÆķĆŻńĄÉŃüÖŃéŗķÜøŃü½ŃĆüõĖĆÕ«ÜŃü«Ķ¬┐µĢ┤ŃéÆĶĪīŃüåŃüōŃü©Ńü¦ńÅŠÕ£░Õ¤║µ║¢Ńü«µĢ░ÕĆżŃéÆŃüØŃü«ŃüŠŃüŠÕł®ńö©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīĶ©▒Õ«╣ŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüIFRSŃéÆķü®ńö©ŃüÖŃéŗĶ”¬õ╝ÜńżŠŃüīÕŁÉõ╝ÜńżŠŃéÆķĆŻńĄÉŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«õ╝ÜĶ©łÕć”ńÉåŃéÆIFRSŃü½Õ«īÕģ©Ńü½µ║¢µŗĀŃüĢŃüøŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüJ-GAAPŃéƵÄĪńö©ŃüÖŃéŗµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«IFRSŃāÖŃā╝Ńé╣Ńü«Ķ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©ŃéÆŃĆüJ-GAAPŃü«ķĆŻńĄÉŃāæŃāāŃé▒Ńā╝ŃéĖŃü½ÕÅ¢ŃéŖĶŠ╝ŃéĆŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«ÕĘ«ńĢ░ŃéƵŁŻńó║Ńü½µŖŖµÅĪŃüŚŃĆüÕ┐ģĶ”üŃü¬õ┐«µŁŻõ╗ĢĶ©│’╝łńĄäµø┐õ╗ĢĶ©│’╝ēŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹõĖ╗Ķ”üŃü¬õ╝ÜĶ©łÕć”ńÉåŃü«ÕĘ«ńĢ░Ńü½Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬ķĀģńø«ŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
| ÕøĮķÜøĶ▓ĪÕŗÖÕĀ▒ÕæŖÕ¤║µ║¢’╝łIFRS’╝ē | µŚźµ£¼Õ¤║µ║¢’╝łJ-GAAP’╝ē | ķĆŻńĄÉŃüĖŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ | |
|---|---|---|---|
| Ńü«ŃéīŃéō (Goodwill) | ķØ×Õä¤ÕŹ┤ŃĆüµ»ÄÕ╣┤Ńü«µĖøµÉŹŃāåŃé╣ŃāłŃéÆÕ«¤µ¢Į | Ķ”ÅÕēćńÜäŃü¬Õä¤ÕŹ┤’╝łµ£ĆķĢĘ20Õ╣┤’╝ē | IFRSŃü¦Ńü»µĖøµÉŹŃüīŃü¬ŃüæŃéīŃü░Õł®ńøŖŃüīÕż¦ŃüŹŃüÅĶ©łõĖŖŃüĢŃéīŃéŗõĖƵ¢╣ŃĆüµĖøµÉŹµÖéŃü½Ńü»ÕĘ©ķĪŹŃü«µÉŹÕż▒ŃüīńÖ║ńö¤ŃüÖŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŖŃĆüÕł®ńøŖŃü«ÕżēÕŗĢµĆ¦Ńüīķ½śŃüŠŃéŗŃĆé |
| Õø║Õ«ÜĶ│ćńöŻŃü«Ķ®ĢõŠĪ (Valuation of Fixed Assets) | ÕåŹĶ®ĢõŠĪŃāóŃāćŃā½’╝łÕģ¼µŁŻõŠĪÕĆżĶ®ĢõŠĪ’╝ēŃü«ķüĖµŖ×ķü®ńö©ŃüīÕÅ»ĶāĮ | ÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ÕÅ¢ÕŠŚÕĤõŠĪŃāóŃāćŃā½ | ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Ķ│ćńöŻõŠĪÕĆżŃüīJ-GAAPŃéłŃéŖŃééķ½śŃüÅĶ®ĢõŠĪŃüĢŃéīŃĆüķĆŻńĄÉŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣ŃéĘŃā╝ŃāłõĖŖŃü«Ķ│ćńöŻķĪŹŃéäĶć¬ÕĘ▒Ķ│ćµ£¼ŃüīÕżēÕŗĢŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃĆé |
| Õ£©Õ║½Ķ®ĢõŠĪ (Inventory Valuation) | ÕŠīÕģźÕģłÕć║µ│Ģ’╝łLIFO’╝ēŃü»ń”üµŁó | ÕŠīÕģźÕģłÕć║µ│Ģ’╝łLIFO’╝ēŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŗ | J-GAAPŃü¦LIFOŃéƵÄĪńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüIFRSŃüĖŃü«õ┐«µŁŻŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüÕŻ▓õĖŖÕĤõŠĪŃü©Õł®ńøŖŃü½ÕĘ«ńĢ░Ńüīńö¤ŃüśŃéŗŃĆé |
| Ńā¬Ńā╝Ńé╣ (Leases) | IFRSń¼¼16ÕÅĘŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõĮ┐ńö©µ©®Ķ│ćńöŻŃü©ŃüŚŃü”Ńü╗Ńü╝Õģ©Ńü”Ńü«Ńā¬Ńā╝Ńé╣ŃéÆĶ│ćńöŻŃā╗Ķ▓ĀÕéĄŃü©ŃüŚŃü”Ķ©łõĖŖ | Ńé¬ŃāÜŃā¼Ńā╝ŃāåŃéŻŃā│Ńé░Ńā╗Ńā¬Ńā╝Ńé╣Ńü»Ńé¬ŃāĢŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣Õć”ńÉåŃüīõŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”õĖĆĶł¼ńÜä | ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«ŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣ŃéĘŃā╝ŃāłŃüīĶæŚŃüŚŃüŵŗĪÕż¦ŃüŚŃĆüĶć¬ÕĘ▒Ķ│ćµ£¼µ»öńÄćŃéäĶ▓ĀÕ饵»öńÄćŃü¬Ńü®Ńü«Ķ▓ĪÕŗÖµī浩ÖŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆõĖÄŃüłŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŗŃĆé |
ŃüōŃéīŃéēŃü«ÕĘ«ńĢ░Ńü»ŃĆüÕŹśŃü¬Ńéŗõ╝ÜĶ©łÕć”ńÉåõĖŖŃü«ŃāåŃé»ŃāŗŃé½Ńā½Ńü¬ÕĢÅķĪīŃü½Ńü©Ńü®ŃüŠŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüŃĆīŃü«ŃéīŃéōŃĆŹŃü«ķØ×Õä¤ÕŹ┤Ńā╗µĖøµÉŹŃāóŃāćŃā½Ńü»ŃĆüĶ▓ĘÕÅÄÕŠīŃü«ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«µźŁńĖŠŃüīõĖŹµī»Ńü½ķÖźŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü«ķĆŻńĄÉµÉŹńøŖĶ©łń«ŚµøĖŃü½õ║łµĖ¼õĖŹĶāĮŃü¬ÕĘ©ķĪŹŃü«µĖøµÉŹµÉŹÕż▒ŃéÆĶ©łõĖŖŃüĢŃüøŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆÕåģÕīģŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕø║Õ«ÜĶ│ćńöŻŃü«ÕåŹĶ®ĢõŠĪŃéäŃā¬Ńā╝Ńé╣Ńü«Ńé¬Ńā│ŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣Õī¢Ńü»ŃĆüķĆŻńĄÉĶ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©õĖŖŃü«Ķ│ćńöŻŃā╗Ķ▓ĀÕéĄŃü«Ķ”ŵ©ĪŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅÕżēÕŗĢŃüĢŃüøŃĆüµĀ¬õĖ╗ŃéäķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃü¬Ńü®Ńü«Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶ¬¼µśÄĶ▓¼õ╗╗Ńü½ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣ŃüĖŃü«ķĆ▓Õć║Ńéäõ╝üµźŁĶ▓ĘÕÅÄŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»ŃĆüµ│ĢÕŗÖŃāćŃāźŃā╝ŃāćŃā¬ŃéĖŃé¦Ńā│Ńé╣Ńü©õĖ”ĶĪīŃüŚŃü”ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«õ╝ÜĶ©łÕ¤║µ║¢Ńü«ÕĘ«ńĢ░ŃüīĶć¬ńżŠŃü«ķĆŻńĄÉĶ▓ĪÕŗÖŃü½õĖÄŃüłŃéŗÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©Õģ▒Ńü½ń▓Šµ¤╗ŃüŚŃĆüõ║ŗÕēŹŃü½Õ»ŠńŁ¢ŃéÆĶ¼øŃüśŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü»Ķŗ▒ÕøĮµ│ĢŃéÆÕ¤║ńżÄŃü©ŃüÖŃéŗŃé│ŃāóŃā│ŃāŁŃā╝Ńü«õĮōń│╗Ńü½Õ▒×ŃüŚŃĆüŃüØŃü«Ķ¦ŻķćłŃü©ķüŗńö©Ńü»µłÉµ¢ćµ│ĢŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüń®ŹŃü┐ķćŹŃüŁŃéēŃéīŃü¤ÕłżõŠŗŃü½ŃéłŃüŻŃü”µĘ▒ŃüÅÕĮóõĮ£ŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢńÜäĶāīµÖ»Ńü«ķüĢŃüäŃüīŃĆüõ╝ÜńżŠķüŗÕ¢ČŃü«ŃüéŃéēŃéåŃéŗÕü┤ķØóŃü½µŚźµ£¼Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃéÆĶ”üµ▒éŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃüÜŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü©ŃüäŃüåńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ│Ģõ║║µĀ╝Ńü«Õł®ńøŖŃéƵ£ĆÕż¦Õī¢ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗÕÄ│µĀ╝Ńü¬ŃĆīĶ¬ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃĆüŃüØŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü»µĀ¬õĖ╗ŃéäĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüéŃüÅŃüŠŃü¦ŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü«ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃüØŃü«ŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü«µäÅÕÉæŃü©ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖŃüīńøĖÕÅŹŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½ķćŹÕż¦Ńü¬Õłżµ¢ŁŃéÆĶ┐½ŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéµ¼ĪŃü½ŃĆüÕģ©Ńü”Ńü«õ╝ÜńżŠŃü½Ķ©ŁńĮ«ŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆīõ╝ÜńżŠń¦śµøĖÕĮ╣ŃĆŹŃü»ŃĆüµ│ĢիܵøĖķĪ×Ńü«µÅÉÕć║ŃüŗŃéēµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü«ķüŗÕ¢Čµö»µÅ┤ŃüŠŃü¦ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣µ®¤ĶāĮŃéÆõĖĆÕģāńÜäŃü½µŗģŃüåŃĆüµŚźµ£¼Ńü½Ńü»Ńü¬ŃüäŃā”ŃāŗŃā╝Ńé»ŃüŗŃüżķćŹĶ”üŃü¬ÕĮ╣ĶüĘŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü½ŃüŖŃüæŃéŗիܵ¼ŠÕżēµø┤Ńü¬Ńü®Ńü«ķćŹĶ”üõ║ŗķĀģŃü«ÕÅ»µ▒║Ńü½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«3ÕłåŃü«2ŃéÆõĖŖÕø×Ńéŗ75%õ╗źõĖŖŃü«Ķ│øµłÉŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¬ŃĆīńē╣Õłźµ▒║ĶŁ░ŃĆŹŃüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃĆüŃüōŃéīŃüīÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü«µ©®Õł®ŃéÆŃéłŃéŖÕ╝ĘŃüÅõ┐ØĶŁĘŃüÖŃéŗµ¦ŗķĆĀŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆü2024Õ╣┤Ńü«µ£Ćµ¢░ÕłżõŠŗŃü»ŃĆüÕ£¦Ķ┐½ĶĪīńé║Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕ░æµĢ░µĀ¬õĖ╗Ńü«µĢæµĖłµēŗńČÜŃüŹŃüīÕÅĖµ│ĢŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ«¤ÕŖ╣ńÜäŃü½µŗģõ┐ØŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£ĆÕŠīŃü½ŃĆüõ╝ÜĶ©łŃā╗ńøŻµ¤╗ÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕģ©ńżŠŃü½Õ╝ĘÕłČķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗÕøĮķÜøĶ▓ĪÕŗÖÕĀ▒ÕæŖÕ¤║µ║¢’╝łIFRS’╝ēŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õ╝ÜĶ©łÕ¤║µ║¢’╝łJ-GAAP’╝ēŃü©Õż¦ŃüŹŃüÅńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüńē╣Ńü½Ńü«ŃéīŃéōŃü«õ╝ÜĶ©łÕć”ńÉåŃéäĶ│ćńöŻĶ®ĢõŠĪŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü«ķĆŻńĄÉµ▒║ń«ŚŃü½ÕżÜÕż¦Ńü¬Õ«¤ÕŗÖńÜäÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü«ńøĖķüĢńé╣Ńü»ŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗµēŗńČÜŃüŹõĖŖŃü«ķüĢŃüäŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõ║ŗµźŁµł”ńĢźŃĆüŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃü«µ¦ŗń»ēŃĆüŃüØŃüŚŃü”Ńā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåŃü«ŃüéŃéŖµ¢╣ŃéƵĀ╣µ£¼ŃüŗŃéēÕĘ”ÕÅ│ŃüÖŃéŗµł”ńĢźńÜäĶ”üÕøĀŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«µ│ĢÕŗÖŃā╗õ╝ÜĶ©łõĖŖŃü«ńē╣µĆ¦ŃéÆõ║ŗÕēŹŃü½µĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüķü®ÕłćŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃĆüŃéŁŃāŚŃāŁŃé╣Ńü¦Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ŃéƵłÉÕŖ¤Ńü½Õ░ÄŃüÅŃü¤ŃéüŃü«õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¬ķŹĄŃü©Ńü¬ŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ