キプロスでの契約書作成・交渉時に問題となる民法・契約法

キプロス(正式名称、キプロス共和国)は、単なる観光地としてだけでなく、欧州連合(EU)の加盟国として、また、ビジネスフレンドリーな法制度を持つ国として、国際的なビジネスの舞台で注目を集めています。特に、日本企業がキプロスでの事業展開を検討する際、その契約法の理解は不可欠です。キプロスの契約法は、英国のコモン・ローを色濃く受け継いでおり、日本の民法とは根本的な思想や要件において重要な相違点が存在します。これらの違いを理解しないまま日本法と同じ感覚で契約交渉や締結に臨むと、意図せぬ法的リスクを抱え込む可能性があります。
本記事では、キプロスでのビジネスを検討されている日本企業を対象に、同国の契約法の根幹をなす「契約法(Cap. 149)」を中心に、その基本原則を解説します。契約が法的に有効と認められるための成立要件に焦点を当て、特に日本法との比較において注意すべき三つの重要な概念、すなわち「約因(Consideration)」、「契約締結意思(Intention to Create Legal Relations)」、そして「違約金・ペナルティ条項の特異な扱い」について、法令の条文や現地の判例を交えながら詳述します。
キプロスの契約法は、単なる当事者間の合意(意思表示の一致)だけでは契約の有効性を認めず、取引の形式や背景にある当事者の意図を厳格に問うコモン・ロー特有の構造を持っています。この構造を把握することは、キプロスにおける円滑かつ安全な事業活動の礎となります。
本稿では、キプロス共和国の契約法について、特に日本企業がビジネスを展開する上で留意すべき点を中心に解説します。
この記事の目次
キプロス契約法の基礎と英国コモン・ロー
キプロスの法制度は、公法分野ではフランス法などの大陸法の影響が見られる一方で、私法、特に契約法や不法行為法といったビジネスに直結する分野では、英国のコモン・ローの原則がその根幹をなしている「混合法体系(Mixed Legal System)」であることが特徴です。これは、1878年から1960年までの英国統治時代に、コモン・ローの諸原則が法典化され、制定法として導入された歴史的経緯に由来します。
その代表例が、キプロスの契約関係を規律する基本法である「契約法(The Contract Law, Chapter 149)」(以下「Cap. 149」といいます)です。この法律は、19世紀の英国コモン・ローの原則を法典化した1872年のインド契約法をほぼそのまま継受したものであり、英国法の影響が極めて色濃く反映されています。この法律の解釈において決定的に重要なのが、Cap. 149第2条の規定です。この条文は、同法で使用される表現は英国法で付与されている意味を持つものと推定され、法律全体の解釈は英国の法解釈の原則に従わなければならないと定めています。
This Law shall be interpreted in accordance with the principles of legal interpretation obtaining in England, and expressions used in it shall be presumed, so far as is consistent with their context, and except as may be otherwise expressly provided, to be used with the meaning attaching to them in English law and shall be construed in accordance therewith.
契約法(Cap. 149)第2条
この規定により、Cap. 149という成文法が存在するにもかかわらず、その解釈と適用は、判例を通じて形成・発展してきた英国のコモン・ローに大きく依存するという、二元的な構造が生まれています。日本の法務担当者が民法典の条文解釈に主眼を置くのとは異なり、キプロスの契約法を理解するためには、成文法の条文だけでなく、それを具体的に適用したキプロス最高裁判所の判例、さらには参照元である英国の判例法理の動向をも常に視野に入れる必要があります。キプロスの裁判所は、判例拘束性の原則(stare decisis)を採用しており、最高裁判所の判決は下級裁判所を法的に拘束するため、判例法が実務上、極めて重要な法源となっています。
キプロスにおける契約の成立要件と日本法との比較
Cap. 149第10条(1)は、有効な契約(contract)の成立要件を包括的に定めています。それによれば、「すべての合意(agreement)は、契約を締結する能力のある当事者の自由な同意によって、合法的な約因(consideration)と合法的な目的のために行われ、かつ、この法律によって明示的に無効と宣言されていない場合には、契約となる」とされています。この条文から、契約成立には「申込みと承諾による合意」「約因」「契約締結意思」「当事者の法的行為能力」といった複数の要素が必要であることがわかります。以下、日本法との比較の観点から、特に重要な要素について解説します。
申込みと承諾
契約の出発点となる「申込み(Offer/Proposal)」と「承諾(Acceptance)」については、Cap. 149第2条(a)項および(b)項に定義があります。ある者が他者の同意を得る目的で、特定の行為をすることまたはしないことの意思を表示することが「申込み」であり、その申込みに対して相手方が同意を示すことが「承諾」です。この二つの意思表示が合致することにより、法的な拘束力を持つ「約束(Promise)」が成立します。これは、日本法における「意思表示の一致」によって契約が成立するという考え方と概ね共通しています。
ただし、コモン・ローの世界では、何が法的な「申込み」に該当し、何が単なる「申込みの誘引(invitation to treat)」(例:商品の陳列や広告など、相手方からの申込みを誘うための表示)に過ぎないのかという区別が、判例法理を通じて精緻に議論されてきました。この判断は、当事者の主観的な意図ではなく、客観的な状況から合理的に判断されます。キプロス最高裁判所も、*Cyprus Airways事件(1998年)*において、「申込みであるか、契約交渉への誘いであるかは、当事者の主観的意図に関わらず、客観的に判断される事実問題である」との判断を示しており、この分野における判例の重要性がうかがえます。
約因(Consideration)
キプロス契約法を理解する上で、日本法の観点から最も注意を要するのが「約因(Consideration)」の概念です。これは日本法における「対価」の概念に似ていますが、その要件ははるかに厳格であり、契約の有効性を左右する形式的な要件として機能します。約因とは、単に取引の対価というだけでなく、約束を法的に強制力のあるものにするための「取引された交換(bargained-for exchange)」そのものを指します。
Cap. 149第2条(d)項では、約因を次のように定義しています。
「約束者(promisor)の要望により、被約束者(promisee)またはその他の者が、何かを既に行ったか、行うことを差し控えたか、行うか、行うことを差し控えるか、または行うこと、もしくは行うことを差し控えることを約束する場合、その行為、差し控え、または約束は、その約束に対する約因と呼ばれる。」
この定義から、約因に関する以下の重要な原則が導かれます。これらは日本企業の契約実務に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
第一に、約因は価値あるものでなければならないが、等価である必要はないという点です。裁判所は、当事者が合意した交換の公正さや妥当性には立ち入らず、法律上の価値が認められる何かが交換されていれば、約因の要件は満たされると判断します。
第二に、過去の約因は有効な約因ではない(Past consideration is not good consideration)という原則です。これは、ある約束がなされる前に既に行われた行為は、その約束を支える有効な約因にはならないことを意味します。例えば、ある取引先が過去に行った協力に対して感謝の意を示すため、「来期は無償で技術サポートを提供する」と約束したとします。日本法では、当事者間の合意として一定の拘束力が認められる可能性がありますが、キプロス法では、この約束は過去の行為に対するものであり、新たな交換が存在しないため、「約因の欠如」を理由に法的に無効とされる可能性が非常に高いです。
第三に、既存の義務の履行は有効な約因ではないという原則です。契約上または法律上、既に負っている義務を履行することを約束しても、それは新たな約因とは見なされません。
これらの原則の帰結として、Cap. 149第25条は「約因なしになされた合意は無効である」と明確に規定しています。つまり、キプロス法では、当事者間に明確な合意があったとしても、そこに約因という形式的な交換の要素がなければ、その合意は法的な契約としては成立しないのです。これは、当事者の意思表示の一致を重視する日本法との決定的な違いです。日本企業がキプロスで一方的な贈与約束や無償のサービス提供などを法的に拘束力のあるものとしたい場合、例えば1ユーロのような名目的な約因を設定するか、後述する「捺印証書(deed)」という特殊な形式を用いるといった、コモン・ロー特有の工夫が必要となります。
契約締結意思(Intention to Create Legal Relations)
契約が成立するためには、当事者が自らの合意によって法的な権利義務関係を創設する意思、すなわち「契約締結意思」を持っていることが必要です。日本法ではこの意思は契約解釈の中で総合的に判断されることが多いですが、コモン・ローでは独立した成立要件として扱われ、特定の状況に応じて法的な「推定(presumption)」が働きます。
ビジネス上の取引、すなわち商業的合意においては、当事者は法的に拘束される意思を持っていると強く推定されます。この推定を覆すことは困難ですが、契約書中に「この合意は法的な拘束力を有しない(subject to contract)」といった明確な反対の意思表示を記載することで、推定を覆すことが可能です。
一方で、家族間の約束や友人同士の約束といった家庭内・社会的合意においては、原則として当事者は法的に拘束される意思を持っていないと推定されます。この原則を確立したのが、英国の著名な判例である*Balfour v. Balfour事件(1919年)*です。この事件では、夫が妻に対して約束した生活費の支払いが、家庭内の取り決めに過ぎず、法的な契約ではないと判断されました。ビジネスの文脈でこの推定が直接問題となることは稀ですが、契約とは単なる合意ではなく、法的な強制力を意図した合意でなければならないという、コモン・ローの基本的な考え方を示すものとして重要です。
当事者の法的行為能力
契約を締結する当事者は、その内容を理解し、自己の利益に与える影響について合理的な判断を下す能力、すなわち法的行為能力(Capacity)を有していなければなりません。Cap. 149第11条は、原則として「健全な精神(sound mind)」を有するすべての者が契約締結能力を持つと定めています。
そして第12条は、「健全な精神」とは、契約締結時に「その内容を理解し、自己の利益への影響について合理的な判断を形成することができる」状態を指すと定義しています。この能力の有無は、契約締結の時点における当事者の事実上の精神状態に基づいて判断されるのが原則です。
しかし、この原則には重要な例外があります。キプロス最高裁判所が下したCharalambous v. Krystallis事件(1984年)の判決は、この点について重要な示唆を与えています。この事件では、ある人物が契約を締結した際、事実としては契約内容を理解できる精神状態にあった可能性がありました。しかし、その人物は契約締結以前に「精神病患者法(Mental Patients Law, Cap. 252)」に基づき、裁判所から精神病患者であるとの宣告を受けていました。最高裁判所は、この宣告が法的に有効である限り、その人物は自己の財産を有効に処分する法的能力を欠いており、たとえ契約締結時に一時的に正常な判断能力を有していたように見えても、彼が締結した契約は無効であると判断しました。この判例から、個人の事実上の判断能力だけでなく、裁判所の命令などによって法的に能力が制限されている場合には、それが契約の有効性に決定的な影響を与えるということが言えるでしょう。
この判決に関する公式な記録は、キプロス法律情報研究所(Cyprus Legal Information Institute)のウェブサイトで確認することができます。
参考:キプロス法律情報研究所
キプロスの契約形式と書面が必須となる場合
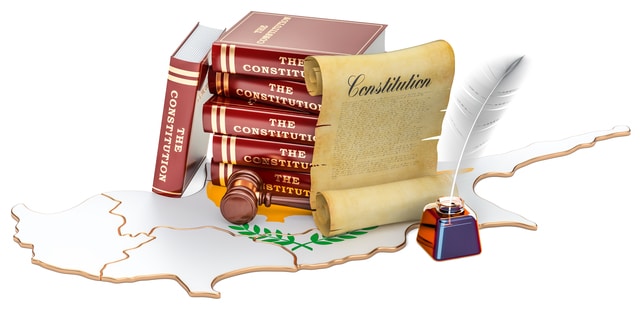
Cap. 149第10条(1)は、契約が「書面、口頭、または一部書面かつ一部口頭」で成立しうるとしており、原則として契約の形式に厳格な要件を課していません(形式の自由)。しかし、同条(2)項は、他の法律によって書面での締結や証人の立会いが要求される契約については、その効力を妨げないとする例外規定を設けています。実務上、特に日本企業が関わる可能性の高い取引分野で、書面形式が法的に、あるいは事実上必須となるケースが存在します。
不動産取引契約
キプロスで不動産を売買する契約自体は、Cap. 149の一般原則に基づき口頭でも有効に成立し得ます。しかし、買主がその権利を第三者に対抗し、万一売主が所有権移転を拒んだ場合に裁判所に対して所有権の移転を強制する「特定履行(Specific Performance)」を請求するためには、書面による契約が不可欠です。
具体的には、「不動産売買(特定履行)法(The Sale of immovable Property (Specific Performance) Law, No. 81(I)/2011)」の規定が重要となります。この法律によれば、買主は、署名された売買契約書を、契約締結日から6ヶ月以内に管轄の土地登記所に寄託(deposit)しなければなりません。この寄託手続きを経ることで、契約は当該不動産に対する一種の「負担(encumbrance)」として登記され、売主が同じ不動産を第三者に二重譲渡することを防ぐ強力な法的保護が買主に与えられます。したがって、キプロスでの不動産取引においては、詳細な条件を定めた書面契約を作成し、期限内に土地登記所に寄託することが、買主の権利保全のために極めて重要です。
保証契約
第三者の債務を保証する契約も、書面が要求される典型例です。Cap. 149第84条は保証契約を定義していますが、その形式については、より特別な法律である「特定カテゴリーの保証人保護法(Law on the Protection of Certain Categories of Guarantors)」が厳格な要件を定めています。
この法律によれば、保証契約が有効かつ強制力を持つためには、必ず書面で作成され、保証人によって署名および日付が記入されなければならないとされています。この要件は、保証人が負うことになる潜在的なリスクの重大性に鑑み、保証人の保護を図ることを目的としています。口頭による保証の約束は、たとえ当事者間で明確な合意があったとしても、法的には一切効力を持ちません。この点は、書面によらない保証契約を無効とする日本の民法第446条第2項の規定と類似しており、日本人にとって理解しやすい規制と言えるでしょう。
キプロスにおける契約違反と救済措置
損害賠償の考え方
契約が有効に成立したにもかかわらず、一方の当事者がその義務を履行しない場合、契約違反(Breach of Contract)となります。その際の主要な救済措置は、金銭による損害賠償です。
Cap. 149第73条は、損害賠償の範囲について基本的な原則を定めています。これによれば、契約違反によって損害を被った当事者は、違反した当事者から、「違反から通常の事の成り行きとして自然に生じた損害、または契約締結時に当事者双方が違反の結果として生じる可能性が高いと知っていた損害」について賠償を受ける権利があります。これは、損害の予見可能性を基準とする考え方であり、コモン・ローにおける有名なHadley v. Baxendale事件の原則を反映したものです。また、キプロスの判例法では、契約違反をされた当事者にも、その損害を軽減するために合理的な措置を講じる義務(損害軽減義務)があるとされており、この義務を怠った場合に生じた損害については賠償を請求できないとされています。この点は、George Charalambous Ltd v. Kalos Kafes Ltd事件(1997年)の最高裁判決でも確認されています。
違約金・ペナルティ条項の扱い
契約書において、違反があった場合に支払うべき金額をあらかじめ定めておく条項(違約金条項)の扱いについては、キプロス法は英国コモン・ローの伝統的な考え方とは異なる、独自の規律を設けています。
英国法では、このような条項は、発生しうる損害の合理的な事前予測である「損害賠償額の予定(liquidated damages)」と、違反を抑止するための懲罰的な「違約罰(penalty)」とに厳格に区別されます。前者は有効ですが、後者は公序良俗に反するとして無効とされます。
しかし、キプロスのCap. 149第74条は、これとは異なるアプローチを採用しています。
「契約違反の場合に支払われるべき金額として契約に定められている場合、または契約が違約罰の方法による他の規定を含んでいる場合、違反を申し立てる当事者は、それによって実際の損害または損失が生じたことが証明されるか否かにかかわらず、その定められた金額または規定された違約罰を超えない範囲で、合理的な賠償を受ける権利を有する。」
この条文は、契約に定められた金額が損害賠償額の予定であろうと違約罰であろうと、裁判所はその金額に拘束されないことを意味します。裁判所は、実際の損害等を考慮して「合理的な賠償額」を決定する裁量権を有します。ただし、契約で定められた金額は、裁判所が命じることのできる賠償額の
上限として機能します。つまり、キプロスでは、違約金条項は「賠償額の上限設定条項」として解釈・適用されるのです。この点は、Charalambous v. Liberty Life Insurance Co事件(2011年)において、最高裁判所が「契約条項で定められた固定額の賠償は裁判所を拘束しない」と判示したことからも明らかです。このため、日本企業がキプロスで契約を締結する際には、高額なペナルティ条項が完全に無効になるわけではなく、賠償額の上限として機能しうることを念頭に置いて交渉に臨む必要があります。
まとめ
キプロスの法制度は、EU加盟国としての安定性と、英国コモン・ローに基づく予測可能性を兼ね備えていますが、その根底にある法思想は日本の民法とは大きく異なります。
まず、契約の成立には、当事者間の合意だけでなく、「約因(Consideration)」という厳格な形式要件が不可欠です。無償の約束や過去の行為に対する約束は、原則として法的な拘束力を持ちません。次に、ビジネス上の合意には「契約締結意思(Intention to Create Legal Relations)」が強く推定される一方で、この意思がないことを明示すれば、法的拘束力のない合意とすることも可能です。さらに、不動産取引や保証契約など、特定の重要な契約については書面形式が法律で要求されており、口頭での合意は無効となります。最後に、契約違反時の違約金条項は、定められた金額がそのまま認められるわけではなく、裁判所が判断する「合理的な賠償額」の上限として機能するという、特有の扱いがなされます。
これらの相違点は、単なる学術的な違いに留まらず、契約の有効性や執行可能性に直接影響を及ぼす実務上の重要事項です。キプロス市場で安全に事業を遂行するためには、これらのコモン・ロー特有の原則を深く理解し、契約書の作成や交渉の段階から適切な法的助言を得ることが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































