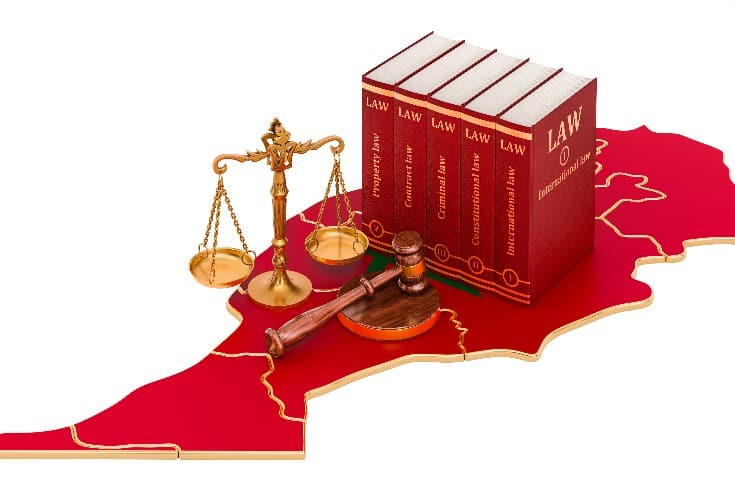ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňů▒ňĺîňŤŻŃü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŃéĺŔŽĆňżőŃüÖŃéőŃé┤ŃââŃâëŃâĽŃâęŃâ│Š│ĽŃüĘSRENŠ│ĽŃâ╗NIS2Šîçń╗Ą

ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŠ│ĽŃü»ŃÇüń╝ŁšÁ▒šÜäŃü¬ňłĹŠ│ĽňůŞŃéĺňč║šŤĄŃüĘŃüŚŃüĄŃüĄŃÇüŠľ░ŃüčŃü¬Š│ĽšÜäŠ×ášÁäŃü┐ŃéäEUŠîçń╗ĄŃü«ňŤŻňćůŠ│ĽňîľŃéĺÚÇÜŃüśŃüŽŃÇüŠÇąÚÇčŃüźÚÇ▓ňîľŃéĺÚüéŃüĺŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüŁŃü«Š│ĽńŻôš│╗Ńü»ŃÇüňŹśŃü¬ŃéőŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝šŐ»šŻ¬Ńü«ń║őňżîšÜäŃü¬ň玚Ż░ŃüźšĽÖŃüżŃéëŃüÜŃÇüń╝üŠąşŃü«ŃéČŃâÉŃâŐŃâ│Ńé╣ŃéäŃéÁŃâŚŃâęŃéĄŃâüŃéžŃâ╝Ńâ│ňůĘńŻôŃüźŃéĆŃüčŃéőń║łÚś▓šÜäŃü¬Ńâ¬Ńé╣Ń黚«íšÉćŃéĺň╝ĚŃüĆŠ▒éŃéüŃéőňĄÜň▒ĄšÜäŃü¬ŠžőÚÇáŃéĺňŻóŠłÉŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŠťČŔĘśń║őŃü»ŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŠ│ĽŃéĺńŻôš│╗šÜäŃüźŔžúŔ¬ČŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
Ńü¬ŃüŐŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ňîůŠőČšÜäŃü¬Š│ĽňłÂň║ŽŃü«ŠŽéŔŽüŃü»ńŞőŔĘśŔĘśń║őŃüźŃüŽŃüżŃüĘŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŃüôŃü«ŔĘśń║őŃü«šŤ«ŠČí
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝šŐ»šŻ¬Š│ĽňłÂ
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŠ│ĽňłÂŃü«Šá╣ň╣╣Ńü»ŃÇü1988ň╣┤ŃüźňłÂň«ÜŃüĽŃéîŃüčŃÇîŃé┤ŃââŃâëŃâĽŃâęŃâ│Š│ĽŃÇŹŃüźšö▒ŠŁąŃüÖŃéőňłĹŠ│ĽňůŞŃü«ŔŽĆň«ÜŃüźŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéňÉîŠ│ĽŃü»ŃÇüŠâůňá▒ŠŐÇŔíôŃü«šÖ║ň▒ĽŃüźń╝┤Ńü抾░ŃüčŃü¬šŐ»šŻ¬Úí×ň×őŃüźň»żň┐ťŃüÖŃéőŃüčŃéüŃÇüŃâçŃâ╝Ńé┐Ŕç¬ňőĽň玚ÉćŃéĚŃé╣ŃâćŃâá´╝łSTAD´╝ÜSyst├Ęme de Traitement Automatis├ę de Donn├ęes´╝ëŃüŞŃü«ńżÁň«│Ŕíîšé║Ńé劜Ěó║ŃüźšŐ»šŻ¬ŃüĘň«ÜŃéüŃüżŃüŚŃüčŃÇéŃüôŃéîŃéëŃü«ŔŽĆň«ÜŃü»ŃÇüšĆżňťĘŃÇüňłĹŠ│ĽňůŞšČČ323ŠŁíŃüőŃéëšČČ323-7ŠŁíŃüźÚŤćš┤äŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŃÇîńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣ŃÇŹŃü«ň«ÜšżęŃüĘň玚Ż░
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňłĹŠ│ĽňůŞšČČ323-1ŠŁíŃü»ŃÇüŃÇîńŞŹŠşúŃüźŃÇüŃâçŃâ╝Ńé┐Ŕç¬ňőĽň玚ÉćŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃü«ňůĘÚâĘŃüżŃüčŃü»ńŞÇÚâĘŃüźŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣ŃüŚŃÇüŃüżŃüčŃü»ŃüŁŃü«šŐŠůőŃéĺšÂşŠîüŃüÖŃéőŔíîšé║ŃÇŹŃéĺšŐ»šŻ¬ŃüĘŃüŚŃüŽŔŽĆň«ÜŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«ŠŁíŠľçŃü»ŃÇüŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ŕíîšé║ŃüŁŃü«ŃééŃü«Ńéĺň玚Ż░ŃüÖŃéőšé╣ŃüžŠŚąŠťČŃü«ńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣šŽüŠşóŠ│ĽŃüĘňů▒ÚÇÜŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃüîŃÇüšë╣šşćŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃÇîńŞŹŠşúŃü¬šÂşŠîüŃÇŹ(maintien frauduleux) ŃüĚó║ŃüźšŐ»šŻ¬ŠžőŠłÉŔŽüń╗ÂŃüźňÉźŃüżŃéîŃüŽŃüäŃéőšé╣ŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃü»ŃÇüŠşúŔŽĆŃü«ŠĘęÚÖÉŃéĺŠîüŃüčŃü¬ŃüäŔÇůŃüîňüšäÂŃüźŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃüźńżÁňůąŃüŚŃüŽŃüŚŃüżŃüúŃüčňżîŃÇüŠäĆňŤ│šÜäŃüźŃüŁŃü«šŐŠůőŃéĺšÂÖšÂÜŃüÖŃéőŔíîšé║Ńééň玚Ż░Ńü«ň»żŔ▒íŃüĘŃü¬ŃéőŃüôŃüĘŃéĺŠäĆňĹ│ŃüŚŃüżŃüÖŃÇéňůĚńŻôšÜäŃü¬ńżőŃüĘŃüŚŃüŽŃÇüń╗ľń║║Ńü«ŃâşŃé░ŃéĄŃâ│Šâůňá▒ŃéĺńŞŹŠşúŃüźňłęšöĘŃüÖŃéőŔíîšé║ŃéäŃÇüŃâĹŃé╣Ńâ»Ńâ╝ŃâëŃü«šĚĆňŻôŃüčŃéŐŠö╗ŠĺâŃüźŃéłŃüúŃüŽŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃüŞŃü«ŠÄąšÂÜŃéĺŔęŽŃü┐ŃéőŔíîšé║Ńü¬ŃüęŃüîŔę▓ňŻôŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
ňŹśš┤öŃü¬ńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ŕíîšé║ŃüžŃüéŃüúŃüŽŃééŃÇü2ň╣┤Ńü«šŽüÚî«ňłĹŃüĘ6ńŞçŃâŽŃâ╝ŃâşŃü«šŻ░ÚçĹŃüîšžĹŃüŤŃéëŃéîŃéőŃü¬ŃüęŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Š│ĽŃü»Š»öŔ╝âšÜäňÄ│ŃüŚŃüäň玚Ż░Ńéĺň«ÜŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇ銌ąŠťČŃü«ńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣šŽüŠşóŠ│ĽŃüîŃÇîńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ŕíîšé║ŃÇŹŃüĘŃÇîńŞŹŠşúŃü«šŤ«šÜäŃÇŹŃéĺŔŽüń╗ÂŃüĘŃüÖŃéőŃü«Ńüźň»żŃüŚŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňłĹŠ│ĽňůŞšČČ323-1ŠŁíŃü»ŃÇîńŞŹŠşúŃüź´╝łfrauduleusement´╝ëŃÇŹŃüĘŃüäŃüćńŞ╗ŔŽ│šÜäŔŽüń╗ÂŃéĺň«ÜŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŃÇîńŞŹŠşúŃüźŃÇŹŃéĺňĚíŃéőŠ│ĽŔžúÚçłŃü»ŃÇüňÇőŃÇůŃü«ŔúüňłĄńżőŃéĺÚÇÜŃüśŃüŽňŻóŠłÉŃüĽŃéîŃüŽŃüŹŃüżŃüŚŃüčŃÇéńżőŃüłŃü░ŃÇüŃâĹŃ⬊ĞŔĘ┤ÚÖóŃü»ŃÇüňĄÜŠĽ░Ńü«Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúńŞŐŃü«ŠČáÚÖąŃüîŃüéŃéőŃéŽŃéžŃâľŃéÁŃéĄŃâłŃüźňŹśš┤öŃü¬ŃâľŃâęŃéŽŃéÂŃüžŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣ŃüžŃüŹŃüčňá┤ňÉłŃÇüŃüŁŃü«Ŕíîšé║Ńü»ň玚Ż░Ńü«ň»żŔ▒íŃüĘŃü¬ŃéëŃü¬ŃüäŃüĘňłĄŠľşŃüŚŃüčŃüôŃüĘŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃü»ŃÇüŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣ňłÂňżíŠęčŔâŻŃüîňŹüňłćŃüźŠęčŔâŻŃüŚŃüŽŃüäŃü¬Ńüäňá┤ňÉłŃÇüńżÁňůąŔÇůŃü«Šé¬ŠäĆŃéĺŔĘ╝ŠśÄŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüîÚŤúŃüŚŃüäŃüĘŃüäŃüćňłĄŠľşŃüźňč║ŃüąŃüĆŃééŃü«ŃüžŃüŚŃüčŃÇéńŞÇŠľ╣ŃüžŃÇüňÉîŃüśŃâĹŃ⬊ĞŔĘ┤ÚÖóŃü«ňłąŃü«ňłĄńżőŃüžŃü»ŃÇüŃé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúńŞŐŃü«ŠČáÚÖąŃüîŃÇüŔóźňĹŐń║║ŃüźŃüĘŃüúŃüŽńŞŹŠşúŃüźŃâçŃâ╝Ńé┐ŃéĺňĆľňżŚŃüÖŃéőŃüčŃéüŃü«ŃÇîňĆúň«čŃéäŔĘÇŃüäŔĘ│ŃüźŃü»Ńü¬ŃéëŃü¬ŃüäŃÇŹŃüĘšÁÉŔźľń╗śŃüĹŃüŽŃüŐŃéŐŃÇüňĆŞŠ│ĽŃü«ňłĄŠľşŃüîšŐŠ│üŃüźŃéłŃüúŃüŽňłćŃüőŃéîŃéőŃüôŃüĘŃé嚥║ŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ń╗ąńŞőŃü«ŔíĘŃü»ŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňłĹŠ│ĽňůŞŃüĘŠŚąŠťČŃü«ńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣šŽüŠşóŠ│ĽŃüźŃüŐŃüĹŃéőńŞ╗ŔŽüŃü¬ŠžőŠłÉŔŽüń╗ÂŃüĘň玚Ż░ňćůň«╣Ńü«Š»öŔ╝âŃüžŃüÖŃÇé
| ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňłĹŠ│ĽňůŞ´╝łšČČ323ŠŁí´╝ë | ŠŚąŠťČŃü«ńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣šŽüŠşóŠ│Ľ | |
|---|---|---|
| ň»żŔ▒íŔíîšé║ | ńŞŹŠşúŃü¬ŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣ŃüŐŃéłŃü│šÂşŠîü | ńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ŕíîšé║ |
| ŃÇîńŞŹŠşúŃÇŹŃü«ň«Üšżę | ńŞ╗ŔŽ│šÜäŔŽüń╗ÂŃÇîfrauduleusementŃÇŹ | ŃÇîńŞŹŠşúŃü«šŤ«šÜäŃÇŹŃüĘŃüäŃüćŔŽüń╗ |
| ň玚Ż░Ńü«š»äňŤ▓ | ŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ŕíîšé║ŃüĘŃÇîšÂşŠîüŃÇŹŃü«ńŞíŠľ╣Ńé劜ÄŔĘś | ńŞ╗ŃüźŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ŕíîšé║Ńéĺň玚Ż░ |
| šŻ░ňëç | 2ň╣┤Ńü«šŽüÚî«ŃÇü6ńŞçÔéČšŻ░ÚçĹ´╝łňŹśš┤öŔíîšé║´╝ë | 3ň╣┤ń╗ąńŞőŃü«Šç▓ňŻ╣ŃÇü100ńŞçňććń╗ąńŞőŃü«šŻ░ÚçĹ |
| Š│Ľń║║Ńü«Ŕ▓Čń╗╗ | Š│Ľń║║Ńé隯░ňëçŃü«ň»żŔ▒íŃüĘŃü¬Ńéő | Š│ĽňżőńŞŐŃÇüńŞíšŻ░ŔŽĆň«ÜŃüéŃéŐ |
ŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŠęčŔâŻŃüŞŃü«ňŽĘň«│ŃüĘŃâçŃâ╝Ńé┐Šö╣ŃüľŃéô
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňłĹŠ│ĽňůŞŃü»ŃÇüŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃüŞŃü«ńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ŕíîšé║ŃüŁŃü«ŃééŃü«ŃüźňŐáŃüłŃÇüŃéłŃéŐŠĚ▒ňł╗Ńü¬šÁɊםŃéĺŃééŃüčŃéëŃüÖŔíîšé║ŃééňÄ│Šá╝Ńüźň玚Ż░ŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
ŃüżŃüÜŃÇüňłĹŠ│ĽňůŞšČČ323-2ŠŁíŃü»ŃÇüŃÇîŃâçŃâ╝Ńé┐Ŕç¬ňőĽň玚ÉćŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃü«ŠęčŔâŻŃéĺňŽĘň«│ŃüżŃüčŃü»ňüŻŔúůŃüÖŃéőŔíîšé║ŃÇŹŃéĺň玚Ż░ŃüŚŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃü»ŃÇüDDoSŠö╗ŠĺâŃéäŃé╣ŃâĹŃâáŃâíŃâ╝ŃâźŃü«ňĄžÚçĆÚÇüń┐íŃüźŃéłŃéőŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃü«Ú║╗šŚ║Ńü¬ŃüęŃüîŔę▓ňŻôŃüŚŃÇü5ň╣┤Ńü«šŽüÚî«ňłĹŃüĘ15ńŞçŃâŽŃâ╝ŃâşŃü«šŻ░ÚçĹŃüĘŃüäŃüćÚ珚Ż¬ŃüîšžĹŃüŤŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇéŠČíŃüźŃÇüšČČ323-3ŠŁíŃü»ŃÇüŃÇîńŞŹŠşúŃüźŃâçŃâ╝Ńé┐ŃéäŠâůňá▒ŃéĺŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃüźň░ÄňůąŃÇüŠŐŻňç║ŃÇüń┐ŁŠîüŃÇüŔĄçŔúŻŃÇüÚÇüń┐íŃÇüňëŐÚÖĄŃÇüŃüżŃüčŃü»ňĄëŠŤ┤ŃüÖŃéőŔíîšé║ŃÇŹŃéĺšŐ»šŻ¬ŃüĘň«ÜŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«šŻ¬ŃééŃÇü5ň╣┤Ńü«šŽüÚî«ňłĹŃüĘ15ńŞçŃâŽŃâ╝ŃâşŃü«šŻ░ÚçĹŃüĘŃüäŃüćňÉśŃü«Ú珚Ż¬ŃüžŃüÖŃÇéŃüĽŃéëŃüźŃÇüŃüôŃéîŃéëŃü«šŐ»šŻ¬ŃüîňŤŻň«ÂŃü«ÚüőšöĘŃüÖŃéőŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃéäňÇőń║║ŃâçŃâ╝Ńé┐ň玚ÉćŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃüźň»żŃüŚŃüŽŔíîŃéĆŃéîŃüčňá┤ňÉłŃÇüšŻ░ňëçŃü»ńŞÇň▒ĄÚçŹŃüĆŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
1988ň╣┤Ńü«Ńé┤ŃââŃâëŃâĽŃâęŃâ│Š│ĽŃüîňłÂň«ÜŃüĽŃéîŃüčňŻôŠÖéŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝šŐ»šŻ¬Ńü«ńŞ╗ńŻôŃü»ńŞ╗ŃüźŃÇîŃâĆŃââŃéźŃâ╝ŃÇŹŃüĘňĹ╝Ńü░ŃéîŃéőňÇőń║║Ńü«šŐ»ŔíîŃüžŃüéŃéŐŃÇüŠ│ĽŃééňÇőń║║Ńü«Ŕíîšé║Ńéĺň玚Ż░ŃüÖŃéőŠžőÚÇáŃüĘŃü¬ŃüúŃüŽŃüäŃüżŃüŚŃüčŃÇéŃüŚŃüőŃüŚŃÇüšĆżń╗úŃü«ŔäůňĘüŃü»ŃÇüŃâęŃâ│ŃéÁŃâáŃéŽŃéžŃéóŃéäšÁäš╣öšÜäŃü¬ŃâçŃâ╝Ńé┐šŤŚÚŤúŃÇüščąšÜäŔ▓íšöúŠĘęńżÁň«│ŃüŞŃüĘÚÇ▓ňîľŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃüźń╝┤ŃüäŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«Š│ĽňłÂň║ŽŃü»ŃÇüňŹśŃüźšŐ»šŻ¬ŔÇůŃéĺň玚Ż░ŃüÖŃéőŃüáŃüĹŃüžŃü¬ŃüĆŃÇüń╝üŠąşŃü«Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúň»żšşľŃü«ńŞŹňéÖŃüźŃé隍«ŃéĺňÉĹŃüĹňžőŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
Ńâ┤ŃéžŃâźŃéÁŃéĄŃ⎊ĞŔĘ┤ÚÖóŃü«ňłĄńżőŃüžŃü»ŃÇüňůâňżôŠąşňôíŃüîń╝ÜšĄżŃü«Šęčň»ćŃâçŃâ╝Ńé┐ŃéĺńŞŹŠşúŃüźŃé│ŃâöŃâ╝ŃüŚŃüčŃé▒Ńâ╝Ńé╣ŃüžŃÇüŃüŁŃü«Ŕíîšé║ŃéĺňÄ│ŃüŚŃüĆň玚Ż░ŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃü»ŃÇüňżôŠąşňôíŃüźŃéłŃéőńŞŹŠşúŔíîšé║Ńüźň»żŃüÖŃéőń╝üŠąşŃü«šŤúšŁúŔ▓Čń╗╗ŃéäŃÇüńŞŹŠşúŔíîšé║ŃüźŃéłŃüúŃüŽŠÉŹň«│ŃéĺŔóźŃüúŃüčňá┤ňÉłŃü«ń╝üŠąşŃü«Ńâ¬Ńé╣Ńé»ŃéĺŠÁ«ŃüŹňŻźŃéŐŃüźŃüŚŃüżŃüÖŃÇéŃüĽŃéëŃüźŃÇü2019ň╣┤Ńü«ŠťÇÚźśŔúüňłĹń║őÚÖóŃü«ňłĄńżőŃü»ŃÇüń╝üŠąşŃü«ňĆľšĚáňŻ╣ŃüîŃé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúň»żšşľŃéĺŠÇáŃüúŃüčňá┤ňÉłŃüźÚüÄňĄ▒Ŕ▓Čń╗╗ŃéĺňĽĆŃéĆŃéîŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃé嚥║ňöćŃüŚŃüŽŃüŐŃéŐŃÇüŃüôŃü«ŔÇâŃüłŠľ╣Ńü»ňżîŔ┐░ŃüÖŃéőNIS2Šîçń╗ĄŃü«ŃÇîšÁîňľÂÚÖúŃü«Ŕ▓Čń╗╗ŃÇŹŃüĘŃüäŃüćŔÇâŃüłŠľ╣ŃüĘň╝ĚŃüĆšÁÉŃü│ŃüĄŃüäŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃéëŃü«ňĄëňîľŃü»ŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŃüîŃééŃü»ŃéäITÚâĘÚľÇŃüáŃüĹŃü«Ŕ¬▓ÚíîŃüžŃü»Ńü¬ŃüĆŃÇüšÁîňľÂŠłŽšĽąŃü«ńŞşŠáŞŃüĘŃüŚŃüŽńŻŹšŻ«ŃüąŃüĹŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéëŃü¬ŃüäŃüôŃüĘŃé嚥║ňöćŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŠťÇŠľ░Š│ĽšÜäňőĽňÉĹ
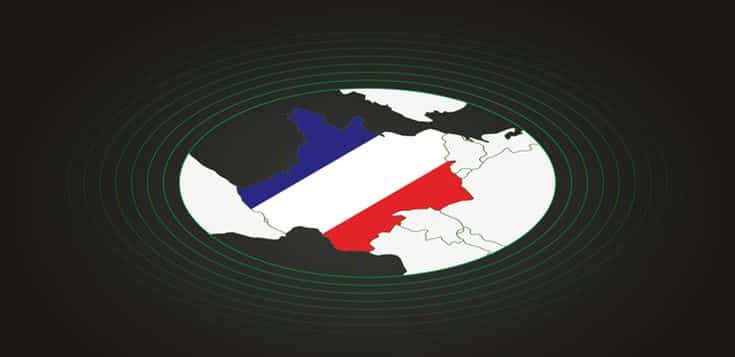
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŠ│ĽŃü»ŃÇüń╝ŁšÁ▒šÜäŃü¬ňłĹŠ│ĽňůŞŃüźŃüĘŃüęŃüżŃéëŃüÜŃÇüŠľ░ŃüčŃü¬ŔäůňĘüŃüźň»żň┐ťŃüÖŃéőŃüčŃéüŃÇüŠÇąÚÇčŃüźÚÇ▓ňîľŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéšë╣ŃüźŃÇü2024ň╣┤ŃüźŠłÉšźőŃüŚŃüčSRENŠ│ĽŃüĘŃÇüEUŃü«NIS2Šîçń╗ĄŃü»ŃÇüń╝üŠąşŃü«Ńé│Ńâ│ŃâŚŃâęŃéĄŃéóŃâ│Ńé╣ŃüźňĄžŃüŹŃü¬ňŻ▒Úč┐ŃéĺńŞÄŃüłŃüżŃüÖŃÇé
Šľ░ŃüčŃü¬ŃâçŃéŞŃé┐Ńâźšę║ÚľôŃü«ŔŽĆňłÂŃéĺŔíîŃüćSRENŠ│Ľ
2024ň╣┤5Šťł21ŠŚąŃüźňůČňŞâŃüĽŃéîŃüčSRENŠ│Ľ´╝łLoi SRENŃÇüŃâçŃéŞŃé┐Ńâźšę║ÚľôŃü«ň«ëňůĘšó║ń┐ŁŃâ╗ŔŽĆňłÂŠ│Ľ´╝ëŃü»ŃÇüŃâçŃéŞŃé┐Ńâźšę║ÚľôŃéĺŃéłŃéŐň«ëňůĘŃüźŃÇüŃüőŃüĄŔŽĆňłÂŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃé嚍«šÜäŃüĘŃüŚŃüčňîůŠőČšÜäŃü¬Š│ĽňżőŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃü«Š│ĽňżőŃü»ŃÇüŠť¬ŠłÉň╣┤ŔÇůń┐ŁŔşĚŃÇüŔęÉŠČ║Ńâ╗ŠćÄŠé¬Ńé│Ńâ│ŃâćŃâ│Ńâäň»żšşľŃÇüŃâçŃéúŃâ╝ŃâŚŃâĽŃéžŃéĄŃé»ŃüŞŃü«ň»żň┐ťŃÇüŃé»ŃâęŃéŽŃâëňŞéňá┤Ńü«šźÂń║ëń┐âÚÇ▓Ńü¬ŃüęŃÇüň║âš»äŃü¬ŔŽĆňłÂňćůň«╣ŃéĺšÂ▓šżůŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ńŞ╗ŔŽüŃü¬ŠÄ¬šŻ«ŃüĘŃüŚŃüŽŃÇüŃüżŃüÜŠť¬ŠłÉň╣┤ŔÇůń┐ŁŔşĚŃü«ŔŽ│šé╣ŃüőŃéëŃÇüŃâŁŃâźŃâÄŃéÁŃéĄŃâłŃüŞŃü«ŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣Ńüźň»żŃüÖŃéőňÄ│Šá╝Ńü¬ň╣┤ÚŻóšó║Ŕ¬ŹŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃü«ň░ÄňůąŃéĺšżęňőÖń╗śŃüĹŃÇüÚüĽňĆŹŃüŚŃüčňá┤ňÉłŃü»ŠťÇňĄž2ň╣┤ÚľôŃü«ŃéÁŃéĄŃâłÚü«ŠľşŃüĘ48ŠÖéÚľôń╗ąňćůŃü«ŠĄťš┤óŃéĘŃâ│ŃéŞŃâ│ŃüőŃéëŃü«ÚÖĄňĄľŃüîňĹŻŃüśŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇéŃüżŃüčŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝šŐ»šŻ¬Ńâ╗ŃâśŃéĄŃâłŃé│Ńâ│ŃâćŃâ│Ńâäň»żšşľŃüĘŃüŚŃüŽŃÇüŔęÉŠČ║ŃéÁŃéĄŃâłŃéäŃé¬Ńâ│ŃâęŃéĄŃâ│ŃâśŃéĄŃâłŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝ŃâĆŃâęŃé╣ŃâíŃâ│ŃâłŃüžŠťëšŻ¬ňłĄŠ▒║ŃéĺňĆŚŃüĹŃüčŔÇůŃüźň»żŃüŚŃÇüŔúüňłĄň«śŃüÇňĄž1ň╣┤ÚľôŃü«SNSŃéóŃéźŃéŽŃâ│ŃâłňüťŠşóňçŽňłćŃéĺšžĹŃüÖŃüôŃüĘŃüîňĆ»ŔâŻŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüŚŃüčŃÇéŃüĽŃéëŃüźŃÇüAIŃüžńŻťŠłÉŃüĽŃéîŃüčŃÇîŃâçŃéúŃâ╝ŃâŚŃâĽŃéžŃéĄŃé»ŃÇŹŃüźŃü»ŃÇü7ńŞç5ňŹâŃâŽŃâ╝ŃâşŃü«šŻ░ÚçĹŃüĘ3ň╣┤Ńü«šŽüÚî«ňłĹŃüîšžĹŃüŤŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇé
SRENŠ│ĽŃü»ŃÇüŠČžňĚ×Ńü«DSA´╝łŃâçŃéŞŃé┐ŃâźŃéÁŃâ╝ŃâôŃé╣Š│Ľ´╝ëŃüŐŃéłŃü│DMA´╝łŃâçŃéŞŃé┐ŃâźňŞéňá┤Š│Ľ´╝ëŃéĺŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňŤŻňćůŠ│ĽŃüźÚüęšöĘŃüÖŃéőŃüčŃéüŃü«Š×ášÁäŃü┐Ńéĺň«ÜŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃüźŃéłŃéŐŃÇüCNIL´╝łŠâůňá▒ň玚ÉćŃüŐŃéłŃü│Ŕ笚ö▒ŃüźÚľóŃüÖŃéőňŤŻň«Âňžöňôíń╝Ü´╝ëŃéäArcom´╝łŔŽľŔü┤ŔŽÜŃâ╗ŃâçŃéŞŃé┐ŃâźÚÇÜń┐íŔŽĆňłÂň║ü´╝ëŃüĘŃüäŃüúŃüčŔŽĆňłÂňŻôň▒ÇŃüźŠľ░ŃüčŃü¬ŠĘęÚÖÉŃüîń╗śńŞÄŃüĽŃéîŃüżŃüŚŃüčŃÇé
ŠŚąŠťČŃü«ŃâŚŃâşŃâÉŃéĄŃâÇŔ▓Čń╗╗ňłÂÚÖÉŠ│ĽŃüîŃÇüÚÇÜń┐íŃü«šžśň»ćŃéäŔíʚƿŃü«Ŕ笚ö▒ŃüźÚůŹŠů«ŃüŚŃüŽŃé│Ńâ│ŃâćŃâ│ŃâäňëŐÚÖĄŃé劻öŔ╝âšÜäŠůÄÚçŹŃüźŔíîŃü択őÚÇáŃüžŃüéŃéőŃü«Ńüźň»żŃüŚŃÇüSRENŠ│ĽŃü»ŃÇüŠť¬ŠłÉň╣┤ŔÇůń┐ŁŔşĚŃéäňůČňů▒Ńü«ň«ëňůĘŃé嚍«šÜäŃüĘŃüŚŃüčŃÇîŃâĽŃéúŃâźŃé┐Ńâ¬Ńâ│Ńé░ŃÇŹŃéäŃÇîŃéÁŃéĄŃâłÚü«ŠľşŃÇŹŃüĘŃüäŃüúŃüčňŤŻň«ÂŠĘęÚÖÉŃéĺň╝ĚňîľŃüŚŃüŽŃüäŃéőšé╣ŃüîňĄžŃüŹŃü¬ÚüĽŃüäŃüžŃüÖŃÇéŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«Š│ĽňłÂň║ŽŃü»ŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝šŐ»šŻ¬Ńüżń╝ÜňůĘńŻôŃüźňĆŐŃü╝ŃüÖňŻ▒Úč┐ŃüîŠőíňĄžŃüŚŃüŽŃüäŃéőŃüĘŃüäŃüćŔ¬ŹŔşśŃüźňč║ŃüąŃüŹŃÇüŠö┐ň║ťŃüîŃéłŃéŐň╝ĚňŐŤŃü¬ń╗őňůąŃéĺŔĘ▒ň«╣ŃüÖŃéőňéżňÉĹŃüźŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«ňéżňÉĹŃü»ŃÇüPharosŃüĘŃüäŃüćŃâŚŃâęŃââŃâłŃâĽŃéęŃâ╝ŃâáŃüîŃÇüŠőĚňĽĆŃéäÚçÄŔŤ«Ńü¬Ŕíîšé║Ńü«šö╗ňâĆŃéĺ24ŠÖéÚľôń╗ąňćůŃüźňëŐÚÖĄŃÇüÚü«ŠľşŃÇüŃüżŃüčŃü»ŠĄťš┤óŃéĘŃâ│ŃéŞŃâ│ŃüőŃéëÚÖĄňĄľŃüÖŃéőŠĘęÚÖÉŃéĺň«čÚĘôšÜäŃüźń╗śńŞÄŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃéőŃüôŃüĘŃüźŃééŔíĘŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ńŞÇŠľ╣ŃüžŃÇüŠťÇÚźśŠ│ĽŔŽĆŃüžŃüéŃéőŠć▓Š│ĽŔęĽŔş░ń╝ÜŃüîŃÇüŃé¬Ńâ│ŃâęŃéĄŃâ│ńŞŐŃüžŃü«ŃÇîńż«Ŕż▒šŻ¬ŃÇŹňëÁŔĘşŃéäŃÇüňŤŻň«ÂŃüźŃéłŃéőŃâçŃéŞŃé┐ŃâźIDŃâŚŃâęŃââŃâłŃâĽŃéęŃâ╝ŃâáňëÁŔĘşŃüĘŃüäŃüúŃüčńŞÇÚâĘŃü«ŔŽĆň«ÜŃéĺŃÇîÚüĽŠć▓šźőŠ│ĽŃÇŹŃüĘŃüŚŃüŽňëŐÚÖĄŃüŚŃüčń║őň«čŃü»ŃÇüŔíîŃüŹÚüÄŃüÄŃüčňŤŻň«ÂŠĘęňŐŤŃüźň»żŃüŚŃüŽŠş»ŠşóŃéüŃéĺŃüőŃüĹŃéőŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«Š│ĽŃü«Šö»ÚůŹŃü«ń╗ĽšÁäŃü┐ŃüîŠęčŔâŻŃüŚŃüŽŃüäŃéőŃüôŃüĘŃé嚥║ŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
NIS2Šîçń╗ĄŃü«ňŤŻňćůŠ│ĽňîľŃüĘŠŚąš│╗ń╝üŠąşŃüŞŃü«ňŻ▒Úč┐
ŠČžňĚ×ňůĘńŻôŃüžŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŠ░┤Š║ľŃéĺňÉĹńŞŐŃüĽŃüŤŃéőŃüôŃüĘŃé嚍«šÜäŃüĘŃüŚŃüčNIS2Šîçń╗ĄŃü»ŃÇüšĆżňťĘŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňŤŻňćůŠ│ĽŃüŞŃü«šž╗ŔíîńŻťŠąşŃüîÚÇ▓ŃéüŃéëŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéEUŃü«ŠťÇšÁ銝čÚÖÉ´╝ł2024ň╣┤10Šťł17ŠŚą´╝ëŃüźŃü»ÚľôŃüźňÉłŃéĆŃü¬ŃüőŃüúŃüčŃééŃü«Ńü«ŃÇü2025ň╣┤ňĄĆÚáâŃü«ŠľŻŔíîŃü«ŠĘÖŃüĘŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
NIS2Šîçń╗ĄŃü»ŃÇüŃéĘŃâŹŃâźŃé«Ńâ╝ŃÇüŔ╝ŞÚÇüŃÇüÚŐÇŔíîŃÇüňî╗šÖéŃüĘŃüäŃüúŃüčňżôŠŁąŃü«ÚçŹŔŽüŃéĄŃâ│ŃâĽŃâęń║őŠąşŃüźňŐáŃüłŃÇüŔúŻÚÇáŃÇüŃâçŃéŞŃé┐ŃâźŃéÁŃâ╝ŃâôŃé╣ŃÇüÚâÁńż┐ŃÇüÚúčňôüŃü¬ŃüęŃÇü18Ńü«ň║âš»äŃü¬ŃÇîÚçŹŔŽüŃÇŹňłćÚçÄŃü«ń╝üŠąşŃéĺň»żŔ▒íŃüĘŃüŚŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃéëŃü«ń╝üŠąşŃü»ŃÇüŃÇîň┐ůÚáłń║őŠąşŔÇů´╝łEssential Entities´╝ëŃÇŹŃüĘŃÇîÚçŹŔŽüń║őŠąşŔÇů´╝łImportant Entities´╝ëŃÇŹŃüźňłćÚí×ŃüĽŃéîŃÇüňëŹŔÇůŃü»ŃéłŃéŐňÄ│Šá╝Ńü¬šŤúšŁú´╝łń║őňëŹŃü«šŤúŠč╗Ńü¬Ńüę´╝ëŃéĺňĆŚŃüĹŃüżŃüÖŃÇé
NIS2Šîçń╗ĄŃü»ŃÇüň»żŔ▒íń╝üŠąşŃüźň»żŃüŚŃÇüń╗ąńŞőŃéĺňÉźŃéÇňîůŠőČšÜäŃü¬Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúň»żšşľŃéĺšżęňőÖń╗śŃüĹŃüżŃüÖŃÇé
- ňÄ│Šá╝Ńü¬ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńâ¬Ńé╣Ń黚«íšÉć´╝ÜňĄÜŔŽüš┤áŔ¬ŹŔĘ╝´╝łMFA´╝ëŃéäŃâçŃâ╝Ńé┐Ńü«ŠÜŚňĆĚňîľŃÇüň«ÜŠťčšÜäŃü¬Ńâ¬Ńé╣Ńé»ŔęĽńżíŃü¬ŃüęŃÇüŠŐÇŔíôšÜäŃâ╗šÁäš╣öšÜäŠÄ¬šŻ«Ńü«ň░ÄňůąŃÇé
- Ŕ┐ůÚÇčŃü¬ŃéĄŃâ│ŃéĚŃâçŃâ│Ńâłňá▒ňĹŐ´╝ÜÚçŹňĄžŃü¬ŃéĄŃâ│ŃéĚŃâçŃâ│ŃâłŃüîšÖ║šöčŃüŚŃüčňá┤ňÉłŃÇüňŻôň▒Ç´╝łńŞ╗ŃüźANSSI´╝ëŃüŞŃü«ňá▒ňĹŐšżęňőÖŃÇé
- ŃéÁŃâŚŃâęŃéĄŃâüŃéžŃâ╝Ńâ│Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéú´╝ÜŃéÁŃâ╝ŃâôŃé╣ŠĆÉńżŤŠąşŔÇůŃü«Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúň»żšşľŃé隍úšŁúň»żŔ▒íŃüĘŃü¬ŃéőŃüčŃéüŃÇüňĆľň╝ĽňůłŃü«Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŃééšó║ń┐ŁŃüŚŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇé
- šÁîňľÂÚÖúŃü«šŤ┤ŠÄąŔ▓Čń╗╗´╝ÜšÁîňľÂň╣╣ÚâĘŃüîŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúň»żšşľŃé嚍úšŁúŃüÖŃéőŔ▓Čń╗╗ŃéĺŔ▓áŃüäŃÇüÚçŹňĄžŃü¬ÚüÄňĄ▒ŃüîŔ¬ŹŃéüŃéëŃéîŃüčňá┤ňÉłŃüźŃü»ňÇőń║║ŃüźŃééňłÂŔúüŃüîšžĹŃüĽŃéîŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃüôŃü«NIS2Šîçń╗ĄŃü«ň»żŔ▒íš»äňŤ▓Ńü»ŠąÁŃéüŃüŽň║âŃüäŃüčŃéüŃÇüŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣ňŤŻňćůŃüźŠőášé╣Ńé嚯«ŃüĆŠŚąš│╗ń╝üŠąşŃü»ŃÇüŔç¬Ŕ║źŃü«ń║őŠąşŃüîŃÇîň┐ůÚáłŃÇŹŃüżŃüčŃü»ŃÇîÚçŹŔŽüŃÇŹń║őŠąşŔÇůŃüźŔę▓ňŻôŃüÖŃéőŃüőŃéĺŃüżŃüÜšó║Ŕ¬ŹŃüÖŃéőň┐ůŔŽüŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŠ│ĽšÜäŠőśŠŁčňŐŤŃüÁŃéüŃüŽň╝ĚŃüĆŃÇüÚüĽňĆŹŃüŚŃüčňá┤ňÉłŃü»ŠťÇňĄž1,000ńŞçŃâŽŃâ╝ŃâşŃÇüŃüżŃüčŃü»ňůĘńŞľšĽîň╣┤Úľôňú▓ńŞŐÚźśŃü«2%Ńü«šŻ░ÚçĹŃüĘŃüäŃüćÚźśÚíŹŃü¬ňłÂŔúüŃüîšžĹŃüĽŃéîŃéőŃüčŃéüŃÇüňŹśŃü¬ŃéőŃâČŃâöŃâąŃâćŃâ╝ŃéĚŃâžŃâ│Ńâ¬Ńé╣Ńé»ŃüźšĽÖŃüżŃéëŃüÜŃÇüń╝üŠąşŃü«ňşśšÂÜŃüźÚľóŃéĆŃéőÚçŹňĄžŃü¬Ŕ▓íňőÖŃâ¬Ńé╣Ńé»ŃéĺŠäĆňĹ│ŃüŚŃüżŃüÖŃÇéšë╣ŃüźŃÇüšÁîňľÂÚÖúŃü«šŤ┤ŠÄąšÜäŃü¬Ŕ▓Čń╗╗ŃüîňĽĆŃéĆŃéîŃéőŃüĘŃüäŃüćšé╣Ńü»ŃÇüŠŚąŠťČŃü«ń╝üŠąşŠľçňîľŃüźŠůúŃéîŃüčšÁîňľÂŔÇůŃüźŃüĘŃüúŃüŽňĄžŃüŹŃü¬ŠäĆňĹ│ŃéĺŠîüŃüíŃüżŃüÖŃÇé
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúšŤúšŁúńŻôňłÂ
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúńŻôňłÂŃü»ŃÇüŔĄçŠĽ░Ńü«ň░éھNJęčÚľóŃüîÚÇúŠÉ║Ńâ╗ňłćŠőůŃüŚŃüŽšÁ▒ŠőČŃüÖŃéőŠžőÚÇáŃüĘŃü¬ŃüúŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüŁŃü«ńŞşň┐âŃüźŃü»ŃÇüANSSIŃüĘCNILŃüĘŃüäŃüćń║îŃüĄŃü«ńŞ╗ŔŽüŃü¬ŠęčÚľóŃüîňşśňťĘŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
ANSSI´╝łňŤŻň«ÂŠâůňá▒ŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúň║ü´╝ëŃü»ŃÇüÚŽľšŤŞšŤ┤ň▒×Ńü«ŠęčÚľóŃüžŃüéŃéŐŃÇüňŤŻň«ÂŃü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Úś▓ŔíŤŃéĺŠőůŃüćńŞşň┐âšÜäŃü¬ňşśňťĘŃüžŃüÖŃÇéŃüŁŃü«ŃâčŃââŃéĚŃâžŃâ│Ńü»ŃÇüňŤŻň«ÂŃü«ÚçŹŔŽüŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃéäŔ╗Źń║őŃâ╗ŃéĄŃâ│ŃâĽŃâęÚľóÚÇúŃü«Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúšó║ń┐ŁŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Šö╗ŠĺâŃü«šŤúŔŽľŃâ╗ŠĄťščąŃâ╗ň»żň┐ťŃÇüňůČňů▒ŠęčÚľóŃéäń╝üŠąşŃüŞŃü«ňŐęŔĘÇŃÇüŃüŁŃüŚŃüŽŃé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŔúŻňôüŃéäŃéÁŃâ╝ŃâôŃé╣Ńü«Ŕ¬ŹŔĘ╝Ńâ╗ŃâęŃâÖŃâźń╗śŃüĹŃéĺŔíîŃüćŃüôŃüĘŃüžŃüÖŃÇéŃüżŃüčŃÇüNIS2Šîçń╗ĄŃü«ňŤŻňćůŠ│ĽňîľŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃééŃÇüANSSIŃü»ň«čŠľŻŃâ╗š«íšÉćŃâ╗šŤúšŁúŃüźŃüŐŃüäŃüŽńŞşň┐âšÜäŃü¬ňŻ╣ňë▓ŃéĺŠőůŃüćŃüôŃüĘŃüźŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ńŞÇŠľ╣ŃÇüCNIL´╝łŠâůňá▒ň玚ÉćŃüŐŃéłŃü│Ŕ笚ö▒ŃüźÚľóŃüÖŃéőňŤŻň«Âňžöňôíń╝Ü´╝ëŃü»ŃÇüŠČžňĚ×Ńü«GDPR´╝łńŞÇŔłČŃâçŃâ╝Ńé┐ń┐ŁŔşĚŔŽĆňëç´╝ëŃü«ňŤŻňćůšŤúšŁúŠęčÚľóŃüžŃüéŃéŐŃÇüńŞ╗ŃüźňÇőń║║ŃâçŃâ╝Ńé┐Ńü«ń┐ŁŔşĚŃé嚍úšŁúŃüŚŃüżŃüÖŃÇéSRENŠ│ĽŃü«ŠľŻŔíîŃüźń╝┤ŃüäŃÇüDSA´╝łŃâçŃéŞŃé┐ŃâźŃéÁŃâ╝ŃâôŃé╣Š│Ľ´╝ëŃüźňč║ŃüąŃüĆňÇőń║║ŃâçŃâ╝Ńé┐ÚľóÚÇúŃü«šżęňőÖ´╝łŠť¬ŠłÉň╣┤ŔÇůŃüŞŃü«ň║âňĹŐŃâŚŃâşŃâĽŃéíŃéĄŃâ¬Ńâ│Ńé░ňłÂÚÖÉŃü¬Ńüę´╝ëŃü«šŤúŔŽľŃâ╗šŤúšŁúŃüĘŃüäŃü抾░ŃüčŃü¬ŠĘęÚÖÉŃüîń╗śńŞÄŃüĽŃéîŃüżŃüŚŃüčŃÇé
ŠŚąŠťČŃü«NISC´╝łňćůÚľúŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŃé╗Ńâ│Ńé┐Ńâ╝´╝ëŃüîŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŠłŽšĽąŃü«ňĆŞń╗ĄňíöŃüĘŃüŚŃüŽŠęčŔâŻŃüŚŃÇüňÇőń║║Šâůňá▒ń┐ŁŔşĚňžöňôíń╝ÜŃüîňÇőń║║Šâůňá▒ń┐ŁŔşĚŠ│ĽŃé嚍úšŁúŃüÖŃéőńŻôňłÂŃüĘÚí×ń╝╝ŃüŚŃüŽŃüŐŃéŐŃÇüANSSIŃüĘCNILŃü«ňŻ╣ňë▓Ńü»ŠśÄšó║ŃüźňłćŃüőŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéANSSIŃü»ŃÇîŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃü«ň«ëňůĘŠÇžŃÇŹŃüĘŃÇîŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Úś▓ŔíŤŃÇŹŃéĺŃÇüCNILŃü»ŃÇîňÇőń║║Šâůňá▒Ńü«ń┐ŁŔşĚŃÇŹŃéĺńŞ╗ŔŽüŃü¬š«íŔŻäÚáśňččŃüĘŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
SRENŠ│ĽŃüźŃéłŃüúŃüŽňëÁŔĘşŃüĽŃéîŃüčŃÇîŃâçŃéŞŃé┐ŃâźŃéÁŃâ╝ŃâôŃé╣ŔŽĆňłÂŔ¬┐ŠĽ┤Ńü«ŃüčŃéüŃü«ňŤŻň«ÂŃâŹŃââŃâłŃâ»Ńâ╝Ńé»ŃÇŹŃü»ŃÇüŃüôŃéîŃéëŃü«ňŻôň▒ÇŃüîŠâůňá▒Ńéĺňů▒ŠťëŃüŚŃÇüÚÇúŠÉ║Ńéĺň╝ĚňîľŃüÖŃéőŃüčŃéüŃü«ń╗ĽšÁäŃü┐ŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃüźŃéłŃéŐŃÇüňŹśńŞÇŃü«ŃéĄŃâ│ŃéĚŃâçŃâ│ŃâłŃüîŃÇüŠŐÇŔíôšÜäŃü¬ňü┤ÚŁóŃüžANSSIŃü«šŤúŔŽľň»żŔ▒íŃüĘŃü¬ŃéŐŃÇüňÇőń║║ŃâçŃâ╝Ńé┐Ńü«ňü┤ÚŁóŃüžCNILŃü«Ŕ¬┐Šč╗ň»żŔ▒íŃüĘŃü¬ŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇ銌ąš│╗ń╝üŠąşŃü»ŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝ŃéĄŃâ│ŃéĚŃâçŃâ│ŃâłšÖ║šöčŠÖéŃüźŃÇüńŞíňŻôň▒ÇŃüŞŃü«ňá▒ňĹŐšżęňőÖŃéĺŔ▓áŃüćňĆ»Ŕ⯊ǞŃéĺŔ¬ŹŔşśŃüŚŃÇüÚüęňłçŃü¬ÚÇúšÁíńŻôňłÂŃé办őš»ëŃüŚŃüŽŃüŐŃüĆň┐ůŔŽüŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃüżŃüĘŃéü
ŃâĽŃâęŃâ│Ńé╣Ńü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńé╗ŃéşŃâąŃâ¬ŃâćŃéúŠ│ĽŃü»ŃÇüňĆĄňůŞšÜäŃü¬ňłĹŠ│ĽŃÇüňőĽšÜäŃü¬ňŤŻňćůŠ│Ľ´╝łSRENŠ│Ľ´╝ëŃÇüŃüŁŃüŚŃüŽEUŠîçń╗Ą´╝łNIS2Šîçń╗Ą´╝ëŃü«ňŤŻňćůŠ│ĽňîľŃüĘŃüäŃüćňĄÜň▒ĄšÜäŃü¬ŠžőÚÇáŃéĺŠîüŃüúŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«Š│ĽńŻôš│╗Ńü»ŃÇüŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝šŐ»šŻ¬Ńü«šÖ║šöčňżîŃüźŃÇîšŐ»ń║║Ńéĺň玚Ż░ŃüÖŃéőŃÇŹŃüĘŃüäŃüćňżôŠŁąŃü«ŔÇâŃüłŠľ╣ŃüőŃéëŃÇüŃÇżń╝ÜňůĘńŻôŃü«ŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝Ńâ¬Ńé╣Ńé»ŃéĺŔ╗ŻŠŞŤŃüÖŃéőŃÇŹŃüĘŃüäŃüćń║łÚś▓šÜäŃü¬ŃéóŃâŚŃâşŃâ╝ŃâüŃüŞŃüĘšž╗ŔíîŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŠŚąš│╗ń╝üŠąşŃü»ŃÇüňŹśŃüźŃÇîńŞŹŠşúŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣ŃÇŹŃéĺňłĹŠ│ĽńŞŐŃü«šŐ»šŻ¬ŃüĘŃüŚŃüŽŠŹëŃüłŃéőŃüáŃüĹŃüžŃü¬ŃüĆŃÇüNIS2Šîçń╗ĄŃüźňč║ŃüąŃüĆŃÇîšÁîňľÂÚÖúŃü«Ŕ▓Čń╗╗ŃÇŹŃéäŃÇüŠľ░ŃüčŃü¬ňá▒ňĹŐšżęňőÖŃÇüŃéÁŃâŚŃâęŃéĄŃâüŃéžŃâ╝Ńâ│ňůĘńŻôŃü«Ńâ¬Ńé╣Ń黚«íšÉćŃüĘŃüäŃüúŃüčň║âš»äŃü¬Ńé│Ńâ│ŃâŚŃâęŃéĄŃéóŃâ│Ńé╣ŔŽüń╗ÂŃéĺšÉćŔžúŃüÖŃéőň┐ůŔŽüŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŃéÁŃéĄŃâÉŃâ╝ŃéĄŃâ│ŃéĚŃâçŃâ│ŃâłšÖ║šöčŠÖéŃüźŃü»ŃÇüŃâ┤ŃéžŃâźŃéÁŃéĄŃ⎊ĞŔĘ┤ÚÖóŃü«ňłĄńżőŃü║ŃüÖŃéłŃüćŃüźŃÇüŔóźň«│ń╝üŠąşŃüîŃÇîňůĚńŻôšÜäŃü¬ŠÉŹň«│ŃÇŹŃéĺšźőŔĘ╝ŃüÖŃéőŔ▓Čń╗╗ŃéĺŔ▓áŃüćŃüčŃéüŃÇüń║őňëŹŃü«Š║ľňéÖŃüĘŠşúšó║Ńü¬Ŕóźň«│ŔĘśÚî▓ŃüîńŞŹňĆ»ŠČáŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃéźŃâćŃé┤Ńâ¬Ńâ╝: ITŃâ╗ŃâÖŃâ│ŃâüŃâúŃâ╝Ńü«ń╝üŠąşŠ│ĽňőÖ