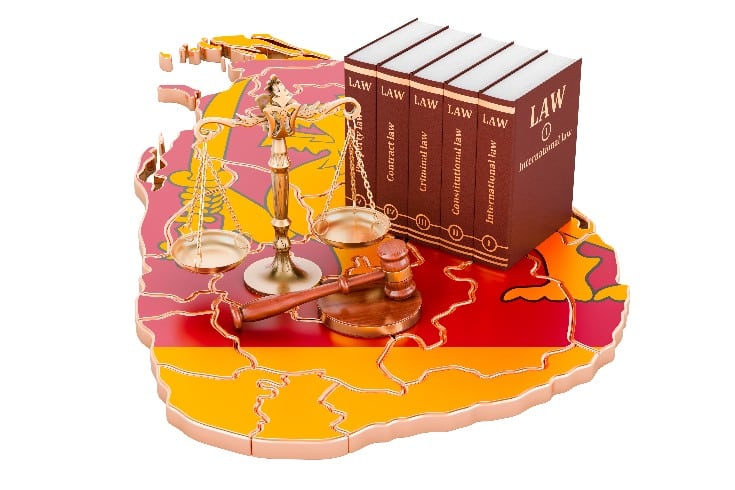مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ه…±ه’Œه›½مپ®ه¤–ه›½ç›´وژ¥وٹ•è³‡ï¼ˆFDI)ه¯©وں»هˆ¶ه؛¦م‚’解èھ¬

مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ï¼ˆن»¥ن¸‹م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ه…±ه’Œه›½ï¼‰مپ¯م€پن¼çµ±çڑ„مپ«è³‡وœ¬مپ®è‡ھç”±مپھ移ه‹•م‚’هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€په›½ه®¶مپ®ه®‰ه…¨ن؟éڑœمپ¨ه…¬ه…±مپ®ç§©ه؛ڈم‚’ن؟è·مپ™م‚‹مپںم‚پم€پ特ه®ڑمپ®ه¤–ه›½ç›´وژ¥وٹ•è³‡ï¼ˆFDI)مپ«ه¯¾مپ—مپ¦هژ³و ¼مپھه¯©وں»هˆ¶ه؛¦م‚’è¨مپ‘مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®هˆ¶ه؛¦مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ه¤–ه›½ç‚؛و›؟هڈٹمپ³ه¤–ه›½è²؟وک“و³•ï¼ˆه¤–ç‚؛و³•ï¼‰مپ«هں؛مپ¥مپڈه¯¾ه†…ç›´وژ¥وٹ•è³‡مپ®م€Œن؛‹ه‰چه±ٹه‡؛م€چهˆ¶ه؛¦مپ¨مپ¯و ¹وœ¬çڑ„مپ«ç•°مپھم‚ٹم€پ経و¸ˆمƒ»è²،ه‹™ه¤§è‡£مپ«م‚ˆم‚‹م€Œن؛‹ه‰چèھچهڈ¯م€چم‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚特مپ«م€پè؟‘ه¹´مپ¯ه؛¦é‡چمپھم‚‹و³•و”¹و£مپ«م‚ˆم‚ٹمپمپ®éپ©ç”¨ç¯„ه›²مپ¨ه¤§è‡£مپ®و¨©é™گمپŒه¤§ه¹…مپ«ه¼·هŒ–مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پو—¥وœ¬ن¼پو¥مپŒمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ن¼پو¥مپ¸مپ®وٹ•è³‡م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹éڑ›مپ«مپ¯م€پمپ“مپ®è¤‡é›‘مپھو³•çڑ„و 組مپ؟م‚’و£ç¢؛مپ«çگ†è§£مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€پوœ€و–°مپ®و³•ن»¤م€پ特مپ«2023ه¹´وœ«مپ«ه°ژه…¥مپ•م‚Œمپںه¤‰و›´ç‚¹م‚’è¸ڈمپ¾مپˆم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ه¤–ه›½ç›´وژ¥وٹ•è³‡ه¯©وں»هˆ¶ه؛¦مپ®ه…¨è²Œمپ¨م€پو—¥وœ¬مپ®هˆ¶ه؛¦مپ¨مپ®é‡چè¦پمپھ相éپ•ç‚¹م€پمپمپ—مپ¦M&Aه®ںه‹™مپ«مپٹمپ‘م‚‹ه…·ن½“çڑ„مپھç•™و„ڈ点مپ«مپ¤مپ„مپ¦è©³ç´°مپ«è§£èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپھمپٹم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هŒ…و‹¬çڑ„مپھو³•هˆ¶ه؛¦مپ®و¦‚è¦پمپ¯ن¸‹è¨کè¨کن؛‹مپ«مپ¦مپ¾مپ¨م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ®ç›®و¬،
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ه¤–ه›½ç›´وژ¥وٹ•è³‡ه¯©وں»هˆ¶ه؛¦
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ه¤–ه›½ç›´وژ¥وٹ•è³‡مپ«é–¢مپ™م‚‹و³•هˆ¶ه؛¦مپ¯م€پ金èچمƒ»é€ڑ貨و³•ه…¸مپ«مپمپ®و ¹و‹ م‚’وœ‰مپ—مپ¾مپ™م€‚هگŒو³•ه…¸ç¬¬L.151-1و،مپ¯م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ¨وµ·ه¤–مپ¨مپ®é–“مپ®é‡‘èچهڈ–ه¼•مپ®è‡ھç”±م‚’هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦ه®ڑم‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پوٹ•è³‡م‚’هگ«م‚€è³‡وœ¬مپ®è‡ھç”±مپھ移ه‹•مپŒهں؛وœ¬çڑ„مپھ考مپˆو–¹مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پمپ“مپ®هژںه‰‡مپ«مپ¯م€په›½ه®¶مپ®ه®‰ه…¨ن؟éڑœم€په…¬è،†è،›ç”ںم€پمپٹم‚ˆمپ³ه…¬ه…±مپ®ç§©ه؛ڈم‚’ن؟è·مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®é‡چè¦پمپھن¾‹ه¤–مپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚هگŒو³•ه…¸ç¬¬L.151-3و،مپ¯م€پمپ“م‚Œم‚‰مپ®م€Œه›½ه®¶مپ®هˆ©ç›ٹم€چمپ«ه½±éں؟م‚’هڈٹمپ¼مپ™ç‰¹ه®ڑمپ®و´»ه‹•مپ¸مپ®ه¤–ه›½وٹ•è³‡م‚’م€پ経و¸ˆمƒ»è²،ه‹™ه¤§è‡£مپ®ن؛‹ه‰چèھچهڈ¯مپ®ه¯¾è±،مپ¨ه®ڑم‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®م€Œهژںه‰‡è‡ھç”±م€پن¾‹ه¤–è¦ڈهˆ¶م€چمپ¨مپ„مپ†و§‹é€ مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ه¤–ç‚؛و³•مپ«مپٹمپ‘م‚‹è€ƒمپˆو–¹مپ¨é،ن¼¼مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
è؟‘ه¹´م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®FDIه¯©وں»هˆ¶ه؛¦مپ¯م€په›½ه®¶مپ®çµŒو¸ˆن¸»و¨©م‚’ç¢؛ن؟مپ™م‚‹ç›®çڑ„مپ‹م‚‰م€پ継ç¶ڑçڑ„مپ«مپمپ®éپ©ç”¨ç¯„ه›²مپ¨هژ³و ¼و€§م‚’é«کم‚پمپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚مپمپ®وµپم‚Œمپ¯م€پ2019ه¹´مپ«هˆ¶ه®ڑمپ•م‚ŒمپںPACTEو³•ï¼ˆن¼پو¥وˆگé•·مپ¨ه¤‰é©مپ®مپںم‚پمپ®è،Œه‹•è¨ˆç”»و³•ï¼‰مپ«ç«¯م‚’ç™؛مپ—مپ¾مپ™م€‚PACTEو³•مپ¯م€پ経و¸ˆمƒ»è²،ه‹™ه¤§è‡£مپ«م€پéپ•هڈچ者مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ç½°é‡‘賦èھ²م‚„وٹ•è³‡مپ®هژںçٹ¶ه›ه¾©ه‘½ن»¤مپ¨مپ„مپ£مپںه¼·هٹ›مپھو¨©é™گم‚’ن»کن¸ژمپ—مپ¾مپ—مپںم€‚مپمپ®ه¾Œم€پ2019ه¹´12وœˆ31و—¥ن»کمƒ‡م‚¯مƒ¬ç¬¬2019-1590هڈ·مپŒم€پو¬§ه·é€£هگˆه…¨ن½“مپ§مپ®FDIم‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ‹مƒ³م‚°è¦ڈه‰‡ï¼ˆEU)2019/452مپ®وژ،وٹمپ¨é€£ه‹•مپ™م‚‹ه½¢مپ§م€پFDIه¯©وں»هˆ¶ه؛¦م‚’ه…¨é¢çڑ„مپ«هˆ·و–°مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚مپ“مپ®و”¹و£مپ¯م€په¯©وں»و‰‹ç¶ڑمپچمپ«ن؛Œو®µéڑژمƒ—مƒم‚»م‚¹م‚’ه°ژه…¥مپ™م‚‹مپھمپ©م€په®ںه‹™ن¸ٹمپ®éپ‹ç”¨م‚’ه¤§مپچمپڈه¤‰مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
2024ه¹´1وœˆ1و—¥ن»¥é™چمپ®مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹FDIهˆ¶ه؛¦ه¤‰و›´
è؟‘ه¹´مپ®FDIهˆ¶ه؛¦ه¼·هŒ–مپ®و½®وµپمپ¯م€پ2023ه¹´12وœˆ28و—¥ن»کمƒ‡م‚¯مƒ¬ç¬¬2023-1293هڈ·مپ¨هگŒه¹´هگŒو—¥ن»کمپ®ه‘½ن»¤مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پمپ•م‚‰مپ«هٹ é€ںمپ—م€پوپ’ن¹…çڑ„مپھم‚‚مپ®مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚مپ“مپ®و³•و”¹و£مپ¯م€پ特مپ«و—¥وœ¬مپ®وٹ•è³‡ه®¶مپŒو³¨و„ڈمپ™مپ¹مپچن»¥ن¸‹مپ®é‡چè¦پمپھه¤‰و›´م‚’هگ«م‚“مپ§مپ„مپ¾مپ™م€‚
第ن¸€مپ«م€پè°و±؛و¨©é–¾ه€¤مپ®وپ’ن¹…هŒ–مپ§مپ™م€‚و–°ه‹م‚³مƒمƒٹم‚¦م‚¤مƒ«م‚¹مپ®çµŒو¸ˆçڑ„ه½±éں؟مپ«ه¯¾ه‡¦مپ™م‚‹مپںم‚پم€پ2020ه¹´7وœˆمپ«ن¸€و™‚çڑ„مپھوژھç½®مپ¨مپ—مپ¦ه°ژه…¥مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€پن¸ٹه ´ن¼پو¥مپ¸مپ®éEU/EEAوٹ•è³‡ه®¶مپ«م‚ˆم‚‹è°و±؛و¨©10%ن»¥ن¸ٹمپ®هڈ–ه¾—م‚’ن؛‹ه‰چèھچهڈ¯مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپ™م‚‹مƒ«مƒ¼مƒ«مپŒم€پ2024ه¹´1وœˆ1و—¥ن»¥é™چم€پوپ’ن¹…çڑ„مپھهˆ¶ه؛¦مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€په¾“و¥مپ®ن¸ٹه ´ن¼پو¥مپ¸مپ®25%مپ¨مپ„مپ†é–¾ه€¤مپ¯ن؛‹ه®ںن¸ٹéپ©ç”¨مپ•م‚Œمپھمپڈمپھم‚ٹم€پم‚ˆم‚ٹه°‘é،چمپ®وٹ•è³‡مپ§مپ‚مپ£مپ¦م‚‚ه¯©وں»مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒé«کمپ¾م‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
第ن؛Œمپ«م€په¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹و©ںه¾®هˆ†é‡ژمپ®مƒھم‚¹مƒˆمپŒو‹،ه¤§مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚特مپ«م€پé‡چè¦پهژںوگو–™مپ®وٹ½ه‡؛مƒ»هٹ ه·¥مƒ»مƒھم‚µم‚¤م‚¯مƒ«و´»ه‹•م€پن½ژç‚ç´ م‚¨مƒچمƒ«م‚®مƒ¼م€پمƒ•م‚©مƒˆمƒ‹م‚¯م‚¹م€پمپمپ—مپ¦هˆ‘ه‹™و‰€è¦ه‚™م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒو–°مپںمپ«هٹ م‚ڈم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®هˆ†é‡ژمپ®è؟½هٹ مپ¯م€پهœ°و”؟ه¦çڑ„مپھç·ٹه¼µمپ®é«کمپ¾م‚ٹم‚„م€پEUه…¨ن½“مپ§مپ®é‡چè¦پم‚µمƒ—مƒ©م‚¤مƒپم‚§مƒ¼مƒ³ç¢؛ن؟مپ®ه؟…è¦پو€§مپ¨مپ„مپ£مپںم€پم‚ˆم‚ٹه؛ƒç¯„مپھ背و™¯مپ«هں؛مپ¥مپ„مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
第ن¸‰مپ«م€په¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹وٹ•è³‡مپ®é،ه‹مپŒو‹،ه¤§مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚ن»¥ه‰چمپ¯م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•مپ«و؛–و‹ مپ™م‚‹و³•ن؛؛مپŒè¨ç«‹مپ—مپںن¼پو¥مپ¸مپ®وٹ•è³‡مپ®مپ؟مپŒه¯¾è±،مپ§مپ—مپںمپŒم€پ2024ه¹´1وœˆ1و—¥ن»¥é™چمپ¯م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ه›½ه†…مپ§ç™»è¨کمپ•م‚Œمپںه¤–ه›½و³•ن؛؛مپ®ه•†و¥و”¯ه؛—مپ®è²·هڈژم‚‚ه¯©وں»ه¯¾è±،مپ«هگ«مپ¾م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پFDIه¯©وں»م‚’ه›éپ؟مپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ™م‚‹è©¦مپ؟م‚’éک²مپگو„ڈه›³مپŒمپ‚م‚‹مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®ç¶™ç¶ڑçڑ„مپھهˆ¶ه؛¦ه¼·هŒ–مپ®ه‹•مپچمپ¯م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®FDIه¯©وں»هˆ¶ه؛¦مپŒهچکمپھم‚‹ه›½ه†…çڑ„مپھè¦ڈهˆ¶مپ«مپ¨مپ©مپ¾م‚‰مپڑم€پEUمپ®ه®‰ه…¨ن؟éڑœوˆ¦ç•¥مپ¨ه¯†وژ¥مپ«é€£ه‹•مپ—م€پ特ه®ڑمپ®ه¤–çڑ„è¦په› (مƒ‘مƒ³مƒ‡مƒںمƒƒم‚¯م€پهœ°و”؟ه¦çڑ„ç·ٹه¼µï¼‰مپ«è؟…é€ںمپ«ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹وں”è»ںمپھم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¨مپ—مپ¦é€²هŒ–مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛ه”†مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ—مپںمپŒمپ£مپ¦م€پو—¥وœ¬مپ®وٹ•è³‡ه®¶مپ¯م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هˆ¶ه؛¦م‚’çگ†è§£مپ™م‚‹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پو¬§ه·مپ®ه؛ƒç¯„مپھه®‰ه…¨ن؟éڑœمپٹم‚ˆمپ³çµŒو¸ˆو”؟ç–مپ®ه‹•هگ‘مپ«م‚‚ç›®م‚’هگ‘مپ‘م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹FDIمپ§ه¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹م€Œوٹ•è³‡ه®¶م€چمپ¨م€Œوٹ•è³‡م€چ

م€Œه¤–ه›½وٹ•è³‡ه®¶م€چمپ®ه؛ƒç¯„مپھه®ڑ義
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®é‡‘èچمƒ»é€ڑ貨و³•ه…¸ç¬¬R.151-1و،مپ¯م€پن؛‹ه‰چèھچهڈ¯مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹م€Œه¤–ه›½وٹ•è³‡ه®¶م€چم‚’ه؛ƒç¯„مپ«ه®ڑ義مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®مپ„مپڑم‚Œمپ‹مپ«è©²ه½“مپ™م‚‹ه€‹ن؛؛مپ¾مپںمپ¯و³•ن؛؛مپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚
- ه¤–ه›½ç±چمپ®ه€‹ن؛؛
- مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ه›½ه†…مپ«ç¨ژو³•ن¸ٹمپ®ن½ڈو‰€م‚’وŒپمپںمپھمپ„مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ç±چمپ®ه€‹ن؛؛
- ه¤–ه›½و³•مپ«و؛–و‹ مپ™م‚‹و³•ن؛؛
- ن¸ٹè¨که€‹ن؛؛مپ¾مپںمپ¯و³•ن؛؛مپ«و”¯é…چمپ•م‚Œم‚‹مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•مپ«و؛–و‹ مپ™م‚‹و³•ن؛؛
مپ“مپ®ه®ڑ義مپ¯م€پوٹ•è³‡مƒ•م‚،مƒ³مƒ‰م‚’é€ڑمپکمپ¦وٹ•è³‡م‚’è،Œمپ†ه ´هگˆم€پمƒ•م‚،مƒ³مƒ‰مƒمƒچمƒ¼م‚¸مƒ£مƒ¼م‚„مƒ•م‚،مƒ³مƒ‰م‚’و”¯é…چمپ™م‚‹ه€‹ن؛؛مƒ»و³•ن؛؛مپ®è؛«ه…ƒم‚‚é–‹ç¤؛مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹مپھمپ©م€پوœ€çµ‚çڑ„مپھو”¯é…چ者مپ¾مپ§éپ،هڈٹمپ—مپ¦ه¯©وں»مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚
ن؛‹ه‰چèھچهڈ¯مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹م€Œوٹ•è³‡م€چمپ®é،ه‹
金èچمƒ»é€ڑ貨و³•ه…¸ç¬¬R.151-2و،مپ¯م€پن؛‹ه‰چèھچهڈ¯مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹وٹ•è³‡م‚’ن»¥ن¸‹مپ®4é،ه‹مپ«هˆ†é،مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®مپ†مپ،م€پمپ„مپڑم‚Œمپ‹ن¸€مپ¤مپ«è©²ه½“مپ™م‚Œمپ°ه¯©وں»مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- و”¯é…چو¨©مپ®هڈ–ه¾—(Control Test)ï¼ڑه•†و³•ه…¸ç¬¬L.233-3و،مپ«ه®ڑم‚پم‚‹م€Œو”¯é…چو¨©م€چم‚’هڈ–ه¾—مپ™م‚‹هڈ–ه¼•مپŒه¯¾è±،مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®ن¼ڑ社و³•مپ§مپ¯م€پè°و±؛و¨©مپ®éپژهچٹو•°ن؟وœ‰مپŒهگن¼ڑ社مپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم‚‹هژںه‰‡çڑ„مپھè¦پن»¶مپ§مپ™مپŒم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ه•†و³•ه…¸مپ§مپ¯è°و±؛و¨©مپ®éپژهچٹو•°ن»¥ه¤–مپ«م€پو ھن¸»é–“هچ”ه®ڑمپ«هں؛مپ¥مپڈو”¯é…چم‚„هڈ–ç· ه½¹ن¼ڑمپ«مپٹمپ‘م‚‹ه¤ڑو•°و´¾ه½¢وˆگ能هٹ›مپھمپ©م‚‚م€Œو”¯é…چو¨©م€چمپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€پè°و±؛و¨©مپ®40%ن»¥ن¸ٹم‚’ن؟وœ‰مپ™م‚‹مپ¨و”¯é…چو¨©مپŒمپ‚م‚‹مپ¨وژ¨ه®ڑمپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- ن؛‹و¥éƒ¨é–€مپ®هڈ–ه¾—(Asset Test)ï¼ڑمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•ن؛؛مپŒè¨ç«‹مپ—مپںن؛‹و¥éƒ¨é–€مپ®ه…¨éƒ¨مپ¾مپںمپ¯ن¸€éƒ¨م‚’هڈ–ه¾—مپ™م‚‹هڈ–ه¼•مپŒه¯¾è±،مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- è°و±؛و¨©25%مپ®هڈ–ه¾—(Threshold Test)ï¼ڑéEU/EEAوٹ•è³‡ه®¶مپŒم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•ن؛؛مپ®è°و±؛و¨©مپ®25%ن»¥ن¸ٹم‚’هچک独مپ§م€پمپ¾مپںمپ¯ه…±هگŒمپ—مپ¦هڈ–ه¾—مپ™م‚‹هڈ–ه¼•مپŒه¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- è°و±؛و¨©10%مپ®هڈ–ه¾—(Listed Company Threshold)ï¼ڑ2024ه¹´1وœˆ1و—¥ن»¥é™چم€پéEU/EEAوٹ•è³‡ه®¶مپŒم€پو©ںه¾®هˆ†é‡ژمپ®و´»ه‹•م‚’è،Œمپ†مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ن¸ٹه ´ن¼پو¥مپ®è°و±؛و¨©مپ®10%ن»¥ن¸ٹم‚’هڈ–ه¾—مپ™م‚‹هڈ–ه¼•مپŒوپ’ن¹…çڑ„مپ«ه¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هˆ¶ه؛¦مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œو”¯é…چو¨©م€چمپ®و¦‚ه؟µمپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®و³•ه‹™و‹…ه½“者مپŒé€ڑه¸¸وƒ³ه®ڑمپ™م‚‹ç¯„ه›²م‚’超مپˆمپ¦ه؛ƒç¯„مپ§مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پهچکمپ«è°و±؛و¨©و¯”çژ‡م‚’見م‚‹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پن¼ڑ社مپ®ه®ڑو¬¾م‚„و ھن¸»é–“ه¥‘ç´„مپ«هں؛مپ¥مپڈ特هˆ¥مپھè°و±؛و¨©م‚„و”¯é…چو¨©é™گم€پمپ¾مپںمپ¯é–“وژ¥çڑ„مپھو”¯é…چو§‹é€ م‚’詳細مپ«هˆ†وگمپ—مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپھمپ„مپ“مپ¨م‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پè¦ھن¼ڑ社مپ«ه¯¾مپ™م‚‹è°و±؛و¨©é–¾ه€¤مپ®è¶…éپژمپŒم€پمپمپ®مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹هگن¼ڑ社مپ«مپٹمپ‘م‚‹é–“وژ¥çڑ„مپھè°و±؛و¨©é–¾ه€¤مپ®è¶…éپژمپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚ٹم€پهڈ–ه¼•ه…¨ن½“مپ®مƒھم‚¹م‚¯è©•ن¾،مپ«ه¤ڑه±¤çڑ„مپھ視点مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹FDIمپ®ه¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹م€Œو©ںه¾®هˆ†é‡ژم€چ
ه¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹و©ںه¾®هˆ†é‡ژمپ¯م€پ金èچمƒ»é€ڑ貨و³•ه…¸ç¬¬L.151-3و،مپٹم‚ˆمپ³é–¢é€£مƒ‡م‚¯مƒ¬مپ§è©³ç´°مپ«ه®ڑم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپمپ®مƒھم‚¹مƒˆمپ¯م€پن¼çµ±çڑ„مپھهˆ†é‡ژمپ«هٹ مپˆم€پو™‚ن»£مپ®ه¤‰هŒ–مپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦ç¶™ç¶ڑçڑ„مپ«و›´و–°مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«مپ¯م€په›½éک²مƒ»è»چن؛‹م€په…¬ه®‰م€په…¬è،†è،›ç”ںم€پم‚¨مƒچمƒ«م‚®مƒ¼م€پé€ڑن؟،م€پمƒ‡مƒ¼م‚؟ن؟هکم€پن؛¤é€ڑم€پé£ںو–™ه®‰ه…¨ن؟éڑœمپ¨مپ„مپ£مپںهˆ†é‡ژمپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ç ”ç©¶é–‹ç™؛(R&D)و´»ه‹•مپ¸مپ®و³¨هٹ›
è؟‘ه¹´مپ®FDIه¯©وں»مپ«مپٹمپ„مپ¦م€په½“ه±€مپ¯ç‰¹مپ«ç ”究開ç™؛و´»ه‹•م‚’وŒپمپ¤ن¼پو¥مپ¸مپ®وٹ•è³‡مپ«و³¨هٹ›مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپŒه ±ه‘ٹمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚2024ه¹´مپ®ه¹´و¬،ه ±ه‘ٹو›¸مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پR&Dو´»ه‹•م‚’وŒپمپ¤ن¼پو¥مپ¸مپ®وٹ•è³‡مپ®مپ†مپ،م€پ61%مپŒو،ن»¶ن»کمپچèھچهڈ¯م‚’هڈ—مپ‘مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€په½“ه±€مپŒه°†و¥مپ®ه›½ه®¶مپ®ç«¶ن؛‰هٹ›مپ«ç›´çµگمپ™م‚‹وٹ€è،“م‚„çں¥çڑ„è²،産مپ®ç¢؛ن؟م‚’FDIه¯©وں»مپ®é‡چè¦پمپھç›®çڑ„مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ه½“ه±€مپŒèھ²مپ™و،ن»¶مپ®ن¾‹مپ¨مپ—مپ¦م€پ特許مƒمƒ¼مƒˆمƒ•م‚©مƒھم‚ھم‚’مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•ن؛؛مپ«ن؟وœ‰مپ•مپ›م‚‹ç¾©ه‹™م‚„م€په½“ه±€مپ¸مپ®وƒ…ه ±وڈگن¾›ç¾©ه‹™مپھمپ©مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه®ںه‹™ن¸ٹمپ®ن¸چç¢؛ه®ںو€§مپ¸مپ®ه¯¾ه؟œ
ه¯©وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹و©ںه¾®هˆ†é‡ژمپ®ه®ڑ義مپ¯هŒ…و‹¬çڑ„مپ§مپ‚م‚ٹم€په€‹م€…مپ®ن؛‹و¥و´»ه‹•مپŒمپ“م‚Œمپ«è©²ه½“مپ™م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹مپ®هˆ¤و–مپ¯ه®¹وک“مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھن¸چç¢؛ه®ںو€§مپ«ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹مپںم‚پم€پ金èچمƒ»é€ڑ貨و³•ه…¸ç¬¬R.151-4و،مپ¯م€پوٹ•è³‡ه®¶مپŒه¯¾è±،ن¼پو¥مپ¨مپ®هگˆو„ڈمپ«هں؛مپ¥مپچم€پ経و¸ˆمƒ»è²،ه‹™ه¤§è‡£مپ«م€Œن؛‹ه‰چ相談(demande d’avis)م€چم‚’و±‚م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹هˆ¶ه؛¦م‚’ه®ڑم‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ه¤§è‡£مپ¯2مپ‹وœˆن»¥ه†…مپ«ه›ç”مپ™م‚‹ç¾©ه‹™مپŒمپ‚م‚ٹم€پمپ“مپ®هˆ¶ه؛¦م‚’هˆ©ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پو£ه¼ڈمپھèھچهڈ¯ç”³è«‹مپ«ه…¥م‚‹ه‰چمپ«هڈ–ه¼•مپ®FDIه¯©وں»è©²ه½“و€§م‚’ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹FDIمپ®ن؛‹ه‰چèھچهڈ¯و‰‹ç¶ڑمپچ
ن؛Œو®µéڑژمپ®ه¯©وں»مƒ—مƒم‚»م‚¹
FDIèھچهڈ¯مپ®ç”³è«‹مپ¯م€پ経و¸ˆمƒ»è²،ه‹™çœپمپ®م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مƒ—مƒ©مƒƒمƒˆمƒ•م‚©مƒ¼مƒ م‚’é€ڑمپکمپ¦è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚ه¯©وں»مپ¯هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦ن؛Œو®µéڑژهˆ¶مپŒوژ،用مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
- مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛1ï¼ڑ申請هڈ—çگ†ه¾Œم€پ30ه–¶و¥و—¥ن»¥ه†…مپ«ه¤§è‡£مپŒن»¥ن¸‹مپ®مپ„مپڑم‚Œمپ‹م‚’و±؛ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚
- ه¯©وں»ه¯¾è±،ه¤–مپ§مپ‚م‚‹مپ¨هˆ¤و–مپ™م‚‹م€‚
- ç„،و،ن»¶مپ§èھچهڈ¯مپ™م‚‹م€‚
- 詳細مپھه¯©وں»ï¼ˆمƒ•م‚§مƒ¼م‚؛2)مپŒه؟…è¦پمپ§مپ‚م‚‹مپ¨هˆ¤و–مپ™م‚‹م€‚
- مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛2ï¼ڑمƒ•م‚§مƒ¼م‚؛1مپ§è©³ç´°مپھه¯©وں»مپŒه؟…è¦پمپ¨هˆ¤و–مپ•م‚Œمپںه ´هگˆم€په¤§è‡£مپ¯è؟½هٹ مپ§45ه–¶و¥و—¥ن»¥ه†…مپ«م€پèھچهڈ¯ï¼ˆو،ن»¶ن»کمپچم‚’هگ«م‚€ï¼‰مپ¾مپںمپ¯و‹’هگ¦م‚’و±؛ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚
و—¥وœ¬مپ®ه¤–ç‚؛و³•مپ¨هگŒو§کم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هˆ¶ه؛¦مپ«مپٹمپ„مپ¦م‚‚م€په¯©وں»وœںé–“مپ¯وƒ…ه ±è¦پو±‚مپŒمپ‚مپ£مپںه ´هگˆمپ«ن¸و–مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚特مپ«م€پمƒ•م‚§مƒ¼م‚؛1مپ®ه¯©وں»وœںé–“مپ¯م€په½“ه±€مپ‹م‚‰مپ®وƒ…ه ±è¦پو±‚مپŒمپ‚مپ£مپںو™‚点مپ§ن¸و–مپ•م‚Œم€پوƒ…ه ±وڈگن¾›مپŒه®Œن؛†مپ™م‚‹مپ¾مپ§ه†چé–‹مپ•م‚Œمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€په®ںéڑ›مپ®ه¯©وں»وœںé–“مپ¯ه¤§ه¹…مپ«é•·وœںهŒ–مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
و—¥وœ¬مپ®م€Œن؛‹ه‰چه±ٹه‡؛م€چمپ¨مپ®ç›¸éپ•ç‚¹
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®FDIه¯©وں»هˆ¶ه؛¦مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ه¤–ç‚؛و³•مپ«هں؛مپ¥مپڈه¯¾ه†…ç›´وژ¥وٹ•è³‡هˆ¶ه؛¦مپ¨وœ€م‚‚é‡چè¦پمپھ相éپ•ç‚¹م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®éپ•مپ„مپ¯م€پهڈ–ه¼•مپ®م‚¯مƒمƒ¼م‚¸مƒ³م‚°مƒھم‚¹م‚¯مپ«هٹ‡çڑ„مپھه½±éں؟م‚’ن¸ژمپˆمپ¾مپ™م€‚
- و—¥وœ¬مپ®هˆ¶ه؛¦ï¼ڑو—¥وœ¬مپ®هˆ¶ه؛¦مپ§مپ¯م€پن؛‹ه‰چه±ٹه‡؛ه¾Œم€پهژںه‰‡30و—¥é–“مپ®ه¾…و©ںوœںé–“ن¸مپ«و”؟ه؛œمپ‹م‚‰وک¯و£ه‘½ن»¤ç‰مپŒمپھمپ‘م‚Œمپ°م€پوٹ•è³‡ه®¶مپ¯وٹ•è³‡م‚’ه®ںè،Œمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پو”؟ه؛œمپ‹م‚‰مپ®وکژç¤؛çڑ„مپھم‚¢م‚¯م‚·مƒ§مƒ³مپŒمپھمپ„é™گم‚ٹوٹ•è³‡مپ¯هڈ¯èƒ½مپ¨مپھم‚‹م€Œé»™ç¤؛مپ®ç„،ç•°è°م€چمپ®هژںه‰‡مپ«هں؛مپ¥مپ„مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
- مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هˆ¶ه؛¦ï¼ڑمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هˆ¶ه؛¦مپ§مپ¯م€په¯©وں»وœںé–“ه†…مپ«çµŒو¸ˆمƒ»è²،ه‹™ه¤§è‡£مپ‹م‚‰مپ®وکژç¤؛çڑ„مپھم€Œèھچهڈ¯م€چم‚’ه¾—مپھمپ‘م‚Œمپ°م€پوٹ•è³‡م‚’ه®ںè،Œمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¯مپ§مپچمپ¾مپ›م‚“م€‚وœںé–“ه†…مپ«ه›ç”مپŒمپھمپ„ه ´هگˆم€پمپمپ®ç”³è«‹مپ¯م€Œé»™ç¤؛مپ®و‹’هگ¦م€چمپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®و³•çڑ„هٹ¹وœمپ®éپ•مپ„مپ¯م€پM&Aهڈ–ه¼•مپ®م‚¯مƒمƒ¼م‚¸مƒ³م‚°مƒھم‚¹م‚¯م‚’هٹ‡çڑ„مپ«ه¢—ه¤§مپ•مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®هˆ¶ه؛¦مپ§مپ¯م€پن؛ˆè¦‹هڈ¯èƒ½مپھه¾…و©ںوœںé–“مپ®çµŒéپژم‚’م‚‚مپ£مپ¦هڈ–ه¼•مپŒو³•çڑ„مپ«وœ‰هٹ¹مپ¨مپھم‚‹مپںم‚پم€پمƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†مپŒو¯”較çڑ„ه®¹وک“مپ§مپ™م€‚ن¸€و–¹م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هˆ¶ه؛¦مپ§مپ¯م€پن؛ˆوœںمپ›مپ¬ه¤§è‡£مپ®و²ˆé»™ï¼ˆه¯©وں»وœںé–“مپ®و؛€ن؛†ï¼‰مپ¯م€پهڈ–ه¼•م‚’ç¶ڑè،Œمپ§مپچمپھمپ„م€Œو‹’هگ¦م€چم‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®مپںم‚پم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ن¼پو¥مپ¸مپ®M&Aمپ§مپ¯م€پFDIèھچهڈ¯مپ®هڈ–ه¾—مپŒم‚¯مƒمƒ¼م‚¸مƒ³م‚°مپ®ه؟…é ˆو،ن»¶مپ¨مپھم‚ٹم€پن¸چç¢؛ه®ںو€§مپŒé«کمپ¾م‚ٹمپ¾مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®و³•ه‹™و‹…ه½“者مپ«مپ¨مپ£مپ¦م€پمپ“مپ®م€Œé»™ç¤؛مپ®و‹’هگ¦م€چمپ¨مپ„مپ†هژںه‰‡مپ¯وœ€م‚‚馴وں“مپ؟مپŒè–„مپڈم€پé‡چه¤§مپھمƒھم‚¹م‚¯è¦په› مپ¨مپ—مپ¦èھچèکمپ—مپ¦مپٹمپڈه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ§مپ®ç„،èھچهڈ¯وٹ•è³‡مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ç½°ه‰‡مپ¨ه¤§è‡£مپ®و¨©é™گ
هژ³و ¼مپھç½°ه‰‡مپ¨ç„،هٹ¹هŒ–مپ®و³•هٹ¹وœ
ن؛‹ه‰چèھچهڈ¯مپŒه؟…è¦پمپھوٹ•è³‡م‚’ç„،èھچهڈ¯مپ§ه®ںè،Œمپ—مپںه ´هگˆم€پمپمپ®هڈ–ه¼•مپ¯و³•ه¾‹ن¸ٹم€Œç„،هٹ¹م€چ(nul)مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€پ金èچمƒ»é€ڑ貨و³•ه…¸ç¬¬L.151-4و،مپ¯م€په¤§è‡£مپŒن»¥ن¸‹مپ®ه‘½ن»¤م‚’ç™؛مپ™م‚‹و¨©é™گم‚’ه®ڑم‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
- ن؛‹ه‰چèھچهڈ¯ç”³è«‹مپ®وڈگه‡؛
- ç„،許هڈ¯وٹ•è³‡ه‰چمپ®çٹ¶و…‹مپ¸مپ®هژںçٹ¶ه›ه¾©ï¼ˆè²»ç”¨مپ¯وٹ•è³‡ه®¶è² و‹…)
- وٹ•è³‡ه†…ه®¹مپ®ه¤‰و›´
مپ“م‚Œم‚‰مپ®ه‘½ن»¤مپ¨ن½µمپ›مپ¦م€پن»¥ن¸‹مپ®مپ„مپڑم‚Œمپ‹é«کمپ„é،چمپ®ç½°é‡‘مپŒèھ²مپ•م‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- و³•ن؛؛مپ®ه ´هگˆï¼ڑç„،許هڈ¯وٹ•è³‡é،چمپ®2ه€چم€پمپ¾مپںمپ¯ه¯¾è±،ن¼پو¥مپ®ه¹´é–“ه£²ن¸ٹé«کمپ®10%م€پمپ¾مپںمپ¯500ن¸‡مƒ¦مƒ¼مƒ
- ه€‹ن؛؛مپ®ه ´هگˆï¼ڑ100ن¸‡مƒ¦مƒ¼مƒ
مپ“م‚Œم‚‰مپ®ç½°ه‰‡مپ¯و—¥وœ¬مپ®ه¤–ç‚؛و³•مپ«و¯”مپ¹مپ¦éه¸¸مپ«هژ³و ¼مپ§مپ‚م‚ٹم€په®‰وک“مپھوٹ•è³‡ه®ںè،Œمپ¯è‡´ه‘½çڑ„مپھمƒھم‚¹م‚¯م‚’ن¼´مپ„مپ¾مپ™م€‚
èھچهڈ¯ه¾Œمپ®ç¶™ç¶ڑçڑ„مپھ監視مپ¨ه¤§è‡£مپ®و¨©é™گ
ه¤§è‡£مپ¯م€پو،ن»¶ن»کمپچمپ§èھچهڈ¯م‚’ن¸ژمپˆمپںه ´هگˆم€پمپمپ®و،ن»¶مپŒéپµه®ˆمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹ç¶™ç¶ڑçڑ„مپ«ç›£è¦–مپ—مپ¾مپ™م€‚وٹ•è³‡ه®¶مپŒو،ن»¶مپ«éپ•هڈچمپ—مپںه ´هگˆم€په¤§è‡£مپ¯èھچهڈ¯م‚’هڈ–م‚ٹو¶ˆمپ—مپںم‚ٹم€پو–°مپںمپھو،ن»¶م‚’èھ²مپ—مپںم‚ٹم€پهژںçٹ¶ه›ه¾©م‚’ه‘½مپکمپںم‚ٹمپ™م‚‹ه¼·هٹ›مپھو¨©é™گم‚’وœ‰مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پو،ن»¶ن»کمپچèھچهڈ¯مپ¯م€پوٹ•è³‡ه®¶مپ«ن¼ڑ社و³•ن¸ٹمپ®ç¾©ه‹™مپ¨مپ®é–“مپ§ن؛ˆوœںمپ›مپ¬م‚³مƒ³مƒ•مƒھم‚¯مƒˆم‚’ç”ںمپکمپ•مپ›م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ن¼ڑ社و³•مپ¯م€پو ھن¸»م‚„هڈ–ç· ه½¹مپ«ه¯¾مپ—م€پن¼ڑ社مپ®هˆ©ç›ٹ(l’intأ©rأھt social)مپ«و²؟مپ£مپ¦è،Œه‹•مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’و±‚م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پو”؟ه؛œمپŒèھ²مپ—مپںو،ن»¶مپŒن¼ڑ社مپ®هˆ©ç›ٹمپ¨è،çھپمپ—مپںه ´هگˆم€پوٹ•è³‡ه®¶مپ¯مپ©مپ،م‚‰م‚’ه„ھه…ˆمپ™مپ¹مپچمپ‹مپ¨مپ„مپ†م‚¸مƒ¬مƒ³مƒمپ«é™¥م‚ٹمپ¾مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پ雇用ç¶وŒپم‚„特ه®ڑوٹ€è،“مپ®مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ه›½ه†…ç¶وŒپمپ¨مپ„مپ£مپںو”؟ه؛œمپ®و،ن»¶مپŒم€پن؛‹و¥مپ®هگˆçگ†و€§م‚„ن¼ڑ社مپ®هˆ©ç›ٹمپ«هڈچمپ™م‚‹ه ´هگˆم€پو”؟ه؛œمپ®و،ن»¶م‚’ه„ھه…ˆمپ—مپںçµگوœم€پن¼ڑ社و³•ن¸ٹمپ®ç¾©ه‹™éپ•هڈچمپ¨مپ—مپ¦è¨´è¨ںمپ®ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚‹مƒھم‚¹م‚¯مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ•م‚‰مپ«م€پéپژه؛¦مپھو”؟ه؛œمپ®ن»‹ه…¥مپ¯م€په¤–ه›½وٹ•è³‡ه®¶مپŒه¯¾è±،ن¼ڑ社مپ®م€Œن؛‹ه®ںن¸ٹمپ®çµŒه–¶è€…م€چمپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم€پن¼ڑ社مپ®ه‚µه‹™مپ«ه¯¾مپ—مپ¦ه€‹ن؛؛çڑ„مپھ責ن»»م‚’ه•ڈم‚ڈم‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§م‚‚ç”ںمپکه¾—مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پFDIه¯©وں»مپŒهچکمپھم‚‹و‰‹ç¶ڑمپچن¸ٹمپ®مƒڈمƒ¼مƒ‰مƒ«مپ§مپ¯مپھمپڈم€پوٹ•è³‡ه¾Œمپ®م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹مپ¨و³•çڑ„مƒھم‚¹م‚¯مپ«مپ¾مپ§و·±مپڈه½±éں؟م‚’هڈٹمپ¼مپ™مپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپ¨م‚پ
وœ¬ç¨؟مپ§مپ¯م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ«مپٹمپ‘م‚‹ه¤–ه›½ç›´وژ¥وٹ•è³‡ه¯©وں»هˆ¶ه؛¦مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پمپمپ®و³•çڑ„و ¹و‹ م€پوœ€و–°مپ®هˆ¶ه؛¦ه¤‰و›´م€پمپٹم‚ˆمپ³و—¥وœ¬مپ®ه¤–ç‚؛و³•مپ¨مپ®و±؛ه®ڑçڑ„مپھéپ•مپ„م‚’解èھ¬مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®FDIه¯©وں»مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®م€Œن؛‹ه‰چه±ٹه‡؛مƒ»é»™ç¤؛مپ®ç„،ç•°è°م€چمپ¨مپ¯ç•°مپھم‚ٹم€په¤§è‡£مپ®وکژç¤؛çڑ„مپھم€Œن؛‹ه‰چèھچهڈ¯م€چم‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ—م€پوœںé™گه†…مپ®ç„،ه›ç”مپ¯م€Œé»™ç¤؛مپ®و‹’هگ¦م€چمپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم‚‹و¥µم‚پمپ¦هژ³و ¼مپھهˆ¶ه؛¦مپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€پç½°ه‰‡مپ¯و—¥وœ¬مپ®هˆ¶ه؛¦مپ¨و¯”較مپ—مپ¦مپ¯م‚‹مپ‹مپ«هژ³مپ—مپڈم€پç„،èھچهڈ¯وٹ•è³‡مپ¯و³•çڑ„مپ«ç„،هٹ¹مپ¨مپھم‚‹مƒھم‚¹م‚¯م‚’ن¼´مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€په¯©وں»ه¯¾è±،هˆ†é‡ژمپ¯هœ°و”؟ه¦çڑ„ç·ٹه¼µم‚„وٹ€è،“é©و–°م‚’背و™¯مپ«ç¶™ç¶ڑçڑ„مپ«و‹،ه¤§مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پèھچهڈ¯ه¾Œمپ®م‚³مƒ³مƒ—مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³م‚¹é †ه®ˆم‚‚هژ³و ¼مپ«ç›£è¦–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ن¼پو¥مپ¸مپ®M&Aم‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹éڑ›م€پهڈ–ه¼•مپ®هˆوœںو®µéڑژمپ§FDIه¯©وں»مپ®è¦پهگ¦م‚’هˆ¤و–مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¯م€پهڈ–ه¼•مپ®وˆگهگ¦مپ¨م‚؟م‚¤مƒ مƒ©م‚¤مƒ³م‚’ه·¦هڈ³مپ™م‚‹وœ€م‚‚é‡چè¦پمپھè¦پç´ مپ§مپ™م€‚ه¯¾è±،ن¼پو¥مپ®ن؛‹و¥ه†…ه®¹مپŒو©ںه¾®هˆ†é‡ژمپ«è©²ه½“مپ™م‚‹مپ‹هگ¦مپ‹مپ®هˆ¤و–مپ«ن¸چç¢؛ه®ںو€§مپŒمپ‚م‚‹ه ´هگˆمپ¯م€پç©چو¥µçڑ„مپ«ه¤§è‡£مپ¸مپ®ن؛‹ه‰چ相談(مƒ¬م‚¹م‚¯مƒھ)م‚’و±‚م‚پم‚‹مپ¹مپچمپ§مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پFDIه¯©وں»مپ¯م€پهگˆن½µه¯©وں»مپھمپ©مپ®ن»–مپ®è¦ڈهˆ¶و‰‹ç¶ڑمپچمپ¨ن¸¦è،Œمپ—مپ¦é€²م‚پم‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚هگ„و‰‹ç¶ڑمپچمپ®م‚؟م‚¤مƒ مƒ©م‚¤مƒ³م‚’و£ç¢؛مپ«وٹٹوڈ،مپ—م€په…¨ن½“مپ®م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«م‚’ç¶؟ه¯†مپ«ç®،çگ†مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
م‚«مƒ†م‚´مƒھمƒ¼: ITمƒ»مƒ™مƒ³مƒپمƒ£مƒ¼مپ®ن¼پو¥و³•ه‹™