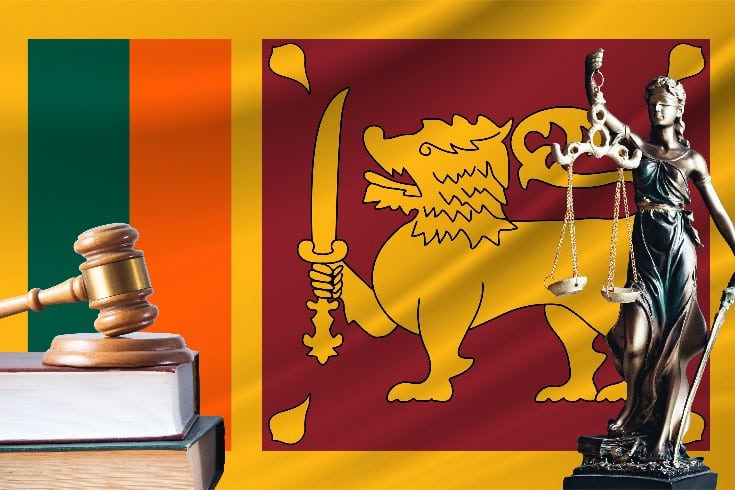гғүгӮӨгғ„гҒ§гҒ®еҘ‘зҙ„жӣёдҪңжҲҗгғ»дәӨжёүжҷӮгҒ«е•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮӢж°‘жі•гғ»еҘ‘зҙ„жі•

гғүгӮӨгғ„гҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁе…ұйҖҡзӮ№гҒҢеӨҡгҒ„дёҖж–№гҒ§гҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®йҒӢз”ЁгӮ„иЈҒеҲӨжүҖгҒ®д»Ӣе…Ҙеҹәжә–гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжұәе®ҡзҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгғүгӮӨгғ„ж°‘жі•е…ёпјҲBГјrgerliches Gesetzbuch, BGBпјүгҒ«гҒқгҒ®ж №жӢ гӮ’зҪ®гҒҸеҘ‘зҙ„жі•гҒҜгҖҒгҖҢдҝЎзҫ©иӘ е®ҹгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгӮ’е„Әи¶Ҡзҡ„гҒӘеҖ«зҗҶеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҺіж јгҒ«йҒ©з”ЁгҒ—гҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®иҮӘз”ұгӮ’еј·гҒҸзөұеҲ¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®зөұеҲ¶гҒ®жңҖгҒҹгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒдјҒжҘӯгҒҢдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢзҙ„ж¬ҫгӮ„еҲ©з”ЁиҰҸзҙ„гӮ’еҺігҒ—гҒҸеҜ©жҹ»гҒҷгӮӢдёҖиҲ¬еҸ–еј•жқЎд»¶пјҲAllgemeine GeschГӨftsbedingungen, AGBпјүгҒ®иҰҸеҲ¶гҒ§гҒҷгҖӮAGBиҰҸеҲ¶гҒҜгҖҒдјҒжҘӯй–“еҸ–еј•пјҲB2BпјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е•Ҷж…Јзҝ’гҒ§ж…ЈдҫӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиІ¬д»»еҲ¶йҷҗжқЎй …гӮ„жҗҚе®іиі е„ҹгҒ®еҲ¶йҷҗжқЎй …гҒҢгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҜз„ЎеҠ№гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢйқһеёёгҒ«й«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒBGBгҒ®еЈІиІ·жі•гҒҜгҖҒз‘•з–өгҒӮгӮӢиЈҪе“ҒгҒ®гҖҢеҸ–еӨ–гҒ—гғ»еҶҚиЁӯзҪ®иІ»з”ЁгҖҚгӮ’еЈІдё»гҒ«зҫ©еӢҷзҡ„гҒ«иІ жӢ…гҒ•гҒӣгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгӮөгғ—гғ©гӮӨгғӨгғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдәҲжңҹгҒӣгҒ¬еӨ§гҒҚгҒӘиІЎеӢҷгғӘгӮ№гӮҜгӮ’иӘІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҘ‘зҙ„дёҠгҒ®и«ӢжұӮжЁ©гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒҢгҖҒжЁҷжә–гҒ§3е№ҙй–“пјҲеЈІиІ·гҒ®з‘•з–өгҒҜ2е№ҙй–“пјүгҒЁжҜ”ијғзҡ„зҹӯгҒ„дёҠгҖҒгҒқгҒ®иө·з®—зӮ№гҒ«гҖҢе№ҙжң«иө·з®—гҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзү№ж®ҠгҒӘгғ«гғјгғ«гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжЁ©еҲ©гҒ®з®ЎзҗҶгҒ«гҒҜзҙ°еҝғгҒ®жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҺіж јгҒӘжі•з’°еўғгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҘ‘зҙ„гғҶгғігғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжҘөгӮҒгҒҰеҚұйҷәгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзү№гҒ«AGBиҰҸеҲ¶гҒ«гӮҲгӮӢиІ¬д»»еҲ¶йҷҗжқЎй …гҒ®з„ЎеҠ№еҢ–гғӘгӮ№гӮҜгҖҒBGHеҲӨдҫӢгҒҢзӨәгҒҷгҖҢгҒҝгҒӘгҒ—еҗҢж„ҸгҖҚгҒ®дёҚжҲҗз«ӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰз‘•з–өжӢ…дҝқиІ¬д»»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҸ–еӨ–гҒ—гғ»еҶҚиЁӯзҪ®иІ»з”ЁиІ жӢ…гҒ®жӢЎеӨ§гҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•зү№жңүгҒ®ж§ӢйҖ зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘжҲҰз•ҘгҒЁз¶ҝеҜҶгҒӘж–ҮжӣёеҢ–гҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғүгӮӨгғ„еҘ‘зҙ„жі•гҒ®дё»иҰҒгҒӘи«–зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢдәӢеүҚгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒеҜҫзӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢгҒ№гҒҚгғӘгӮ№гӮҜгҒЁе®ҹеӢҷдёҠгҒ®жіЁж„ҸзӮ№гӮ’и©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғүгӮӨгғ„еҘ‘зҙ„жі•гҒ®еҹәжң¬еҺҹеүҮгҒЁеҘ‘зҙ„иҮӘз”ұгҒёгҒ®еҲ¶зҙ„
гғүгӮӨгғ„еҘ‘зҙ„жі•гҒҜгҖҒBGBгӮ’жҲҗж–Үжі•дёҠгҒ®дёӯеҝғгҒ«жҚ®гҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®жҲҗз«ӢгҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҢз”іиҫјгҒҝгҖҚгҒЁгҖҢжүҝи«ҫгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдәҢгҒӨгҒ®ж„ҸжҖқиЎЁзӨәгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҸЈй ӯгҒ§гҒ®еҗҲж„ҸгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮжі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҘ‘зҙ„иҮӘз”ұгҒ®иЎҢдҪҝгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е•Ҷж…Јзҝ’гӮҲгӮҠгӮӮеј·гҒ„еҖ«зҗҶзҡ„еҺҹеүҮгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дҝЎзҫ©иӘ е®ҹгҒ®еҺҹеүҮпјҲTreu und Glauben, В§ 242 BGBпјүгҒ®йҒ©з”Ё
гғүгӮӨгғ„жі•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®жҲҗз«ӢгҒӢгӮүеұҘиЎҢгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒе…ЁгҒҰгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢе„Әи¶Ҡзҡ„гҒӘеҖ«зҗҶеҺҹеүҮгҒҢгҖҒBGB В§242 гҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢдҝЎзҫ©иӘ е®ҹгҒ®еҺҹеүҮгҖҚпјҲTreu und GlaubenпјүгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒҜгҖҒгҖҢеӮөеӢҷиҖ…гҒҜгҖҒдҝЎзҫ©иӘ е®ҹеҸҠгҒіеҸ–еј•ж…Јзҝ’гӮ’ж–ҹй…ҢгҒ—гҒҰгҖҒзөҰд»ҳгӮ’гҒӘгҒҷгҒ№гҒҚзҫ©еӢҷгӮ’иІ гҒҶгҖҚгҒЁе®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҢдҝЎзҫ©иӘ е®ҹгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҒ®жҰӮеҝөгҒҜж„Ҹеӣізҡ„гҒ«жӣ–жҳ§гҒ•гӮ’ж®ӢгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢжі•е®ҡгҒ®ж–ҮиЁҖгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚе…¬е№ігҒӘзөҗжһңгӮ’жӢӣгҒҸе ҙеҗҲгҒ«гҖҒжі•еүөйҖ зҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҖҒеҘ‘зҙ„гҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„д»ҳйҡҸзҫ©еӢҷгӮ„иІ¬д»»гӮ’еҪ“дәӢиҖ…гҒ«иӘІгҒҷгҒ“гҒЁгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒӮгӮӢгҒӢгӮүе…ЁгҒҰгҒҢе®ҲгӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҗҲзҗҶзҡ„гҒӘеҪ“дәӢиҖ…гҒҢеҖ«зҗҶзҡ„гҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгӮӢиЎҢеӢ•еҹәжә–пјҲзӣёжүӢж–№гҒ®еҲ©зӣҠгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҹиЎҢеӢ•пјүгҒҢеёёгҒ«иҰҒжұӮгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒ®йҒ©з”ЁзҜ„еӣІгҒҢеәғзҜ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ§гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҠҖиЎ“зҡ„гҒӘеҘ‘зҙ„йҒ•еҸҚгҒ®жңүз„ЎгӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҖҒгҖҢе…¬жӯЈжҖ§гҖҚгҒЁгҖҢеҖ«зҗҶзҡ„й…Қж…®гҖҚгҒҢеёёгҒ«е•ҸгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е–„иүҜгҒӘйўЁдҝ—гҒ«еҸҚгҒҷгӮӢеҘ‘зҙ„гҒ®з„ЎеҠ№пјҲSittenwidrigkeit, В§ 138 BGBпјү
BGB В§138 гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®еҶ…е®№гҒҢзӨҫдјҡзҡ„гҒӘеҖ«зҗҶгӮ„йҒ“еҫіпјҲе–„иүҜгҒӘйўЁдҝ—гҖҒSittenwidrigkeitпјүгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®жі•еҫӢиЎҢзӮәгӮ’з„ЎеҠ№гҒЁе®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢе–„иүҜгҒӘйўЁдҝ—гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҜгҖҒиӢұзұіжі•гҒ®гҖҢе…¬еәҸгҖҚгӮ„гҖҢдёҚйҒ“еҫігҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҰӮеҝөгӮҲгӮҠгӮӮи‘—гҒ—гҒҸеәғзҜ„гҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒ®дёҖж–№гҒҢд»–ж–№гҒ®гҖҢеӣ°зӘ®гҖҒзөҢйЁ“дёҚи¶ігҖҒеҲӨж–ӯеҠӣгҒ®ж¬ еҰӮгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜж„ҸжҖқгҒ®и‘—гҒ—гҒ„ејұгҒ•гҖҚгӮ’дёҚеҪ“гҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒгҖҢз•°еёёгҒ«йҮҚгҒ„иІ жӢ…гҖҚгӮ’дёҖж–№зҡ„гҒ«иӘІгҒҷгӮҲгҒҶгҒӘеҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒдёҚйҒ“еҫігҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰз„ЎеҠ№гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғүгӮӨгғ„гҒ®жҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒж°‘дәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒВ§138 гӮ„ В§242 гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҖиҲ¬жқЎй …гӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢз§Ғзҡ„иҮӘжІ»гҒ®еҹәжң¬жЁ©гҖҚгӮ’йҒөе®ҲгҒ—гҒӨгҒӨгӮӮгҖҒдёҖж–№гҒ®еҪ“дәӢиҖ…гҒ«гҖҢз•°еёёгҒ«йҮҚгҒ„иІ жӢ…гҖҚгӮ’иӘІгҒҷеҘ‘зҙ„еҶ…е®№гӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’е‘ҪгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдәӨжёүеҠӣгҒ®ж је·®гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰжҘөз«ҜгҒ«дёҚе…¬е№ігҒӘжқЎд»¶гӮ’жҠјгҒ—д»ҳгҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲзҪІеҗҚгҒ•гӮҢгҒҹеҘ‘зҙ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз„ЎеҠ№еҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„дёҖиҲ¬еҸ–еј•жқЎд»¶пјҲAGBпјүгҒ®зөұеҲ¶

дјҒжҘӯгҒҢиӨҮж•°гҒ®еҘ‘зҙ„гҒ§е®ҡеһӢзҡ„гҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒдҪңжҲҗгҒ—гҒҹзҙ„ж¬ҫгӮ„еҲ©з”ЁиҰҸзҙ„гҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•гҒ®дёӢгҒ§гҒҜдёҖиҲ¬еҸ–еј•жқЎд»¶пјҲAllgemeine GeschГӨftsbedingungen, AGBпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒBGB §§305 д»ҘдёӢгҒ«гӮҲгӮӢйқһеёёгҒ«еҺіж јгҒӘеҜ©жҹ»гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе®ҡеһӢзҙ„ж¬ҫгҒ®иҰҸеҲ¶гӮҲгӮҠгӮӮгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҢж јж®өгҒ«й«ҳгҒ„зӮ№гҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
AGBгҒ®е®ҡзҫ©гҒЁгҖҢеҖӢеҲҘеҗҲж„ҸгҖҚпјҲIndividualabredeпјүгҒ®иЁјжҳҺ
гҒӮгӮӢжқЎй …гҒҢAGBгҒЁиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢе®ҡеһӢеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҖҒгҖҢиӨҮж•°гҒ®еҘ‘зҙ„гҒ§дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢж„ҸеӣігҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҢеҖӢеҲҘдәӨжёүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҚгҒ®дёүгҒӨгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷе ҙеҗҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲеҘ‘зҙ„жӣёгӮ’еҖӢеҲҘгҒ«дәӨгӮҸгҒ—гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ®жқЎй …гҒҢе®ҡеһӢеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгғҶгғігғ—гғ¬гғјгғҲгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзңҹгҒ®дәӨжёүгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®жқЎй …гҒҜAGBгҒЁиӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
AGBгҒ®еҺіж јгҒӘиҰҸеҲ¶гӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҖҒжқЎй …гҒ®жңүеҠ№жҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢе”ҜдёҖгҒ®зўәе®ҹгҒӘж–№жі•гҒҜгҖҒгҒқгҒ®жқЎй …гҒҢеҖӢеҲҘдәӨжёүгҒ•гӮҢгҒҹеҗҲж„ҸпјҲIndividualabredeпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮеҖӢеҲҘеҗҲж„ҸгҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҖҒгҒқгҒ®з«ӢиЁјиІ¬д»»гҒҜеёёжҷӮAGBгҒ®дҪҝз”ЁиҖ…еҒҙпјҲдјҒжҘӯеҒҙпјүгҒҢиІ гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- дәӨжёүж„ҸжҖқгҒ®жҳҺзӨәпјҡжқЎй …гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзңҹгҒ«дәӨжёүгӮ’иЎҢгҒҶж„ҸжҖқгӮ’зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҖӮ
- еӨүжӣҙгҒ®зҸҫе®ҹзҡ„гҒӘж©ҹдјҡпјҡзӣёжүӢж–№еҪ“дәӢиҖ…гҒҢгҖҒжқЎй …гҒ®еӨүжӣҙгӮ’жҸҗжЎҲгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жҸҗжЎҲгҒҢжңҖзөӮеҘ‘зҙ„гҒ«зө„гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгӮӢзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘж©ҹдјҡгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгғүгӮӨгғ„еҗ‘гҒ‘гҒ®еҘ‘зҙ„жӣёгӮ’иө·иҚүгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒиІ¬д»»еҲ¶йҷҗгӮ„дҝқиЁјгҒӘгҒ©йҮҚиҰҒгҒӘгғӘгӮ№гӮҜй…ҚеҲҶжқЎй …гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰAGBиҰҸеҲ¶гӮ’йҒҝгҒ‘гҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒдәӨжёүйҒҺзЁӢгҒ§зӣёжүӢж–№гҒӢгӮүгҒ®жҸҗжЎҲгӮ’зө„гҒҝиҫјгӮ“гҒ гӮҠгҖҒдәӨжёүгҒ®иӯ°дәӢйҢІгӮ„йӣ»еӯҗгғЎгғјгғ«гӮ’з¶ҝеҜҶгҒ«ж–ҮжӣёеҢ–гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
B2BеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҶ…е®№еҜ©жҹ»гҒ®еҺіж јжҖ§
BGB В§310 гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„зӣёжүӢгҒҢдәӢжҘӯиҖ…пјҲUnternehmerпјүгҒ§гҒӮгӮӢB2BеҸ–еј•гҒ®е ҙеҗҲгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®еҺігҒ—гҒ„зҰҒжӯўжқЎй …пјҲ§§308,309 BGBпјүгҒҜзӣҙжҺҘйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘзҰҒжӯўжқЎй …гҒ®гҖҢжі•зҡ„гҒӘеҹәжң¬жҖқжғігҖҚгӮ’гҖҒBGB В§307 гҒ®дёҖиҲ¬жқЎй …пјҲдҝЎзҫ©иӘ е®ҹгҒ®иҰҒжұӮгҒ«еҸҚгҒ—гҒҰеҘ‘зҙ„зӣёжүӢгҒ«дёҚеҗҲзҗҶгҒӘдёҚеҲ©зӣҠгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„пјүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒB2BеҸ–еј•гҒ®AGBеҜ©жҹ»гҒ«йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гӮ’еј·гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒB2BеҘ‘зҙ„гҒ®AGBгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢиІ¬д»»еҲ¶йҷҗжқЎй …гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒж•…ж„ҸпјҲVorsatzпјүгҖҒйҮҚйҒҺеӨұпјҲGrobe FahrlГӨssigkeitпјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиІ¬д»»гҒ®еҲ¶йҷҗгҒҜз„ЎеҠ№гҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®йҒ©еҲҮгҒӘеұҘиЎҢгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒӘдёӯж ёзҡ„зҫ©еӢҷпјҲKardinalpflichtпјүгҒ®йҒ•еҸҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҚҳзҙ”гҒӘйҒҺеӨұпјҲeinfache FahrlГӨssigkeitпјүгҒ«гӮҲгӮӢиІ¬д»»гӮӮгҖҒйҖҡеёёдәҲиҰӢеҸҜиғҪгҒӘе…ёеһӢзҡ„гҒӘжҗҚе®ігҒ®зҜ„еӣІгӮ’и¶…гҒҲгҒҰеҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
з„ЎеҠ№гҒӘAGBжқЎй …гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгҖҢжңүеҠ№жҖ§з¶ӯжҢҒзҡ„жёӣзё®гҖҚгҒ®еҗҰе®ҡ
ж—Ҙжң¬гҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒ§гҒҜгҖҒз„ЎеҠ№гҒӘжқЎй …гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®и¶Јж—ЁгӮ’жҙ»гҒӢгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«еҸҜиғҪгҒӘзҜ„еӣІгҒ§жңүеҠ№гҒӘйғЁеҲҶгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢи§ЈйҮҲгҒ®дҪҷең°гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғүгӮӨгғ„жі•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢжңүеҠ№жҖ§з¶ӯжҢҒзҡ„жёӣзё®гҖҚпјҲgeltungserhaltende ReduktionгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгғ–гғ«гғјгғҡгғігӮ·гғ«гғ»гғ«гғјгғ«пјүгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
AGBгҒ®жқЎй …гҒҢгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°йҖҸжҳҺжҖ§гӮ’ж¬ гҒҸгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ§з„ЎеҠ№гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®жқЎй …е…ЁдҪ“гҒҢе®Ңе…ЁгҒ«еҘ‘зҙ„гҒӢгӮүжҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«BGBгҒ®жі•е®ҡиҰҸе®ҡгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒҢж„ҸеӣігҒ—гҒҹиІ¬д»»дёҠйҷҗгҒҢе®Ңе…ЁгҒ«ж¶Ҳж»…гҒ—гҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬з„ЎеҲ¶йҷҗгҒ®жі•е®ҡиІ¬д»»пјҲйҖёеӨұеҲ©зӣҠгӮ’еҗ«гӮҖпјүгӮ’иІ гҒҶгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒAGBгҒ®иө·иҚүжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒз„ЎеҠ№еҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒзү№гҒ«жіЁж„ҸгӮ’жү•гҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
AGBгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢгҒҝгҒӘгҒ—еҗҢж„ҸжқЎй …гҖҚгҒ®з„ЎеҠ№еҢ–
гғүгӮӨгғ„йҖЈйӮҰиЈҒеҲӨжүҖпјҲBGHпјүгҒҜгҖҒ2021е№ҙ4жңҲ27ж—ҘгҒ®еҲӨжұәгҖҒгҒҠгӮҲгҒі2024е№ҙ11жңҲ19ж—ҘгҒ®еҲӨжұәпјҲXI ZR 139/23пјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҠҖиЎҢгҒ®AGBгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖҒеҘ‘зҙ„жқЎд»¶гӮ„ж–ҷйҮ‘гҒ®еӨүжӣҙгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒйЎ§е®ўгҒҢдёҖе®ҡжңҹй–“еҶ…гҒ«з•°иӯ°гӮ’иҝ°гҒ№гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«еҗҢж„ҸгҒ—гҒҹгҒЁгҖҢгҒҝгҒӘгҒҷгҖҚжқЎй …пјҲZustimmungsfiktionsklauselkпјүгӮ’гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒЁгҒ®еҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜз„ЎеҠ№гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
BGHгҒҜгҖҒйЎ§е®ўгҒҢеҚҳгҒ«еҸЈеә§гӮ’з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒҢгҖҒеҘ‘зҙ„жқЎд»¶гҒ®еӨүжӣҙгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҗҢж„ҸгҒ®ж„ҸжҖқиЎЁзӨәгҒЁгҒҜиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁжҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨж–ӯгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®жҲҗз«ӢгӮ„еӨүжӣҙгҒ«гҒҜгҖҒBGBгҒ®еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰдёЎеҪ“дәӢиҖ…гҒ®жҳҺзўәгҒӘж„ҸжҖқиЎЁзӨәпјҲеҗҢж„ҸпјүгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гӮ’еј·иӘҝгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№иҰҸзҙ„гҒӘгҒ©гҒ§еәғгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖҢгҒҝгҒӘгҒ—еҗҢж„ҸгҖҚгҒ®гғӯгӮёгғғгӮҜгҒҢгғүгӮӨгғ„жі•гҒ®дёӢгҒ§гҒҜйҖҡз”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеЈІиІ·еҘ‘зҙ„гҒ®з‘•з–өжӢ…дҝқиІ¬д»»гҒЁж•‘жёҲ
гғүгӮӨгғ„еЈІиІ·жі•пјҲBGB §§433 ff.пјүгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢз‘•з–өжӢ…дҝқиІ¬д»»гҒ®дҪ“зі»гҒҜгҖҒиІ·дё»гҒ®ж•‘жёҲжүӢж®өгҒ«иЎҢдҪҝгҒ®й ҶеәҸпјҲйҡҺеұӨпјүгӮ’иӘІгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒЁгҖҒеЈІдё»гҒ®иІ»з”ЁиІ жӢ…гҒҢжӢЎеӨ§гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢзү№гҒ«жіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жі•е®ҡжӢ…дҝқиІ¬д»»пјҲGewГӨhrleistungпјүгҒЁеҘ‘зҙ„дёҠгҒ®дҝқиЁјпјҲGarantieпјү
гғүгӮӨгғ„жі•гҒ§гҒҜгҖҒжі•е®ҡгҒ®з‘•з–өиІ¬д»»гӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢжӢ…дҝқиІ¬д»»пјҲGewГӨhrleistungпјүгҒЁгҖҒеЈІдё»гҒҢд»»ж„ҸгҒ§зү№е®ҡгҒ®е“ҒиіӘгӮ„иҖҗд№…жҖ§гӮ’зҙ„жқҹгҒҷгӮӢеҘ‘зҙ„дёҠгҒ®дҝқиЁјпјҲGarantieпјүгҒҢжҳҺзўәгҒ«еҢәеҲҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮиӢұиӘһгҒ®гҖҢWarrantyгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүдёЎж–№гҒ«зҝ»иЁігҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёдёҠгҒ§жӣ–жҳ§гҒӘиЎЁзҸҫгӮ’дҪҝгҒҶгҒЁгҖҒеЈІдё»гҒҢж„ҸеӣігҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеҺігҒ—гҒ„иІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶGarantieгҒЁи§ЈйҮҲгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
GewГӨhrleistungгҒҜгҖҒеЈІдё»гҒ®йҒҺеӨұгӮ’е•ҸгӮҸгҒҡгҖҒеј•гҒҚжёЎгҒ—жҷӮзӮ№гҒ§ж¬ йҷҘгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶе®ўиҰізҡ„дәӢе®ҹгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮгҒ«гҒҜйҖҡеёёгҖҒеЈІдё»гҒ®йҒҺеӨұпјҲж•…ж„ҸгҒҫгҒҹгҒҜйҒҺеӨұпјүгҒҢиҰҒжұӮгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒGarantieгҒҜгҖҒзҙ„жқҹгҒ•гӮҢгҒҹзү№жҖ§гҒҢж¬ гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹе ҙеҗҲгҖҒйҒҺеӨұгҒ®жңүз„ЎгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡеЈІдё»гҒҢеҺіж јиІ¬д»»гӮ’иІ гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж•‘жёҲжүӢж®өгҒ®йҡҺеұӨгҒЁеұҘиЎҢгҒ®иҝҪе®ҢпјҲNacherfГјllungпјүгҒ®е„Әе…Ҳ
иІ·дё»гҒҢз‘•з–өгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒBGB В§437 гҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒгҒҫгҒҡеұҘиЎҢгҒ®иҝҪе®ҢпјҲNacherfГјllungпјүгӮ’еЈІдё»гҒ«и«ӢжұӮгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеұҘиЎҢгҒ®иҝҪе®ҢгҒ«гҒҜгҖҒж¬ йҷҘгҒ®йҷӨеҺ»пјҲдҝ®зҗҶпјүгҒҫгҒҹгҒҜж¬ йҷҘгҒ®гҒӘгҒ„д»Јжӣҝе“ҒгҒ®еј•жёЎгҒ—гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮ’гҖҒиІ·дё»гҒҢйҒёжҠһгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҢеұҘиЎҢгҒ®иҝҪе®ҢгҖҚгҒҢеӨұж•—гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒеЈІдё»гҒҢжӢ’еҗҰгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒ®гҒҝгҖҒиІ·дё»гҒҜеҲқгӮҒгҒҰеҘ‘зҙ„и§ЈйҷӨгҖҒд»ЈйҮ‘жёӣйЎҚгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜжҗҚе®іиі е„ҹгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдәҢж¬Ўзҡ„гҒӘж•‘жёҲжүӢж®өгҒ«йҖІгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеЈІдё»гҒ«ж¬ йҷҘгӮ’жҳҜжӯЈгҒҷгӮӢж©ҹдјҡгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҖҢдәҢж¬Ўзҡ„еұҘиЎҢгҒ®жЁ©еҲ©гҖҚгҒҢгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•гҒ§гҒҜеј·еҲ¶зҡ„гҒ«е„Әе…ҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ–еӨ–гҒ—гҒҠгӮҲгҒіеҶҚиЁӯзҪ®иІ»з”ЁпјҲBGB В§439(3)пјү
зү№гҒ«йғЁе“ҒдҫӣзөҰгӮ„е»әиЁӯй–ўйҖЈгҒ®B2BеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒ2018е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹBGB В§439(3) гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иҰҸе®ҡгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж¬ йҷҘгҒ®гҒӮгӮӢе•Ҷе“ҒгҒҢиІ·дё»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж—ўгҒ«д»–гҒ®иЈҪе“ҒгҒ«иЁӯзҪ®гҒҫгҒҹгҒҜзө„гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒеЈІдё»гҒҜгҖҒгҒқгҒ®ж¬ йҷҘе“ҒгӮ’еҸ–гӮҠеӨ–гҒ—гҖҒдҝ®зҗҶгҒҫгҒҹгҒҜдәӨжҸӣгҒ•гӮҢгҒҹе•Ҷе“ҒгӮ’еҶҚиЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зҷәз”ҹгҒҷгӮӢе…ЁгҒҰгҒ®иІ»з”ЁгӮ’иІ жӢ…гҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгӮ’иІ гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иІ»з”ЁиІ жӢ…зҫ©еӢҷгҒҜгҖҒеЈІдё»гҒ®йҒҺеӨұгҒ®жңүз„ЎгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҖҒж¬ йҷҘгҒ«еҹәгҒҘгҒҸеј·еҲ¶зҡ„гҒӘиІ¬д»»гҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдҪҺеҚҳдҫЎгҒ®йғЁе“ҒгҒҢжңҖзөӮиЈҪе“ҒгҒ«зө„гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҒҹеҫҢгҒ«ж¬ йҷҘгҒҢзҷәиҰҡгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒйғЁе“ҒгӮөгғ—гғ©гӮӨгғӨгғјгҒҜгҖҒйғЁе“ҒгҒ®дҫЎж јгӮ’йҒҘгҒӢгҒ«и¶…гҒҲгӮӢеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘи§ЈдҪ“гғ»еҶҚиЁӯзҪ®гҒ®гғӯгӮёгӮ№гғҶгӮЈгӮҜгӮ№гҒҠгӮҲгҒідәә件費гӮ’иІ гҒҶгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘеҘ‘зҙ„гғүгғ©гғ•гғҶгӮЈгғігӮ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®еј·еҲ¶зҡ„гҒӘиІ»з”ЁиІ жӢ…гӮ’AGBгҒ§жҺ’йҷӨгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒз„ЎеҠ№гҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒдҫЎж јиЁӯе®ҡгӮ„гғӘгӮ№гӮҜгғһгғјгӮёгғігҒ®иЁҲз®—гҒ«гҒ“гҒ®жҪңеңЁзҡ„гҒӘгӮігӮ№гғҲгӮ’еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҗҚе®іиі е„ҹгҒ®ж§ӢйҖ гҒЁиІ¬д»»еҲ¶йҷҗгҒ®йҷҗз•Ң

гғүгӮӨгғ„гҒ®жҗҚе®іиі е„ҹжі•пјҲBGB §§249 ff.пјүгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„йҒ•еҸҚгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӘгӮүгҒ°еӯҳеңЁгҒ—гҒҹгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶзҠ¶ж…ӢгҒ«иў«е®іиҖ…гӮ’еӣһеҫ©гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢеҺҹзҠ¶еӣһеҫ©гҒ®еҺҹеүҮгҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҺҹеүҮгҒҜгҖҒйҖёеӨұеҲ©зӣҠпјҲВ§252 BGBпјүгҒ®иЈңе„ҹгӮӮеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢзӮ№гҒ§гҖҒеәғзҜ„гҒӘйҒ©з”ЁгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢй–“жҺҘжҗҚе®ігҖҚжқЎй …гҒ®дҝЎй јжҖ§гҒ®дҪҺгҒ•
гӮігғўгғігғӯгғјжі•еҹҹгҒ§дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖҢй–“жҺҘжҗҚе®ігҖҚпјҲindirect lossпјүгӮ„гҖҢзөҗжһңзҡ„жҗҚе®ігҖҚпјҲconsequential lossпјүгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•пјҲBGB §§249 ff.пјүгҒ§гҒҜе…¬ејҸгҒ«е®ҡзҫ©гӮӮдҪҝз”ЁгӮӮгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒAGBгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢй–“жҺҘжҗҚе®ігҖҒйҖёеӨұеҲ©зӣҠгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдәӢжҘӯдёӯж–ӯжҗҚеӨұгӮ’е…ЁгҒҰжҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘеҲ¶йҷҗжқЎй …гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з”ЁиӘһгҒҢгғүгӮӨгғ„жі•дёӢгҒ§дёҚжҳҺзўәгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз„ЎеҠ№гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮжқЎй …гҒҢз„ЎеҠ№еҢ–гҒ•гӮҢгӮҢгҒ°гҖҒдјҒжҘӯгҒҜж„ҸеӣігҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе…ЁжҗҚе®ійЎҚпјҲйҖёеӨұеҲ©зӣҠгӮ’еҗ«гӮҖпјүгӮ’иЈңе„ҹгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’иІ гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒиІ¬д»»гӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҖҢйҖёеӨұеҲ©зӣҠгҖҚгҖҒгҖҢдәӢжҘӯдёӯж–ӯгӮігӮ№гғҲгҖҚгҖҒгҖҢгҒ®гӮҢгӮ“гҒ®жҗҚеӨұгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒйҷӨеӨ–гҒ—гҒҹгҒ„е…·дҪ“зҡ„гҒӘжҗҚеӨұй …зӣ®гӮ’еҲ—жҢҷгҒ—гҒҰжҳҺзӨәзҡ„гҒ«жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒжі•зҡ„зўәе®ҹжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢдёҠгҒ§еҝ…й ҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёӯж ёзҡ„зҫ©еӢҷпјҲKardinalpflichtпјүйҒ•еҸҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҲ¶йҷҗ
AGBгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҚҳзҙ”гҒӘйҒҺеӨұпјҲeinfache FahrlГӨssigkeitпјүгҒ«гӮҲгӮӢиІ¬д»»гӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҘ‘зҙ„гҒ®ж №е№№гҒ«й–ўгӮҸгӮӢдёӯж ёзҡ„зҫ©еӢҷпјҲKardinalpflichtпјүгҒ®йҒ•еҸҚгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиІ¬д»»гӮ’е®Ңе…ЁгҒ«жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒиІ¬д»»гҒ®еҲ¶йҷҗгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®зЁ®йЎһгҒ«й‘‘гҒҝгҒҰдәҲиҰӢеҸҜиғҪгҒ§е…ёеһӢзҡ„гҒӘжҗҚе®ігҒ®иЈңе„ҹйЎҚгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӯж ёзҡ„зҫ©еӢҷгҒ«йҒ•еҸҚгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮөгғ—гғ©гӮӨгғӨгғјгҒҜеҘ‘зҙ„дҫЎеҖӨгӮ’йҒҘгҒӢгҒ«и¶…гҒҲгӮӢйҖёеӨұеҲ©зӣҠгӮ’иі е„ҹгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®жҰӮеҝөгӮ’еҘ‘зҙ„з· зөҗеүҚгҒ«еҫ№еә•зҡ„гҒ«еҲҶжһҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„гҒ®жҷӮеҠ№жңҹй–“пјҲVerjГӨhrungпјүгҒЁе№ҙжң«иө·з®—гҒ®еҺҹеүҮ
гғүгӮӨгғ„еҘ‘зҙ„жі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҷӮеҠ№пјҲVerjГӨhrung, §§194 ff. BGBпјүгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жңҹй–“гҒ®зҹӯгҒ•гҒЁиө·з®—зӮ№гҒ®зү№ж®ҠжҖ§гҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢи«ӢжұӮжЁ©гӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жЁҷжә–зҡ„гҒӘжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒЁгҖҢе№ҙжң«иө·з®—гҒ®еҺҹеүҮгҖҚ
BGB В§195 гҒҢе®ҡгӮҒгӮӢжЁҷжә–зҡ„гҒӘжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒҜ3е№ҙй–“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒЁжҜ”гҒ№гҒҰжҜ”ијғзҡ„зҹӯгҒ„жңҹй–“гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзү№ж®ҠжҖ§гҒҜгҖҒжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒ®иө·з®—зӮ№гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҖҢе№ҙжң«иө·з®—гҒ®еҺҹеүҮгҖҚпјҲNew Year’s Eve Limitation PeriodпјүгҒ§гҒҷгҖӮжЁҷжә–зҡ„гҒӘжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®дәҢгҒӨгҒ®жқЎд»¶гҒҢжәҖгҒҹгҒ•гӮҢгҒҹе№ҙгҒ®зөӮгӮҸгӮҠгҒ«й–Ӣе§ӢгҒҷгӮӢгҒЁиҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲBGB В§199(1)пјүгҖӮ
- и«ӢжұӮжЁ©гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҖӮ
- еӮөжЁ©иҖ…гҒҢи«ӢжұӮжЁ©зҷәз”ҹгҒ®зҠ¶жіҒгҒЁеӮөеӢҷиҖ…гҒ®иә«е…ғгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁпјҲгҒҫгҒҹгҒҜйҮҚйҒҺеӨұгҒӘгҒҸзҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁпјүгҖӮ
гҒ“гҒ®иҰҸеүҮгҒ®зөҗжһңгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҒӮгӮӢи«ӢжұӮжЁ©гҒҢе№ҙгҒ®еҲқгӮҒпјҲ1жңҲ1ж—ҘпјүгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒ®иө·з®—гҒҜгҒқгҒ®е№ҙгҒ®12жңҲ31ж—ҘгҒҫгҒ§еҫ…гҒӨгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒҢе®ҹиіӘзҡ„гҒ«жңҖй•·гҒ§гҒ»гҒј4е№ҙй–“гҒ«е»¶й•·гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷйғЁе“ЎгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®йҒ…延гҒ—гҒҹиө·з®—иҰҸеүҮгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒи«ӢжұӮжЁ©гҒ®жңҹйҷҗеҲҮгӮҢгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ®жӯЈзўәгҒӘгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°дҪ“еҲ¶гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еЈІиІ·еҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзү№еҲҘжҷӮеҠ№жңҹй–“
жЁҷжә–жңҹй–“гҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒзү№е®ҡгҒ®и«ӢжұӮжЁ©гҒ«гҒҜзү№еҲҘжңҹй–“гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- еЈІиІ·еҘ‘зҙ„гҒ®з‘•з–өгҒ«гӮҲгӮӢи«ӢжұӮжЁ©пјҡдёҖиҲ¬гҒ«2е№ҙй–“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе•Ҷе“ҒгҒ®еј•жёЎгҒ—жҷӮгҒ«иө·з®—гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- B2BеҸ–еј•гҒ®зҹӯзё®пјҡиІ·дё»гҒЁеЈІдё»гҒ®еҸҢж–№гҒҢдәӢжҘӯиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢB2BеҸ–еј•гҒ®е ҙеҗҲгҖҒAGBгҒ®иҰҸе®ҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®2е№ҙй–“гҒ®жңҹй–“гӮ’1е№ҙй–“гҒ«зҹӯзё®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиЁұе®№гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- е»әзү©гҒ®з‘•з–өпјҡе»әзү©гҒ®ж§ӢйҖ зү©гӮ„гҒқгҒ®ж¬ йҷҘгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҹжқҗж–ҷгҒ®з‘•з–өгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҷӮеҠ№жңҹй–“гҒҜ5е№ҙй–“гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дјҒжҘӯгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҜ”ијғзҡ„зҹӯгҒ„жҷӮеҠ№жңҹй–“гҒЁгҖҒAGBгҒ«гӮҲгӮӢзҹӯзё®гҒ®иЁұе®№жҖ§гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒеҘ‘зҙ„жӣёдёҠгҒ§жҷӮеҠ№жңҹй–“гӮ’жҳҺзўәгҒ«иҰҸе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒи«ӢжұӮжЁ©гҒ®з®ЎзҗҶгӮ’еҫ№еә•гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гғүгӮӨгғ„гҒ®ж°‘жі•гғ»еҘ‘зҙ„жі•гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„иҮӘз”ұгҒ®еҺҹеүҮгӮ’иӘҚгӮҒгҒӨгҒӨгӮӮгҖҒгҒқгҒ®иғҢеҫҢгҒ«гҒӮгӮӢгҖҢдҝЎзҫ©иӘ е®ҹгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгӮ„AGBиҰҸеҲ¶гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒзү№гҒ«иІ¬д»»еҲ¶йҷҗгӮ„з‘•з–өжӢ…дҝқиІ¬д»»гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҲ¶еәҰгӮҲгӮҠгӮӮеҺіж јгҒӢгҒӨжҹ”и»ҹгҒӘиЈҒеҲӨжүҖгҒ®д»Ӣе…ҘгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дјҒжҘӯгҒҢж…ЈдҫӢзҡ„гҒ«з”ЁгҒ„гӮӢиІ¬д»»еҲ¶йҷҗжқЎй …гӮ„гҖҢгҒҝгҒӘгҒ—еҗҢж„ҸгҖҚжқЎй …гҒҢгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®B2BеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮAGBеҜ©жҹ»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз„ЎеҠ№гҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬з„ЎеҲ¶йҷҗгҒ®жі•е®ҡиІ¬д»»пјҲйҖёеӨұеҲ©зӣҠгҖҒеҸ–еӨ–гҒ—гғ»еҶҚиЁӯзҪ®иІ»з”ЁгҒӘгҒ©пјүгҒ«зӣҙйқўгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҜжҘөгӮҒгҒҰй«ҳгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•зҡ„дәҲжё¬еҸҜиғҪжҖ§гҒ®дҪҺгҒ•гӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®иө·иҚүж®өйҡҺгҒ§гҖҒAGBгҒ®йҒ©з”ЁзҜ„еӣІгӮ’жӯЈзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒйҮҚиҰҒгҒӘгғӘгӮ№гӮҜй…ҚеҲҶжқЎй …гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзңҹгҒ®гҖҢеҖӢеҲҘеҗҲж„ҸгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒ§гҒҚгӮӢдәӨжёүеұҘжӯҙгӮ’и©ізҙ°гҒ«ж®ӢгҒҷгҒӘгҒ©гҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘеҜҫзӯ–гҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гғүгӮӨгғ„еёӮе ҙгҒ§гҒ®зўәе®ҹгҒӘжі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гҒЁгғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ®дәҲиҰӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ®BGBгҒҠгӮҲгҒіжңҖж–°гҒ®еҲӨдҫӢжі•пјҲBGHгҒ®еҲӨж–ӯгҒӘгҒ©пјүгҒ«е®Ңе…ЁгҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҹеҘ‘зҙ„дҪ“зі»гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…й ҲгҒ§гҒҷгҖӮгғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҜгҖҒиІҙзӨҫгҒ®гғүгӮӨгғ„гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдәӢжҘӯжҙ»еӢ•гҒҢжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жңҖе°ҸйҷҗгҒ«жҠ‘гҒҲгҖҒе …зүўгҒӘеҹәзӣӨгҒ®дёҠгҒ§еұ•й–ӢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒеҘ‘зҙ„жҲҰз•ҘгҒ®зӯ–е®ҡгҒӢгӮүж–ҮжӣёгҒ®ж•ҙеӮҷгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘгғӘгғјгӮ¬гғ«гӮөгғқгғјгғҲгӮ’жҸҗдҫӣгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ