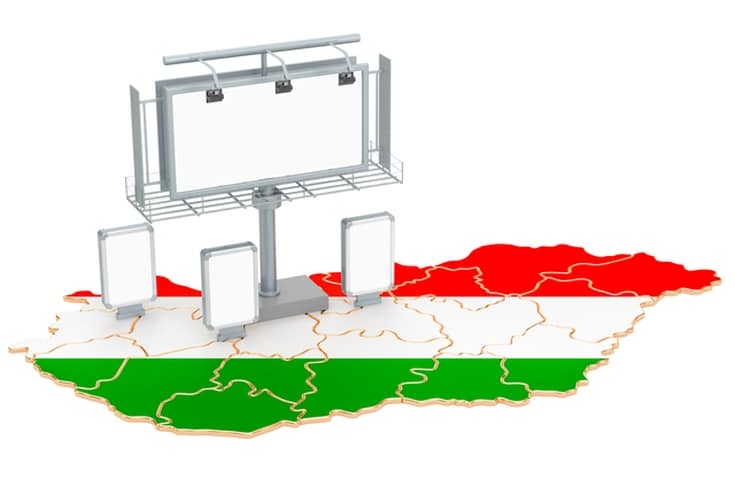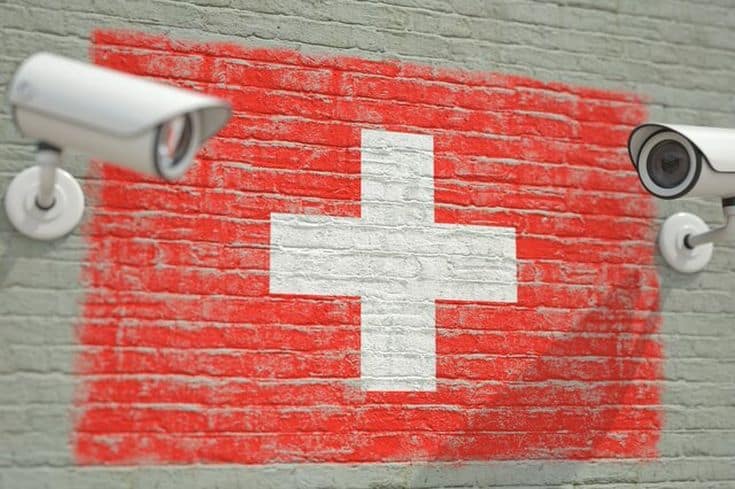ドイツ会社法の定める有限会社(GmbH)のコーポレートガバナンスと指示拘束性

ドイツの有限会社(GmbH)のコーポレートガバナンス構造は、日本企業が欧州でのビジネス展開を成功させるために非常に重要です。このガバナンスの最も重要な特徴であり、日本法との比較で際立つ相違点こそが、取締役(Geschäftsführer)が社員総会(Gesellschafterversammlung)の拘束力のある指示を受ける義務を負う「指示拘束性(Weisungsgebundenheit)」です。これはGmbHG第37条第1項に明確な根拠を持ち、経営判断の独立性を原則とする日本の株式会社(KK)やドイツのAGとは異なり、親会社による現地経営の完全掌握を可能にします。しかし、この強力な指示権は無制限ではありません。
Geschäftsführerは、会社債権者の保護を目的とする資本維持義務(GmbHG第30条第1項)や倒産申立義務といったドイツ法上の強行規定に基づく重大な固有の義務を負っています。これらの義務は社員の指示によって免除されることはなく、違反した場合、Geschäftsführerは会社への損害賠償責任に加え、背任罪や倒産隠蔽罪といった刑事罰に問われる深刻なリスクに直面します。したがって、日本本社がドイツ子会社を指揮する上で最も重要なのは、この指示拘束性の「強さ」と、それを打ち破る「限界」の法的境界線を正確に理解し、現地Geschäftsführerの個人的な法的リスクを最大限に低減させるための厳格な法的チェック体制を構築することにあります。この指示拘束性こそが、GmbHのコーポレートガバナンスの根幹をなす最重要キーワードとなります。
本記事では、GmbHの指示拘束性の定義と日本のKKとの違いを解説し、特に資本維持義務や倒産申立義務が親会社の指示権を制限する絶対的な限界となる構造を詳述します。これらの法的リスクを回避し、現地Geschäftsführerの個人責任を最小化するための実践的なガバナンスと危機管理の枠組みを提示します。
この記事の目次
ドイツのGmbHガバナンスと指示拘束性(Weisungsgebundenheit)
指示拘束性の法的定義とGmbHGの条文
ドイツの有限会社法(GmbHG)における指示拘束性は、GmbHという法人形態の根幹をなす統治構造の特徴であり、日本の会社法における一般的な株式会社の構造とは決定的に異なります。GmbHG第37条第1項は、Geschäftsführer(取締役)が、社員総会(Gesellschafterversammlung)の決議または会社定款によって定められた、会社の代表権限の範囲に関する制限を遵守する義務を会社に対して負うと明確に規定しています。
この法令の原文は以下の通りです。
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind.
GmbHG第37条第1項
この条文のいう「制限」(Beschränkungen)には、個別の業務執行に関する具体的かつ拘束力のある指示が含まれると広く解釈されています。社員総会は、GmbHG第46条に基づき、会社のあらゆる業務執行について決定を下す包括的な権限を有しており 、この包括的権限を背景に、Geschäftsführerに対し、事業戦略の決定から日常的な業務の進め方まで、広範な事項について指示を与えることが可能です。この指揮権は非常に強力であり、ドイツの法理においては、たとえその指示が客観的に見て会社にとって経済的に不利な行為を伴う場合であっても、社員はその指示を出す権限を持つことが認められています。
日本の株式会社(KK)取締役の立場との相違点
GmbHのこの指示拘束性の原則は、日本の会社法における株式会社(KK)の構造と比較すると、その特異性が際立ちます。日本の会社法では、KKの取締役は、株主総会に対して忠実義務を負いますが、経営判断については独立性を持ちます。原則として、株主総会から個別の業務執行行為について具体的かつ拘束力のある指示を受けることは許容されていません。取締役会は、代表取締役や業務執行取締役の職務執行の監督は行いますが(会社法第362条第2項第2号)、経営判断の責任は執行機関である取締役にあります。
この独立経営の原則は、ドイツの株式法(AktG)に基づく株式会社(AG)においても同様であり、AGの執行役員会(Vorstand)は、監査役会や株主総会から個別の業務執行について原則として指示を受けず、会社経営の独立した責任を負います。
したがって、GmbHの指示拘束性は、AGやKKが採用する「所有と経営の分離」に基づく独立した経営判断の原則を意図的に回避し、「所有と経営の同一性(または密接な結合)」を志向するものです。日本本社がドイツでAGではなくGmbHを選択する動機は、単に設立の容易さや低資本要件だけでなく、この指示拘束性により、本社(親会社=社員総会)が現地経営に直接介入し、迅速かつ一貫したグループポリシー(例えば、グループ内での資金移動や戦略的撤退)を実行できるように設計された統制モデルを求めている点にあります。この構造により、GmbHは、市場の規律や外部少数株主の保護よりも、グループ内の戦略的統制を最優先するガバナンスモデルを提供します。
| 日本:株式会社 | 日本:合同会社 | ドイツ:株式会社 (AG) | ドイツ:有限会社 (GmbH) | |
|---|---|---|---|---|
| 執行機関 | 取締役/代表取締役 | 業務執行社員 | Vorstand (執行役員会) | Geschäftsführer (取締役) |
| 監督機関 | 株主総会/取締役会 | 総社員 | Aufsichtsrat (監査役会)/株主総会 | Gesellschafterversammlung (社員総会) |
| 個別業務執行への指示 | 原則不可 (独立責任) | 原則可能 (定款/社員の決定による) | 原則不可 (独立責任) | 原則可能 (指示拘束性) |
ドイツGmbHのGeschäftsführerと日本の合同会社業務執行社員を比較
GmbHのGeschäftsführerの立場は、日本の会社法における合同会社の業務執行社員の立場に近いと理解することができます。
日本の合同会社は、持分会社の一つであり、内部自治の自由度が非常に高いことが特徴です。業務執行は原則としてすべての社員が行いますが、定款で特定の社員のみが業務執行社員となるよう定めることも可能です。合同会社では、出資者である社員が業務執行に直接関与し、その権限の範囲や業務執行社員への指示権限は、定款や社員間の合意に基づいて柔軟に設定されます。
GmbHのGeschäftsführerも、社員総会の決議 に基づく具体的な指示に従う義務があるため、その機能的な位置づけは、出資者(社員)が業務執行に対して直接的な決定権を持つ合同会社の業務執行社員に類似します。親会社が100%出資するGmbHの場合、親会社(唯一の社員)は、現地法人の業務執行を完全に掌握でき、本社の方針を迅速かつ確実に実行できます。これは、親会社が子会社(GmbH)という法人格の恩恵(社員の有限責任 )を享受しつつ、実質的に持分会社に近いレベルの統制を確保できるという点で、日本本社にとって運用上の極めて大きなメリットをもたらします。
しかし、後に詳述するように、GmbHのGeschäftsführerは、日本の合同会社の業務執行社員とは異なり、ドイツ法上の強行規定に基づく非常に厳格な個人責任を負うという点で、その法的リスクは決定的に異なります。
ドイツGeschäftsführerの固有の義務と指示の絶対的限界

指示拘束性の原則は、あくまで社員とGeschäftsführer間の内部関係(会社に対する義務)に関するものですが、ドイツ法には、会社債権者などの第三者の利益を保護するための強行規定が存在します。これらの強行規定に抵触する社員の指示は法的に無効となり、Geschäftsführerはそれに従う義務を負わず、むしろ拒否する義務が生じます。
資本維持義務(Kapitalerhaltungspflicht)の厳格な適用
Geschäftsführerが負う固有の義務の中でも最も基本的なものが、GmbHG第30条第1項に定められた資本維持義務です。
法令原文のコア規定は「Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden.」(会社の資本維持に必要な財産は、社員に払い戻されてはならない。)です。この規定は、会社の最低資本(Stammkapital)を維持するために必要な資産の流出を厳しく禁止しており、その適用範囲は、単なる現金の配当や払い戻しに限定されません。親会社に対する不当な価格での資産売却、過大なサービス料の支払い、または会社財産を減少させるあらゆる種類の行為が、資本維持規定の違反(verbotene Auszahlung)として扱われます。例外的に、支配・利益移転契約が存在する場合や、社員に対する完全な価値を持つ対価または返還請求権がある場合にのみ、この禁止規定の対象外となります。
社員総会からの指示であっても、このGmbHG第30条第1項に違反し、会社の資本維持に必要な財産を社員に流出させる行為を伴う場合、当該指示は法的に無効です。 ドイツの連邦通常裁判所(BGH)の確立された判例法理によれば、社員の同意や指示があったとしても、資本維持規定に違反する行為は、Geschäftsführerの会社に対する財産保全義務(Vermögensbetreuungspflicht)の違反となり、その責任は免除されません。親会社がグループ内の戦略を優先し、子会社に不当な指示を出した場合、その指示を盲目的に実行するGeschäftsführerは、会社の債権者保護という上位の目的を無視したとして、会社に対する損害賠償責任を負うことになります。
義務違反によるGeschäftsführerの個人責任と刑事罰
GmbHのGeschäftsführerは、強行規定に違反した場合、民事責任に留まらず、極めて重い刑事責任を負う可能性があります。
- 民事上の責任:資本維持義務を含む善管注意義務に違反し会社に損害が生じた場合、Geschäftsführerは会社に対し損害賠償責任を負います(GmbHG第43条第2項)。
- 刑事罰のリスク(背任罪): Geschäftsführerは、会社の法定代表者として、会社の財産を管理・保護する義務を負います。社員の指示によるものであっても、資本維持規定に違反し、会社に財産上の損害を与える行為は、ドイツ刑法(StGB)上の背任罪(Untreue)の構成要件を充足する可能性があります。これは、懲役刑を含む刑事罰の対象となり得る深刻なリスクです。
倒産申立義務(Insolvenzantragspflicht)と経営危機の報告義務
本維持義務と並び、Geschäftsführerにとって最も危険な義務が倒産関連の義務です。
会社が支払不能(Zahlungsunfähigkeit)または債務超過(Überschuldung)の状態に陥った場合、Geschäftsführerは、倒産法(§ 15a InsO)に基づき、遅滞なく、原則としてこれらの状態が発生してから3週間以内 に、裁判所に倒産手続きの開始を申し立てる義務(倒産申立義務)を負います。
さらに、Geschäftsführerには、会社の資本金(Stammkapital)の半額の損失が発生した場合、遅滞なく社員に対し報告する義務(GmbHG第84条)も課されており、この報告義務の不履行も、刑事罰の対象となり得ます。
これらの義務に違反した場合、深刻な結果を招きます。まず、民事上の責任として、倒産申立てを遅延または怠った場合、Geschäftsführerは、倒産発生後に会社が行った支払いについて、会社(または管財人)に対して賠償責任を負います。連邦通常裁判所(BGH)は、倒産発生後の支払いに関するGeschäftsführerの責任の原則を繰り返し確認しています(BGH, Hinweisbeschluss vom 24. September 2019, Az. II ZR 248/17など)。また、刑事上の責任も発生し、倒産申立ての遅延や不履行は、倒産隠蔽罪(Insolvenzverschleppung)として、ドイツ法により厳しく罰せられます。
したがって、指示の限界(Insolvenzreife)として、倒産状態下で親会社からの指示が特定の債権者(特に親会社自身)への優先的な返済など、違法な支払いを強いる場合、Geschäftsführerはこれを拒否しなければなりません。指示拘束性は平時における強力な統制ツールですが、危機に瀕した瞬間、親会社が自己の利益を優先する指示を出すと、その実行者であるGeschäftsführerが個人責任を負うため、指示を拒否せざるを得なくなります。これは、親会社による統制強化の試みが、危機に際して現地Geschäftsführerの個人責任という形で跳ね返ってくる構図であると言えます。
ドイツ判例法理が定める指示拒否権の基準
経済的に不利な指示の許容と「倒産危険性」の境界線
ドイツの法理は、社員総会が会社の経済的成功を追求する義務を負わないという前提に立っています。社員総会は、会社財産の私的な処分権限を持つため、Geschäftsführerは、社員が会社にとって客観的に不利な、または不合理と思われるビジネス判断に関する指示を出しても、原則としてそれに従う義務を負います。これは、株主が会社の経済的命運を最終的に決定する権限を持つという考えに基づいています。
しかし、指示拒否権が発生する絶対的な法的境界線は、その指示の実行が、資本維持義務などの強行規定に違反するか、または「greifbar naheliegend die Gefahr eines Konkurses droht」(明らかに倒産の危険が差し迫っている)場合にあります。
この境界線に関して、フランクフルト高等裁判所(OLG Frankfurt a.M.)は1997年2月7日の判決(Az. 24 U 88/95)において、事業方針に関する指示の合法性について見解を示しています。同判決は、たとえ税務上の理由で利益を海外に不当に(あるいは客観的に不利な形で)移転する意図を持つ指示であっても、それが直ちに拘束力を失うわけではないと述べつつも、その指示が会社の倒産を差し迫って引き起こす危険がある場合には、Geschäftsführerは指示を拒否できることを示唆しています。これは、社員の指示権も、会社の存続と会社債権者の保護という基本的な要件を覆すことは許されないというドイツ会社法の根本原則を反映しています。
親会社指示に基づく資本維持規定違反に対するBGHの立場
親会社からの指示が、GmbHG第30条や倒産法(InsO)に抵触する可能性がある場合、Geschäftsführerは非常に厳しい判断を迫られます。
連邦通常裁判所(BGH)は、Geschäftsführerが会社の危機的状況下で債権者保護の義務を怠った場合の責任について、その原則を厳格に維持しています。例えば、倒産申立義務発生後に、社員である親会社の指示に従い、その親会社にのみ返済を行った場合、これは他の債権者を不当に害する行為となり、Geschäftsführerは会社に対する損害賠償責任を負います。社員の指示に従ったという事実は、強行規定違反を正当化せず、責任を免除する根拠とはなりません。
実務上の教訓として、日本本社がグループ全体の戦略を優先し、現地法人の資産を流用するような指示を出す場合、その指示の実行者であるGeschäftsführerは、指示を直ちにドイツ法の専門家に提示し、強行規定違反のリスクがないかを確認しなければなりません。確認せずに実行した場合、責任はGeschäftsführer個人に帰属するため、現地法人を率いるGeschäftsführerは、親会社にとって都合が良い指示であっても、その合法性を常に判断し、違法性がある場合は拒否する法的義務があります。
日本本社がドイツ進出において取るべきガバナンスとリスク管理
親会社による統制の合法的な範囲の理解
親会社は、GmbHの指示拘束性というメリットを享受しつつ、法的リスクを回避するために、統制の合法的な範囲を厳密に定義し、運用する必要があります。
まず、親会社からの指示は、GmbHGやその他のドイツ法(税法、労働法など)の強行規定に抵触しない範囲内でなければなりません。特に、グループ内取引や資金移動の指示を行う際には、リスク管理が不可欠です。親会社への配当やサービス料の支払いが資本維持規定(GmbHG第30条)に違反しないよう、常に適正な対価(vollwertigen Gegenleistungs)が存在することを保証し、Geschäftsführerが会社財産の毀損を引き起こさないように配慮する必要があります。
また、Geschäftsführerが負う情報提供義務の履行を確実にするため、親会社は現地子会社に対し、透明性の高い財務報告体制を義務付ける必要があります。GmbHG第84条に基づき、資本金(Stammkapital)の半額の損失が発生した場合、Geschäftsführerには遅滞なく社員へ報告する義務があるため 、日本本社は、この報告義務が適切に履行できるよう、迅速な財務・法務チェック体制を現地に整備し、Geschäftsführerをサポートすることが重要です。
危機的状況発生時の情報共有と迅速な対応策
倒産リスクが差し迫った状況においては、Geschäftsführerの法的義務が極限まで高まるため、親会社は迅速な行動をとれるよう準備しておく必要があります。
支払不能または債務超過の兆候が見られた場合、Geschäftsführerは倒産申立義務の期限(原則3週間)を遵守しなければ、即座に刑事責任リスクに直面します。親会社は、このような兆候が確認された場合、現地Geschäftsführerに対し、全ての業務執行を停止し、直ちに外部の倒産法に精通した法律専門家や税理士に相談するプロトコル(取り決め)を事前に確立しておくべきです。
危機的状況下では、親会社からの指示がGeschäftsführer個人の責任を問う引き金とならないよう、全ての指示は、ドイツ法の専門家の意見を付記した上で必ず書面で行い、強行規定に違反しないことを確認しなければなりません。
そして、倒産申立義務の発生そのものを防ぐために、親会社は、即座に債務超過を解消できるだけの資本増強(増資、または債務の劣後化や免除など)の実行準備をしておくことが、Geschäftsführerの刑事罰リスクを回避する上で最も効果的な手段となります。
まとめ
ドイツGmbHの「指示拘束性」は、日本本社による現地子会社の業務執行の徹底的な統制を可能にする、極めて戦略的なメリットを持つ制度です。この指示拘束性の存在により、GmbHのコーポレートガバナンスは、「所有と経営の分離」よりも「所有者(社員)による経営の直接統制」に重点を置く独自の形態をとります。親会社は、この制度を通じて、日本の合同会社に近い柔軟なガバナンス体制を実現できます。しかし、その強力な指示権は、Geschäftsführerが会社債権者保護のために負う強行的な義務、特に資本維持義務(GmbHG第30条第1項)および倒産申立義務(InsO)によって厳しく制限されています。
日本本社がドイツ子会社を指揮する上での法的リスク管理の核心は、この指示の自由度と、Geschäftsführer個人の法的な義務との間のバランスを理解し、資本維持規定に抵触するような指示を絶対に出さないことです。Geschäftsführerが強行規定に違反する指示に従った場合、その責任は免除されず、会社に対する損害賠償のみならず、背任や倒産隠蔽といった重い刑事罰に問われるリスクがあります。
モノリス法律事務所では、ドイツ法の専門知識に基づき、このGmbH特有のコーポレートガバナンス構造の下で、日本本社がドイツ子会社に対して合法的な統制権を行使し、かつ現地Geschäftsführerの法的リスクを最小限に抑えるためのガバナンス構築、指示系統の策定、および危機管理体制の整備についてサポートいたします。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務