EUの薬機法制と欧州医薬品庁(EMA)による中央審査方式(Centralised Procedure)

ヨーロッパは、世界有数の規模を誇る医薬品市場であり、日本の製薬企業にとって重要な事業機会を提供しています。しかし、この巨大市場に参入するためには、欧州連合(EU)の複雑な規制フレームワークを正確に理解し、遵守する必要があります。その中心に位置するのが、単一の承認でEU加盟国全体での販売を可能にする欧州医薬品庁(EMA)による中央審査方式(Centralised Procedure)です。この制度を深く理解することは、欧州事業戦略を策定し、製品上市までのタイムラインを正確に予測し、潜在的な法務リスクを管理する上で不可欠な要素となります。
本記事は、EMA中央審査方式の法的根拠、詳細な審査プロセス、および現在のEU医薬品規制改革の動向を包括的に解説します。さらに、日本の医薬品医療機器総合機構(PMDA)の審査制度とPMD Act(医薬品医療機器等法)の最新改正点を踏まえた上で、両者の制度を多角的に比較します。この比較分析を通じて、欧州市場参入における課題と機会を明確にし、実践的かつ将来を見据えた知見を提供することを目的とします。
この記事の目次
EUの医薬品規制の概要
欧州医薬品庁(EMA)と中央審査方式の概要
EMA中央審査方式の根幹をなすのは、Regulation (EC) No 726/2004です。このEU規制は、ヒト用および動物用医薬品の承認と監督に関する統一的な手続きを確立することを目的としています。この規制に基づき、1995年に設立されたEMA(欧州医薬品庁)は、EUおよび欧州経済領域(EEA)における医薬品の科学的評価と安全監視を担う機関として機能しています。
中央審査方式では、企業はEMAに対して単一のマーケティング承認申請(MAA)を提出します。EMAがその科学的評価を完了した後、最終的な法的拘束力を持つ承認決定を下すのは欧州委員会(European Commission:EC)です。この二段階構造は、科学的評価の独立性を確保しつつ、政治的決定との分離を図るという重要な特徴を持っています。一度欧州委員会によって承認が下されると、その効力はEU加盟国全体に及び、各国の個別承認手続きが不要となります。
中央審査方式は、特定の医薬品に対してその利用が義務付けられています。これには、バイオテクノロジー由来製品、遺伝子治療や細胞治療などの先進的治療薬(ATMPs)、オーファン薬(希少疾病用医薬品)、そしてAIDS、がん、神経変性疾患、糖尿病の治療を目的とする医薬品が含まれます。これらの製品は、その革新性や社会的・技術的な重要性から、EU全体で一貫した高水準の評価を受けることが求められています。
一方、上記に該当しない医薬品であっても、新たな有効成分を含むもの、または重要な治療上・科学的・技術的革新をもたらすものは、中央審査を選択することが可能です。これは、企業がEU全体での迅速な市場参入を目指す上で、戦略的な選択肢を提供しています。
審査プロセスとタイムラインの詳細
中央審査方式の審査プロセスは、厳格に定められたタイムラインに沿って進行します。企業は、製品の品質、安全性、有効性に関する詳細なデータを含むMAAをEMAに提出することから始まります。
申請が受理されると、EMAの医薬品委員会(Committee for Medicinal Products for Human Use:CHMP)が科学的評価を開始します。CHMPはEU加盟国からの代表者で構成されており、共同で申請書類を審査します。この評価の「アクティブ」な期間は通常210日と定められています。
このプロセスにおいて、特に重要な概念が「クロックストップ」です。これは、CHMPが申請書類の審査を通じて生じた疑問点や懸念事項について、申請企業に質問リストを送付した際に、210日のカウントダウンが一時的に停止する期間を指します。第1のクロックストップは通常3ヶ月、第2のクロックストップは1ヶ月とされ、この期間中に企業は質問に対する回答を準備します。この期間は単なる手続き上の遅延ではなく、企業がEMAの懸念に十分対応するための不可欠な機会であり、その後のプロセスをスムーズに進める上で戦略的に利用されるべきものです。
CHMPは審査期間の最後に、承認の可否に関する科学的意見(Opinion)を採択します。この意見は、審査報告書とともに欧州委員会に送付され、欧州委員会はCHMPの勧告を受けてから67日以内に最終的な法的承認決定を下します。
単なる手続き上のガイドラインをはるかに超えた、中央審査方式における実務上の成功要因は、この審査プロセスにおける企業と当局間の継続的な対話にあります。MAAの提出は始まりに過ぎず、その後の審査期間中にCHMPから寄せられる質問に、いかに迅速かつ的確に対応できるかが成功の鍵を握ります。これには、技術的な専門知識に加え、EUのClinical Trials Regulation (CTR) などの法規制要件を深く理解した上で、EMAとの継続的な対話(pre-submission meetingsやscientific adviceなど)を通じて戦略的なコミュニケーションを維持することが不可欠です。日本の企業が欧州市場でこのプロセスを円滑に進めるためには、単に申請書を作成するだけでなく、欧州の法務・薬事専門家との緊密な連携体制を構築し、審査期間を通じて能動的な対話を継続することが極めて重要となります。これを怠ると、審査の遅延や、最悪の場合には申請の拒否という結果を招くリスクが高まります。
EMA中央審査方式の課題と医薬品法改正(2023年提案)
EUの医薬品規制は現在、過去20年間で最大規模の改革の真っただ中にあります。2023年4月に欧州委員会が提示した新法案の目的は、「3つのA」、すなわちAffordability(負担可能性)、Accessibility(アクセス可能性)、Availability(入手可能性)を向上させ、医薬品をより多くの患者に迅速に届けることで、この提案は2025年9月現在も三者協議中です。
この改革は、EU域内の製薬業界から大きな懸念を招いています。欧州製薬団体連合会(EFPIA)は、新法案が知的財産権(IP)保護期間を大幅に短縮する可能性があり、その結果として欧州の研究開発(R&D)と競争力が損なわれ、イノベーションの拠点が米国やアジアに移転するリスクがあると指摘しています。また、アンメットメディカルニーズ(UMN)の定義や、サプライチェーンの要件が不釣り合いであるとの批判も上がっています。
この改革の動向は、単に既存のルールを修正するだけでなく、医薬品の知的財産保護を、EU全体での患者アクセス向上や、アンメットメディカルニーズへの対応といった特定の社会的目標を達成するための「インセンティブ」として再定義しようとするものです。これにより、欧州での事業モデル全体が根本的に再考を迫られることになります。
例えば、IP保護期間の削減は、研究開発投資の回収計画に直接的な影響を及ぼし、医薬品不足への対応として提案されたEU域内での製造能力強化を目指すCritical Medicines Act は、サプライチェーン戦略の見直しを促します。これらの変化は、法務部門と事業部門が一体となって、新たな課題に対処する必要があることを示唆しています。
新法案は、2024年4月に欧州議会が、そして2025年6月4日には欧州理事会がそれぞれ自らの交渉立場を採択しました。これにより、現在は欧州委員会、欧州議会、欧州理事会の3者による「三者協議(trilogue)」が進行しており、最初の協議は2025年6月17日に開催されました。最終的な法案の採択は、この協議の結果次第で、2026年後半から2027年半ばになると予測されています。日本の企業は、この不安定な規制環境を継続的に監視し、事業戦略への影響を綿密に分析することが不可欠です。
日本の審査制度の概観
日本の医薬品規制の中心は、厚生労働省(MHLW)と連携する独立行政法人である医薬品医療機器総合機構(PMDA)です 。PMDAは、医薬品、医療機器、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保することを責務としており、その機能は米国FDAや英国MHRAなど、他国の規制当局と多くの点で類似しています 。PMDAの医薬品承認審査は、薬学や医学など多様な専門分野のレビュー担当者からなるチームによって行われ、迅速審査制度も設けられています 。近年、医薬品の品質管理違反や深刻な供給不足といった課題に対応するため、2025年5月14日に医薬品医療機器等法(PMD Act)の改正法が成立しました。この改正は、供給安定性の強化や研究開発の促進を柱としており、次のセクションでEUの制度と詳しく比較します 。
EU中央審査方式と日本法の比較
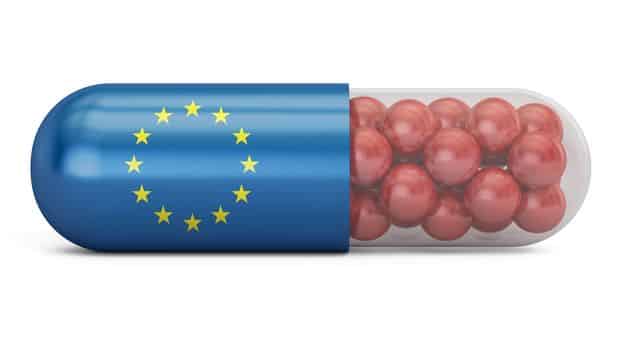
承認権限と意思決定構造の比較
EUと日本とでは、医薬品の承認に関する意思決定構造に根本的な違いがあります。EUでは、科学的評価を行うEMA(CHMP)と、法的承認決定を行う欧州委員会(EC)という二段階の階層構造が採用されています。この構造は、専門家による厳密な科学的評価と、EU全体での承認を決定する政治的・行政的権限の分離を意味しています。
一方、日本は、PMDAが科学的評価を行い、その結果に基づき厚生労働大臣が最終的な承認判断を下すという、一元化された構造をとっています。この違いは、企業の承認戦略に影響を与えます。欧州では、EMAの科学的評価(CHMPの意見)が承認プロセスの中心ですが、最終的な承認決定には欧州委員会の判断が伴うため、科学的側面だけでなく、EUの行政プロセス全体への理解が不可欠となります。
迅速審査・条件付き承認制度の比較と課題
EUと日本はともに、アンメットメディカルニーズが高い製品に対して、迅速な承認を可能にする制度を設けています。しかし、両者の制度には、法的な構造と実務上の強制力において決定的な差異が存在します。
日本の再生医療等製品に対する「期限付き条件付き承認」制度は、予測される有効性と安全性が確認できた場合に、期限を区切って承認を与えるものです。この制度の最もユニークな特徴は、設定された期限内に企業が標準承認を取得できない場合、承認が自動的に失効する点です。この「自動失効」という法的なメカニズムは、企業に市販後義務の履行を強制する非常に強力な手段として機能します。
対照的に、EUの条件付き承認(Conditional Approval)には、このような明確な「期限付き」の自動失効条項は存在しません。過去の報告によれば、EUでは条件付き承認を受けた医薬品の3分の1以上で、市販後義務の不履行や遅延が報告されています。この事実は、EUの制度が、より柔軟な監視と行政的な対応に依存しており、市場撤退の判断がより複雑になる可能性があることを示唆しています。
このような規制アプローチの哲学的差異は、企業が市販後の義務をいかに履行するかという戦略に直接影響します。日本の「期限付き」制度は、企業が市販後研究義務を確実に履行することを法的に担保しようとする、リスク管理を重視したアプローチと言えます。一方、EUの制度は、より柔軟な運用を許容する半面、企業側の自律的な義務履行に依存する度合いが強いと言えます。したがって、日本の企業がEU市場に進出する際には、日本の経験がEUでの市販後義務履行の甘さにつながるリスクを認識し、承認後も継続的な規制当局とのコミュニケーションと市販後データの収集に十分なリソースを投じる戦略を立てる必要があります。
製造・流通(サプライチェーン)に関する規制の比較
EUの中央審査方式は、単一の承認でEU全体での販売を可能にしますが、これはあくまで「販売できる権利」を付与するものです。医薬品の価格決定と償還決定は、各EU加盟国の国家レベルで個別に決定されます。このプロセスは、各国の医療制度や財政状況によって異なり、数ヶ月から数年を要することもあります。日本企業にとって、EMAの承認タイムラインとは別に、各国の価格・償還交渉という大きな「見えない壁」が存在することを理解することが重要です。このため、欧州市場への参入戦略は、EMA承認申請の計画だけでなく、主要なターゲット国(例えばドイツやフランス、イタリアなど)での価格・償還交渉の戦略を同時に立案する必要があると言えます。
近年、医薬品供給の安定性確保は、EUと日本の両方で規制の最重要課題の一つとなっています。EUでは、Critical Medicines Actの提案により、EU域内での製造能力強化やサプライチェーンの脆弱性軽減を目指しています。日本でも、2025年PMD Act改正で、供給管理責任者の設置や出荷停止報告の義務化といった具体的な措置を導入し、供給安定性への企業の責任を強化しています。両者とも医薬品供給不足を喫緊の課題と認識し、法的な手段でサプライチェーンへの介入を強めている点で共通しています。
知的財産権(IP)保護と研究開発インセンティブ
EUの医薬品法改革の新法案は、知的財産権(IP)保護のあり方を根本的に見直すものです。提案された制度では、データ保護期間などの基本期間が短縮される一方、特定の条件(例えば、全EU加盟国での早期上市や、特定のアンメットメディカルニーズへの対応など)を満たすことで、期間が延長される仕組みが導入されています。これは、従来のIP保護がほぼ自動的に与えられる権利であったのに対し、IP保護を「インセンティブ」として再定義し、特定の行動を企業に促すためのツールとして用いる、より複雑で動的なモデルへの移行を意味します。日本の企業は、欧州でのIP戦略を単に特許期間の最大化として捉えるだけでなく、新法案が求める社会的目標(患者アクセス、供給安定性)に合致するよう、事業戦略全体を再構築する必要に迫られる可能性があります。
EUのEMAと日本のPMDAの連携
EUと日本は、規制の国際調和に向けた協力を長年にわたり進めています。その代表的な例が、医薬品の製造管理および品質管理の基準(GMP)に関する相互承認協定(MRA)です。この協定により、両当局は互いのGMP査察結果を信頼し、相手国への製品輸出入時にバッチ試験を免除することができます。これは、サプライチェーンの効率化とコスト削減に大きく貢献します。
また、両機関は2007年から機密情報共有の取り決め(Confidentiality Arrangement)を結んでおり、法規文書、市販後安全性データ、査察報告書などを共有することで、規制の透明性と効率性を高めています。さらに、フェローシッププログラムを通じた短期の職員交換や、特定の治療領域や特殊なトピックに関して定期的に開催される「クラスター」と呼ばれる電話会議により、専門家間の相互理解とベストプラクティスの共有が図られています。
これらの連携は、単なる友好協定にとどまるものではありません。GMPのMRAは、製造・流通のコストと時間を削減する具体的なメリットを企業にもたらします。また、機密情報共有やクラスター活動は、両当局の審査基準や考え方を徐々に収斂させ、結果として、両地域での申請戦略の調和を可能にしています。これにより、日本企業はグローバルな開発戦略を立案する際に、EUと日本を別個の市場としてではなく、より統合された市場として捉え、重複した臨床開発を避け、リソースを効率的に配分できる可能性が高まっています。
まとめ
EUのEMA中央審査方式と日本のPMDAの審査制度は、それぞれ異なる法的・行政的枠組みに基づいて構築されています。EUの制度は、科学的評価と政治的承認を分離する二段階構造であり、単一の承認で広範な市場へのアクセスを可能にします。一方、日本の制度は、PMDAと厚生労働省が一元的に審査を進める構造であり、特に再生医療等製品に対する「期限付き」の条件付き承認制度は、市販後義務の履行を強力に強制する点で独自の強制力を持っています。
日本の企業が欧州市場で成功するためには、これらの制度的な違いを深く理解することが不可欠です。単にEMAの承認を得るだけでなく、その後の各EU加盟国での価格・償還交渉というハードルを越えるための戦略を早期に立案しなければなりません。
現在、EUでは医薬品法の抜本的な改革が進行中であり、今後は知的財産保護のあり方やサプライチェーンの要件が大きく変更される可能性があります。日本の企業は、この不確実な規制環境を注視し、知的財産権の保護が特定の社会的目標の達成と連動する新たな「インセンティブモデル」に備える必要があります。
両機関の継続的な連携、特にGMPの相互承認や情報共有の枠組みは、日本企業にとって大きな機会を提供します。これらの協力を最大限に活用し、欧州と日本での開発・申請戦略を可能な限り調和させることで、リソースの効率化と新製品の迅速な市場投入を図るべきです。法務・経営の両部門が、これらの国際的な規制動向を継続的に分析し、事業戦略に反映させることで、グローバルな競争力を維持し、強化していくことが求められます。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務


































