ルクセンブルク大公国の会社法が定めるコーポレートガバナンス
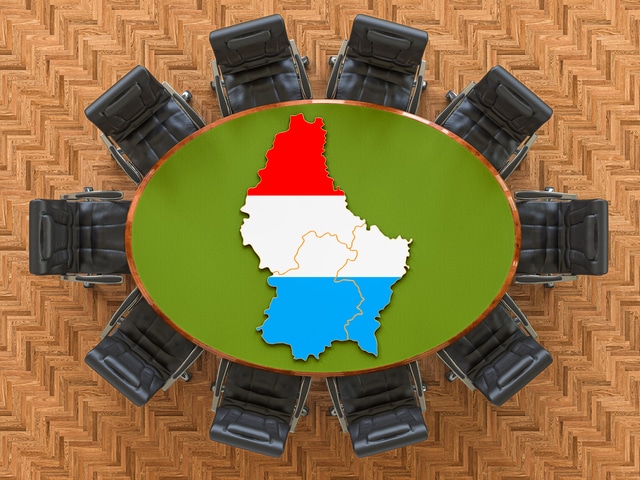
ルクセンブルクは、その政治的安定性、洗練された法的枠組み、そして欧州の中心という地理的優位性から、国際的なビジネス、特に投資ファンドや持株会社(SOPARFI)の設立拠点として揺るぎない地位を確立しています。日本企業がこの地で事業を展開し、その恩恵を最大限に享受するためには、ルクセンブルクのコーポレートガバナンスに関する深い理解が不可欠です。ルクセンブルクの会社法は、日本のそれと類似する基本的な考え方を持つ一方で、進出企業が予期せぬリスクに直面する可能性のある重要な違いも存在します。
本記事では、ルクセンブルクの法体系を紐解き、特に注意すべきガバナンス上の重要ポイント、すなわち役員の居住地要件と税務上の「実態」の関係、および有限会社(SàRL)に固有の監査義務について、専門的な視点から詳細に解説します。
なお、ルクセンブルクの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ルクセンブルクの主要な会社形態
ルクセンブルクでは、日本企業が事業を行う上で主に選択肢となる会社形態として、株式会社に相当するSociété anonyme(SA)と、有限会社に相当するSociété à responsabilité limitée(SàRL)の2つがあります。特にSàRLは、ルクセンブルク国内で設立されている全企業の約3分の2を占める、最も一般的な会社形態です。SAは株式を公開できるのに対し、SàRLは非公開が前提であるという点で大きく異なります。
SAは、日本の株式会社と同様に、株主の責任がその出資額に限定されるという利点があります。SàRLも同様に有限責任の会社形態ですが、SAよりも設立要件が緩やかなため、中小企業にとって魅力的な選択肢となります。
ルクセンブルクSA(株式会社)のガバナンス
SAのコーポレートガバナンスは、日本の会社法にはない柔軟な機関設計を特徴とします。具体的には、単一の取締役会を持つ「一元的構造」(monistic structure / one-tier structure)と、経営と監督を分離した二つの機関を持つ「二元的構造」(dualistic structure / two-tier structure)のいずれかを選択することができます。
一元的構造(単一取締役会)
ルクセンブルクのSAにおいて最も一般的に採用されているのが、この一元的構造です。単一の取締役会(Board of Directors)が、会社の経営と運営に対して全責任を負い、戦略的な方向性を決定します。
日本の会社法における取締役会設置会社と似た構造ですが、決定的に異なるのは、取締役会に執行役員(Executive Directors)と非執行役員(Non-Executive Directors)が混在することです。非執行役員は、経営陣から独立した立場で監督機能を果たします。この仕組みは、執行と監督の分離が曖昧になるという懸念点も指摘される一方、非執行役員が経営の詳細な情報に早期かつ深く関与できるため、より実効的な監督が可能になるという利点があります。
取締役会の権限は極めて広範であり、法令または定款で株主総会に専属的に留保された事項を除き、会社の利益のためにあらゆる行為を行うことができます。日本の会社法では、取締役会の権限が法律で詳細に定められているのに対し、ルクセンブルクでは取締役会の裁量がより広いと言えるでしょう。
二元的構造(経営委員会・監査委員会)
二元的構造は、ドイツなど欧州大陸の他国で一般的なシステムであり、ルクセンブルクではあまり採用されていません。この構造では、経営委員会(Management Board)が日常的な経営を担い、監査委員会(Supervisory Board)が経営委員会の活動を監督します。
日本の指名委員会等設置会社に類似した考え方ですが、異なる点として、経営委員会のメンバーは監査委員会によって選任されます。また、監査委員会は経営委員会に対して助言や監視は行いますが、具体的な指示を出す権限はありません。この構造は、経営と監督の役割を明確に分離することで、ガバナンスの透明性と客観性を高めることを目指すものです。
株主総会の権限
いずれの機関設計においても、株主総会は、取締役の選任・解任、計算書類の承認、定款の変更、増資・減資など、法律または定款によって定められた特定の重要事項について決定権を有します。
ルクセンブルクSàRL(有限会社)のガバナンス
SàRLは、SAに比べてよりシンプルな運営体制が特徴です。1名以上のマネージャー(managers)によって運営され、マネージャーが取締役会のように経営と代表権を担います。定款で定められた権限の範囲内で、マネージャーは会社の事業目的を達成するために必要なあらゆる行為を行うことができます。複数のマネージャーが任命された場合は、SAと同様に合議体を形成することになります。
SàRLの株主総会(general meeting)は、定款の変更、マネージャーの選任・解任、会社の清算など、特定の重要事項を決定します。SàRLの場合、株主数が60名以下であれば、定款で別途定められていない限り、年次株主総会の開催は義務ではありません。
ルクセンブルクのSAとSàRLに共通するガバナンスの重要課題

ルクセンブルクで事業を行う日本企業にとって、会社形態にかかわらず共通して直面する重要なガバナンス上の課題がいくつか存在します。
役員の居住地要件と税務上の「中央管理地」
ルクセンブルクの会社法上、SAの取締役やSàRLのマネージャーに国籍や居住地に関する要件はありません。これは、日本からの役員派遣や、グローバルな人材プールからの役員選任を可能にする大きな利点です。
しかし、この柔軟性は、税務上の「中央管理地」(place of central administration)という概念によって補完されています。ルクセンブルクの税法上、会社は、その登記上の本店所在地または中央管理地のいずれかがルクセンブルクにある場合に、ルクセンブルクの税務上の居住者とみなされます。
この「中央管理地」の概念は、法令で明確に定義されているわけではなく、取締役会や株主総会の開催場所、重要な経営判断がなされる場所、会社の帳簿書類が保管されている場所など、「事実と状況」に基づいて総合的に判断されます。これは「実態が形式に優先する」(substance over form)というルクセンブルク税法の原則に基づきます。
法定監査義務と監査人制度
ルクセンブルクの会社法では、企業の規模や特定の条件によって法定監査が義務付けられます。
- SAの監査義務:SAは、2事業年度連続で、以下の3つの基準のうち2つを超えた場合、法定監査が義務付けられます。
- 貸借対照表合計額:€440万超
- 純売上高:€880万超
- 従業員の年間平均フルタイム人数:50名超
- SàRLの監査義務:SàRLも上記の規模基準に加え、株主数が60名を超えた場合にも法定監査が義務付けられるという、日本法にはない独特の規定があります。
また、ルクセンブルクの監査人制度は、日本のそれとは役割が明確に分かれています。
- Commissaire aux comptes (法定監査人):会社の日常業務に対する監視権限を持つ監査人であり、より広範な監督義務を負います。
- Réviseur d’entreprises agréé (公認監査人):公認会計士協会に所属する専門家であり、年次計算書類の監査という限定された職務を担います。
企業が上記の規模基準を超えた場合、より厳格なréviseur d’entreprises agrééによる監査が義務付けられます。一方、SàRLで株主数が60名を超えた場合は、commissaire aux comptesによる監査が義務付けられます。
上場企業の「コンプライ・オア・エクスプレイン」原則
ルクセンブルク証券取引所(LuxSE)に上場する企業には、「コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)」原則に基づく「ルクセンブルク証券取引所の10のコーポレートガバナンス原則」が適用されます。これは、推奨される原則に従うか、従わない場合はその理由を詳細に説明することを求めるものです。この原則は、単一の厳格なルールではなく、企業の個別事情に合わせた柔軟性と、その「説明」によって投資家からの信頼を勝ち取るという考え方に基づくもので、日本のコーポレートガバナンス・コードと共通する哲学を持っています。
まとめ
ルクセンブルクのコーポレートガバナンスは、柔軟な会社設立要件と、国際的な税務慣行に則った厳格な「実態」要件という、一見矛盾する二つの側面を併せ持っています。日本企業がこの地で成功するためには、単に法令の表面的な規定を遵守するだけでなく、取締役会や経営判断が「どこで」「誰によって」行われているかという「実体」を伴ったガバナンスを構築することが不可欠です。また、特に中小企業にとって人気の高いSàRLについても、その成長を見据えた監査義務の予期せぬ発生リスクを事前に理解しておく必要があります。
このような複雑かつ多岐にわたる法務・税務課題を、進出準備の初期段階から適切に管理することは、事業の安定と成長に直結します。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務
タグ: ルクセンブルク大公国海外事業


































