„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮŚ§ßŚÖ¨ŚõĹ„Āģś≥ēšĹďÁ≥Ľ„Ā®ŚŹłś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀģŤß£Ť™¨

„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀĮ„ÄĀŚģČŚģö„Āó„ĀüśĒŅś≤Ľ„ÉĽÁĶĆśłąÁíįŚĘÉ„Ā®„ÄĀŚõĹťöõÁöĄ„Ā™„Éď„āł„Éć„āĻ„ĀęťĖč„Āč„āĆ„Āüś≥ēŚą∂Śļ¶„āíŤÉĆśôĮ„Āę„ÄĀś¨ßŚ∑ě„Āę„Āä„ĀĎ„āčšłĽŤ¶Ā„Ā™ťáĎŤěć„āĽ„É≥„āŅ„Éľ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŚúįšĹć„āíÁĘļÁęč„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģś≥ēšĹďÁ≥Ľ„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Ā®ŚźĆśßė„Āꌧߝôłś≥ēÁ≥Ľ„ĀęŚĪě„Āó„ÄĀśąźśĖáś≥ē„āíšłĽŤ¶Ā„Ā™ś≥ēśļź„Ā®„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀšłÄŤ¶č„Āó„Āüť°ěšľľśÄß„Ā®„ĀĮŤ£ŹŤÖĻ„Āę„ÄĀÁČĻ„Āꌹ§šĺč„ĀģšĹćÁĹģ„Ā•„ĀĎ„āĄEUś≥ē„Ā®„ĀģťĖĘšŅā„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āčťá捶Ā„Ā™ÁČĻśÄß„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āģś≥ēšĹďÁ≥Ľ„ĀģŚÖ®šĹďŚÉŹ„ā휶āŤ¶≥„Āó„Ā§„Ā§„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āł„Āģšļčś•≠ťÄ≤Śáļ„āíŤÄÉ„Āą„āčšļčś•≠ŤÄÖ„ĀĆś≥ēÁöĄ„É™„āĻ„āĮ„āíś≠£ÁĘļ„Āꍩēšĺ°„Āô„āč„Āü„āĀ„Āꚳ挏Įś¨†„Ā™„ÄĀśąźśĖáś≥ē„ÄĀŚą§šĺč„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶EUś≥ē„ĀģšłČŤÄÖ„ĀģťĖĘšŅā„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśó•śú¨ś≥ē„Ā®„ĀģŚĮĺśĮĒ„āíšļ§„Āą„Ā™„ĀĆ„āČŤ©≥Áīį„ĀęŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Ā™„Āä„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀģŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™ś≥ēŚą∂Śļ¶„Āģś¶āŤ¶Ā„ĀĮšłčŤ®ėŤ®ėšļč„Āę„Ā¶„Āĺ„Ā®„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āģś≥ēšĹďÁ≥Ľ
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„Ā®ś†Ļśú¨ÁöĄ„ĀꌟƄĀėŚ§ßťôłś≥ēÁ≥ĽÔľącivil law systemԾȄĀęŚĪě„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚüļÁõ§„ĀĮśąźśĖáś≥ēŚÖł„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģšĹďÁ≥Ľ„ĀĮ„ÄĀ„É≠„Éľ„É쌳̌õĹ„Āģ„Ä錳āśįĎś≥ēŚ§ßŚÖ®„ÄŹÔľąCorpus Juris CivilusԾȄĀęÁĒĪśĚ•„Āó„ÄĀś≥ēŚĺč„ĀģšłĽŤ¶Ā„Ā™ś†Ļśč†„āíŤ≠įšľö„ĀĆŚą∂Śģö„Āó„Āüś≥ēŚÖł„āĄś≥ēšĽ§„ĀęśĪā„āĀ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚą§šĺč„Āꌾ∑„ĀŹšĺ̜膄Āô„āčŤčĪÁĪ≥ś≥ēÁ≥Ľ„Āģ„ÄĆŚÖąšĺčśčėśĚü„ĀģŚéüŚČá„ÄćÔľąStare DecisisԾȄĀ®„ĀĮŚĮĺÁÖßÁöĄ„Āß„Āô„Äā
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āģś≥ēŚĺč„Āģś†ĻŚĻĻ„āíśąź„Āô„Āģ„ĀĮ„ÄĀ1868ŚĻī„Āꌹ∂Śģö„Āē„āĆ„ĀüśÜ≤ś≥ēÔľąConstitution du Grand-Duch√© de LuxembourgԾȄĀß„Āô„Äā„Āď„ĀģśÜ≤ś≥ē„ĀĮ„ÄĀŤ°ĆśĒŅŚļú„ÄĀÁęčś≥ēŚļú„ÄĀŚŹłś≥ēŚļú„ĀģšłČś®©„āíśėéÁĘļ„ĀꌹܝõĘ„Āó„ÄĀŚŹłś≥ē„ĀĆś≥ē„ĀģťĀ©Śąá„Ā™Śü∑Ť°Ć„āíÁõ£Ť¶Ė„Āô„āčŚĹĻŚČ≤„āíśčÖ„ĀÜ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀś®©ŚäõŚąÜÁęč„ĀģŚéüŚČá„āíŚģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āē„āČ„Āę„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āģś≥ēšĹďÁ≥Ľ„ĀĮ„ÄĀ„Éä„É̄ɨ„ā™„É≥ś≥ēŚÖł„ĀģŚĹĪťüŅ„ā팾∑„ĀŹŚŹó„ĀĎ„ĀüŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™ś≥ēŚÖł„Āę„āą„Ā£„Ā¶śĒĮ„Āą„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšĽ£Ť°®ÁöĄ„Ā™„āā„Āģ„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀÁßĀś≥ēŚÖ®Ťą¨„ā퍶ŹŚģö„Āô„āčśįĎś≥ēŚÖłÔľąCode civilԾȄāĄ„ÄĀŚēÜŚŹĖŚľē„ā퍶ŹŚĺč„Āô„āčŚēÜś≥ēŚÖłÔľąCode de commerceԾȄĀ™„Ā©„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ÄĀšľöÁ§ĺ„ÄĀŤ≤°ÁĒ£„ÄĀŚāĶś®©ŚāĶŚčô„Ā™„Ā©„ÄĀ„Éď„āł„Éć„āĻ„Āꚳ挏Įś¨†„Ā™ŚļÉÁĮĄ„Ā™šļ蝆քĀĆśąźśĖáś≥ē„Āę„āą„Ā£„Ā¶Á∂≤ÁĺÖÁöĄ„ĀꍶŹŚĺč„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„ĀģŚÖ¨ÁöĄ„Ā™ś≥ēšĽ§„ā퍙ŅśüĽ„Āô„āčšłä„Āß„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮśĒŅŚļú„ĀģŚÖ¨ŚľŹ„ā¶„āß„ÉĖ„āĶ„ā§„Éą„ÄĆLegilux„Äć„ĀĮśúÄ„āāšŅ°ť†ľśÄß„Āģťęė„ĀĄśÉÖŚ†Īśļź„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
Legilux„Āß„ĀĮ„ÄĀśÜ≤ś≥ē„āí„ĀĮ„Āė„āĀ„ÄĀŤ≠įšľö„ĀßśČŅŤ™ć„Āē„āĆ„Āüś≥ēŚĺč„ÄĀŚ§ßŚÖ¨ŚõĹšĽ§„ÄĀŚ§ßŤá£Ť¶ŹŚČá„Ā™„Ā©„ÄĀś≥ēšĽ§„ĀģťöéŚĪ§„ĀęŚĺď„Ā£„ĀüśĖáśõł„ĀĆŚÖ¨ťĖč„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀśúÄśĖį„ĀģśĚ°śĖá„ā팏āÁÖß„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀś≥®śĄŹ„Āô„ĀĻ„ĀćÁāĻ„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀŚźĆ„āĶ„ā§„Éąšłä„Āߌ֨ťĖč„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģŚąÜťáé„Āģś≥ēŚĺč„āí„Āĺ„Ā®„āĀ„Āü„ÄĆ„ā≥„É≥„ÉĒ„ɨ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„ÄćÔľąCodes-compilationsԾȄĀĮ„ÄĀ„Āā„ĀŹ„Āĺ„ĀߌŹāÁÖßÁĒ®„Āß„Āā„āä„ÄĀŤ£ĀŚą§„Āßś≠£ŚľŹ„Ā™ś≥ēÁöĄś†Ļśč†„Ā®„Āó„Ā¶ÁĒ®„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮŚŹłś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀģśßčťÄ†„Ā®ŚĹĻŚČ≤
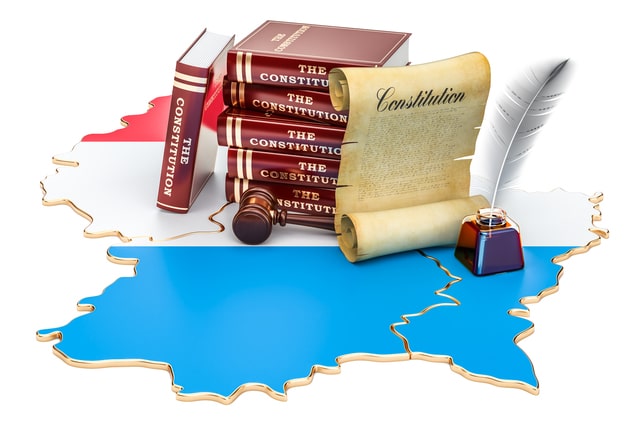
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀĮ„ÄĀÁęčśÜ≤ŚźõšłĽŚą∂„ĀģŤ≠įšľöŚą∂śįĎšłĽšłĽÁĺ©ŚõĹ„Āß„Āā„āä„ÄĀŤ°ĆśĒŅŚļú„ÄĀÁęčś≥ēŚļú„ÄĀŚŹłś≥ēŚļú„ĀĆšļí„ĀĄ„ĀęÁč¨Áęč„Āó„ĀüšłČś®©ŚąÜÁęčšĹ∂„āíÁĘļÁęč„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚŹłś≥ē„ĀģÁč¨Áęč„ĀĮśÜ≤ś≥ē„Āę„āą„Ā£„Ā¶šŅĚťöú„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŤ£ĀŚą§Śģė„ĀĮŚ§ßŚÖ¨ÔľąGrand DukeԾȄĀę„āą„Ā£„Ā¶šĽĽŚĎĹ„Āē„āĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤļꌹ܄ĀĮšŅĚťöú„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄÁĶĄÁĻĒ„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Āģ„ĀĚ„āĆ„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āčšļĆŚÖÉÁöĄ„Ā™śßčťÄ†„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāśįĎšļč„ÉĽŚąĎšļčšļ蚼∂„āíśČĪ„ĀÜ„ÄĆŚŹłś≥ēŤ£ĀŚą§śČÄÔľąordre judiciaireԾȄÄć„Ā®„ÄĀŤ°ĆśĒŅšļ蚼∂„āíŚįāťĖÄ„ĀęśČĪ„ĀÜ„ÄĆŤ°ĆśĒŅŤ£ĀŚą§śČÄÔľąordre administratifԾȄÄć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀšļĆ„Ā§„ĀģÁč¨Áęč„Āó„ĀüÁ≥ĽÁĶĪ„ĀĆšĹĶŚ≠ė„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆŤ°ĆśĒŅšļ蚼∂„ā팟ę„āĀ„Ā¶ŚćėšłÄ„ĀģÁ≥ĽÁĶĪ„ĀęŚĪě„Āô„āč„Āģ„Ā®„ĀĮŚĮĺÁÖßÁöĄ„Ā™„Āď„ĀģśßčťÄ†„ĀĮ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮś≥ēŚčô„āíÁźÜŤß£„Āô„āčšłä„Āßťá捶Ā„Ā™Ť¶ĀÁī†„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
ŚŹłś≥ēŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĀšłČ„Ā§„ĀģťöéŚĪ§„Āč„āČ„Ā™„āč„ÉĒ„É©„Éü„ÉÉ„ÉČŚěč„ĀģśßčťÄ†„āíŚĹĘśąź„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁ¨¨šłÄŚĮ©„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŤĽĹŚĺģ„Ā™śįĎšļč„ÉĽŚēÜšļčšļ蚼∂„āĄŤĽĹÁäĮÁĹ™„āíśČĪ„ĀÜšłČ„Ā§„Āģś≤ĽŚģČŤ£ĀŚą§śČÄÔľąJustices de paixԾȄĀ®„ÄĀ„āą„āäťá挧߄Ā™śįĎšļč„ÉĽŚēÜšļč„ÉĽŚąĎšļčšļ蚼∂„āíśČĪ„ĀÜšļĆ„Ā§„ĀģŚúįśĖĻŤ£ĀŚą§śČÄÔľąTribunaux d’arrondissementԾȄĀĆŤ®≠„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ĀĚ„ĀģšłäÁīöŚĮ©„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀťęėÁ≠ČŤ£ĀŚą§śČÄÔľąCour sup√©rieure de justiceԾȄĀĆÁĹģ„Āč„āĆ„ÄĀ„ĀĚ„Āģšłč„ĀęŚúįśĖĻŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§śĪļ„ĀęŚĮĺ„Āô„āčśéߍ®ī„āíśČĪ„ĀÜśéߍ®īťôĘÔľąCour d’appelԾȄĀ®„ÄĀś≥ēŚĺč„ĀģŤß£ťáąťĀ©ÁĒ®„Āꍙ§„āä„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āč„āíŚĮ©śüĽ„Āô„āčÁ†īśĮÄťôĘÔľąCour de cassationԾȄĀĆťÖćÁĹģ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁ†īśĮÄťôĘ„ĀĮ„ÄĀśéߍ®īťôĘ„Āģ„āą„ĀÜ„Āęšļ蚼∂„ĀģšļčŚģüťĖĘšŅā„āíŚÜćŚĮ©śüĽ„Āô„āč„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀšłčÁīöŚĮ©„ĀģŚą§śĪļ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ś≥ēŤß£ťáą„ĀĆś≠£„Āó„ĀŹŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„Āč„ā휧úŤ®ľ„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„ÄĆś≥ēŚĺč„ĀģŤß£ťáąÁĶĪšłÄ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚĹĻŚČ≤„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Āę„Āä„ĀĎ„āčśúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚĹĻŚČ≤„Ā®ťĚ쌳ł„Āęť°ěšľľ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮś≥ē„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹§šĺč„Āģś≥ēÁöĄśčėśĚüŚäõ
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āģś≥ēšĹďÁ≥Ľ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśó•śú¨„Āģś≥ēŚčôŚģüŚčôŤÄÖ„ĀĆśúÄ„āāś∑Ī„ĀŹÁźÜŤß£„Āô„ĀĻ„Ā朆łŚŅÉÁöĄ„Ā™ťĀē„ĀĄ„ĀĮ„ÄĀŚą§šĺč„Āģś≥ēÁöĄśčėśĚüŚäõ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŤÄÉ„ĀąśĖĻ„Āß„Āô„Äā„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āß„ĀĮ„ÄĀŤčĪÁĪ≥ś≥ēÁ≥Ľ„Āģ„ÄĆŚÖąšĺčśčėśĚü„ĀģŚéüŚČá„ÄćÔľąStare DecisisԾȄĀģ„āą„ĀÜ„Ā™„ÄĀŚé≥ś†ľ„ĀęŤ£ĀŚą§Śģė„āíśčėśĚü„Āô„ā茹§šĺčś≥ē„ĀĮŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀ„Āā„āčŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§śĪļ„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„Āģť°ěšľľšļ蚼∂„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶šĽĖ„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄ„āíś≥ēÁöĄ„ĀęśčėśĚü„Āô„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮŚą§šĺč„ĀĆŚģĆŚÖ®„ĀęÁĄ°Śäõ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āô„āč„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāÁ†īśĮÄťôĘ„Ā™„Ā©„ĀßšłÄŤ≤ę„Āó„Ā¶ÁĻį„āäŤŅĒ„Āē„āĆ„ā茟ƚłÄ„Āģś≥ēŤß£ťáą„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚą§šĺč„ĀģÁ∂ôÁ∂öśÄß„ÄćÔľąJurisprudence ConstanteԾȄĀ®„Āó„Ā¶šļčŚģüšłä„ĀģŤ™¨ŚĺóŚäõ„āíśĆĀ„Ā§„ÄĆ„āĹ„Éē„Éą„É≠„Éľ„Äć„Ā®„Āó„Ā¶ś©üŤÉĹ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚÄč„ÄÖ„ĀģŤ£ĀŚą§Śģė„ĀĮ„ÄĀŚÖąšĺč„Āęś≥ēÁöĄ„ĀęŚĺď„ĀÜÁĺ©Śčô„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„āā„Āģ„Āģ„ÄĀś≥ē„ĀģŚģČŚģöśÄß„Ā®šļąŤ¶čŚŹĮŤÉĹśÄß„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„Āĺ„ĀüŤá™Ťļę„ĀģŚą§śĪļ„ĀĆšłäÁīöŚĮ©„Āߍ¶Ü„Āē„āĆ„āč„É™„āĻ„āĮ„āíťĀŅ„ĀĎ„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„Āď„ĀģÁ∂ôÁ∂öÁöĄ„Ā™Śą§šĺč„āíŚįäťáć„Āó„ÄĀŚŹāÁÖß„Āô„āčŚā匟τĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āā„āčŚįāťĖÄŚģ∂„ĀĮ„ÄĀŚą§šĺč„ĀĮ„ÄĆŤ£ĀŚą§Śģė„ĀģśÄĚŤÄÉ„ĀģŚáļÁôļÁāĻ„Äć„Āß„Āā„āä„ÄĀŚįäťáć„Āē„āĆ„āč„Āģ„ĀĮś≥ēÁöĄ„Ā™ŚģČŚģöśÄß„āĄšłäÁīöŚĮ©„Āß„ĀģÁ†īś£Ą„āíśĀź„āĆ„āčŚŅÉÁźÜ„Āč„āČ„Ā†„ÄĀ„Ā®ŤŅį„ĀĻ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„Āģ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀģťĀčÁĒ®„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Āę„Āä„ĀĎ„āčśúÄťęėŤ£ĀŚą§šĺč„ĀģŚľ∑„ĀĄŚĹĪťüŅŚäõ„Ā®ŚĮĺśĮĒ„Āô„āč„Ā®„ÄĀ„ĀĚ„ĀģÁČĻśģäśÄß„ĀĆ„āą„āäśėéÁĘļ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨„āāŚ§ßťôłś≥ēÁ≥Ľ„ĀęŚĪě„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀśúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§šĺč„ĀĮšłčÁīöŚĮ©„āĄŚģüŚčô„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶šļčŚģüšłäťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄśčėśĚüŚäõ„āíśĆĀ„Ā§„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨„ĀģśúÄťęėŤ£ĀŚą§śČčᙍļę„āā„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶Ťá™Ťļę„ĀģŚą§šĺč„ā퍳ŹŤ•≤„Āó„ÄĀ„Āď„āĆ„ā팧Ȝõī„Āô„āčťöõ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚ§ßś≥ēŚĽ∑„Āß„ĀģŚĮ©ÁźÜ„āíÁĶĆ„Ā¶„ÄĆŚĺďśĚ•„ĀģŚą§šĺč„ĀĮ„Āď„āĆ„ā팧Ȝõī„Āô„āč„Äć„Ā®śėéÁĘļ„ĀęŚģ£Ť®Ä„Āô„āčśÖ£Ť°Ć„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„Āģ„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀśó•śú¨„Ā®„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹§šĺč„ĀģŚĹĻŚČ≤„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆś≥ēÁöĄ„Ā™śčėśĚüŚäõ„ĀģśúČÁĄ°„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚćėÁīĒ„Ā™šļĆŚÖÉŤęĖ„Āß„ĀĮśćČ„Āą„Āć„āĆ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆ„āŹ„Āč„āä„Āĺ„Āô„Äāšł°ŚõĹ„ĀģťĀē„ĀĄ„ĀĮ„ÄĀ„āÄ„Āó„āć„ÄĆŚą§šĺč„ĀĆŚģüŚčô„Āęšłé„Āą„āčšļčŚģüšłä„ĀģśčėśĚüŚäõ„ĀģŚľ∑Śļ¶„Äć„ĀģŚ∑ģ„Ā®śćČ„Āą„āč„ĀĻ„Āć„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äāśó•śú¨šľĀś•≠„ĀĮ„ÄĀťĀéŚéĽ„ĀģśúÄťęėŤ£ĀŚą§šĺč„ā퍙Ņ„ĀĻ„āč„Āď„Ā®„Āߌįܜ̕„Āģś≥ēŤß£ťáą„Āꌾ∑„ĀĄšļąŤ¶čŚŹĮŤÉĹśÄß„āíŚĺó„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āß„ĀĮ„ĀĚ„Āģ„āĘ„Éó„É≠„Éľ„ÉĀ„ĀĆťÄöÁĒ®„Āó„Ā™„ĀĄ„Āü„āĀ„ÄĀś≥ēÁöĄ„É™„āĻ„āĮŤ©ēšĺ°„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀťĀéŚéĽ„ĀģŚą§šĺč„ĀģÁ©ć„ĀŅťáć„Ā≠„āą„āä„āā„ÄĀśąźśĖáś≥ē„ĀģśĚ°śĖá„ĀĚ„Āģ„āā„Āģ„ĀģÁ∑ĽŚĮÜ„Ā™Ťß£ťáą„āĄś≥ēŚ≠¶ŤÄÖ„ĀģŤ¶čŤß£„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ŚĺĆŤŅį„Āô„āčEUś≥ē„ĀģŚčēŚźĎ„Āę„āą„āäťáć„Āć„āíÁĹģ„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āß„ĀģŚģüŚčô„Āꚳ挏Įś¨†„Ā™EUś≥ē„ĀģÁźÜŤß£
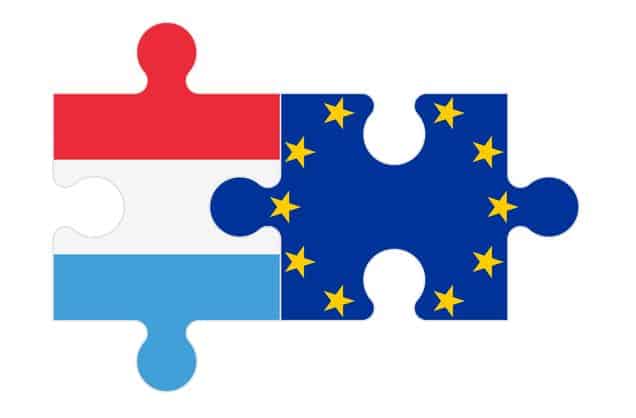
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀĮ„ÄĀś¨ßŚ∑ěťÄ£ŚźąÔľąEUԾȄĀģŚČĶŤ®≠„É°„É≥„Éź„Éľ„Āß„Āā„āä„ÄĀś¨ßŚ∑쌏łś≥ēŤ£ĀŚą§śČÄÔľąECJԾȄā팟ę„āÄŚ§ö„ĀŹ„ĀģEUś©üťĖĘ„ā흶ĖťÉĹ„ĀęśďĀ„Āô„āčEUÁĶĪŚźą„Āģšł≠ŚŅÉŚúį„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀģŚõĹŚÜÖś≥ē„ĀĮEUś≥ē„ĀģÁõīśé•ÁöĄ„Ā™ŚĹĪťüŅ„ā팾∑„ĀŹŚŹó„ĀĎ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀÁČĻ„Āę„Éď„āł„Éć„āĻ„Āģś≥ēÁöĄÁíįŚĘÉ„āíŤÄÉ„Āą„āčšłä„ĀßšłćŚŹĮś¨†„Ā™Ť¶ĀÁī†„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
EUś≥ē„āíÁźÜŤß£„Āô„āčšłä„ĀßśúÄ„āāťá捶Ā„Ā™ŚéüŚČá„ĀĮ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮŚõĹŚÜÖś≥ē„Āꌥ™ŚÖą„Āó„Ā¶ťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„āč„ÄĆŚĄ™Ť∂ä„ĀģŚéüŚČá„ÄćÔľąPrimaut√© du droit de l’UEԾȄĀß„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀECJ„ĀģŚą§šĺčÔľąCosta v ENELŚą§śĪļ„Ā™„Ā©ÔľČ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁĘļÁęč„Āē„āĆ„Āüś≥ēŚéüŚČá„Āß„Āā„āä „ÄĀEUś≥ē„Ā®ÁüõÁõĺ„Āô„āčŚõĹŚÜÖś≥ē„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģś≥ēšĽ§„ĀĆEUś≥ē„āą„āäŚĺĆ„Āꌹ∂Śģö„Āē„āĆ„Āü„āā„Āģ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„āĄŤ°ĆśĒŅŚĹďŚĪÄ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ťĀ©ÁĒ®„ĀĆśč팟¶„Āē„āĆ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āď„ĀģŚéüŚČá„ĀĮ„ÄĀEUś≥ē„ĀĆ„ÄĀÁČĻŚģö„Āģś®©ťôź„ĀĆEU„ĀęÁ߼Ť≠≤„Āē„āĆ„ĀüŚąÜťáé„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚõĹŚÜÖś≥ē„āĄ„ÄĀšłÄťÉ®„ĀģŤß£ťáą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮŚõĹŚģ∂śÜ≤ś≥ē„Āę„Āē„ĀąŚĄ™Ť∂ä„Āô„āčŚäĻŚäõ„āíśĆĀ„Ā§„Āď„Ā®„āíÁ§ļŚĒÜ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀĮŚõĹťöõÁöĄ„Ā™ťáĎŤěć„āĽ„É≥„āŅ„Éľ„Āß„Āā„āč„Āü„āĀ„ÄĀEU„ĀģťáĎŤěć„ÉĽšľĀś•≠ś≥ēŚčô„ĀęťĖĘ„Āô„ā荶ŹŚą∂„ĀģŚĹĪťüŅ„āíśúÄ„āāŚľ∑„ĀŹŚŹó„ĀĎ„āčŚõĹ„ĀģšłÄ„Ā§„Āß„Āô„ÄāEU„ĀĆŚą∂Śģö„Āô„āčťáĎŤěć„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĆᚼ§ÔľąDirectivesԾȄāĄŤ¶ŹŚČáÔľąRegulationsԾȄĀĮ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀģŚõĹŚÜÖś≥ē„ĀęÁõīśé•ŚĹĪťüŅ„ā팏ä„Āľ„Āó„ÄĀŚõĹŚÜÖś≥ēśĒĻś≠£„ĀģŚľē„ĀćťáĎ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ĀĚ„ĀģŚÖ∑šĹďÁöĄšļčšĺč„ĀĮŚ§öśēį„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Ā®„Āą„Āį„ÄĀŤ≠≤śł°śÄߍ®ľŚął„āíśäēŤ≥áŚĮĺŤĪ°„Ā®„Āô„āčśäēŤ≥ášŅ°Ť®óÔľąUCITSԾȄĀęťĖĘ„Āô„āčEUśĆᚼ§ÔľąUCITS V DirectiveԾȄĀĮ„ÄĀ2016ŚĻī„ĀģŚõĹŚÜÖś≥ēśĒĻś≠£ÔľąLoi du 10 mai 2016ԾȄāíťÄö„Āė„Ā¶„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮś≥ē„ĀꍼʜŹõ„Āē„āĆ„ÄĀťáĎŤěćŚēÜŚďĀ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģÁĶĪšłÄÁöĄ„Ā™ŚüļśļĖ„ĀĆÁĘļÁęč„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀťáĎŤěćŚēÜŚďĀ„ĀģŚŹĖŚľē„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™Ť¶ŹŚą∂„Āß„Āā„āčMiFID IIÔľąťáĎŤěćŚēÜŚďĀŚłāŚ†īśĆᚼ§ÔľČ„āā„ÄĀ2018ŚĻīÔľąLoi du 30 mai 2018ԾȄĀę„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮŚõĹŚÜÖś≥ē„ĀłŤĽĘśŹõ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āē„āČ„Āę„ÄĀŤŅĎŚĻī„ĀģŚčē„Āć„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£Ôľącrypto-assetsԾȄĀęťĖĘ„Āô„āčEUŚÖ®Śüü„Āę„āŹ„Āü„āčÁĶĪšłÄÁöĄ„Ā™Ť¶ŹŚą∂„Āß„Āā„āčMiCAÔľąśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£ŚłāŚ†īŤ¶ŹŚą∂ԾȄĀĆ„ÄĀ2023ŚĻī6śúą„ĀęÁôļŚäĻ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģEUś≥ēŚą∂„āíÁ©ćś•ĶÁöĄ„ĀꌏĖ„āäŤĺľ„ĀŅ„ÄĀŚõĹŚÜÖ„Āģ„ÄĆ„ÉĖ„É≠„ÉÉ„āĮ„ÉĀ„āß„Éľ„É≥ś≥ē„Äć„āíśēīŚāô„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀśöóŚŹ∑Ť≥áÁĒ£„Éď„āł„Éć„āĻ„Āę„Āä„ĀĎ„āčś≥ēÁöĄŚģČŚģöśÄß„āíťęė„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀģŚõĹŚÜÖś≥ē„Āę„Āä„ĀĎ„ā茹§šĺč„ĀģśčėśĚüŚäõ„ĀĆŚľĪ„ĀĄšłÄśĖĻ„Āß„ÄĀEUś≥ē„Āę„ĀĮCosta v ENELŚą§śĪļ„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™„ÄĀECJ„ĀģŚą§šĺč„āíťÄö„Āė„Ā¶ÁĘļÁęč„Āē„āĆ„ĀüŚľ∑Śäõ„Ā™ś≥ēŚéüŚČá„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀģŚõĹŚÜÖŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆŚÄ茹•„Āģšļčś°ą„Āߌֹšĺč„Āęś≥ēÁöĄ„ĀęśčėśĚü„Āē„āĆ„Ā™„ĀĄšłÄśĖĻ„ÄĀEUś≥ē„ĀĆŤ¶ŹŚģö„Āô„āčśě†ÁĶĄ„ĀŅ„Āģšł≠„Āß„ĀĮ„ÄĀECJ„ĀģŚą§šĺč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĆŚą•„Āģś¨°ŚÖÉ„ĀģŚÖąšĺč„Äć„ĀęšļčŚģüšłäŚĺď„āŹ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ§áťõĎ„Ā™Áä∂ś≥Ā„āíÁĒü„ĀŅŚáļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀEUś≥ē„ĀģŚčēŚźĎ„ĀĮ„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āę„Āä„ĀĎ„āčś≥ēÁöĄšļąŤ¶čŚŹĮŤÉĹśÄß„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āģťá捶Ā„Ā™ťćĶ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ
„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„ĀĮ„ÄĀŚ§ßťôłś≥ēÁ≥Ľ„ĀģšľĚÁĶĪ„āíŚģą„āä„Ā§„Ā§„āā„ÄĀEUÁĶĪŚźą„Āģšł≠ŚŅÉŚúį„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĚ„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„āíÁĶ∂„Āą„ĀöťÄ≤ŚĆĖ„Āē„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāťĀéŚéĽ„ĀģŚą§šĺč„ĀģÁ©ć„ĀŅťáć„Ā≠„Āꌾ∑„ĀŹšĺ̜膄Āô„āčśó•śú¨„ĀģŚģüŚčô„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āä„ÄĀ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮ„Āß„Āģś≥ēÁöĄ„É™„āĻ„āĮŤ©ēšĺ°„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśąźśĖáś≥ē„ĀģśĚ°śĖá„ĀĚ„Āģ„āā„Āģ„āĄ„ÄĀśúÄśĖį„ĀģEUŤ¶ŹŚČá„ÉĽśĆᚼ§„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶EUŚŹłś≥ēŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§šĺč„ĀĆ„ÄĀ„Éď„āł„Éć„āĻ„Āģś≥ēÁöĄÁíįŚĘÉ„āíŚĹĘśąź„Āô„āčšłä„ĀßśĪļŚģöÁöĄ„Ā™Ť¶ĀÁī†„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„Āģ„Éę„āĮ„āĽ„É≥„ÉĖ„Éę„āĮÁ訍ᙄĀģś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀģÁČĻśÄß„āíś≠£ÁĘļ„ĀęÁźÜŤß£„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚćė„Āę„Éď„āł„Éć„āĻ„ā퍰ƄĀÜšłä„Āß„ĀģšļąŤ¶čŚŹĮŤÉĹśÄß„āíÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀśĹúŚú®ÁöĄ„Ā™„É™„āĻ„āĮ„āíŚõěťĀŅ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āꚳ挏Įś¨†„Āß„Āô„Äā
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô


































