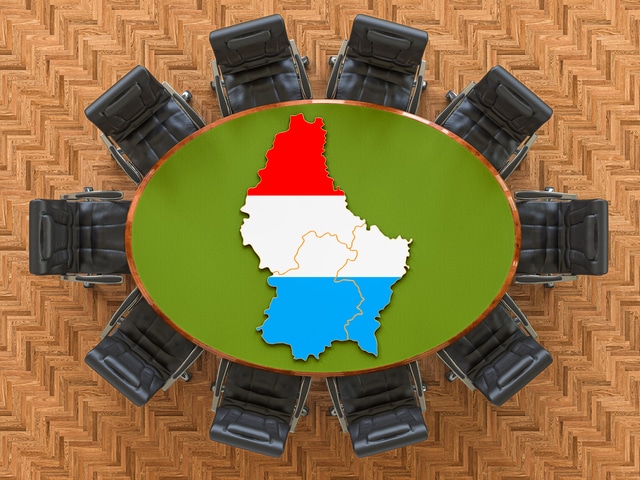гғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲ¶еәҰгҒ®е…ЁдҪ“еғҸ

гғӯгӮ·гӮўгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«еӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еұһгҒ—гҖҒжҲҗж–Үжі•гӮ’дё»иҰҒгҒӘжі•жәҗгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒдёҖиҰӢгҒҷгӮӢгҒЁж—Ҙжң¬жі•гҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜгӮ„е®ҹеӢҷдёҠгҒ®йҒӢз”ЁгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҒҢеӨҡж•°еӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжҶІжі•гӮ„йҖЈйӮҰжҶІжі•жі•еҫӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…¬зҡ„гҒӘжі•д»ӨгӮ’ж №жӢ гҒ«гҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®иЈҒеҲӨеҲ¶еәҰгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгҖҒзү№гҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨеҲ¶еәҰгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰз•ҷж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚйҮҚиҰҒгҒӘзӣёйҒ•зӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгӮӢжі•и§ЈйҮҲгҒ®зөұдёҖгғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№зҙӣдәүгӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«жүұгҒҶе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҪ№еүІгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиҝ‘е№ҙиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©иЈҒеҲӨжүҖгҒ®ж©ҹиғҪгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®иғҪеӢ•зҡ„гҒӘеҪ№еүІгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨеҲ¶еәҰгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒӘгҒҢгӮүи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғӯгӮ·гӮўгҒ®иЈҒеҲӨеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҸёжі•гҒ®дәҢеұӨж§ӢйҖ гҒЁдёүгҒӨгҒ®зі»зөұ
гғӯгӮ·гӮўгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬118жқЎгҒҠгӮҲгҒійҖЈйӮҰжҶІжі•жі•еҫӢгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒйҖЈйӮҰгғ¬гғҷгғ«гҒЁең°еҹҹгғ¬гғҷгғ«гҒ®дәҢеұӨж§ӢйҖ гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйҖЈйӮҰгғ¬гғҷгғ«гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҢжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеҸёжі•жЁ©гӮ’иЎҢдҪҝгҒ—гҖҒең°еҹҹгғ¬гғҷгғ«гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜзү№е®ҡгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жӢ…гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶйҡҺеұӨзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгҒ®жЁ©йҷҗгҒЁз®ЎиҪ„гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒд»ҘдёӢгҒ®дёүгҒӨгҒ®зі»зөұгҒ«жҳҺзўәгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
第дёҖгҒ«гҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҷгҖӮжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒжі•еҫӢгӮ„еӨ§зөұй ҳд»ӨгҒӘгҒ©гҒҢгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжҶІжі•гҒ«йҒ©еҗҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢгҖҒжҶІжі•дёҠгҒ®зӣЈиҰ–гӮ’е°Ӯй–ҖгҒЁгҒҷгӮӢзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒеӨ§зөұй ҳгҖҒйҖЈйӮҰиӯ°дјҡгҖҒж”ҝеәңгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜеёӮж°‘гҒӢгӮүгҒ®иҰҒи«ӢгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒзү№е®ҡгҒ®жі•еҫӢгӮ„иЎҢзӮәгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’еҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгҖҒжҶІжі•з§©еәҸгҒ®еҹәзӣӨгҖҒеҹәжң¬зҡ„дәәжЁ©гҖҒгҒҠгӮҲгҒіиҮӘз”ұгӮ’дҝқиӯ·гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
第дәҢгҒ«гҖҒдёҖиҲ¬з®ЎиҪ„иЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҷгҖӮдёҖиҲ¬з®ЎиҪ„иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒеҲ‘дәӢгҖҒж°‘дәӢгҖҒиЎҢж”ҝдәӢ件гҒӘгҒ©гҖҒйҖҡеёёгҒ®иЁҙиЁҹгӮ’е№…еәғгҒҸжүұгҒҶиЈҒеҲӨжүҖгҒ®зі»зөұгҒ§гҖҒгғ”гғ©гғҹгғғгғүеһӢгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ第дёҖеҜ©гӮ’жӢ…гҒҶжІ»е®үеҲӨдәӢиЈҒеҲӨжүҖгӮ„ең°еҢәиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒдёҠиЁҙеҜ©гҖҒз ҙжЈ„еҜ©гӮ’зөҢгҒҰгҖҒжңҖй«ҳеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
第дёүгҒ«гҖҒе•ҶдәӢпјҲArbitrazhпјүиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҷгҖӮе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒзөҢжёҲзҙӣдәүгӮ„гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢзҙӣдәүгӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«жүұгҒҶиЈҒеҲӨжүҖгҒ®зі»зөұгҒ§гҒҷгҖӮж—§гӮҪйҖЈжҷӮд»ЈгҒ«е•ҶдәӢжЎҲ件гӮ’жүұгҒҶжә–д»ІиЈҒж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®е•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒёгҒЁзҷәеұ•гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶжӯҙеҸІзҡ„зөҢз·ҜгӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
2014е№ҙгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹеҸёжі•еӨ§ж”№йқ©гҒ®д»ҘеүҚгҒҜгҖҒж°‘дәӢгғ»еҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®жңҖй«ҳеҜ©гҒ§гҒӮгӮӢгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҖҒзөҢжёҲзҙӣдәүгҒ®жңҖй«ҳеҜ©гҒ§гҒӮгӮӢгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжңҖй«ҳе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжңҖй«ҳеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйҖЈйӮҰжҶІжі•жі•еҫӢгҒ®ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдёЎиҖ…гҒҜзөұеҗҲгҒ•гӮҢгҖҒгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢе”ҜдёҖгҒ®жңҖй«ҳеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
| жҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖ | дёҖиҲ¬з®ЎиҪ„иЈҒеҲӨжүҖ | е•ҶдәӢпјҲArbitrazhпјүиЈҒеҲӨжүҖ | |
|---|---|---|---|
| жңҖй«ҳеҜ© | гғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖ | гғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖ | гғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјҲж—§жңҖй«ҳе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒҺпјү |
| дёҠзҙҡеҜ© | еҗ„е…ұе’ҢеӣҪгғ»е·һгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒӘгҒ© | жҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖ | |
| 第дёҖеҜ© | ең°еҢәгғ»еёӮиЈҒеҲӨжүҖгҖҒжІ»е®үеҲӨдәӢиЈҒеҲӨжүҖ | еҗ„е…ұе’ҢеӣҪгғ»е·һгҒ®е•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖ | |
| дё»гҒӘз®ЎиҪ„ | жі•еҫӢгғ»ж”ҝд»ӨгҒ®еҗҲжҶІжҖ§еҜ©жҹ»гҖҒеӣҪ家ж©ҹй–ўй–“гҒ®жЁ©йҷҗдәүиӯ° | еҲ‘дәӢгҖҒж°‘дәӢгҖҒиЎҢж”ҝгҖҒеҠҙеғҚгҖҒ家дәӢдәӢ件 | жі•дәәгғ»еҖӢдәәдәӢжҘӯдё»й–“гҒ®зөҢжёҲзҙӣдәүпјҲеҘ‘зҙ„гҖҒеӮөжЁ©еӣһеҸҺпјүгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©зҙӣдәүгҒ®дёҖйғЁ |
гғӯгӮ·гӮўгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖз·Ҹдјҡжұәиӯ°гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®еҲӨдҫӢжі•дё»зҫ©гҒЁгҒ®йҒ•гҒ„

ж—Ҙжң¬гҒ®жі•е®ҹеӢҷ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңҖгӮӮзү№з•°гҒ«жҳ гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢе®ҡжңҹзҡ„гҒ«жҺЎжҠһгҒҷгӮӢгҖҢз·Ҹдјҡжұәиӯ°гҖҚгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҷгҖӮгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжҶІжі•з¬¬126жқЎгҒҠгӮҲгҒійҖЈйӮҰжҶІжі•жі•еҫӢгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгӮӢжі•еҫӢгҒ®зөұдёҖзҡ„гҒӢгҒӨжӯЈгҒ—гҒ„йҒ©з”ЁгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзү№е®ҡгҒ®жі•зҡ„иҰҸе®ҡгҒ®и§ЈйҮҲгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӢ§е‘ҠгӮ’е®ҡгӮҒгҒҹз·Ҹдјҡжұәиӯ°гӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«жҺЎжҠһгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®з·Ҹдјҡжұәиӯ°гҒҜгҖҒе…¬ејҸгҒ«гҒҜжҲҗж–Үжі•гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжі•жәҗгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еӢ§е‘ҠгӮ’гҖҢеҺіж јгҒ«йҒөе®ҲгҖҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӮгҒ—дёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҒ“гӮҢгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢеҲӨжұәгӮ’дёӢгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®еҲӨжұәгҒҜдёҠдҪҚеҜ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸ–гӮҠж¶ҲгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®йҒӢз”ЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢгҒҢдёӢзҙҡеҜ©гӮ’дәӢе®ҹдёҠжӢҳжқҹгҒҷгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒҜгҖҒж №жң¬зҡ„гҒӘжҖ§иіӘгҒҢз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жңҖй«ҳиЈҒгҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§еҖӢгҖ…гҒ®дәӢжЎҲгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯгҒ®з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣгҒҜжҳҺж–ҮеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҲӨдҫӢгҒ®еӨүжӣҙгӮӮгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢиҮӘгӮүгҒ®еҲӨж–ӯгӮ’иҰӢзӣҙгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҒӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®з·Ҹдјҡжұәиӯ°гҒҜгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®еҲӨжұәгҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжі•еҫӢгҒ®и§ЈйҮҲгӮ’дёҖе…ғеҢ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®зөұдёҖзҡ„гҒӘйҒ©з”ЁгӮ’дёӢзҙҡеҜ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮе®ҹзҸҫгҒҷгӮӢжҳҺзўәгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜгҖҒжі•еҫӢгҒ®и§ЈйҮҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҖиІ«жҖ§гӮ’дҝқгҒЎгҖҒжі•йҒӢз”ЁгҒ®дәҲиҰӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§йҮҚиҰҒгҒӘж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гғӯгӮ·гӮўгҒ®е•ҶдәӢпјҲArbitrazhпјүиЈҒеҲӨжүҖ
гғӯгӮ·гӮўгҒ®е•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒжі•дәәгҒҫгҒҹгҒҜеҖӢдәәдәӢжҘӯдё»гҒҢеҪ“дәӢиҖ…гҒЁгҒӘгӮӢзөҢжёҲзҙӣдәүгӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«жүұгҒ„гҖҒеҘ‘зҙ„зҙӣдәүгҖҒеӮөжЁ©еӣһеҸҺгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©дҫөе®іиЁҙиЁҹгҒ®дёҖйғЁгҒӘгҒ©гӮ’з®ЎиҪ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иҝ‘е№ҙгҒ®гғӯгӮ·гӮўгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒзү№гҒ«еӣҪйҡӣзҡ„гҒӘгғ“гӮёгғҚгӮ№зҙӣдәүгҒ®и§ЈжұәгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиҮӘеӣҪгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢж–№еҗ‘гҒ«еӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ2015е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢгғқгӮұгғғгғҲд»ІиЈҒгҖҚпјҲдјҒжҘӯгҒҢиҮӘзӨҫеҶ…гҒ«иЁӯз«ӢгҒ—гҒҹд»ІиЈҒж©ҹй–ўпјүгӮ’жҺ’йҷӨгҒ—гҖҒеӣҪеҶ…еӨ–гҒ®д»ІиЈҒж©ҹй–ўгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгғӯгӮ·гӮўеӣҪеҶ…гҒ§гҒ®зҙӣдәүгӮ’жүұгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®еӣҪ家гҒ®иЁұеҸҜгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹжі•еҫӢж”№жӯЈгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҖҒ2018е№ҙгҒ«гҒҜгҒ•гӮүгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢж”№жӯЈгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®зҠ¶жіҒеӨүеҢ–гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒж–°гҒҹгҒӘиҰҸе®ҡгҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰд»ІиЈҒжүӢз¶ҡжі•гҒ«гҒҜгҖҒиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲеӨ–еӣҪгҒ®еҲ¶иЈҒеҜҫиұЎиҖ…гҒЁгҒ®зҙӣдәүгӮ„гҖҒеӨ–еӣҪгҒ®еҲ¶иЈҒгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢзҙӣдәүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®е•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжҺ’д»–зҡ„з®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жңүгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–°гҒҹгҒӘжқЎй …гҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӢ•гҒҚгҒҜгҖҒгғӯгӮ·гӮўеҪ“еұҖгҒҢеӣҪеҶ…еӨ–гҒ®д»ІиЈҒгӮ„иЁҙиЁҹгӮ’еҺігҒ—гҒҸз®ЎзҗҶгҒ—гҖҒиҮӘеӣҪгҒ®з®ЎиҪ„жЁ©гӮ’еј·еҢ–гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж„ҸеӣігҒ®иЎЁгӮҢгҒЁи§ЈйҮҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еӢ•еҗ‘гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйҮҚеӨ§гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲеӣҪйҡӣе•ҶдәӢд»ІиЈҒгӮ’зҙӣдәүи§ЈжұәжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰеҘ‘зҙ„гҒ«жҳҺиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒ®дёҖж–№гҒҫгҒҹгҒҜзҙӣдәүгҒ®еҶ…е®№гҒҢеҲ¶иЈҒгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®е•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ«гӮҲгӮӢз®ЎиҪ„гҒҢеј·еҲ¶гҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғӯгӮ·гӮўгҒ®зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©иЈҒеҲӨжүҖ
зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©зҙӣдәүгҒ®е°Ӯй–ҖжҖ§гҒЁиӨҮйӣ‘жҖ§гҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ§гҒҜ2013е№ҙгҒ«зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©иЈҒеҲӨжүҖгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®е°Ӯй–ҖиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„гҒ®йҖЈйӮҰзү№иЁұиЈҒеҲӨжүҖгӮ’гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰеүөиЁӯгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҒқгҒ®з®ЎиҪ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰдәҢеҖӢгҒ®еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
第дёҖгҒ«гҖҒ第дёҖеҜ©гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒйҖЈйӮҰзҹҘзҡ„иІЎз”ЈеәҒпјҲRospatentпјүгҒӘгҒ©гҒ®иЎҢж”ҝж©ҹй–ўгҒҢдёӢгҒ—гҒҹжұәе®ҡпјҲдҫӢпјҡзү№иЁұгӮ„е•ҶжЁҷгҒ®жӢ’зө¶жҹ»е®ҡгҖҒзҷ»йҢІз„ЎеҠ№гҒӘгҒ©пјүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдёҚжңҚз”із«ӢгҒҰдәӢ件гӮ’зӣҙжҺҘз®ЎиҪ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒиЎҢж”ҝжүӢз¶ҡгҒ®ж®өйҡҺгҒӢгӮүеҸёжі•гҒ®е°Ӯй–Җж©ҹй–ўгҒҢй–ўдёҺгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒЁжұәе®ҡзҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
第дәҢгҒ«гҖҒз ҙжЈ„йҷўпјҲгӮ«гғғгӮөгӮ·гӮӘгғіпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгҒ§гҒҷгҖӮдёӢзҙҡе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҢ第дёҖеҜ©гҒЁгҒ—гҒҰеҜ©зҗҶгҒ—гҒҹзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©дҫөе®іиЁҙиЁҹгҒ®еҲӨжұәгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒз ҙжЈ„еҜ©зҗҶгӮ’иЎҢгҒҶжЁ©йҷҗгӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғӯгӮ·гӮўгҒ®иЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҜҫеҜ©дё»зҫ©гҒЁиҒ·жЁ©жҺўзҹҘдё»зҫ©

гғӯгӮ·гӮўгҒ®ж°‘дәӢгҒҠгӮҲгҒіеҲ‘дәӢиЈҒеҲӨгҒҜгҖҒгҖҢеҚҠеҜҫеҜ©зҡ„гҖҚгҒӘжҖ§иіӘгӮ’жҢҒгҒӨгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪ“дәӢиҖ…гҒҢејҒиӯ·еЈ«гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰд»ЈзҗҶгҒ•гӮҢгҖҒиҮӘгӮүгҒ«жңүеҲ©гҒӘдё»ејөгҒЁиЁјжӢ гӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҖҢеҜҫеҜ©дё»зҫ©гҖҚзҡ„гҒӘеҒҙйқўгӮ’жҢҒгҒӨдёҖж–№гҒ§гҖҒиЈҒеҲӨе®ҳиҮӘиә«гҒҢдәӢе®ҹиӘҝжҹ»гҒ«з©ҚжҘөзҡ„гҒ«й–ўдёҺгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢиҒ·жЁ©жҺўзҹҘдё»зҫ©гҖҚзҡ„гҒӘеҒҙйқўгӮӮгҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢеҪ“дәӢиҖ…дё»зҫ©гҖҚгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒҢиҮӘгӮүиЁјжӢ гӮ’еҸҺйӣҶгғ»жҸҗеҮәгҒ—гҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҜжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҹиЁјжӢ гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҒ®гҒҝеҲӨж–ӯгӮ’дёӢгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®иЈҒеҲӨе®ҳгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«еҪ“дәӢиҖ…гҒҢжҸҗеҮәгҒ—гҒҹиЁјжӢ гӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒдәӢ件гҒ®зңҹзӣёгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰиҮӘгӮүгҒ®иҒ·жЁ©гҒ§иЁјжӢ гҒ®еҸҺйӣҶгӮ„дәӢе®ҹгҒ®иӘҝжҹ»гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғӯгӮ·гӮўгҒ§иЁҙиЁҹгҒ«иҮЁгӮҖе ҙеҗҲгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®иғҪеӢ•зҡ„гҒӘеҪ№еүІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬дәӢе®ҹгҒҢжө®дёҠгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒжғіе®ҡеӨ–гҒ®еҲӨж–ӯгҒҢдёӢгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮӮиҖғж…®гҒ«е…ҘгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰгҒ®иЈҒеҲӨеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжі•еҫӢгҒ®и§ЈйҮҲгӮ’зөұдёҖзҡ„гҒ«зҷәдҝЎгҒҷгӮӢгҖҢз·Ҹдјҡжұәиӯ°гҖҚгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№зҙӣдәүгӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«жүұгҒҶе•ҶдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жӯҙеҸІгҒЁиҝ‘е№ҙгҒ®еӢ•еҗ‘гҖҒгҒқгҒ—гҒҰзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©зҙӣдәүгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ—гҒҰиЎҢж”ҝеәҒгҒ®жұәе®ҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢ第дёҖеҜ©гӮ’з®ЎиҪ„гҒҷгӮӢзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҪ№еүІгҒҜгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ§гҒ®жі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’жӯЈзўәгҒ«жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢдёҠгҒ§дёҚеҸҜж¬ гҒӘиҰҒзҙ гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиЁҙиЁҹжүӢз¶ҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®иғҪеӢ•зҡ„гҒӘеҪ№еүІгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢеҪ“дәӢиҖ…дё»зҫ©гҖҚзҡ„гҒӘиЁҙиЁҹжҲҰз•ҘгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’иҰҒжұӮгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈеҸ–жүұеҲҶйҮҺпјҡеӣҪйҡӣжі•еӢҷгғ»гғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гғӯгӮ·гӮўйҖЈйӮҰжө·еӨ–дәӢжҘӯ